事例概要
- 課題
- PMI(Post Merger Integration)を進める際、相手企業の社員がグループ入りをどのように受け止めているかを把握する手段がなく、現場の本音や感情の理解が難しかった。
- 協力的に対応はされているものの、PMI施策等に効果があっ
たのかどうかわからず、効果検証ができないためPDCAが回しづ らかった。
- 効果
- PMIサーベイにより、相手企業の意識や感情を可視化でき、従来見えなかった課題や構造的な文化の違いを把握することができた。
- 結果から「施策の妥当性」や「修正の必要性」を判断する基盤が得られ、次の打ち手を検討する仕組みが整った。
- 部署別・階層別の傾向を把握できたことで、次のM&AやPMIへの指標が蓄積され、継続的な改善に活用できるようになった。
- 実績
[サービス]
PMI(Post Merger Integration)サーベイ
[対象]
M&Aでグループ入りした企業(従業員数600名弱)の管理職以上245名
[実施概要]
M&A後のPMI推進にあたり、相手企業の受け止め方や意識を可視化するためPMIサーベイを実施。文化の違いや現場の本音を把握し、融合を促進。施策の妥当性や次の打ち手を検討する基盤として活用。
- 担当者の
こだわり -
人材枯渇時代になり、例えば、採用市場においても、企業と個人の関係性が20年前と変わり、より対等になってきています。M&AにおけるPMIも、過去よりも、より相手企業側の社員のポテンシャルを活かすことや、相互シナジーの創出が非常に重要になってきていると感じます。にもかかわらず、ガバナンス面でのDD(Due Diligence)に意識が取られ、相互シナジーの部分が後回しになっていることが多くみられていました。投資に見合うリターンを得るためにも、人・組織面のPMIをより重視すべきだと考えています。今回の事例が、多くの企業のM&Aの成功につながることを願っています。
- 担当者
― 貴社では、これまでM&Aを何度か経験されていますが、PMI(Post Merger Integration)の重要性についてお聞かせください。
金子様:これまでに複数回のM&Aを経験してきましたが、買収しただけでは十分なシナジーを生み出すことは難しいです。そこで、4、5年前から本格的にPMI(Post Merger Integration)を強化しています。一般的にも「買収契約締結までは2~3合目に過ぎない」とよくいわれますが、まさにその通りで、買収後こそが本番です。成否を決めるのはPMIであり、本当に私たちの重要なプロセスだと考えています。PMIでは、取り組むべきことが多岐にわたり、相手によって進め方を変えなければならない点が難しさでもあり、同時に要となります。特に、人の感情やカルチャーの違いを理解し、受け止める姿勢が重要になります。
亀井様:M&Aは多額の投資を伴うため、そのリターンをどう回収するかが最大の課題です。買収後に何も手を打たなければ回収は難しく、ガバナンスやルールの統制、そしてシナジーの創出が不可欠です。ガバナンスが機能しなければ、不祥事のリスクやブランド価値の棄損にもつながりかねませんし、シナジーを積極的に推進しなければ、投資に見合うキャッシュを生み出せる事業には育ちません。そういう意味でPMIは、事業の将来を左右する非常に重要な取り組みです。制度や文化の違いを乗り越え、「相手を知る」ことから始めていくことが、成功の第一歩だと考えています。
「統合」というより「融合」という考え方を大切にしている
― PMIの中でも、業務や制度面と人の意識・カルチャー面に関して、進める上での難しさや問題意識を教えてください。
金子様:カルチャーの違いは想像以上に大きいと感じています。例えば、営業の進め方ひとつを取っても、提案スタイルがまったく異なることがあります。シナジーには「コスト削減」と「トップライン(売上)向上」の2つの側面がありますが、コストシナジーを追求しすぎると、相手の感情面にマイナスの影響を与えかねません。一方でトップラインシナジーを生み出すには、お互いの戦い方や背景を深く理解しながら進めなければ、現場同士が衝突してしまう可能性もあります。
だからこそ私たちは「統合」というより「融合」という考え方を大切にしています。お互いが歩み寄り、すり合わせを重ねていくこと。決して自分たちのやり方を押し付けるのではなく、相手の文化を尊重しながら融合を図ることが、重要なポイントだと思っています。
亀井様:同じBPO事業を手がけていても、領域ややり方は違うものです。そしてお互いに自分たちのやり方に誇りを持っています。そのため、いざ、ビジネスシナジーの発現に向けて具体的な取り組みを始めてみるとスタンスの違いが浮き彫りになる場面も少なくありません。
こうしたカルチャーや制度、やり方の違いは事前に想定していても、実際には最適解を探りながら調整を重ねる必要があり、そこが難しさのひとつです。しかし同時に、自分たちのカルチャーや制度、やり方を客観的に見直すきっかけにもなります。「これは自社の強みとして残すべきことなのか」「改善すべきことなのか」を考えさせられるのです。M&Aを通じて違うDNAを取り込み、融合していくことは、自社の進化にとっても大きな意味があると感じています。
感情などこれまで「見えなかった部分」を可視化して前進できる
― 今回、弊社のPMIサーベイを導入されましたが、導入する際の課題意識と期待について教えて下さい。
亀井様:PMIは相手企業ごとに進め方を変える必要がありますが、実際のところ「相手がどう感じているのか」を把握するのは簡単ではありません。相手企業の中にも、日々接している人だけでなく、直接コミュニケーションを取れていない多くの方々が、私たちのグループ入りをどう受け止めているのかを知ることは、大きな課題でした。
さらに、PMIの施策はガバナンスの整備からシナジー創出に向けた制度変更まで多岐にわたります。協力的な対応はされているものの、実際にどう感じているのかは見えにくく、従来はそれを把握する手段がありませんでした。その点で、意識や受け止め方を可視化できる今回のサーベイは、非常に魅力的であり、導入を決める大きなきっかけとなりました。
金子様:サーベイの結果からは、「現在のPMI施策は正しかったのか」「タイミングは適切だったのか」「進め方を修正すべきではないか」といった次の打ち手を検討するための判断材料が得られます。これにより、PMIを推進する上での進捗を定期的にチェックし、改善につなげていけることに大きな期待を寄せています。
これまでのPMIでは、施策がどのように受け止められているのか、成果がどう出ているのかが不明確な部分もありました。今回のサーベイは、その「見えなかった部分」を可視化し、より確実に前進していくための重要なツールになると考えています。
「可能性を感じる」という声が複数あったことが大変うれしかった
― PMIサーベイを実施してみて、仮説と実態で違いはありましたか。また、報告結果を踏まえて、気づいたこと、およびそれに対するアクションについて教えてください。
金子様:サーベイ結果を相手企業側から見るのと、私たちから見るのとで恐らく印象が違う点があり、それが面白いと感じています。全体で見ると、7割くらいが事前に仮説を立てた通りで自信になり、他3割が想定と異なり、気づきが多かったです。
想定通りだったのは、相手企業を歓迎するために実施したウェルカムイベントについて、多くの参加者が前向きに受け止めてくれたことです。一方で、参加しなかった方には十分に伝わっていなかったことは想定外でした。そこには働き方や企業文化の違いが影響しているのだと気づきました。
また、サーベイの回答率が非常に高く、コメントの回答数も多かったことは印象的でした。中でも「可能性を感じる」という声が複数あったことが大変うれしかったです。グループ会社間で実際に新しいコミュニケーションが生まれており、サーベイで得られたポジティブな兆しが形になっていることに大きな手応えを感じています。
亀井様:階層ごとの傾向は想定通りでしたが、部署別で見ると想定外の結果もありました。評価が高いと思っていたところではそうでもなく、逆に厳しい結果を予想していた部署でプラスの声が多かったのです。それがなぜ起こってるのかという点について、仮説を立てて今対応しているところです。
定性コメントについては、対象がミドルマネジメント層以上だったこともあり、良い/悪いの2択ではなく「まだわからない」といった冷静な意見が多かったのも特徴でした。M&Aから1年経ったタイミングでサーベイを行いましたが、施策が十分に浸透するにはまだ時間が必要であり、やりたいことや、やるべきことが多く残っていると改めて認識しました。
現在は、当社の役員には良い点も課題も含めて整理して報告しており、次のM&Aに活かせるポイントも見えてきています。サーベイを通じて、自分たちの進め方を冷静に振り返るきっかけを得られたことは大きな成果だと思っています。
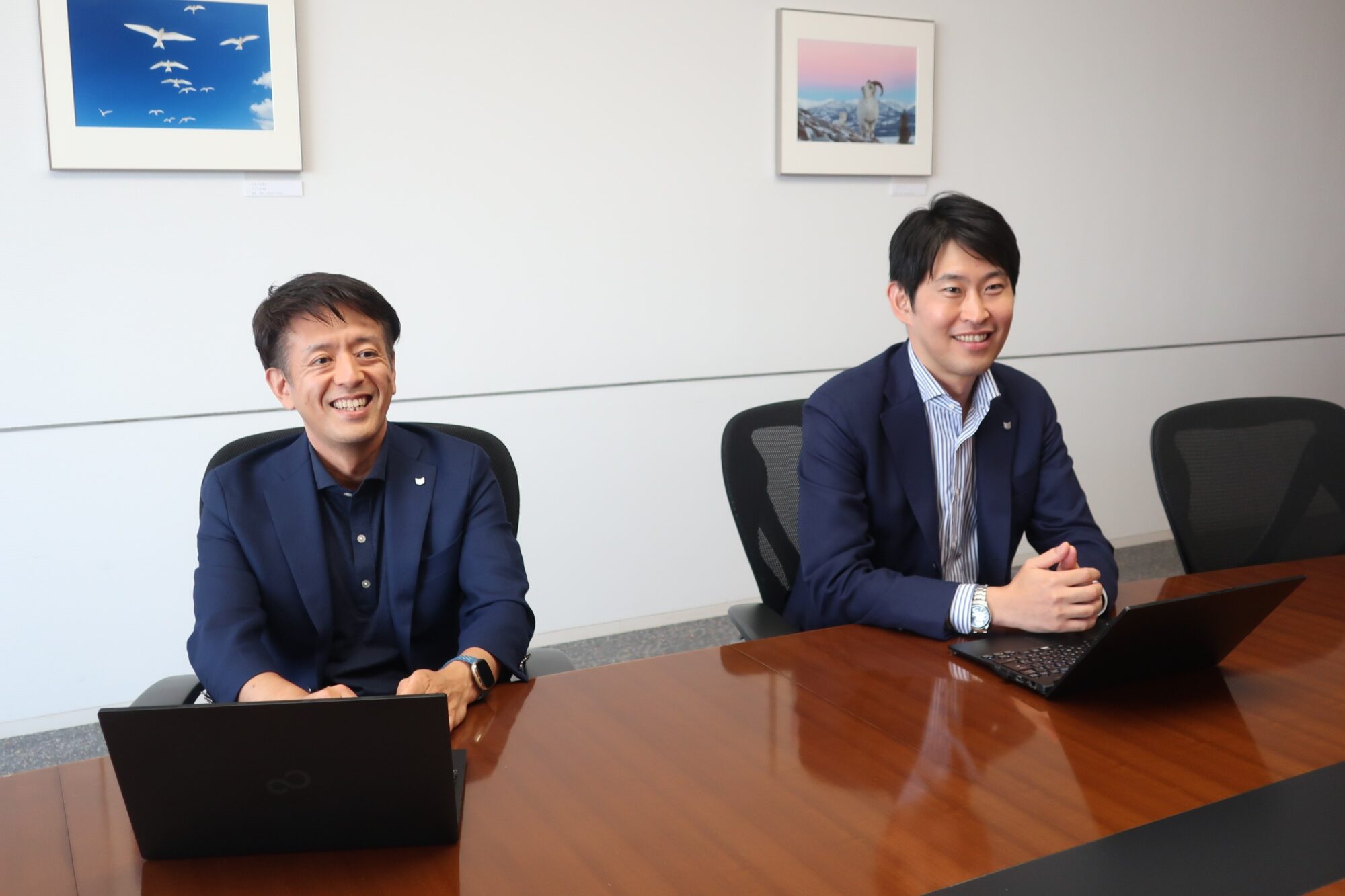
柔軟に改善を繰り返しながらPMIを進めたい企業に有効
― PMIサーベイを実施して良かったこと、また、どういう企業に実施してもらえると良いなと思いますか?
金子様:一番の価値は「可視化できること」です。相手企業の方々が感情的にどう捉えているのか、どんな意識を持っているのかを、言語化された形で確認できたのは非常に大きな収穫でした。
このサーベイは、あらかじめPMIの進め方を細かく決めている企業というよりも、実際にやりながら「どう進めるのが良いか」を考え、状況に応じて施策をカスタマイズしていくスタイルの企業に特に有効だと思います。柔軟に改善を繰り返しながらPMIを進めたい企業にとって、非常に役立つツールになると感じています。
亀井様:可視化できたことに加え、今後「定点観測ができる」点も大きな価値だと思っています。実施した施策が実際に改善につながっているのか、あるいは十分ではないのかを、継続的に確認できるからです。なので、来年もサーベイを実施する予定です。
これにより、「いつまでPMIを続けるのか」といった判断や、従来は問題ないと思っていた部分に対して「もう少しテコ入れすべきだ」と気づくきっかけにもなります。さらに、将来また別の企業をM&Aをした際には、今回との違いを比較できるようになり、より精度の高いPMIにつなげていけるのではないかと期待しています。
成功の鍵は「相互理解」と、企業の「総合力」にある
― 今回の一連のPMIの取り組みを経て、最も強く感じられた「PMIを成功させるための鍵」は何でしょうか?
金子様:成功の鍵はひとつに絞れるものではありませんが、あえて言うなら「総合力」だと思います。PMI、ひいてはM&Aそのものは、企業にとって総合力が試される場面の連続です。人・組織・カルチャーといったソフト面から、コーポレートガバナンスやバックオフィス、さらには事業戦略といったハード面まで、あらゆる要素が絡み合います。
それらを総合的にとらえ、どの領域をどの順番で、どのようにバランス良く高めていくか。そこにこそ、PMIを成功へ導く鍵があると感じています。
― シナジーを生み出すうえで大事なポイントは何でしょうか?
金子様:一番大切なのは「相互理解」だと思います。価値観はもちろん、お互いの強みや弱みを客観的に把握したうえで、最適なフォーメーションを早い段階で組み、融合していくことが特にトップラインシナジーには欠かせません。
コストシナジーは比較的シンプルで、やめるべきことを見極めて実行すればよいのですが、新たに価値をつくり出すトップラインシナジーは難易度が高いです。そのためには、相互理解と早期のアジャストがポイントだと考えています。
亀井様:シナジーを実行するのは「人」です。その人たちがどう感じているかを理解し、配慮することが何より大切だと思います。実行する人が前向きな状態でなければ、良い成果は得られません。
そのためにも、サーベイで意識や感情を可視化し続けることが重要です。取り組みが進むほどに「もっとこうしてほしい」という要望や意見も増えていくはずで、それを冷静に受け止めることが、現状を見極める上で欠かせません。
また、私たちは親会社という立場上、意図せず力関係で優位に立ってしまうことがあり、結果として相手への配慮が不足してしまうこともあります。だからこそ、相手の気持ちを理解し、融合していく姿勢を持つことが、シナジーを本当に生み出すための大事なポイントだと考えています。

相手企業をどれだけ正しく理解できるかがPMIの成否を分ける
― 最後に、これからM&Aを検討している企業や、PMIに課題を抱える企業に向けて、メッセージをお願いいたします。
金子様:M&Aは、今や企業が成長していくうえで避けて通れないアジェンダのひとつだと思います。しかし、成功率は決して高くないとも言われています。その中で注目されているのがPMIの重要性です。
実際には「何をどう進めれば良いのか」と手探りで悩みながら取り組んでいる企業も多いのではないでしょうか。私たちもそうでしたが、経験から言えば、やはり成功の鍵は「総合力」だと感じています。様々な角度から複数の施策を打ちながら進める中で、今回のPMIサーベイは非常に有益な切り口のひとつになりました。試行錯誤を重ねる過程において、取り入れてみる価値があるのではないかと思います。
亀井様:直近の複数の買収を通じて強く感じたのは、同じ言葉を伝えても、相手の企業文化や経営方針によって受け止め方や次の行動がまったく違うということです。そこをどれだけ正しく理解できるかが、PMIの成否を分けます。
普段のコミュニケーションを通じて相手を理解しようと努めてはいますが、実際には直接接していない多くの社員の方々がどう感じているのかを把握するのは難しいものです。その点、PMIサーベイは相手の本音や意識を見える化できる有効なツールだと思います。M&AやPMIに取り組む際には、ぜひこうした仕組みを活用しながら、相互理解を深めて進めていくと良いのではないでしょうか。
― 本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願いします。


