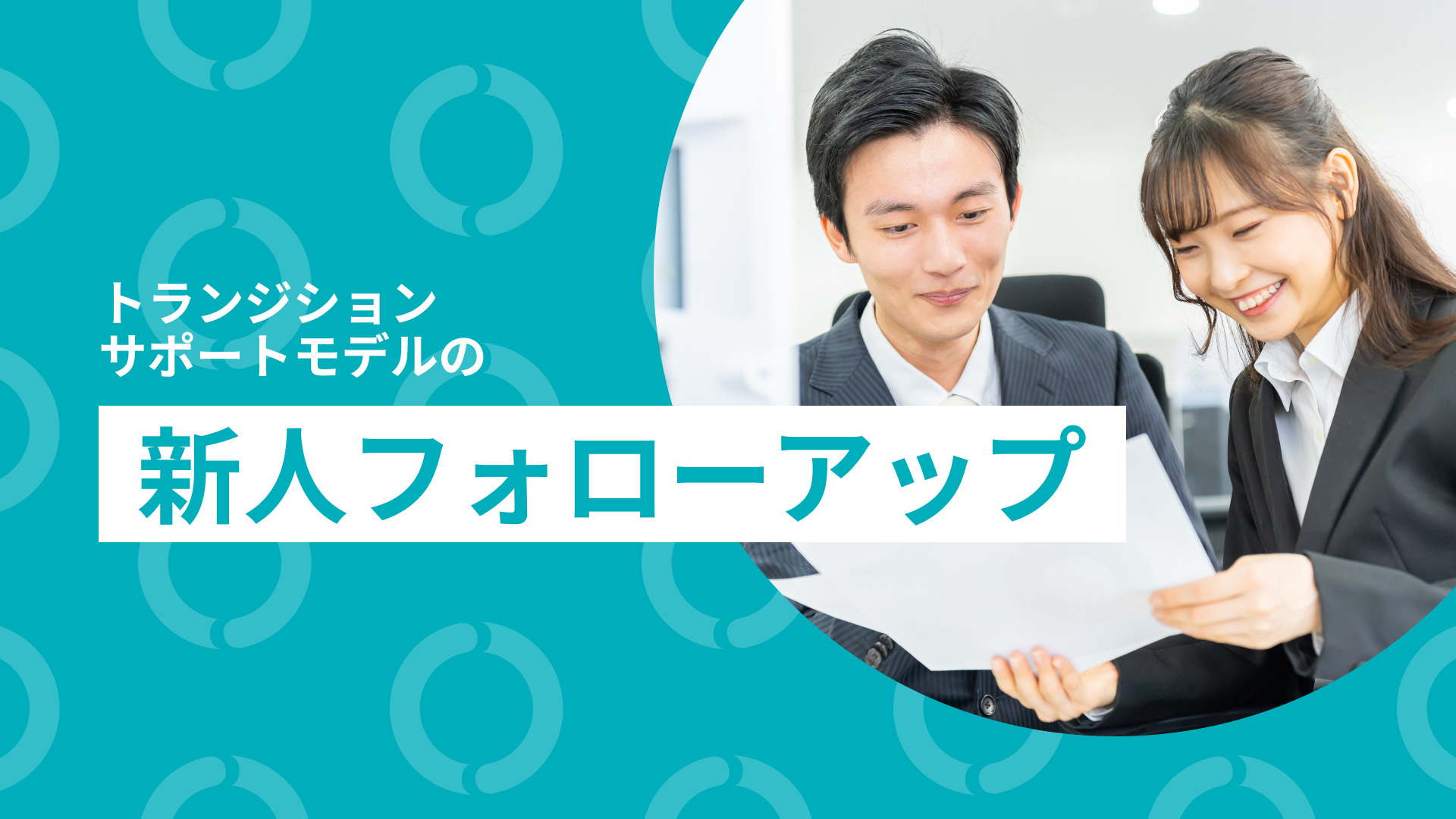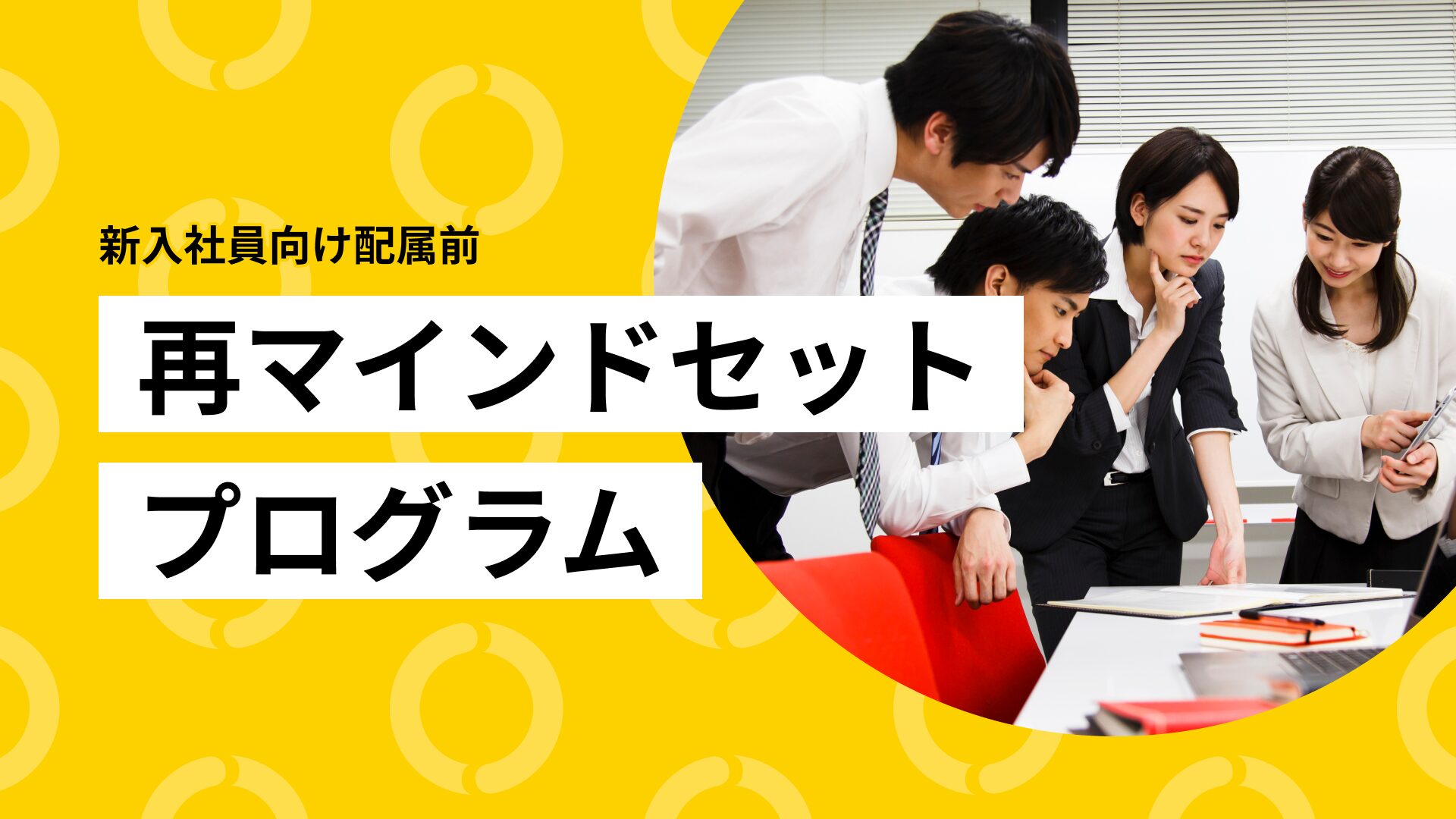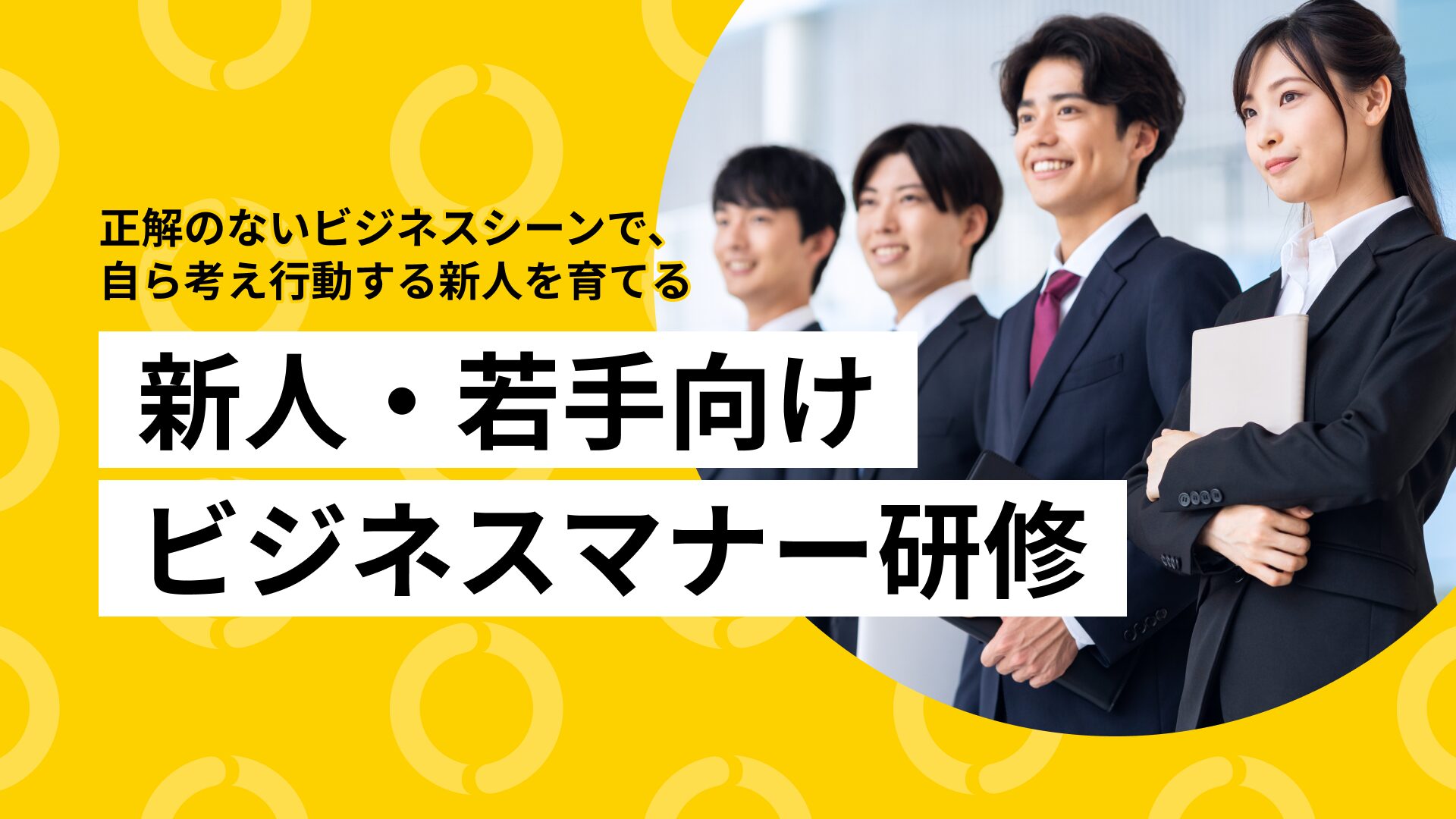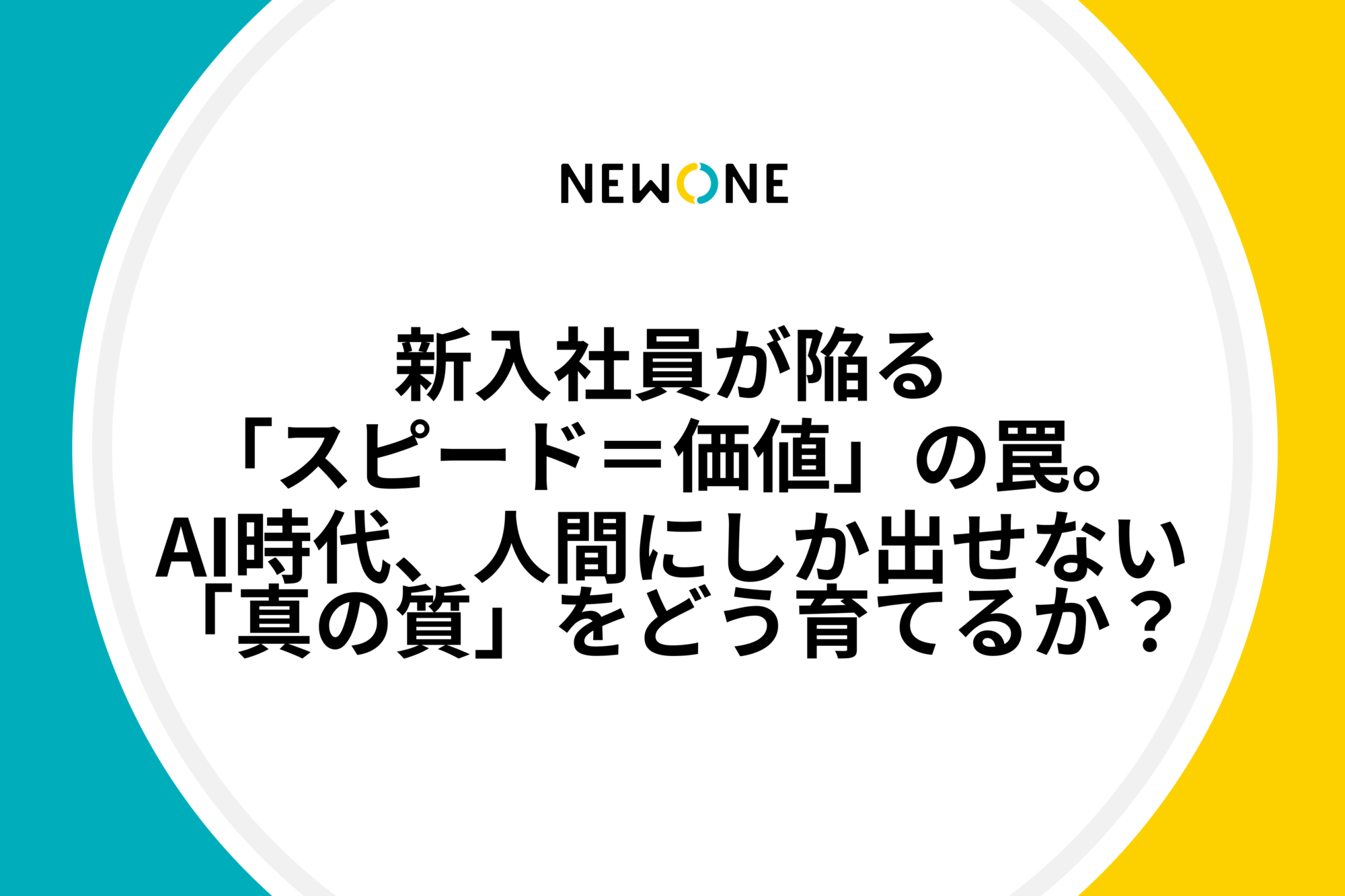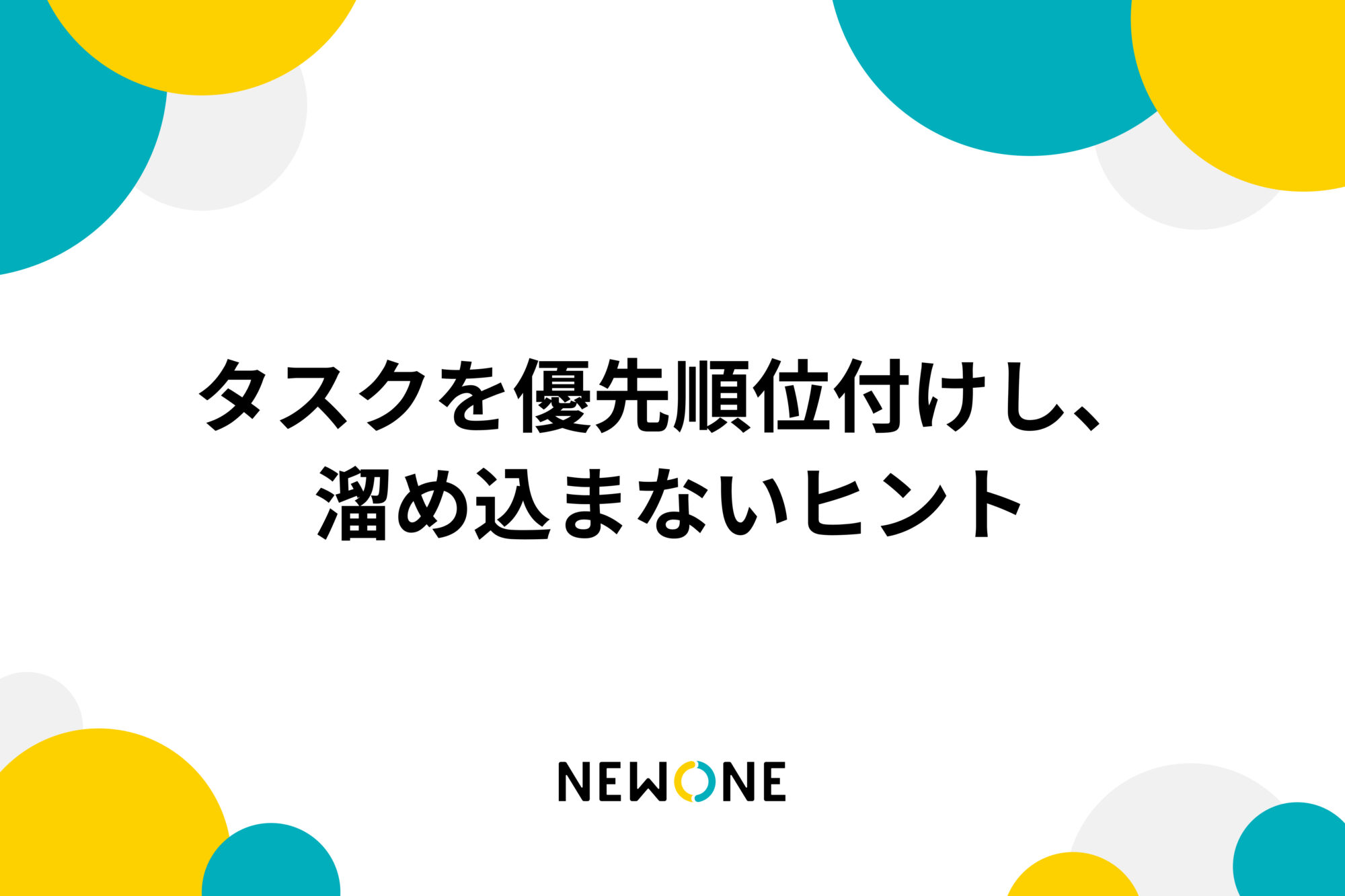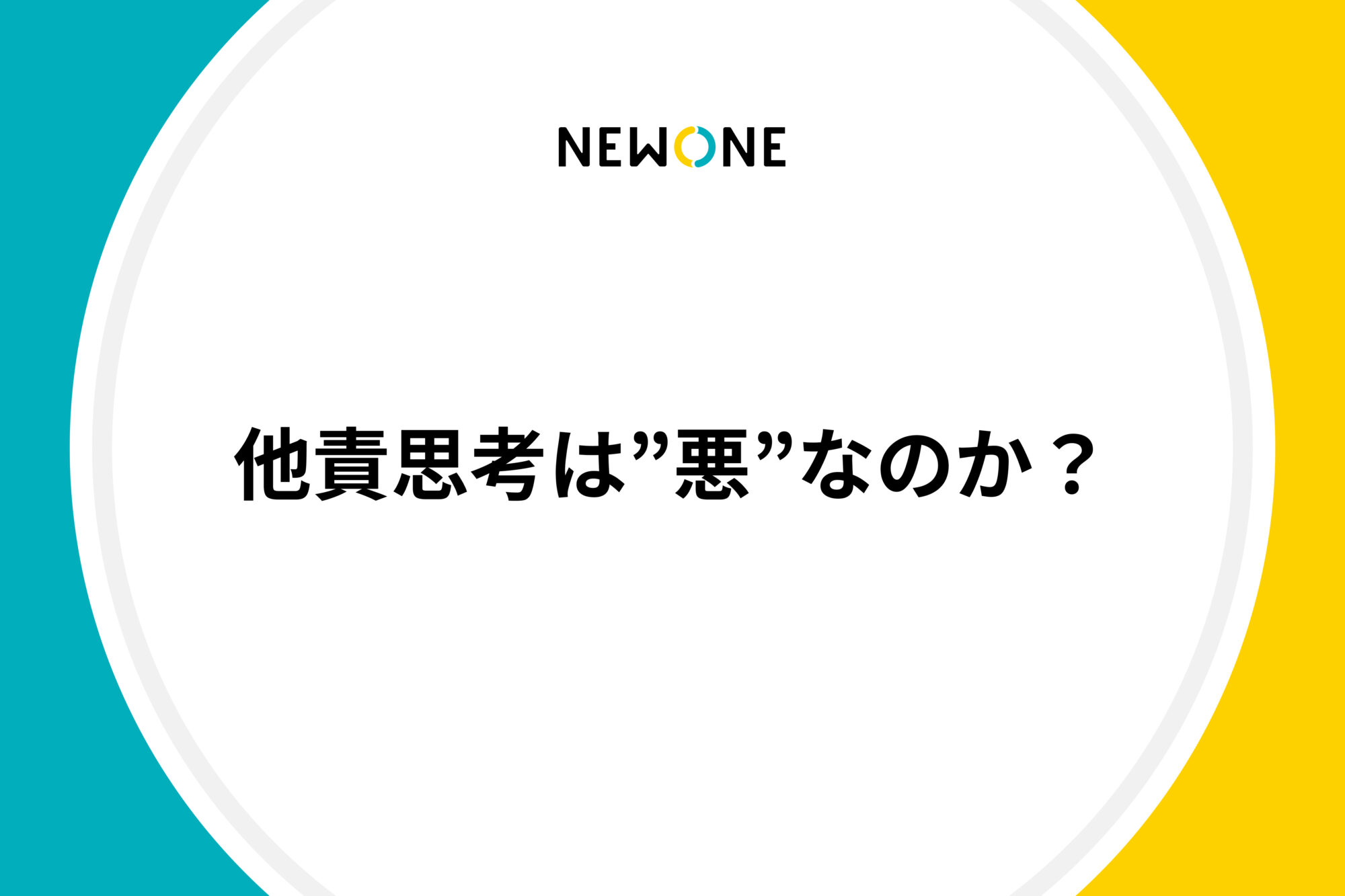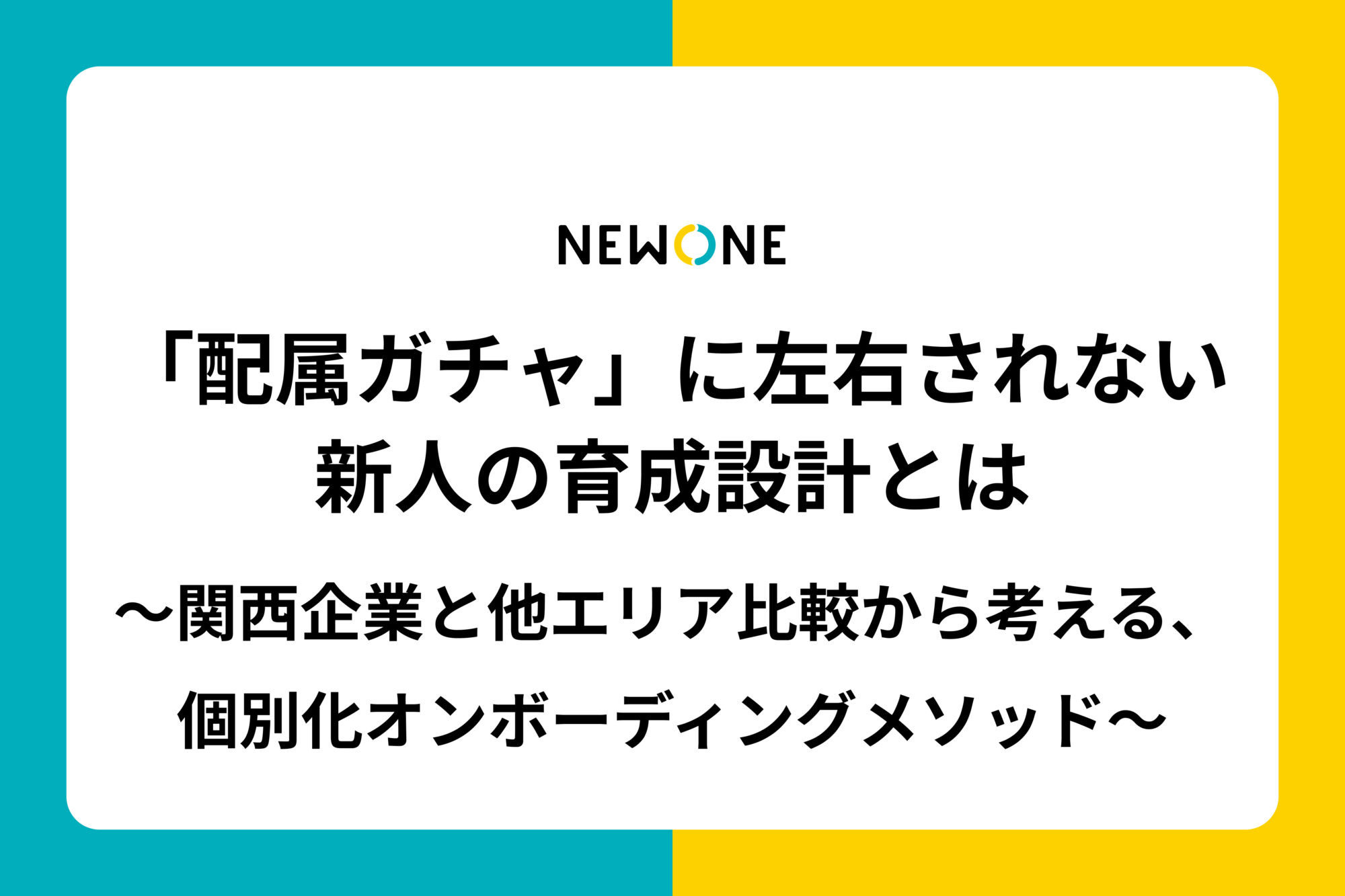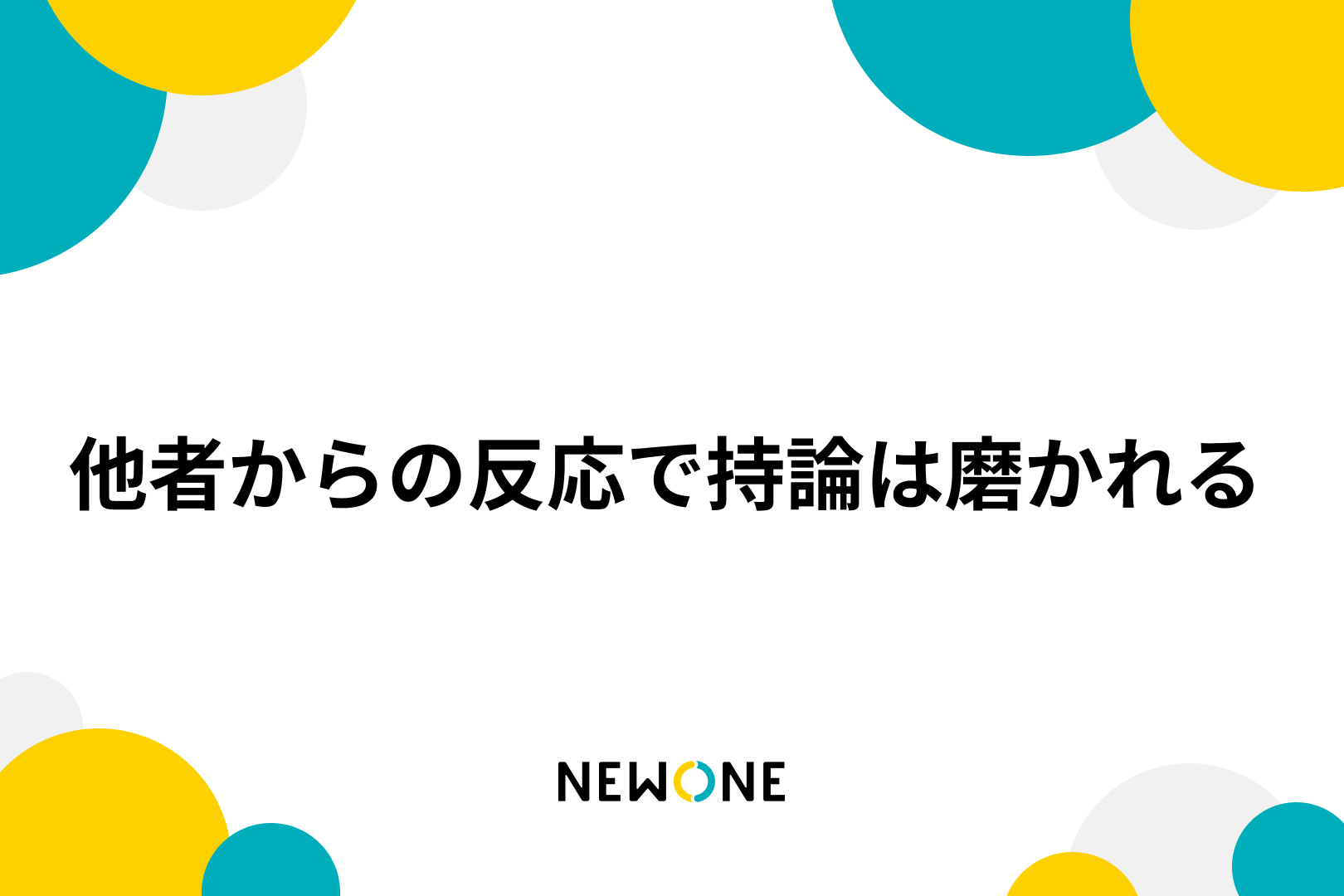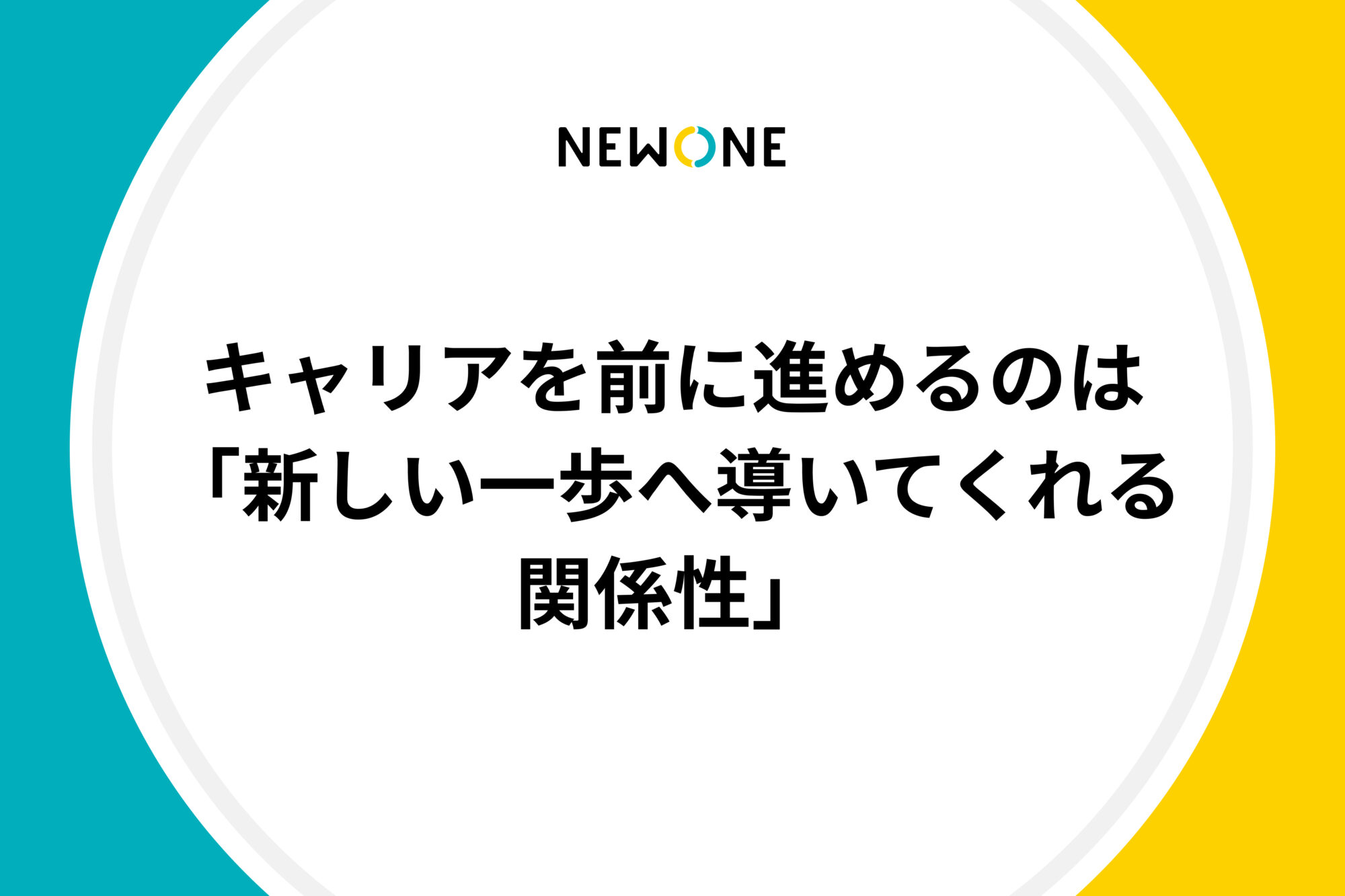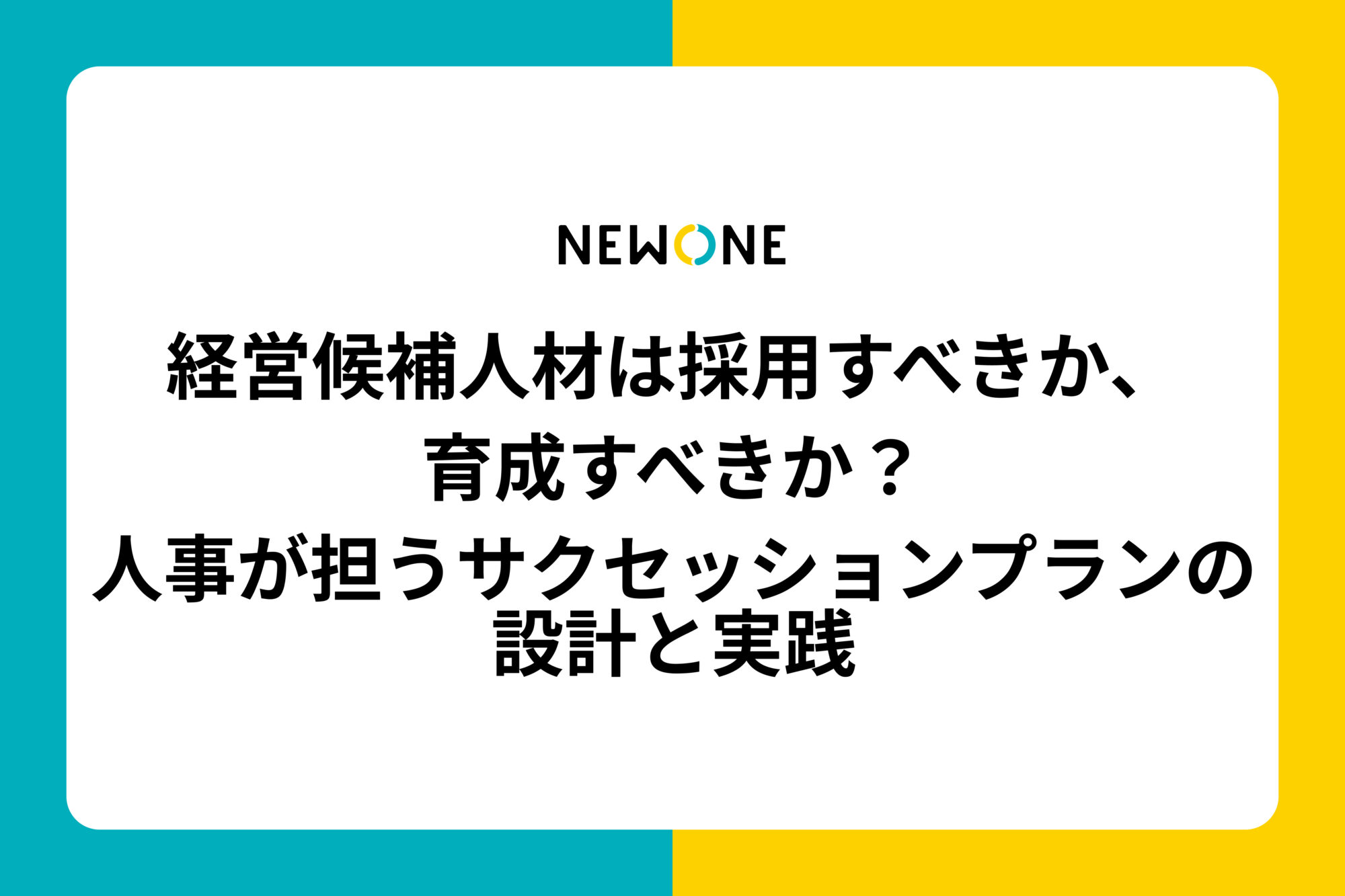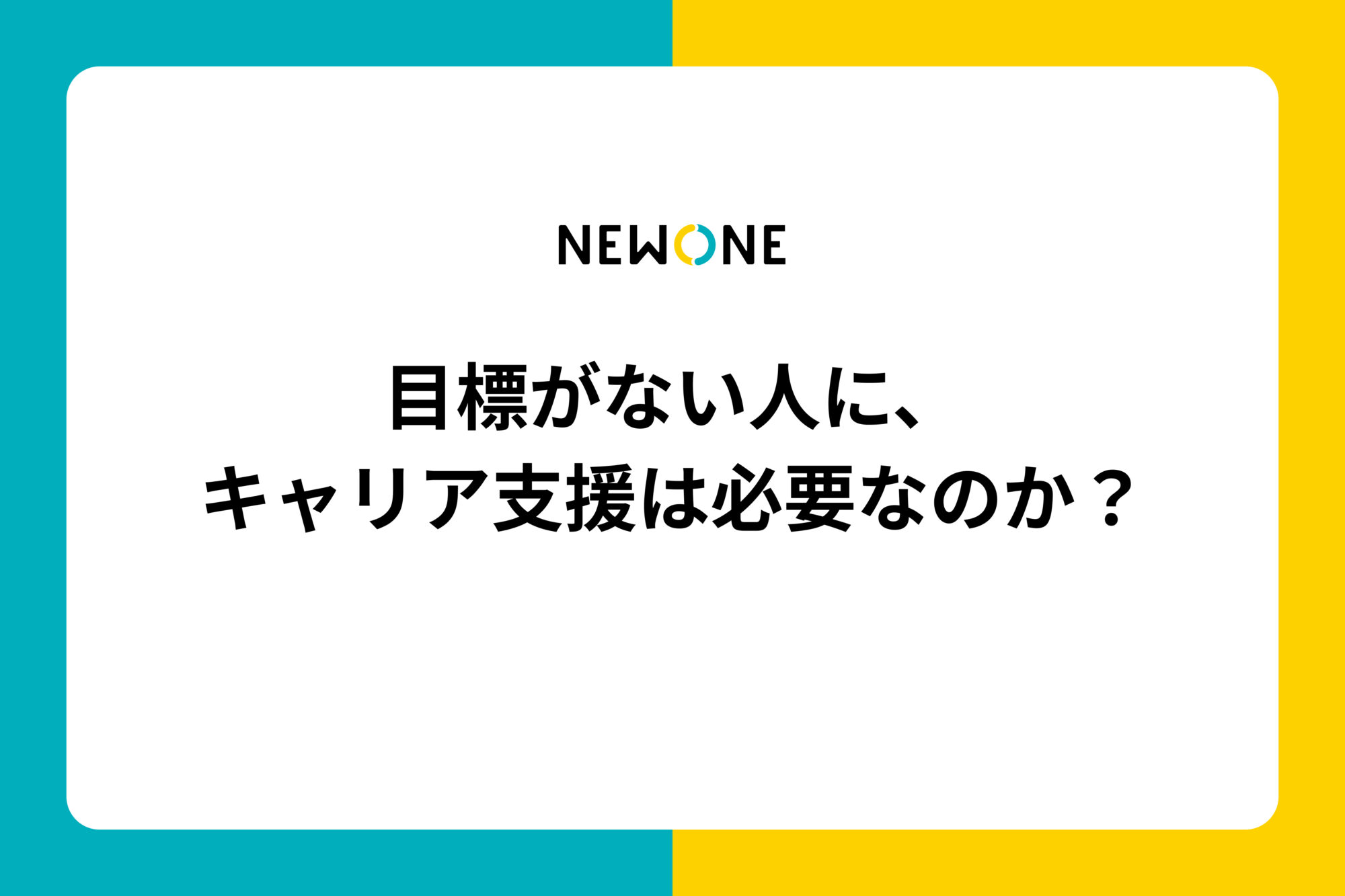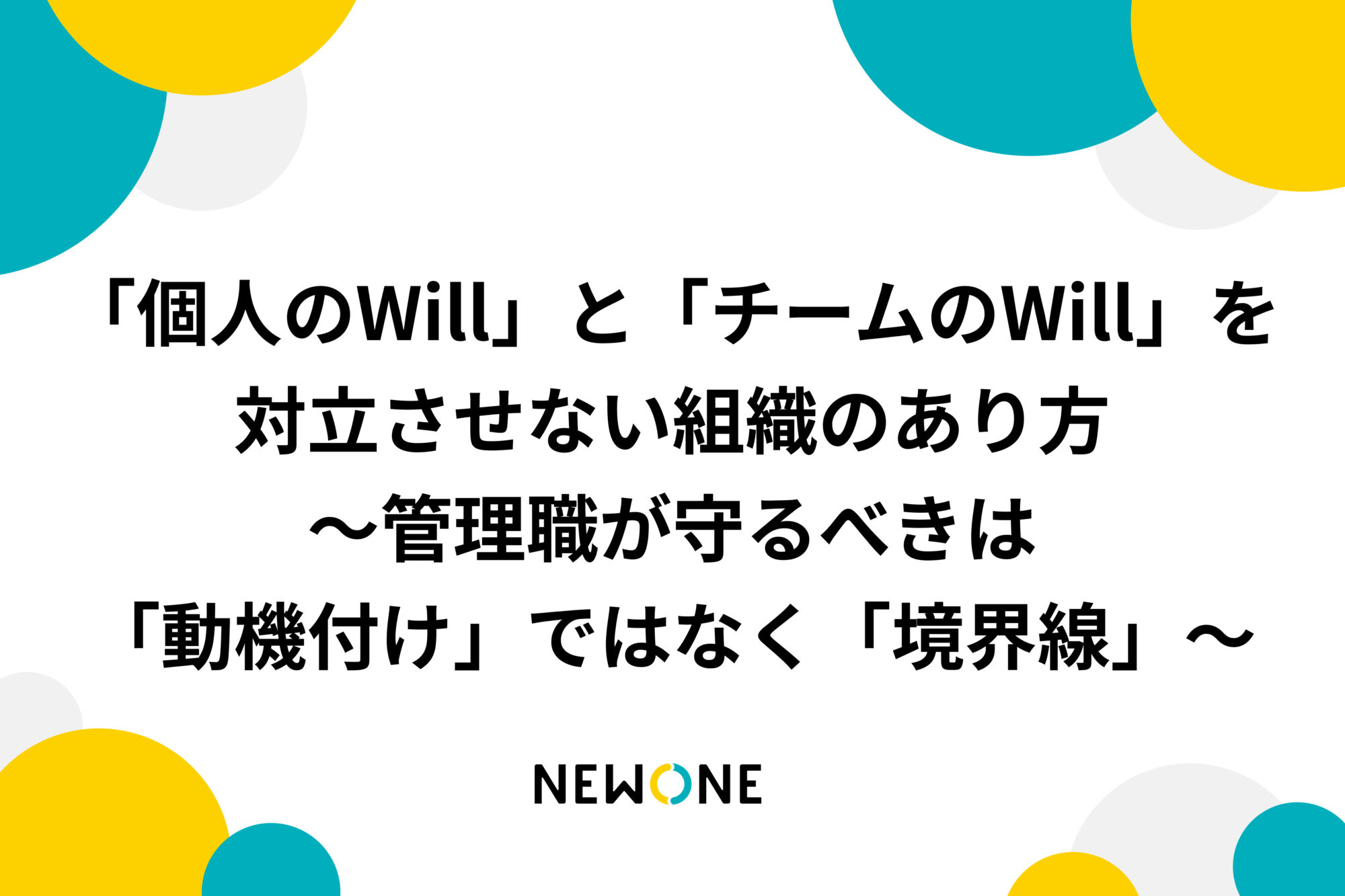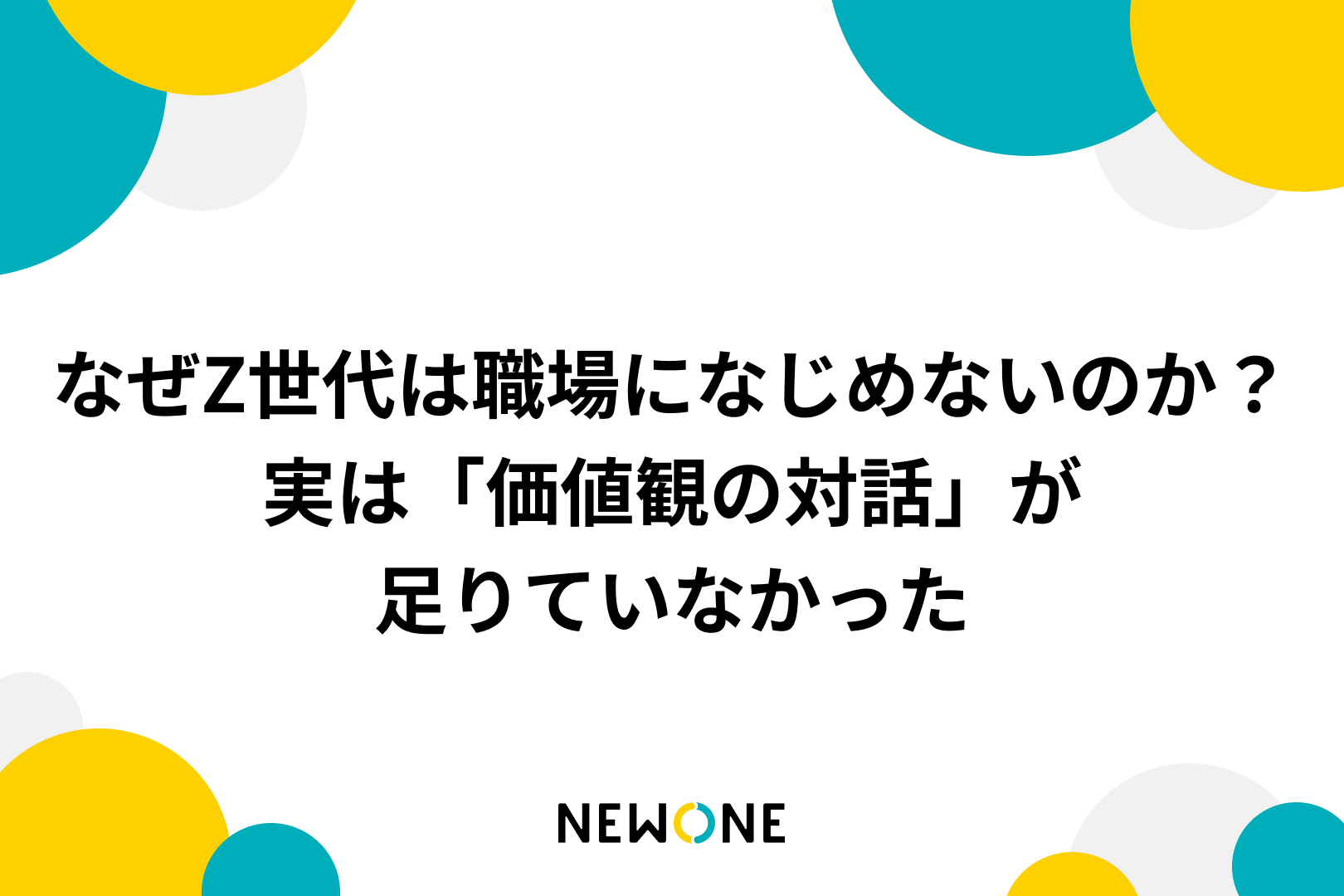
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
近年、新卒や若手社員との関わりの中で、「なかなか組織になじまない」「配属されたチームに馴染めず浮いてしまう」といった課題感を持つ企業が増えています。
その背景には、Z世代と呼ばれる新しい価値観を持った若手層の登場があります。
この世代の特徴としてよく指摘されるのが、「自分に合うものを選ぶ力」と「自己の価値観を大切にする傾向」です。生まれながらに選択肢が多く、SNS等を通じて多様な世界に触れて育ったZ世代は、「周囲に合わせる」よりも「自分らしくあれるか」を重視します。
結果として、組織に対しても「自分にフィットするか?」という視点で向き合い、「納得できない文化や慣習に合わせたくない」と感じる場面が生まれやすくなっています。
一方的な“文化の押しつけ”では、エンゲージメントは生まれない
ここで重要なのは、「若手が組織になじまない」のではなく、「組織側がすり合わせのプロセスを設計していない」という視点です。
たとえば
- ぜこの会社では“報連相”が重視されるのか?
- なぜ根回しや空気を読むことが評価されるのか?
といった、職場特有の暗黙知や価値観を、若手側は文脈を知らないまま体験することになります。
それを「社会とはそういうものだ」と一方的に押しつければ、若手は「理解できない」「納得できない」「自分らしさを否定された」と感じてしまうのです。
必要なのは、“文化の伝承”ではなく、“相互理解のプロセス”
Z世代の若手社員がエンゲージメント高く働くには、組織の価値観と個人の価値観を「対話によってすり合わせる機会」を設計することが必要です。
たとえば、
- 暗黙のルールや慣習を「背景や意味も含めて」言語化する
- 若手側が「それにどう感じたか」「どう工夫して関わろうとしているか」を言語化できるよう支援する
- 価値観のズレを“指摘”ではなく、“相互の理解のきっかけ”として活用する
といったコミュニケーション設計が挙げられます。
大切なのは、「どちらかが正しい」という前提を捨て、違いの中に意味を見出す対話です。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
“自分らしさ”と“組織らしさ”は両立できる──だからこそ、翻訳と対話が必要
Z世代は、決して組織嫌いや個人主義者ではありません。むしろ、自分が納得できる価値観の中で、真摯に貢献しようとする強い意志を持っています。
だからこそ、文化や常識をそのまま渡すのではなく、一度翻訳し、意味づけし直しながら丁寧にすり合わせていくプロセスこそが、エンゲージメントを高める鍵になります。
まとめ:適応とは、「合わせること」ではなく「理解し合うこと」
価値観が多様化した今、組織への適応は「片側の努力」で成立するものではありません。
Z世代の若手が自分の価値観を大切にするからこそ、組織側も、自社の文化を言語化し、若手と共に意味づけを問い直す姿勢が求められます。
エンゲージメントは、「迎え入れる側」と「入ってくる側」が共につくるもの。
その前提に立ったとき、Z世代の個性は“壁”ではなく、組織に新しい問いと学びをもたらす資産となるはずです。
 棚橋 彩香" width="104" height="104">
棚橋 彩香" width="104" height="104">