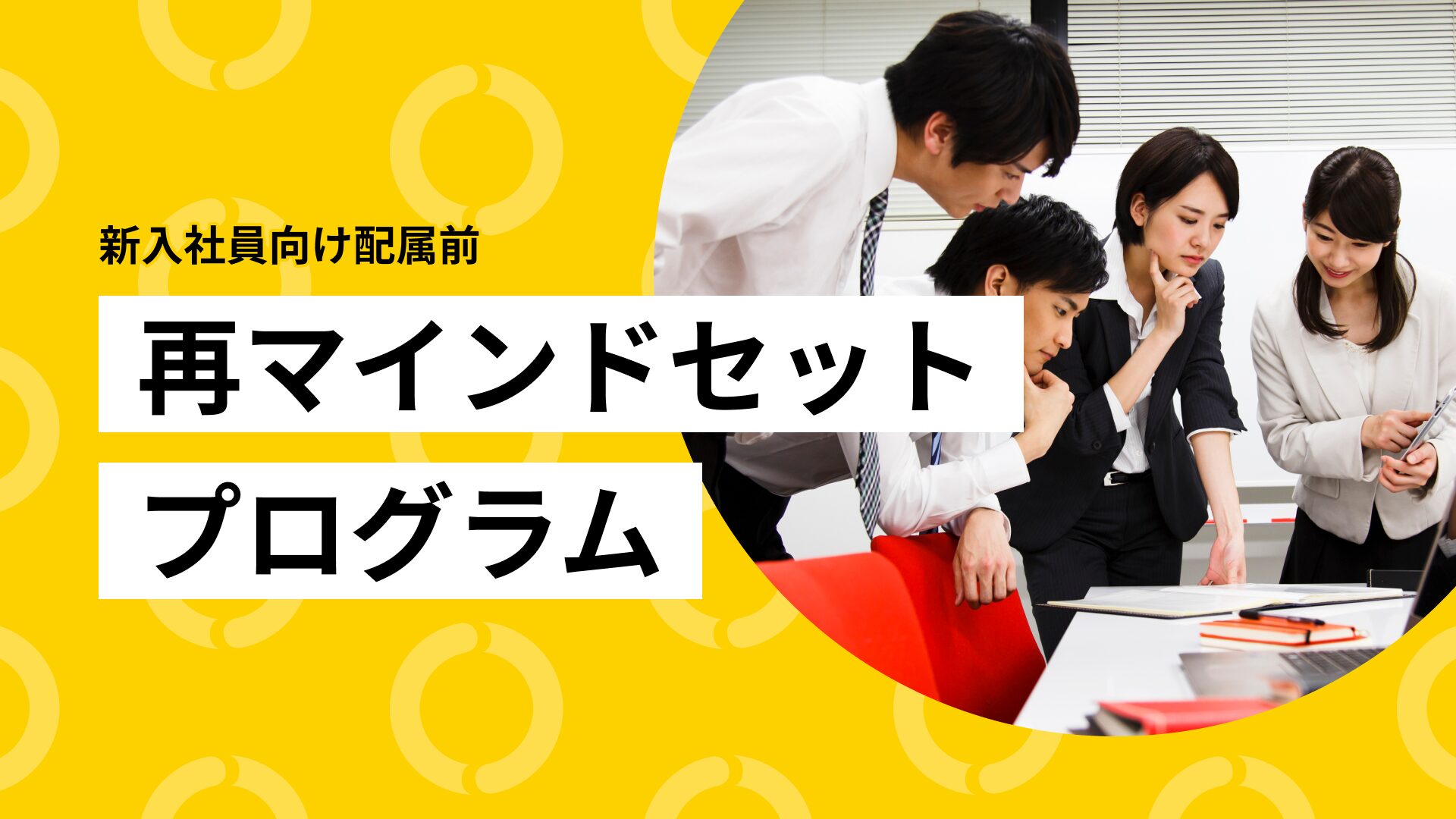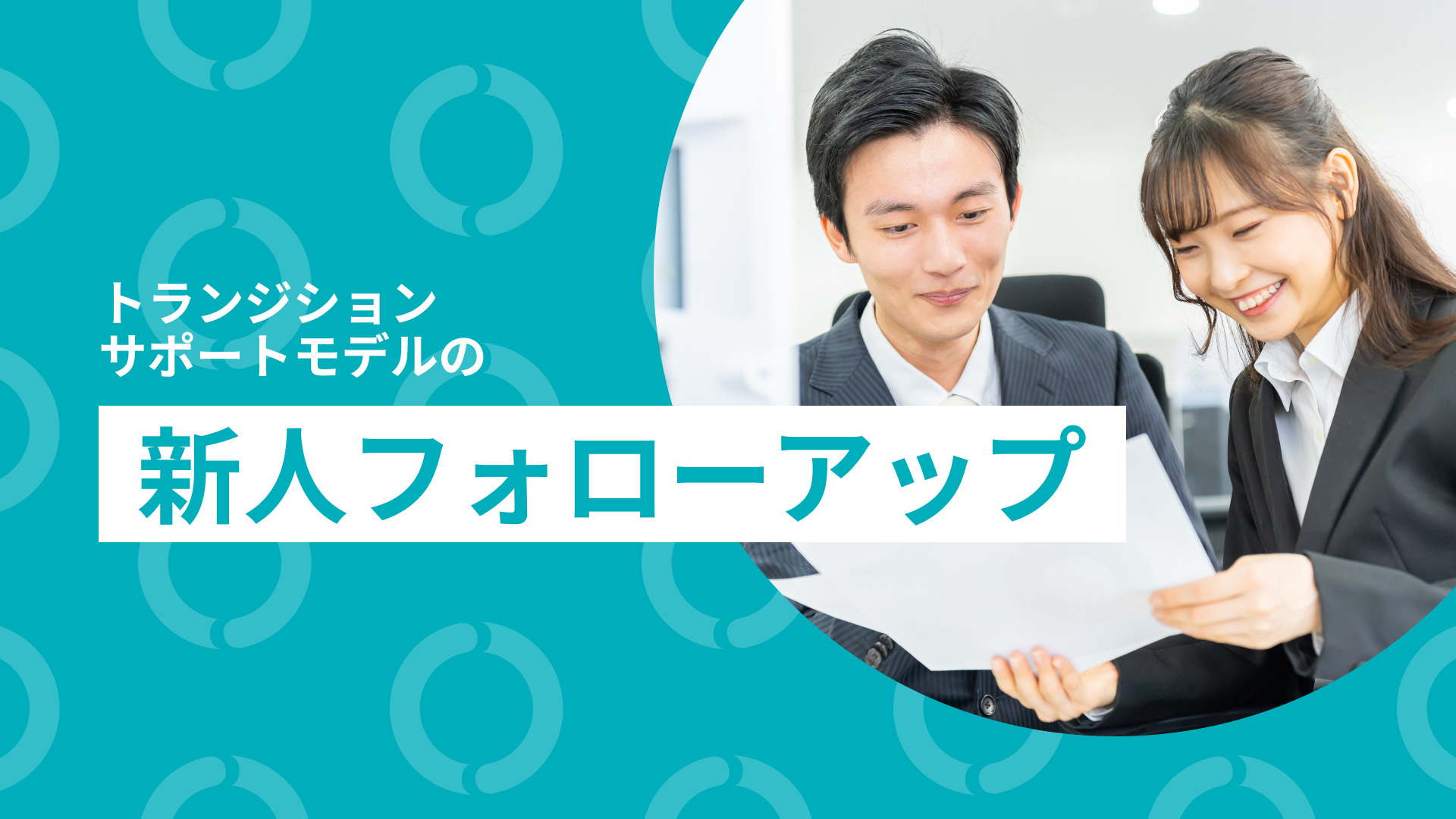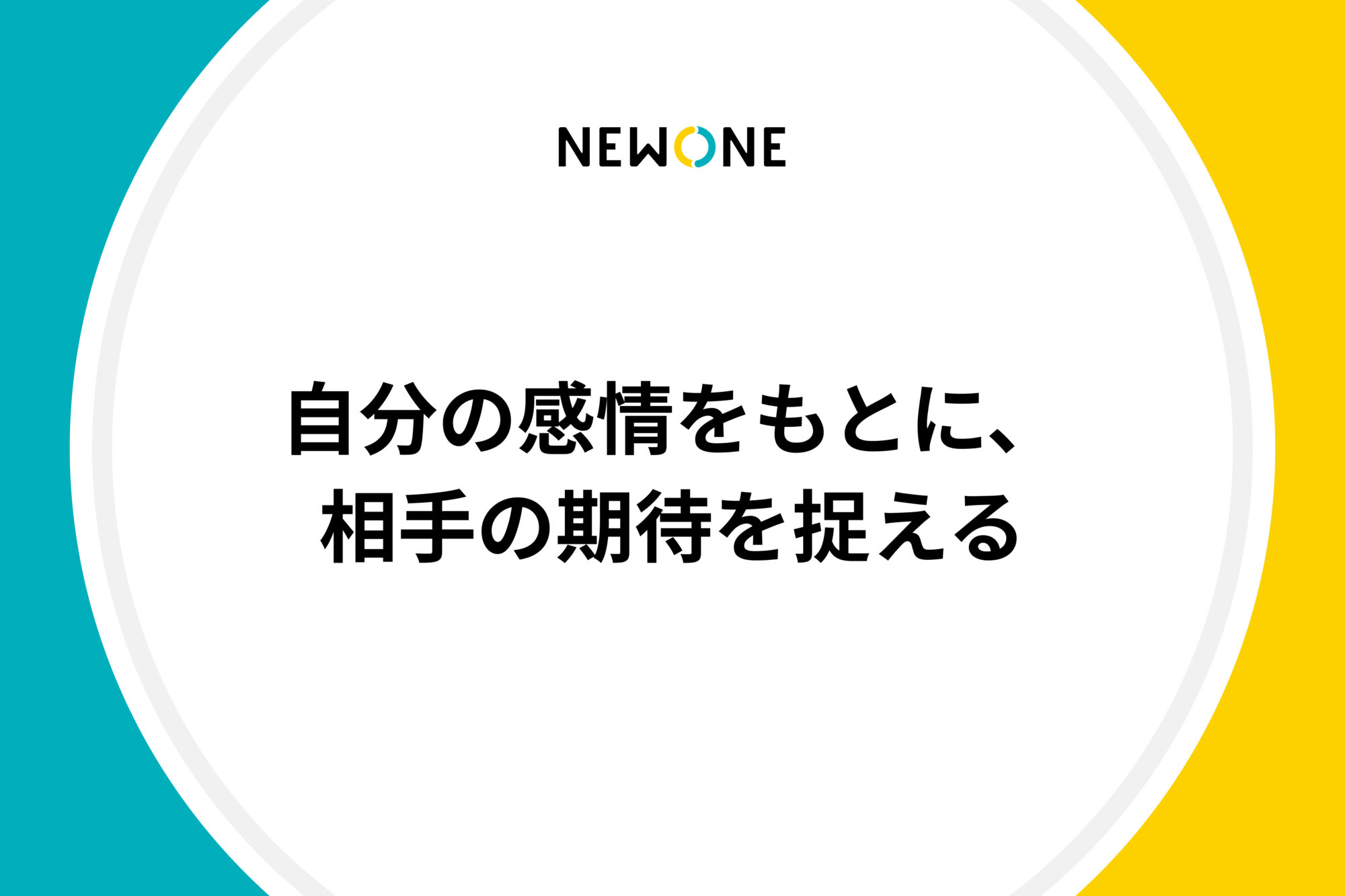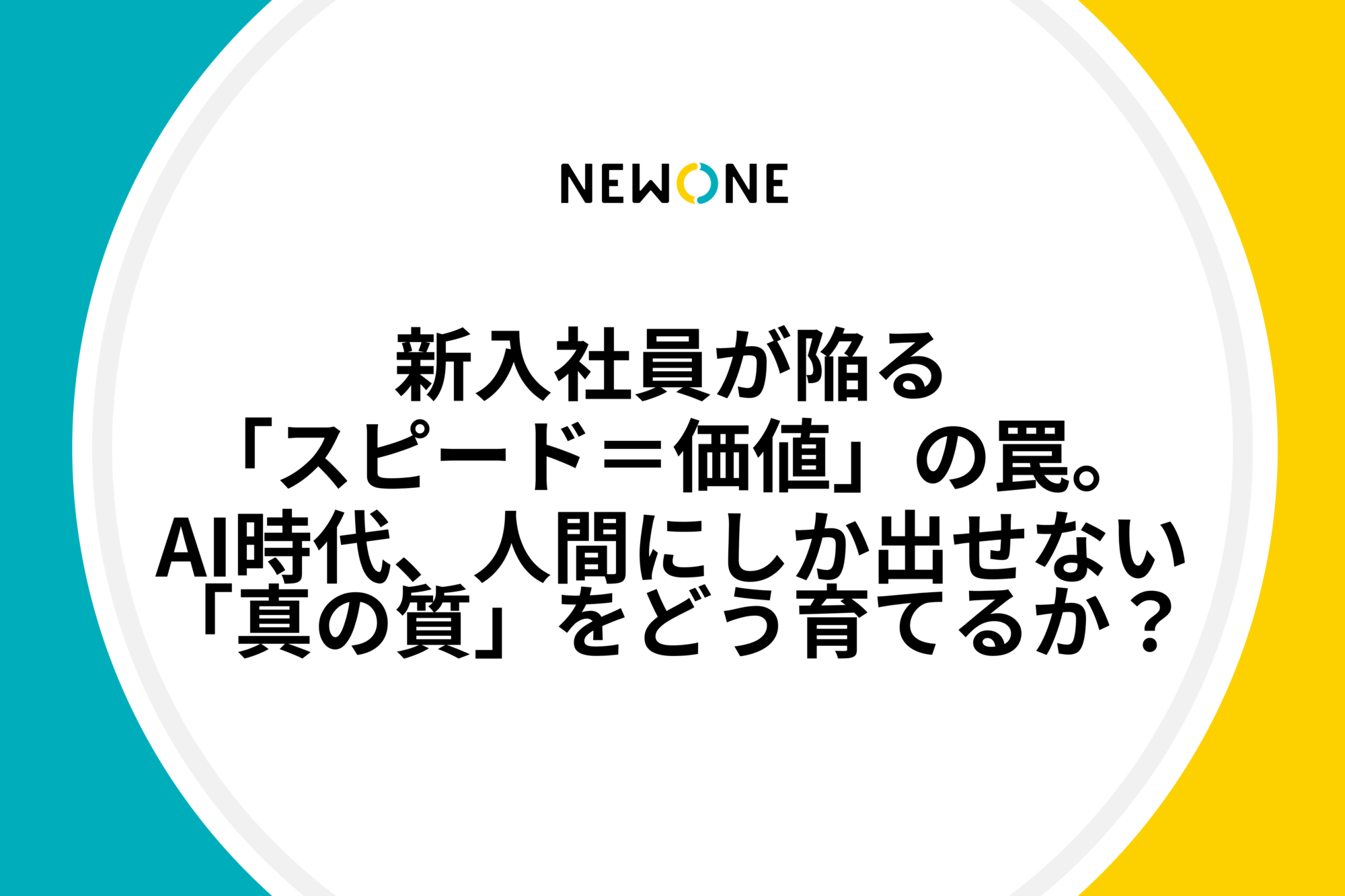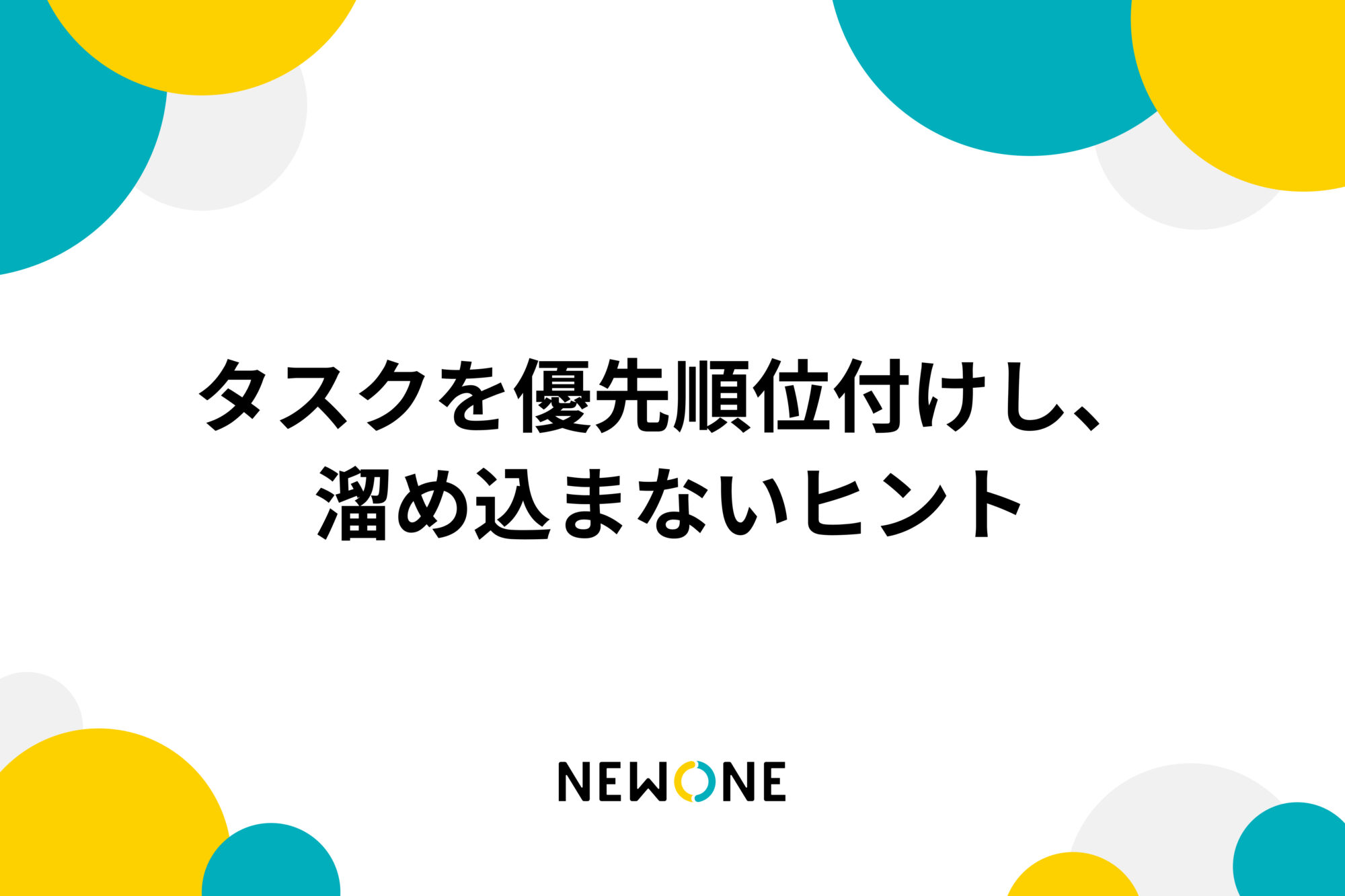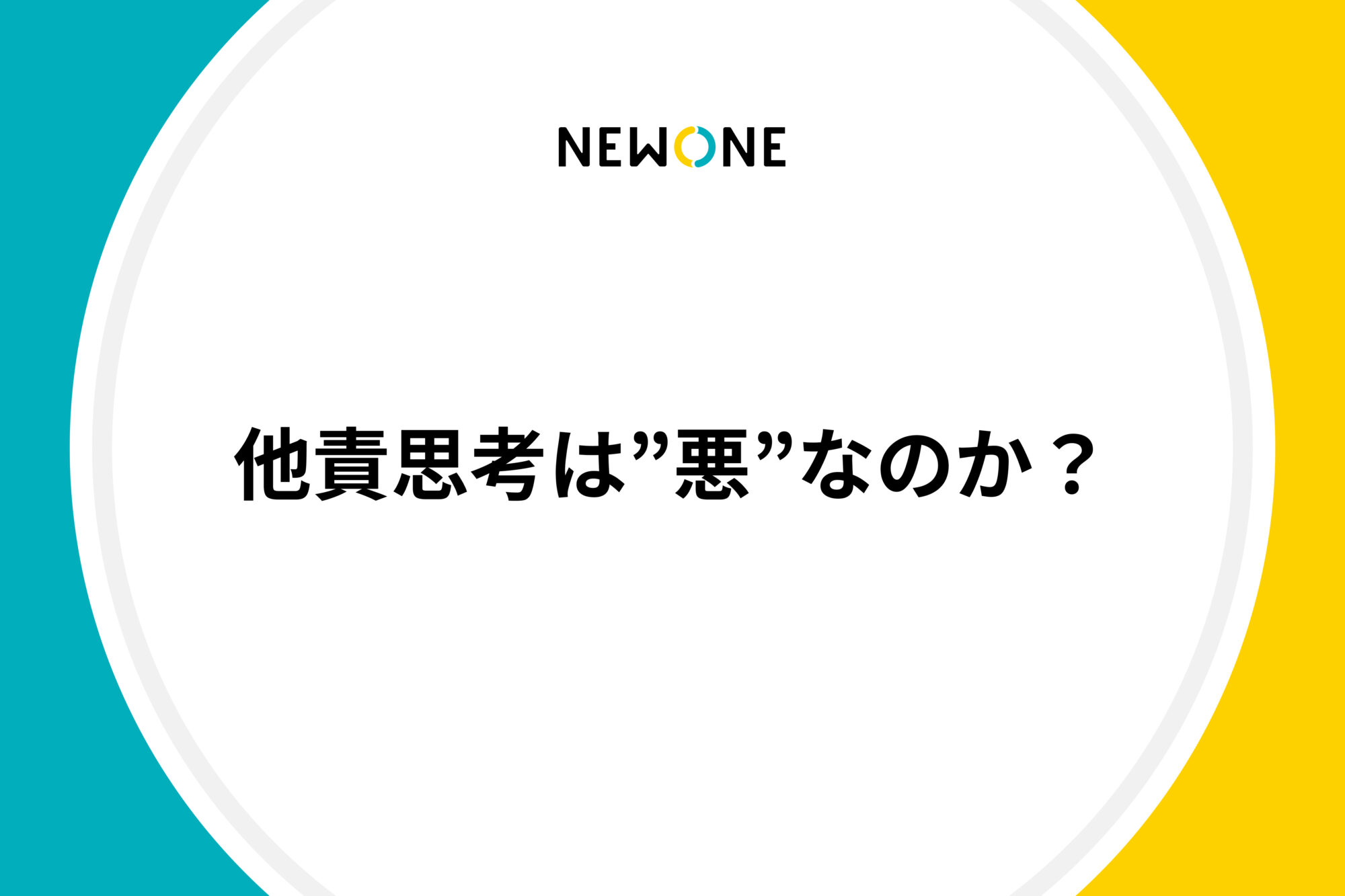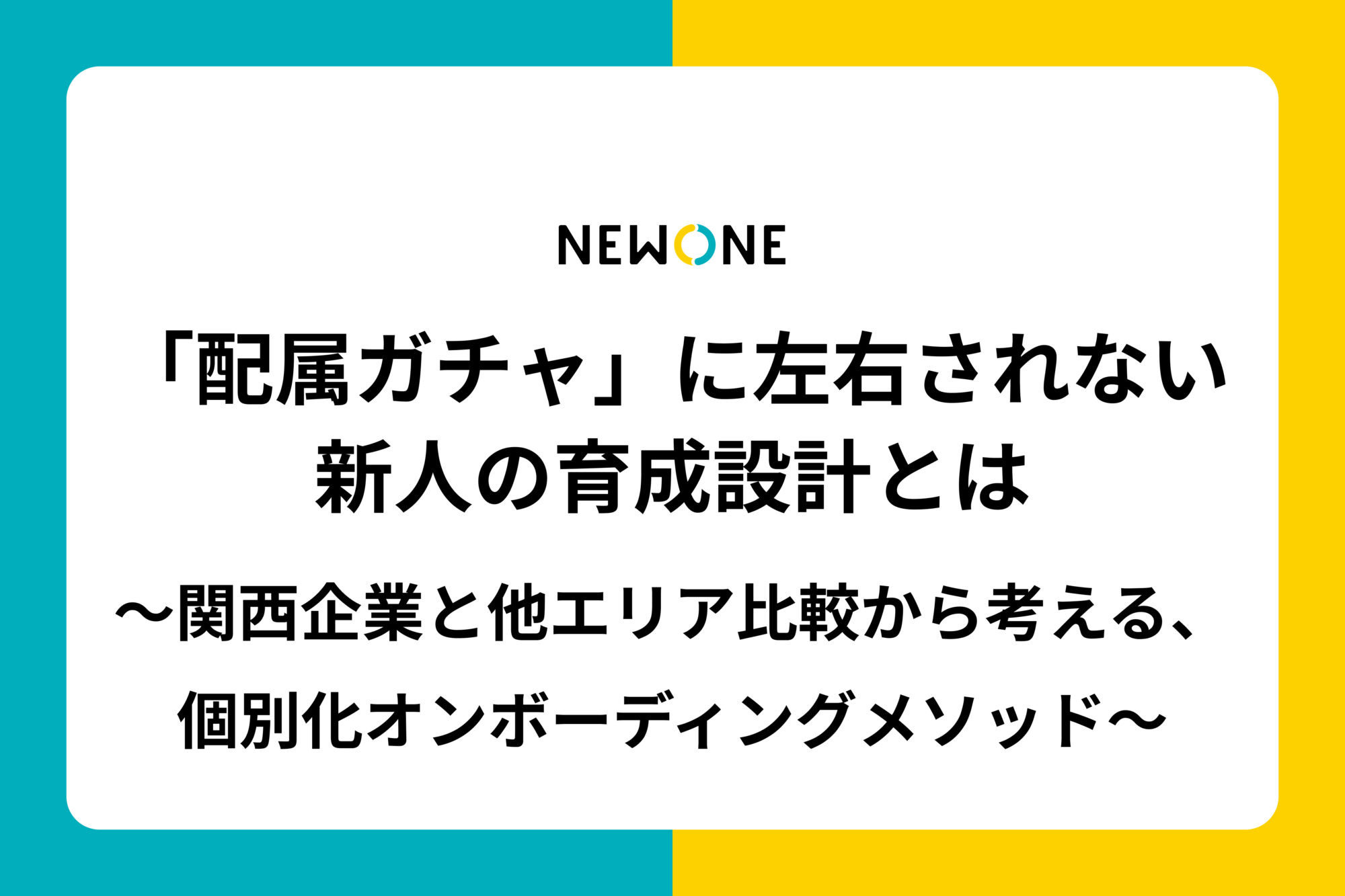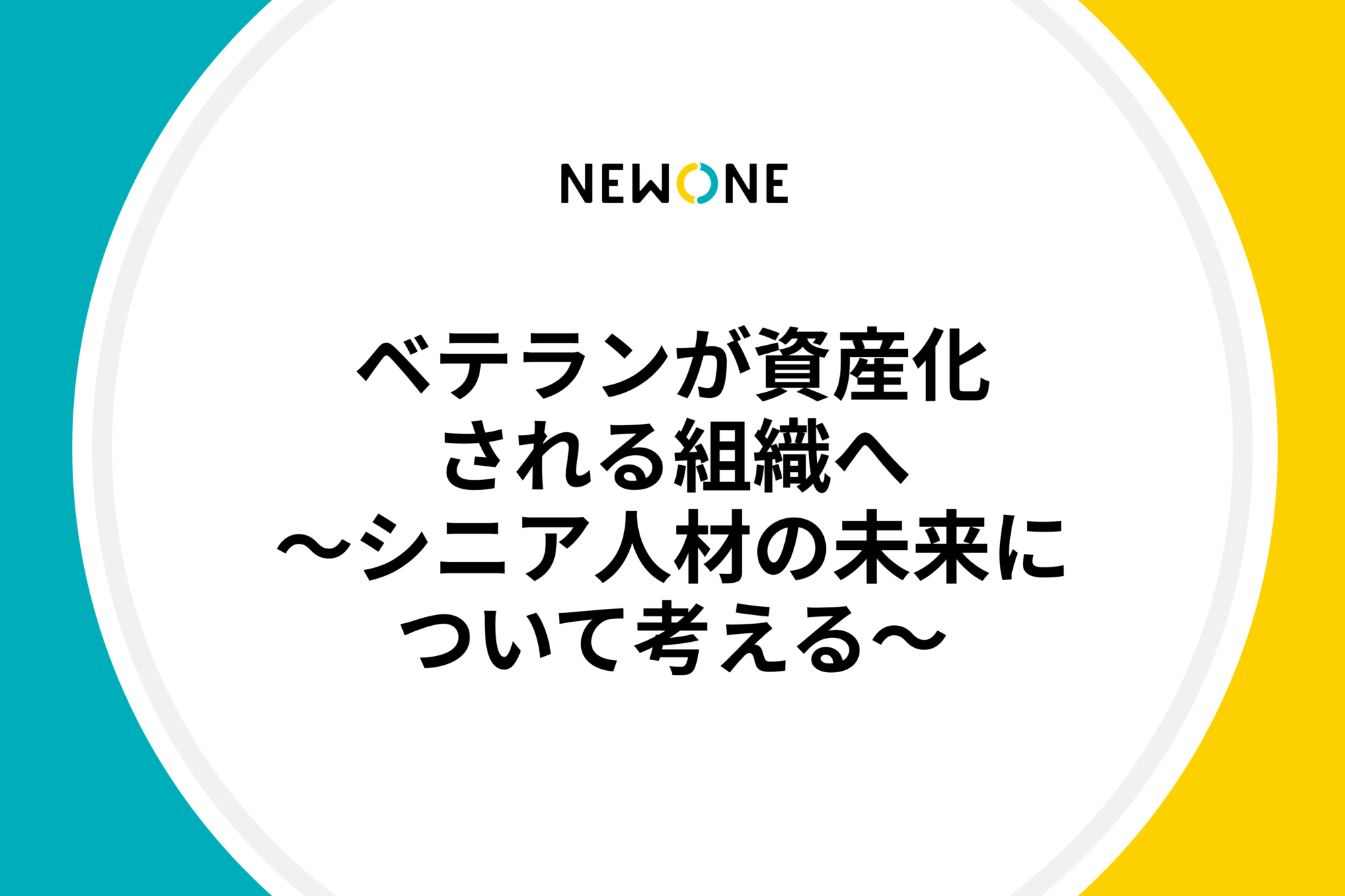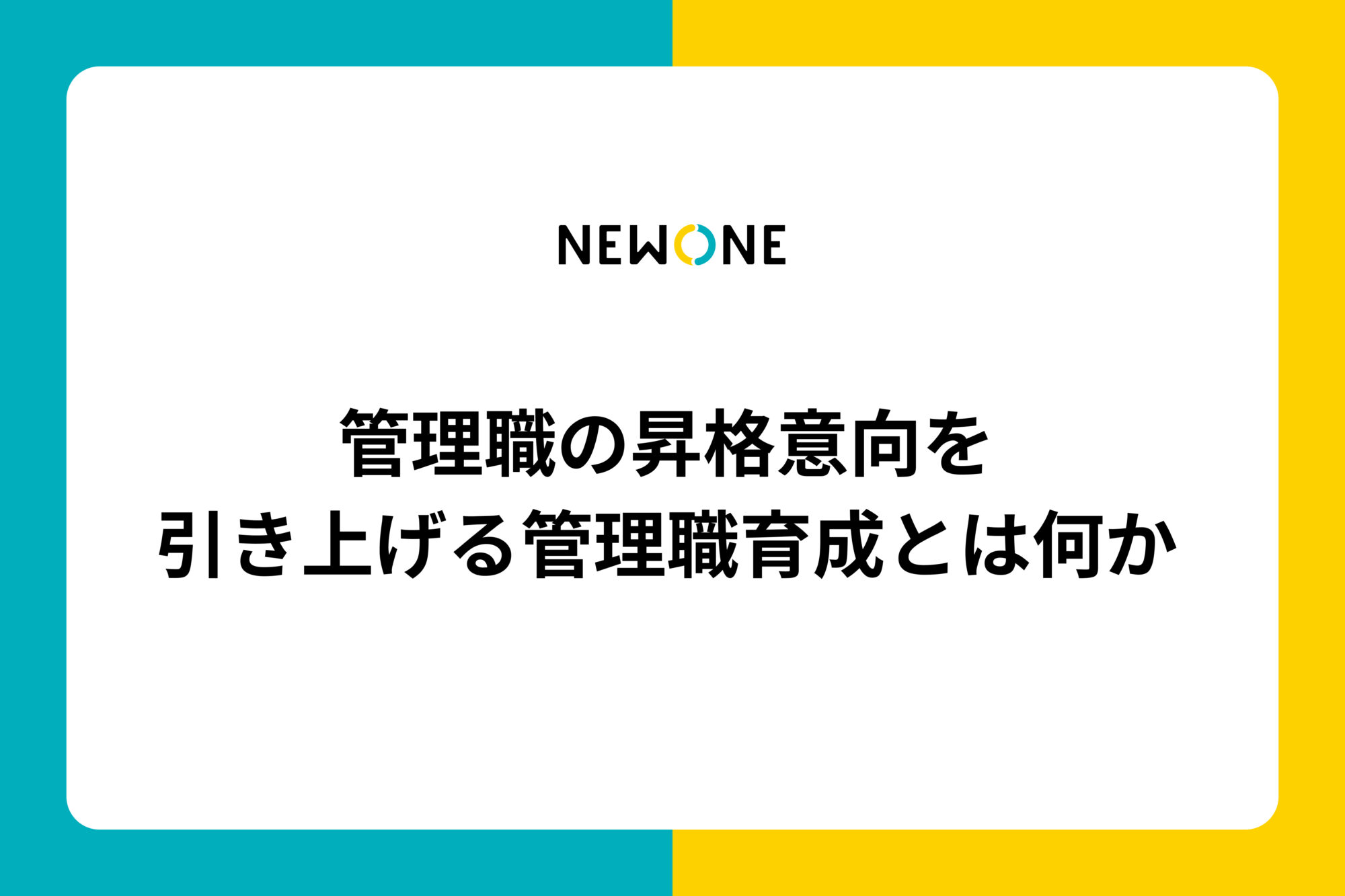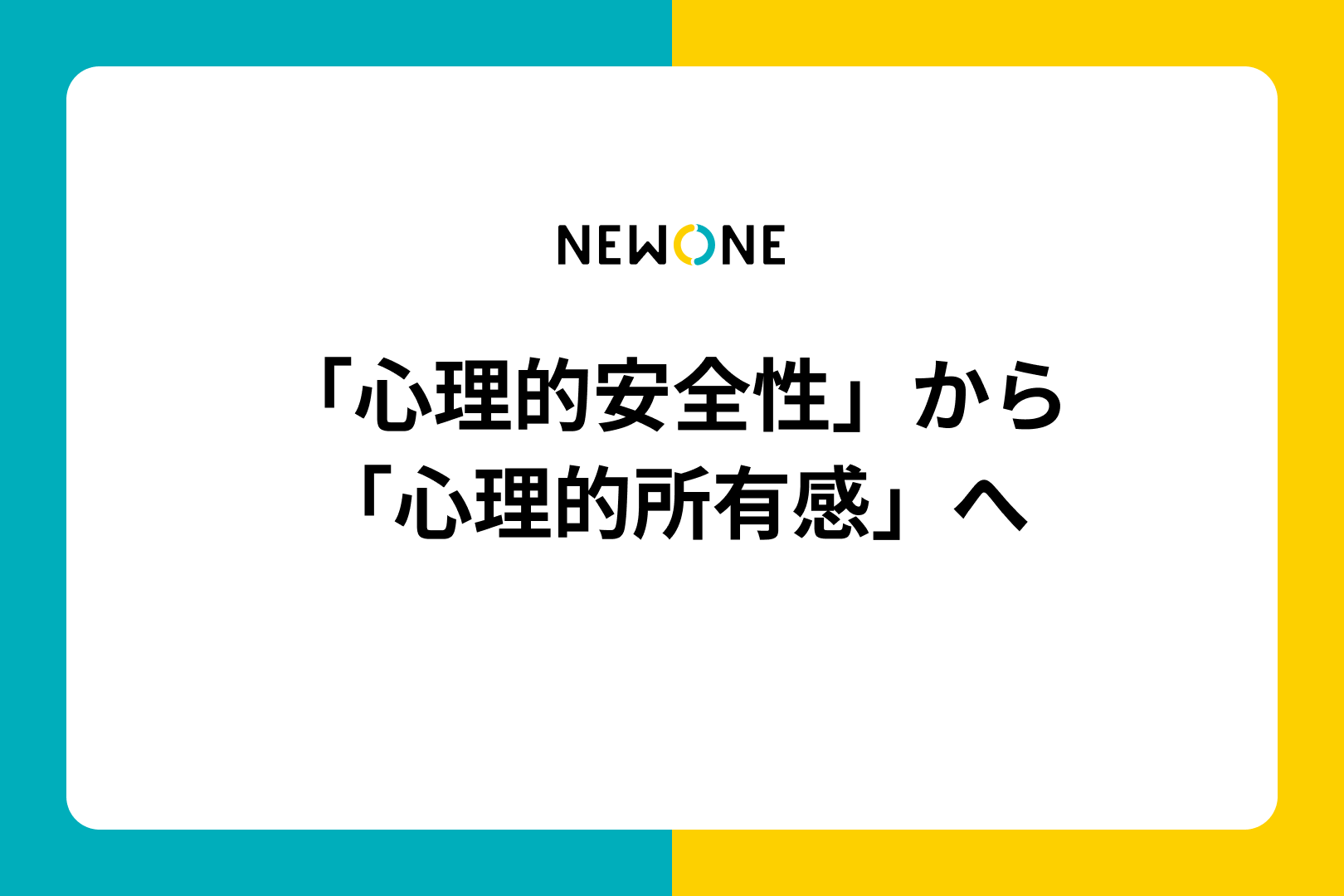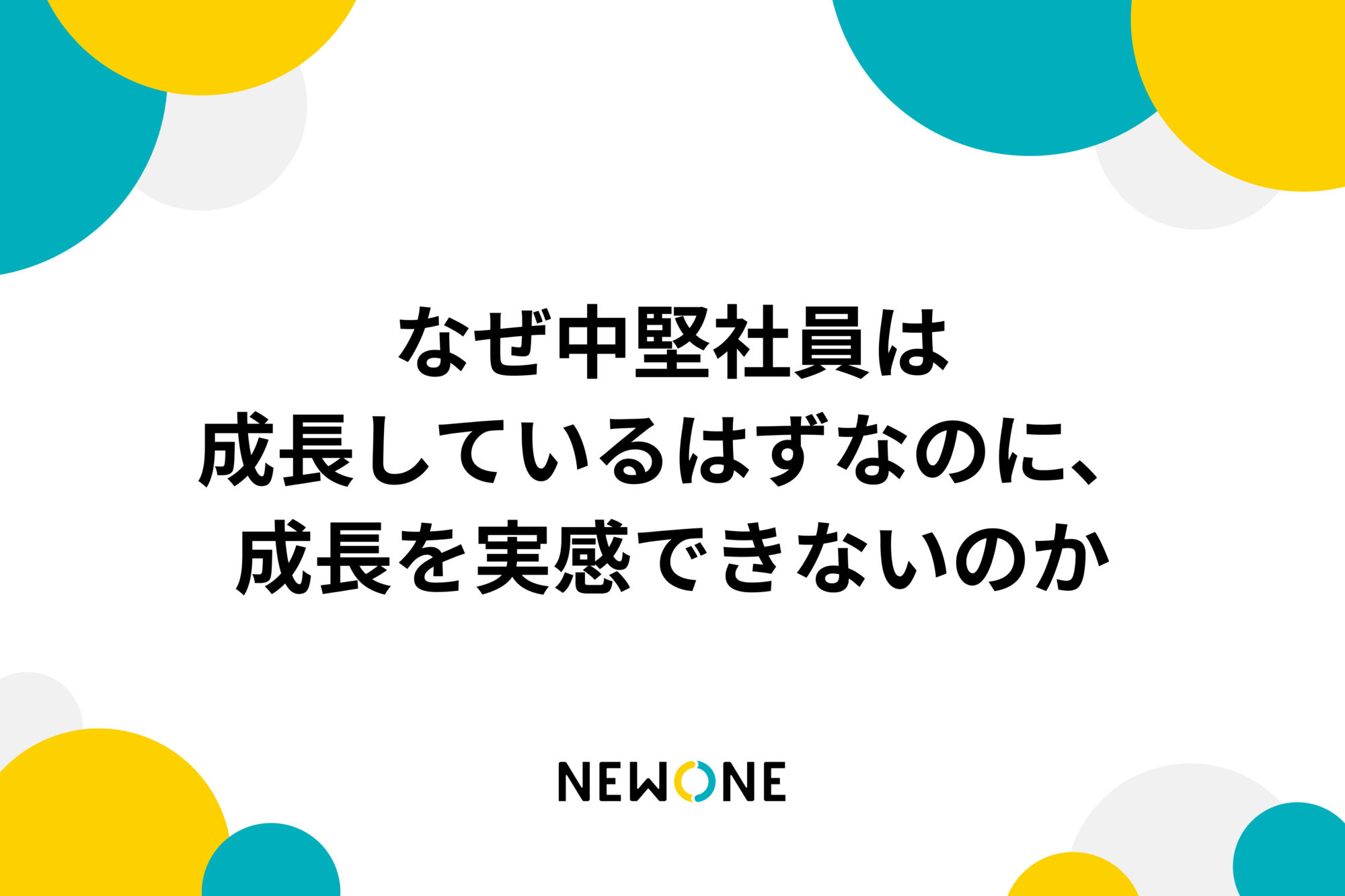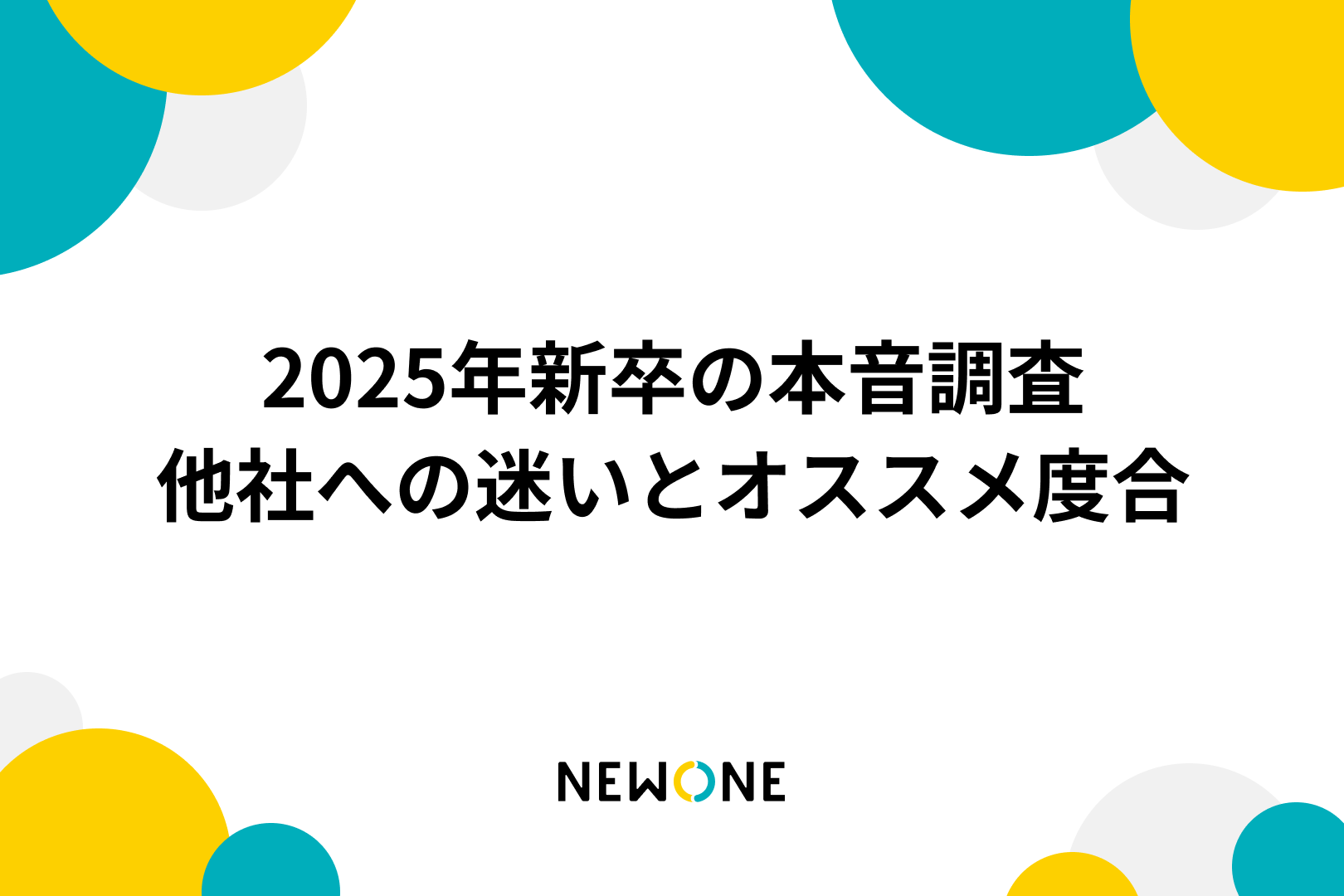
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
いよいよ4月になりました。
NEWONEでは、この3月に入社直前の学生200名強の方に、本音調査を実施しました。
人材枯渇時代と言われる昨今、企業側も新入社員を理解することがより大事となります。
「現段階で、他の会社を選択しておけば良かったという気持ちはありますか」
という問いに、63.2%の学生は、”迷いはない”と言い切れない入社前ブルーを感じる中で、
調査レポートの内容を一部まとめてみたいと思います。
自社をオススメしたいと思う人の割合は?
人にオススメしたくなるということは、入社した企業に対するエンゲージメントが高いとも言え、
そういった人材がどのような特徴があるのかを分析してみました。
結果、入社する会社を人にオススメしたいかを聞くと、とてもそう思うが19.9%であり、
それ以外の人は、心のどこかに、オススメへのブレーキがあることが見て取れます。
ちなみに、オススメする人の属性の傾向としては、
- 男性よりも女性の方が多い傾向
- 他府県より東京勤務予定の人
- 従業員1000名以上の企業所属
が見て取れます。
また、オススメする人の採用プロセス面から見た特徴としては、
- 初期接点での段階で、「元々知っていた」「広告で認知」し、自ら申し込みを行った。
- 内定受諾のタイミングでは、3月までに内定受諾した人(早期選考)の割合が高い。
- 入社決定理由について、仕事内容だけでなく「組織風土や働いている人への共感」が影響している。
- 内定後のフォロー施策について、フォロー施策の満足度がオススメ度合いに直結する。
が見て取れます。
上記の情報を参考に、自社の新入社員がどうなのかを想像してみましょう。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
オススメできる職場(推せる職場)の効果とは
オススメできる人とそうでない人で比べると、
入社する会社や職場に対して、自分自身が積極的に貢献したいですか
で、17.0%→68.3%と上昇する傾向
入社する会社は、自分自身が望む成長ができそうな会社ですか
で、15.2%→80.5%と上昇する傾向
入社する会社に、どのくらいの期間、所属しようと思っていますか
で、長く働きたい人が78.8%→92.7%と上昇する傾向
現段階で、他の会社を選択しておけば良かったという気持ちはありますか
で、迷いがない人が30.9%→61.0%と上昇する傾向
「職場への積極的な貢献意識」「将来への成長期待」「長期就業意向」「他社との迷いの少なさ」で効果があることが見て取れます。
▼レポートの詳細▼
https://oserushokuba.jp/report/freshers-202504-01
入社した人のオススメ度を高めるために
実態だけを見ると、新人にいろいろ与えなければと思いがちですが、
“推し活”を参考にすると、“推し活”とはただあこがれるという心理状態よりも、対象に対して心理的所有感があり、参画できる感覚が大事だと言われています。
すなわち、お客様意識ではなく、自分も組織に貢献していけるのだという手ごたえを感じることが大事です。
なので、新入社員ならではの意見を尊重したり、組織に関与できている感覚をしっかりと得てもらう工夫をしたりすることが、オススメ度を高める上で重要です。
また、従業員体験(EX)としてみても、体験以上にどのような感情を得られたが大事であり、
入社~配属~貢献の間に、高揚感や成長期待感、連帯感などポジティブな感情を得られる機会をどう作るかが大事になってきます。
NEWONEでは、研修時から1年(or2年)間、新入社員や上司に定期的にアンケートを取ることで、
- うまくオンボーディングできているか
- 組織への定着や貢献実感が高まっているか
- 阻害要因があるとすれば何か
を明らかにするPANAIサーベイを無料で展開しております。
50社以上に実施したノウハウでアドバイスも可能ですので、 ご興味ある方、ぜひお声がけいただければと思っております。
 上林 周平" width="104" height="104">
上林 周平" width="104" height="104">