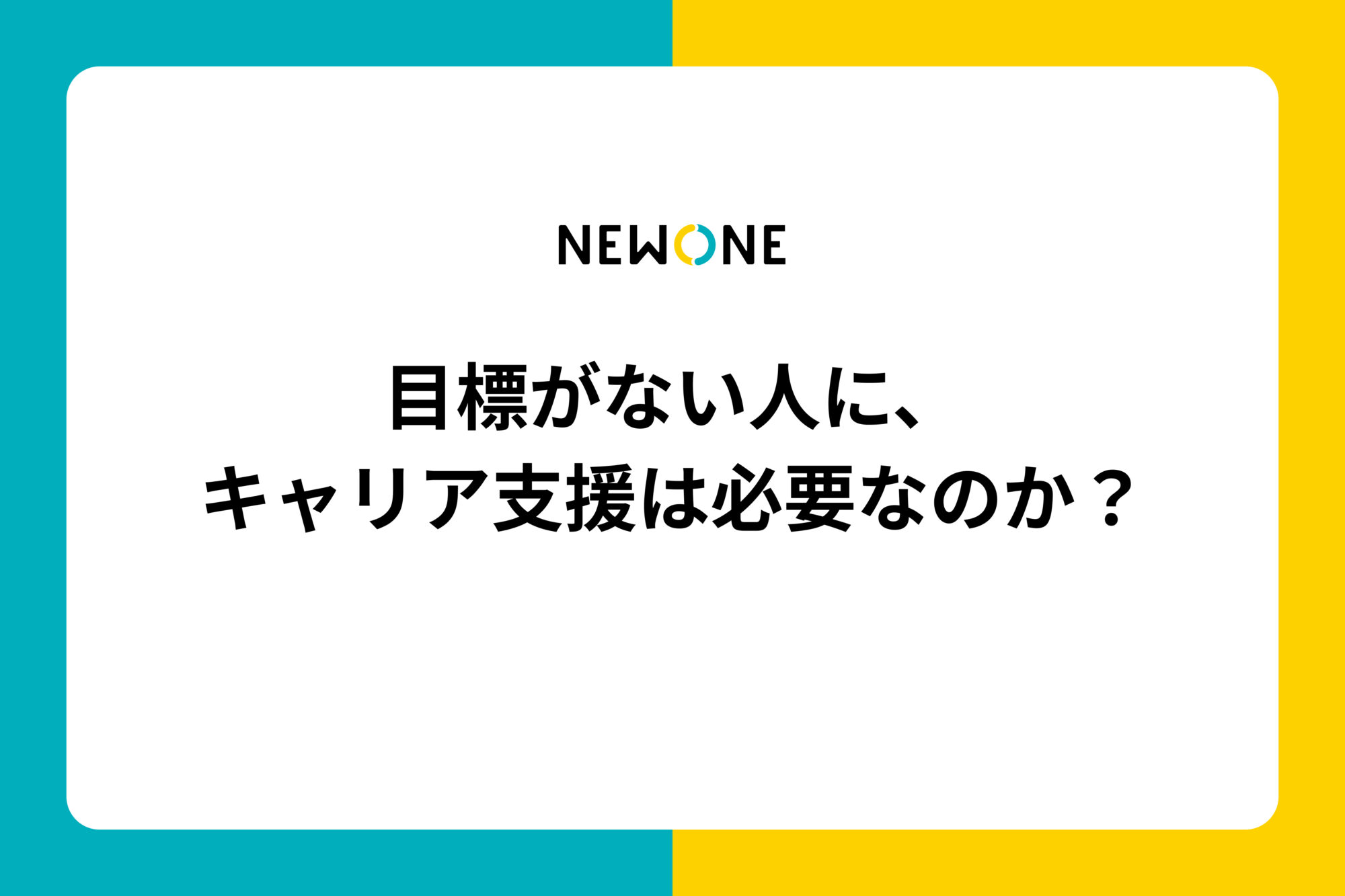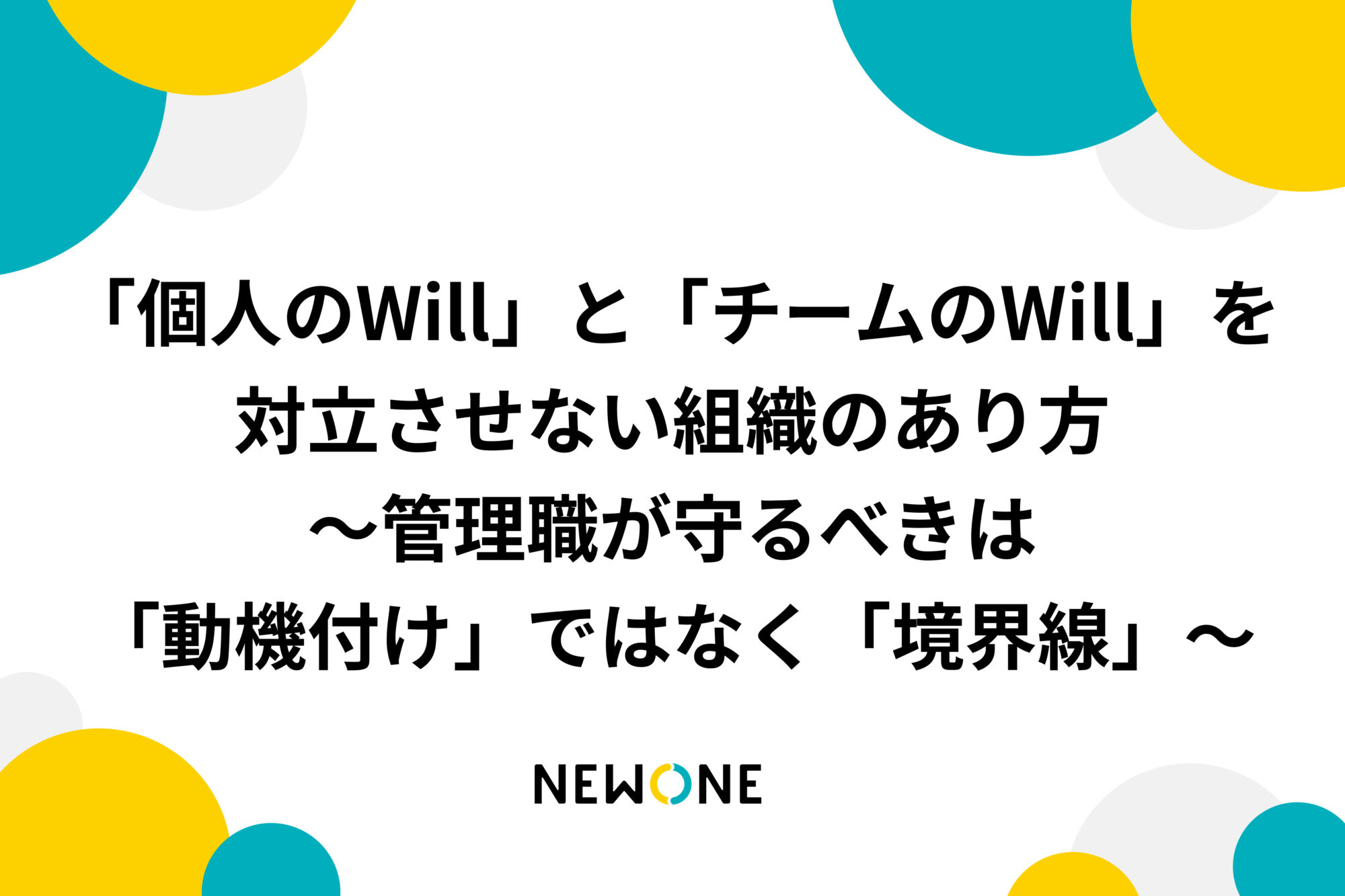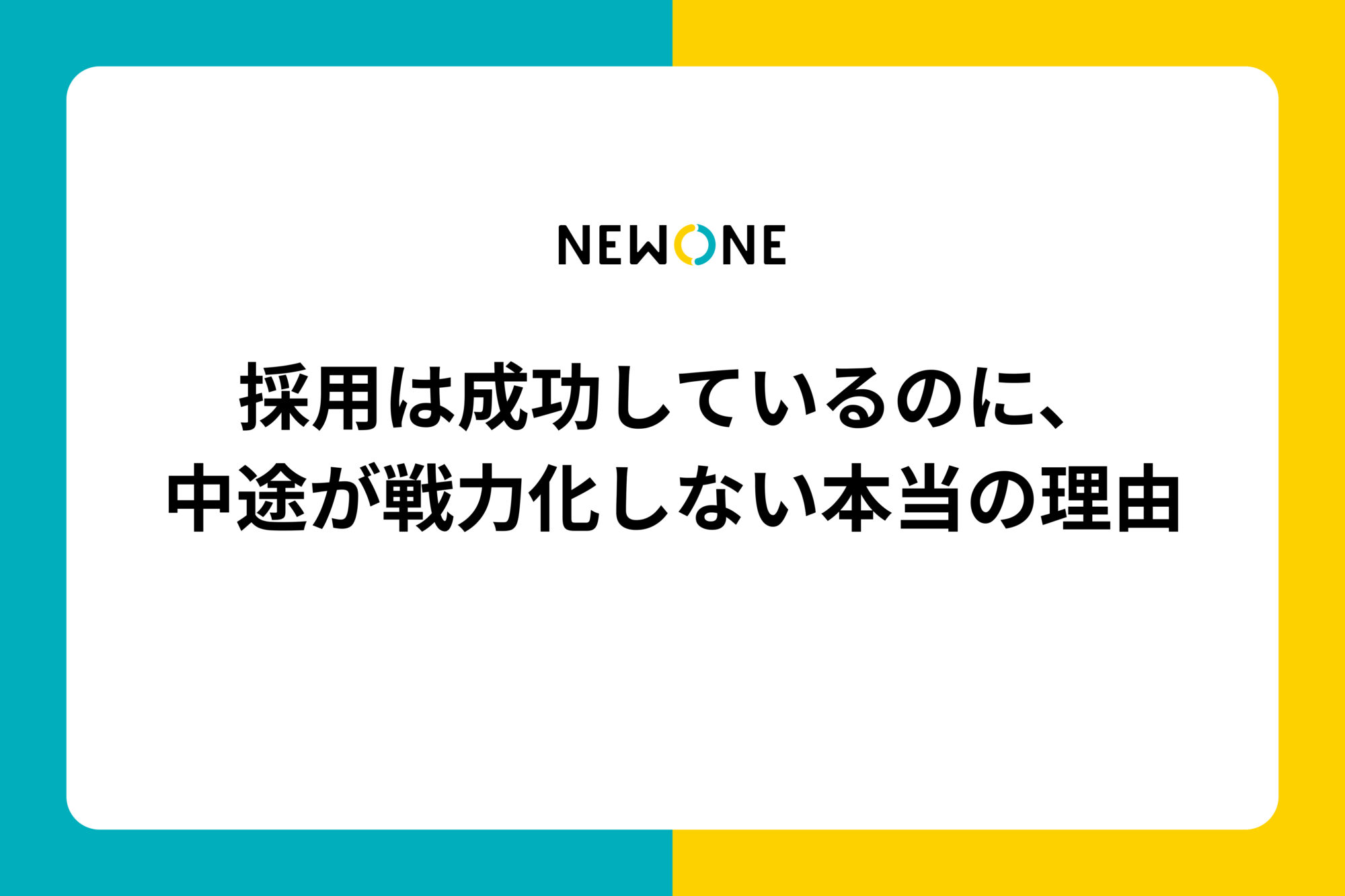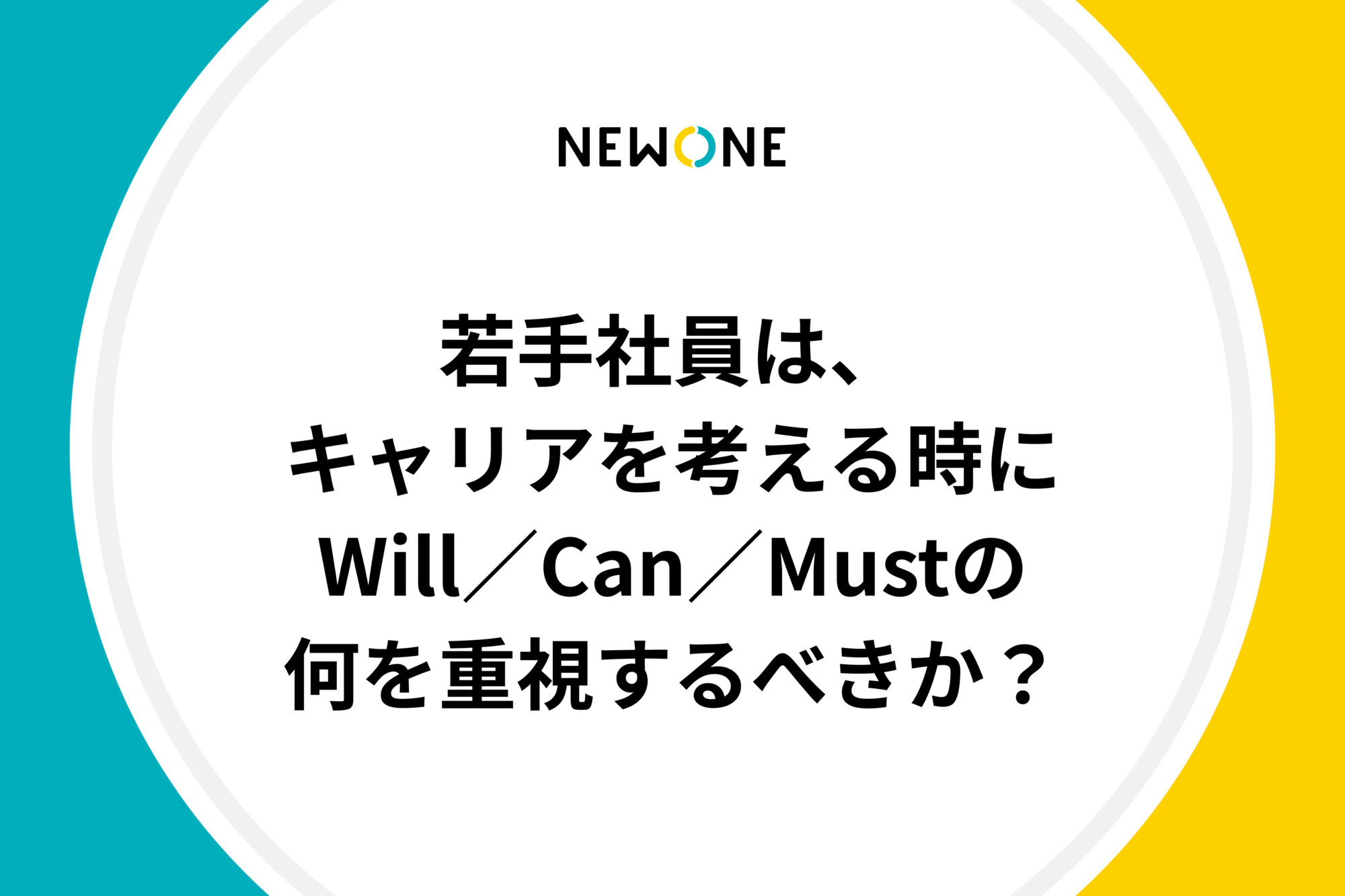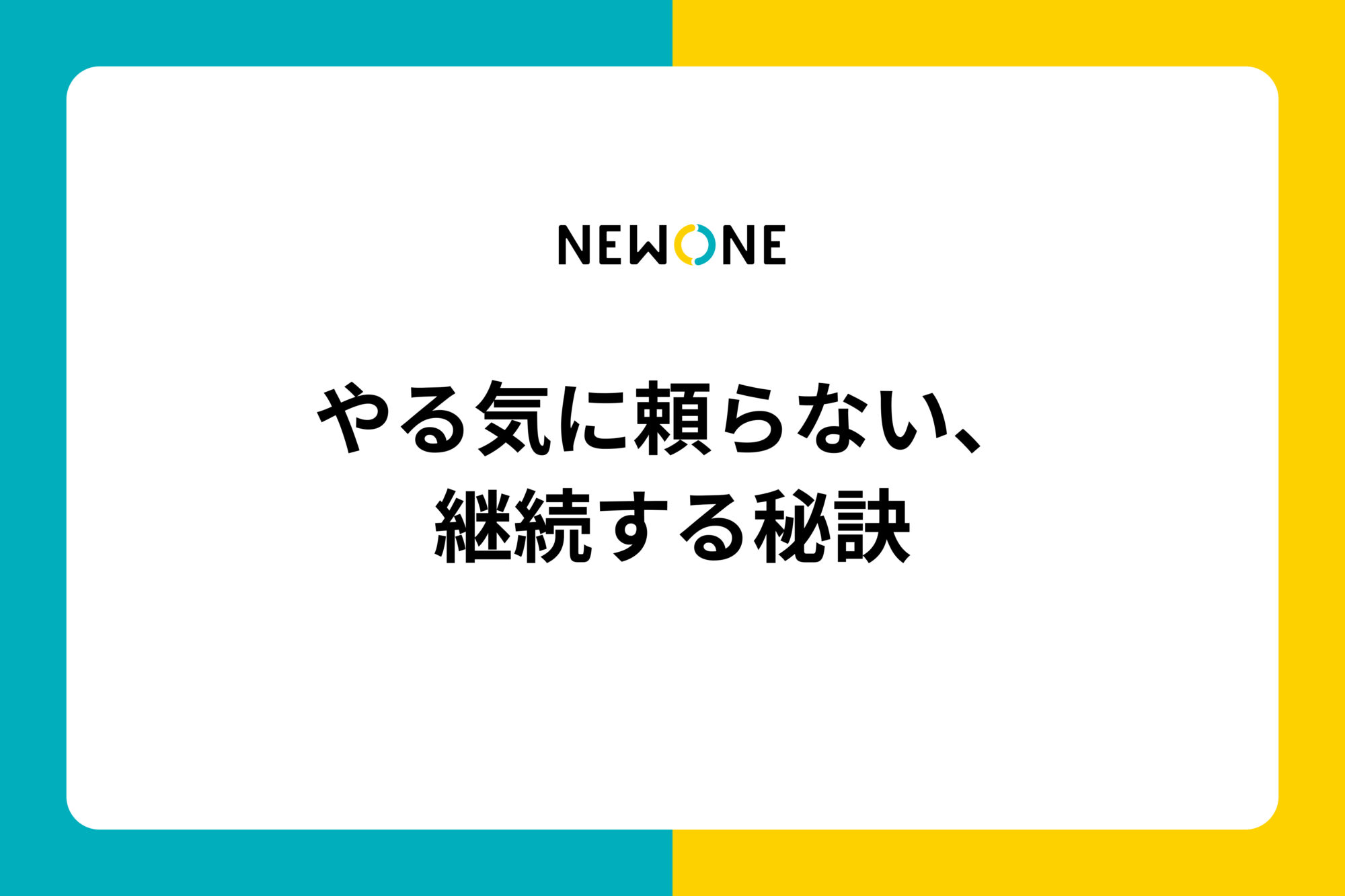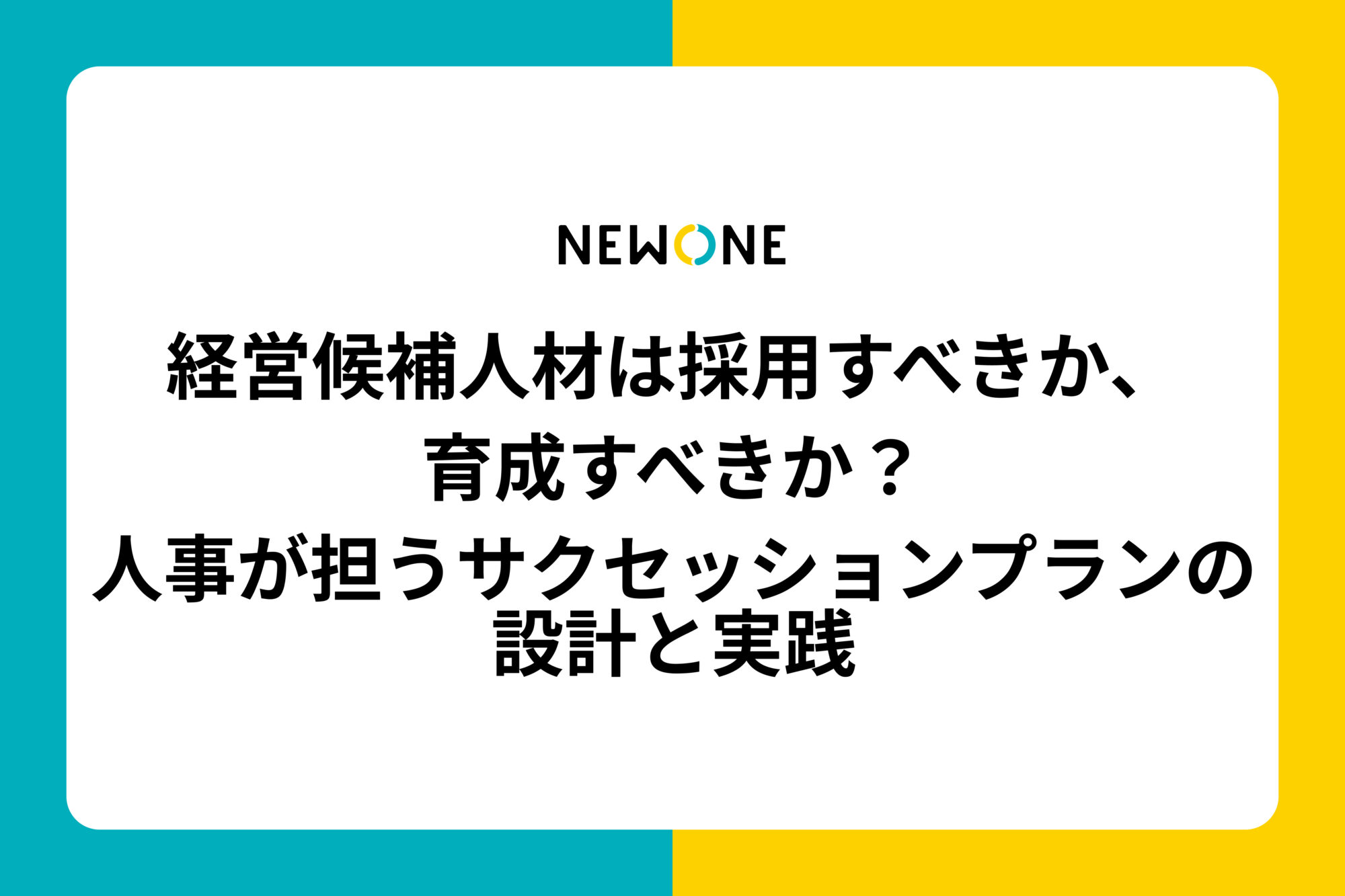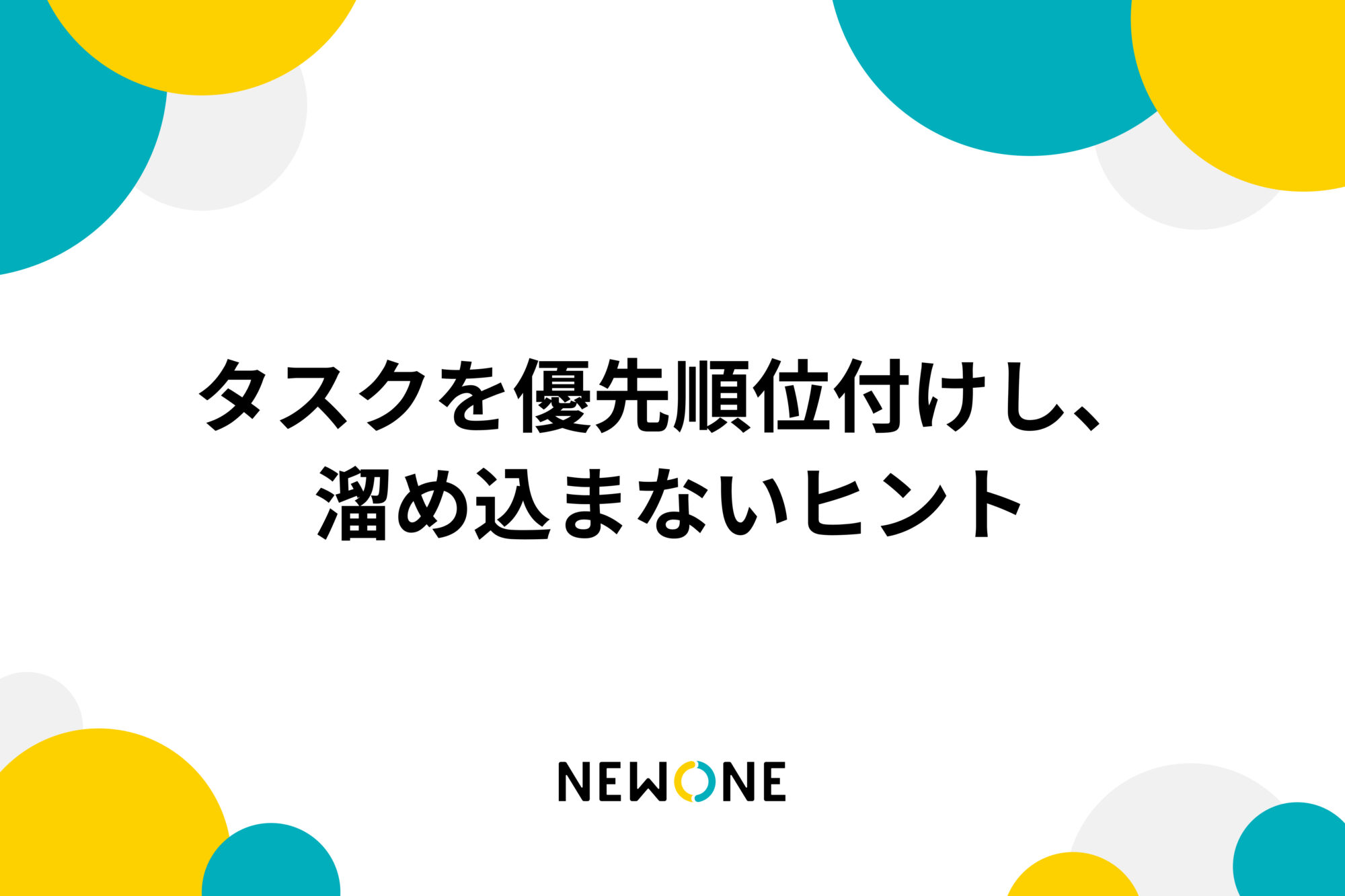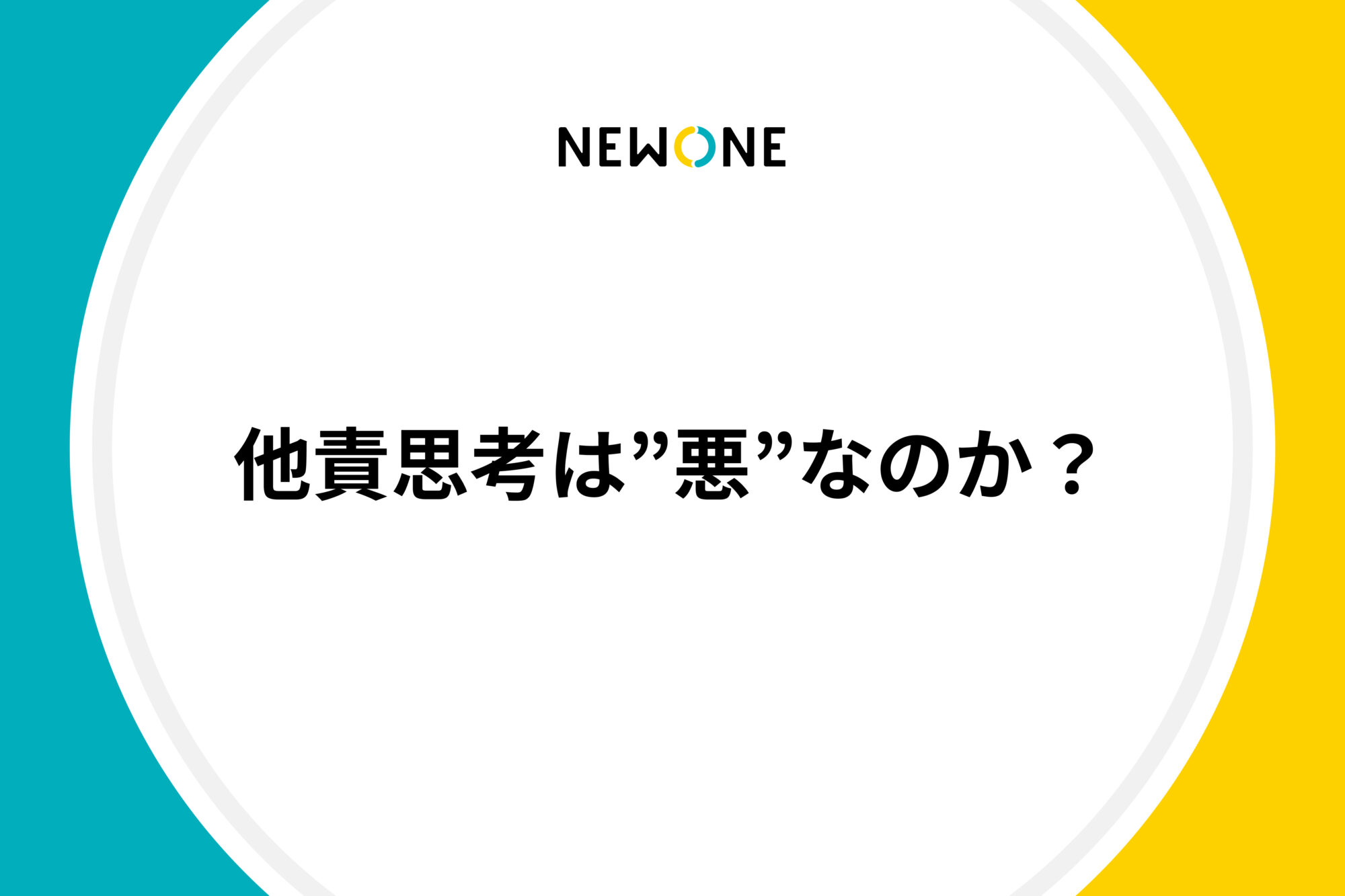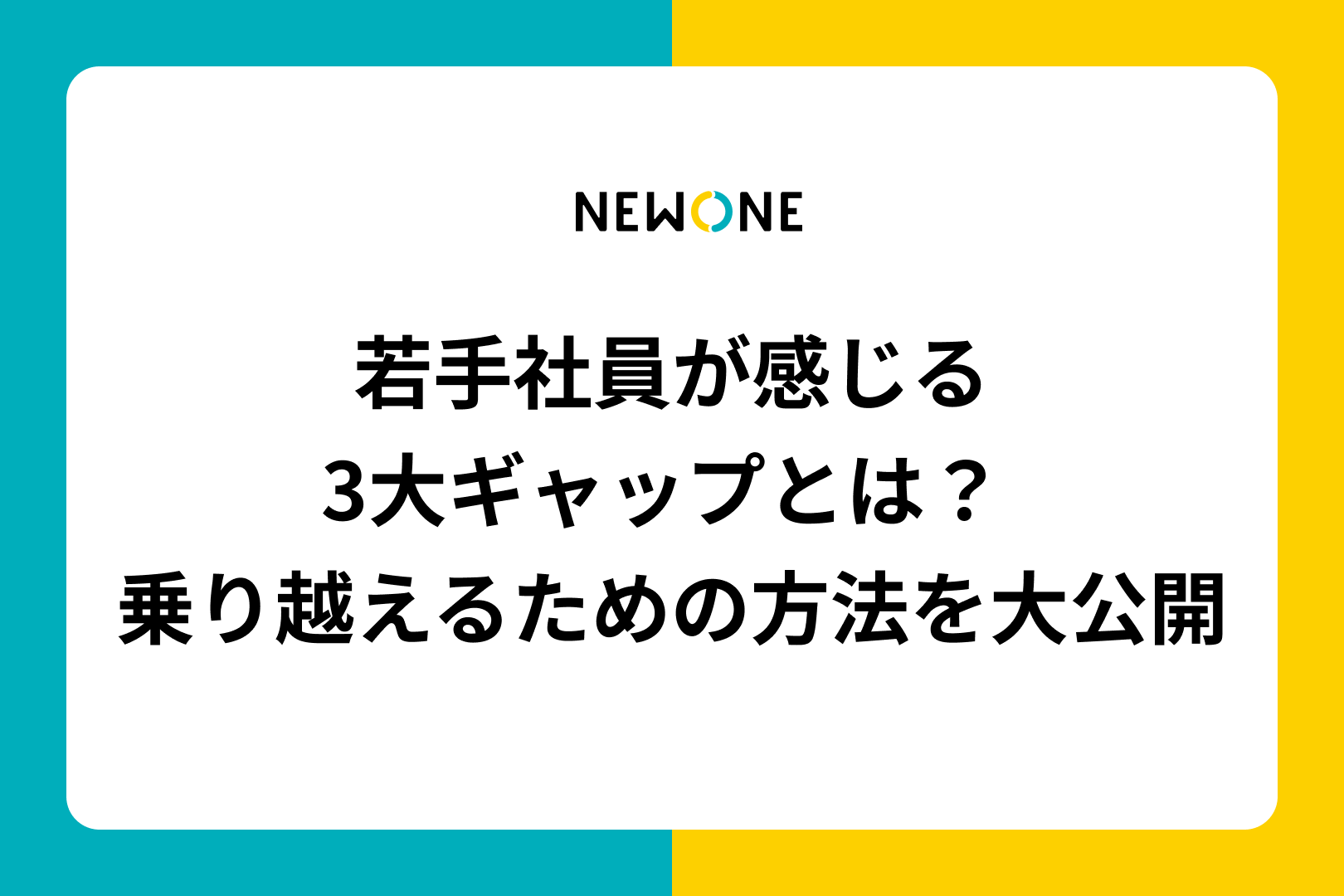
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
「若手がなかなか定着しなくて困っている…」
「どうしたら配属後も活躍してくれるんだろうか」
など、若手社員の育成やサポートは多くの企業が抱える課題です。
今回は、現場配属後に若手社員が感じやすい「3つのギャップ」と、その乗り越え方をご紹介します。効果的なアプローチを取ることで、早期離職の防止やエンゲージメント向上を実現しましょう。
若手社員が感じやすい3つのギャップには、以下のようなものがあります。
ギャップ① 仕事内容に対するギャップ
ギャップ② 自分自身に対するギャップ
ギャップ③ 環境に対するギャップ
それぞれのギャップの原因や影響と、それを乗り越えるための方法をご紹介していきます。
ギャップ① 仕事内容に対するギャップ
原因と影響
多くの若手社員が、入社前や配属前に思い描いていた「やりたい仕事」と、実際の業務内容が違うことに戸惑いを感じます。「希望していた職種ではない」「実際の仕事内容が単調に感じる」など、理想とのギャップからモチベーション低下に繋がることが多いです。やりたいことやビジョンを明確に持って入社してきた若手ほど感じやすいギャップです。
例)就職活動中は「この会社に入ってバリバリ営業をしたい」と思っていたのに、営業ではない部署に配属されたAさん。配属先の、目の前の仕事に意義ややりがいを感じられません。
一方、Bさんは希望通りの営業部配属ではあったけれども、自分が本当にやりたかった「大きな案件を動かす」ことに携われず、基礎的な資料作成や会議録の作成等を任される日々。自分がやりたかった仕事に日々の業務がどう紐づいているのか分からなくなってしまい、モチベーションが低下しています。
▶️こんなAさん、Bさんの悩みに対して、本人や周囲は何ができるでしょうか?本人視点の「乗り越えるためのポイント」と、周囲視点の「周囲のサポート方法」を見ていきましょう。
乗り越えるためのポイント
- 自己成長の機会と捉える:
仕事を「与えられるもの」ではなく、「自分の成長のための機会」として捉え直し、主体的に取り組む姿勢が大切です。
- 目的を見出す:
1つひとつの業務に対して自分なりの目的や意味を見つけることで、仕事に対する充実感が高まります。
周囲のサポート方法
- Whyを明確に:
仕事を渡す際に「なぜ自分がこの仕事をするのか」の目的を明確にし、若手社員が自身の成長と業務を結びつけやすいようにします。その仕事で得られる経験やスキルがどのように相手の目標ややりたいことに繋がるのかを紐づけるといった工夫をします。
- 強みを引き出す:
相手の強みや特性と関連付けながら仕事を任せることで、若手がその強みを発揮しやすい環境を提供します。
若手社員が主体的に環境を活かし、仕事に対するやりがいを自ら生み出すためのサポートとして、NEWONEではジョブクラフティング研修を提供しています。自身の置かれている環境を100%活用できるような意識やスキルの獲得を目指します。
また、そんな悩みを抱える若手社員のサポートをする周囲のために、OJTトレーナー研修を提供しています。若手社員の意欲を引き出せる育成担当者になれるよう、OJTトレーナーが自ら高いエンゲージメントを持ち、新入社員との関わり方を明確にイメージできている状態にします。
ギャップ② 自分自身に対するギャップ
原因と影響
学生時代には高いパフォーマンスを発揮していた若手社員も、職場に入ると「自分は何もできない」と感じやすく、自己評価が下がることがあります。結果として、周囲との比較による自己不安や、自分の理想と現実との乖離が、成長の妨げとなることがあります。これは、自分の能力や経験に自信を持っている若手ほど感じやすいギャップです。
例)学生時代、何でもそつなくこなしてきて非常に優秀なAさん。しかし入社後、長年の経験を積んできた優秀な上司や先輩と比較することで、優秀だった学生時代の自分と、圧倒的に能力不足な自分の現状との差に落胆します。
一方、合わないことはすぐにやめて、自分に合う他のものをすぐに探しにいく学生時代を過ごしたBさん。おかげで大抵のことは難なくできている感覚がありましたが、社会人の仕事はそうはいきません。「できない自分」と長い期間対峙し続ける中で、自信を喪失していきました。
▶️理想と現実の違いに苦しむAさん、Bさん自身は何ができるでしょうか?周りはどんなサポートができるでしょうか?
乗り越えるためのポイント
- 成長は段階的であると認識する:
最初からすべてを完璧を目指さず、経験を積んで成長する姿勢を育むことが大切です。仕事を任せてもらえると、最初から先輩たちのように円滑に仕事を進めて高い基準の成果を出したい、と考えがちですが、人は誰しも初めてのことに取り組むのは難しさを感じます。ある日突然完璧にできるようになるのは難しく、算数の学習のように段階的に新しい経験や知識を経て人は成長していきます。
- 自分の現在地を知る:
「今は未熟でも、経験を積むことで成長していける」という意識を持つことが大切です。社会人は、学校教育と異なって幅広い経験値の人が身近にいるからこそ「自分の無力さ」にギャップを感じてしまうことも多くあります。まずは「自分にはできない事がある」、と素直に正しく今の状況を認め、周囲の先輩や上司から学ぶ、という姿勢に立つことが重要です。
周囲のサポート方法
- 期待と成長のビジョンを共有:
仕事の依頼時に期待されるスキルや目的を伝え、業務を通じてどのような成長が期待されているかを明確にします。
例)文書作成の依頼をする際に、「この文書を来週中に作成して下さい」と伝えるだけでなく、「この文書を来週中に作成して下さい。作成を通して、文書作成スキルだけでなく自分でスケジュールを立てる、というスキルの向上も目的にしているから、そのつもりで進めてね」と伝えるのとでは、相手に渡している期待、この仕事を進める目的の設定が異なります。仕事を渡された若手も「文書を作成する」ことが期待なのではなく、「文書を作成する中でスケジュール管理のスキルを向上させてほしい」という期待を認識し、意識することができます。
- 成長の可視化:
成果物のフィードバックでは、スキルの伸びしろや今後の成長ポイントを具体的に示し、若手が成長の手ごたえを感じられるように支援します。その結果、若手自身が成果物だけで自分の成長を評価するのではなく、スキルやスタンスの成長にも目を向けやすくなり、自己成長の手ごたえを掴むことにつながります。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
ギャップ③ 環境に対するギャップ
原因と影響
若手社員は、理想の人間関係や上司との関係が現実と違う場合にギャップを感じることがあります。特に人間関係を重視するタイプは、コミュニケーションの少ない職場や期待する関係が築けない環境で疎外感を覚えやすいです。このギャップは特に、上手く関係構築ができなかったり、上司との関わり方が自分の理想と乖離している、といった状況において生じます。
例)今までは物腰の柔らかい、優しい上司のもとで働いてきたAさん。新しく配属されたチームの上司は厳しくぶっきらぼうな人でした。Aさんは内心、関係構築ができていない上司の部下との関わり方に不満を抱いていました。
▶️こんな場合でも、周囲のアプローチだけでなく、Aさん自身にもできることがあります。
このギャップを乗り越えるためには、若手、組織双方からの主体的なかかわりを引き出し、オンボーディングを円滑に進めることが鍵です。
乗り越えるためのポイント
- 環境依存ではなく、環境活用:
若手社員が主体的に環境を活用する姿勢を持つことが大切です。環境のせいにせず、自分で行動できるポイントを見出すことで、自立した対応力が身に付きます。
例)先ほどの、上司の関わり方への不満を抱えるAさん。「上司が悪い」ではなく、「自分から心を開いて話しかけてみようかな」「言葉は厳しいけどフィードバックの内容は勉強になるし、もっと貰いにいって成長機会にしよう」など、状況を前向きに捉え直すことで、状況が好転します。
周囲のサポート方法
- 自己決定を促す:
若手に業務の進め方やスケジュールを自分で決める機会を与え、自己決定を促し、「環境を活用する力」を育てます。
- 主体的な関与を引き出す:
上司側は若手社員が主体的に行動するようサポートし、組織として積極的に受け入れる体制を整えます。
- オンボーディング支援:
若手の主体性を引き出すためのオンボーディング支援を通じて、環境への適応と成長を後押しします。
オンボーディング支援におけるポイントに関してはこちら
若手社員が「環境をどう活かすかを自分で決められる」と気が付くように関わることで、彼らが受け身ではなく、主体的に行動しようとする意欲を引き出せます。
まとめ
若手社員が感じやすい「仕事内容・自分自身・環境」に関する3つのギャップとその乗り越え方をご紹介しました。これらのギャップは、特に入社半年から2〜3年目の社員が直面しやすく、早期の対応が重要です。状況を早期に察知し、適切なサポートを行うことで、社員のモチベーションや定着率の向上が期待できます。
このような課題解消には「新入社員フォローアップ研修」も効果的です。研修を通じて、複数の観点から自身と仕事や職場との「つながり」を確認する機会を提供することで、若手社員が主体的に成長し、安心して活躍できる環境を整えることが可能です。株式会社NEWONEでは、「すべての人が活躍するためのエンゲージメント」をブランドプロミスとして、研修やコンサルティングサービスを通じて企業の成長を支援しています。若手社員の定着や育成に課題を抱える企業様は、ぜひ私たちのサービスをご検討ください。
 青木 美奈" width="104" height="104">
青木 美奈" width="104" height="104">