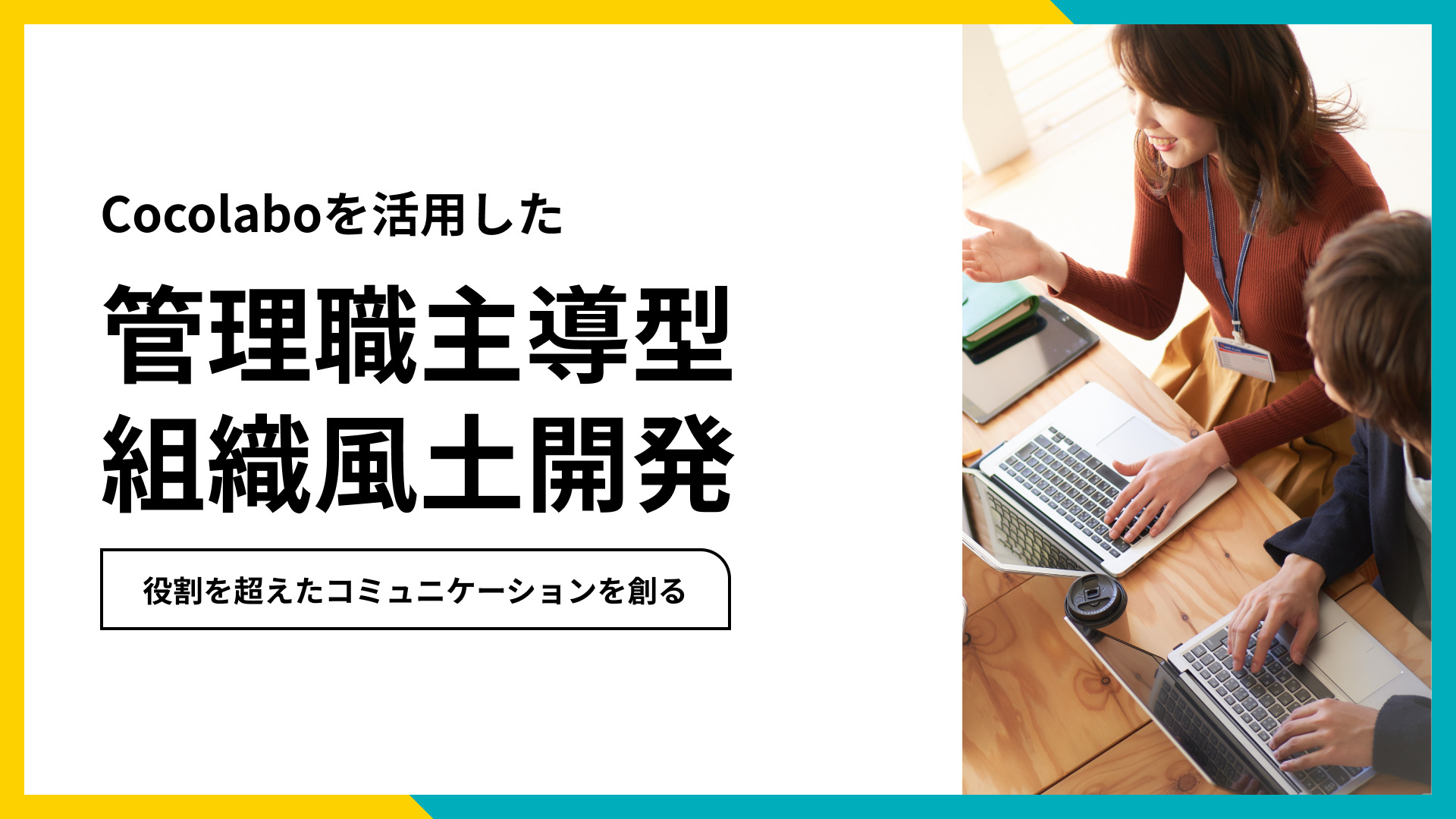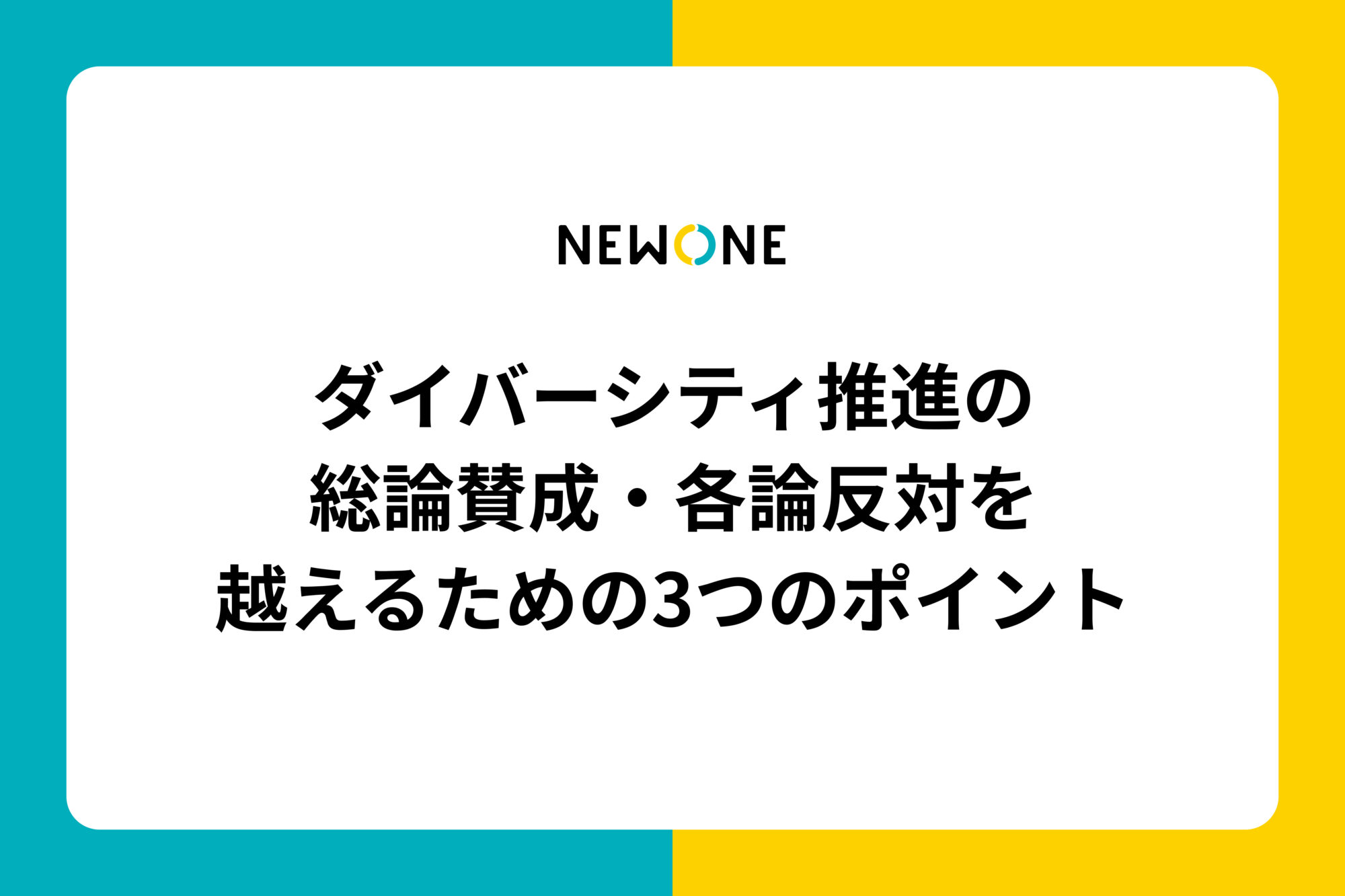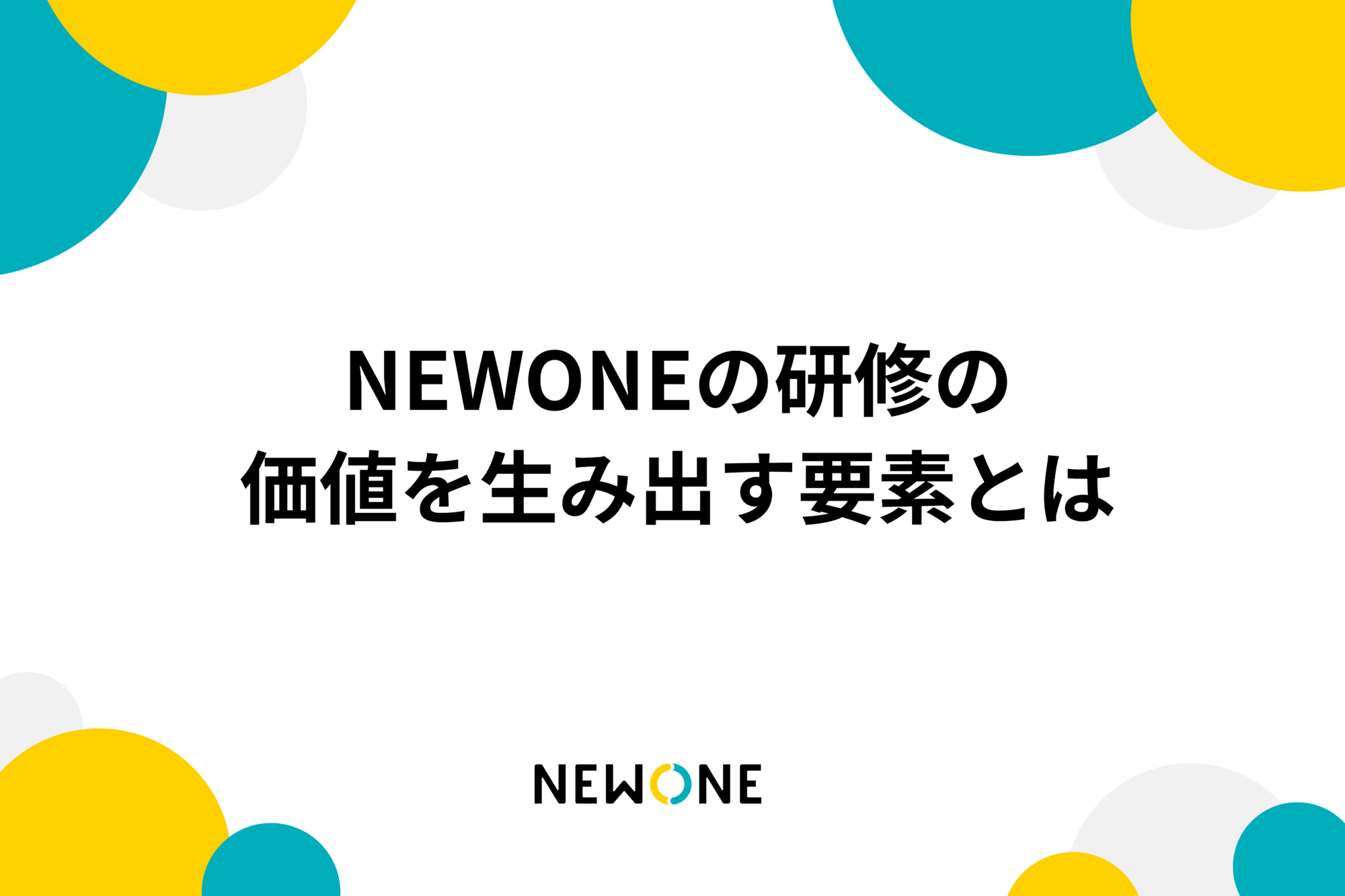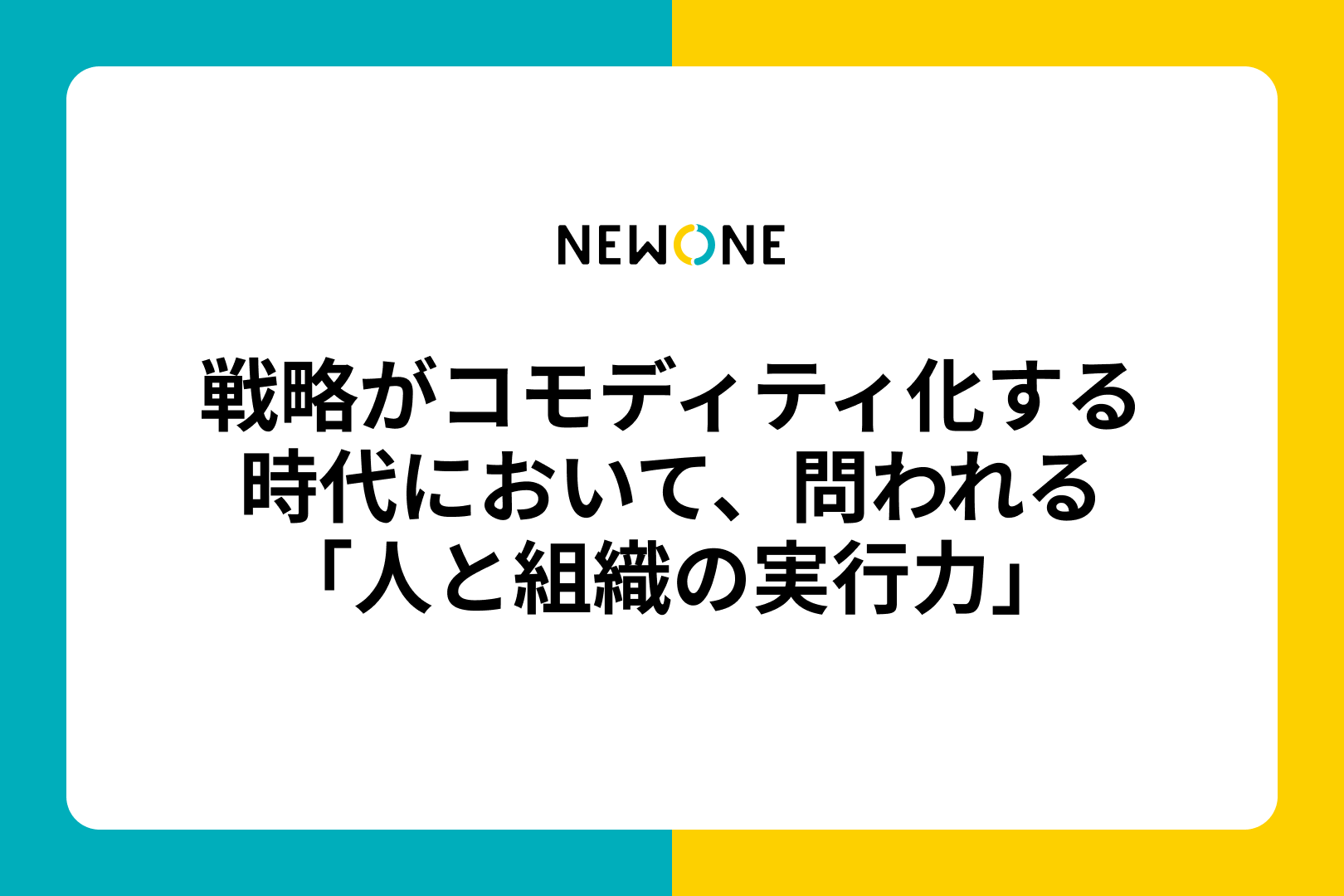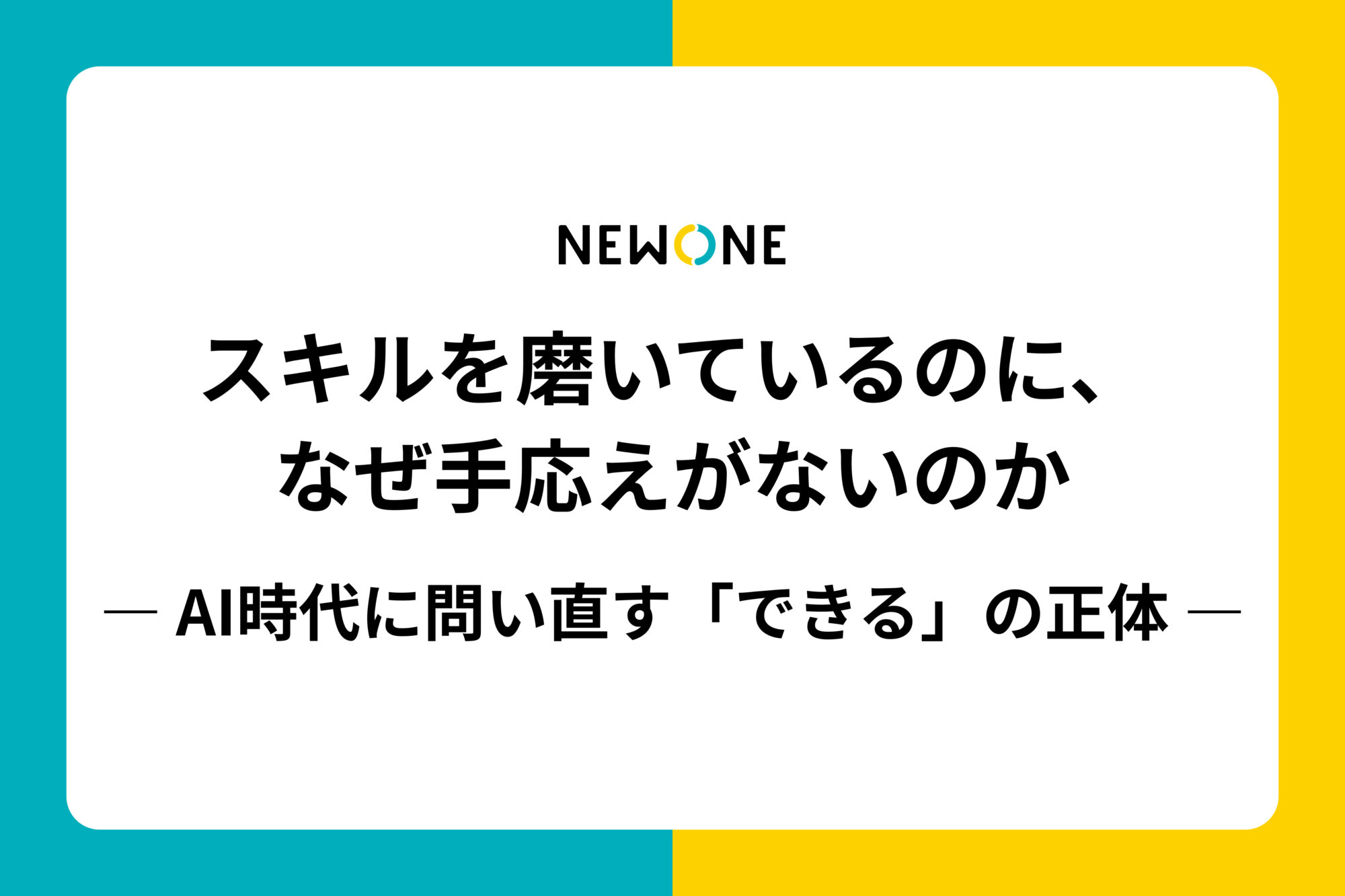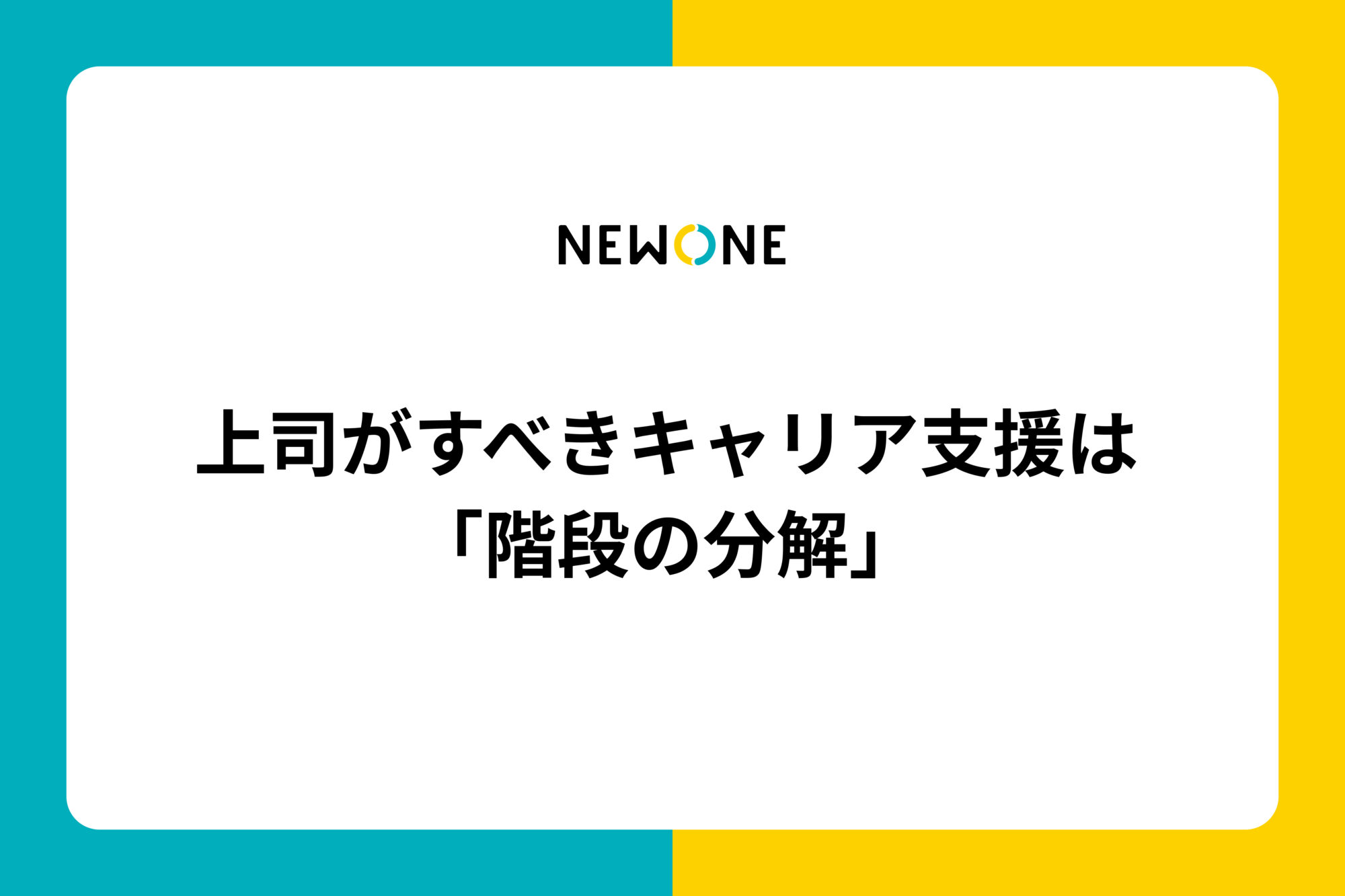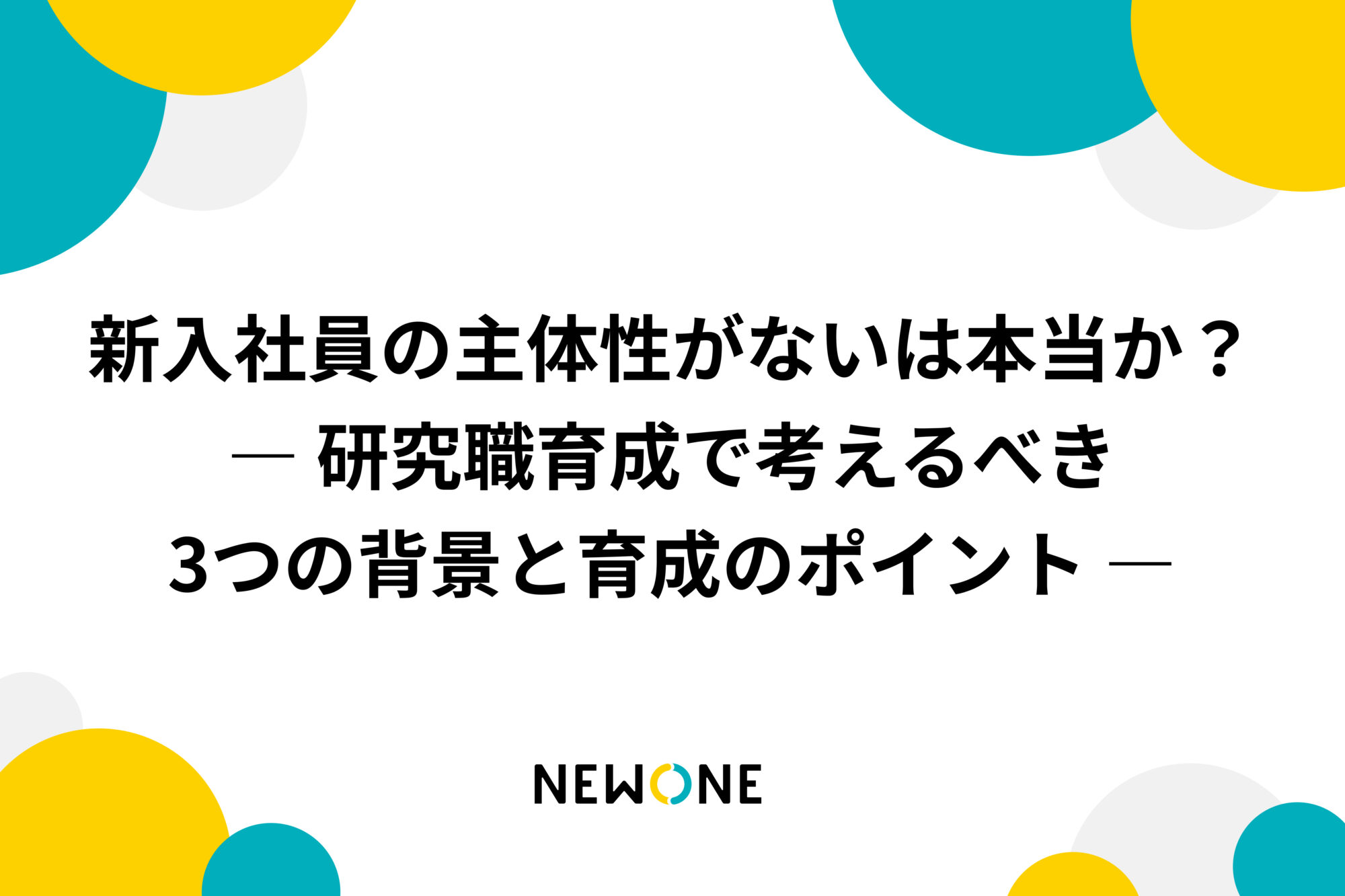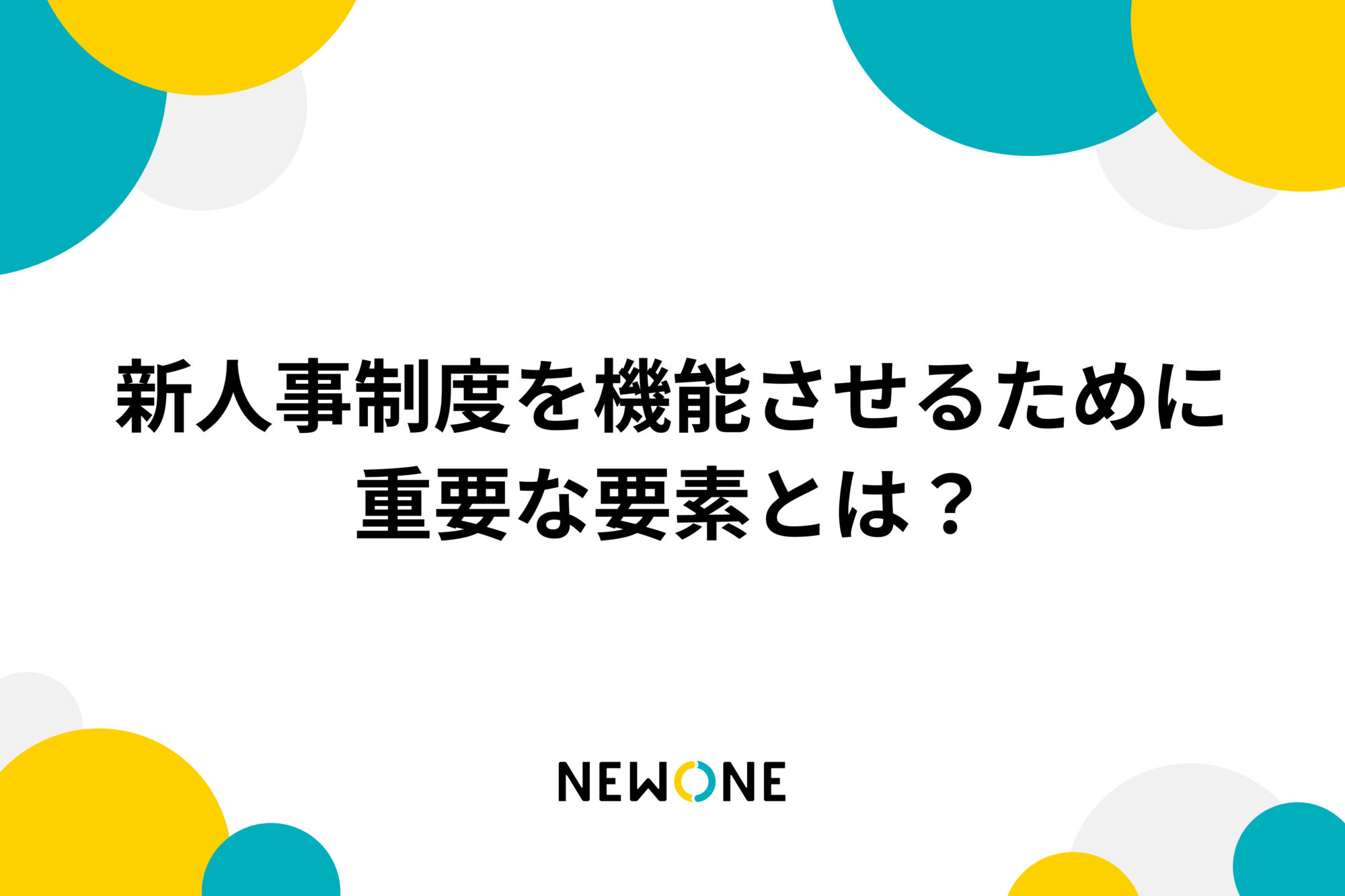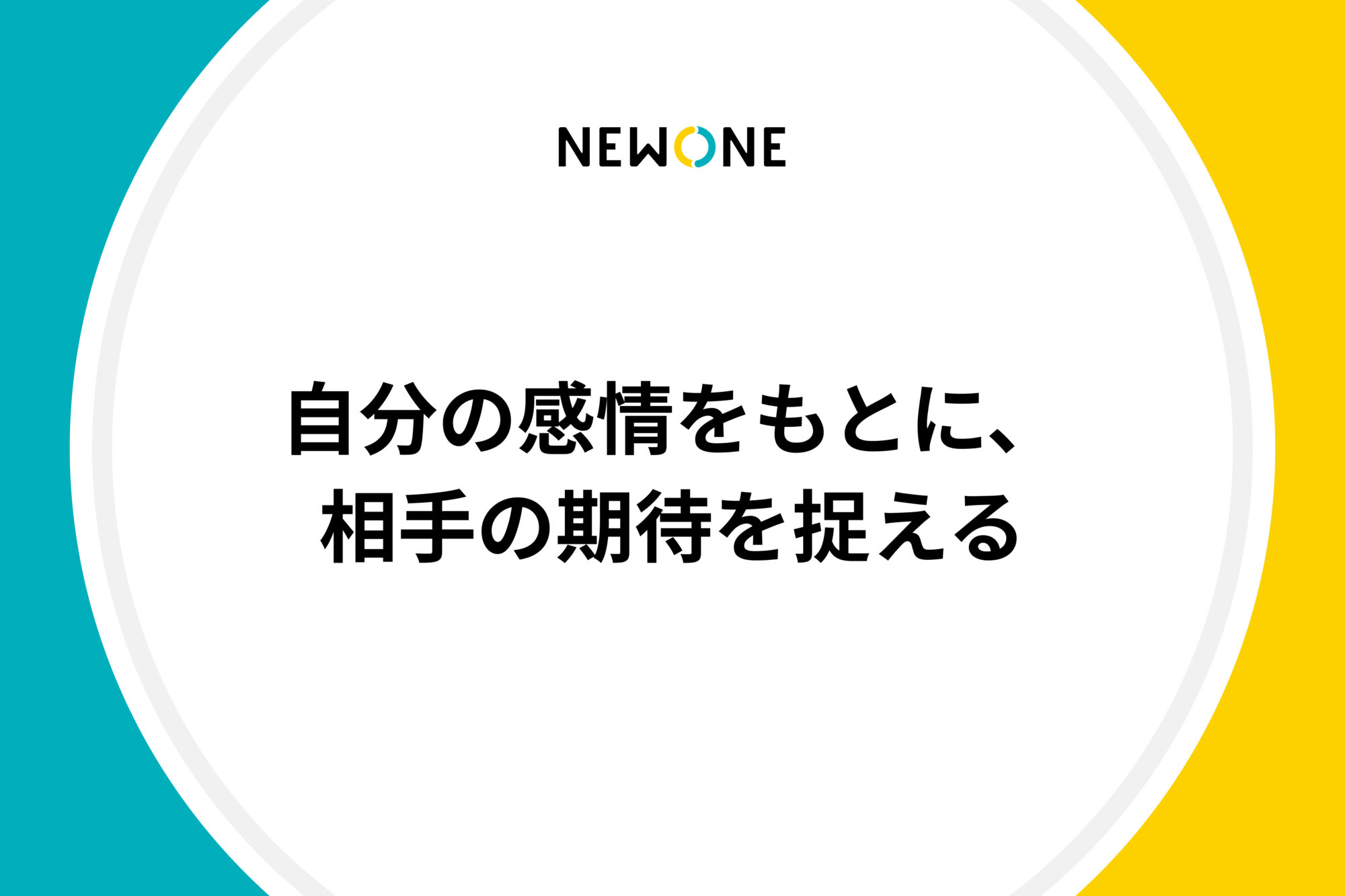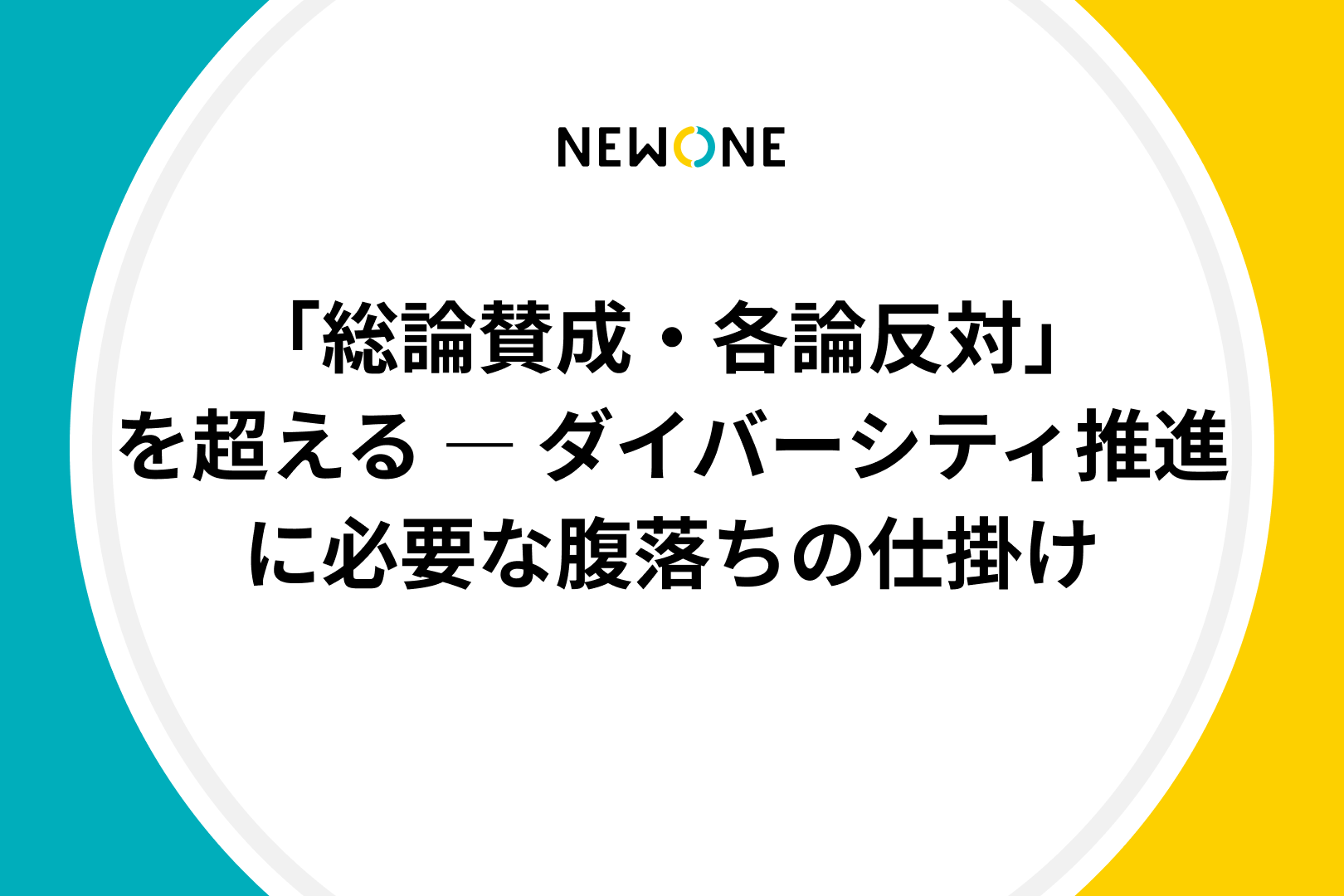
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
弊社では最近、中途採用を強化し、多様な人にご入社いただいていますが、創業初期からの画一的なフェーズから多様化していく中で、難しさを感じる点もあります。
また、クライアント企業のダイバーシティ推進のコンサルティング支援をしていると、ダイバーシティは「必要だ」という点では誰もが賛成するが、いざ具体策を進めようとすると「負担が増えるのでは」「不公平になるのでは」という意見で、推進が難しくなる現実があります。
人材が枯渇し、イノベーションが求められる昨今において、ダイバーシティの推進は重要なテーマであり、この難しさの要因は何で、どのように向き合っていくべきかについてまとめてみたいと思います。
総論賛成・各論反対になりやすいダイバーシティ推進
近年、ダイバーシティやDEI(Diversity, Equity & Inclusion)という言葉を耳にしない日はありません。
上場企業を中心に、人的資本情報の開示が義務化され、女性管理職比率や育児休暇取得率といった数値を掲げることが当たり前になってきました。投資家からの要請も強まり、「女性取締役ゼロは認められない」といった圧力も顕在化しています。社会的な潮流を見ても、ダイバーシティは「やるべきこと」として広く認識されていると言えるでしょう。
しかし現場の実態に目を向けると、必ずしもスムーズには進んでいません。
多くの企業で「総論賛成、各論反対」という状況が生じています。つまり「ダイバーシティは必要だ」という認識には異論がないものの、いざ具体的な施策となると納得感が得られず、現場が抵抗する。
このギャップこそが、ダイバーシティ推進の最大の壁だと感じています。
では、なぜこのようなギャップが起こるのでしょうか。
コミュニケーションコストという現実
「多様性は価値を生む」とはよく言われます。
確かに、異なる視点や経験を持つ人材が集まることでイノベーションが生まれ、組織の競争力が高まることは多くの研究で示されています。しかし一方で、現場レベルでは「同質性の方が楽だ」という本音があるのも事実です。
同質的な組織では、共有された前提が多く、「阿吽の呼吸」で意思決定が進みます。説明が少なくても理解が一致し、効率的です。逆に、多様性が高い組織では、前提の認識合わせが必要となり、誤解や摩擦が生まれやすく、気を遣う場面も増えます。時には不用意な言動がハラスメントと受け取られるリスクも高まります。
つまり、多様性を活かすためには「コミュニケーションコスト」が必然的に発生するのです。このコストを理解しないまま「多様性は良いことだから推進しよう」と声をかけても難しく、一定の対策もセットで行うことが重要です。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
公平と平等のジレンマ
コミュニケーションコスト以上に、ダイバーシティ推進で難しいのが「公平と平等のジレンマ」です。
まずは定義を整理してみましょう。
- 平等(Equality) :すべての人に同じ条件・同じ支援を与えること
- 公平(Equity):一人ひとりの背景や状況に合わせて必要な支援を行うこと
この違いを理解しないまま「みんな同じ条件で扱うべきだ」と進めると、かえって不満や摩擦を生むことになります。
例えば、力が必要なある業務において男性なら一人で完結できる力仕事が、女性の場合は外部委託が必要になるケースがあります。このとき「同じ仕事をしているのに余計なコストがかかるから男性の方が評価されるべきだ」という論調が出やすい。これは、平等=同じ条件で比較 という発想です。
一方で、公平=成果を出すために条件を整える という視点に立てば、話は変わります。荷物の運搬に制約があっても、その人が成果を出せるよう環境を整え、付加価値をどう発揮するかで評価すべきです。
どちらの立場も、論理としてはあっている主張です。
だからこそ難しく、各論反対になりやすいものです。
総論賛成・各論反対に対応するために
ダイバーシティ推進で難しいのは「総論賛成・各論反対」をいかに乗り越えるかです。
必要性は理解されていても、現場では「負担が増えるのでは」「評価が不公平になるのでは」といった懸念が生じ、形骸化してしまう。この背景には、コミュニケーションコストや公平と平等のジレンマといった現実があります。
ではどうすればよいのでしょうか。
重要なのは、経営・人事・マネジャーが同じ方向を見て役割を果たすことです。経営は理念を繰り返し語り、なぜ取り組むのかを明確にする。人事は方針を曖昧にせず、「何を重視するのか」を示す。そしてマネジャーは、現場を預かる経営責任者として多様性を活かす覚悟を持つ。この三位一体が揃うことで、初めてダイバーシティは理念から実践へと進んでいきます。
こうした観点をさらに深めるために、NEWONEではセミナーを開催します。
ダイバーシティ推進の“腹落ち”をどうつくるか
~総論賛成・各論反対を乗り越えるポイントとは~
何を押さえ、現場に腹落ちを生み出すかを具体的に解説します。ぜひご参加いただき、自社の推進の突破口を考える機会としていただければと思います。
ダイバーシティは外圧に応じた義務ではなく、未来を切り拓くための戦略的投資です。多様性を「面倒」ではなく「可能性」として捉え、腹落ちをもって挑戦する。その姿勢こそが、日本企業に求められる真のダイバーシティ推進だと私は考えます。
 上林 周平" width="104" height="104">
上林 周平" width="104" height="104">