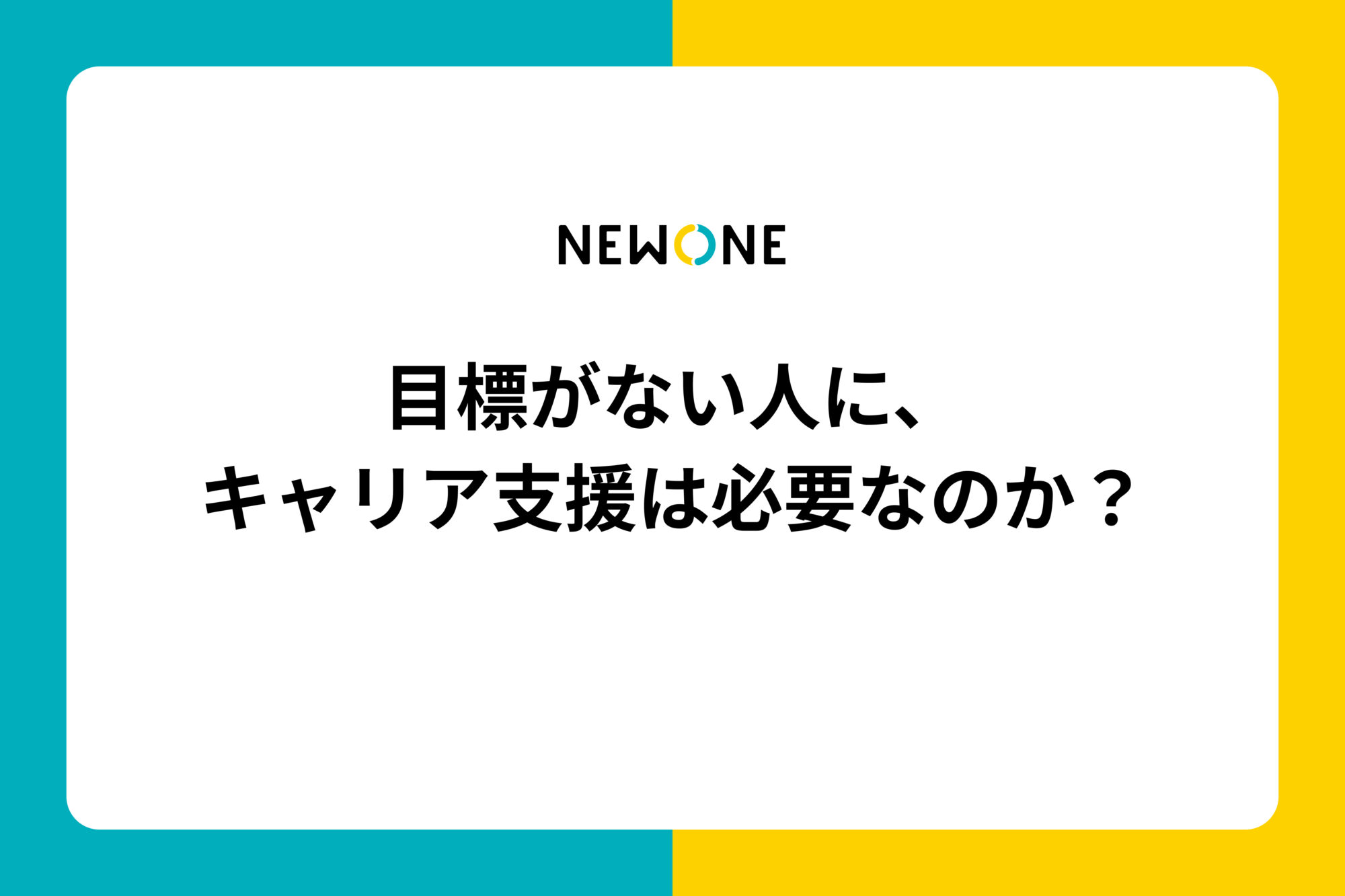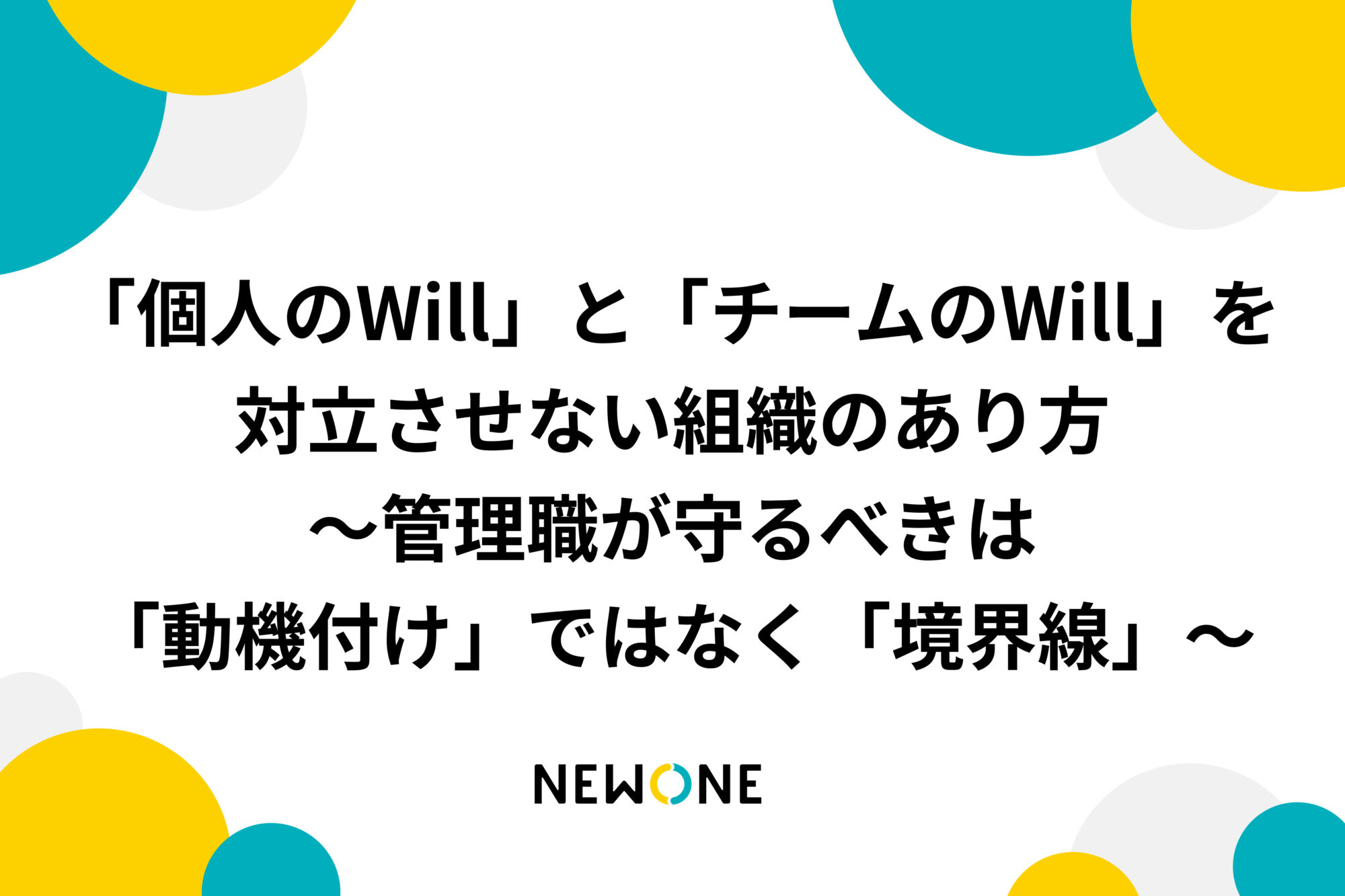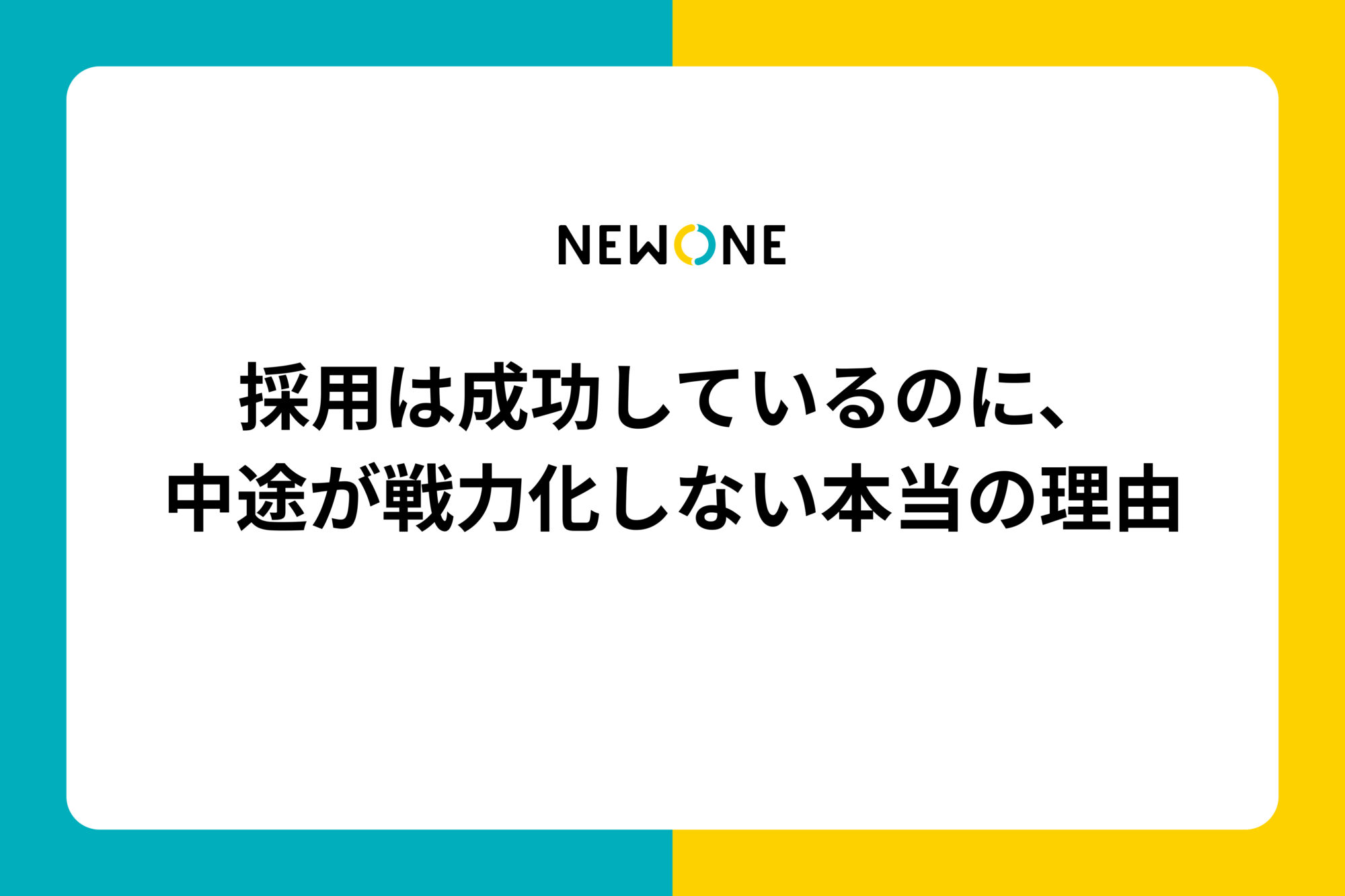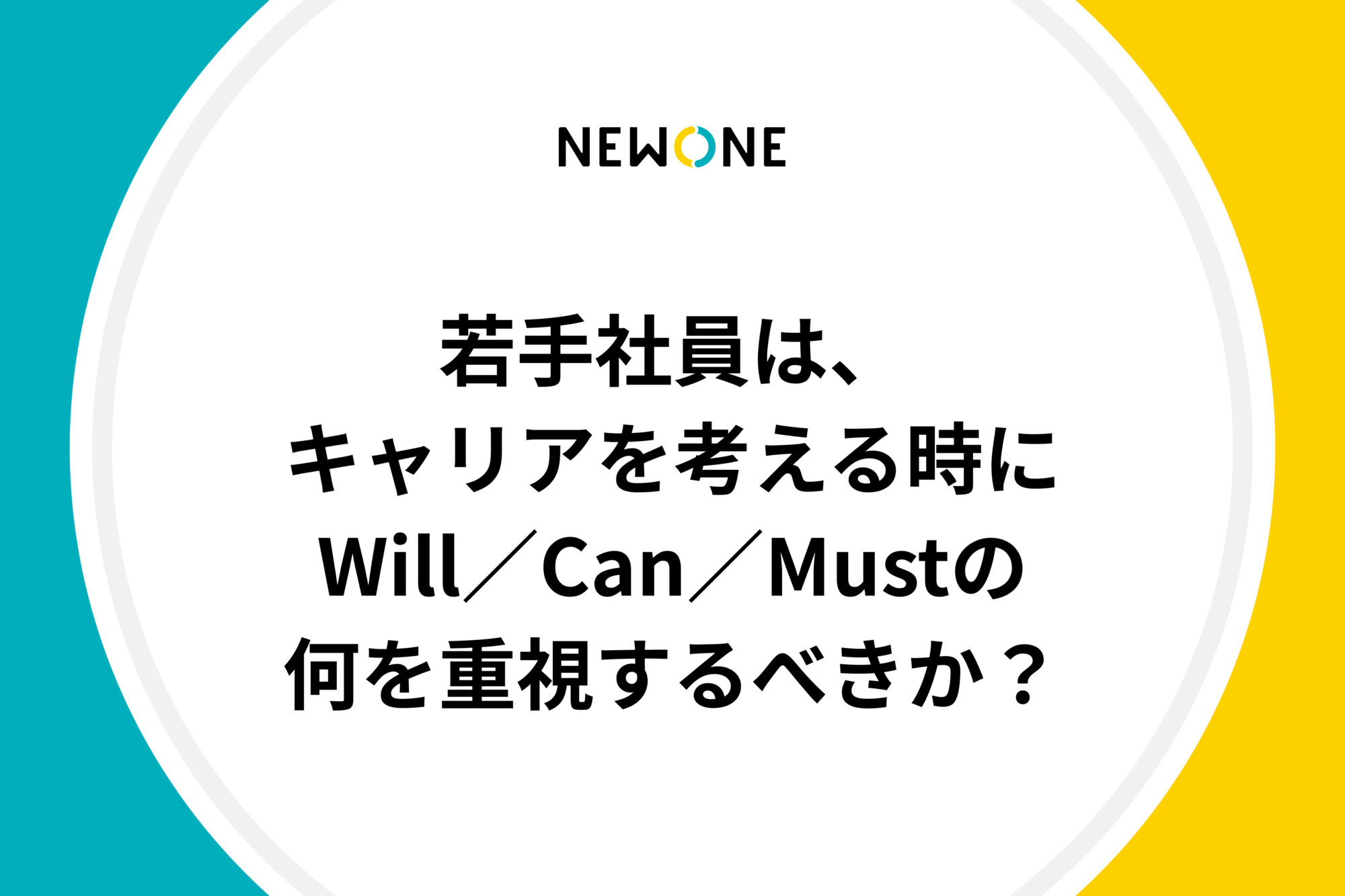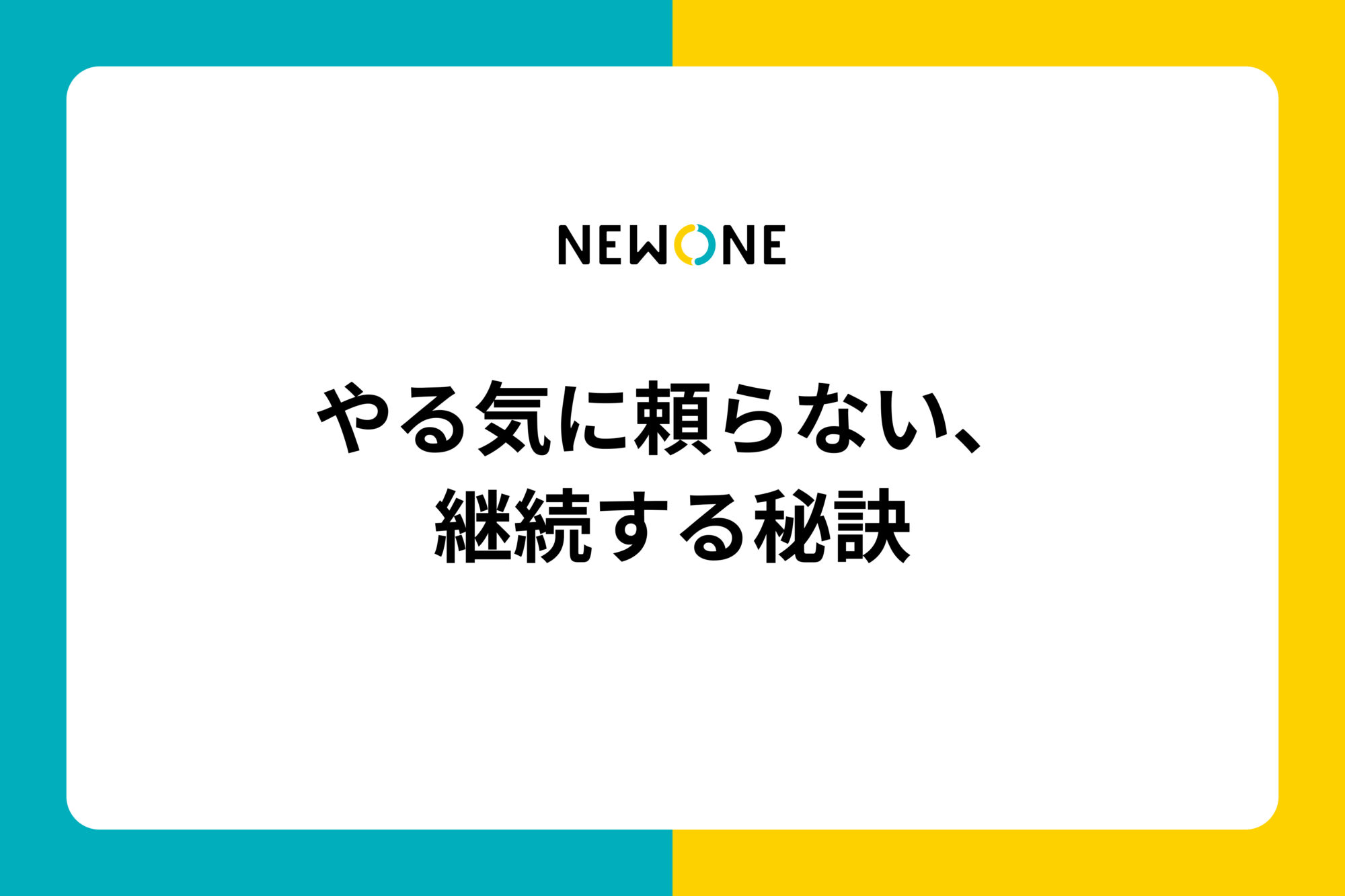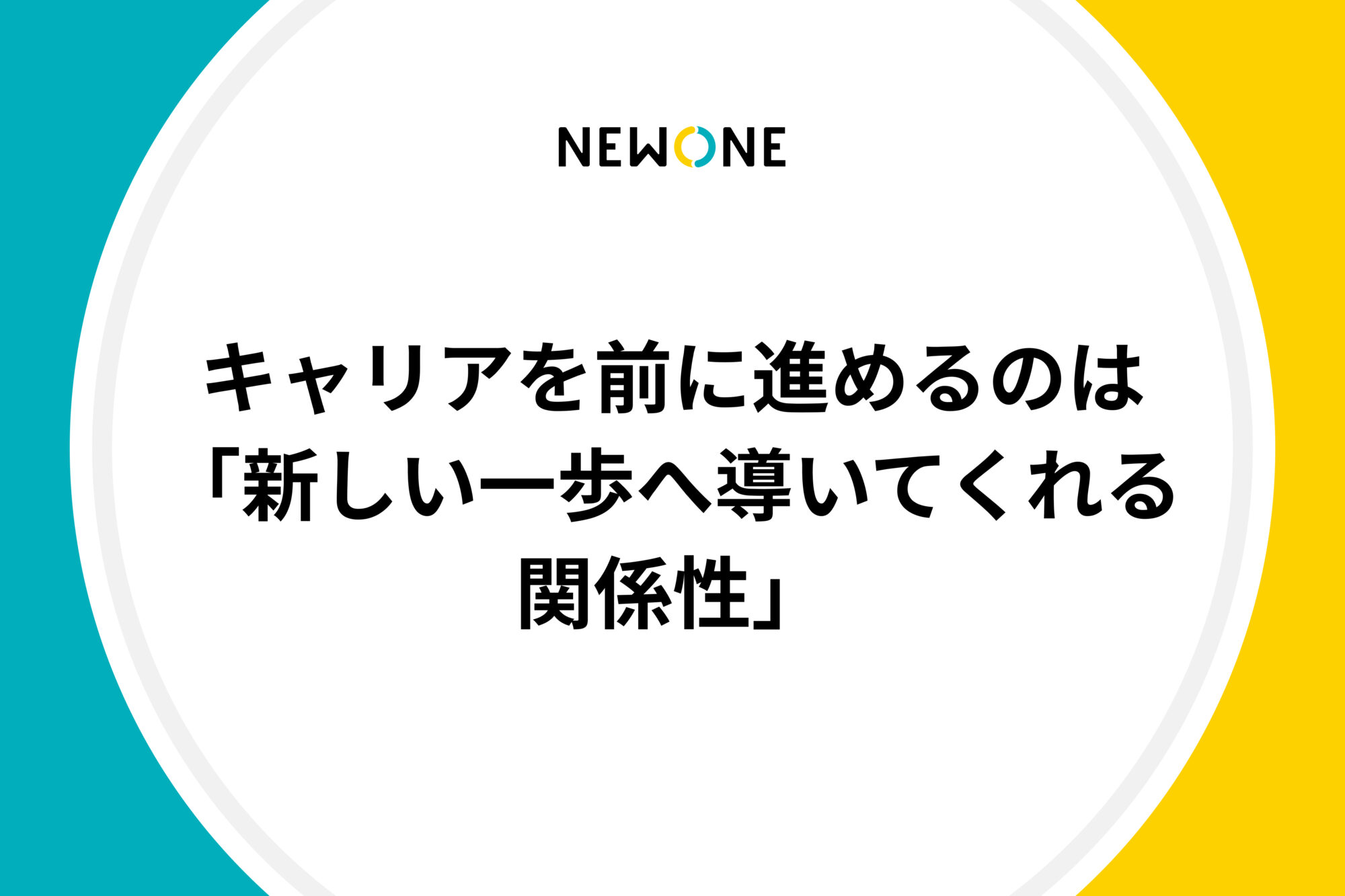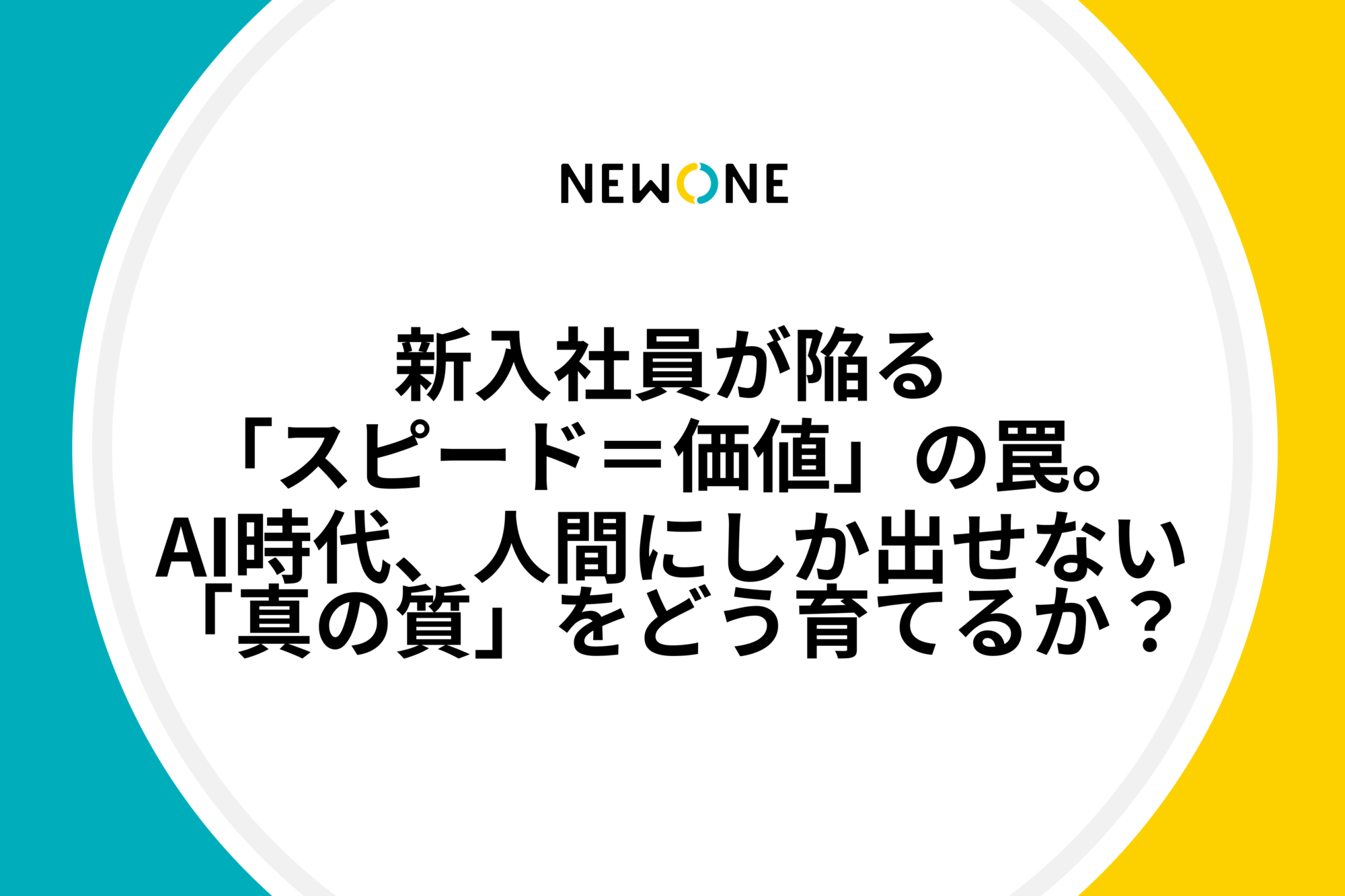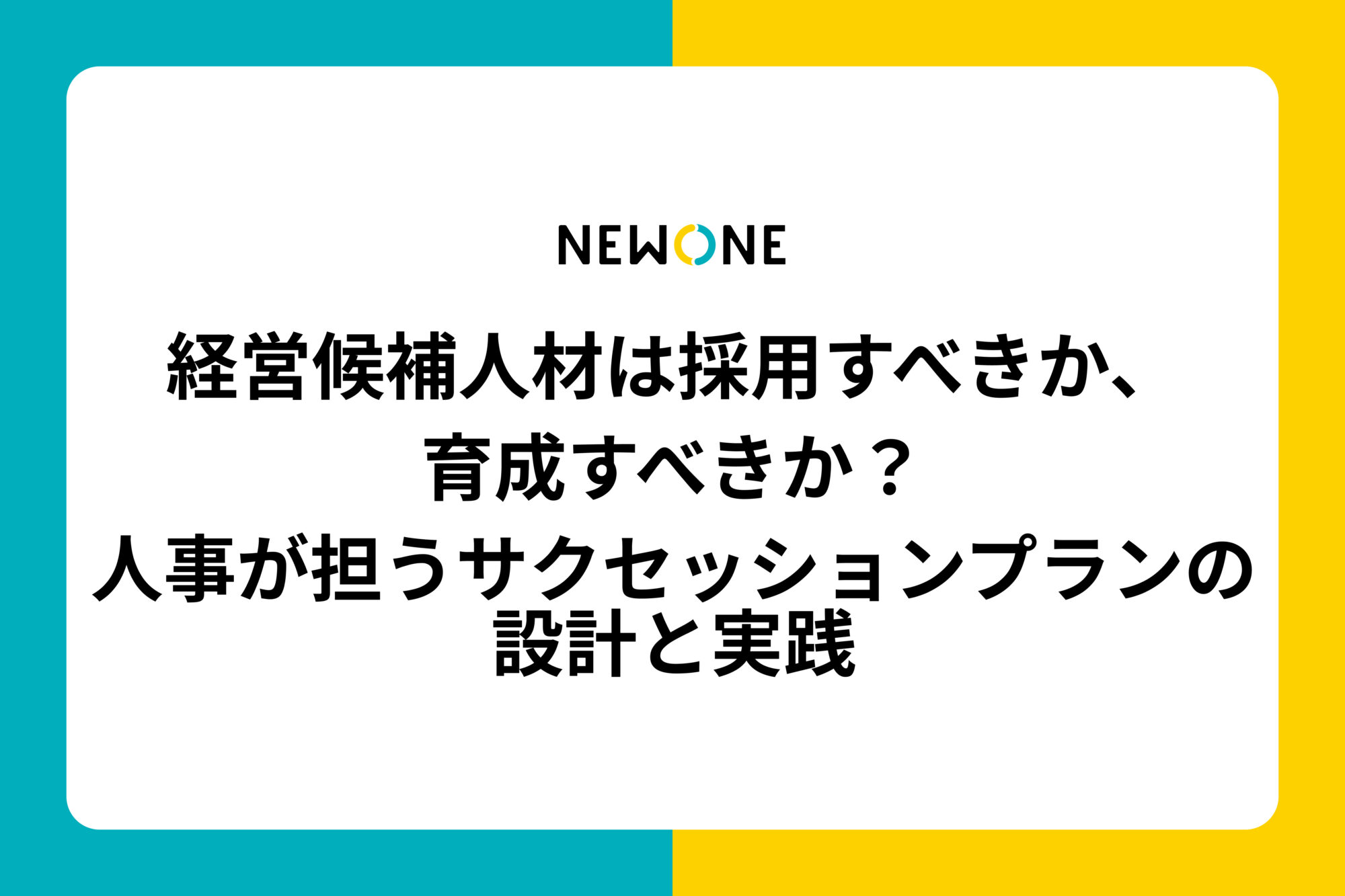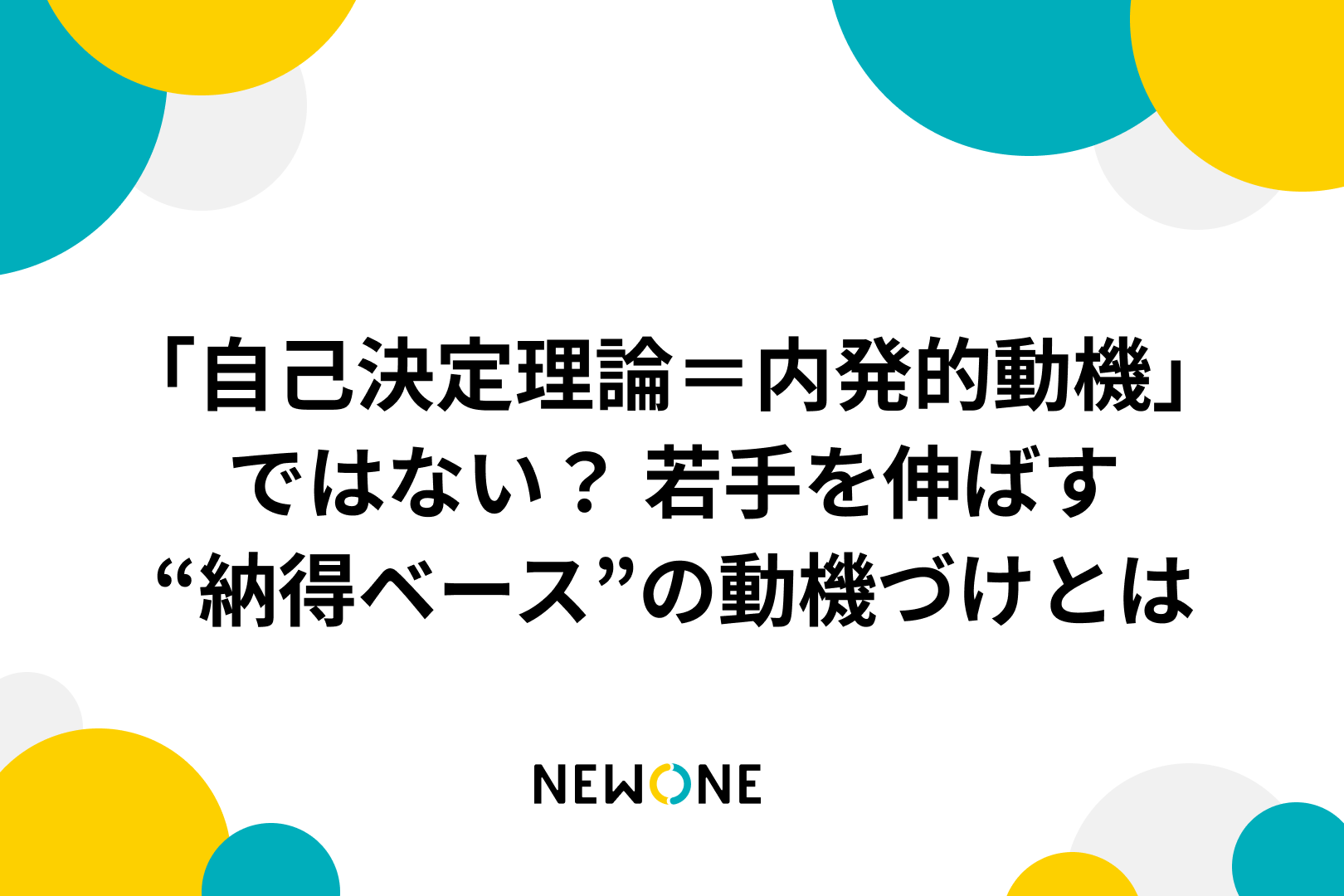
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
昨今、「主体的に動く若手を増やしたい」「内発的に動機づけされた人材を育てたい」という声が、多くの企業から聞こえてきます。特に新人や若手に対して、「自分から動いてほしい」「やらされ感なく仕事に取り組んでほしい」と期待するマネジャーも多いはずです。
この問いに対して、自己決定理論=100%内発的動機づけと捉えるのは誤解であり、「動機の段階的な変化」を理解することが重要だと考えます。モチベーションは「外発か内発か」の二択ではなく、グラデーション(連続体)として存在するのです。
1. “納得ベース”の動機づけが、行動を生む
自己決定理論では、モチベーションを以下のように段階的に整理しています。
- 外発的動機づけ(報酬・罰による)
- 取り入れ的動機づけ(やれと言われたから)
- 同一化的動機づけ(意味や目的に納得している)
- 統合的動機づけ(自分の価値観とつながっている)
- 内発的動機づけ(楽しい・好きだからやっている)
つまり、「楽しいからやる」だけが理想なのではなく、“やらなければいけないこと”でも、そこに自分なりの意味や納得を見出せれば、主体的な行動につながるというのが自己決定理論の本質です。
2. まずは“納得して動く”レベルを目指す
たとえば、上司にやらされ感で動いている部下がいたとします。その部下に「なぜそれをやるのか」「どんな意味があるのか」を一緒に考える対話を重ねることで、「自分が成長するために必要だから」「チームのために貢献したいから」といった“納得”ベースの動機づけに引き上げていくことが可能です。
これは、モチベーションを「外からの強制」ではなく、「自分の中での価値づけ」に変えるプロセスです。そして、これも立派な“自己決定”の一つです。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
3. 内発的じゃなきゃダメ、は思い込みかもしれない
「この仕事は楽しくないから、内発的動機なんて無理」という声もあるかもしれません。ですが、すべてを楽しめる人などいません。むしろ、自分なりに納得できる理由を見つけ、それを軸に行動できる人が“自律的”な人だと考えます。
つまり、自己決定理論は「楽しさ」や「やりがい」だけを求める理論ではなく、“納得”と“選択”を尊重する理論です。私たちにできるのは、内発的動機にこだわりすぎず、「今この人が、どの段階の動機で動いているのか?」を見極めること。そして、「どうすれば一歩先の段階に進めるか?」を一緒に考えることです。
まとめ. モチベーションの“解像度”を上げる
自己決定理論は、「やらされ感をなくすこと」だけが目的ではありません。「どのようにその人の中に“自分の理由”を育てるか」を考えるヒントを与えてくれます。
“外発か内発か”の二択ではなく、グラデーションで捉えることで、部下やチームの動機づけにもっと柔軟にアプローチできるはずです。まずは、「すぐに内発的に動け」という理想を手放し、目の前の人が“納得して動ける状態”をつくることから始めてみてはいかがでしょうか。
 棚橋 彩香" width="104" height="104">
棚橋 彩香" width="104" height="104">