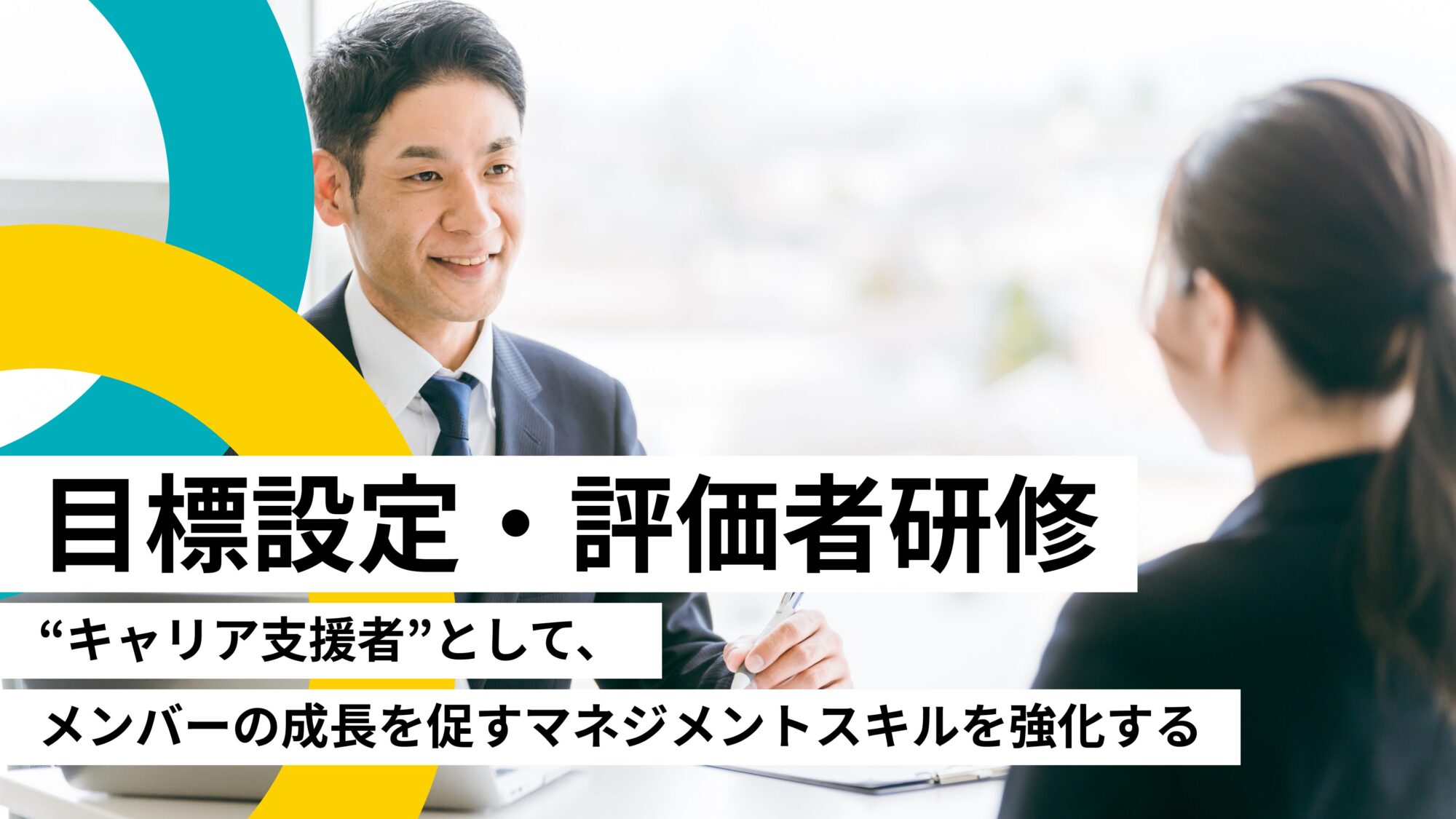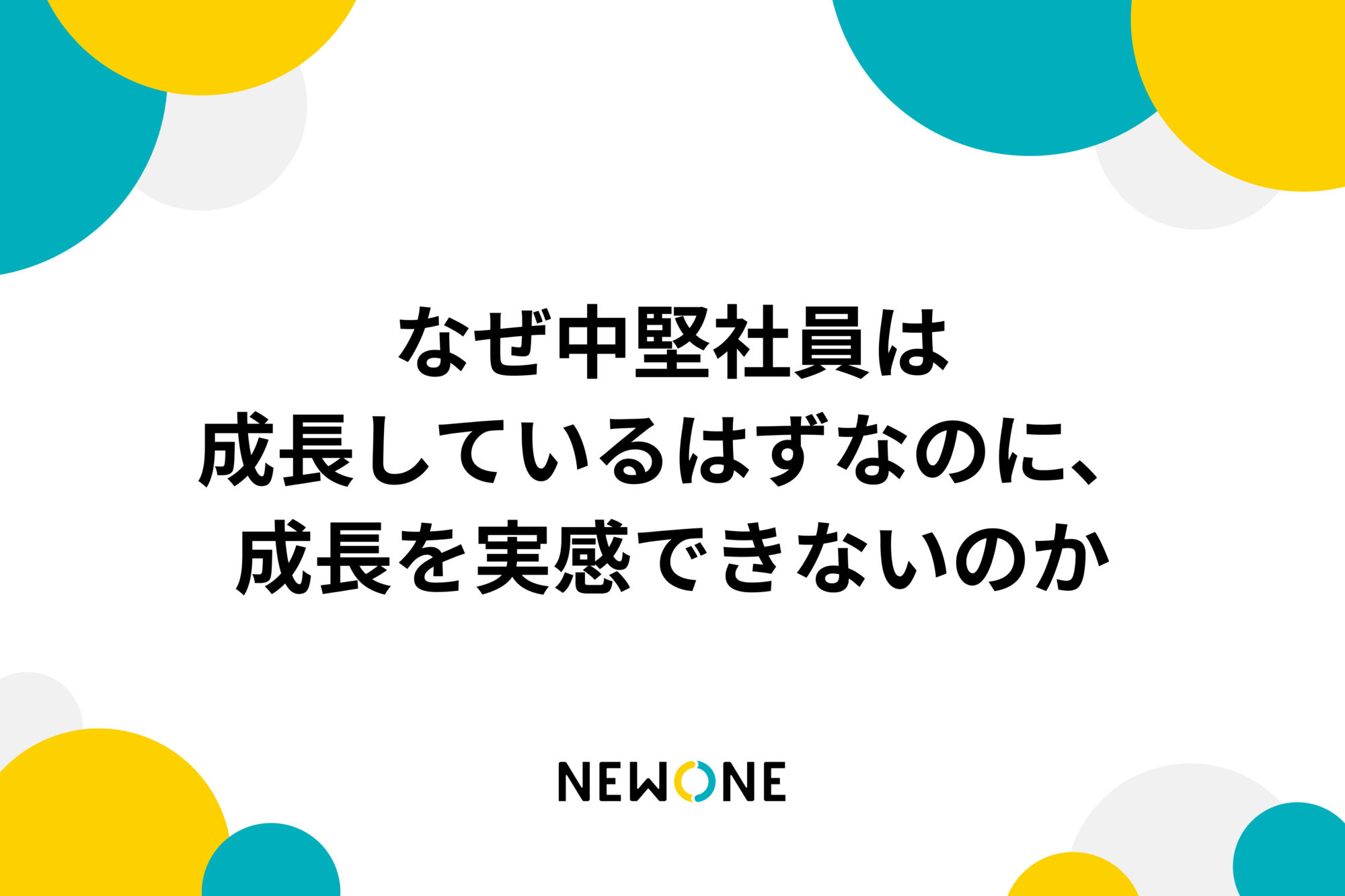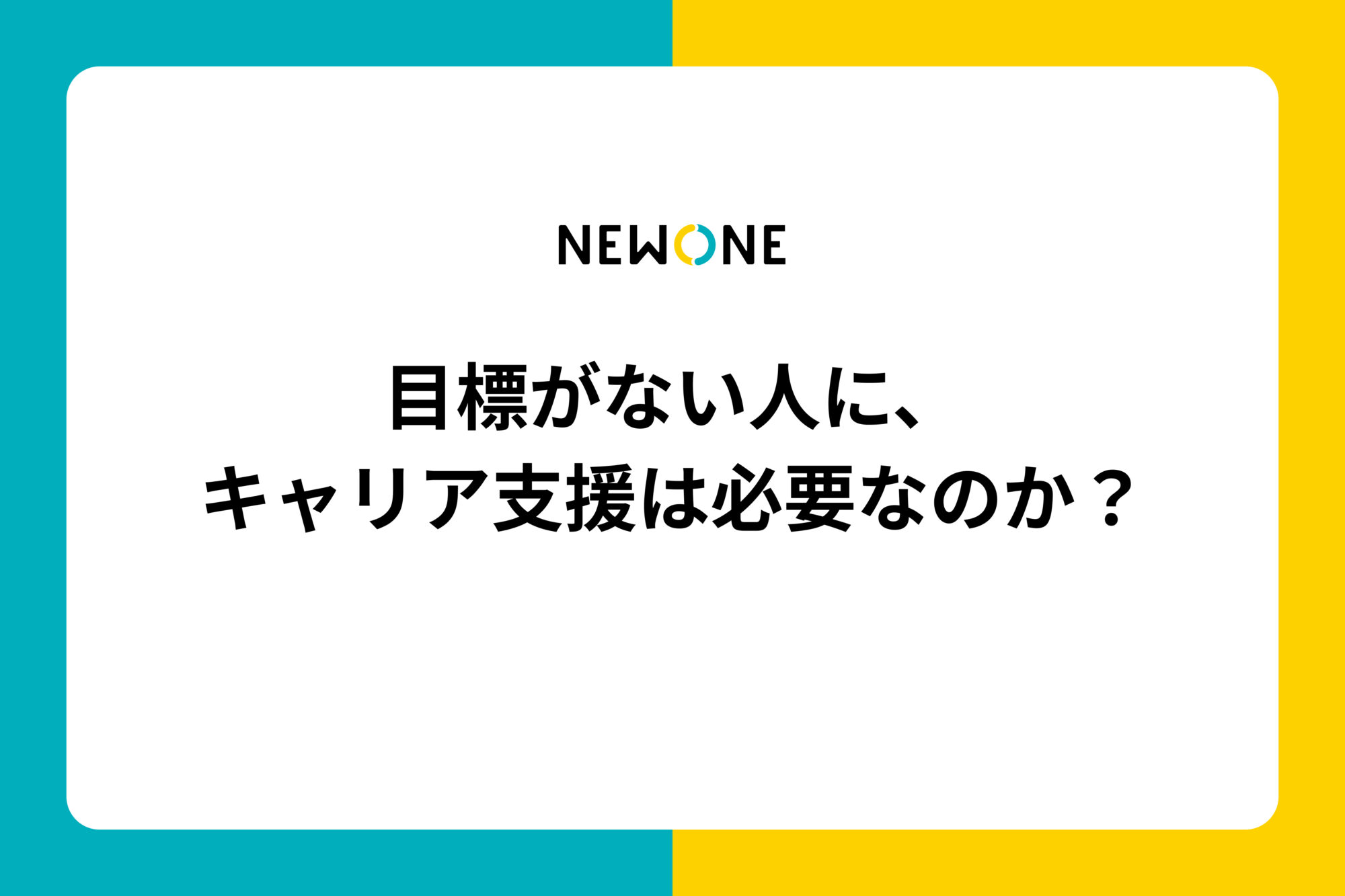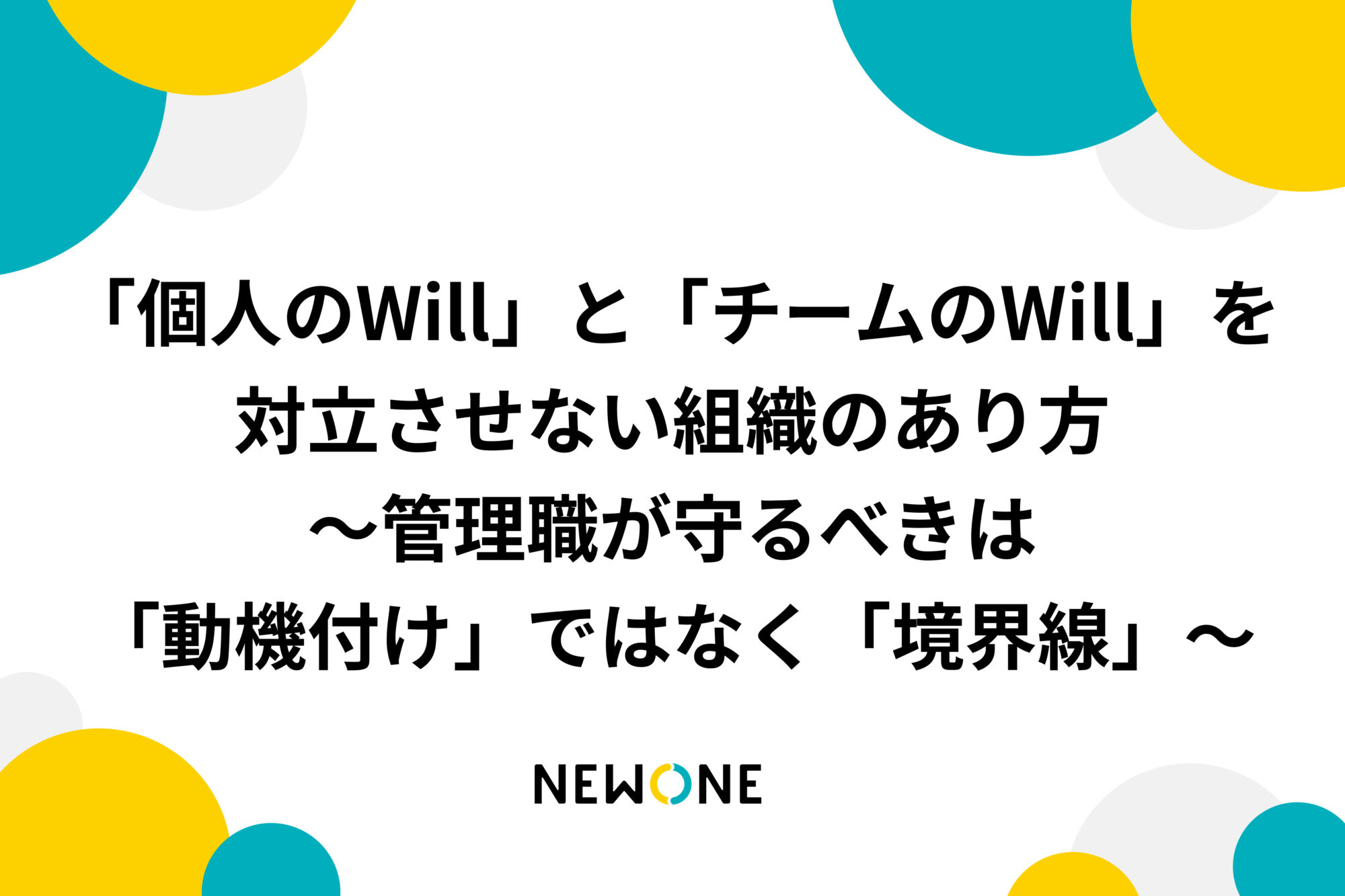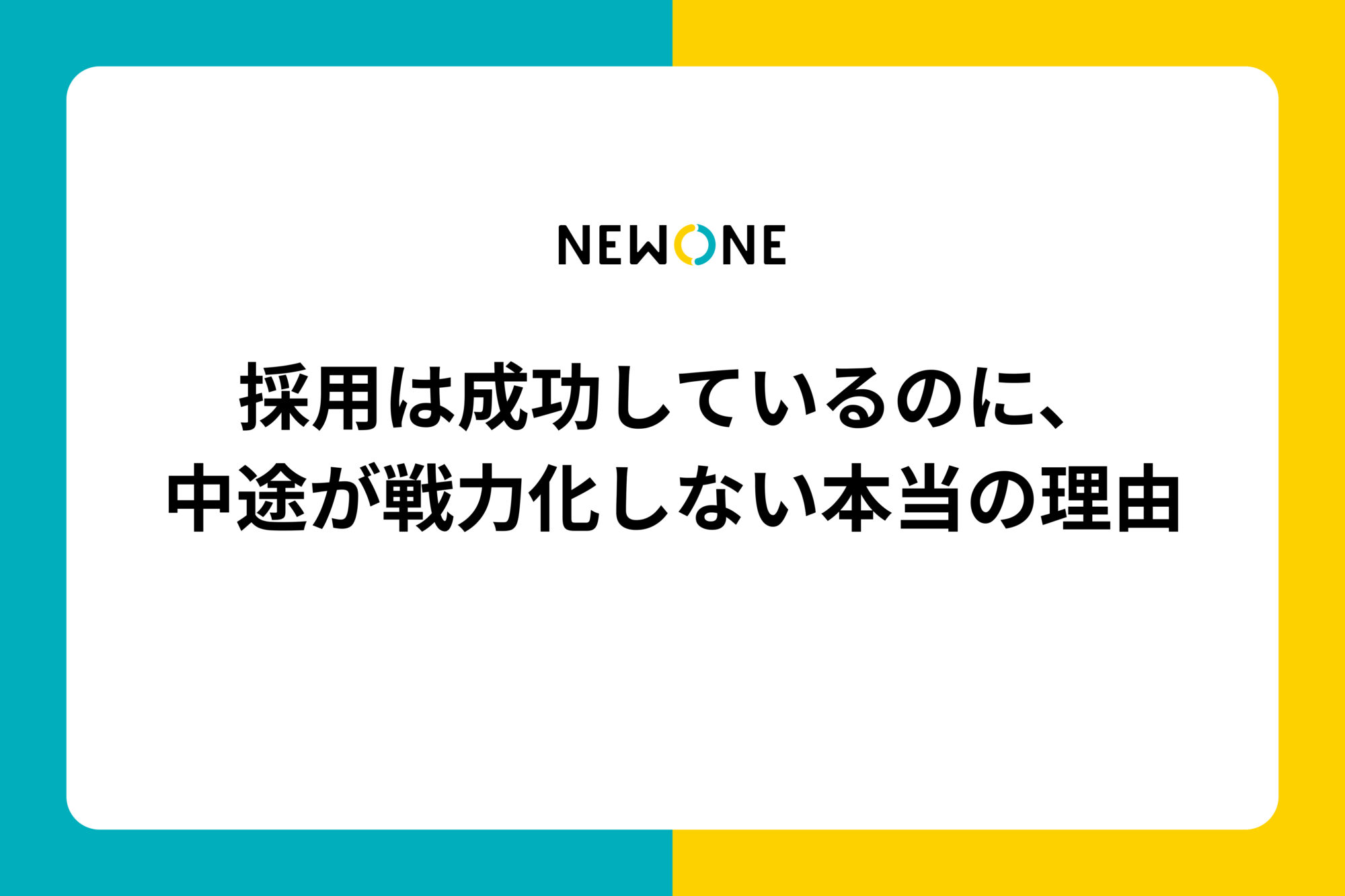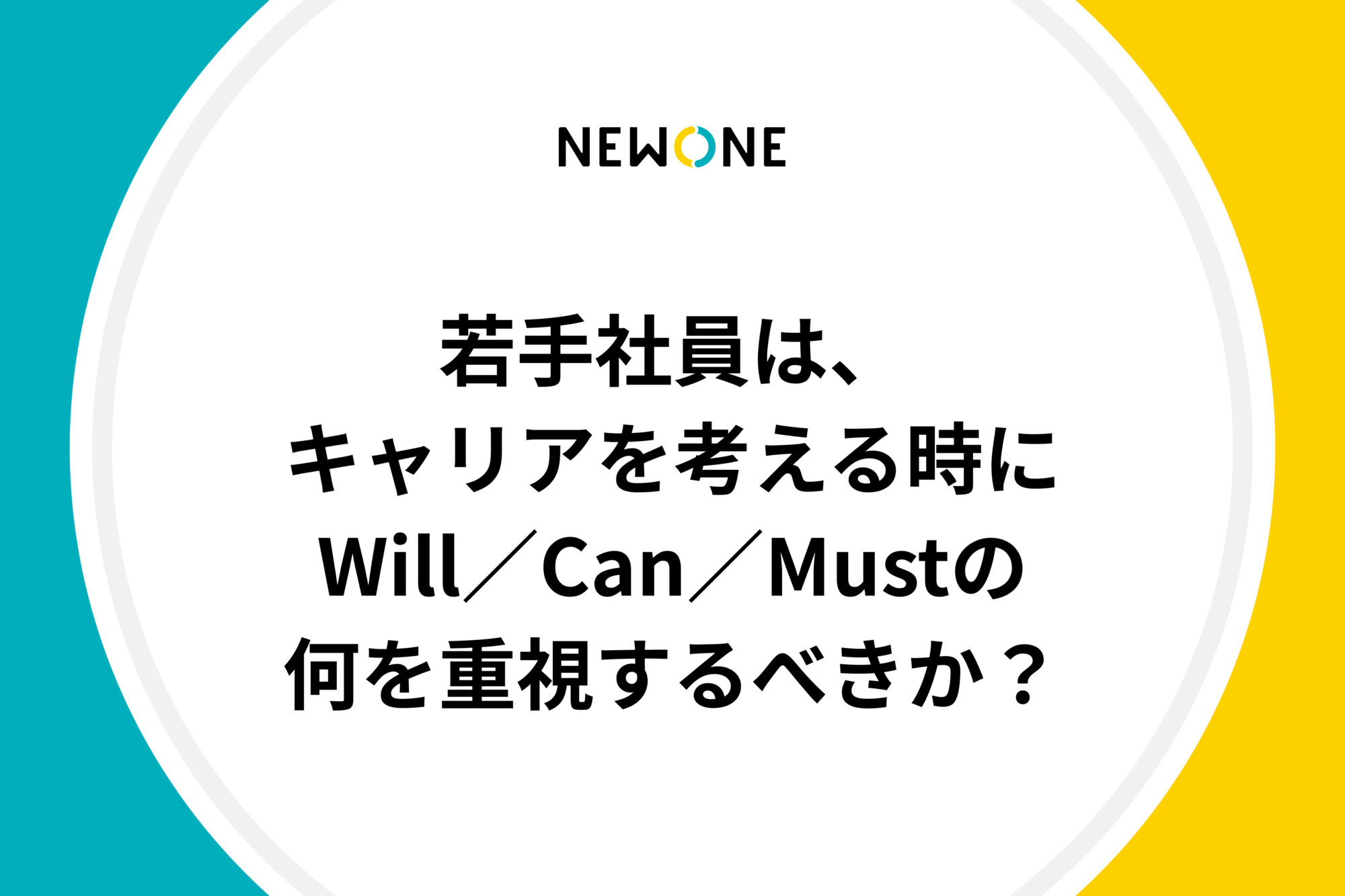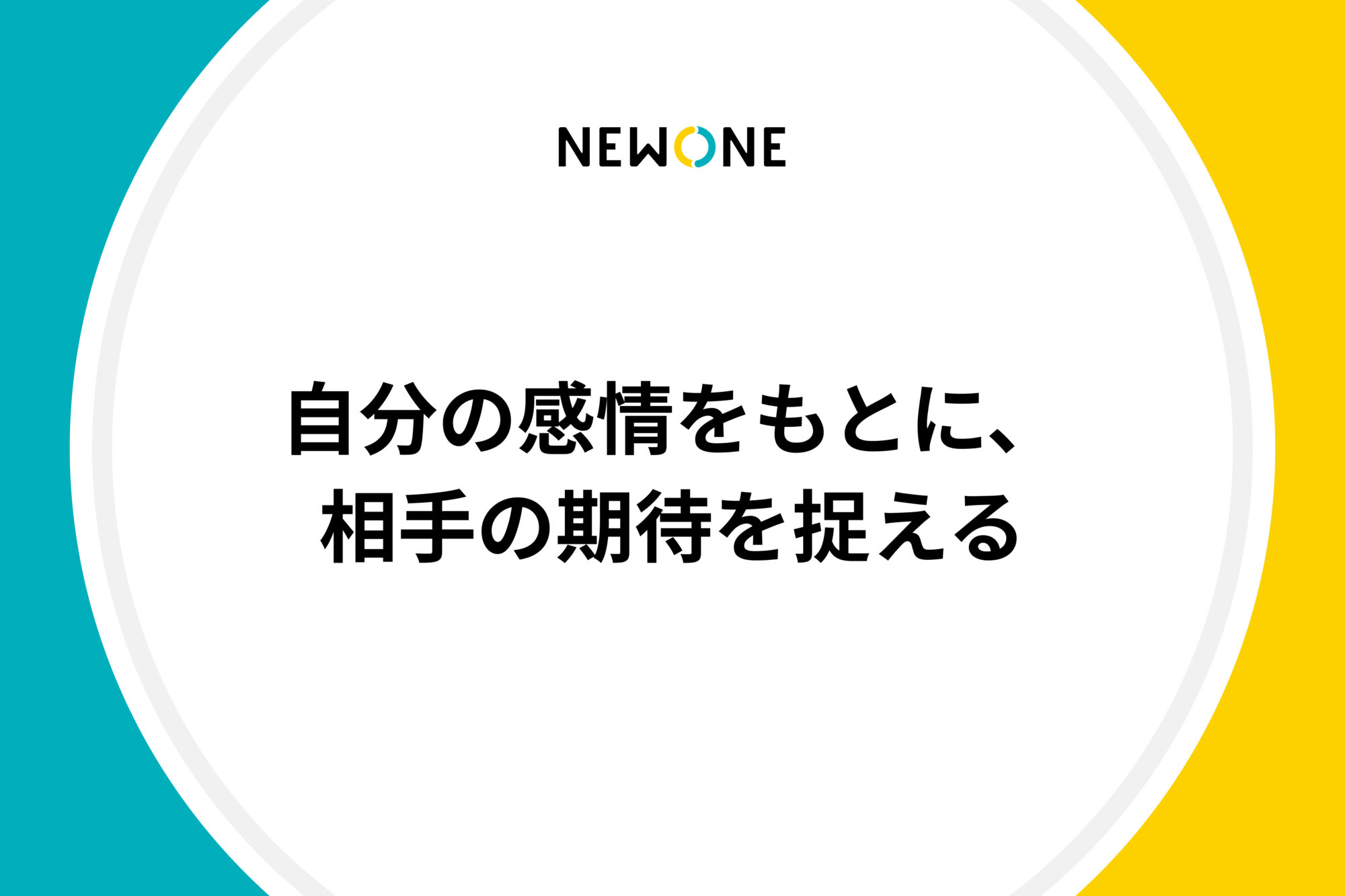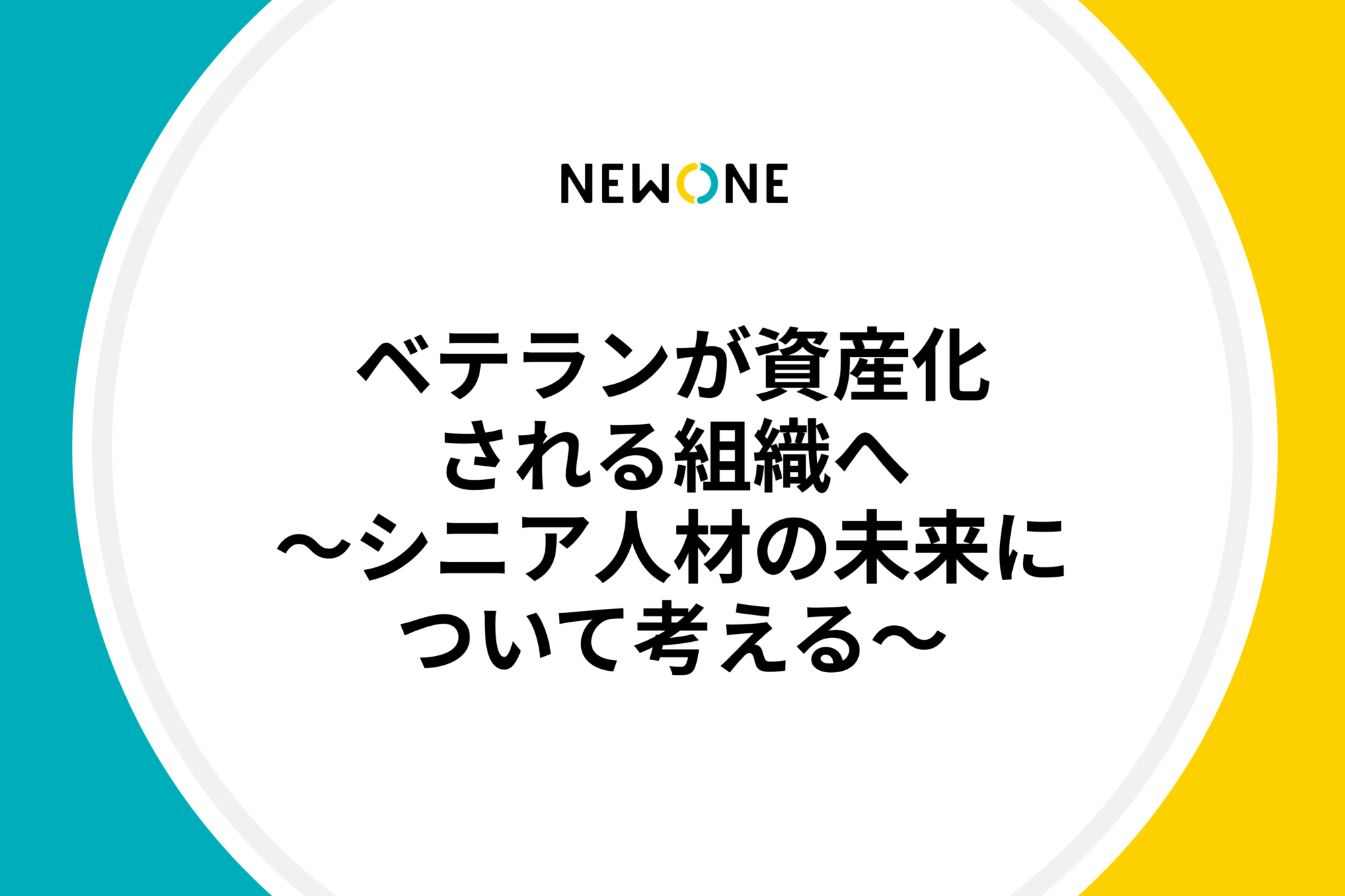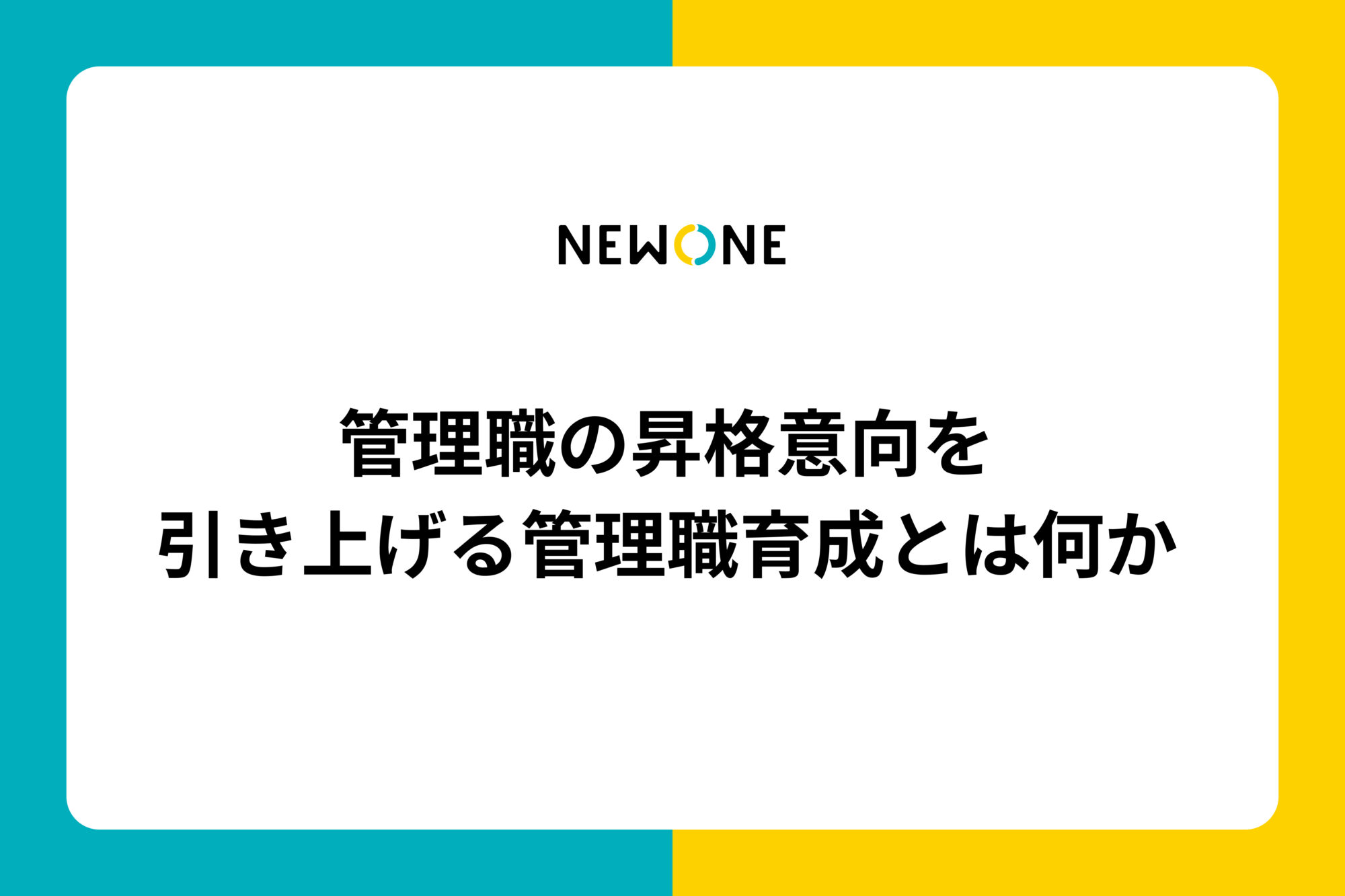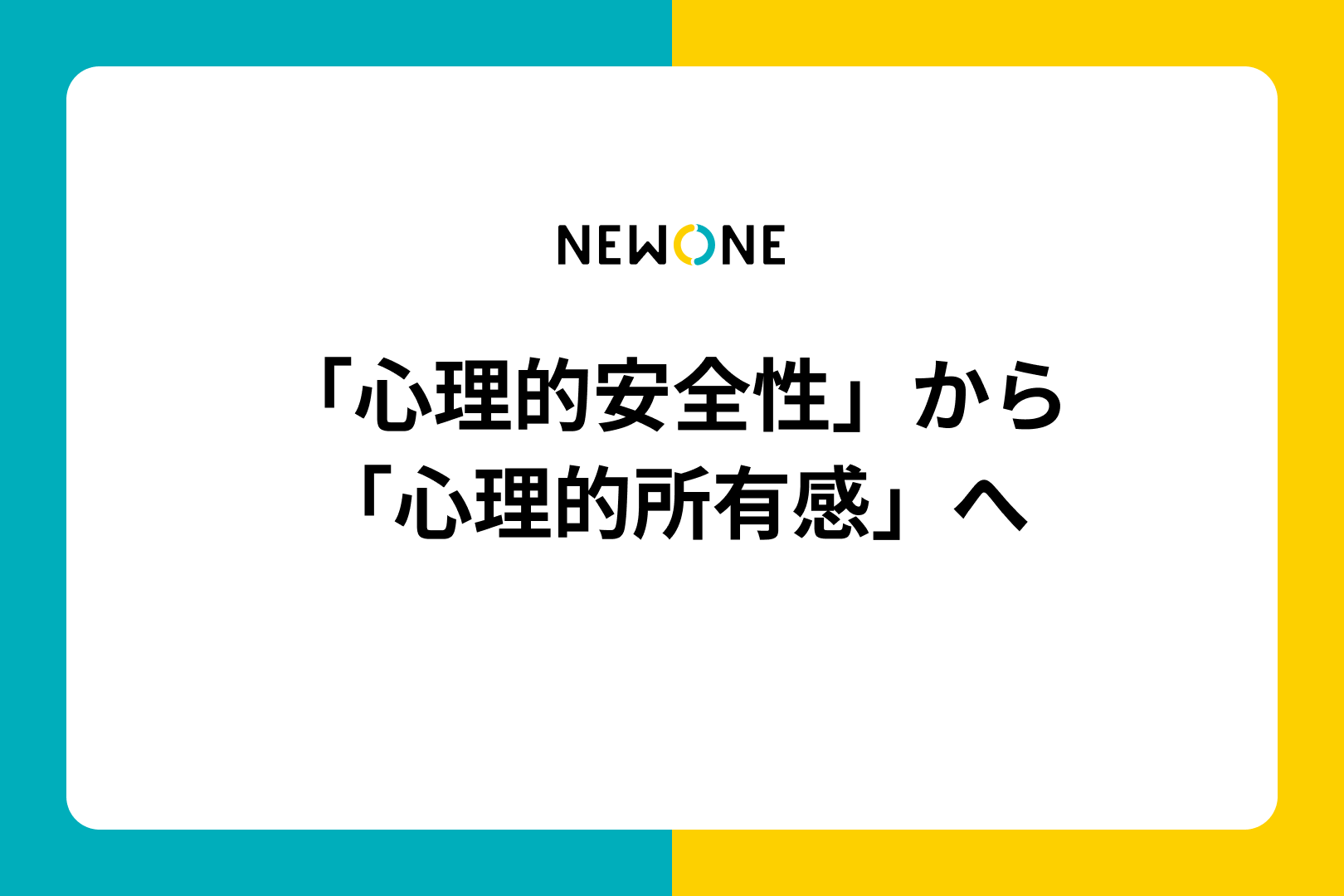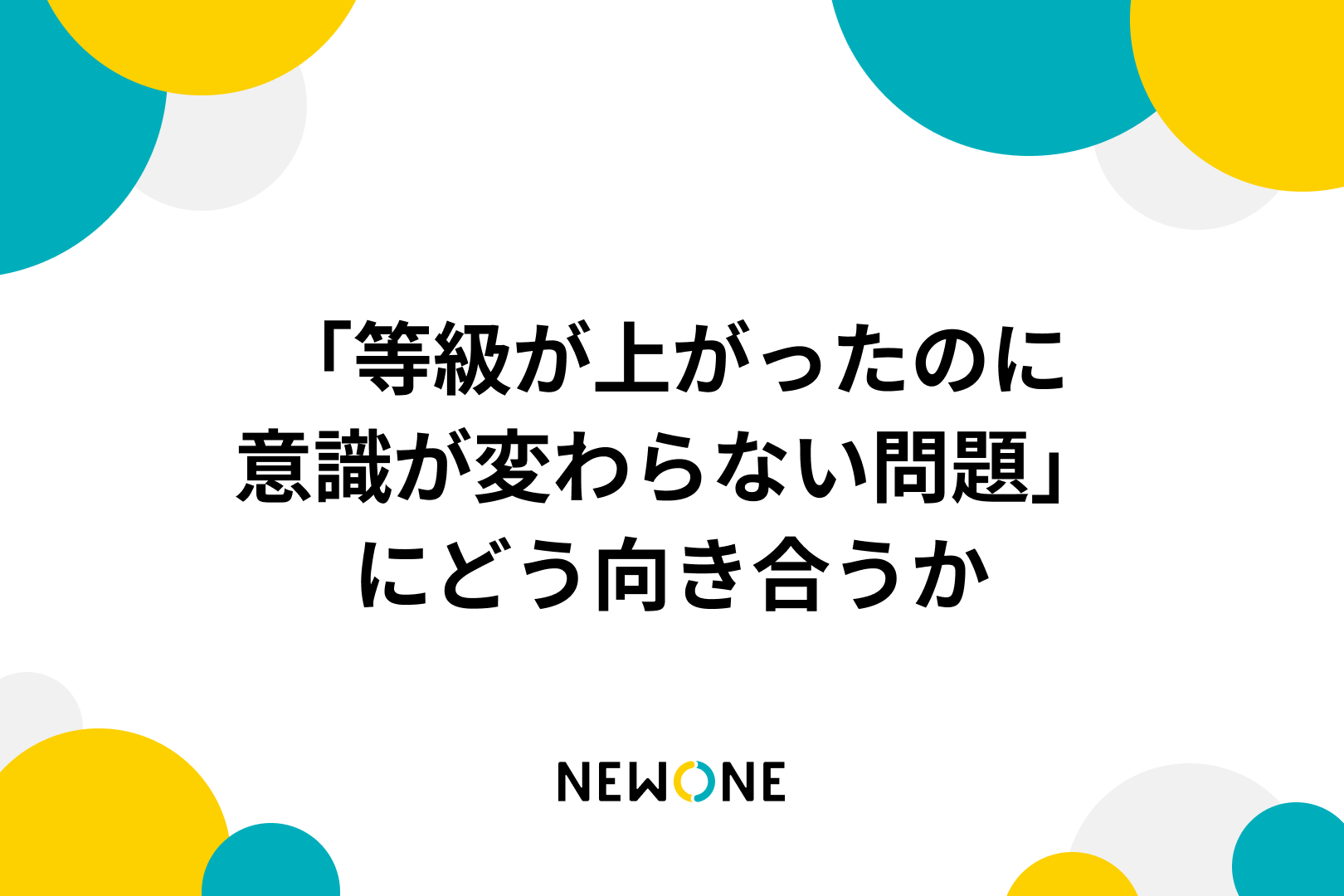
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
期待とのズレをなくすために必要なこと
最近、人事制度を改定される企業が増えており、より早期に等級が上がる若手・中堅層も増えてきています。
そのため、弊社に対しても、等級が上がった社員向けの研修の依頼が増えています。
これは、新しいグレードとなるトランジションのタイミングであり、役割の変化を求められるからです。
特に、非管理職から管理職へ移行する際には、自他ともに求められる役割が明確に変わるため、本人もどのように適応すべきかを意識しやすく、不安を感じることも多いです。これはある意味、健全な心理状態といえます。
しかし、非管理職のまま等級が上がる場合、例えばメンバークラスから主任クラスに上がるようなケースでは、組織として次期管理職としての能力・役割を期待していても、本人の認識が追いついていないことが少なくありません。
実際に、先日とある企業の研修の冒頭で「等級が上がった後の役割を果たすことに不安を感じるか」と質問したところ、大半の方が「まあまあ/そうでもない」と回答されました。理由を尋ねると、
- 「これまでの働きを評価された結果なので、これまで通りの仕事を続ければ問題ないと思う」
- 「管理職になったわけではないので、求められることがどう変わったのか分からない」
といった声が聞かれました。
このような状況に対し、人事側や管理職はどのように対応すべきでしょうか。
等級が上がることの本質を理解してもらう
まず、「等級が上がる」とは何を意味するのか、認識をそろえることが重要です。
等級が上がるのは、「今のグレードの要件を満たしたから」ではなく、「次の等級の役割を担い、さらにその先を目指せると判断されたから」なのです。
つまり、「これまでと変わらない仕事ぶり」では不十分であり、次のステップに向けた意識変革が求められます。
また、等級が上がるほど、求められる役割や期待は明確に言語化されることが少なくなります。
特に管理職ではないグレードでは、業務の中でも定型的・テクニカルなものより、非定型・コンセプチュアルな仕事が増える傾向があります。
そのため、自分が組織から何を期待されているのか、今後どのような能力を伸ばすべきかを自ら考え、動く必要があります。これは、等級が上がるほど、周囲が明示的に教えてくれなくなるからです。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
人事・管理職ができること
こうした背景を踏まえ、人事や管理職側にもできることがあります。
1. 等級が上がる際に背景をしっかり伝える
等級が上がる際には、その理由や期待される役割、これから伸ばしてほしい能力などを明確に伝えることが重要です。
管理職への昇進の際には、多くの企業がこうした対応を徹底し、研修でも「管理職として求める能力要件」に基づいたプログラムを実施します。しかし、非管理職の等級が上がる場合、「おめでとう」の一言で済ませていないでしょうか。
2. キャリア開発の機会を設ける
等級が上がった社員に対し、単なる「昇給」や「評価」の一環として受け止めさせるのではなく、キャリアを見つめ直す機会を提供することも重要です。
具体的には、
- 等級が上がることに対してどう感じているかを対話する
- これまでの経験を棚卸し、価値観や強みを整理する
- 次のステップに向けたキャリアビジョンを考える
といったアプローチが考えられます。
等級が上がることを、ただの「嬉しいイベント」で終わらせてしまうと、主体的に働きぶりを変えようという意識は生まれません。次のステップへ進むための契機とすることが重要です。
等級が上がることを成長の機会にするために
等級が上がることは、単に給与や待遇が良くなることだけを意味するのではなく、さらなる成長の機会であるべきです。しかし、それを本人が理解し、主体的に行動しなければ、「言われたことをやり、評価を待つ」というスタンスから脱却することはできません。
だからこそ、人事や管理職が適切なメッセージを伝え、本人が自身のキャリアについて考える機会をつくることが不可欠なのです。
 髙嶋 耕太郎" width="104" height="104">
髙嶋 耕太郎" width="104" height="104">