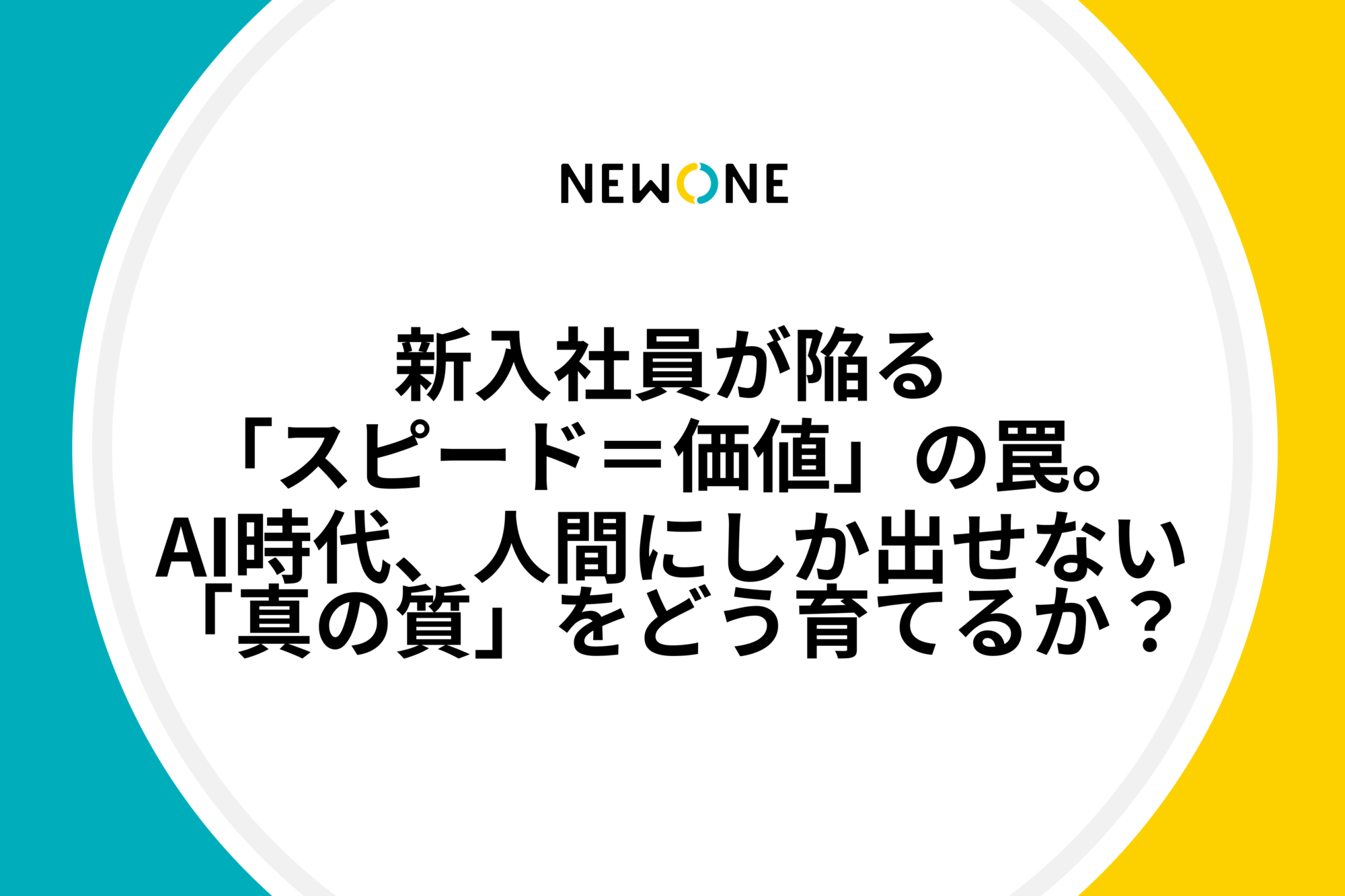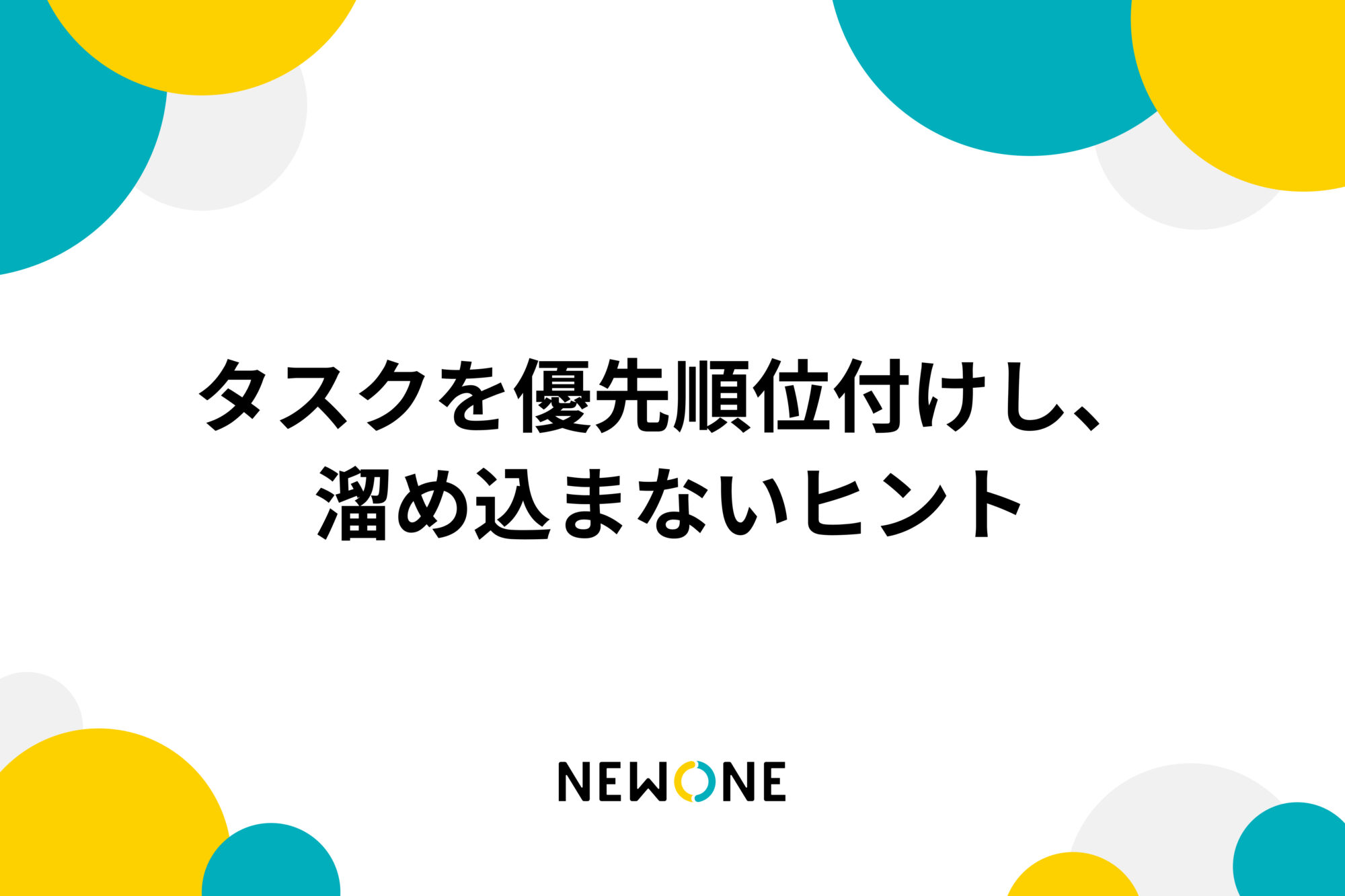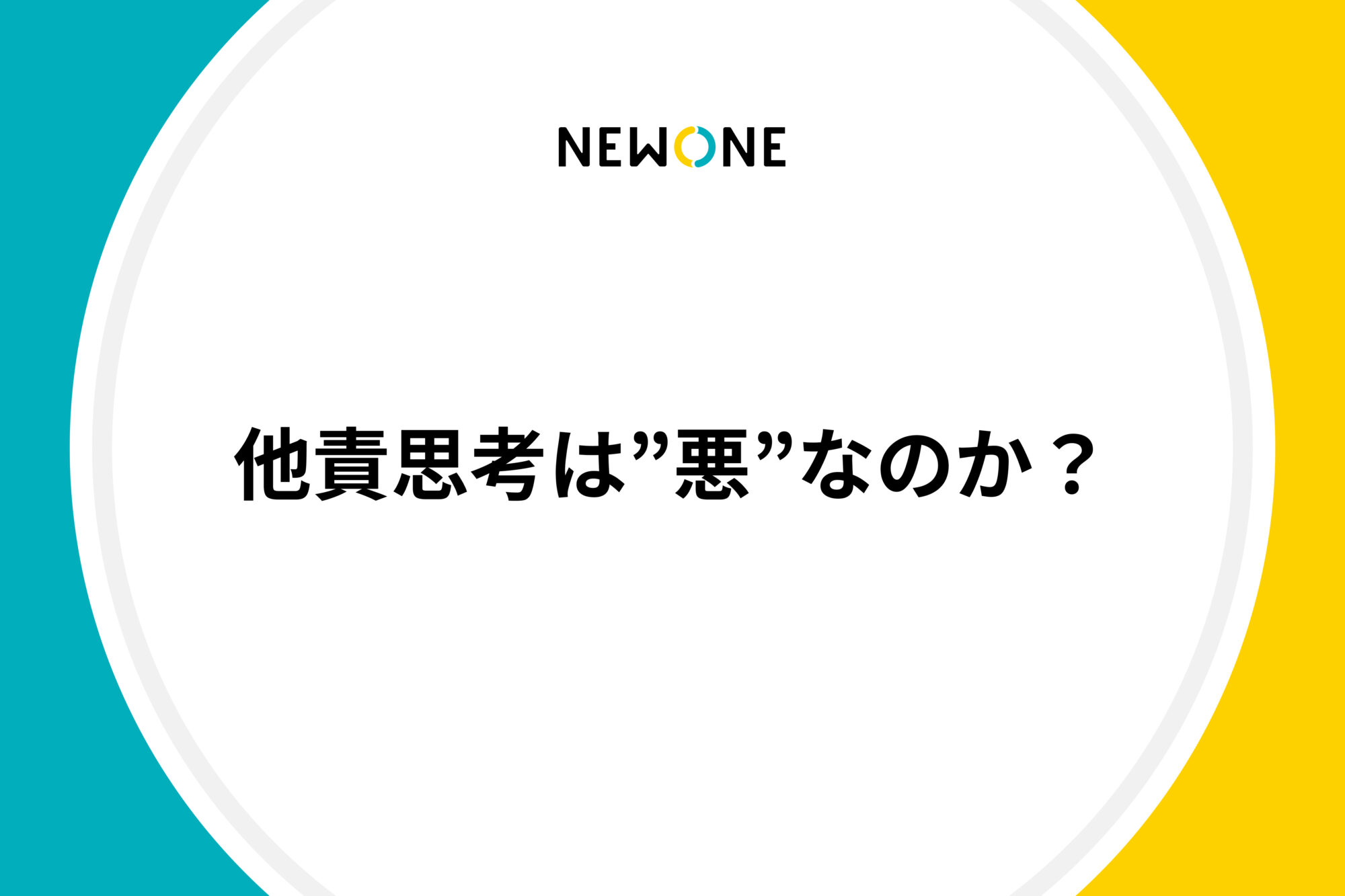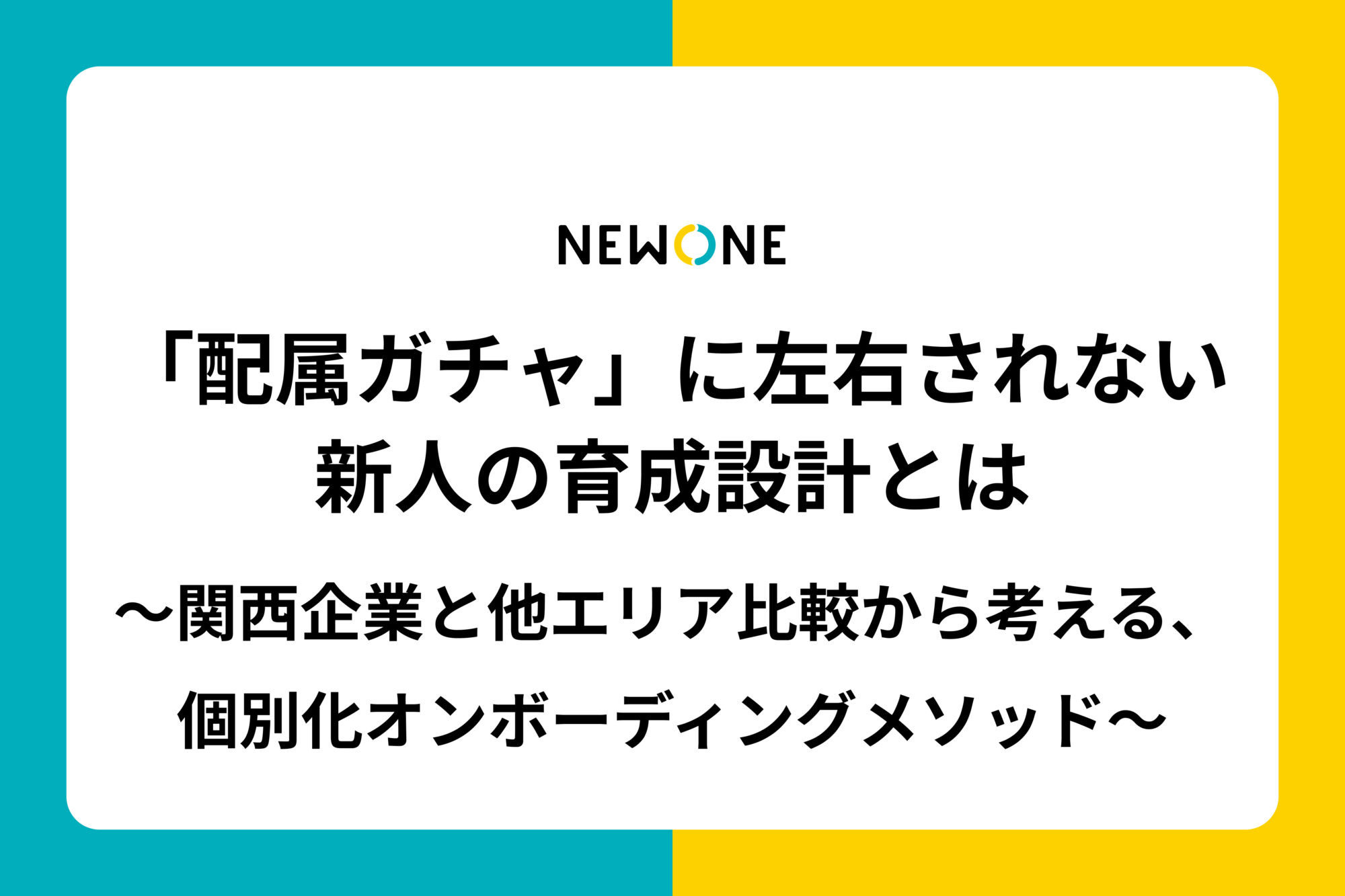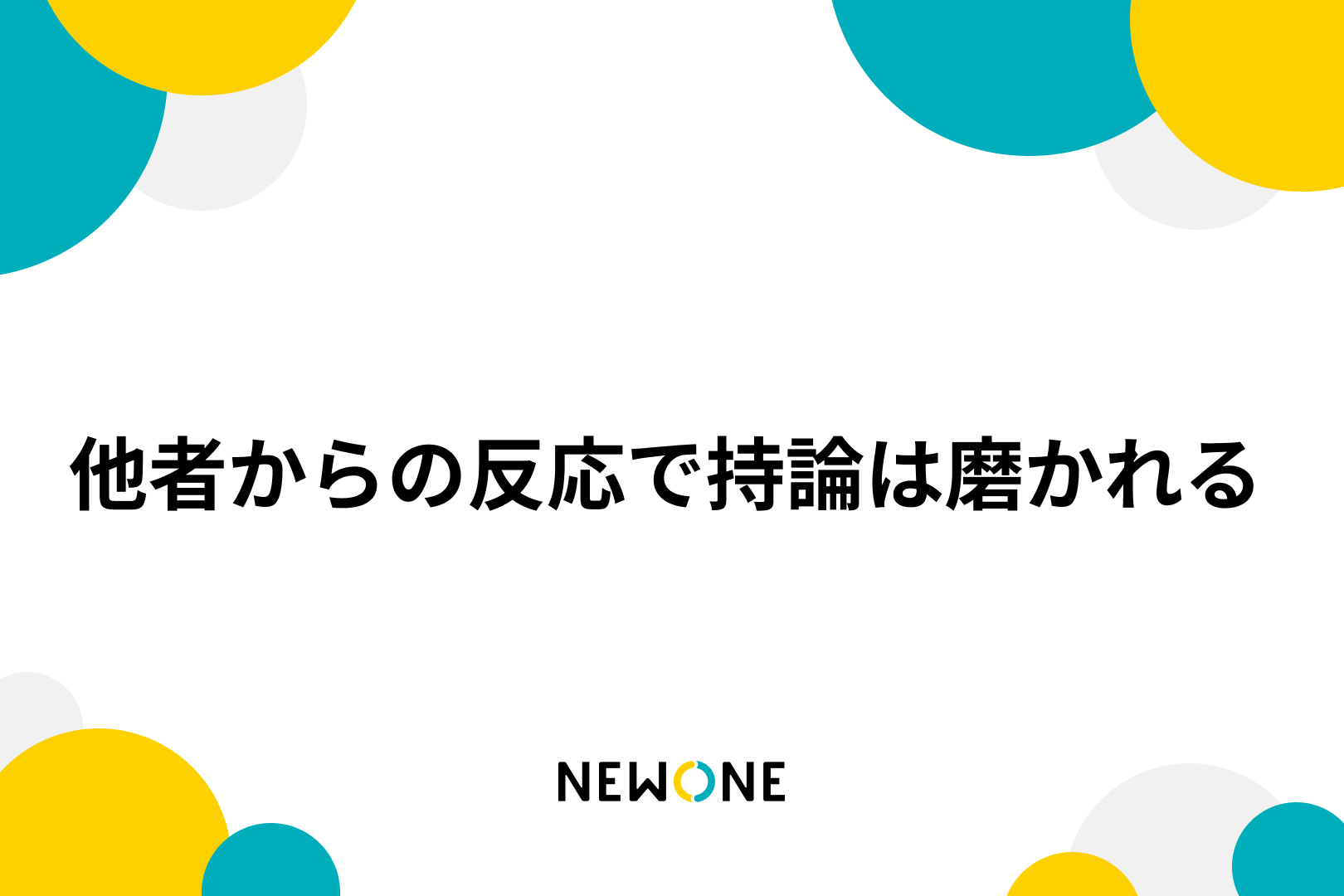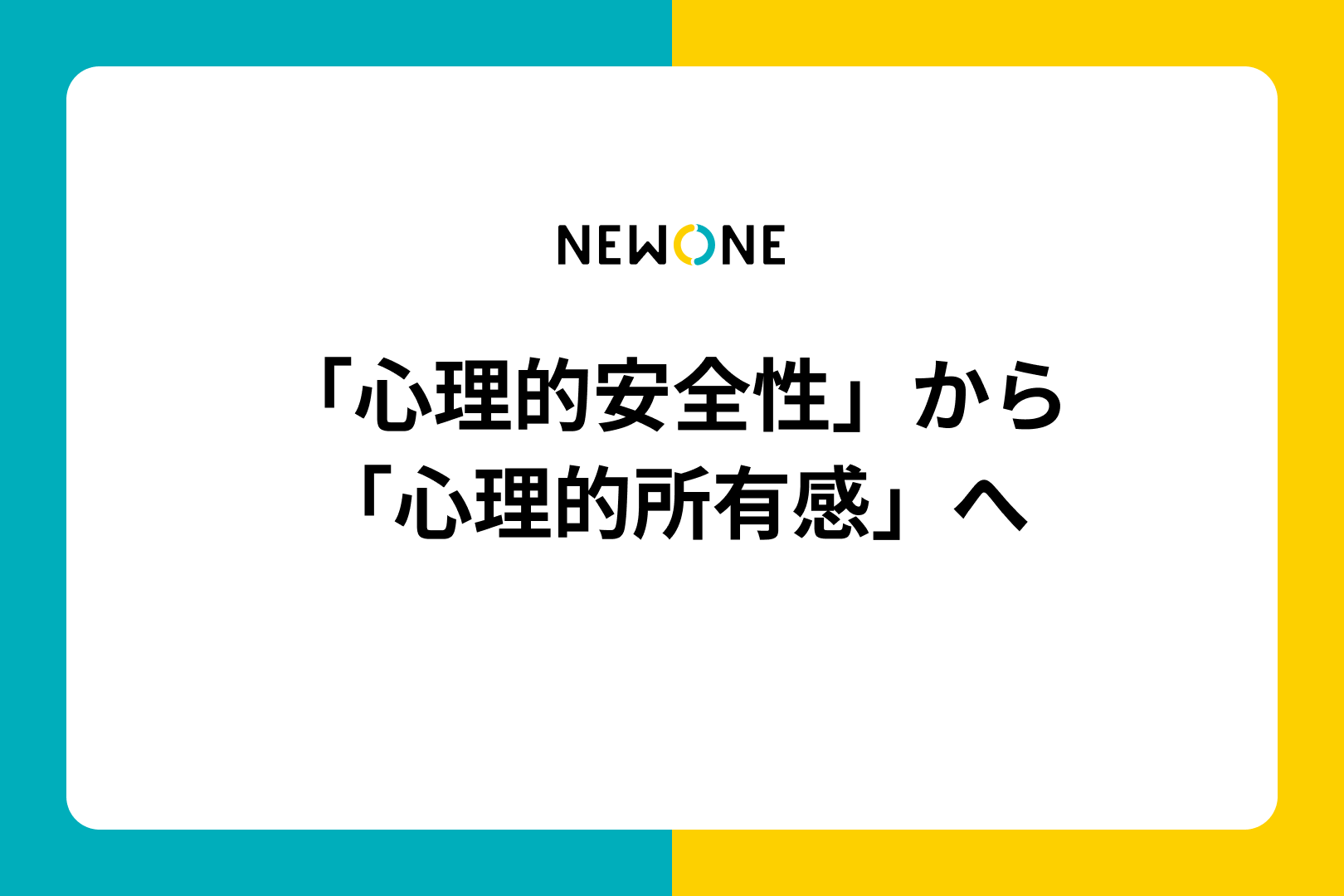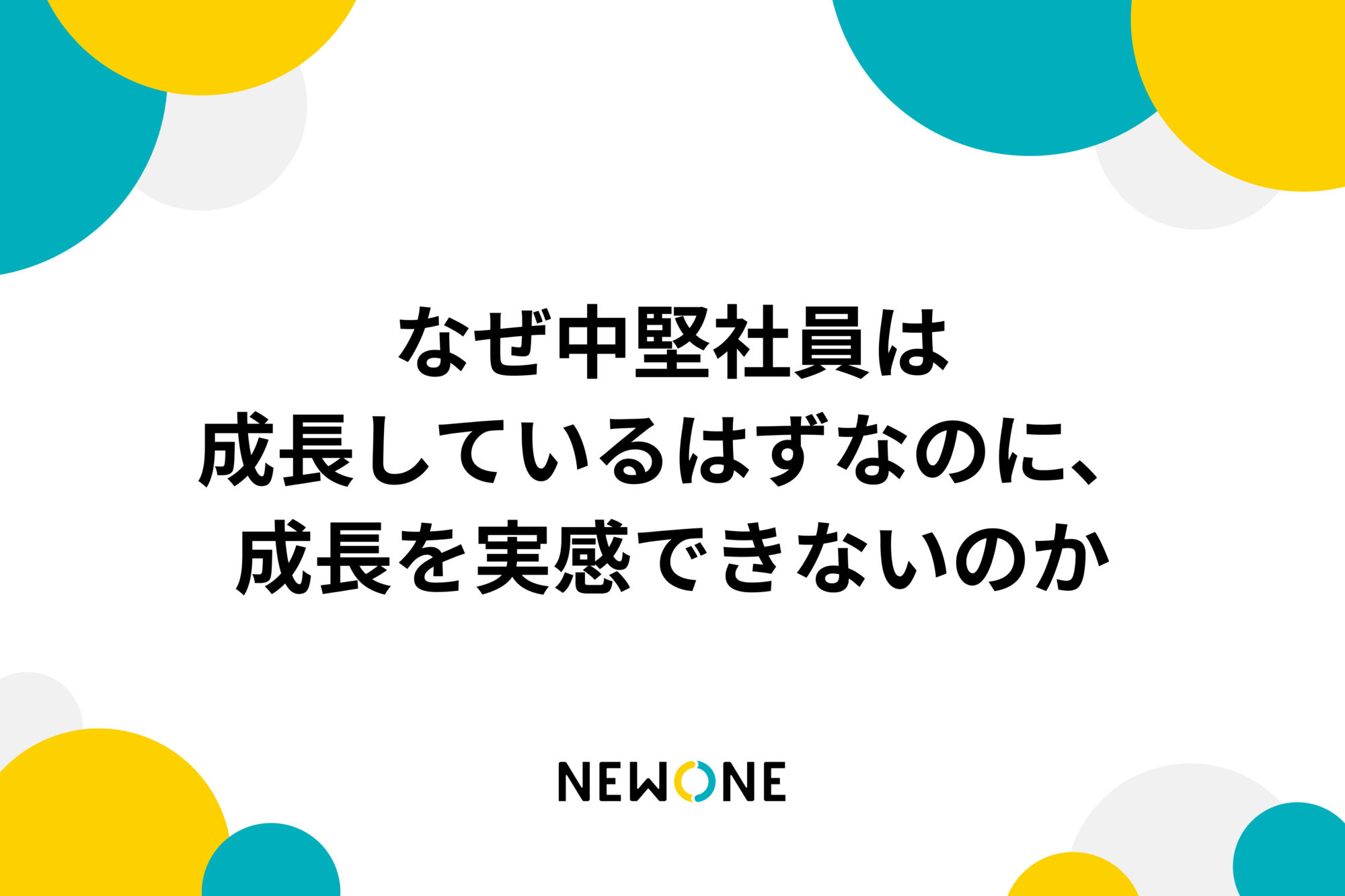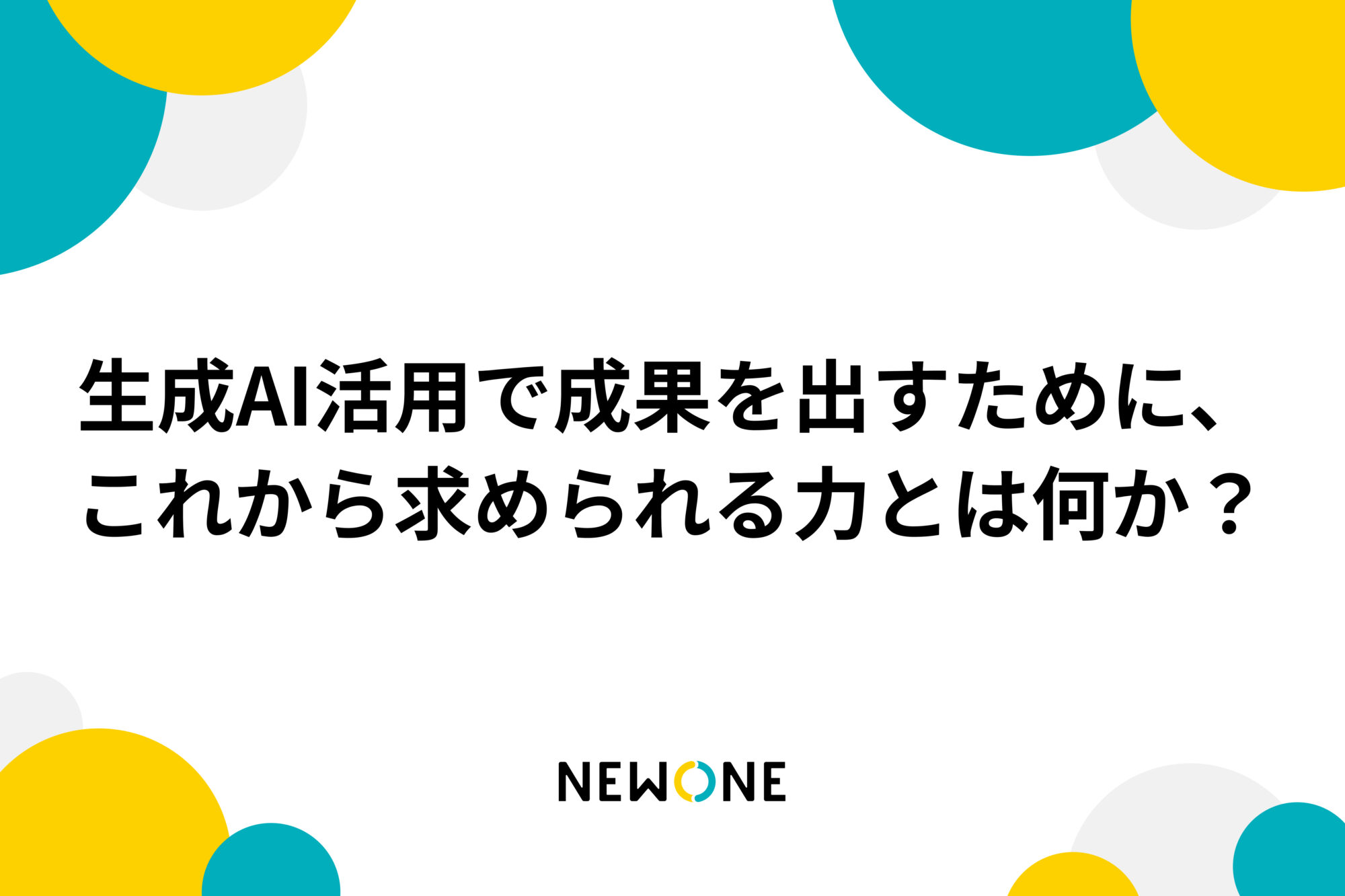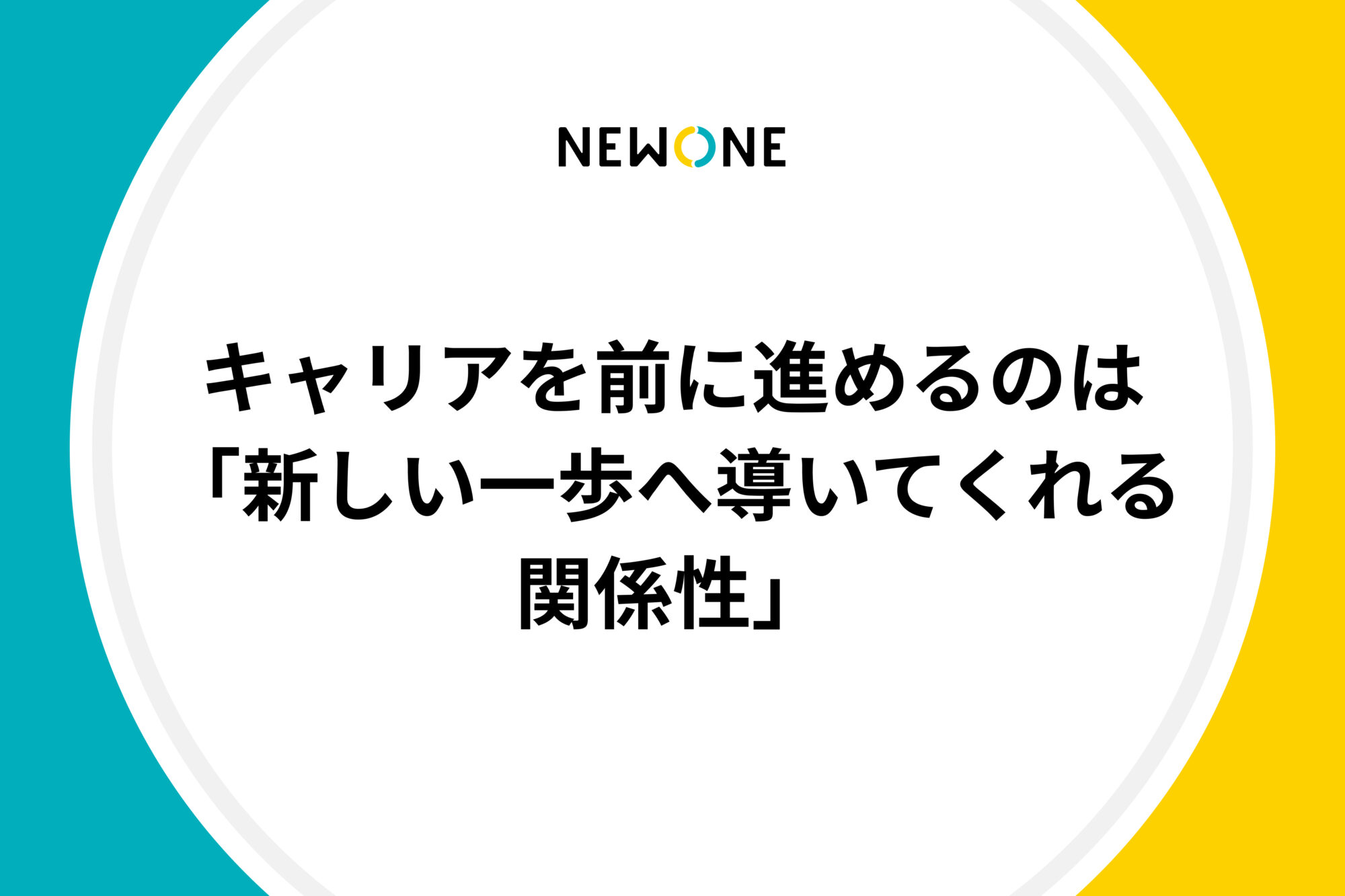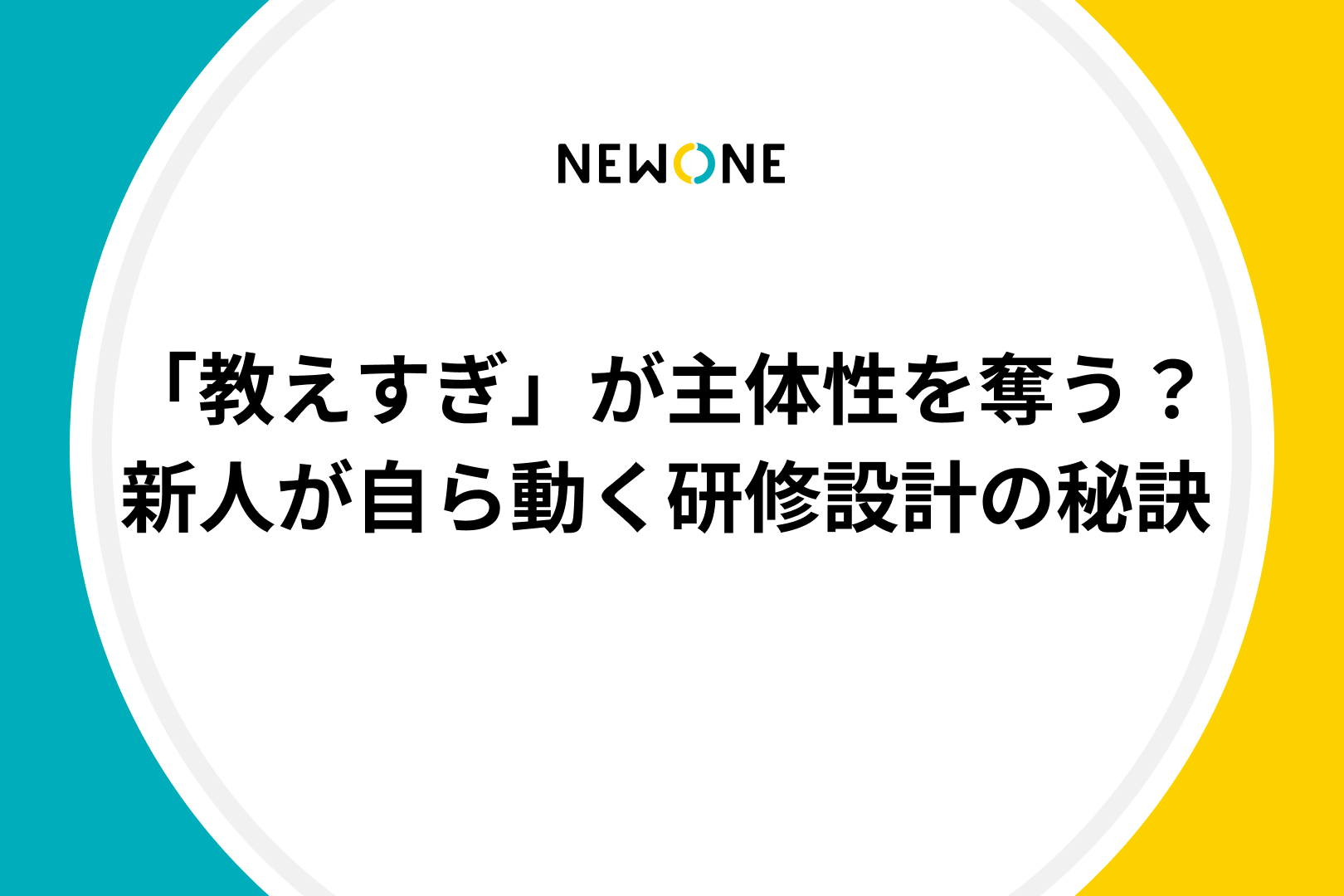
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
昨今、「新入社員にもっと主体的に動いてほしい」「指示待ちではなく、自ら考えて行動する人材に育てたい」というお悩みを、多くの企業の人事担当者様からお聞きします。
とはいえ、数日前まで学生だった新入社員にとっては、これまで「サービスを受ける側」であったため、入社後すぐに「自ら考えて動け」と言われても、どうすればよいのかわからないのが実情です。
この問いに対して、「自己決定の範囲を徐々に広げ、主体的に動く手ごたえを実感させる」ことが大事だと考えます。つまり、主体性とは「持て」と言われて持てるものではなく、小さな成功体験を積み重ねることで「自分で考えて行動することに意味がある」と実感するプロセスが必要なのです。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
主体性を育むための研修設計
具体的には、次の3つのアプローチが有効です。
1. 自己決定の機会を意図的に設計する
まずは、研修内で「自己決定できる範囲」を徐々に広げる設計が重要です。例えば、以下のような仕掛けを用意すると効果的です。
- 小さな選択肢を与える:「このタスクをどのように進めたいか?」「どちらの方法が適切か?」と問いかけ、決定の機会を増やす。
- 役割を設定する:グループワークでリーダーや発表者を決める際、「誰がやる?」と投げかけ、立候補する習慣をつける。
「まずは自分で決めて実行する習慣」を身につけさせることが、主体性の第一歩となります。
2. 失敗を許容し、挑戦を促す環境をつくる
主体性を発揮するには、「間違えてもいい」「挑戦することが大事」という安心感が必要です。しかし、間違いを厳しく指摘されると、「また指示を待とう」と萎縮してしまいます。
そこで、研修設計においては、以下のような仕掛けを取り入れることが重要です。
- フィードバックを重視する:「できたこと」「改善点」を明確に伝え、小さな成長を実感させる。
- 試行錯誤のプロセスを評価する:「結果」だけではなく、「向き合い方(スタンス)」「取り組んだプロセス」にも焦点を当てる。
「主体的に動いたことで学びが得られた」という体験を積ませることで、挑戦する意欲が芽生え、主体性が育っていくのです。
3. 「主体性を発揮することのメリット」を実感させる
新入社員は、「自分から動くことが本当に必要なのか?」という疑問を持っています。そのため、主体的に行動することが自分にとってプラスになると実感させることが大切です。
- 実践型の研修を取り入れる:「主体的に動いたことで、顧客や先輩から良いフィードバックをもらえた」など、主体性を発揮したことが評価される経験を積ませる。
- 「なぜ?」を問い続ける:「この仕事は何のためにやるのか?」「誰のためになるのか?」と問い続けることで、目的意識を持たせる。
「主体的に動くことは自分の成長につながる」という手ごたえを感じさせることで、自然と自ら考え行動する習慣が身についていきます。
まずは小さな意思決定の場を作ってみてはいかがでしょうか?
まずは、研修の中で「どの方法でやるかを選ばせる」「どの役割を担うか決めさせる」など、小さな意思決定の場を意図的に増やしてみてください。選択の積み重ねが、新人の「考えて動く力」を育て、徐々に大きな意思決定にもつながっていきます。
 棚橋 彩香" width="104" height="104">
棚橋 彩香" width="104" height="104">