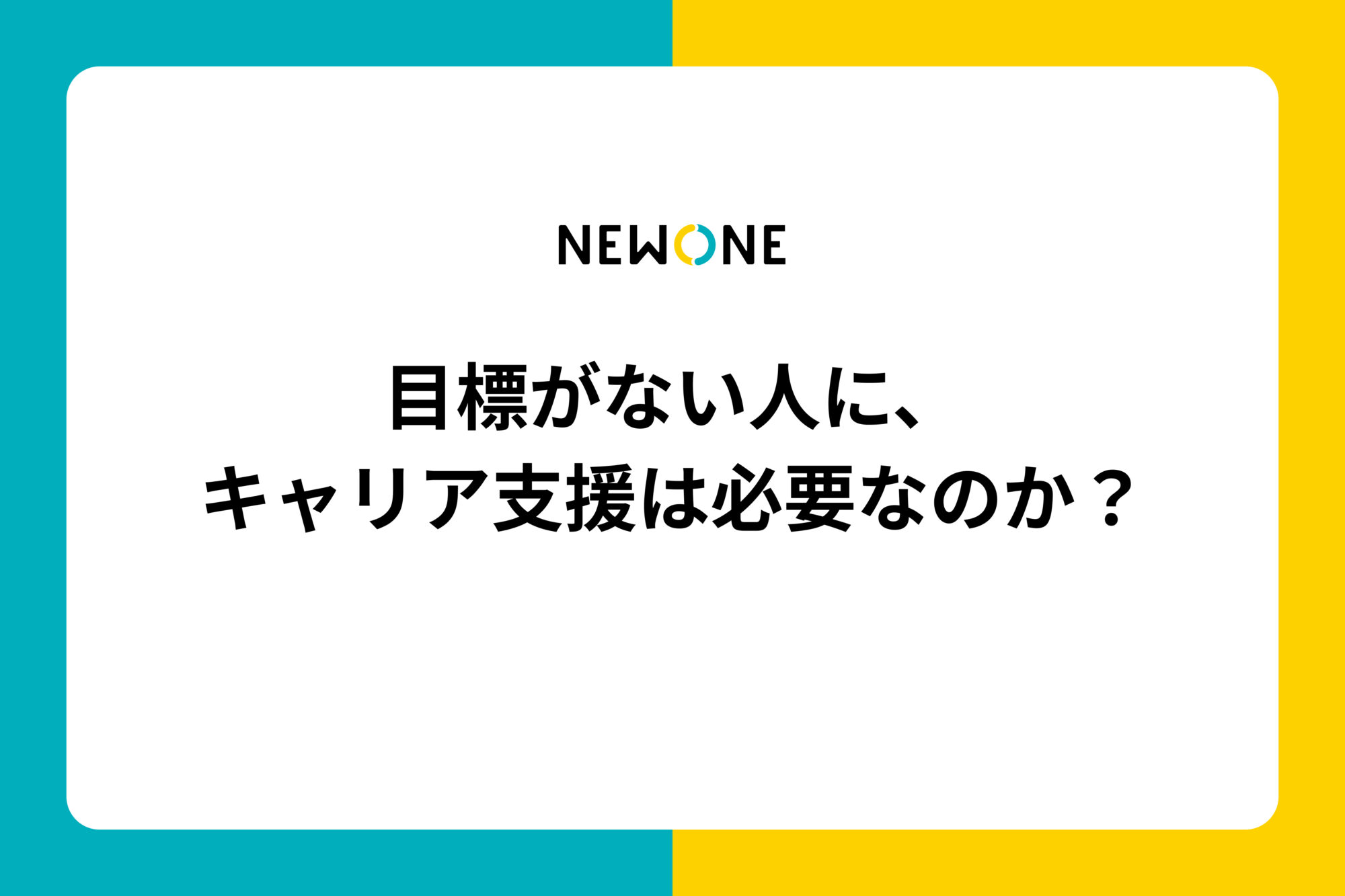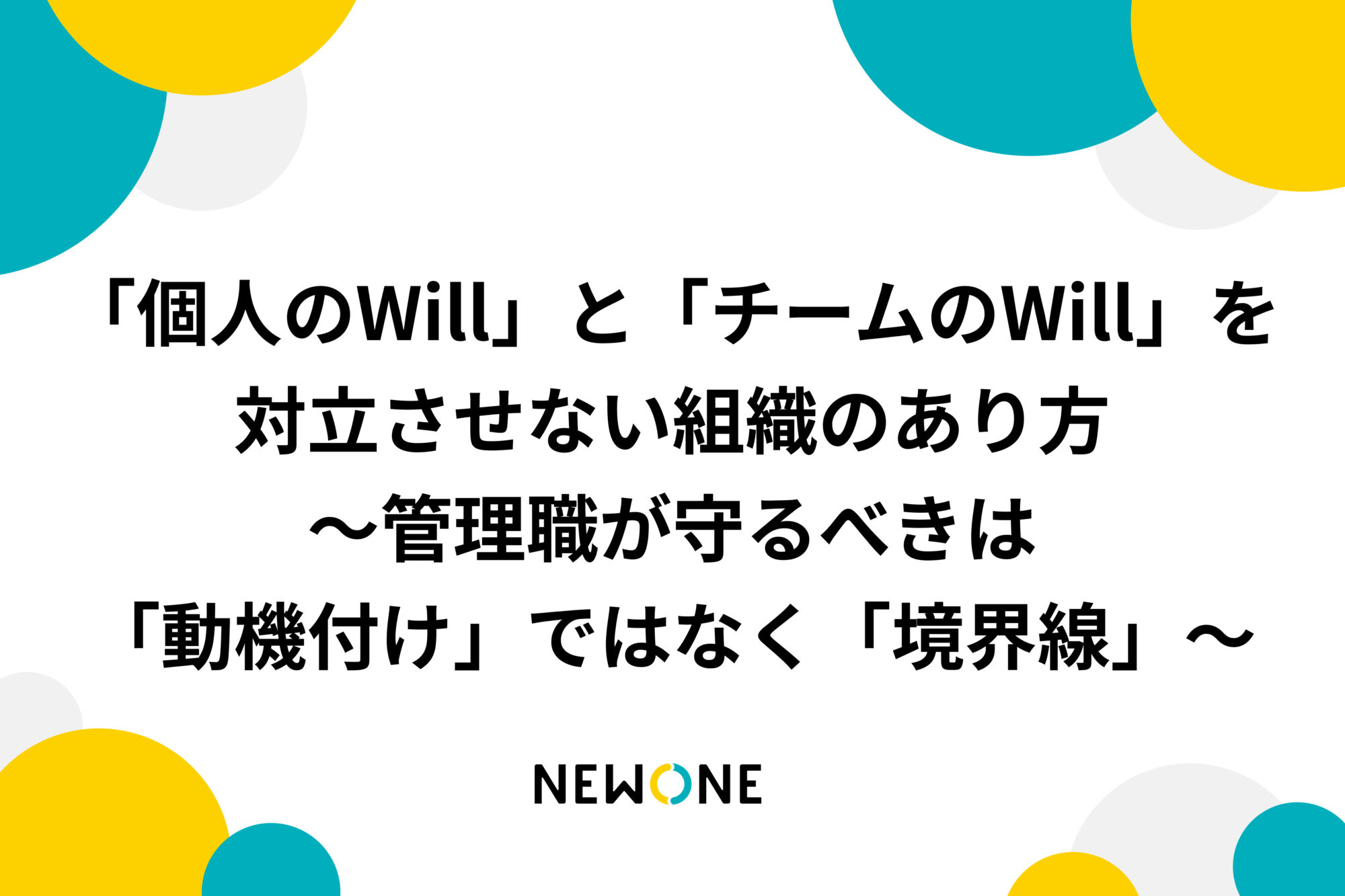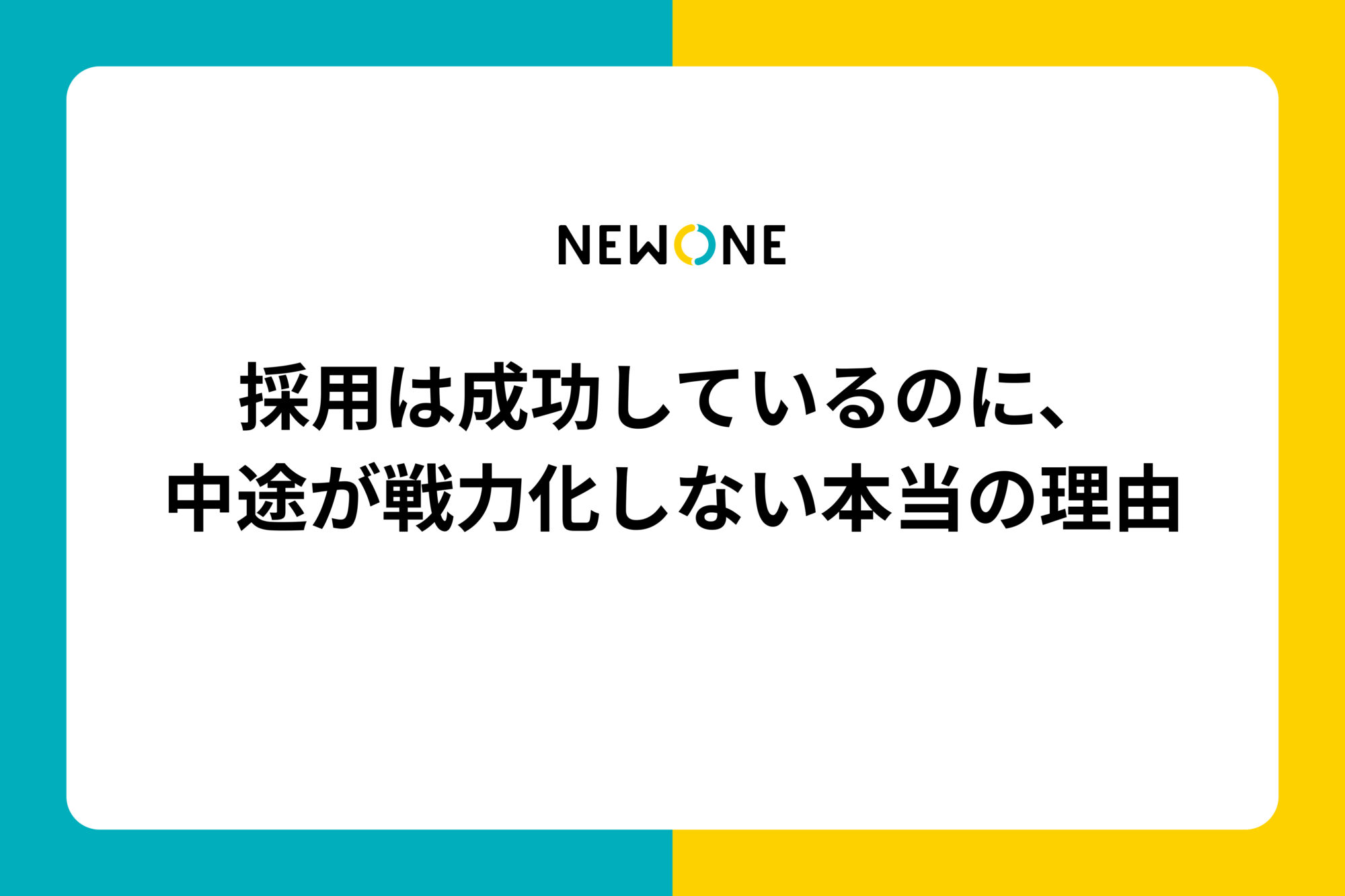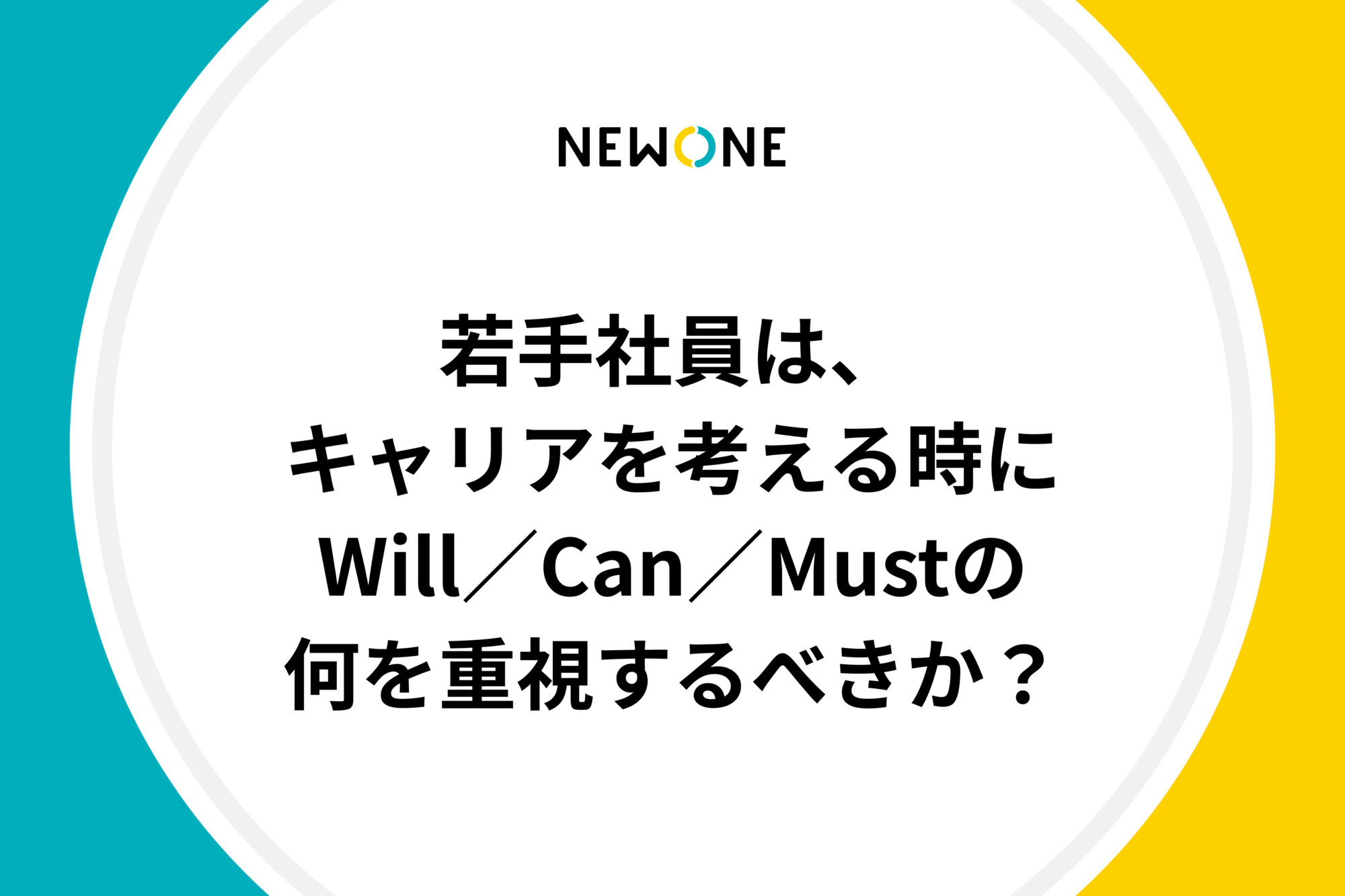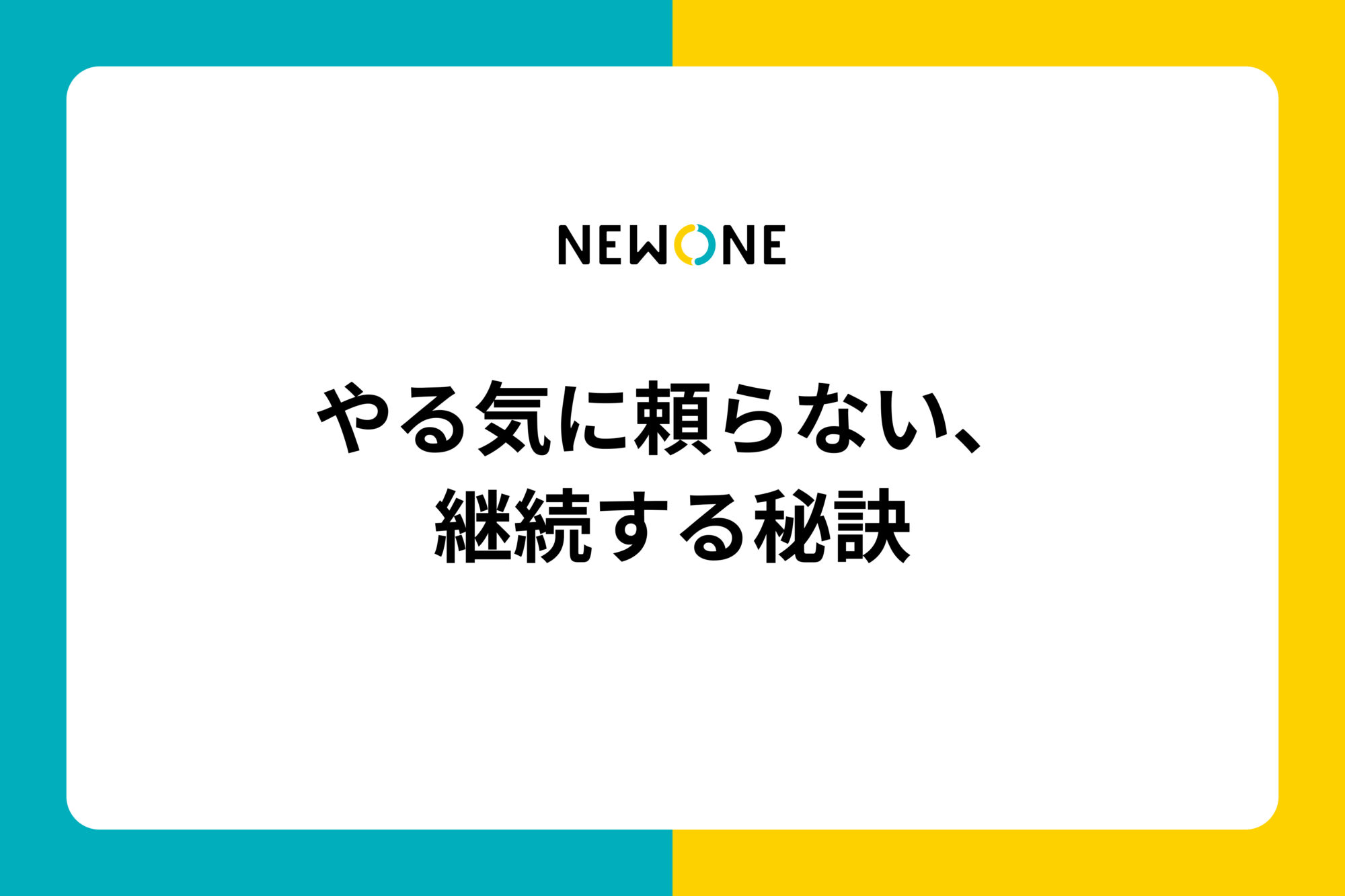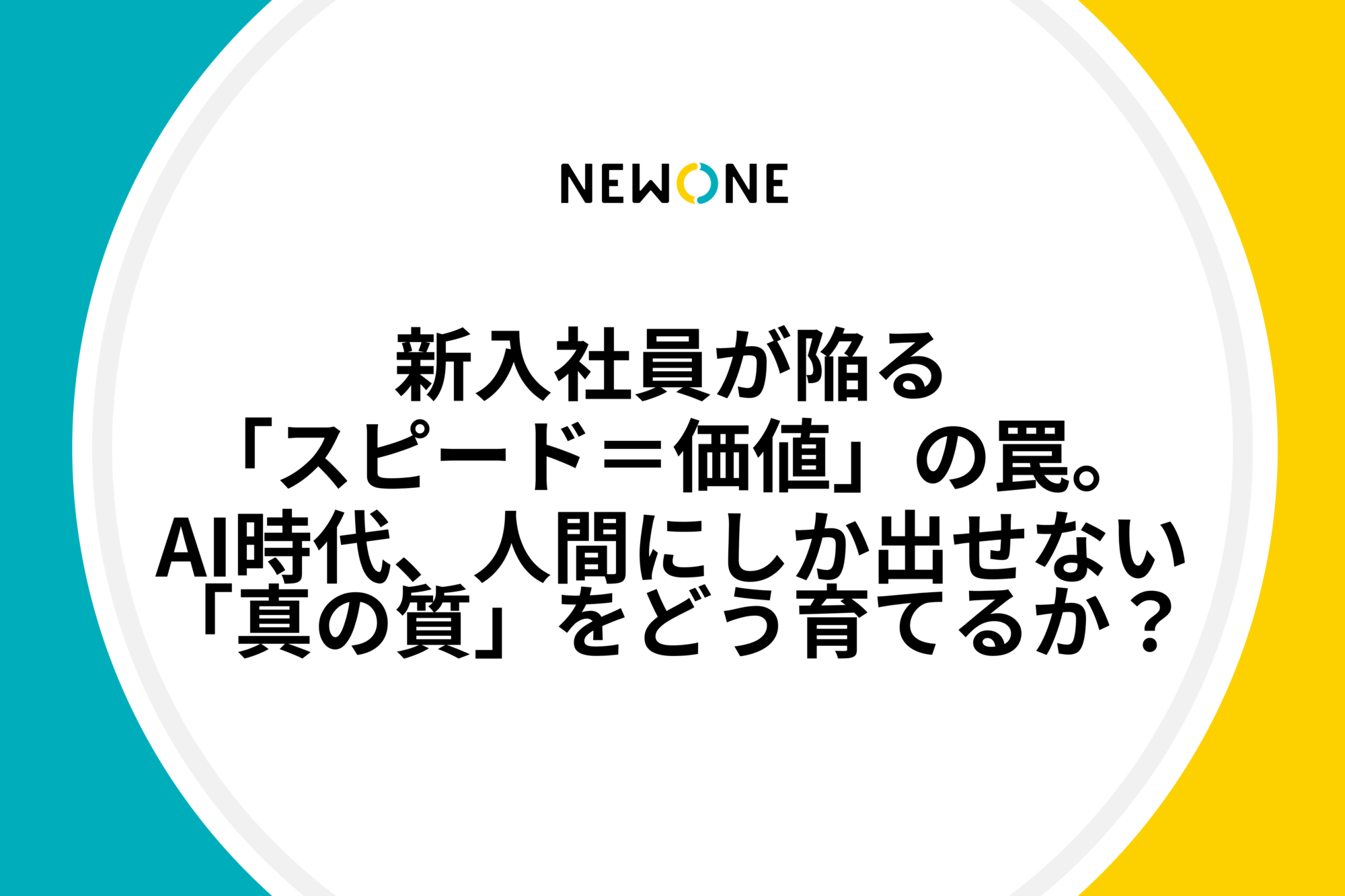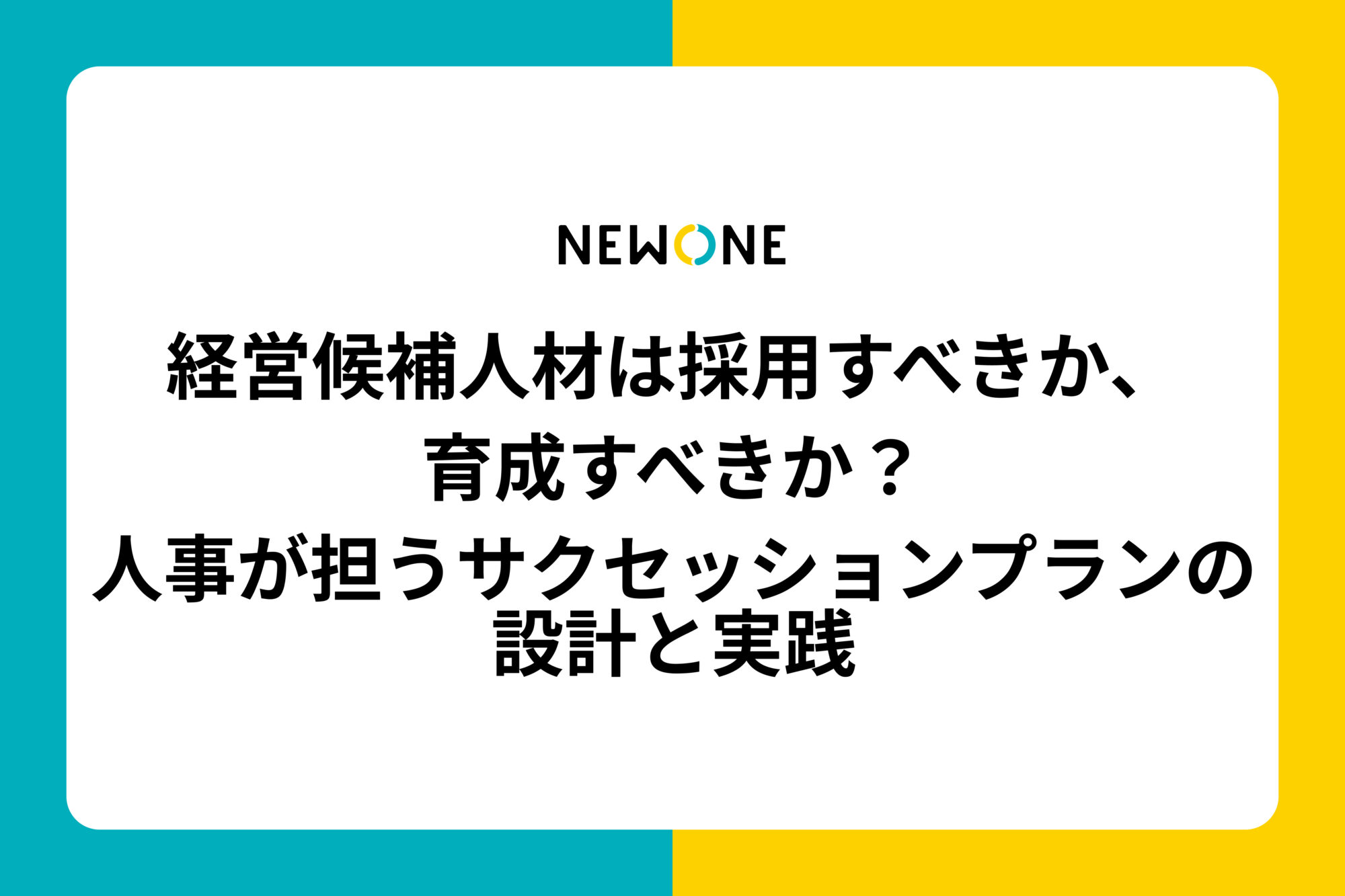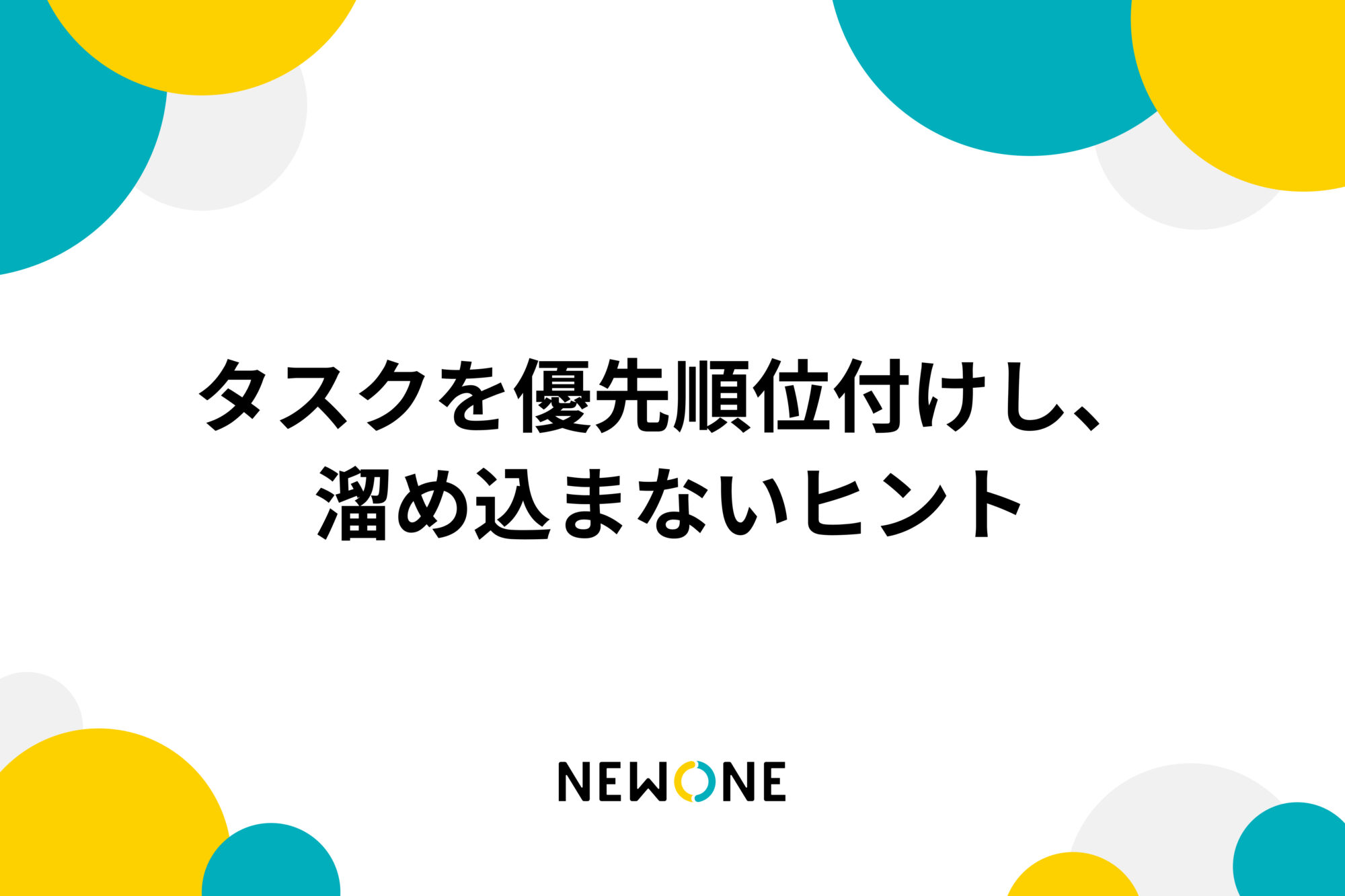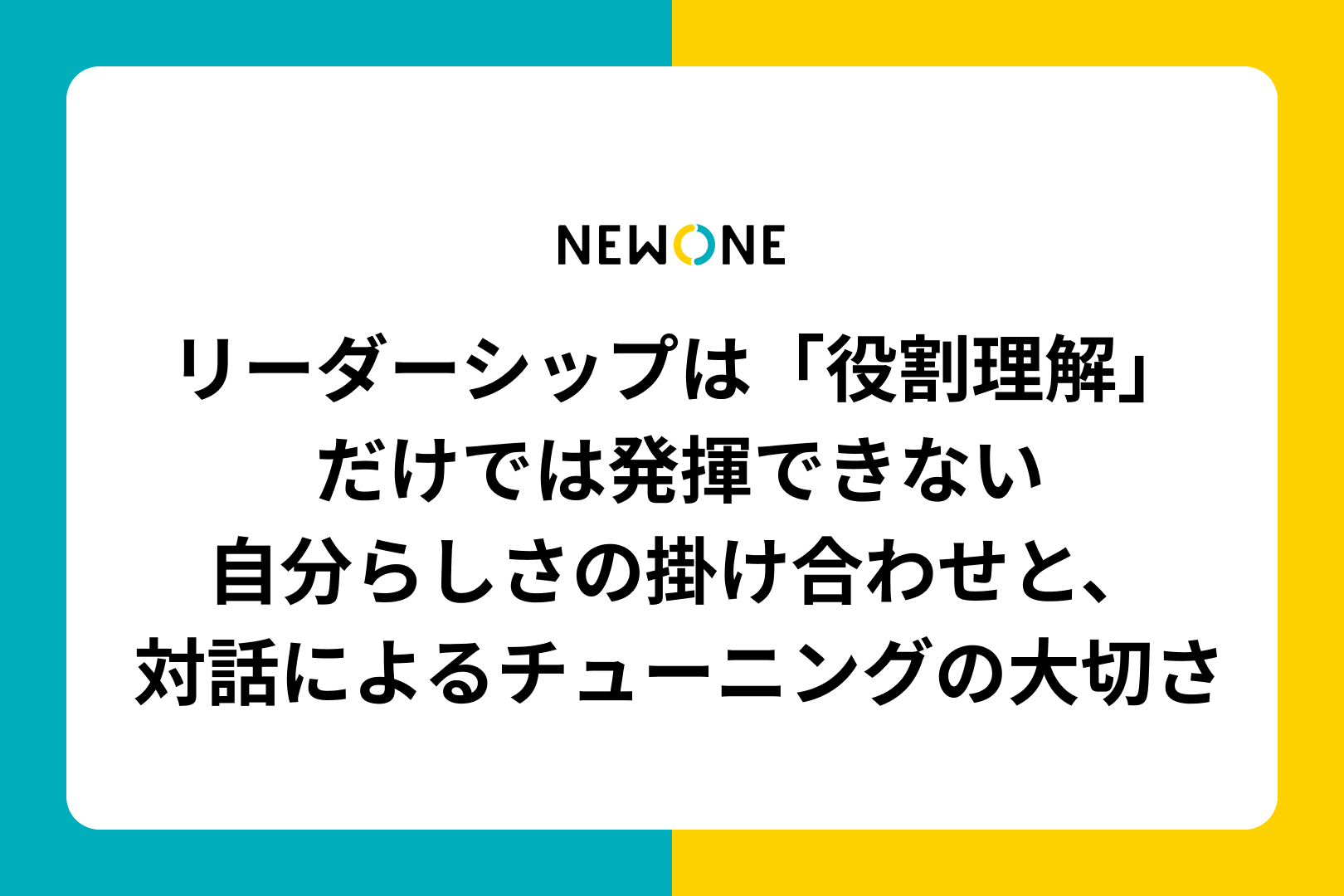
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
多くの組織では、中堅層に「役割を理解し、リーダーシップを発揮してほしい」と期待しています。
確かに、リーダーとして職務や等級に応じた役割を理解し、遂行することは大前提です。
しかし現実には、役割期待を理解するだけのリーダーでは、周囲を動かす力、つまり本物のリーダーシップ発揮にはつながりません。
そこに必要なのは、自分自身の強みや価値観といった“自分らしさ”との掛け合わせです。
そのためには、上司や周囲との対話を通じて調整(チューニング)していくプロセスが欠かせません。
なぜ「役割理解」だけではリーダーシップ発揮につながらないのか
リーダーシップとは「目的に向けて他者を動かす影響力」です。
人は誰の言葉にでも動かされるわけではなく、その人だからこそ感じる熱や覚悟、納得感が必要です。
役割だけを理解して行動する人は、正しいことは言えても、それが本人の想いや人柄とつながっていなければ納得感を生むことができません。結果として周囲も動かないのです。
つまり役割理解は必要条件ですが、自分らしさとの掛け合わせがなければ十分条件にはならないのです。
「自分らしさ」との掛け合わせが自分も周囲も本気にさせる
役割を理解するだけなら、書籍や動画を見ればある程度は理解できます。
しかし、そこに自分の価値観や強み、これまでの経験が重なることで、初めて本人が本気になり、その熱量が伝わって「自分も動きたい」と周囲も本気になるのです。
逆に、自分の価値観や強みをどこでどう活かすのか、役割をどう自分なりに意味づけるのかを言語化できないリーダーは、行動が表面的になりやすく、周囲も動きたいという動機づけがされません。
その掛け合わせには「対話によるチューニング」が欠かせない
多くのリーダーは、役割をどこまで優先し、どこから自分らしさを出すのかで悩みます。
これは最初から正解が分かるものではなく、上司との面談や1on1、周囲からのフィードバックを通じて、少しずつ調整していくしかありません。
つまり、役割理解と自分らしさの掛け合わせは、職場での実践と対話を繰り返す中でしか磨かれないのです。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
なぜ現場でこの「チューニング」がうまくいかないのか
現場では、上司が役割期待を伝えるだけで終わり、部下は「分かりました」と表面的に応じるだけになりがちです。
その一方で心の中では、「自分には合わない」「どう折り合いをつければいいか分からない」と悩んでいます。
しかし、忖度や遠慮から本音を言えず、過度に「自分が未熟だから」と自責したり、「上司が分かってくれない」と他責に走ったりすると、本気になれず、周囲を動かす影響力発揮にはつながりません。
人事が取り組むべき「掛け合わせを支援する対話設計」
人事としては、単に役割を理解させるだけでなく、自分らしさとの掛け合わせを支援する場を用意することが重要です。
具体的には、強みや価値観、これまでの経験を棚卸しし、それを役割とどうつなげるのかを考える機会を設けること。
さらに、上司との定期的な対話を通じて「期待される役割に自分のどんな強みが活きているか」「逆にどこで引っかかっているか」を言語化し、確認していくことが必要です。
また、いきなり大きな役割を任せるのではなく、小さなリーダーシップ発揮から始め、それを上司やチームで振り返るサイクルを回すことで、安心して挑戦できる環境を作ることも欠かせません。
まとめ
リーダーシップは、単に役割を理解しているだけでは発揮できません。
自分の強みや価値観を、組織の期待とどう結びつけるか。
それを職場で試行錯誤し、上司や周囲との対話を重ねながら、葛藤しつつも必死にもがき、リーダーシップを発揮しようとする姿勢にこそ、周囲は心を動かされるのです。
人事に求められるのは、この掛け合わせを中堅層一人で悩ませず、対話と実践の中で育む場を設計することにほかなりません。
 稲里 拓都" width="104" height="104">
稲里 拓都" width="104" height="104">