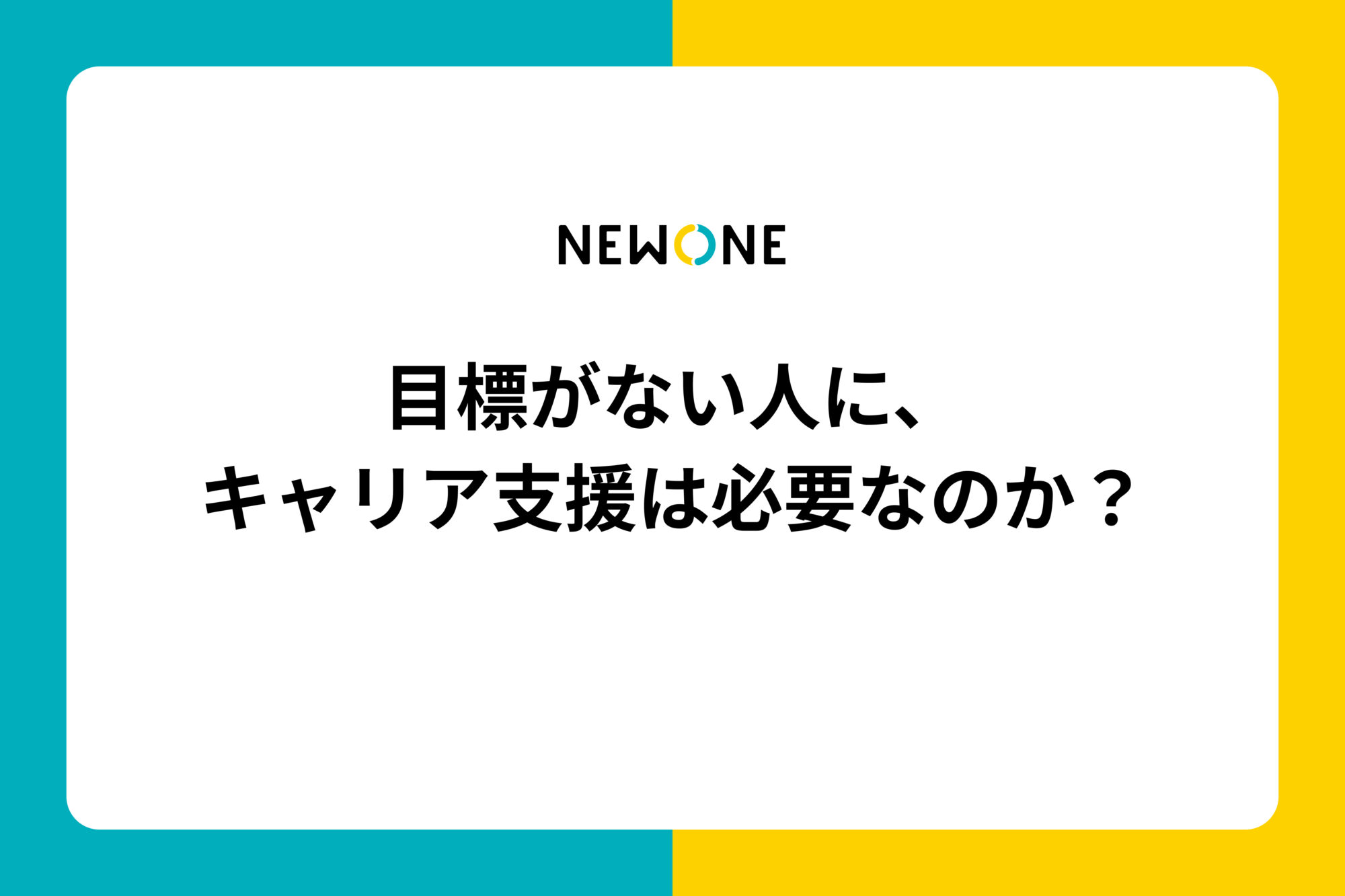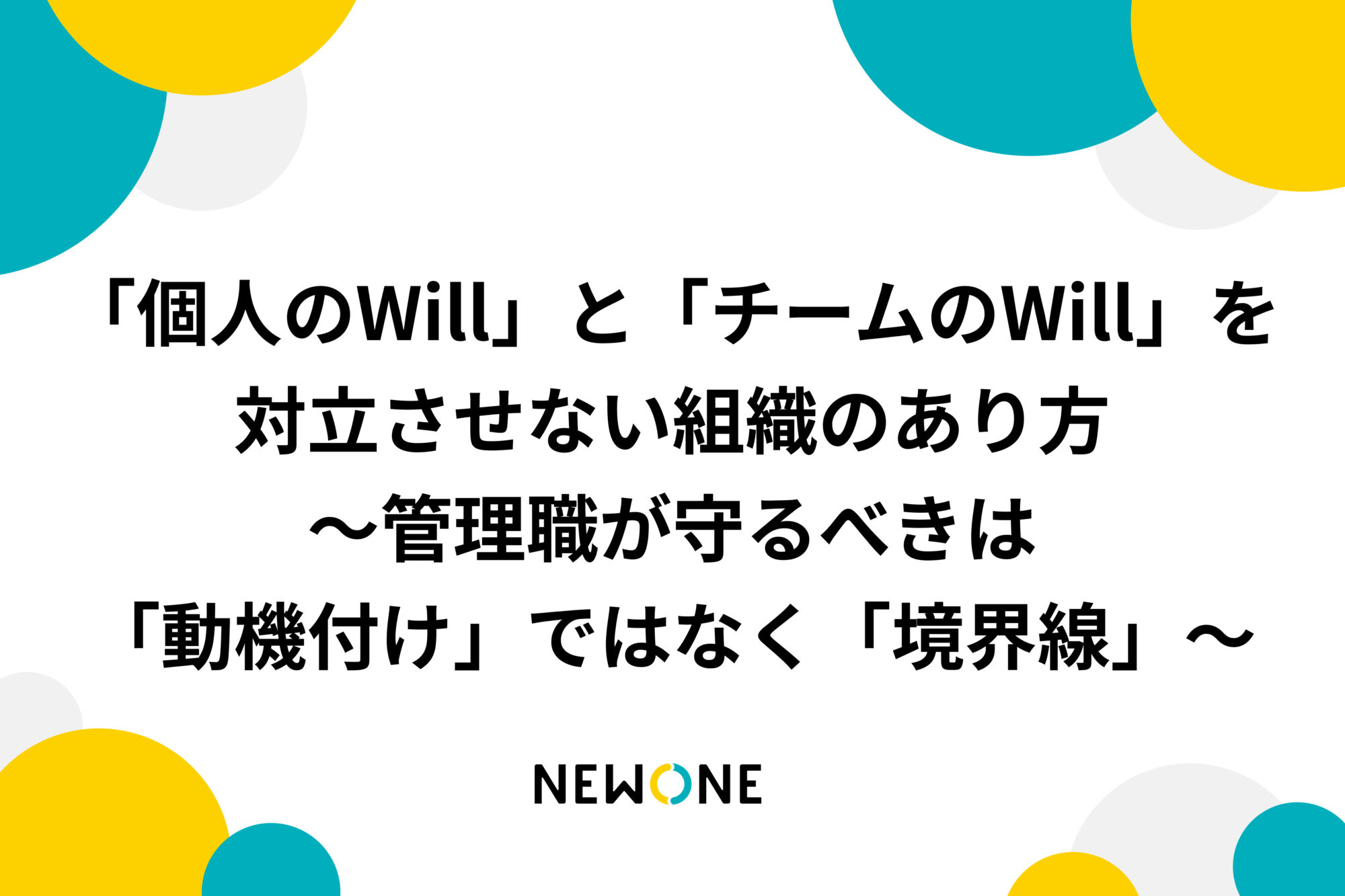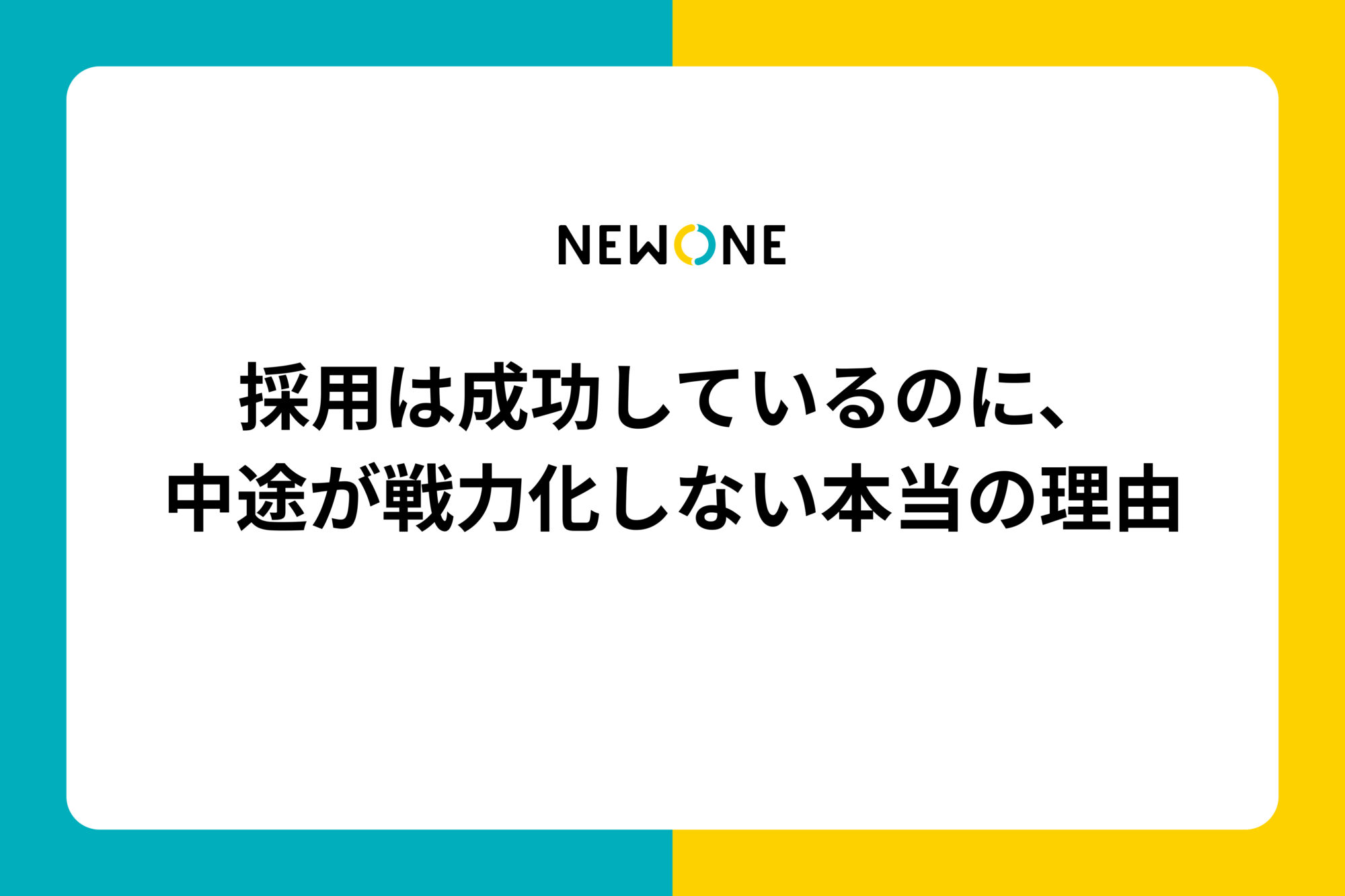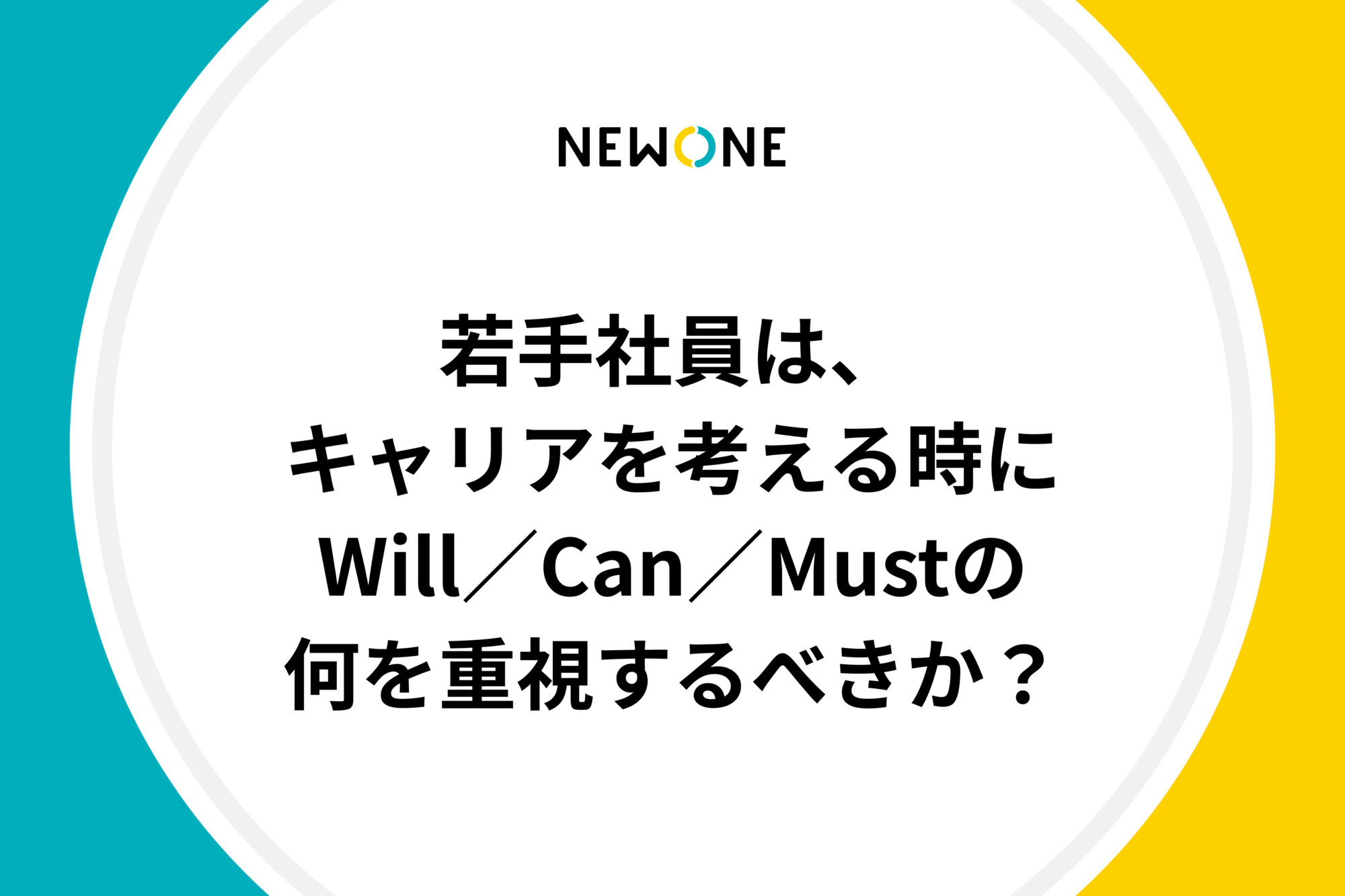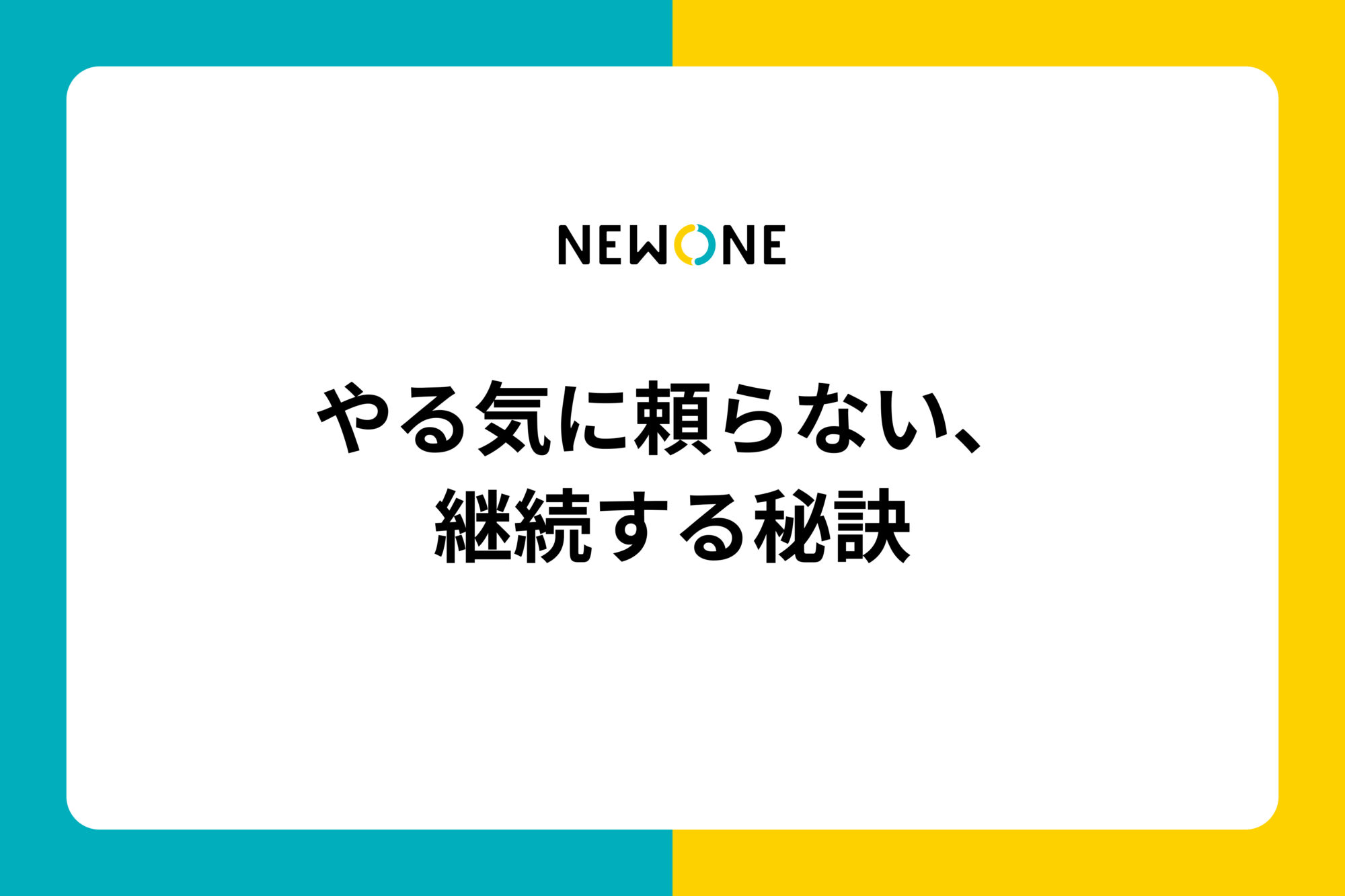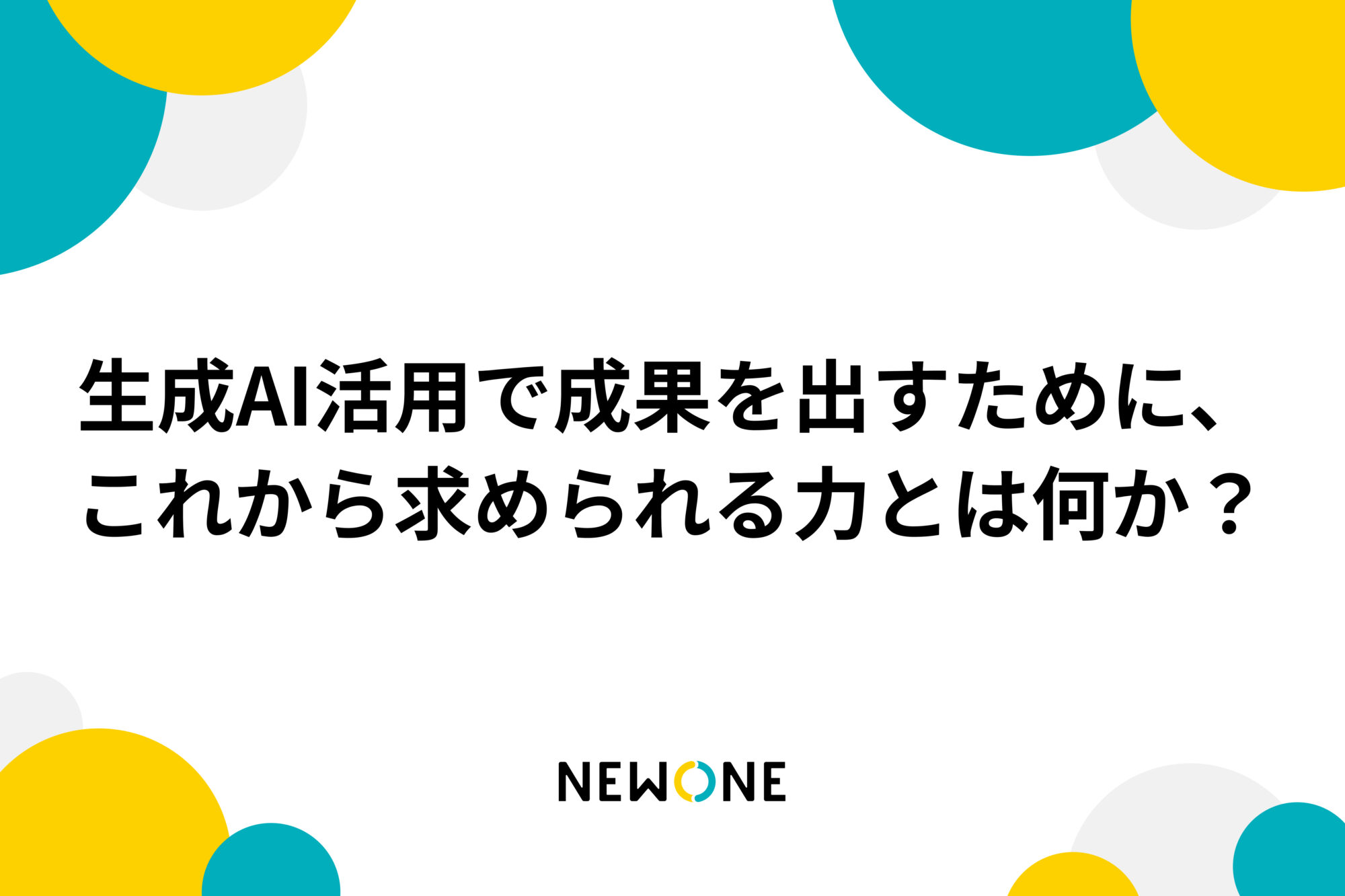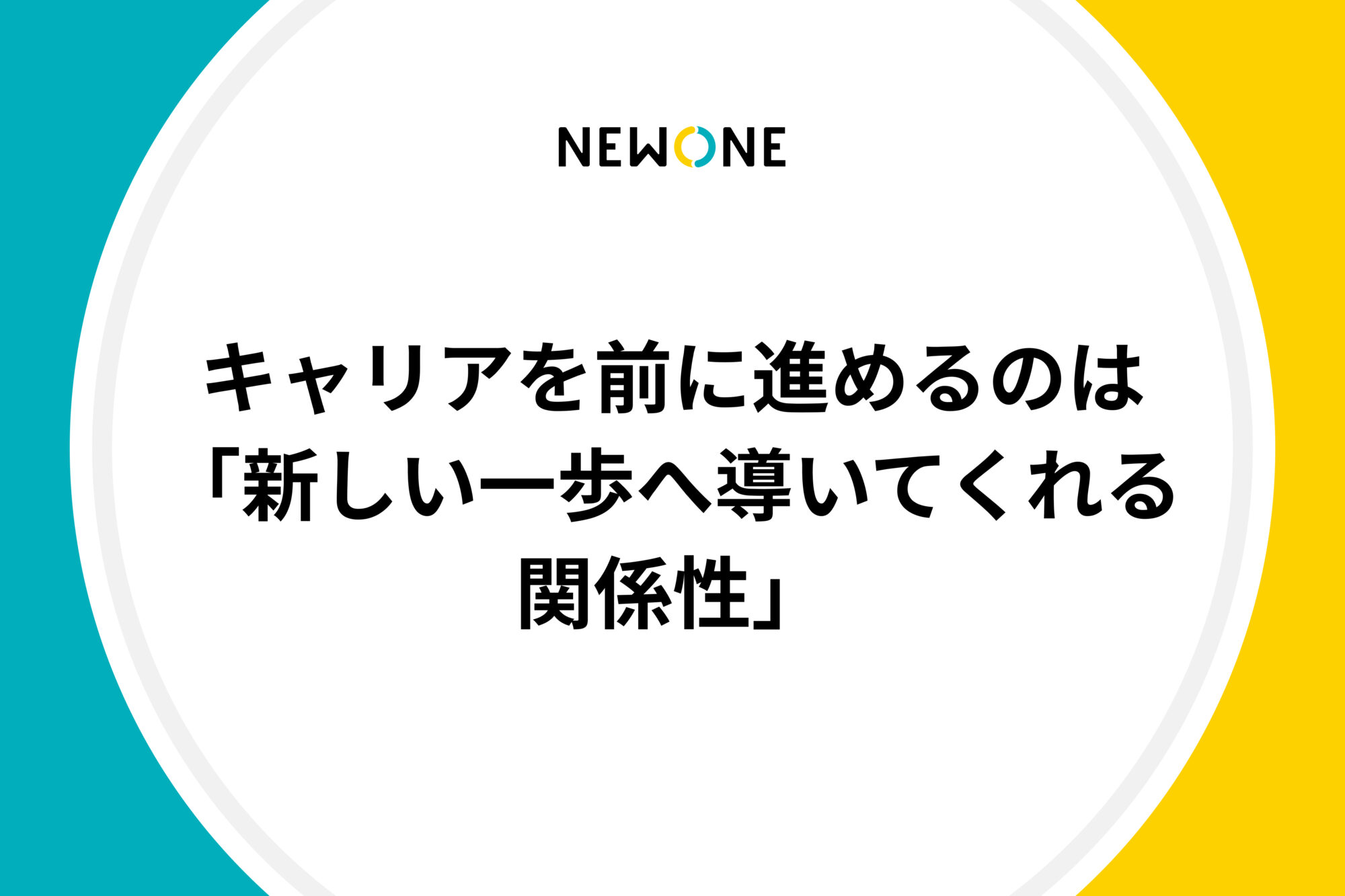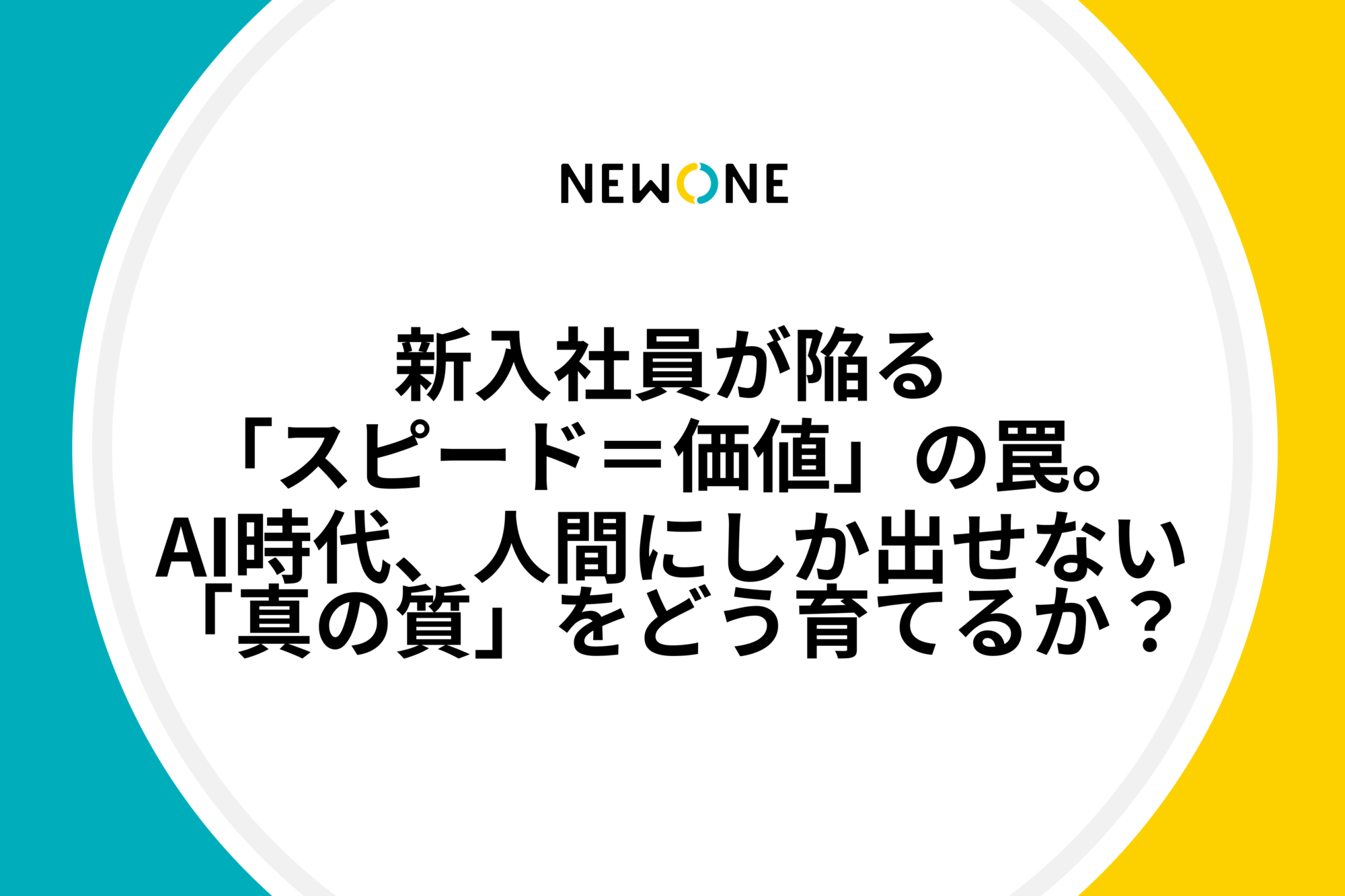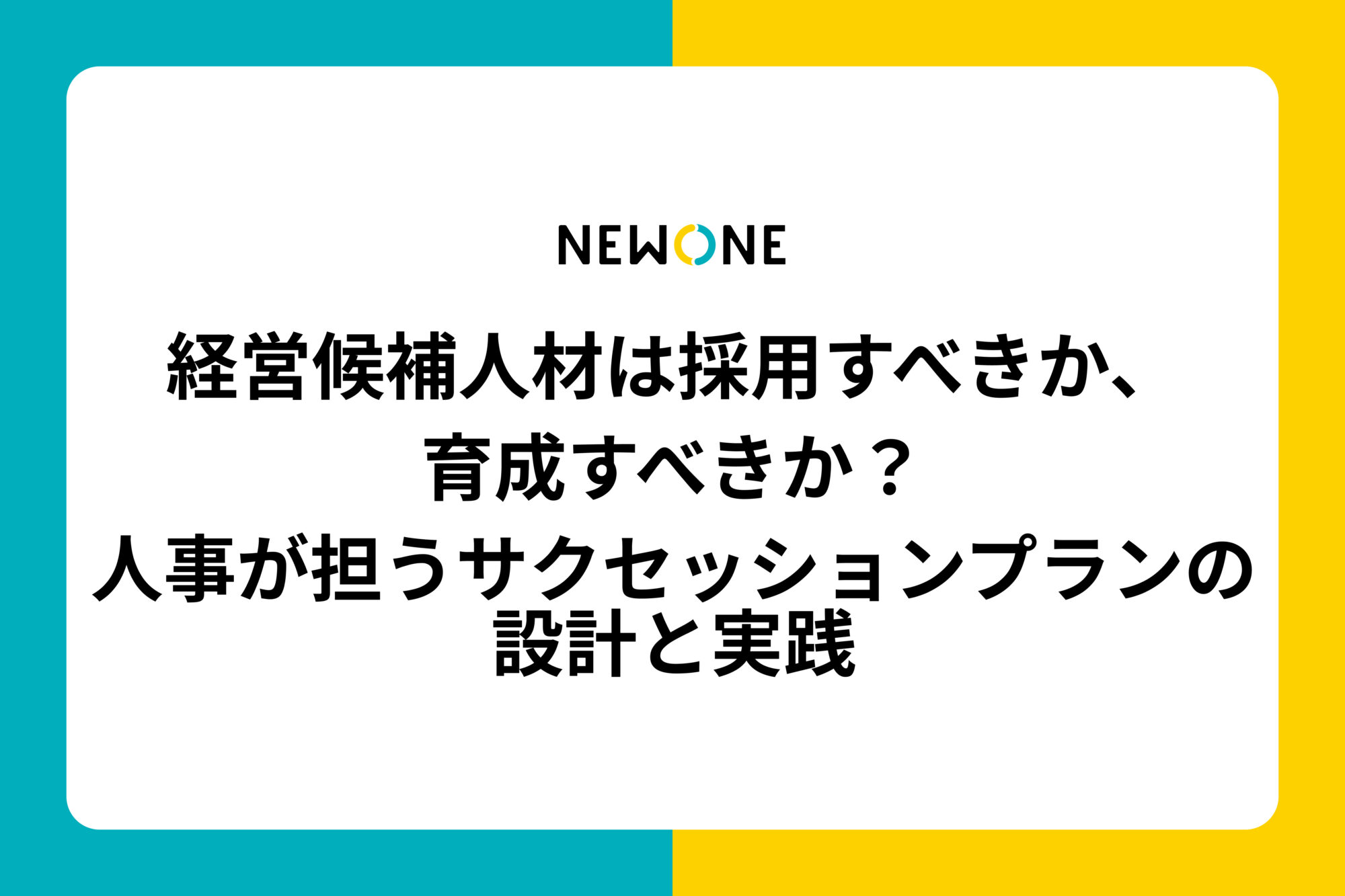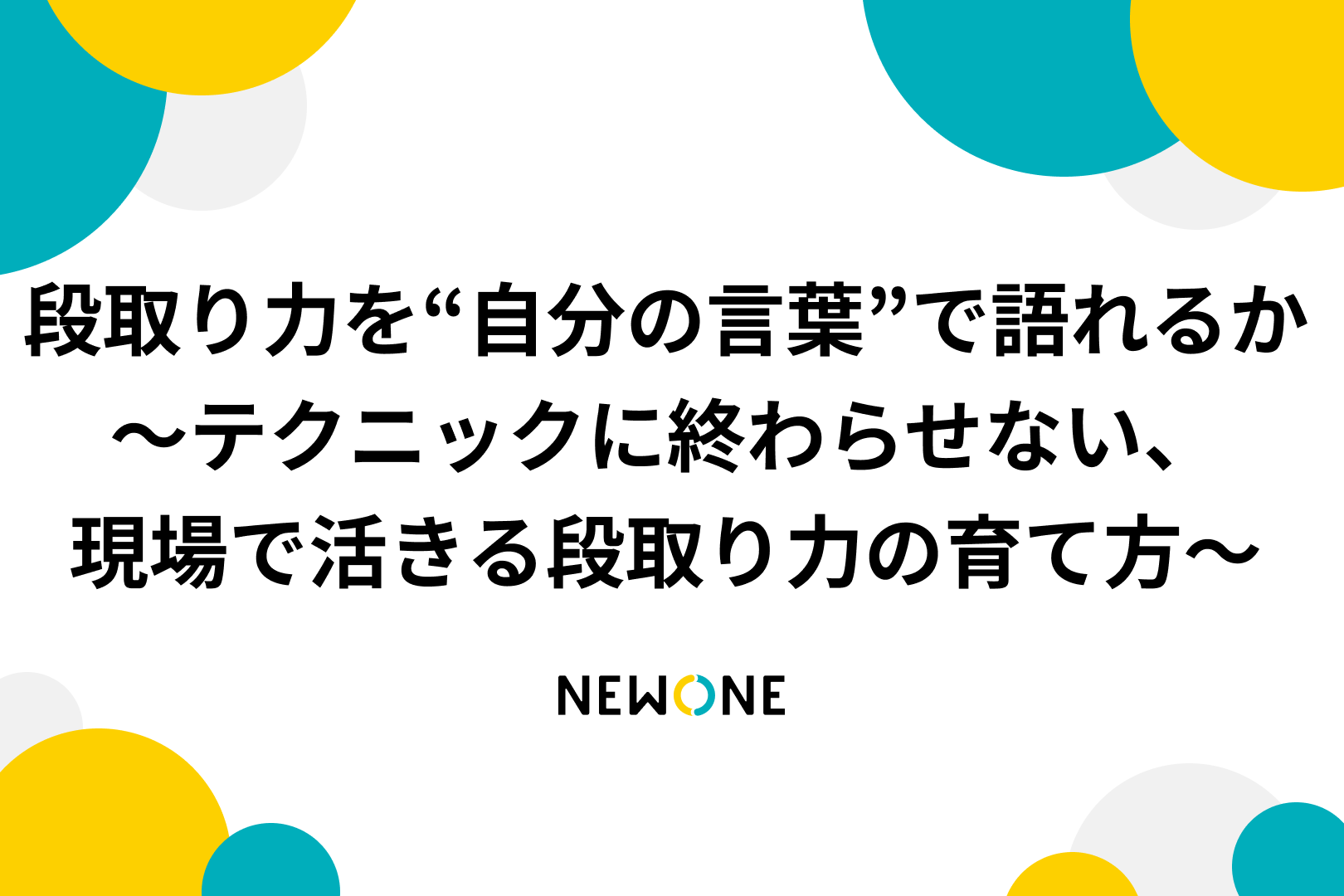
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
「段取り力」と聞くと、タイムマネジメント、優先順位づけ、逆算思考──いわゆる“タスク処理の技術”を連想する方が多いかもしれません。
書籍や研修でも、こうしたテクニカルな知識は豊富に紹介されており、ある程度“学べばできる”という印象も強いスキルです。
しかし、現場で感じるのは、知っているだけでは通用しないリアルな複雑さです。突発対応、関係者の調整、計画変更、抜け漏れの発生…。こうした中で本当に求められるのは、「自分なりの判断軸を持ち、現場で自走できる段取り力」なのではないでしょうか。
テクニックだけでは足りない
段取りとは、「何を」「いつ」「どうやって」やるかを見通し、進めていく力。
ただしそれは、マニュアルどおりにこなすことではありません。
- 優先順位が衝突した時、どちらを先に動かすか?
- 相手に確認を依頼するとき、どのタイミングがベストか?
- 先回りした動きをするには、どの情報を抑えておくべきか?
こうした判断を瞬時に求められる現場では、“知識としての段取り”では不十分です。
だからこそ大切なのは、経験を通じて、自分なりの「段取り観」を持論化していくこと。それが現場でブレない判断を可能にし、再現性ある行動へとつながっていきます。
現場のブリッジの観点から段取り力の強化を考える
段取り力を本質的に高めるには、「何を教えるか」以上に「どう考えさせるか」の設計が重要です。
なかでも効果的なのが、現場の特性や業務課題と接続したうえで、自分たちの段取りの要諦(虎の巻)を言語化するプロセスです。
例えば、以下のような問いをベースにグループワークを行います:
- 自分たちの業務で、段取りの成否を分ける瞬間はどこか?
- 日々の仕事で「もっと前にやっておけば」と思うのは、どんな場面か?
- 連携がスムーズにいったとき、そこにあった工夫は何だったか?
こうした振り返りと対話を通じて、現場の中で“使える段取り”を掘り起こし、それをチームとしての虎の巻にまとめていくのです。
これは研修側が提供する“正解”ではありません。参加者自身が、実践をベースに「自分たちにとって大事な段取りとは何か」を言語化するプロセスに価値があります。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
もう一つの視点:段取り力は“関係性マネジメント”である
段取り力は、自分の業務を整理するだけの力ではありません。
「他者とどう連携するか」「関係者をどう巻き込むか」といった関係性のマネジメント力でもあります。
たとえば──
- 「相手が今忙しそうだ」と判断して、依頼の出し方を変える
- 「あの人は金曜にまとめて処理する」と知っていて、木曜に提出する
- 「この件はあの人が気にする」と読んで、事前に根回ししておく
こうした“相手の動きを読む段取り”は、仕事の成果に直結します。
つまり段取り力とは、「自分の時間」だけでなく「相手の時間」まで見立て、先手を打てる人のスキルなのです。
持論の形成こそ、段取り力を高める
段取り力は、「知っていれば誰でもできる」スキルではありません。
日々の仕事の中で、どこで判断に迷い、どこで失敗し、どこに気づきを得たか──その経験を通じてこそ、段取りの本質が見えてきます。
そして、そこで得た気づきを自分なりの“持論”として言語化し、判断や行動の軸として持てるかどうかが、段取り力の真の差を生みます。
つまり段取り力とは、ただ“計画通りに進める力”ではなく、現場での経験をもとに、判断の勘所を自ら育てていく力なのです。
こうした持論を自分自身の中に持っている人こそが、どんな環境でも先手を打ち、周囲を巻き込みながら、成果を出していける存在になるのではないでしょうか。
 本間 俊平" width="104" height="104">
本間 俊平" width="104" height="104">