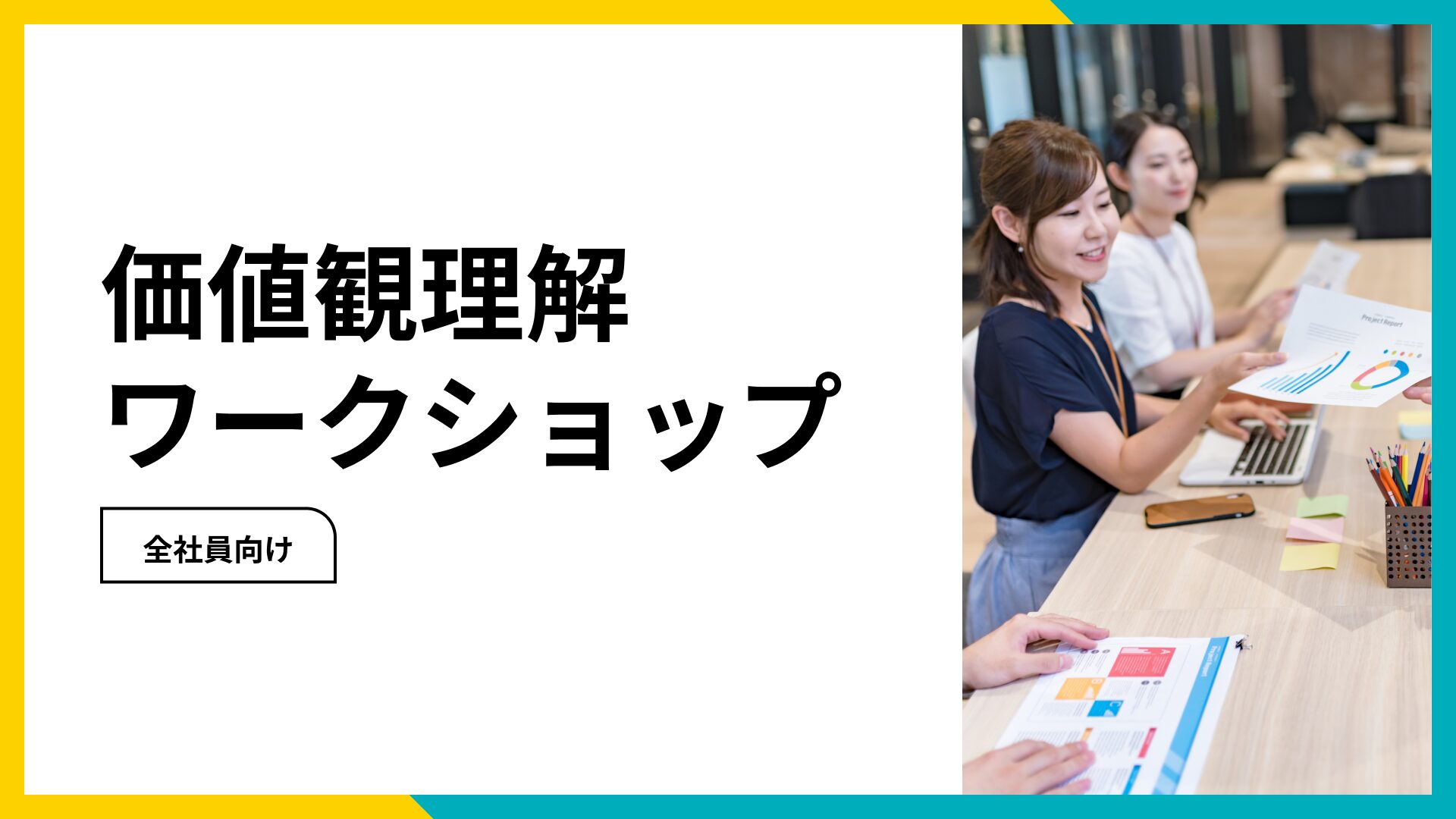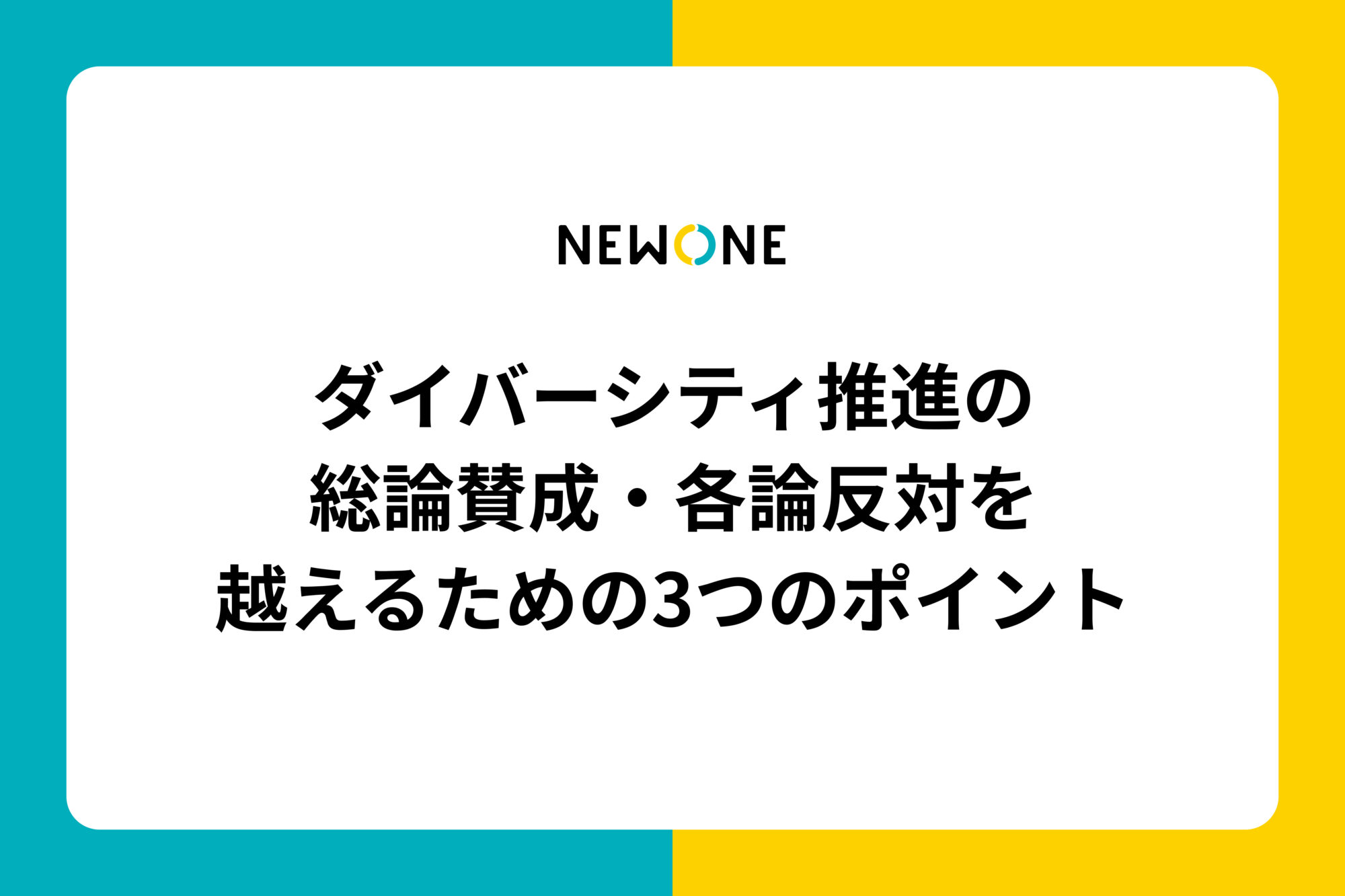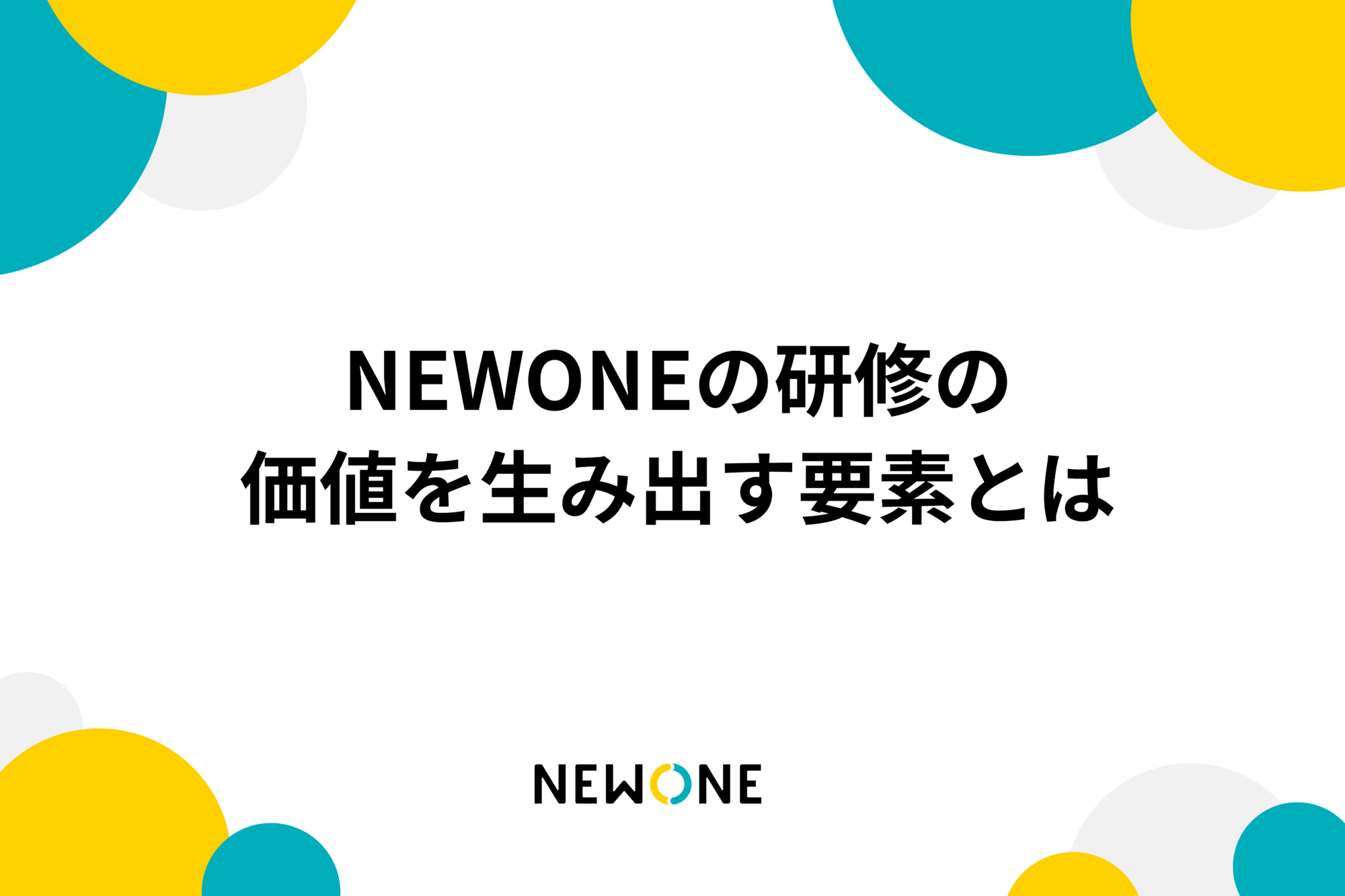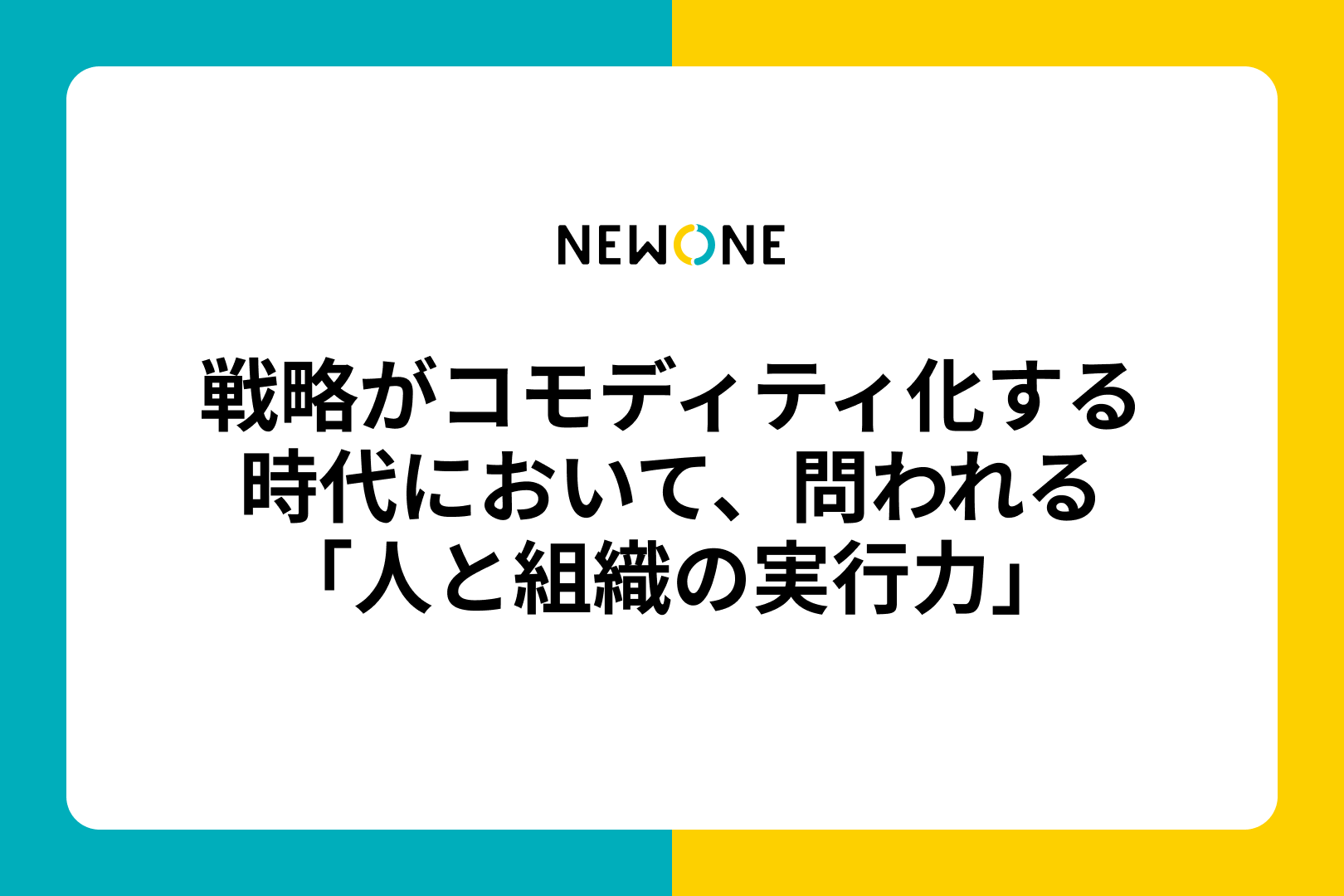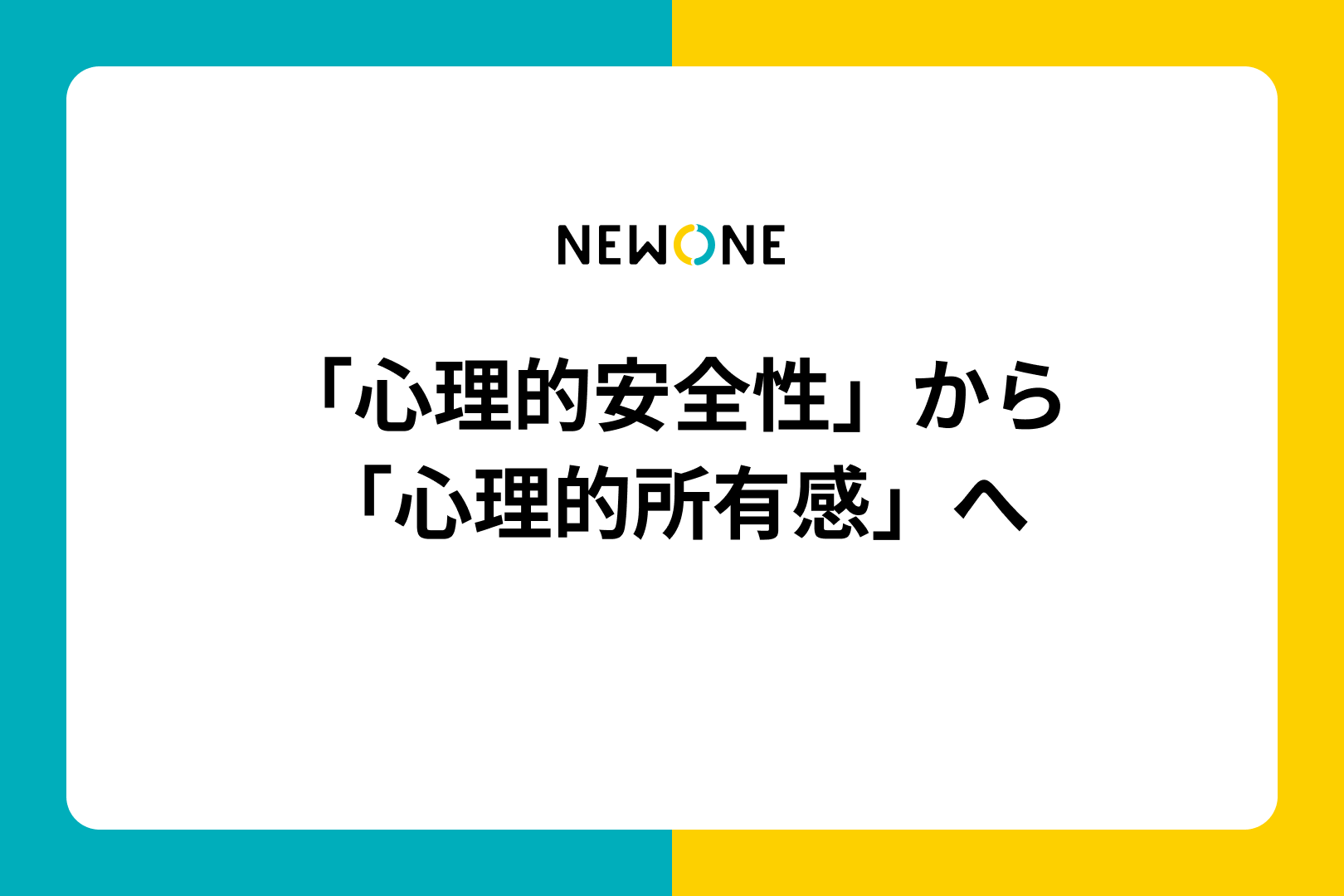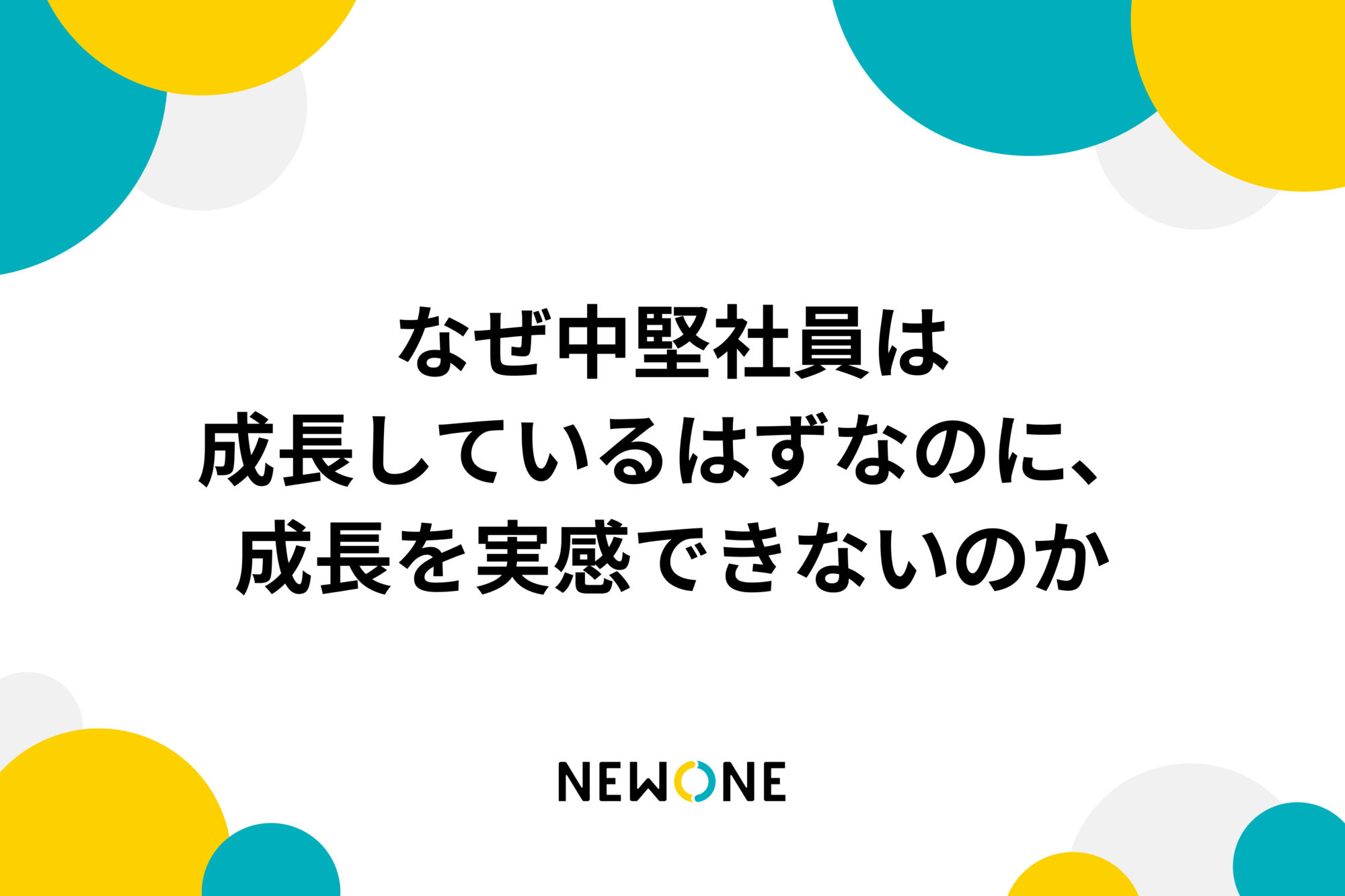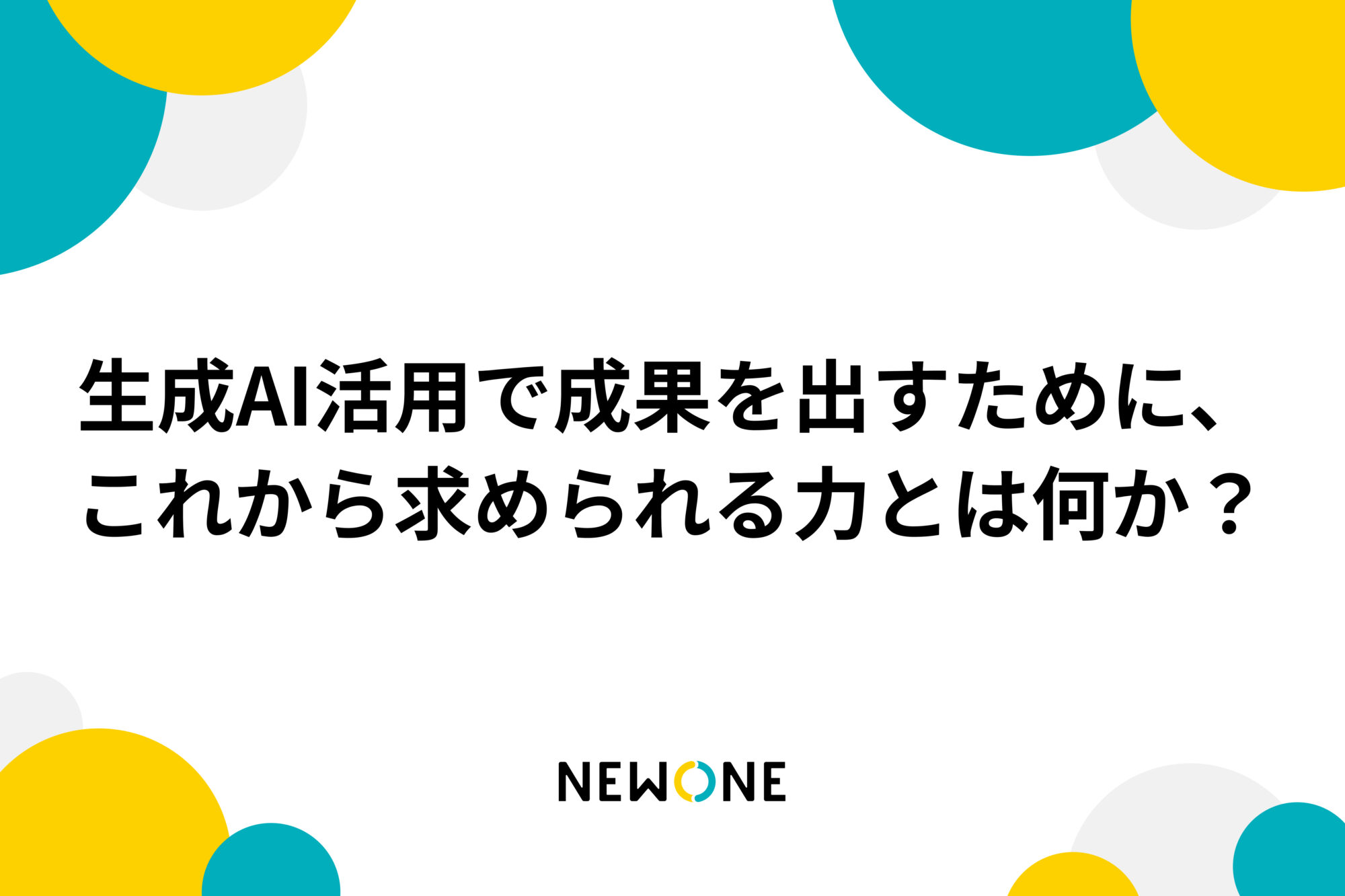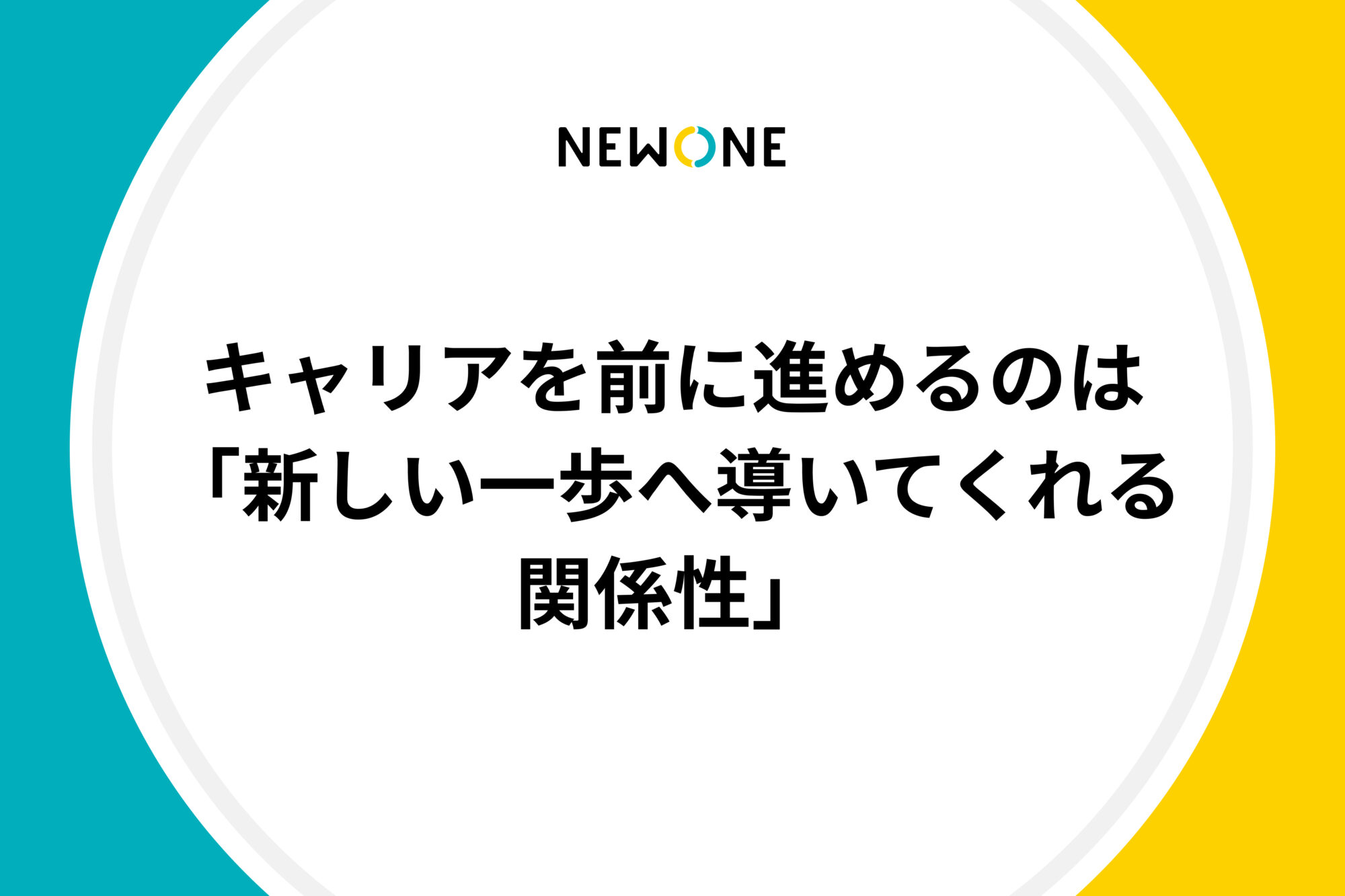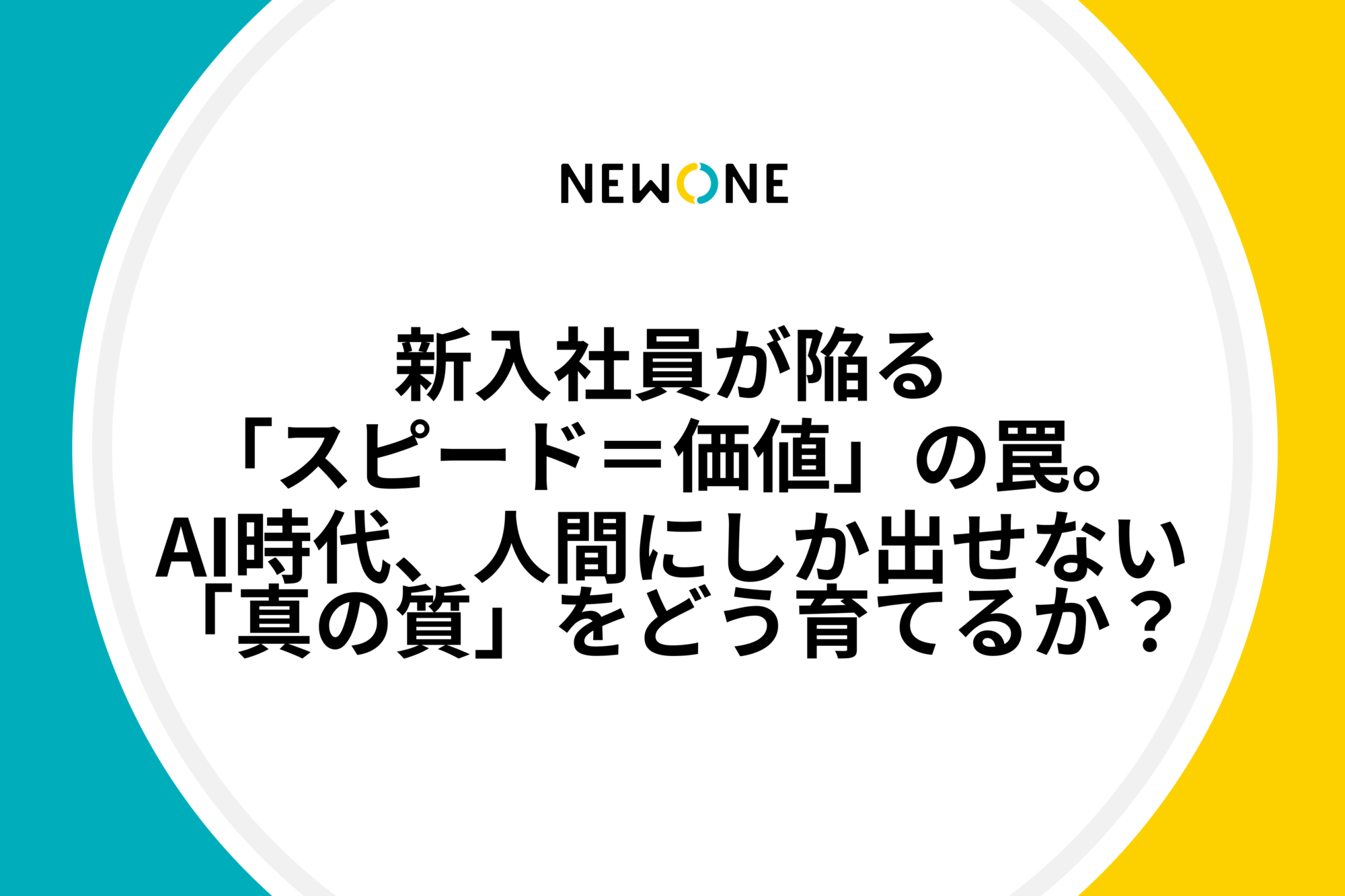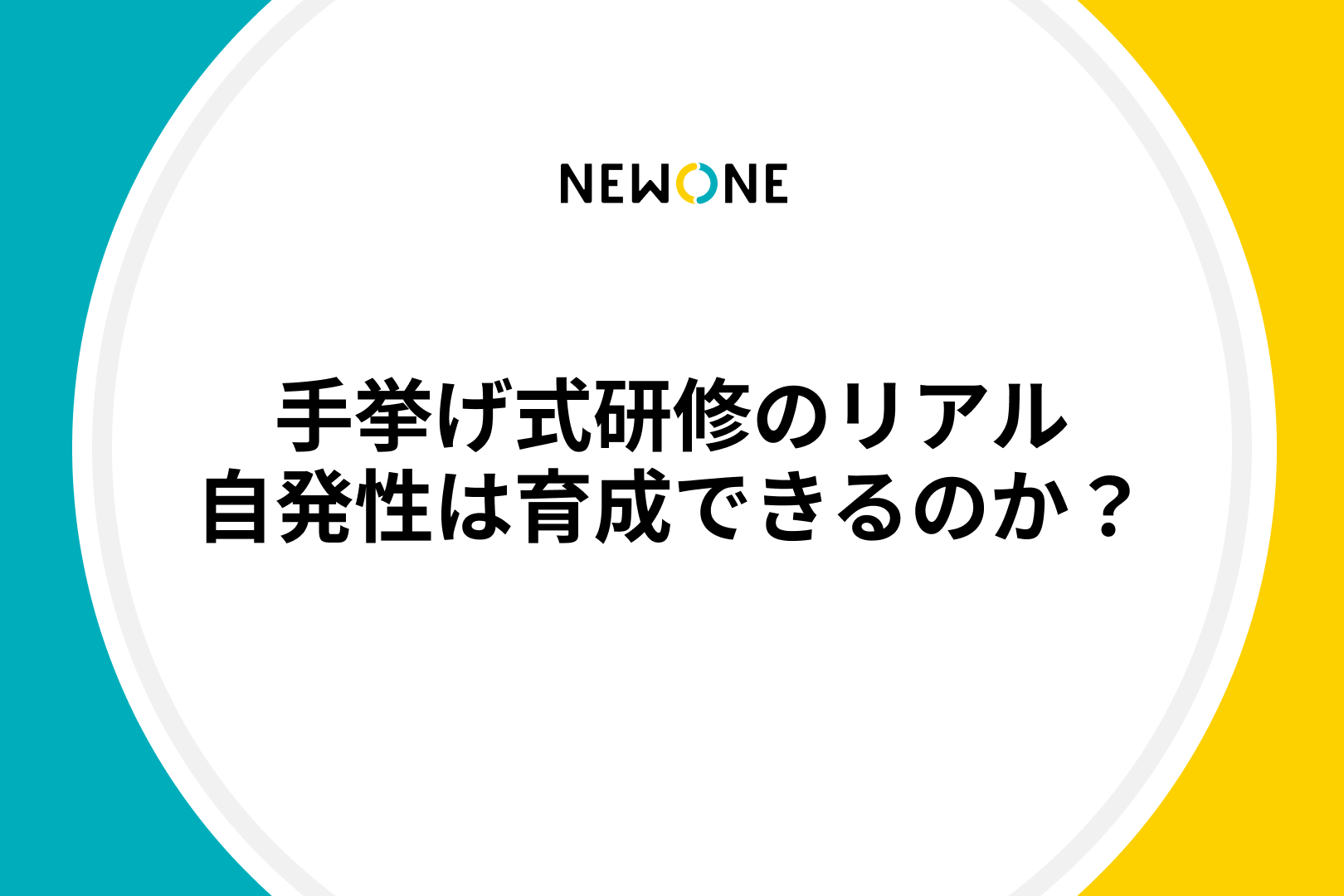
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
近年、多くの企業で採用され始めている「手挙げ式研修」。
これは、社員の自発的な参加によって研修の受講者を決めるスタイルで、義務的な研修とは異なるアプローチとして注目されています。社員の主体性を尊重する姿勢が評価される一方で、運用面や本質的な育成の観点からは、慎重に導入すべきという声もあります。
今回は、手挙げ式研修のメリットとデメリットを整理し、その活用のヒントを考えていきます。
メリット:自発性と学習意欲の高い層が参加する
1. 学びのモチベーションが高い
手挙げ式は「自分から学びたいと思った人」が参加するため、受講者のモチベーションが高く、研修内での発言や行動も活発になります。講師からの問いかけに対して前向きな姿勢を持ち、ワークやディスカッションの質も高まりやすいです。
2. 成果につながりやすい
学びたい意思を持って参加しているため、研修内容を実務に活かす力も強く、学習後の行動変容が促進されやすくなります。人材開発の観点でも、投資対効果が見えやすくなります。
3. “自分で選んだ”という納得感が残る
「手を挙げた自分」が参加するという体験自体が、自己効力感や成長意識につながります。管理職候補者研修などの文脈では、意図的にこの仕組みを用いることで、「次のキャリアへの自覚」を醸成するきっかけになります。
デメリット:受けた方がいい人が受けない
1. 本当に必要な人が参加しない
最大の課題は、「必要な人ほど手を挙げない」問題です。例えば、マネジメントに悩んでいる管理職や、行動変容が求められるミドル層ほど、自分の課題を自覚していなかったり、学ぶことに抵抗を持っていたりします。その結果、現場の本質的な課題が放置されるリスクがあります。
2. “学びの分断”を生み出すリスク
参加者が「前向きな人」に偏るため、非参加者との間で意識差や温度差が生まれることがあります。ときに「あの人たちだけ特別扱いされている」といったネガティブな見られ方をされ、組織内での分断や嫉妬が発生するケースもあります。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
マーケティング的思考で設計する──“参加のきっかけ”を用意する
ある企業では、手挙げ式研修に参加するメンバーが毎回固定化してしまうことに課題を感じていました。
「いつも手を挙げる“学び好きな人”しか集まらない」状況では、組織全体のスキル向上や行動変容にはつながりにくい。そこで同社は、“参加のハードルを下げる”仕掛けとして、1時間のショートウェビナーを導入しました。
このショートウェビナーは、興味喚起を目的とした入門編コンテンツで、「まず話を聞いてみよう」「学び始めてみよう」という気持ちを促す役割を担っています。そのうえで、本格的な研修(手挙げ式)への導線として設計することで、新しい層の参加者を引き込むことに成功しました。
このように、手挙げ式研修を成功させるには、「良いプログラムを作ること」だけでなく、「参加の動機をどう設計するか」というマーケティング的視点が不可欠です。
まとめ:手挙げ式研修を成功させる鍵は「目的の明確化」と「仕掛け」
手挙げ式研修には、自律的な学びを促すという大きな可能性があります。
しかし、それを真に機能させるためには、「誰にどんな行動変容を期待するのか」という目的設定が不可欠です。そのうえで、必要な層に届くような「仕掛け」や「声がけ」が求められます。
たとえば、
- 上司からの推薦という形で背中を押す
- 研修内容に“本人ごとの目的”を紐づける
- 非参加者にも情報や学びの機会を還元する
といった仕掛けを加えることで、制度としての効果が高まります。
単なる「参加自由な仕組み」にとどまらず、企業の育成意図を丁寧にデザインした「戦略的手挙げ制」へと進化させることが、これからの人材開発には求められているように感じます。
 山口 陽輝" width="104" height="104">
山口 陽輝" width="104" height="104">