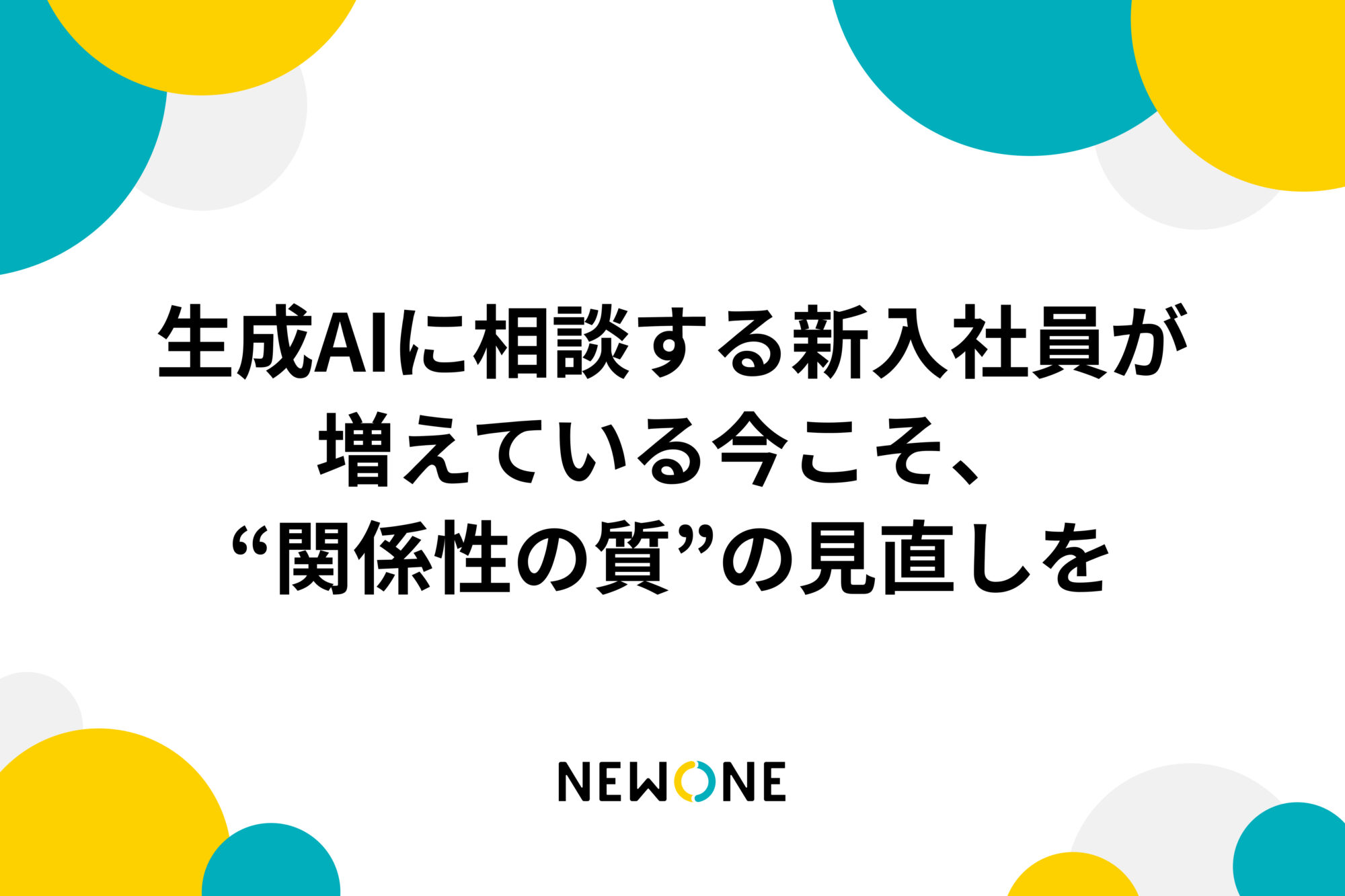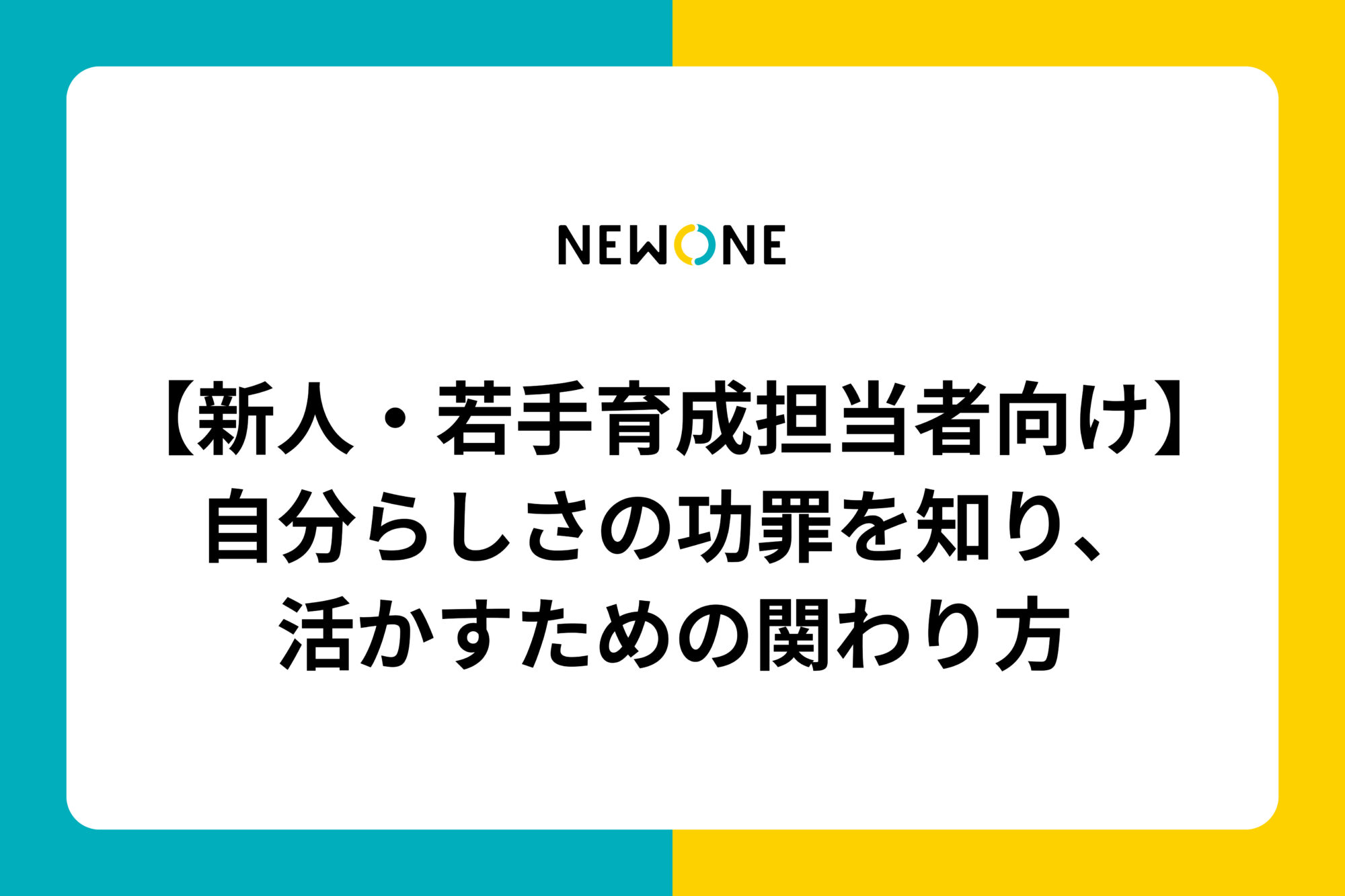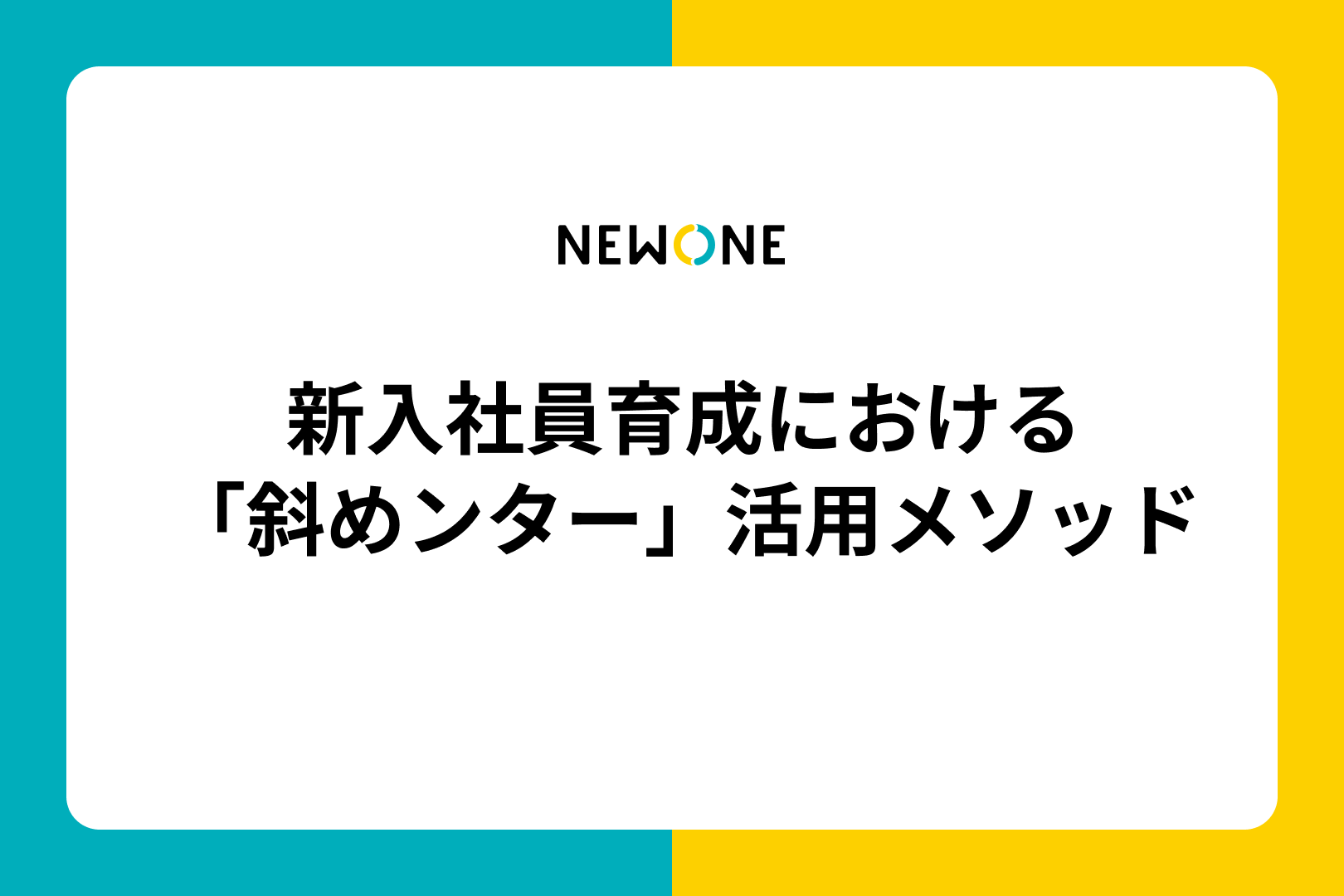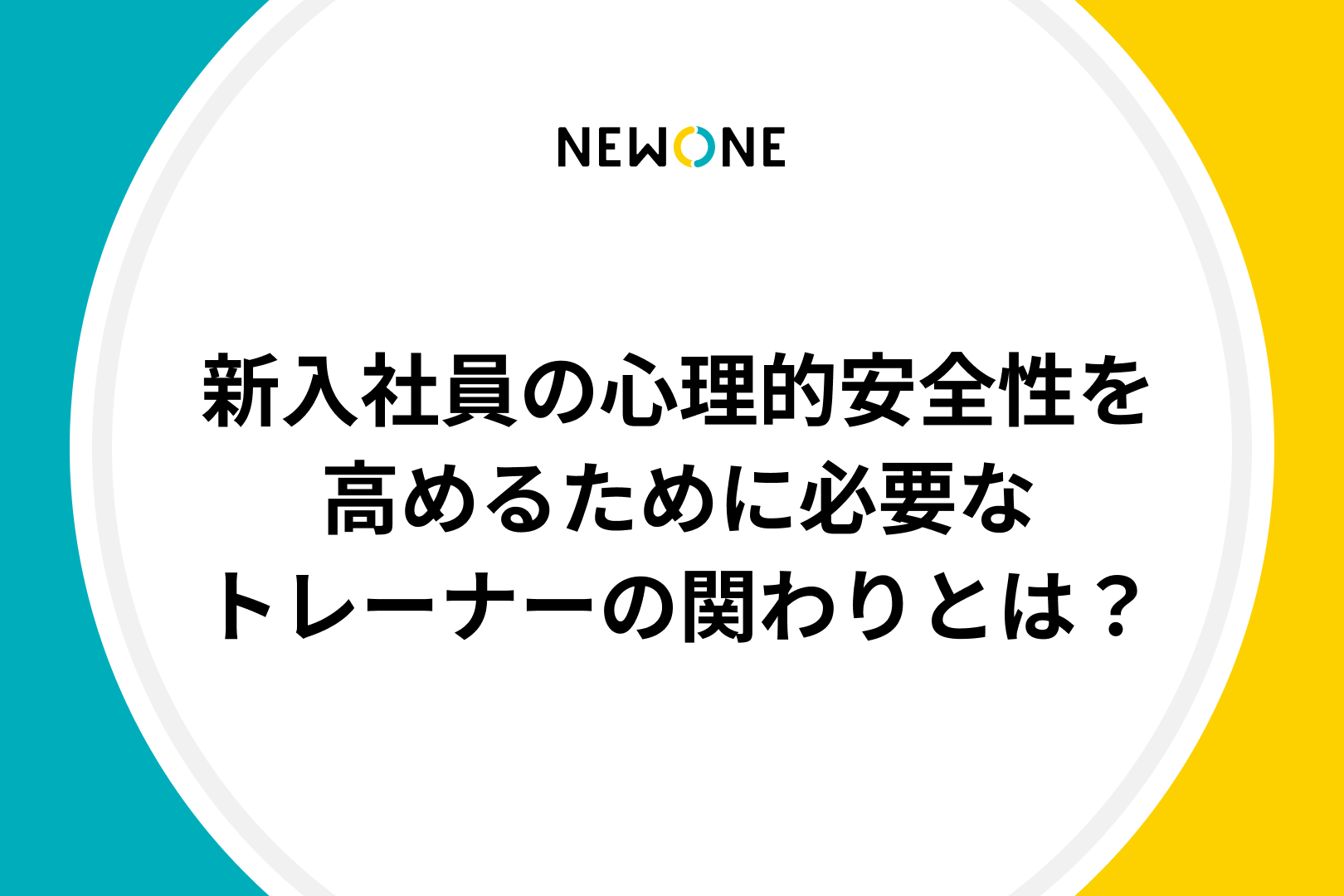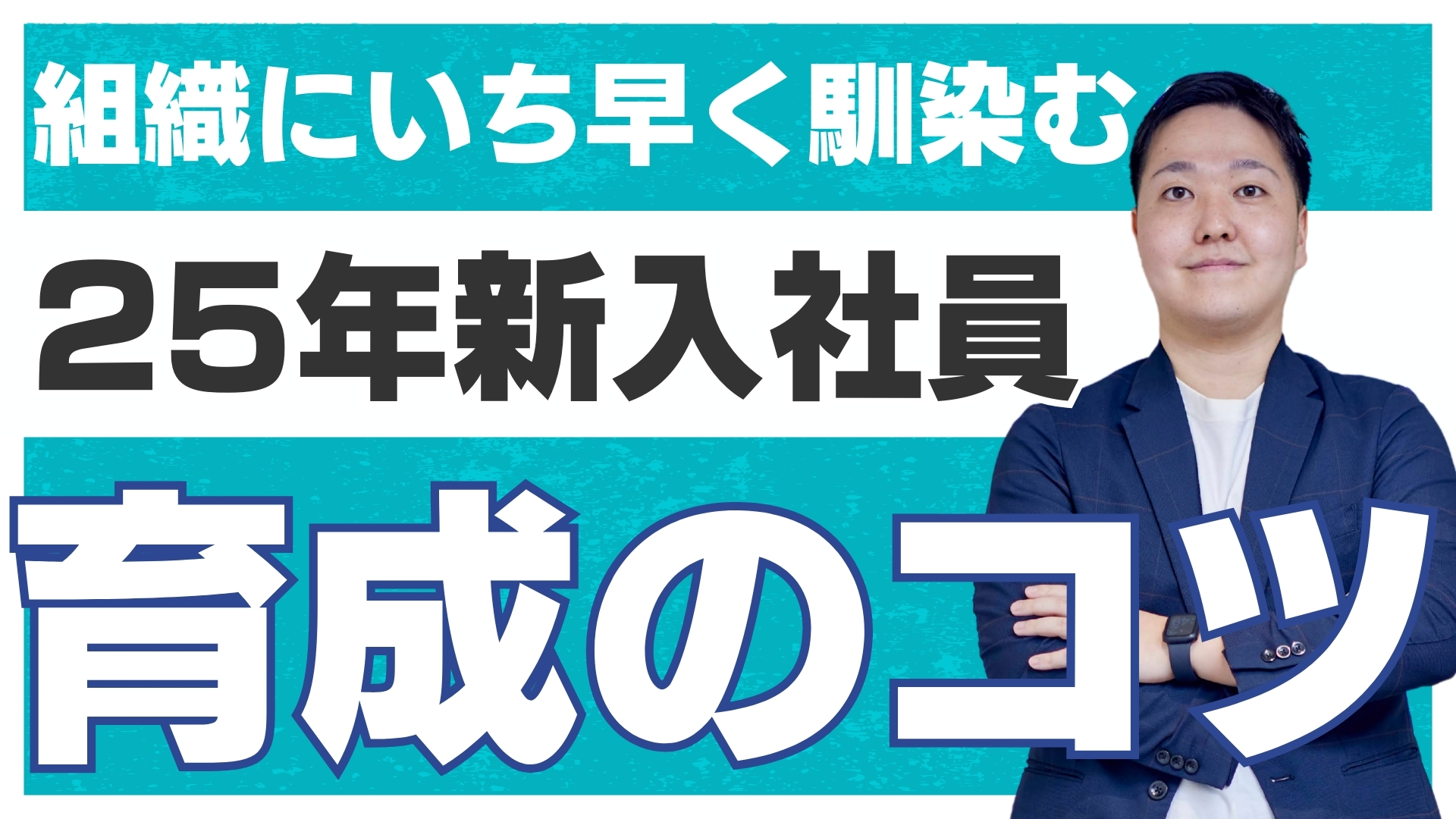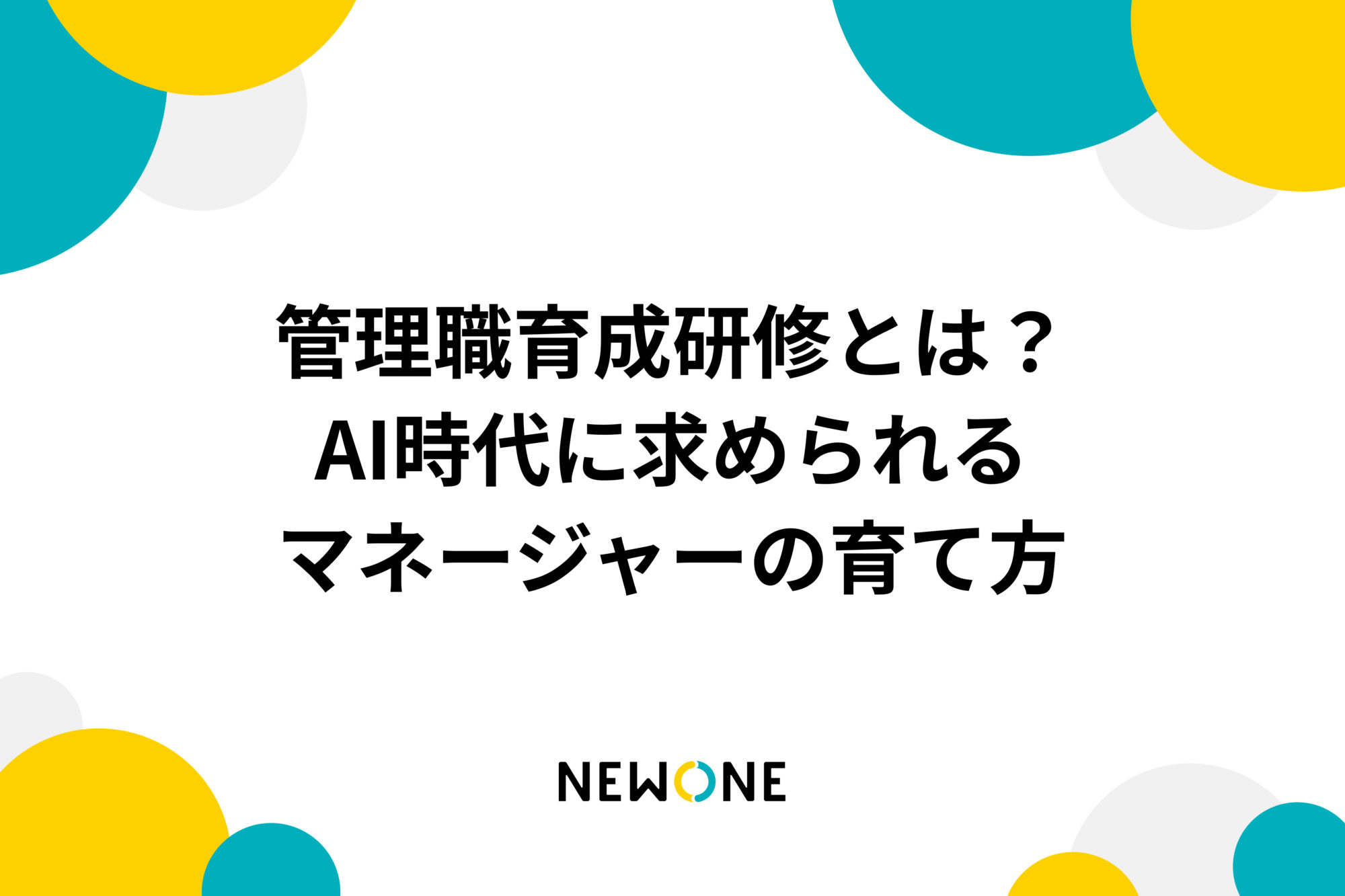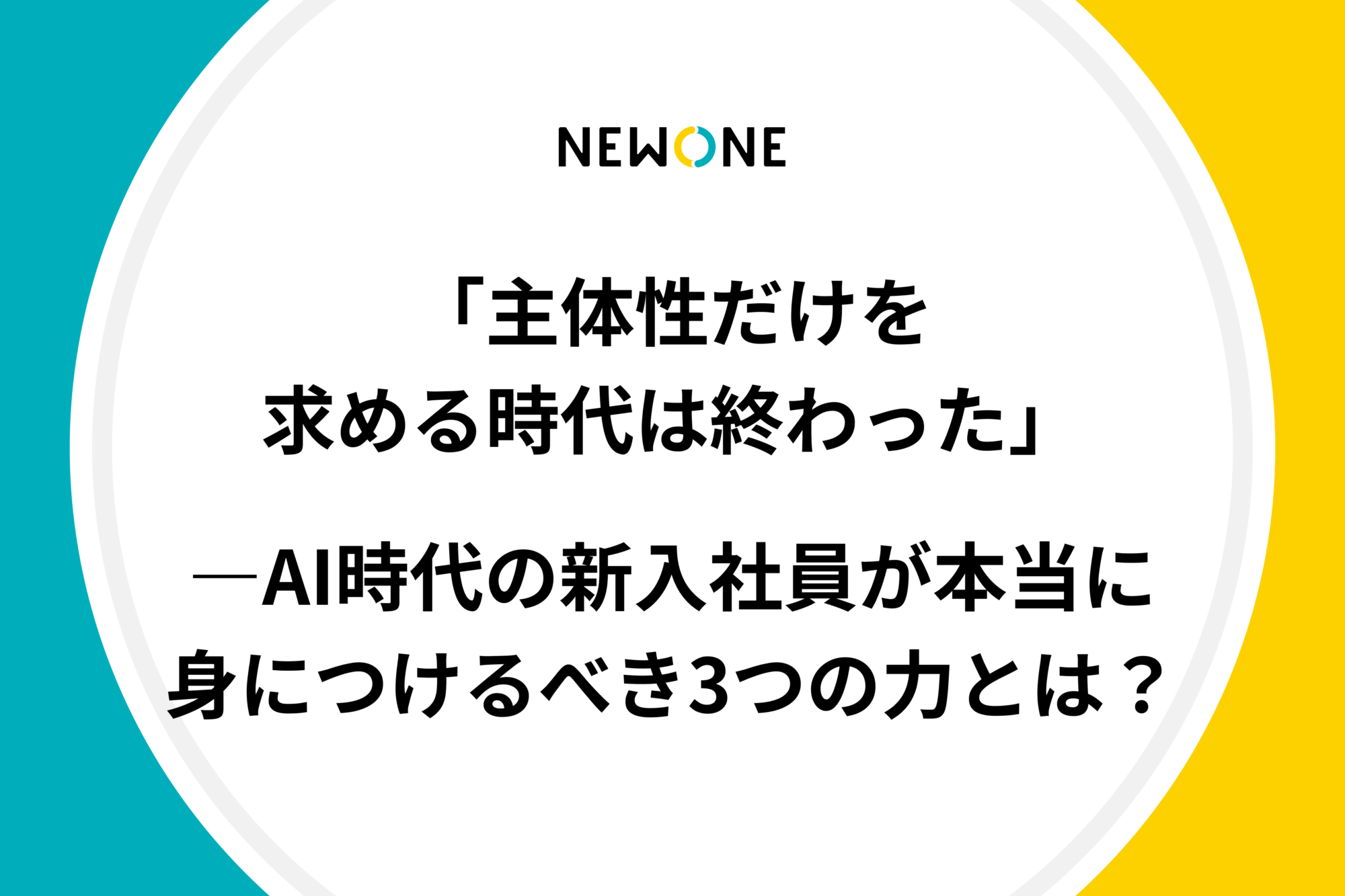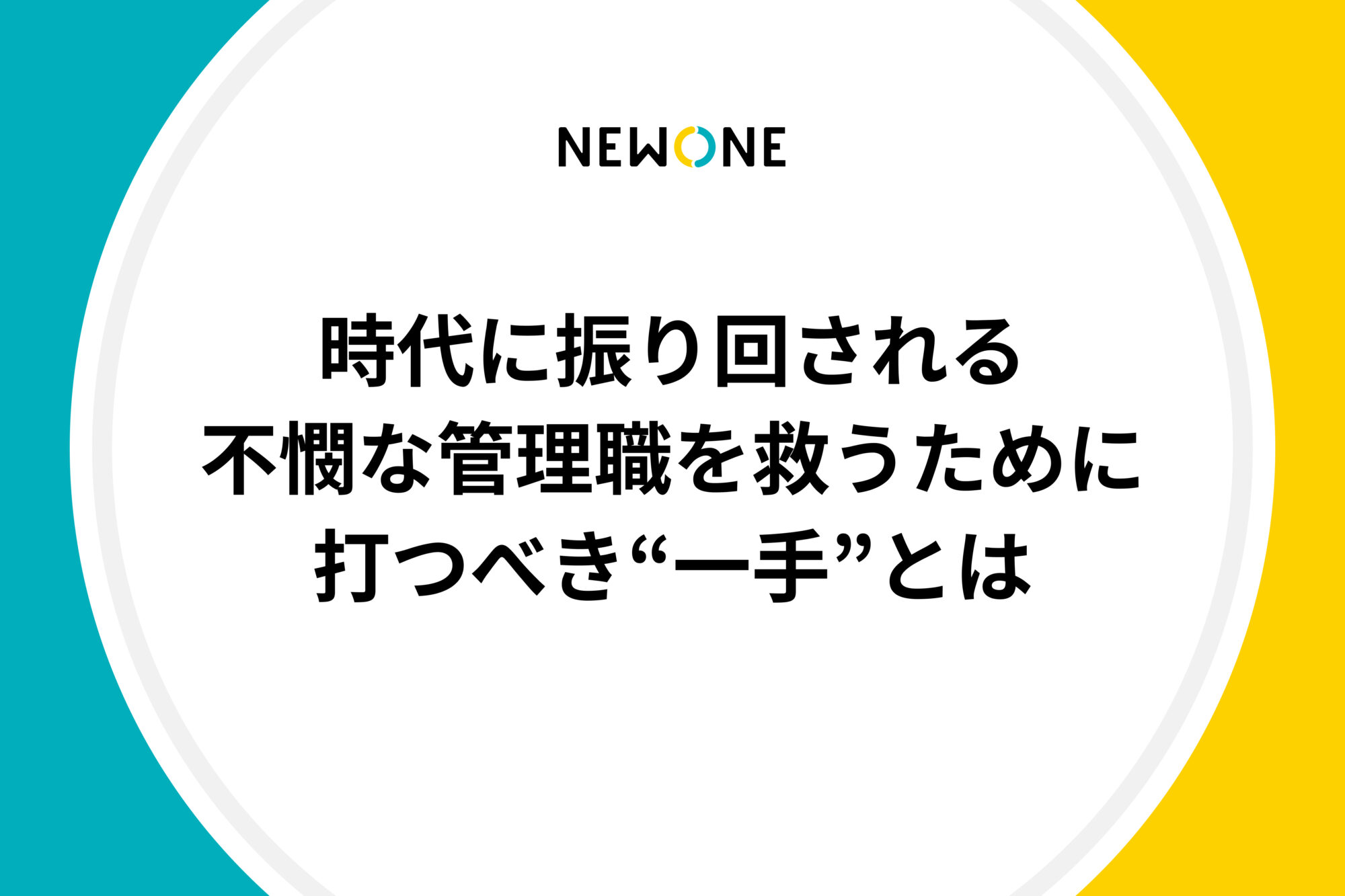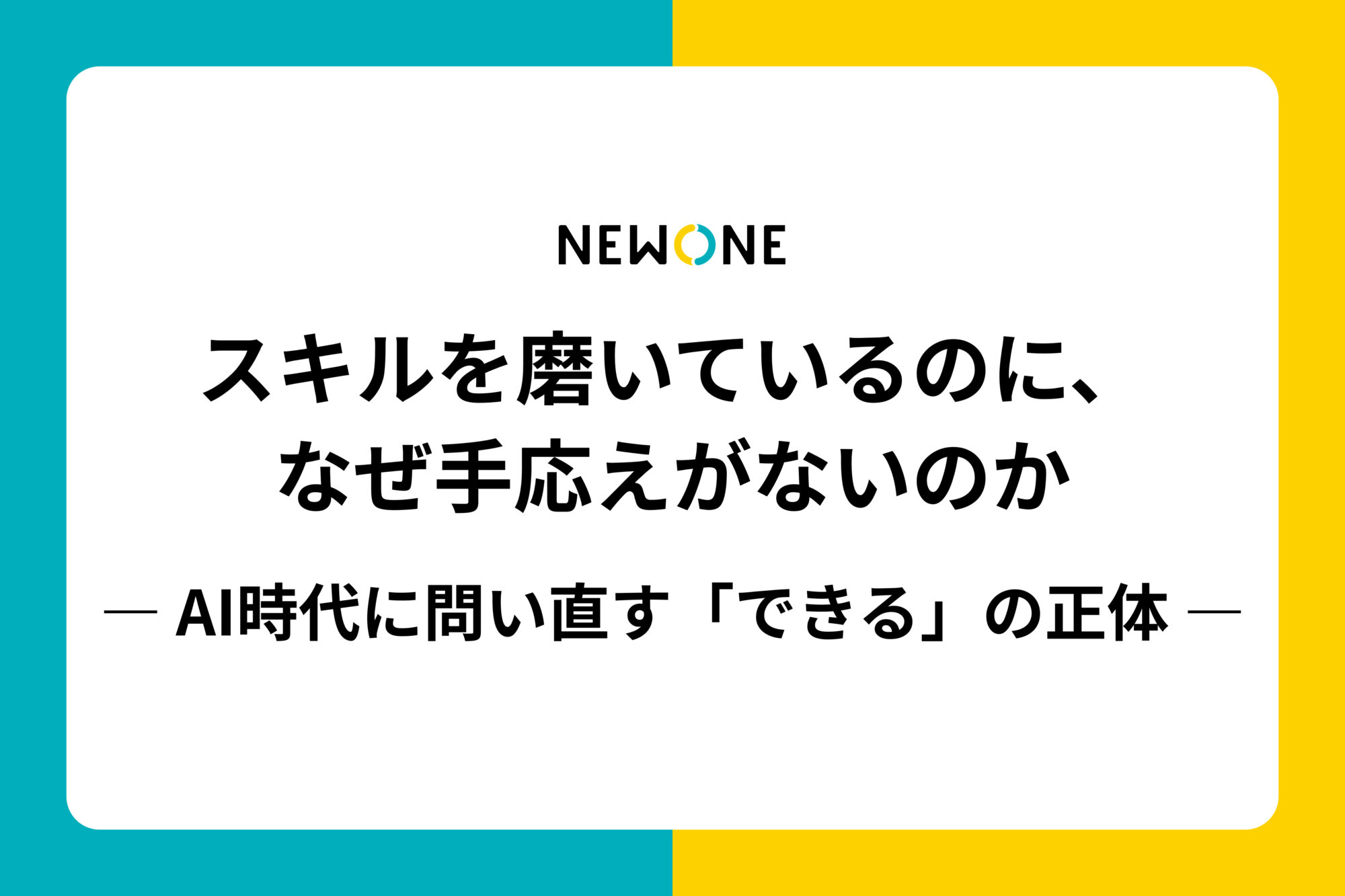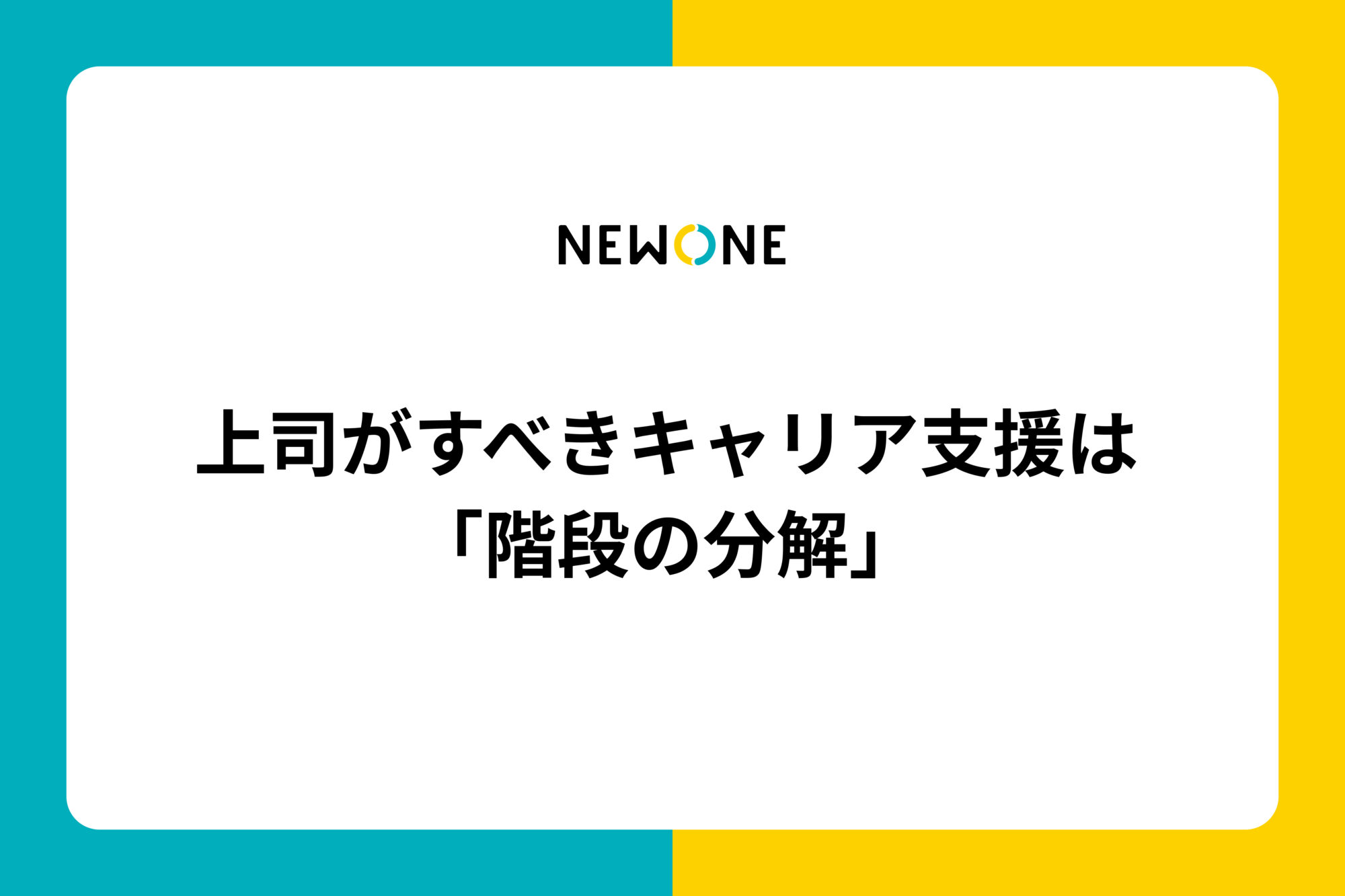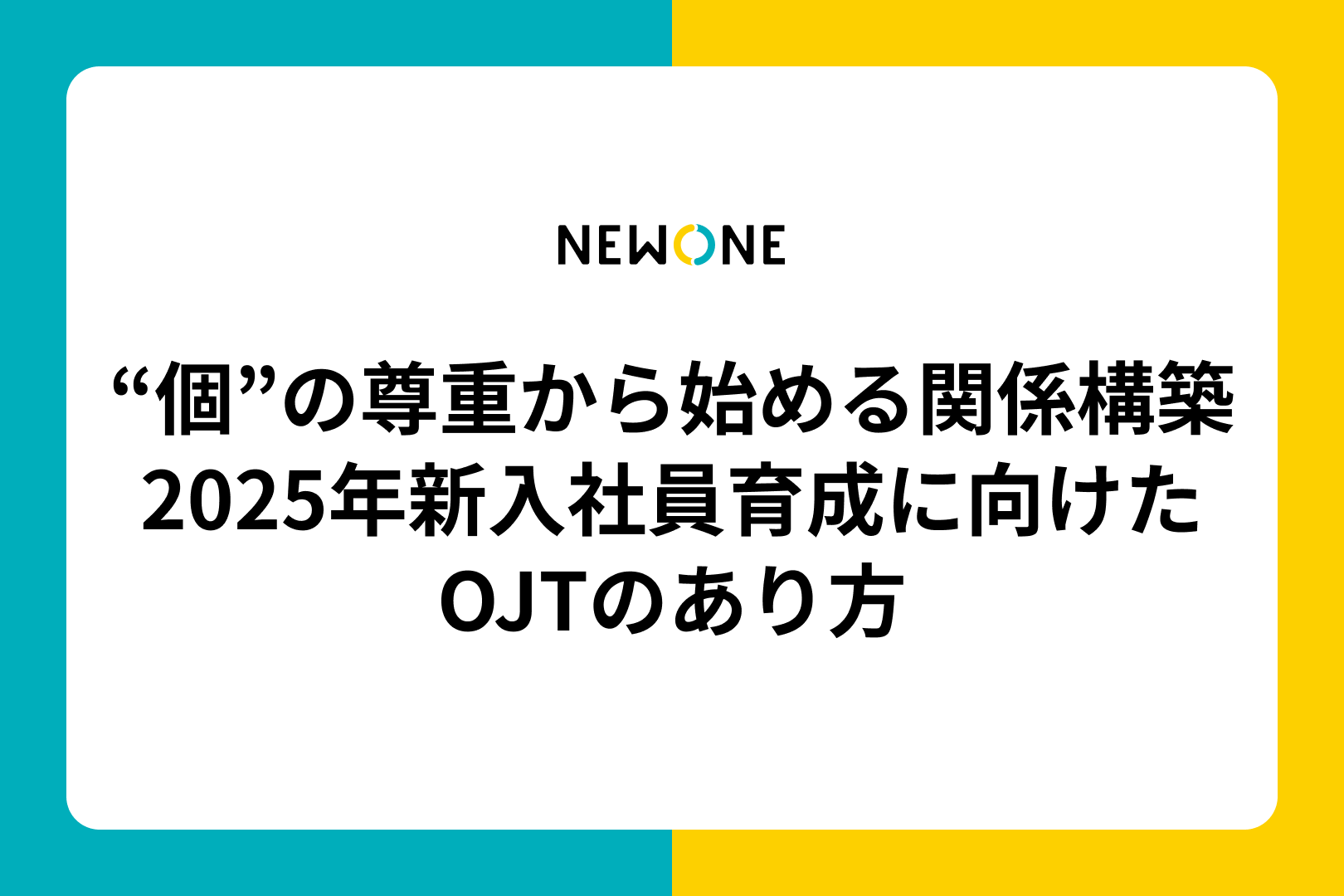
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
4月。多くの企業で新入社員が新たなスタートを切りました。
私自身もこの4月で、10社、約200名を超える新入社員の皆さんと向き合う機会をいただきました。企業ごとに様々な新入社員とお会いすることができ、私自身も刺激を受ける日々でした。
5月以降育成に関わる皆さんは、今後のフォロー施策を練られていることと思います。そこで、私が2025年の新入社員の皆さんから感じた特徴をお伝えしようと思います。「深い関係性を築くことに対する慎重さ」、あるいは「そこに対する壁のようなもの」を多くの場面で感じました。
もちろん、企業ごとに業界・職種・採用基準も異なり、一括りに論じることはできません。それぞれにカラーや傾向がある前提ではありますが、200名という規模の中で共通して見えた傾向は、現場で新入社員と接するOJT担当者や育成を担う人事の皆様にとって一つのヒントとなるのではないでしょうか。
「みんな違って、みんないい」の時代背景
2025年の新入社員たちは、多様性を尊重する環境の中で育ってきました。学校教育やSNSの文化の中で、「自分らしくいること」が推奨され、「違い」は否定されるものではなく、むしろ称賛されるべきものとされています。彼らの多くは、「自分はこういう人間だ」「こういう価値観を持っている」と自分の目標やビジョンを語ることに、ある種の誇りや自然さを持っており、それを周囲も「素晴らしいね」と受け止める風土があります。
このような育ち方は、確かに自己肯定感や自己理解の促進という点で非常に有意義です。一方で、「チームとしてこうありたい」「皆でこのゴールを目指そう」という共通目的のもとに“切磋琢磨する関係性”には、まだあまり慣れていない印象を受けました。
チーム形成における「フィードバックの壁」
ここに、現場でのOJTが直面する課題があります。たとえば、ある新入社員がOJT担当者から「こういう点をもう少し工夫できると良いね」とフィードバックを受けたとします。伝える側としては、成長を願っての前向きな声かけであっても、受け手の心には「否定された」という感覚が先行してしまうことがあります。
これは、本人が「個として認められているかどうか」を非常に敏感に感じ取るからです。「あなたの考えやスタイルは理解したうえでの提案です」という前提が伝わっていないと、たとえ正論であっても届かないのです。また一方で、フィードバックをしなければ、この環境は自分を成長させてくれない、ととらえる可能性もあり、バランスが難しくなっています。
したがって、OJTの現場ではまず“その人をよく知る”という姿勢が、より重要になってくるのではないかと考えます。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
「正しいこと」を伝える前に、「見てくれている」という土壌をつくる
育成の場面でありがちなのが、「正しいことを早く伝えたい」「一日も早く現場で活躍できるように」との思いから、行動や姿勢へのフィードバックを急ぎすぎるケースです。しかし、それが“その人の価値観や目標に寄り添った言葉”でなければ、いくら熱意をもって伝えても心には届きません。
一方で、「〇〇さんのこういう考え方、素敵だね」「目指している方向性、理解できたよ」と一度“個”を尊重した上でのフィードバックは、格段に受け入れられやすくなります。
このプロセスには当然、時間も対話の工数もかかります。しかし、初期のOJTで信頼関係が築かれるかどうかは、今後の定着や活躍に直結します。だからこそ、「相手のビジョンを理解すること」「その人なりの価値観を知ること」にこそ、育成の第一歩を置くべきです。
「価値観を引き出すOJT」のすすめ
このような背景を踏まえると、今の新入社員育成に求められるOJTは、「評価」や「矯正」の場ではなく、「価値観を見出し、思いを引き出す」場であるべきだと感じます。
具体的には、以下のような問いや関わりをOJTの場に取り入れていくことをおすすめします。
・入社時に描いていた理想像やビジョン、ありたい姿は何か?
・そのビジョンは、現場でどのように体現できそうか?
・今取り組んでいる業務に、自分の強みや価値観はどう活かせそうか?
・逆に、「これは苦手だな」と感じる瞬間はどんなときか?
これらの対話は、個人に向き合いながらも、組織で働く一員としての視点を醸成することにもつながります。
OJTは、関係性をつくる“文化の起点”
2025年の新入社員と向き合う中で、私たちはこれまでの育成のあり方を見直す必要があると強く感じています。ただスキルを教えるのではなく、個の背景や目標に寄り添い、その上で組織の中でどう活躍していくのかを共に考えていく。
OJTは、単なる指導の場ではなく、“関係性を築く第一歩”であり、“文化づくりの起点”でもあります。人事や現場が一体となって、「その人らしさ」と「組織としての成長」の両方を支えていけるような関わりを始められることをお勧めいたします。
 渡部 亮太" width="104" height="104">
渡部 亮太" width="104" height="104">