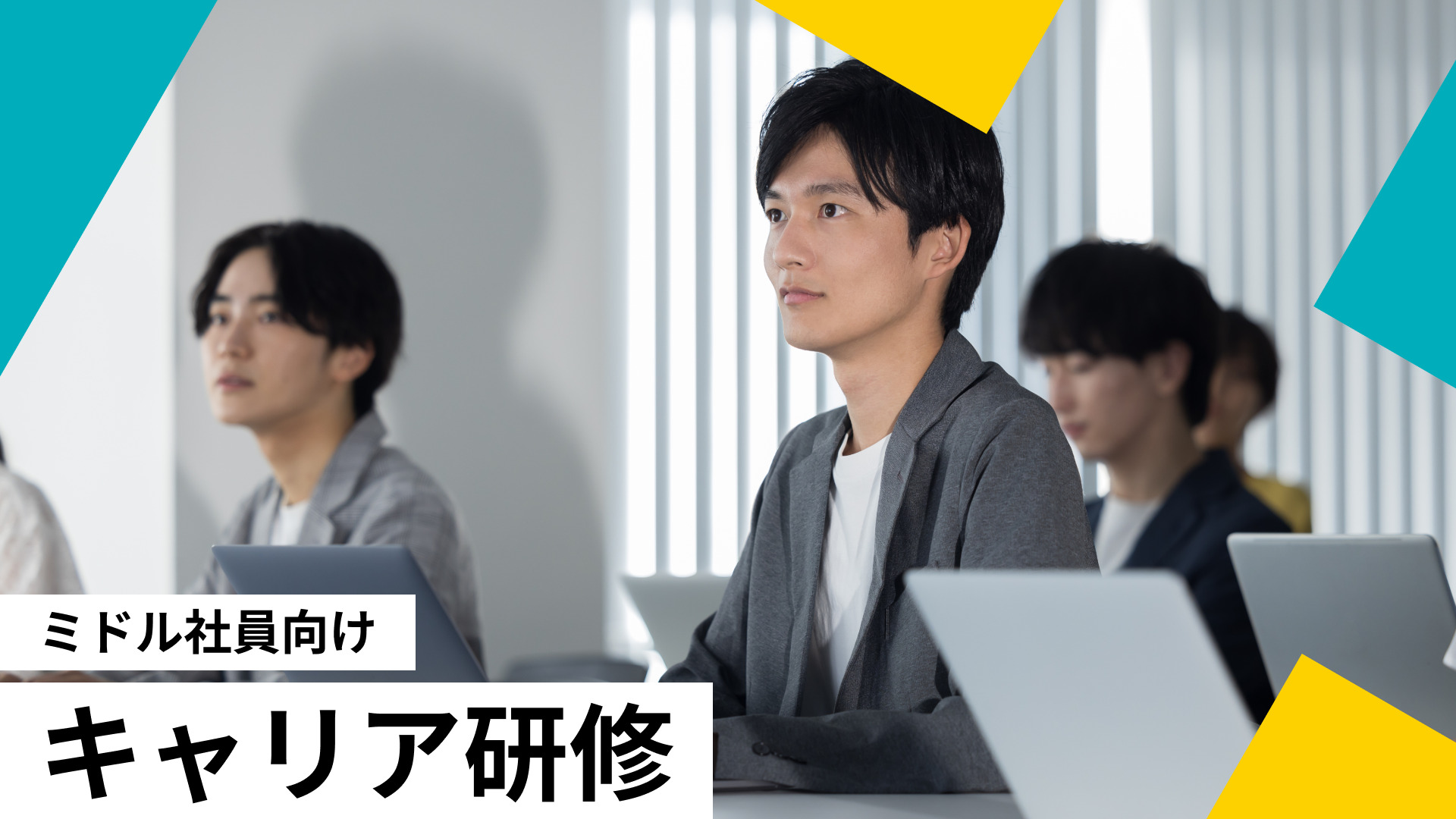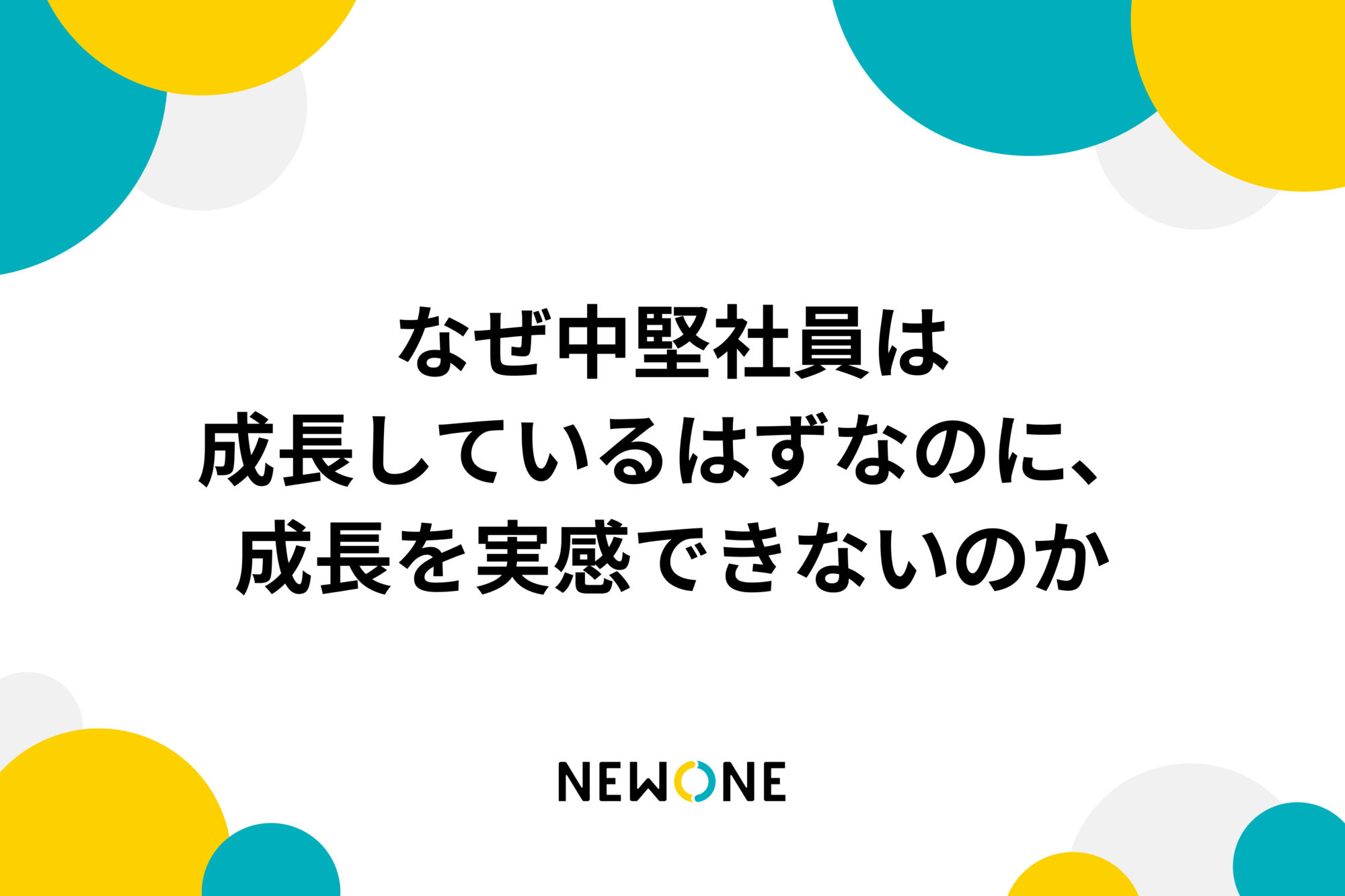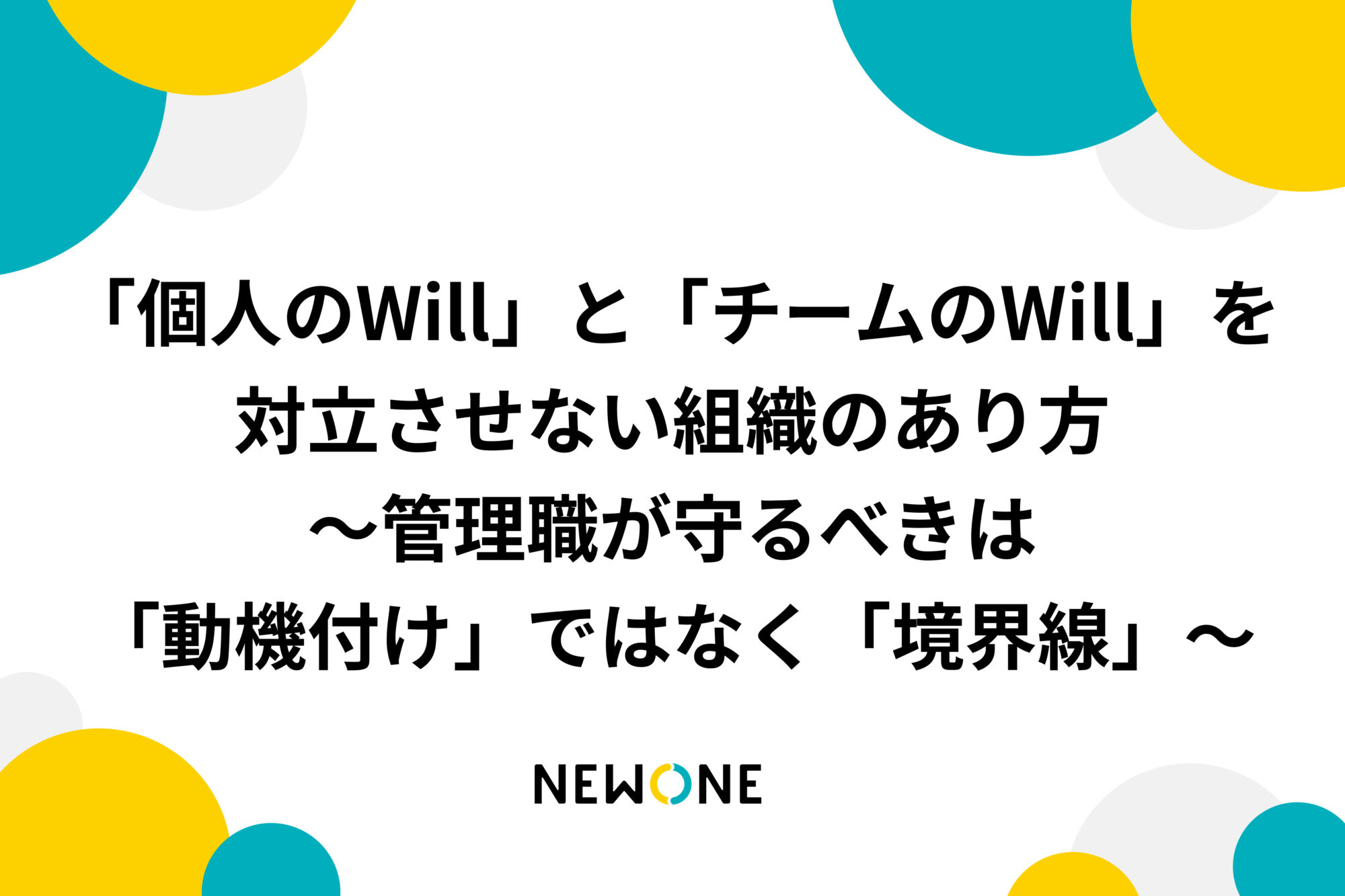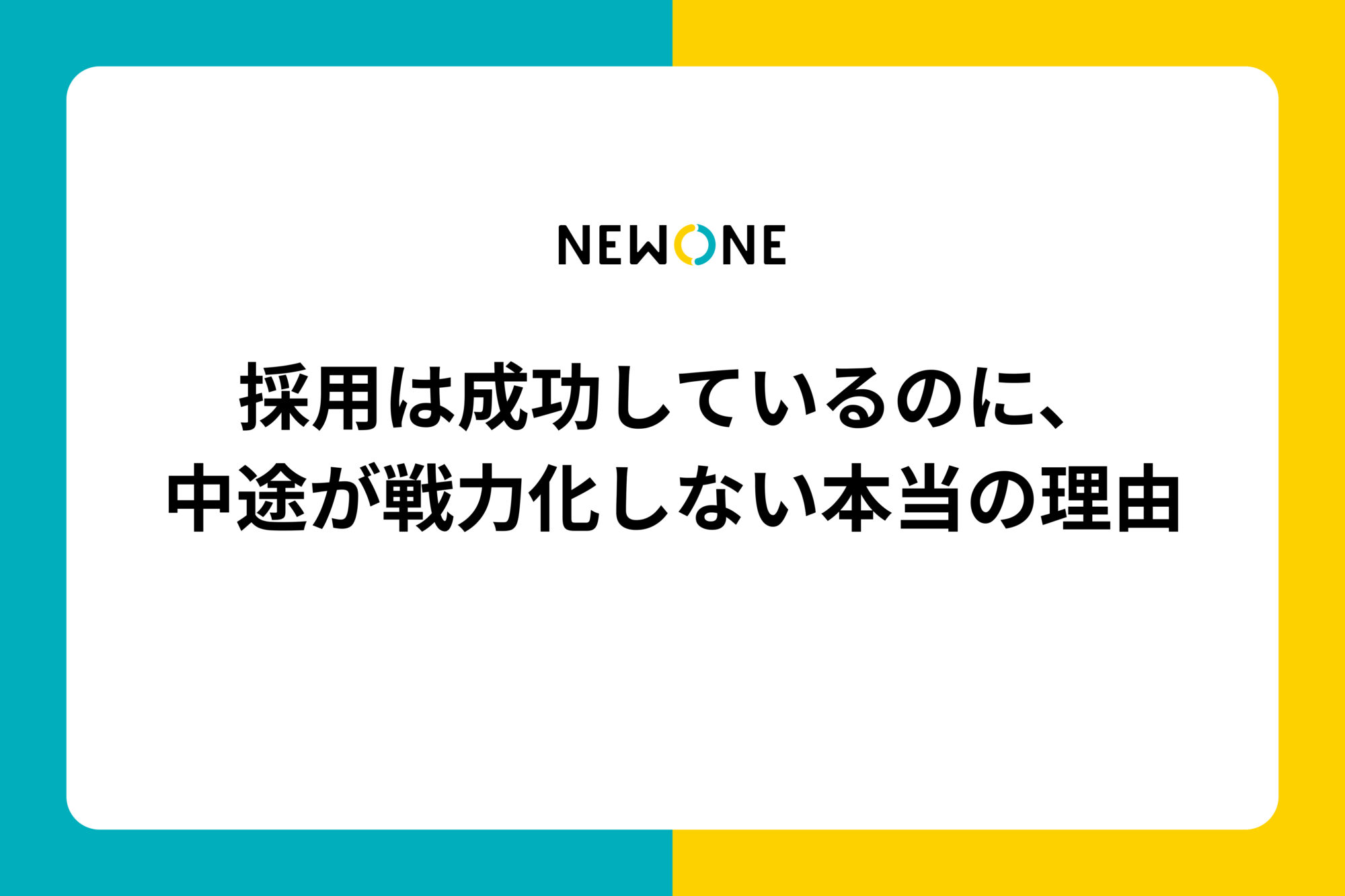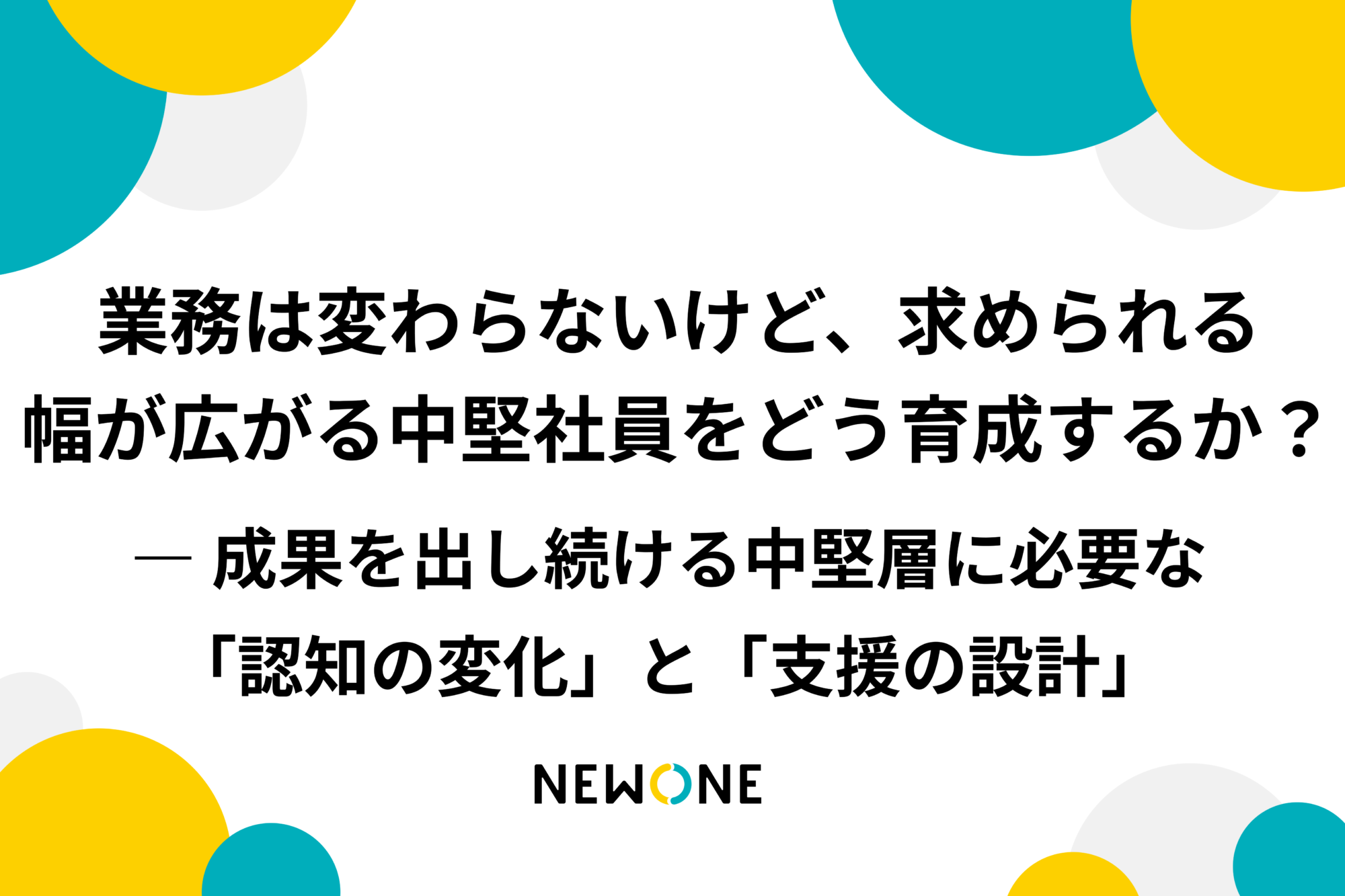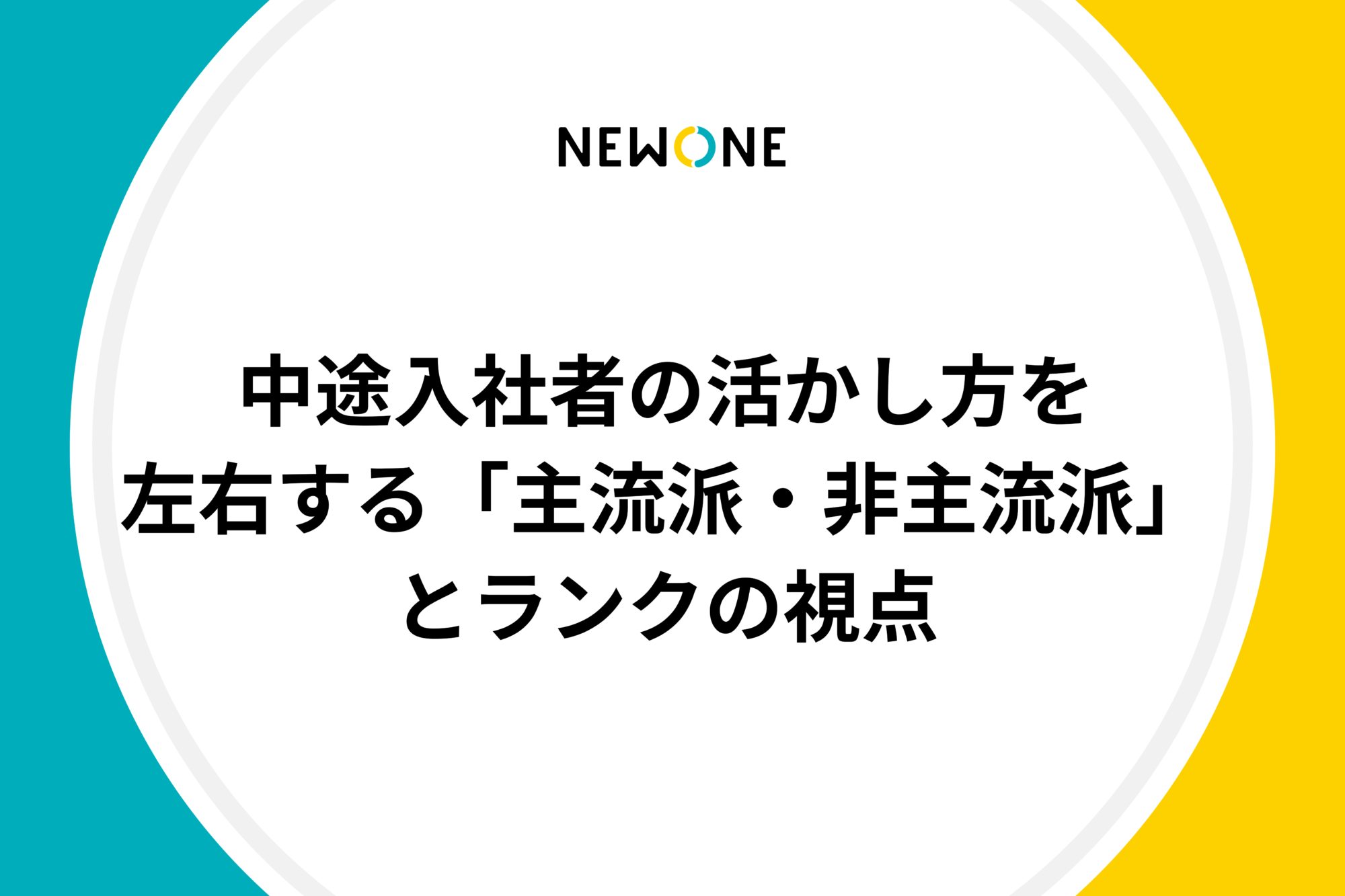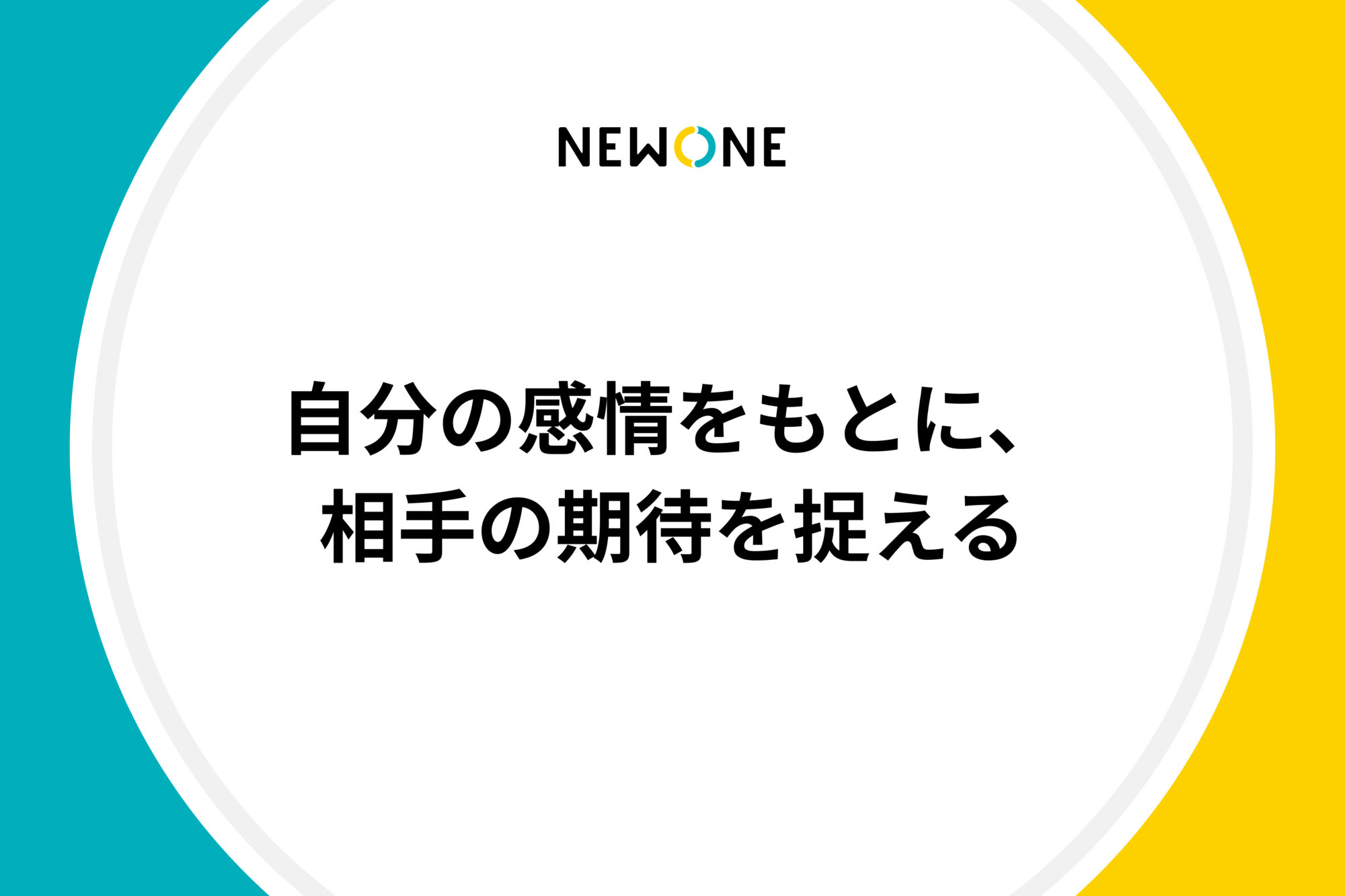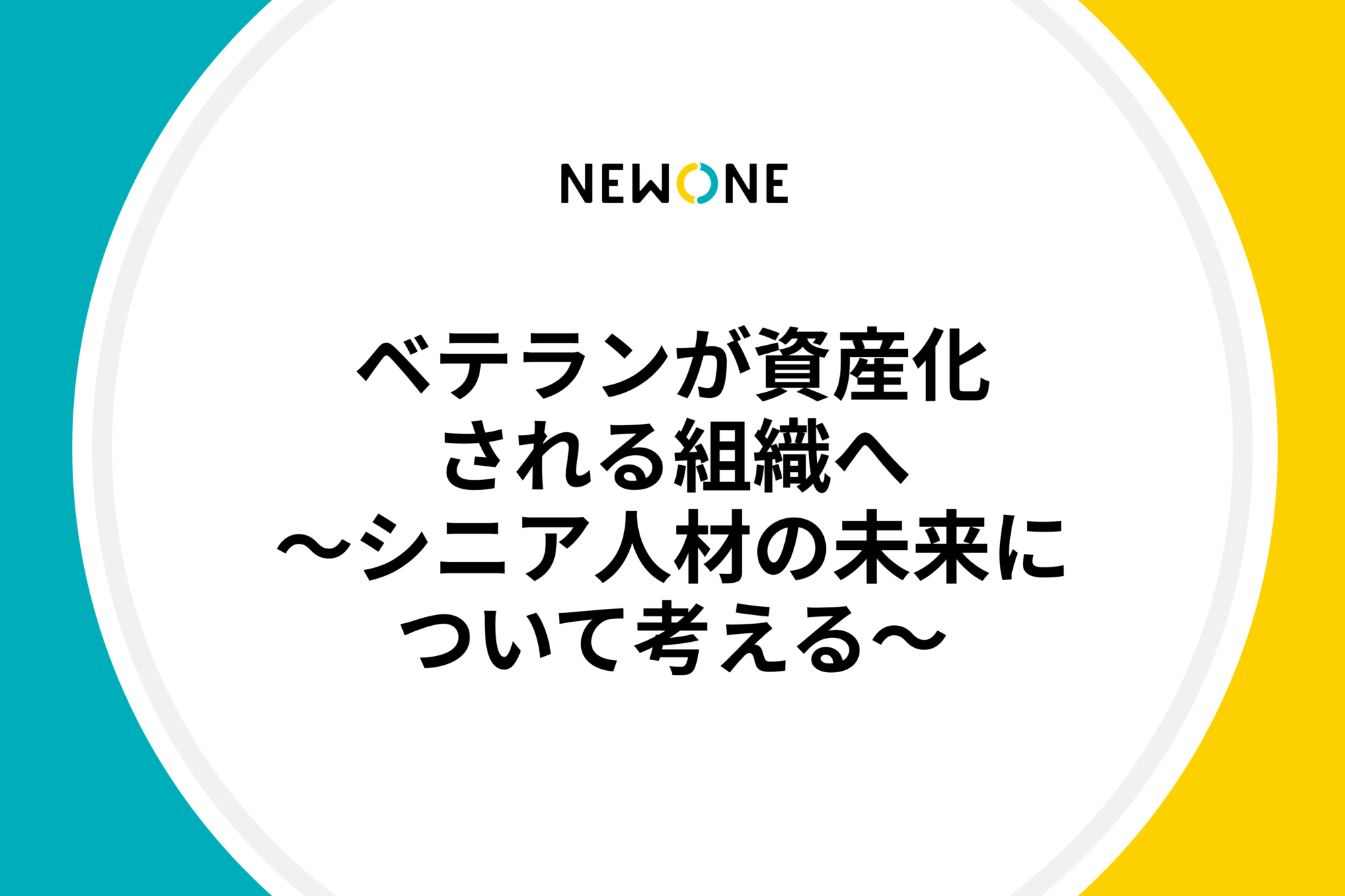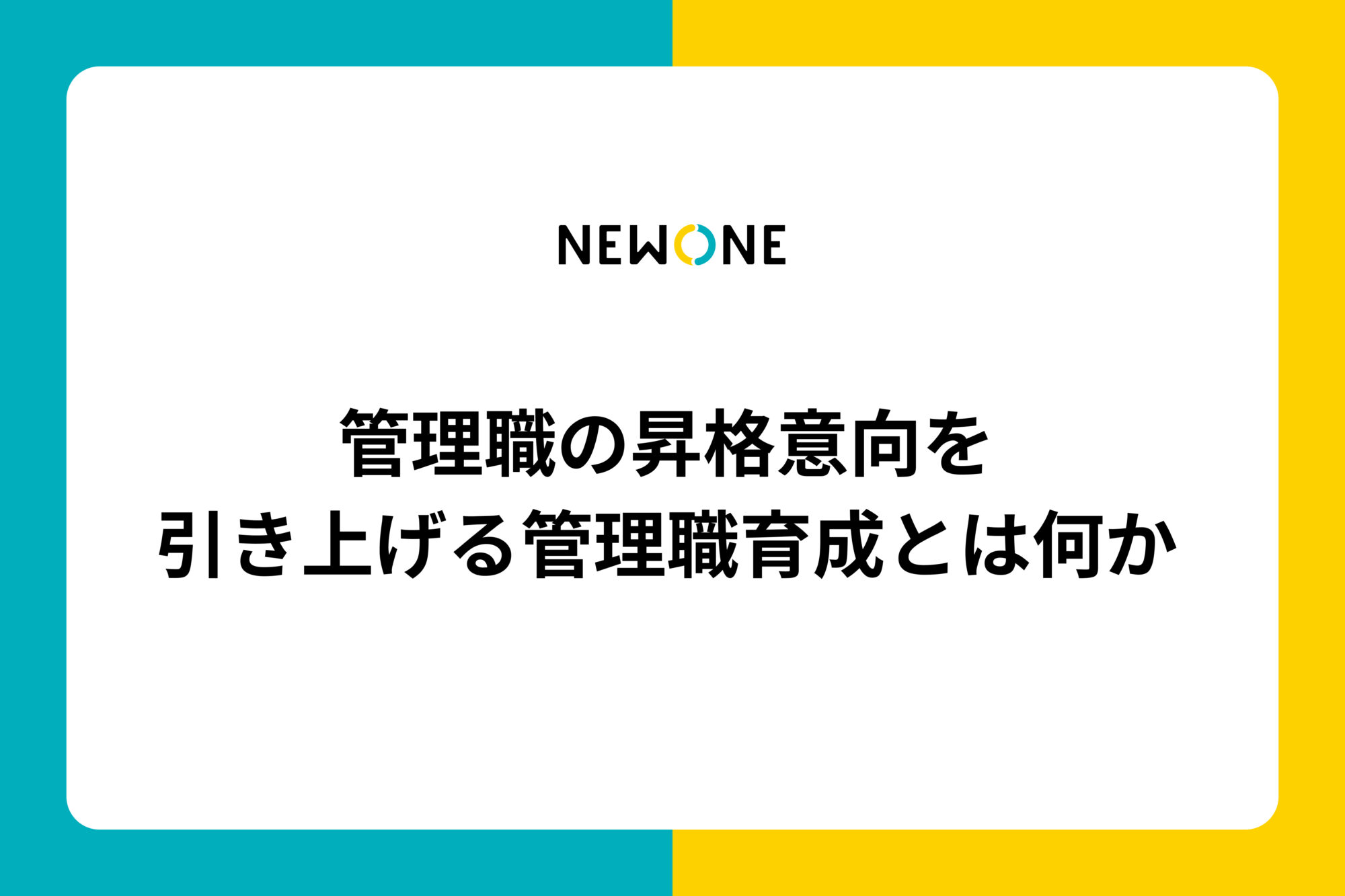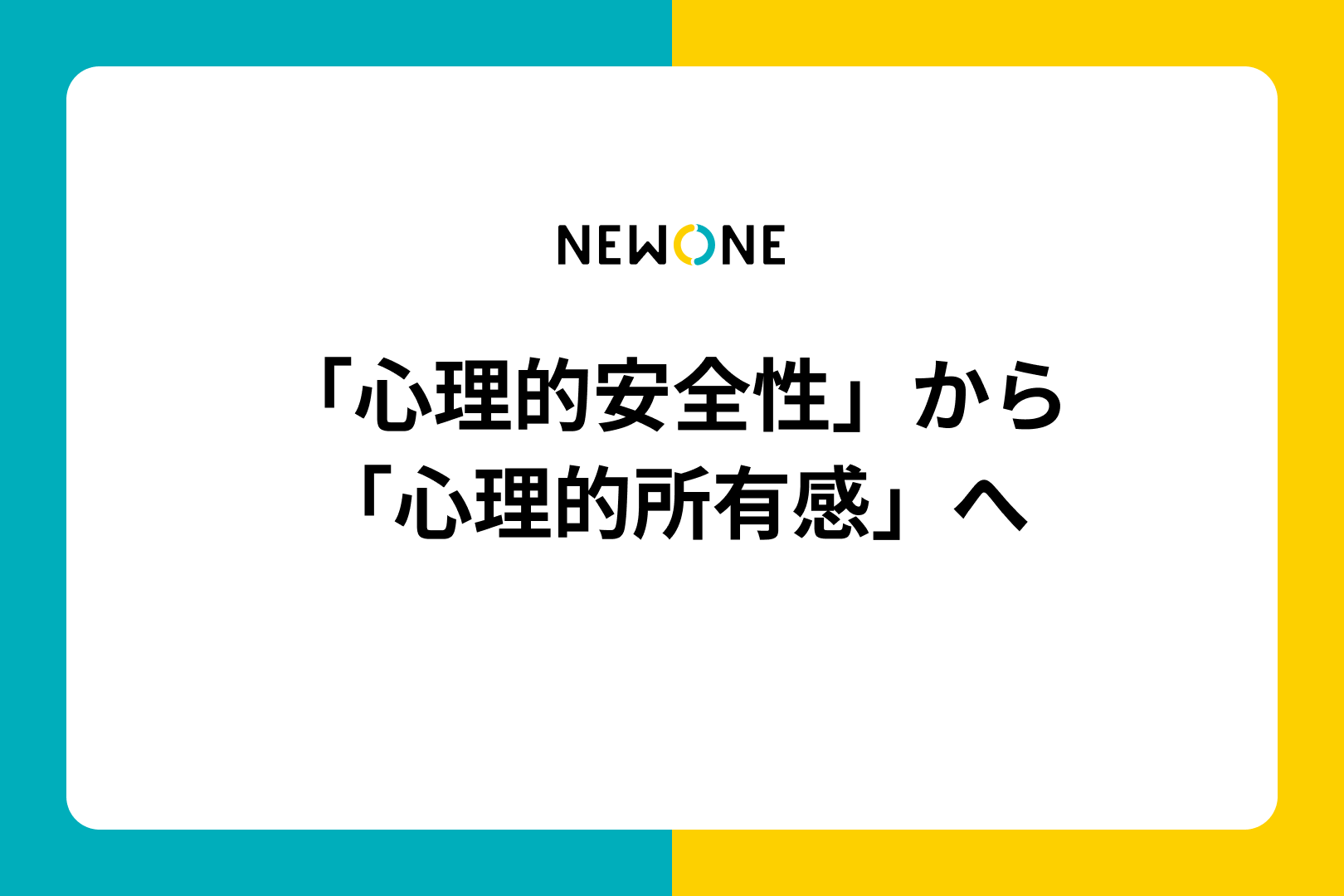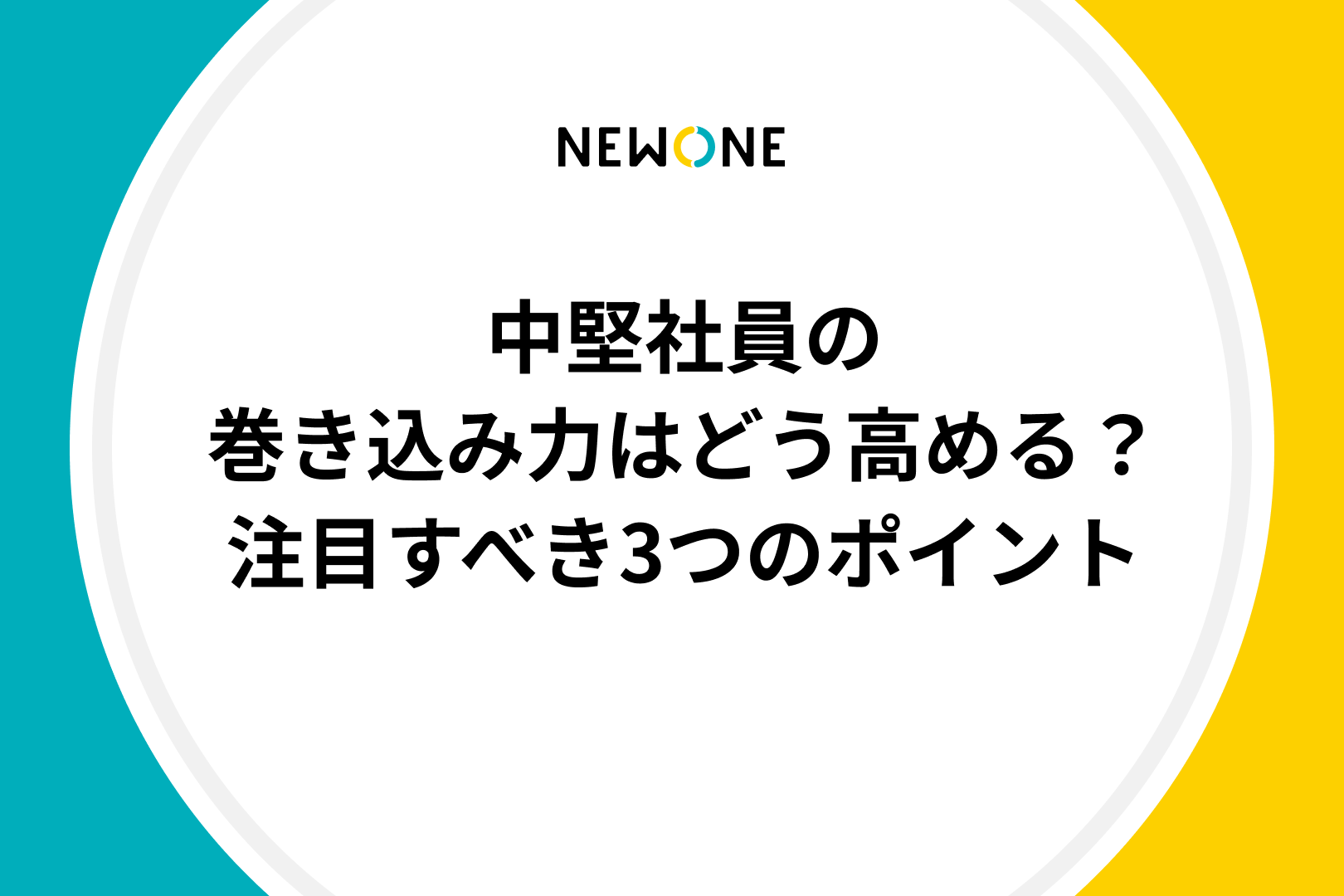
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
はじめに|巻き込みが苦手な中堅社員。その背景にある“見えない壁”
「もっと周囲を巻き込んでほしいのに、結局ひとりで仕事を抱えてしまう」
「チームで進めるべきフェーズにいるのに、なかなか相談ができない」
こうした中堅社員の“巻き込み下手”に悩む声を、育成担当の方からよく伺います。
中堅社員は、経験も実力もついてきたがゆえに、「自分でやった方が早い」と判断し、抱え込んでしまうことがあります。
その背景には、周囲に頼ることへの遠慮や、相談の仕方がわからないという壁が潜んでいることも少なくありません。
本記事では、そうした中堅社員の巻き込み力を引き出すために、支援すべき「3つのフェーズ」に着目しながらアプローチのヒントをお届けします。
1|「頼る=遅くなる」という思い込みをほどく
巻き込みを避けがちな中堅社員に共通するのが、「自分でやった方が早い」という前提です。
確かに、自ら手を動かした方がコントロールしやすく、完了も早いと感じられるかもしれません。
しかし実際には、「巻き込んだ方が速く、また、より良くなる」場面が多く存在します。例えば、1時間かけて調べていたことが、他部署の方や経験者のとの数分の会話で解決する。あるいは、他者の視点が加わることで、より説得力のある提案に仕上がる。こうした経験を重ねることで、初めて“巻き込みの意味”を実感できるのです。
この「頼った方が速くて良い」経験を意図的に設計し、現場での実感を伴わせていくことが求められます。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
2|「巻き込めないのは時間がないから」の本質に気づく
「周囲を巻き込めたらいいと思っているが、忙しくて余裕がない」
この言葉の裏側には、「何を巻き込めばいいのかが、自分でも整理できていない」という構造的な課題が隠れているのではないでしょうか。
つまり、時間の問題ではなく「論点の明確さ」がカギであると考えています。
「このアイデアの方向性について意見がほしい」
「この設計が漏れていないか確認してほしい」
そういった“巻き込みたいテーマ”が明確になれば、周囲にも的確に働きかけることができます。
中堅社員に対して、時間を確保するための支援・サポートではなく、支援・サポートが必要となるポイントを分析する力が求められます。
3|巻き込む=頼るではなく「共創する力」と捉え直す
中堅社員が巻き込みをためらう理由のひとつに、「人に頼ることへの抵抗感」があります。
「迷惑をかけてしまうのではないか」「一人で完結すべきではないか」といった思いが、無意識のうちに巻き込み行動を妨げているのです。
しかし、巻き込みとは“作業をお願いすること”ではありません。
「他者の視点や知見を借りて、より良いアウトプットをつくる共創行動」です。
この“巻き込みの再定義”を言語化し、中堅社員の中に落とし込んでいくことが重要です。
頼ることを「弱さ」ではなく「仕事の質を高める力」として認識してもらうことが、行動変容への鍵になります。
おわりに|巻き込み力は、3つのフェーズを磨くことで必ず伸びる
巻き込み力を高めるために必要なのは、単なる声かけのテクニックではありません。
中堅社員自身が、
- 自分が巻き込めない「壁」に気づき、
- 他者の力が必要な「論点」を整理し、
- 巻き込みを「共創」として実行する方法を体得する
という3つのフェーズを、段階的に磨いていくことが重要です。
「巻き込み力」は学習可能な力であり、確実に伸ばすことができます。
一人で頑張る姿勢から、周囲とともに成果をつくるスタイルへ。
その変化を後押しすることで、個人の成長はもちろん、組織全体の推進力にもつながっていくはずです。
 掛井 柾樹" width="104" height="104">
掛井 柾樹" width="104" height="104">