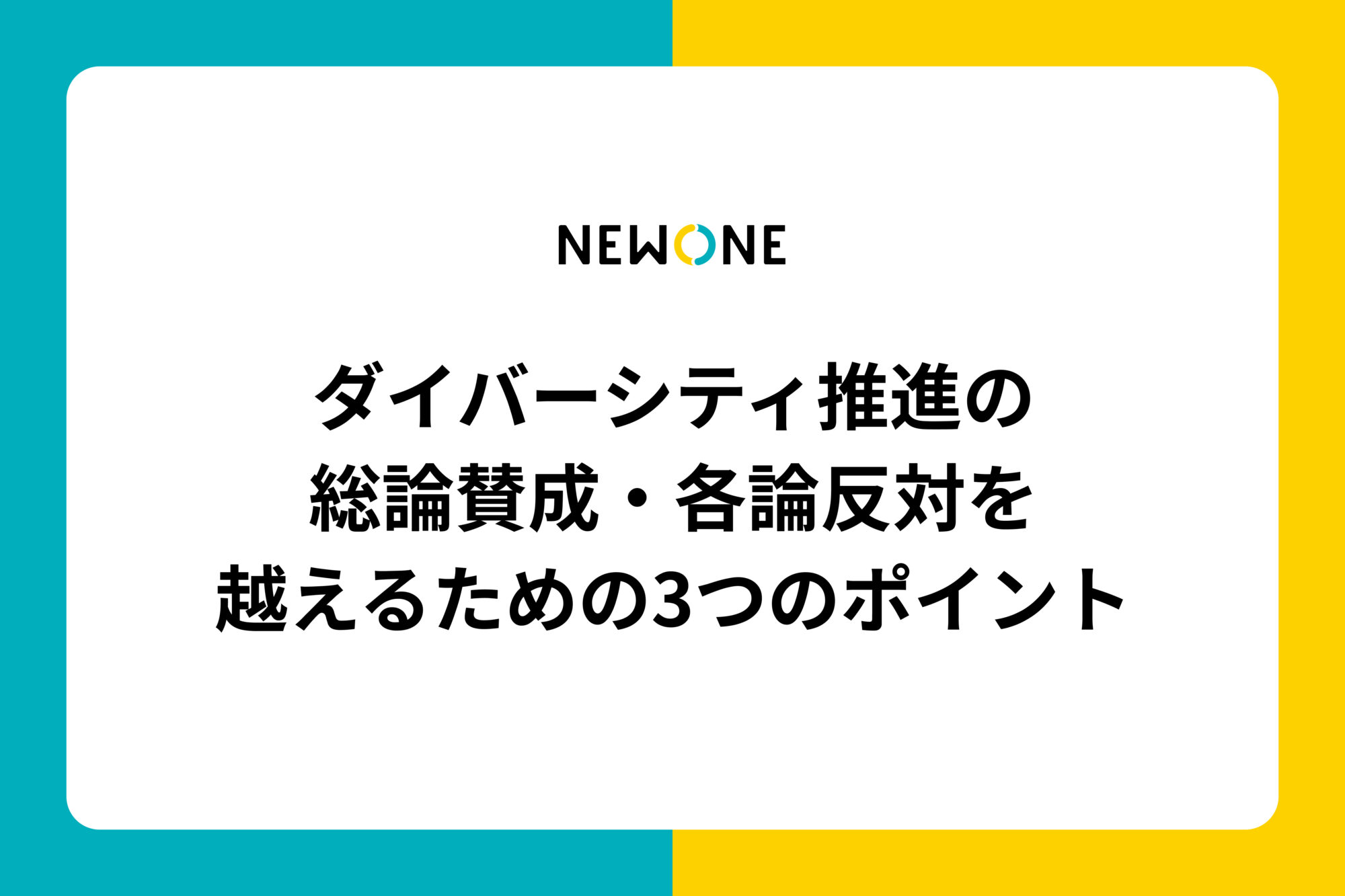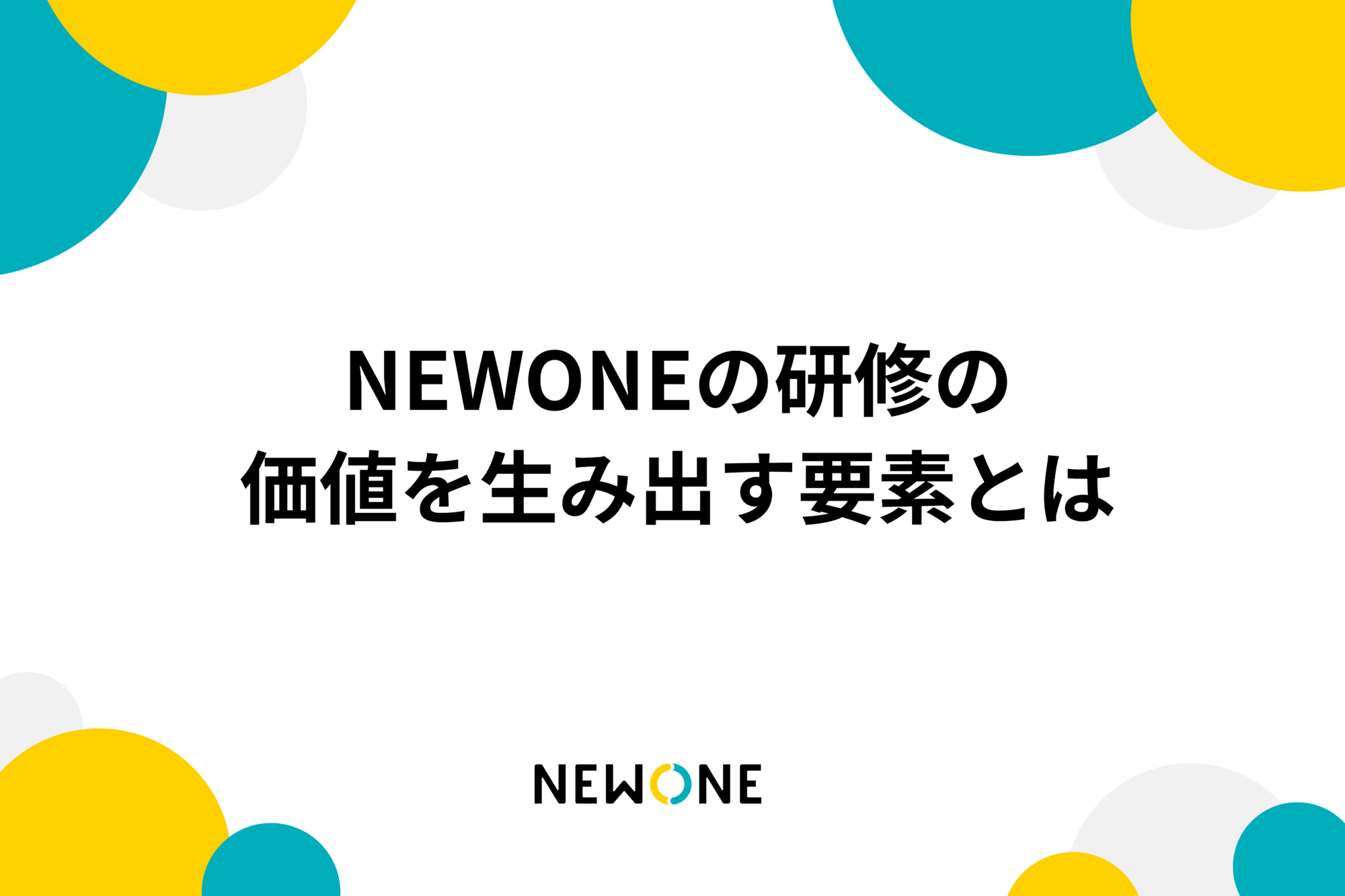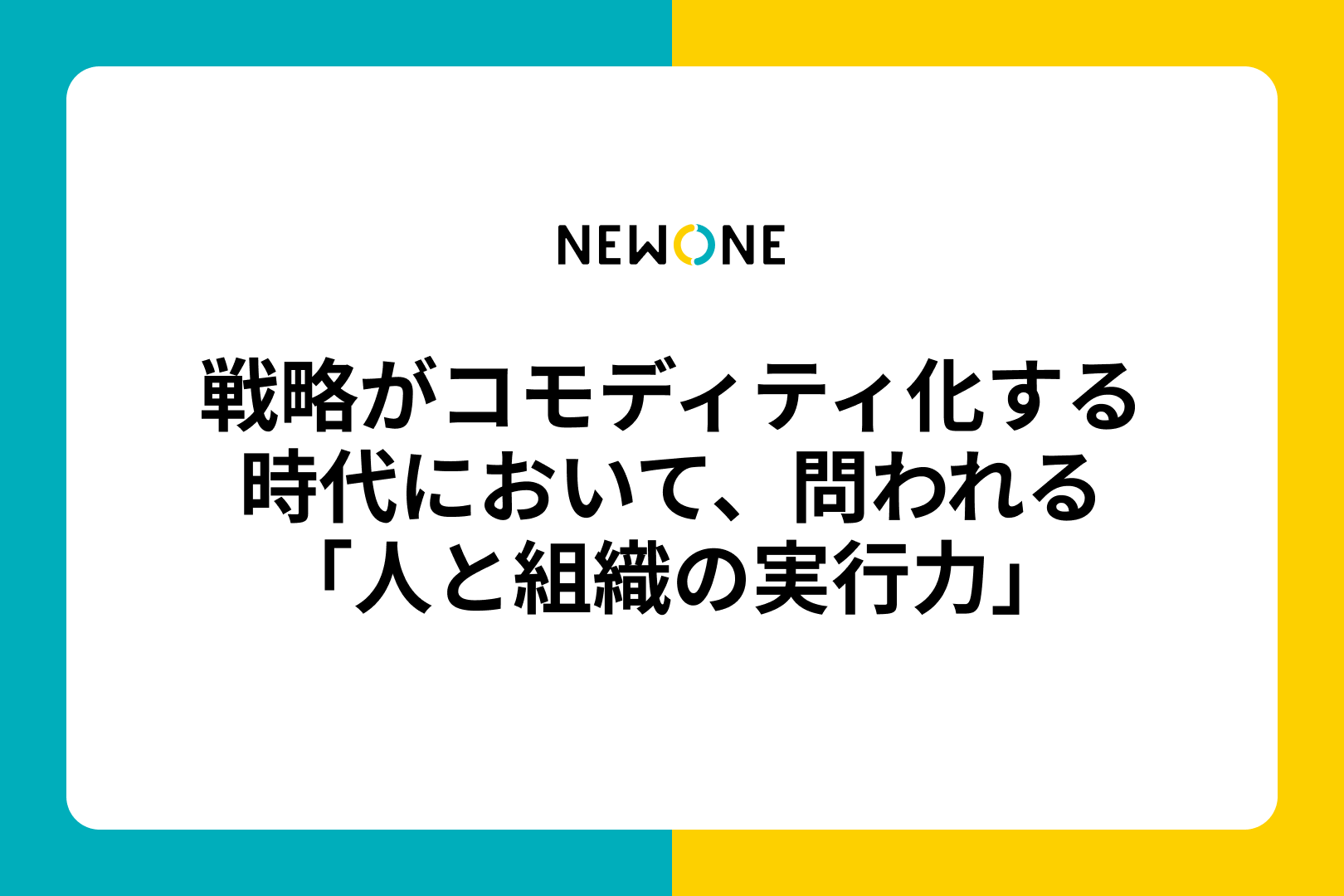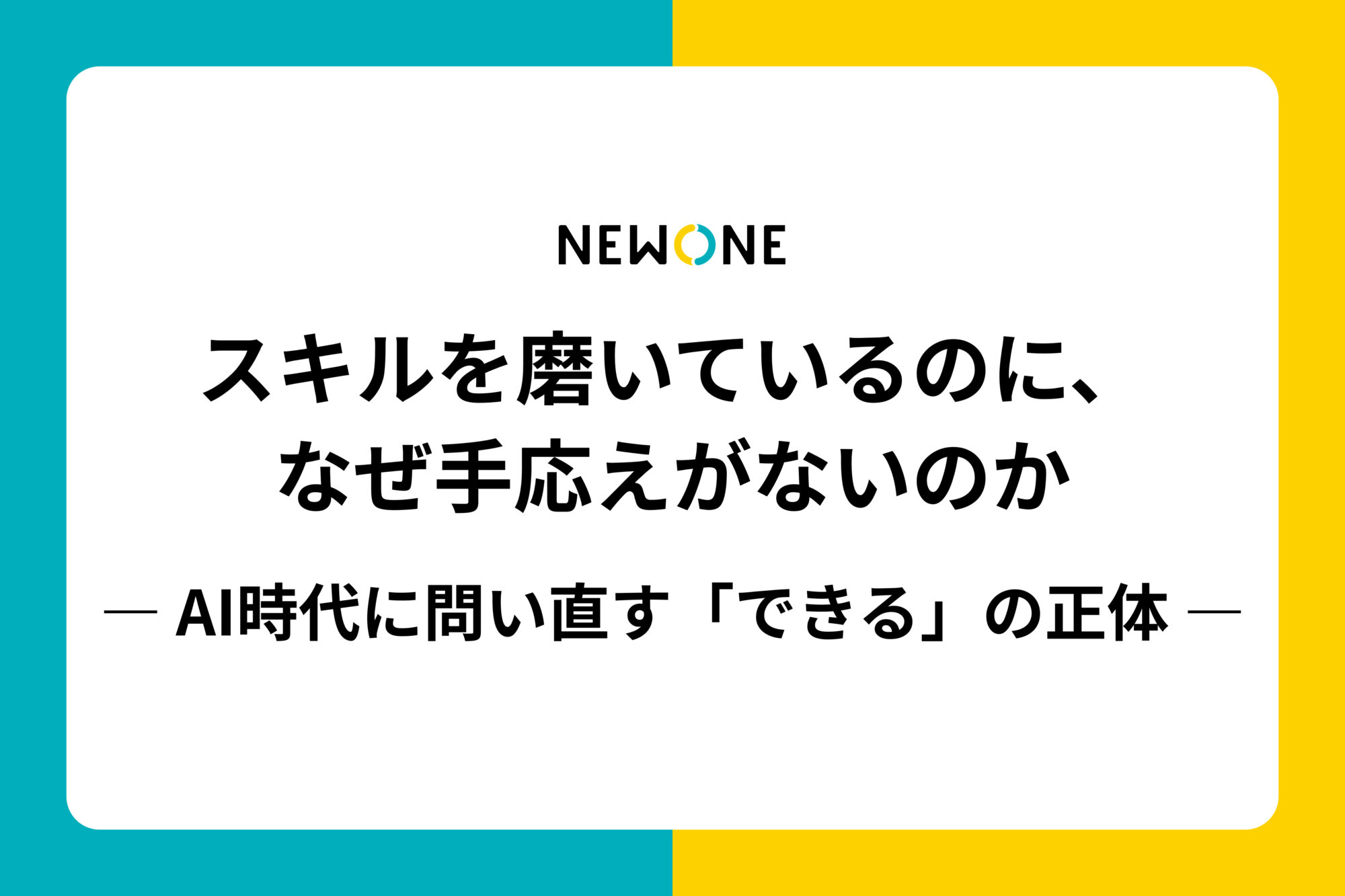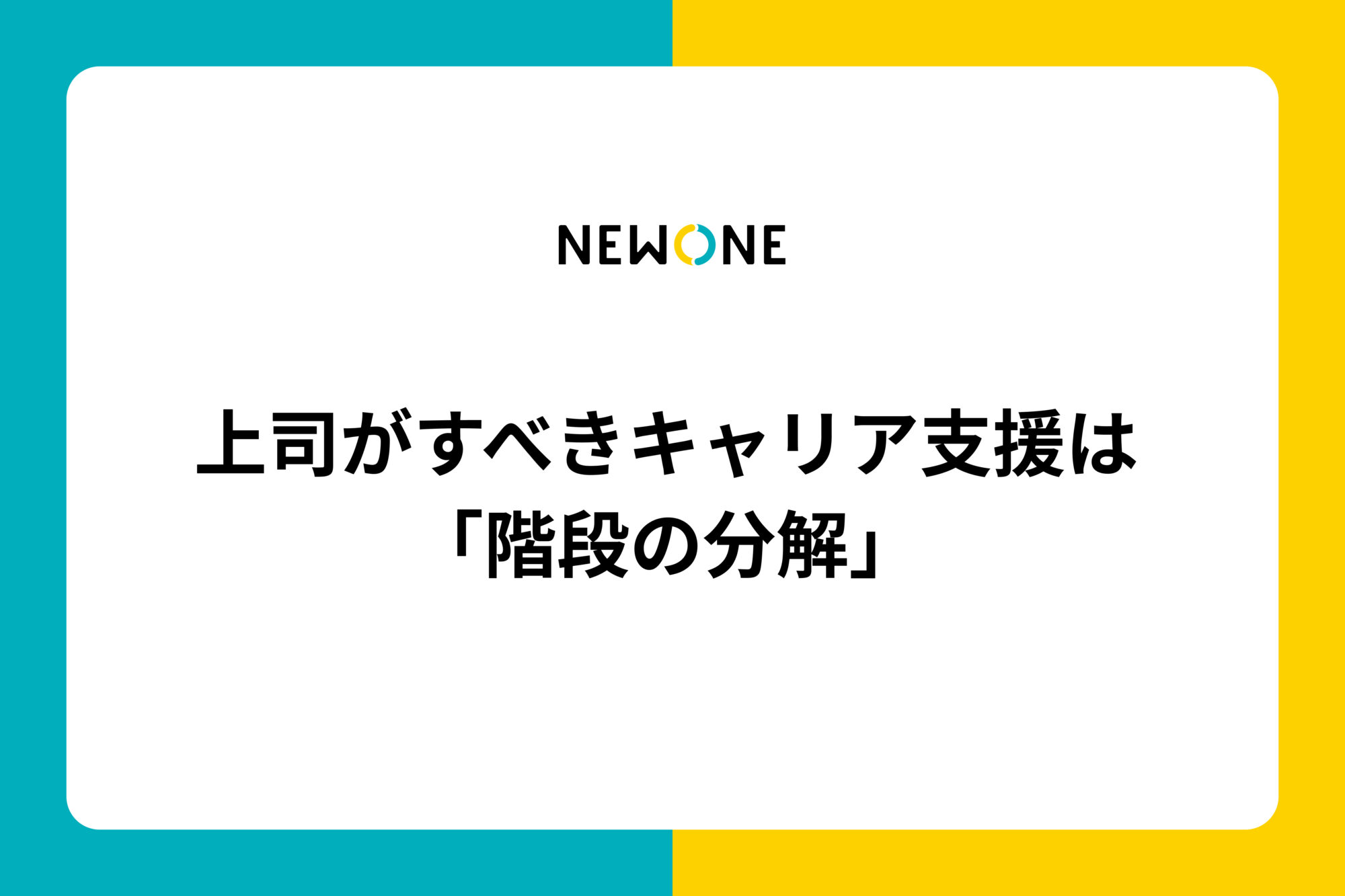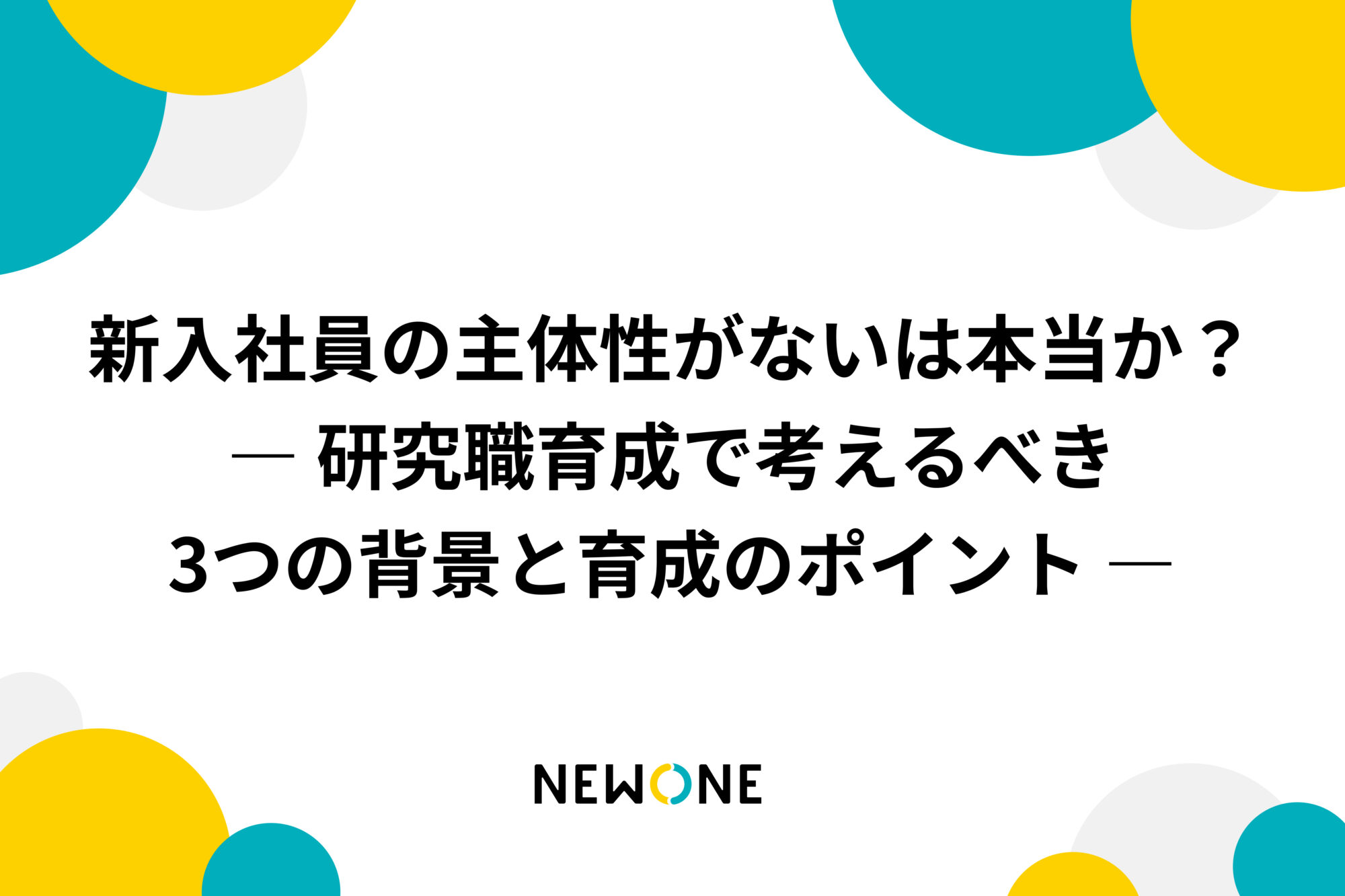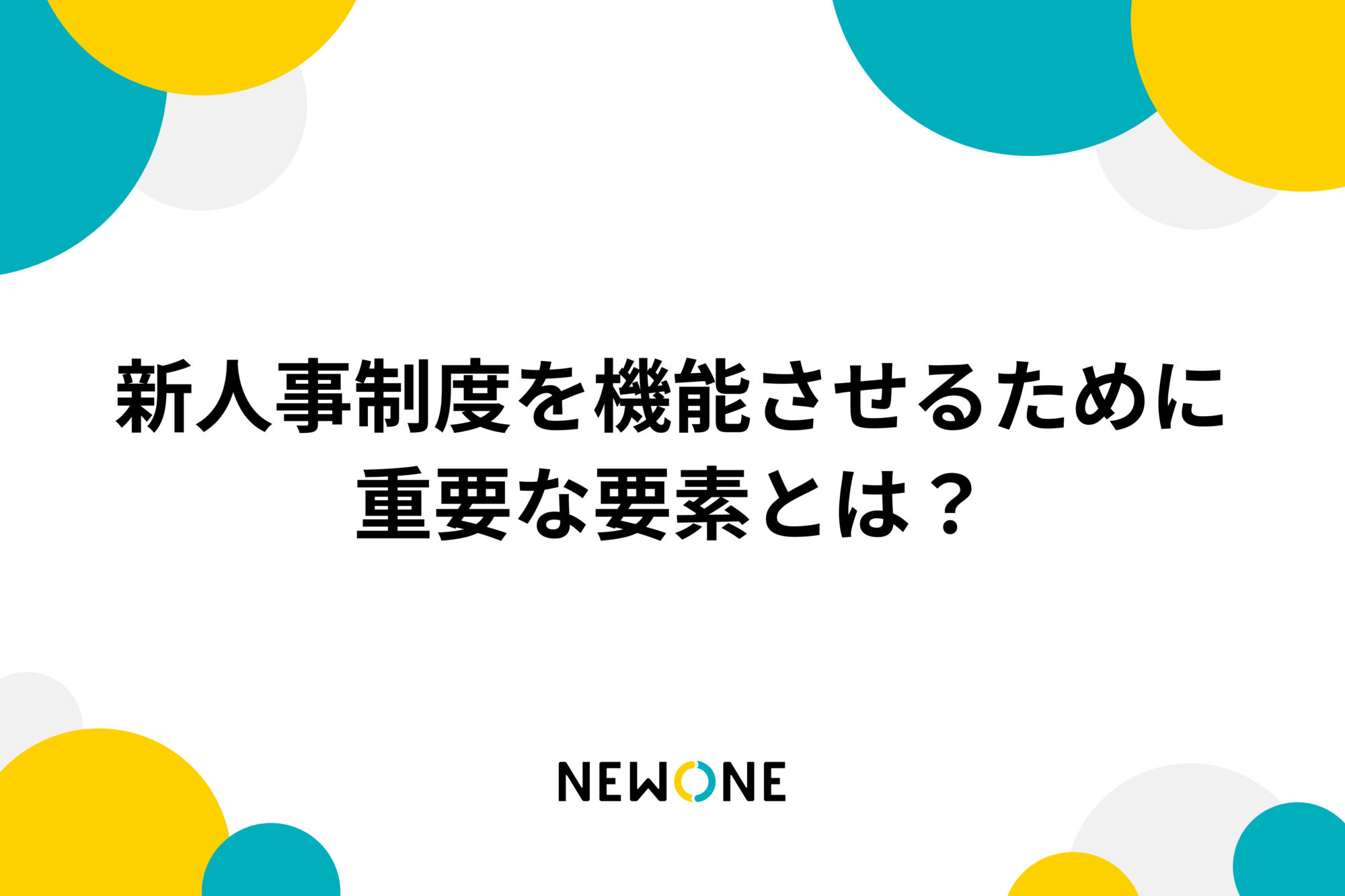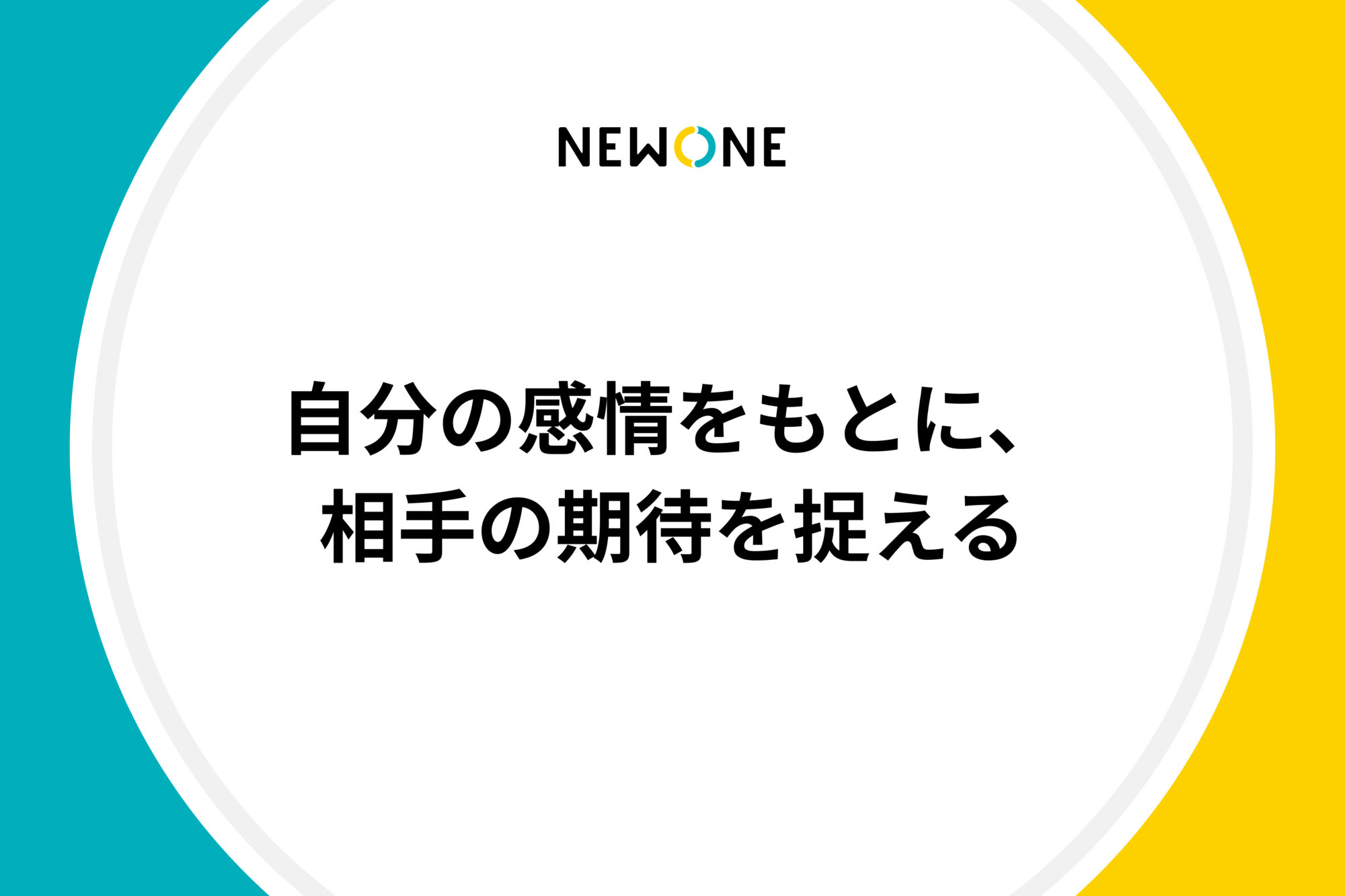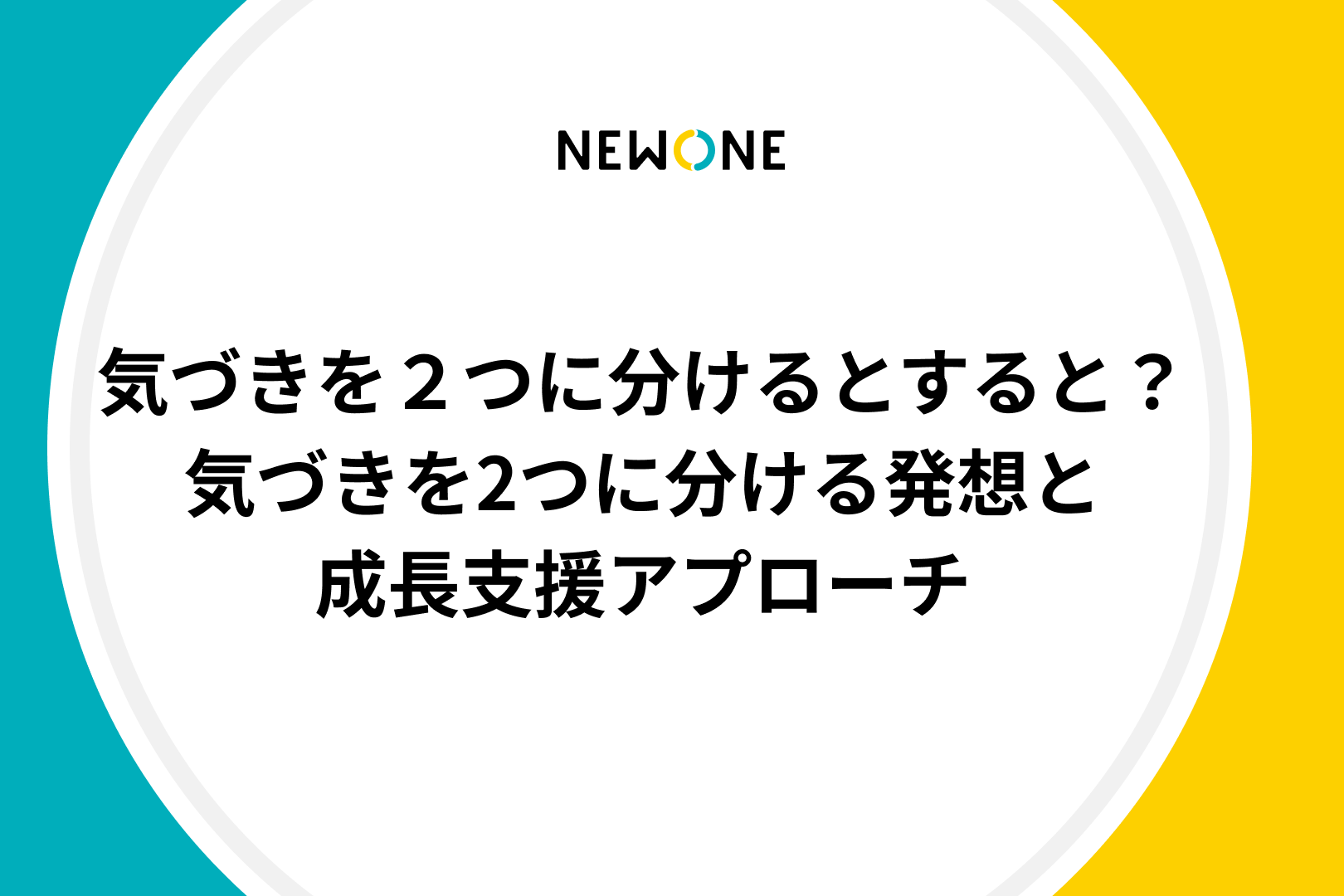
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
部下に業務指導を行う際、
「1人前として自分で仕事を進められるようになるためにも、もっと自分から気付いてほしいな、、」
「何度も似たような指導をしているけど、なんで、Aさんは◯◯に気づけなかったんだろう、、」
「仕事がマンネリ化して、Bさんの成長実感がなくなってきてしまっている気がする。何か気づき・学びを与えられないか?」
「自然と気づきが生まれるときと、そうでないときがある。何が違うんだろう、、」
と思ったことはありませんか?
本記事は、『若者に辞められると困るので、強く言えません(著:横山 信弘)』で述べられていた、気づきを2つに分ける発想をもとに、気づきを起点とした部下への成長支援アプローチを考えていきます。
そもそも、なぜ成長支援に「気づき」が求められているか
行動変容が促される理論的背景の一つに「認知的不協和」という心理学用語があります。認知的不協和は、「自分はできている」という自己認識と、実際やってみると「まだまだ足りていない」という事実の矛盾があることに気づくことでもたらされます。
この気づきにより、現状の俯瞰・振り返りがもたらされ、行動変容が促されます。(詳しくはこちら)
(上記は、経験学習サイクルの経験と内省の間に隠れた重要なステップであると考えています。)
では、部下との関わりのなかで、行動変容を促す気づきはどのようにして生まれるのでしょうか。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
部下の気づきを生み出す2つのアプローチ
このアプローチを考えるうえで参考にしたのが、『若者に辞められると困るので、強く言えません(著:横山 信弘)』で述べられていた、気づきを2つに分ける発想です。
本書で言われている2つとは、
1.発見の気づき
事前に見通すことができなかった質の高い気づき
2.反省の気づき
事前に予想可能なものや、当たり前の事柄に気づくこと
という2つでした。
では、本題の部下の気づきを生み出す2つのアプローチに戻ると、それは「問いかけ」と「指導・ダメだし(フィードバック)」であると考えております。
皆さんは、上記の2つを意識的に使い分けることは出来ていますか?
行動を改善させたり、基準値を高めるうえで「反省の気づき」は重要ではあるものの、「反省の気づき」ばかりでは、部下がしんどくなるのが実状かと思います。仕事に慣れておらず、見通しが全く立っていない状態と言えど、「発見の気づき」を演出できないか、を検討することをオススメします。
とはいえ、「発見の気づき」ばかりを意識し、
「自分なりでいいから、とりあえずやってみて」
と任せっきりでは、部下もどのように進めればいいか、路頭に迷ってしまいます。
納得感のある関わりにするためにも、仕事に取り掛かる前に、仕事の目的・意味を一緒に考えながら、どこまで見通しが立っているか、確認することが重要です。発見の気づきを徐々に増やしていくことで、自分から考えようとする主体性を育むことができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。人が変わろうと思うきっかけには、何かしらの気づきが関係していると思います。
本記事が育成の手応え、そして主体性が育まれるきっかけになっていましたら幸いです。
 高藤 賢" width="104" height="104">
高藤 賢" width="104" height="104">