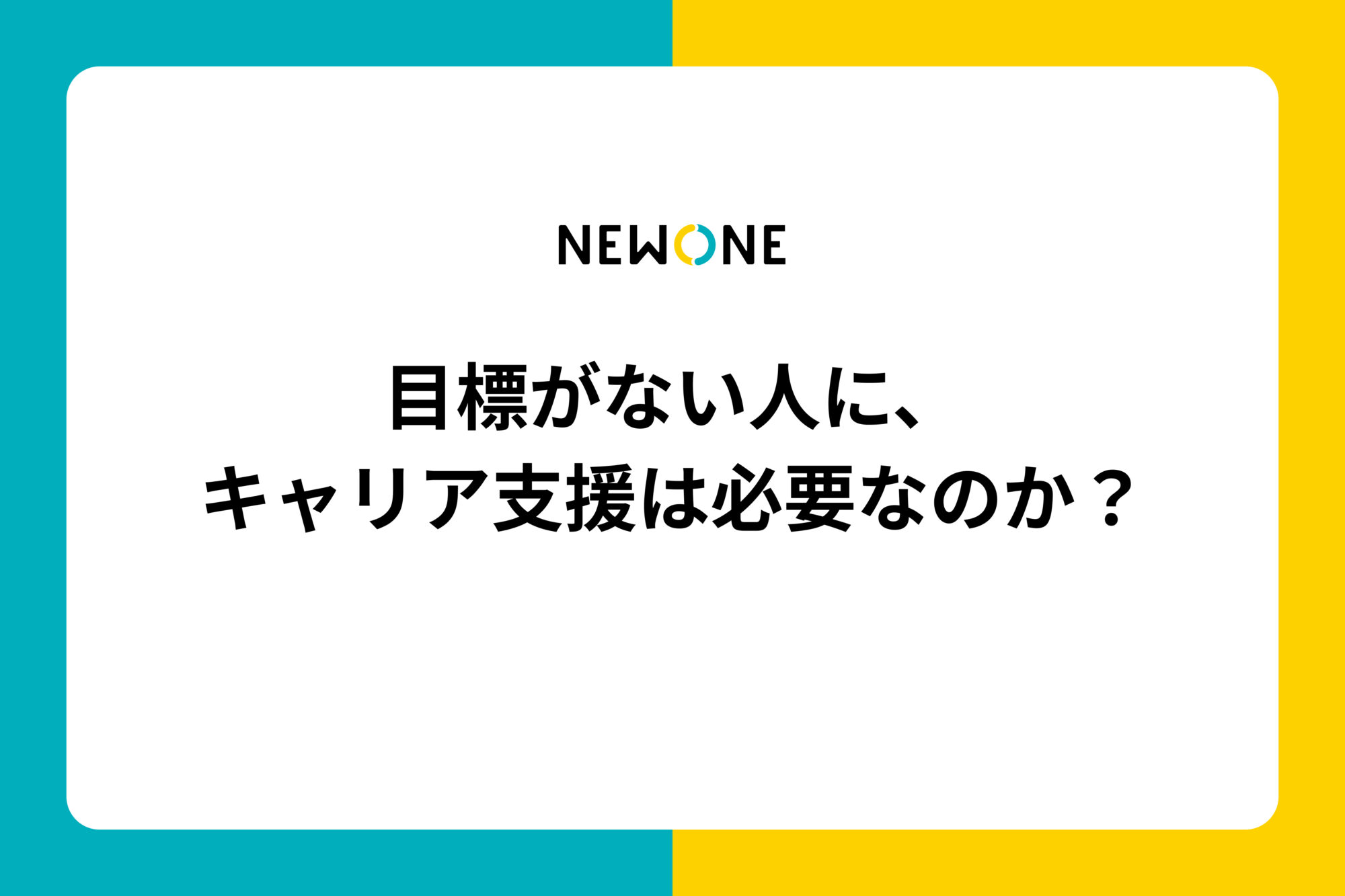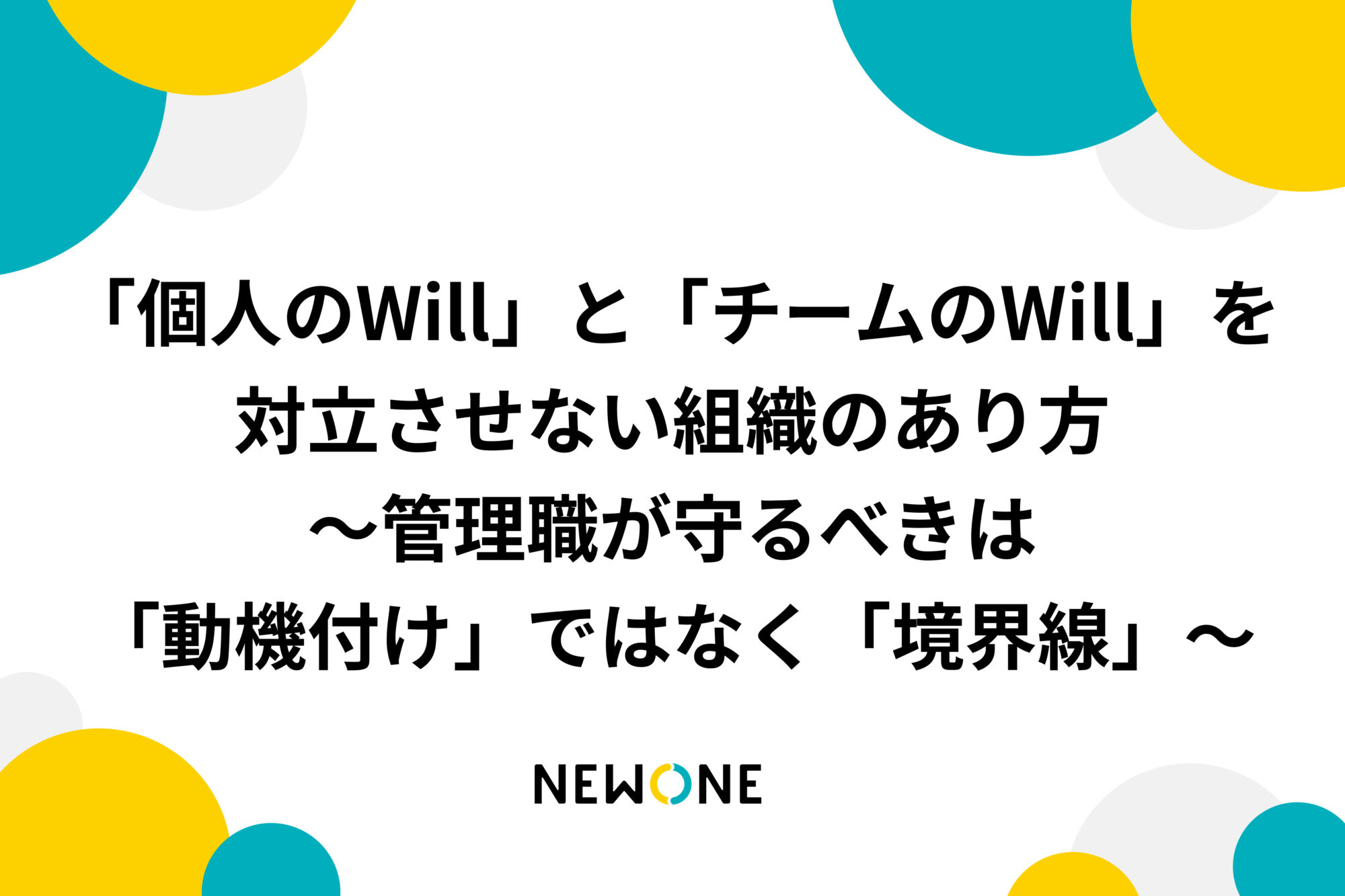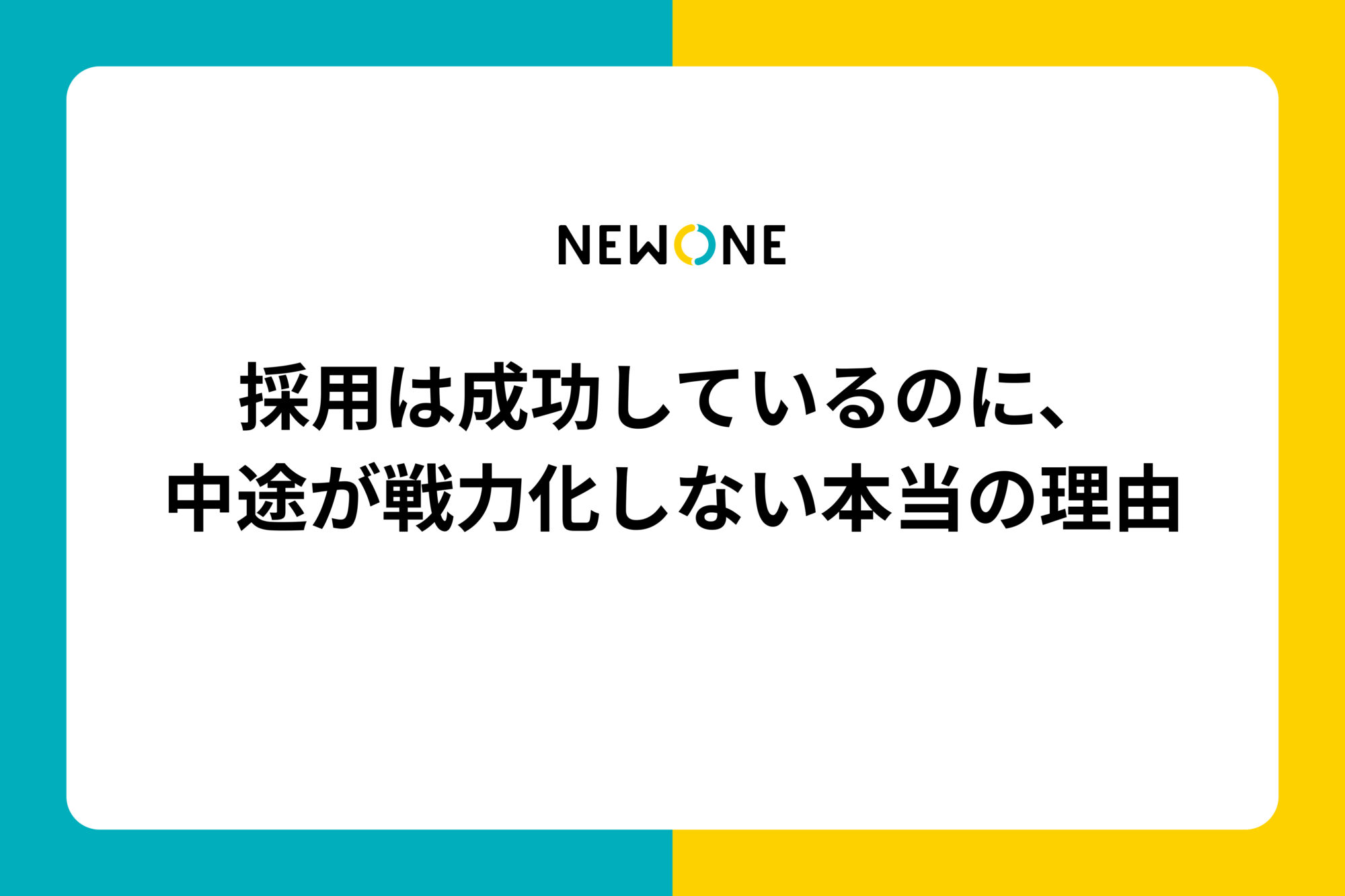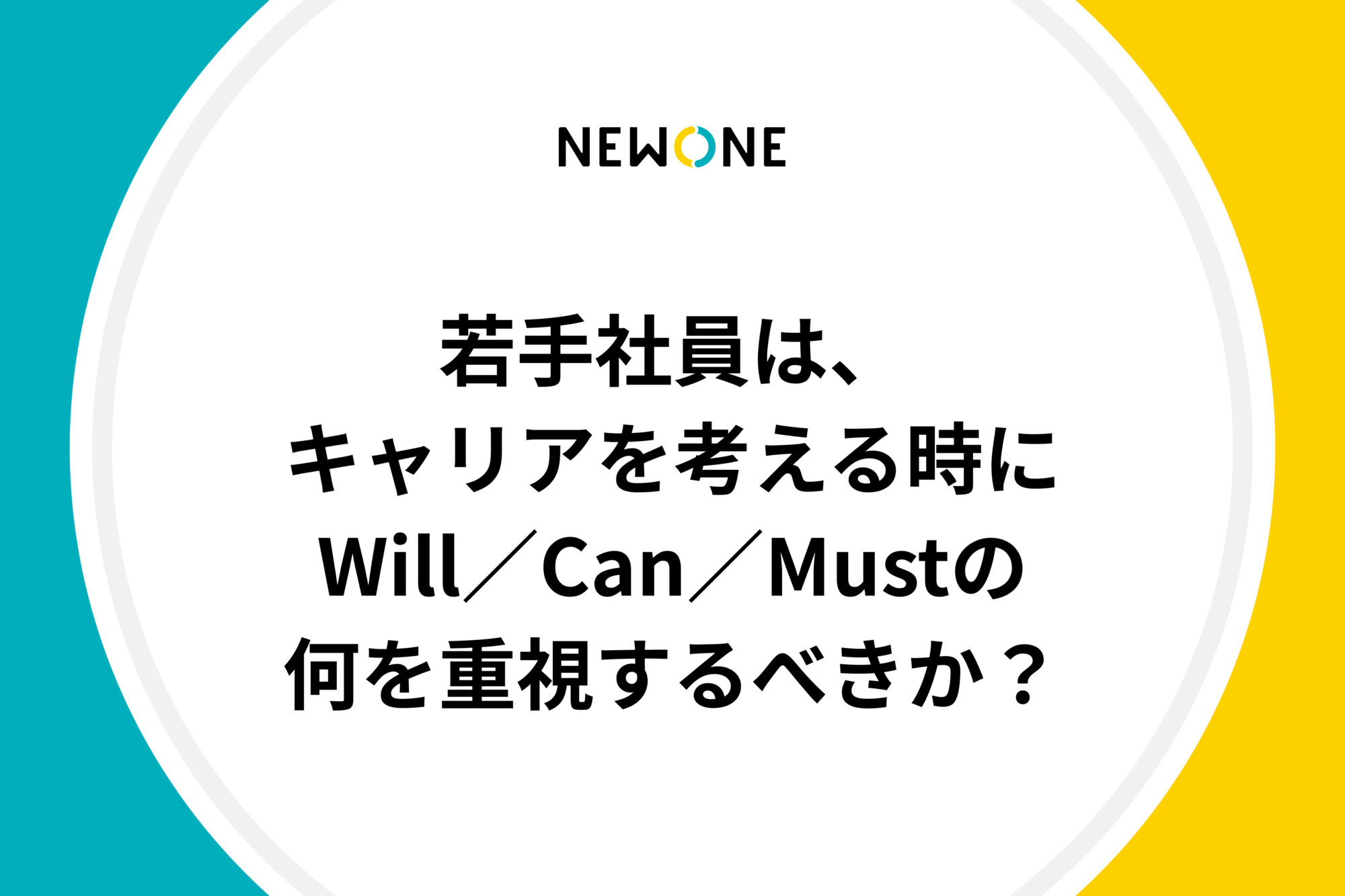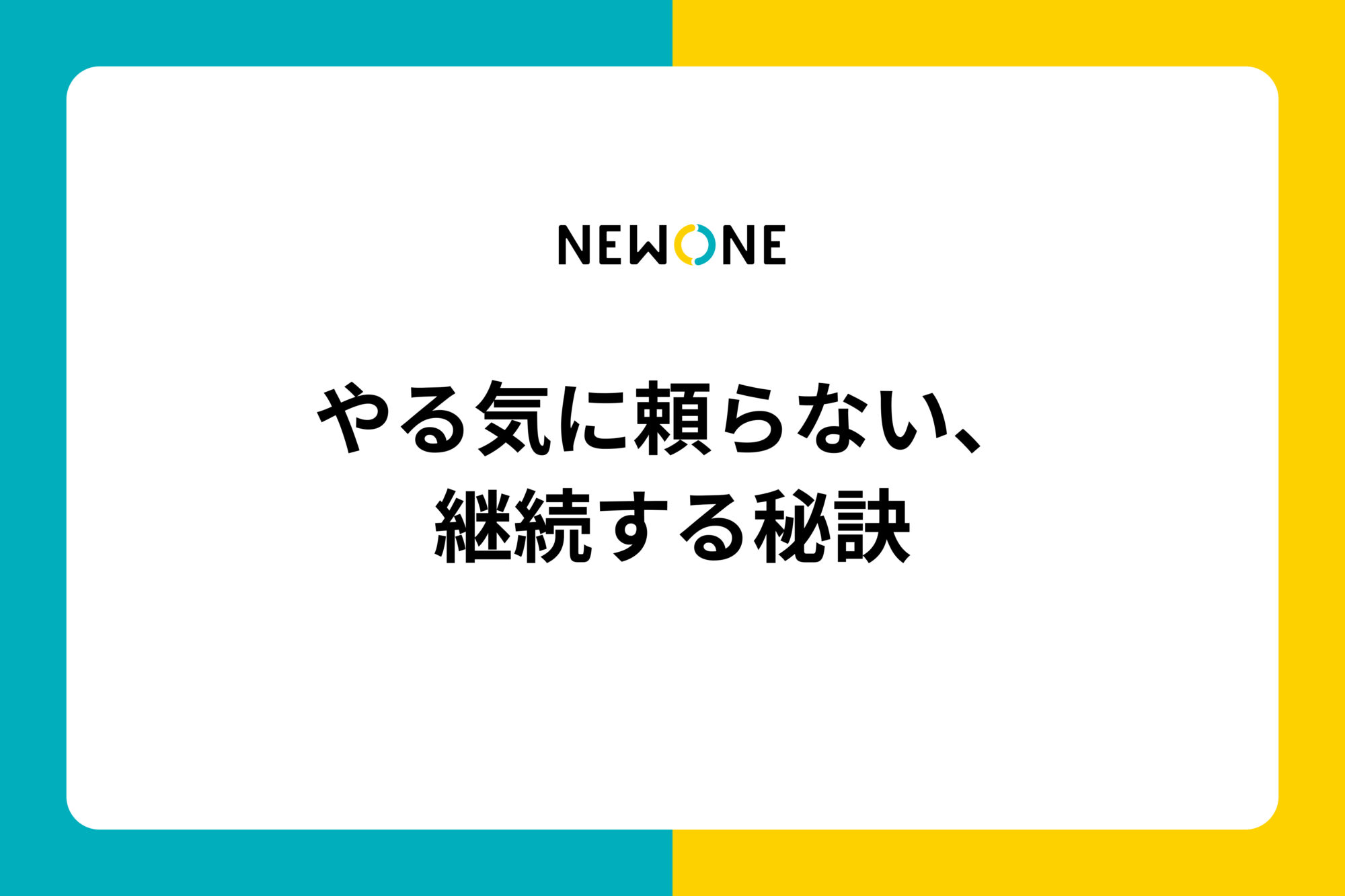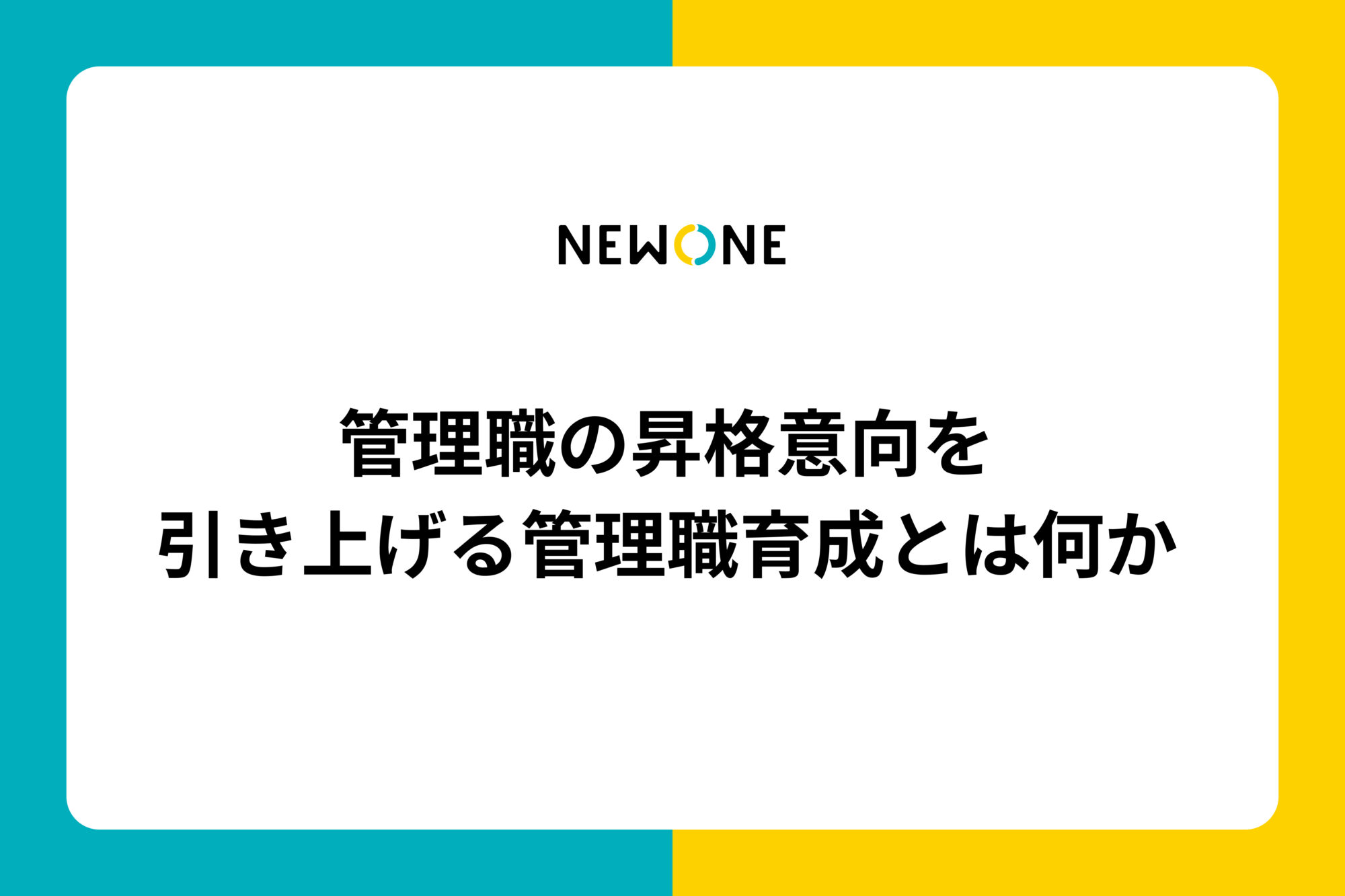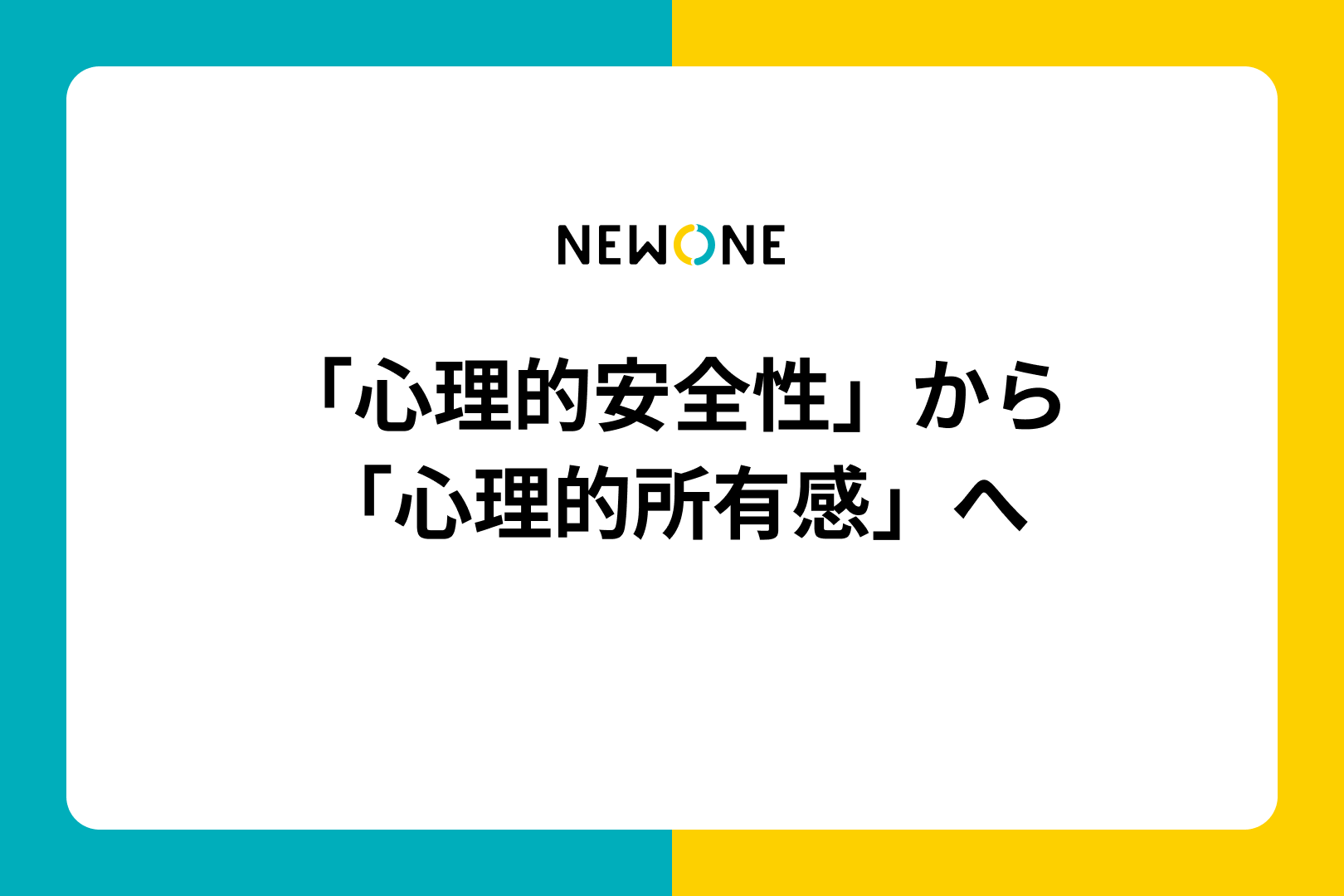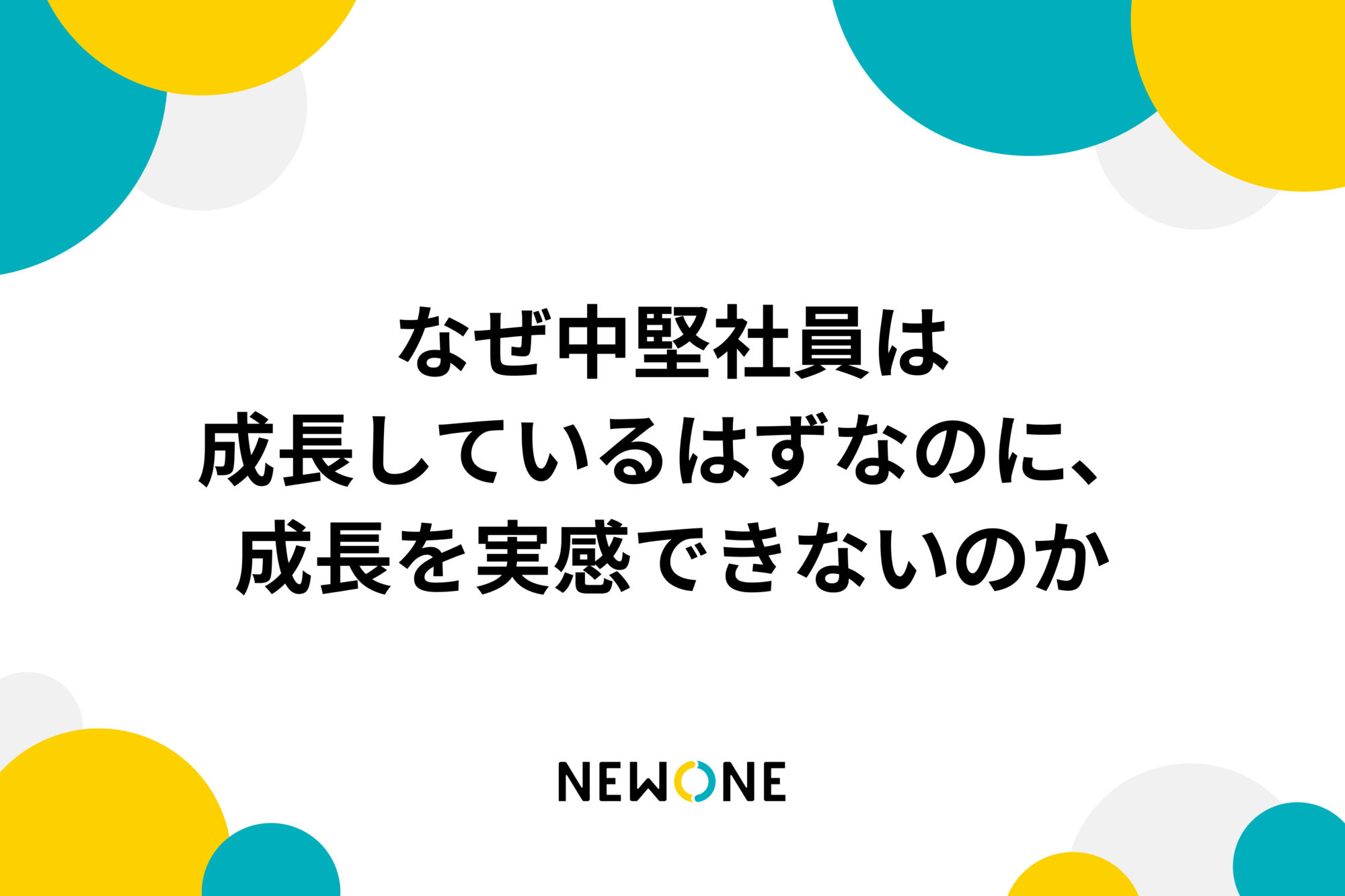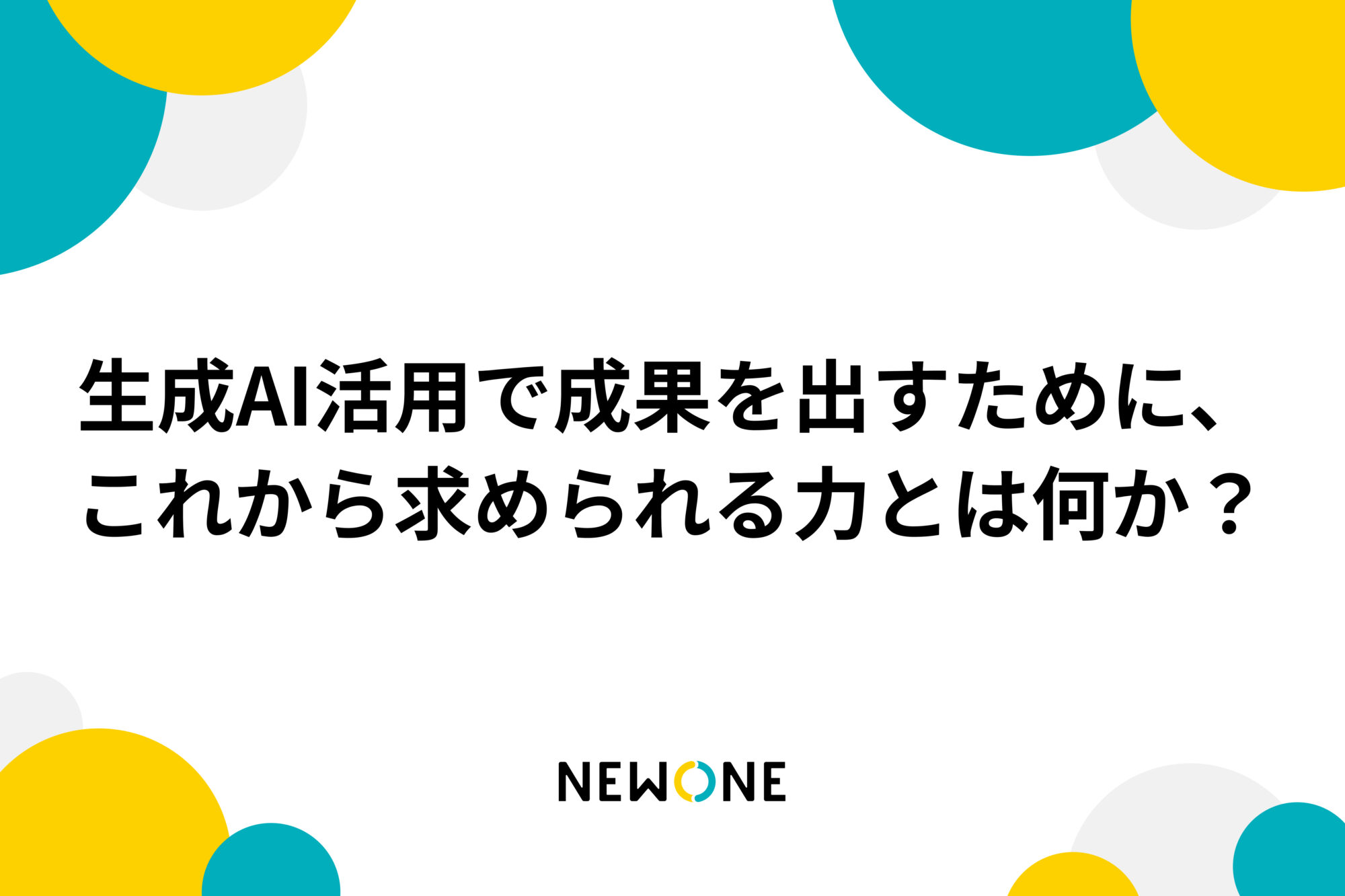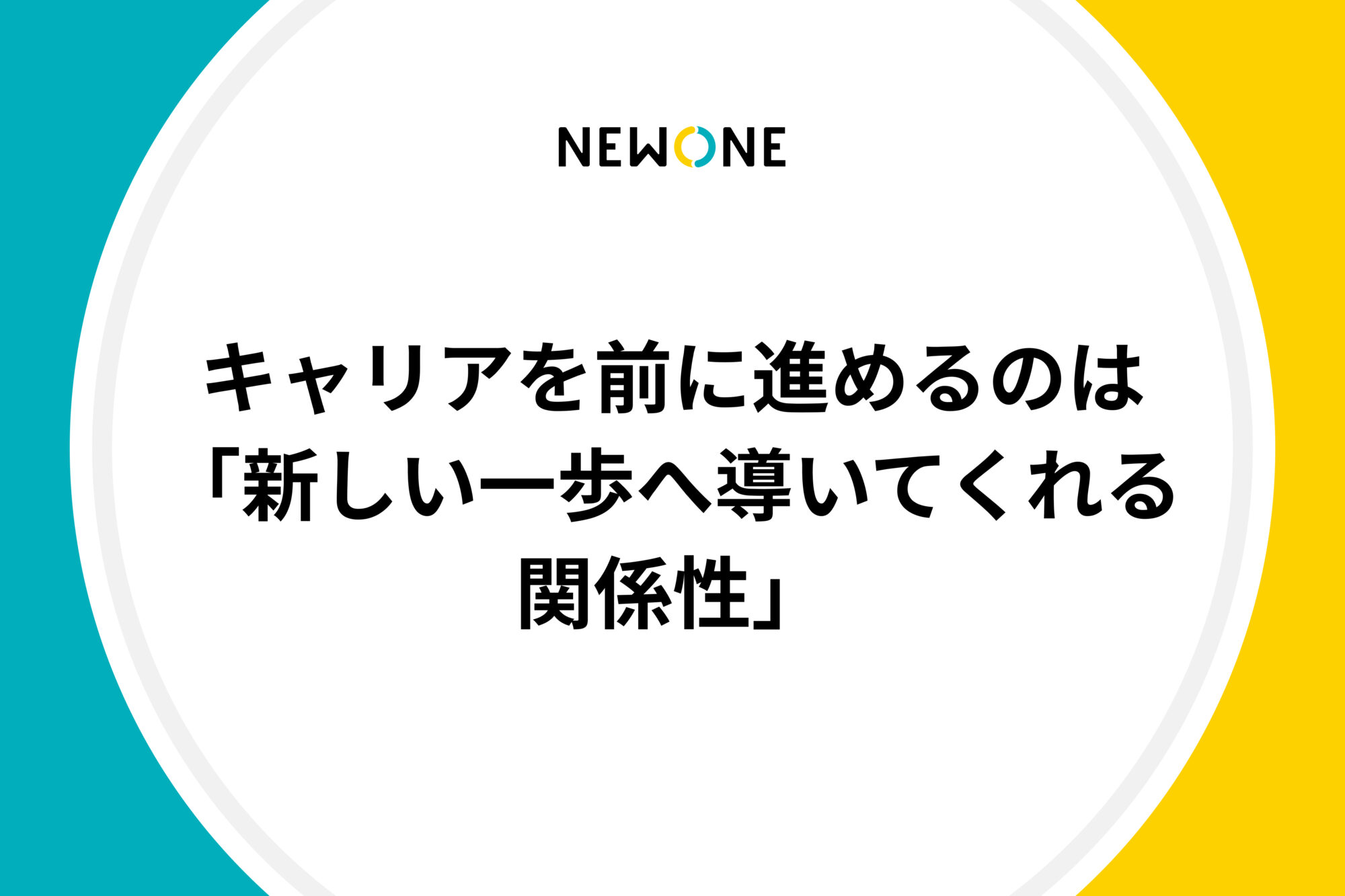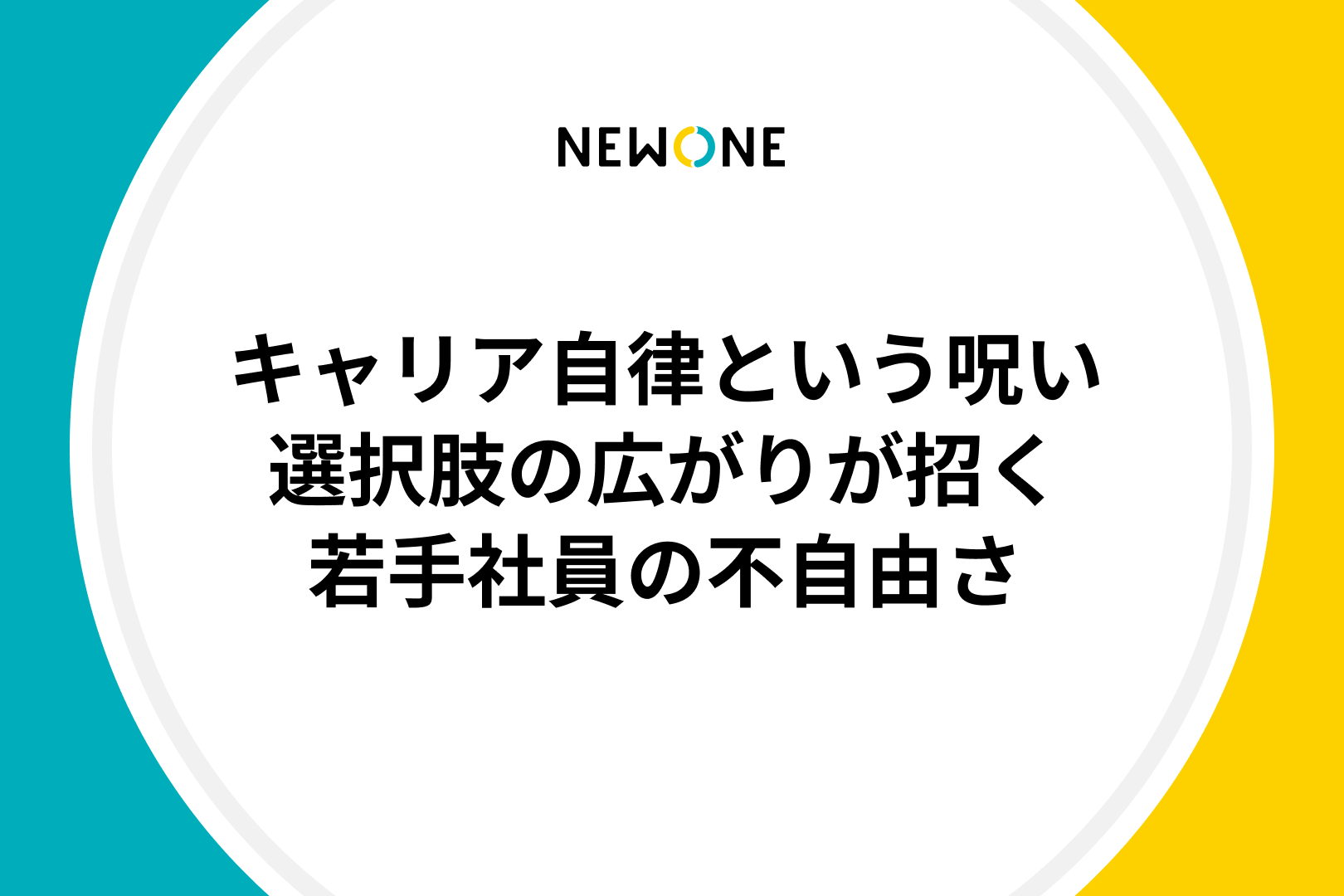
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
はじめに
「入社3年目」というのは、今も昔も1つの「キャリアの節目」と言えます。
3年目という年次は、OJTトレーナーが付きっきりの新人時代→OJT指導が外れて、ひとりで動かす時期→自分で回せるようになるいっぱしの時期。
この段階の社員は、新入社員としての適応期を過ぎ、業務に習熟してきた一方で、自身のキャリアに対する不安や疑問が芽生える時期でもあります。
そのため、昔から3年目研修、という階層別研修はよくあり、またその中身もキャリアに関連することを扱うことが多かったのですが、昨今の不安定・不確実な醸成や人材の流動化の加速化の背景などもあり、そのトレンドにも変化が起きています。
キャリア自律の推進という意味合いからも、3年目階層別研修の施策を見直したい、ですとか、3年目に対して「キャリア」というテーマで取り組みたい、というご相談やお問い合わせが増えてきております。
そのため、今回の記事では
「3年目のキャリア観に何が起こっているのか?」
「一体何に困っているのか?」
「3年目キャリア研修は何をすれば良いのか?」
という観点で、他社様へのご支援実績等から見えてきたポイントを整理しつつお伝えしていきたいと思います。
3年目が陥るキャリアの不安や悩みとは?
昔から、「入社3年目」というのは分かりやすい節目になっていましたし、3年目離職率で語られるように、3年目というのは悩みや不安が出やすい時期と言われていました。
ひと昔前の3年目の悩みや不安としては…
キャリアパスの不透明さ:
かつての3年目社員も現在と同様にキャリアパスについて悩んでいましたが、その当時は終身雇用がまだ一般的であり、長期的なキャリアビジョンを描くことが求められていました。しかし、具体的なキャリアのステップや成長機会が明確に示されることは少なく、不安を感じることが多かったです。
上司や先輩との人間関係:
昔の職場文化は上下関係が厳格であり、上司や先輩とのコミュニケーションが難しいと感じることが多かったです。上意下達が強く、新しいアイデアや意見を積極的に発言することが難しい環境を作り出し、ストレスを感じていたように思います。
仕事のやりがいとモチベーションの低下:
新人としての初期のやる気が薄れ、ルーチンワークに対する不満や仕事のやりがいの欠如を感じることが多かったです。特に、自己成長やスキルアップの機会が少ないと感じることが多く、モチベーションの維持が難しかったと言われています。
ワークライフバランスの欠如:
以前はまだ長時間労働が一般的であり、ワークライフバランスを取ることが難しかったです。これにより、仕事とプライベートのバランスが取れず、疲弊感やバーンアウトのリスクが高まっていました。
これに対して昨今は、以下のような悩みがあるように思えます。
早期成長や自身のキャリア開発への焦り:
現代の3年目社員は、自分の成長やキャリア開発に対して非常に高い期待を持っています。裏を返せば、1つの会社にぶら下がるというより、市場価値や能力成長を期待する側面が強くなっており、具体的なキャリア目標やスキルアップの機会を求める傾向が強く、これが明確に示されなかったり、下積みを要求された場合に不満を感じやすいです。
やりがいを求めるが、得られない:
現代の職場では、職場環境や報酬以外に、やりがいや貢献実感を持ちたいと考えており、仕事に対しても同じように自己決定感ややりがいを求める傾向があるため、それが得られない場合は転職するという選択肢が出やすいです。
ワークライフバランスの重視:
上記と反するようですが、現代の若い世代は、仕事とプライベートのバランスも非常に重視しており、柔軟な働き方やリモートワークを求める傾向があります。過度な労働時間やストレスを避け、プライベートの時間も大切にしたいと考えています。
◆世代傾向について
上記の背景の中にはいわゆる「世代傾向」と言えるものがありますので、少しだけ触れておきたいと思います。
昨今の若手は「Z世代」と言われておりますが、別名「タイパ世代」と称されております。
「タイムパフォーマンスの高さ」を特に重要視しており、仕事もプライベートも、限られた時間内にどれだけの効果・満足度を得られるかを強く意識する特徴がある世代である、という考え方です。また、SNS文化で育っているため、自分自身が「何者なのか」に対する恐れが上の世代よりも強いのではないかと言われています。
上記のような不安感や世代特徴に加えて、昨今の転職のハードルの低さや他者の情報の入手のしやすさも相まって、現在の職場に不満が出た場合は早々に次の環境を探す、という発想になりやすいという特徴があるように思います。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
企業内ではどのような変化が起きているのか?
3年目に対する施策を打つ背景も、少し変化が生じています。
3年目への施策=離職防止という観点が強かったのですが、改めて以下のような観点もあって、位置づけが変わりつつあります。(※過去記事参照)
①人生100年時代の到来
→LIFE SHIFTの流行を発端に「長寿化の時代を生きる」ことへのニーズが高まっている
②日本全体の少子高齢化
→少子高齢化の時代、労働力確保のために定年延長や女性活躍推進に対応する必要が生まれている
③人的資本に関する開示義務
→②に関するデータや離職率データ等、企業としての取り組み状況を開示することが求められている
④メンバーシップ型→ジョブ型への移行
→ジョブ型へのシフトの動きと共に企業としてもジョブやタスク・スキルを定義しアサインする動きが生まれ、従業員も自らのジョブの再定義が求められている
⑤技術革新の加速・不安定化の時代における自律推進
→トップダウンでは時代の変化革新についていけないため、現場でも一人ひとりが自律的に変化成長し、イノベーションを生み出すことが求められている
⑥エンゲージメント向上施策
→エンゲージメント向上とキャリア自律には相関関係があるため、エンゲージメント向上施策の1つとしてキャリア支援が位置づけられている
⑦人材の流動化の加速/若手の労働観の変化
→転職が当たり前の時代になり、若手(次世代)の価値観も多様化してきているため、離職防止や若手の活性化のために必要となっている
代表的なものをいくつか掲げましたが、上記のような背景もあって、3年目に対してキャリア施策として研修を打ちたい、というニーズが高まっているようにも感じます。
特に「キャリア自律」という文脈で言えば
「自分で自分のキャリアや成長に向き合って欲しい」というメッセージが増えておりますが、これが若手にとっては却って混乱を招いており、
「選択肢が増えている(簡単に転職もできちゃう)からこそ、どうしたら良いか分からない、何者にならなければならない(キャリアが成功している、順調だと言いたい)ために、かえって焦る」という、自由さ故の呪い、が生じているように思います。
上記を踏まえると、どういったキャリア施策が有効なのか?
3年目の不安の変化、世代傾向や、企業のニーズの変化を踏まえると、一番のポイントは
「変化が激しい時代、一刻も早く不安なく働きたいが、結局は、何をもってキャリアが成功したと言えるのか定義ができない」という焦りが解消できるかどうか、ではないかと考えています。
それを踏まえますと、企業様の中での3年目研修やキャリア研修についても、変化を生み出すことが必要だと考えています。
昔の要素で言えば、例えば…
・3年間のキャリアの棚卸し→自己効力感の醸成
・willcanmustのフレームによる「ありたい姿」の言語化
・会社の期待や組織状況を踏まえた「やるべきことや能力成長」の言語化
・同期の関係性強化による離職防止
等々、たくさんのパターンがありましたが、多くの場合は終身雇用前提で長く働くための「ねじの巻き直し」だった訳です。
しかしながら、上記の変化を踏まえると、この内容だけでは解消しきれない部分があります。
「成長は分かったけれど、このままで良いのか」
「ありたい姿が見つからない、何となく形になったけどこれでいいのかな」
「石の上にも三年は待てない…早く自分は何者かにならなければ」
この辺りに対しての解消が求められると考えます。
研修設計においては以下のようなポイントが必要と考えています。
(⓪前提:上記のような新たなキャリア観が普通であり、焦る必要はないと腹落ちする)
- キャリアを中長期で描くのではなく、変化して良い前提で、未完成でも良いので短期で描く「短期型」
- 自分のキャリアが前に進んでいる手ごたえを獲得する「高頻度実践型」
それぞれについて、以下もう少し詳細に解説いたします。
①キャリアを中長期で描くのではなく、変化して良い前提で、未完成でも良いので短期で描く「短期型」
ひと昔前のキャリアと言えば、「自分がこの組織の中でどのようなポジションを描いていくのか」ですとか、「自分はどのような仕事将来に着いていきたいのか」といった分かりやすいポジションや仕事に関することを描いて、キャリアプランシートに10年先の方向性を描いて提出していくような形が一般的でした。
これらの大前提は「1つの企業に勤めあげる+終身雇用制が当たり前」の時代背景で生み出されていたものです。
しかしながら、タイパ世代にとって「じっくりと中長期でキャリアを描く」ことは焦りを生み出してしまうため、キャリアに対する誤解を解きほぐし「短期で、未完成でもいいから描いてもいいんだ」という考え方にアップデートすることが大事です。
②自分のキャリアが前に進んでいる手ごたえを獲得する「高頻度実践型」
特にキャリアのテーマとなると、日常に戻った場合は中々実践ができないことが多く、「結局、色々と考える機会にはなったけど、何も変わらないよね」となりがちです。
また、そのために停滞感を覚えてしまい、結果何かを変えようと転職するという選択肢が目に付くわけです。
そういう状態においては、1回の研修で終わり→日常に戻しても中々不安が解消されないため、大事になるのは「日常でキャリアを前に進んでいるかどうか」を実践し、振り返りながら「手ごたえを得ていく(心理的成功)こと」です。
終わりに
3年目の課題は今も昔も根っこでは近しい部分があるように思いますが、大きな違いは彼ら彼女らを取り巻く環境です。価値観も変わり、人材流動化も加速しているからこそ、3年目の研修の位置づけや目的、設計自体も改めて見直してみてはいかがでしょうか。
この辺りに関連して、高頻度実践型の研修モデルについて、下記リンク内の資料にもまとめておりますので、宜しければご参照ください。
また、もう少し詳しく事例を知りたいなどのご要望がございましたら、実際の研修デザインに関して、他社事例を交えての無料ディスカッションの場を設けておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
 庄司 幸平" width="104" height="104">
庄司 幸平" width="104" height="104">