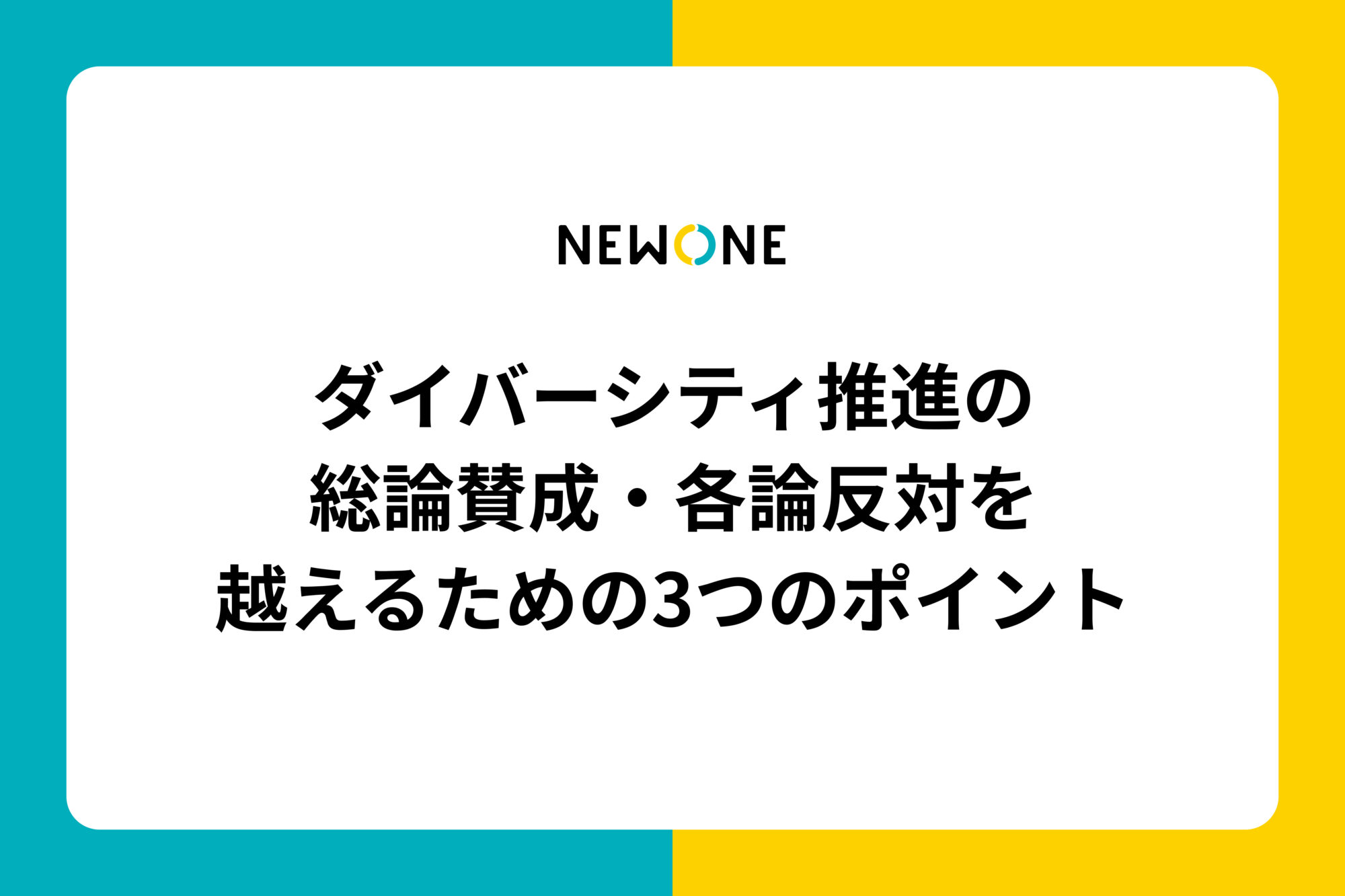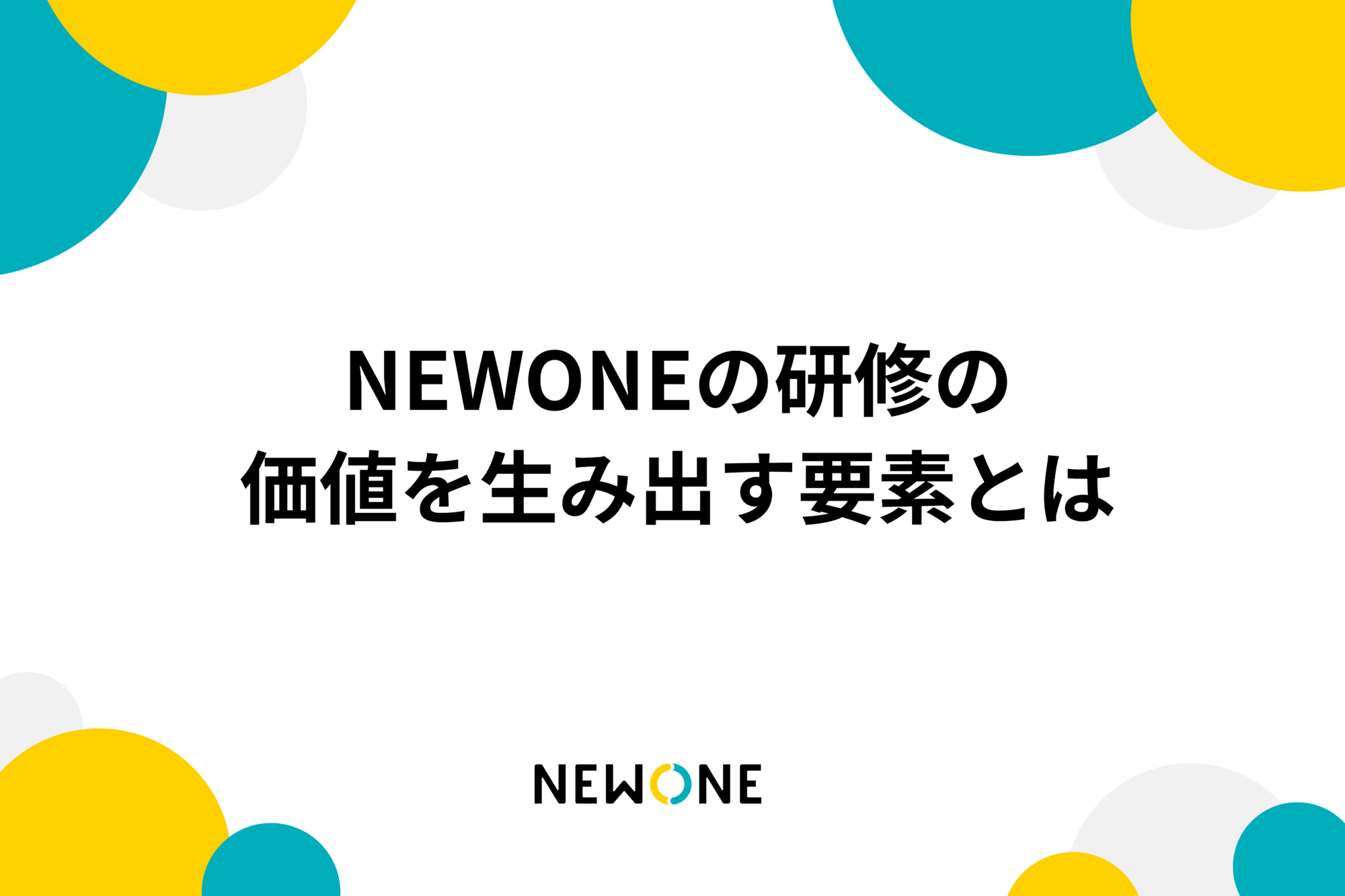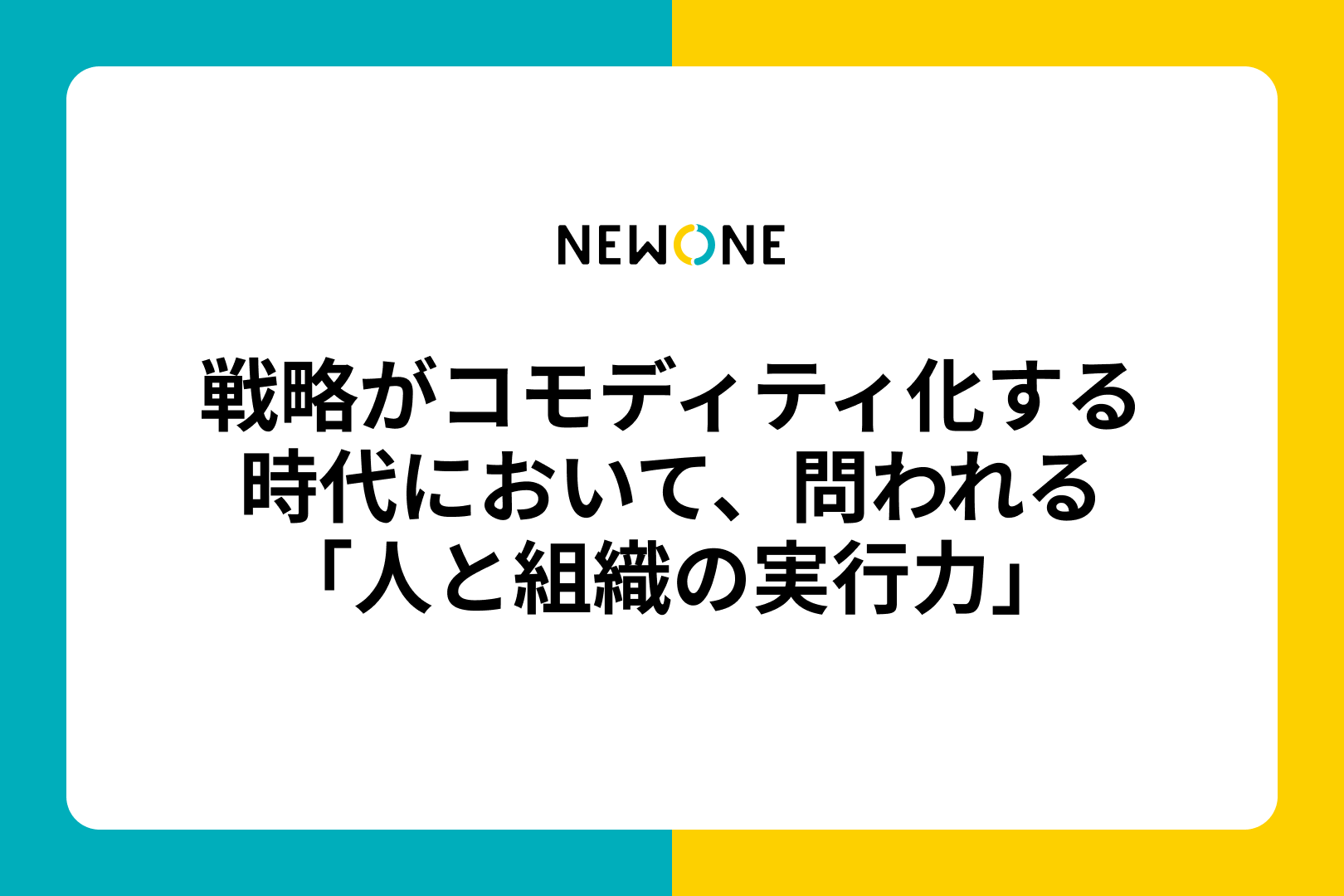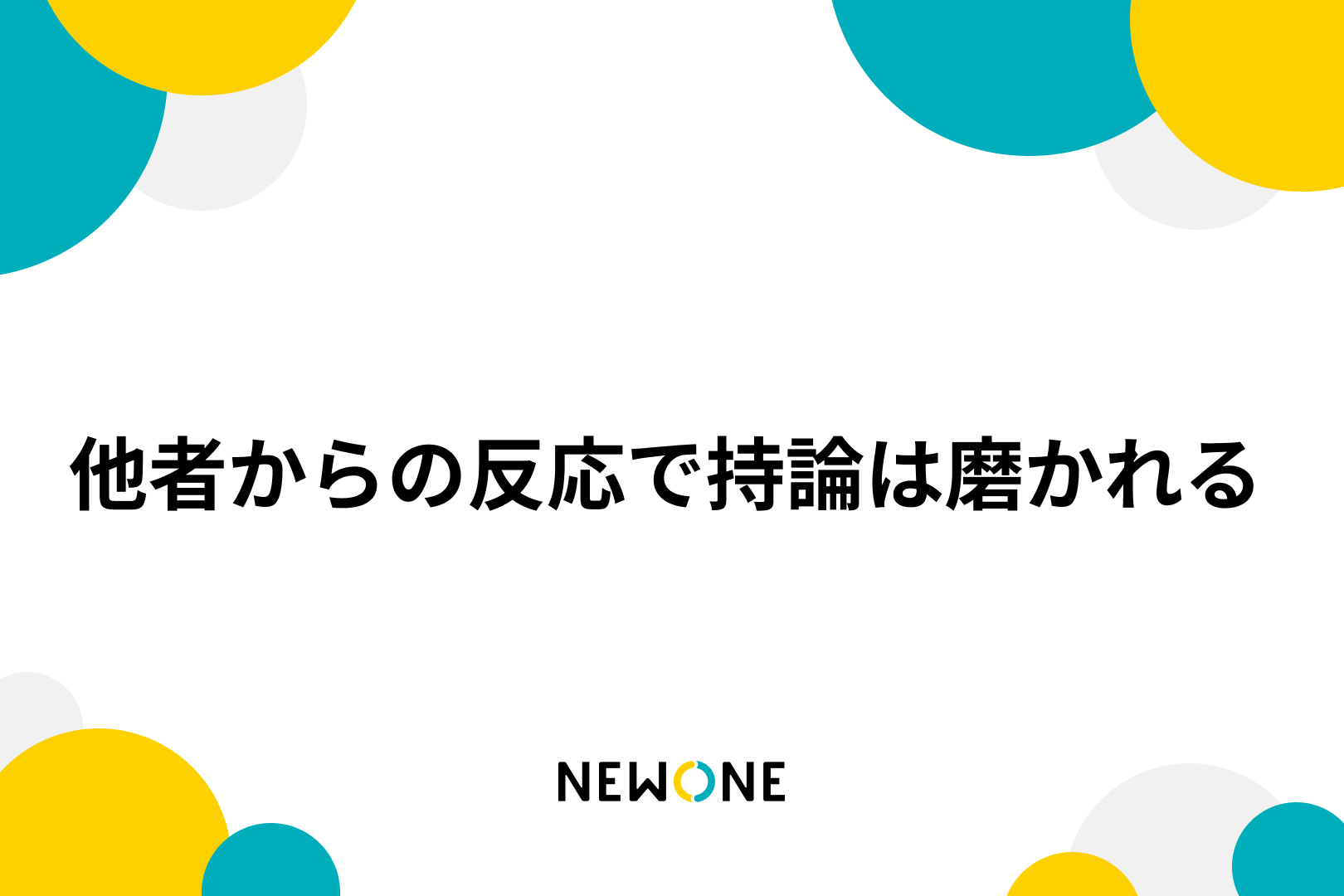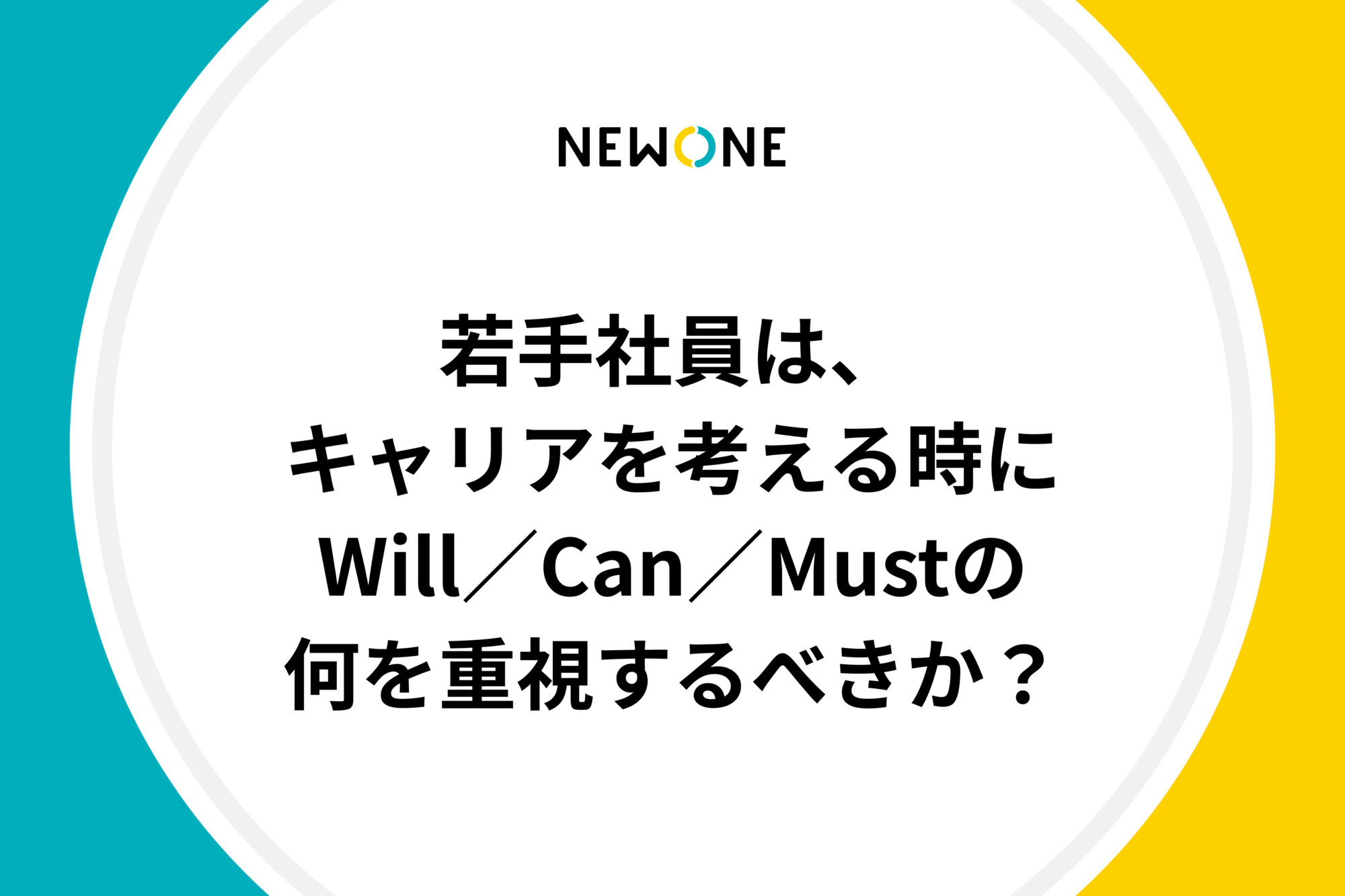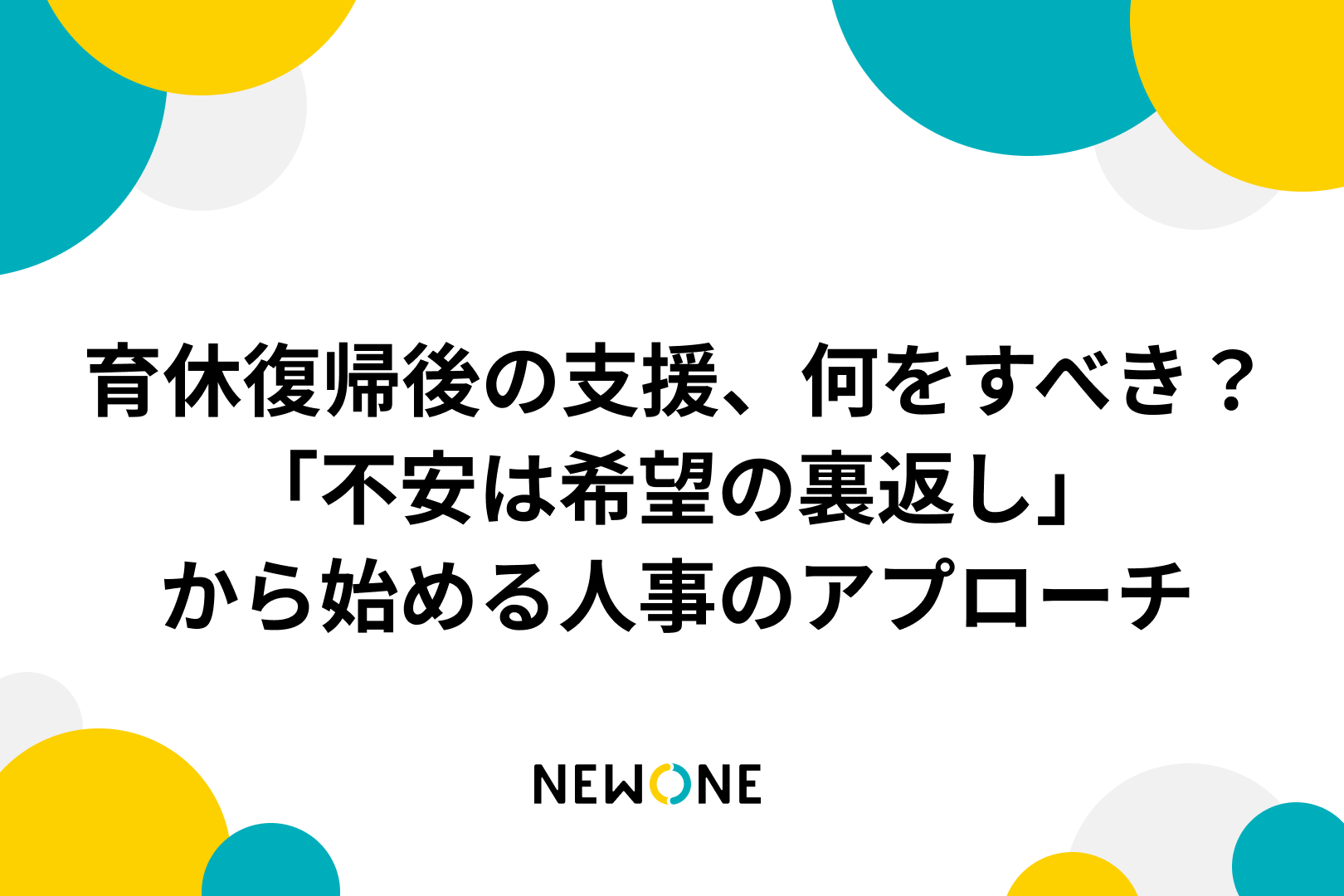
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
「育休復帰後、どう支援すればよいのかわからない」
「制度はあるけれど、復帰後の定着や活躍に課題がある」
人事担当者の中には、こんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
実は、育休復帰を控える社員が抱える不安はネガティブな感情ではありません。
それは、「また活躍したい」「仕事と育児を両立したい」という前向きな希望の裏返し。
この視点を持つことが、育休復帰支援の第一歩になります。
ここでは、人事として押さえておきたい育休復帰支援の3つのポイントを紹介します。
① 復職前面談で「不安の可視化」と「意欲の言語化」をサポート
育休明けの社員が安心して戻ってこられるかは、復職前面談の質に大きく左右されます。
制度や働き方の説明だけで終わらせず、「何が不安か?」「どんな形で働きたいか?」を一緒に言語化する時間を設けましょう。
上司任せにせず、人事も同席することで、「会社として支援している」という安心感を伝えることができます。
こうした対話は、復帰後のミスマッチを防ぎ、早期離職やモチベーション低下のリスクを下げる効果も期待できます。
② 育休復帰後の「段階的な業務設計」がカギ
復帰後すぐにフルパフォーマンスを期待するのではなく、助走期間を設けることが大切です。
たとえば復帰初期は、慣れている業務や裁量の小さいタスクからスタートし、段階的に負荷を上げていくようにしましょう。
週1回の振り返りミーティングや、業務内容のチューニングを可能にする柔軟な設計が、本人の安心感や自律性を高めます。
「急に任されすぎて不安」「何を求められているかわからない」といった声は、設計次第で減らすことができます。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
③ 「孤立させない仕組み」で定着と活躍を支援
育休復帰者が仕事を継続するうえで最も大きな壁は、「自分だけが特別扱いなのでは」という孤立感です。
そのため、社内でのロールモデルの紹介や、復職者同士のコミュニティ形成など、心理的安全性を高める場の提供が重要です。
先輩復帰者のリアルな声や体験談を社内報やイントラに掲載することで、「自分にもできるかも」と前向きな気持ちが芽生えます。
育休復帰支援は、人材活躍の起点になる
少子化や女性活躍推進が進むなかで、育休からのスムーズな復帰支援は企業にとって大きな投資価値を持ちます。
大切なのは、一律の制度ではなく、個々の不安や希望に寄り添う設計です。
「不安を言ってもいい」「自分らしく働ける形を考えてくれている」
そう思える環境があることで、社員は自信を持って再スタートを切ることができます。
人事が果たす役割は、戻れる職場を整えることだけでなく、戻りたいと思える職場をつくることです。
 三浦 琳斗" width="104" height="104">
三浦 琳斗" width="104" height="104">