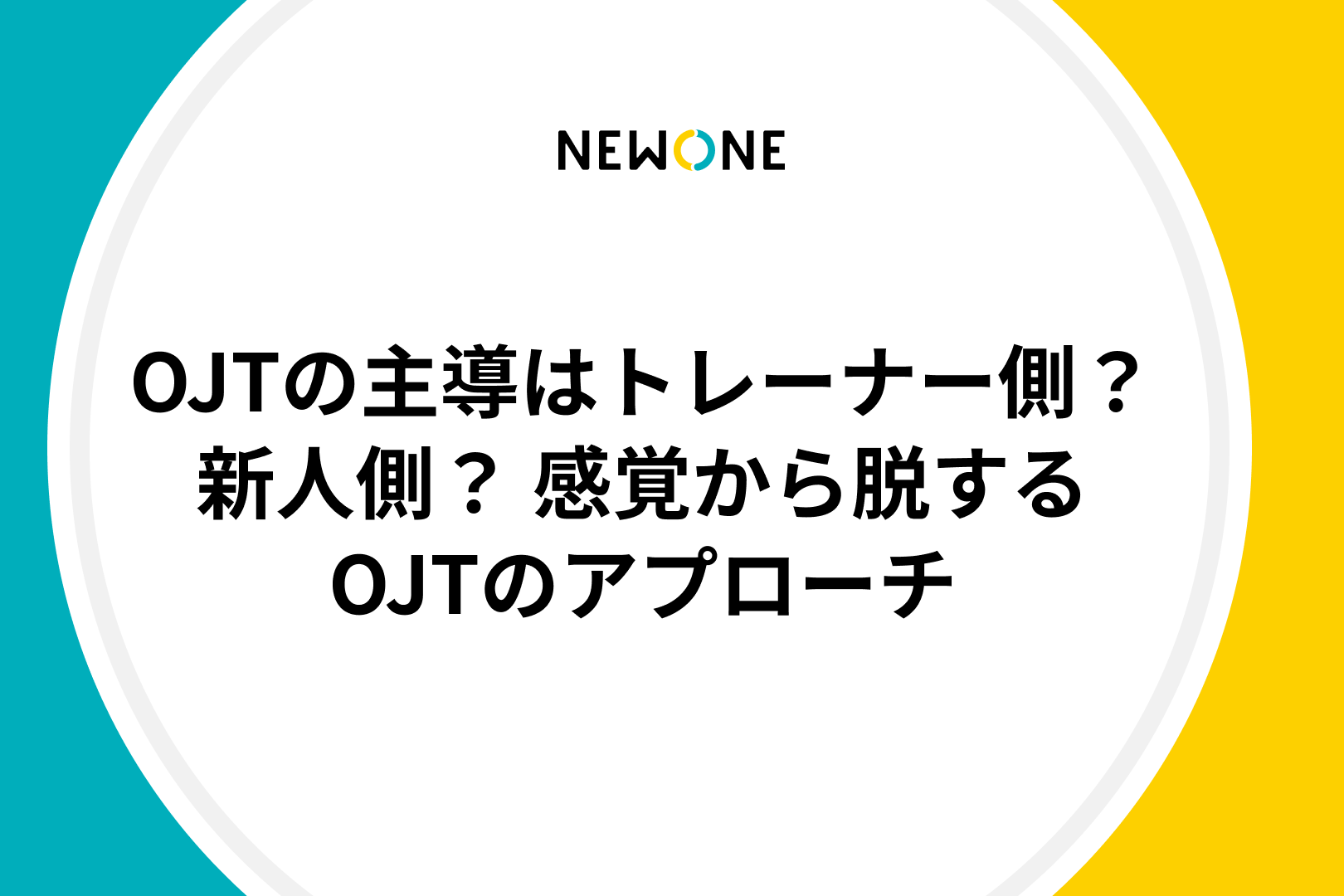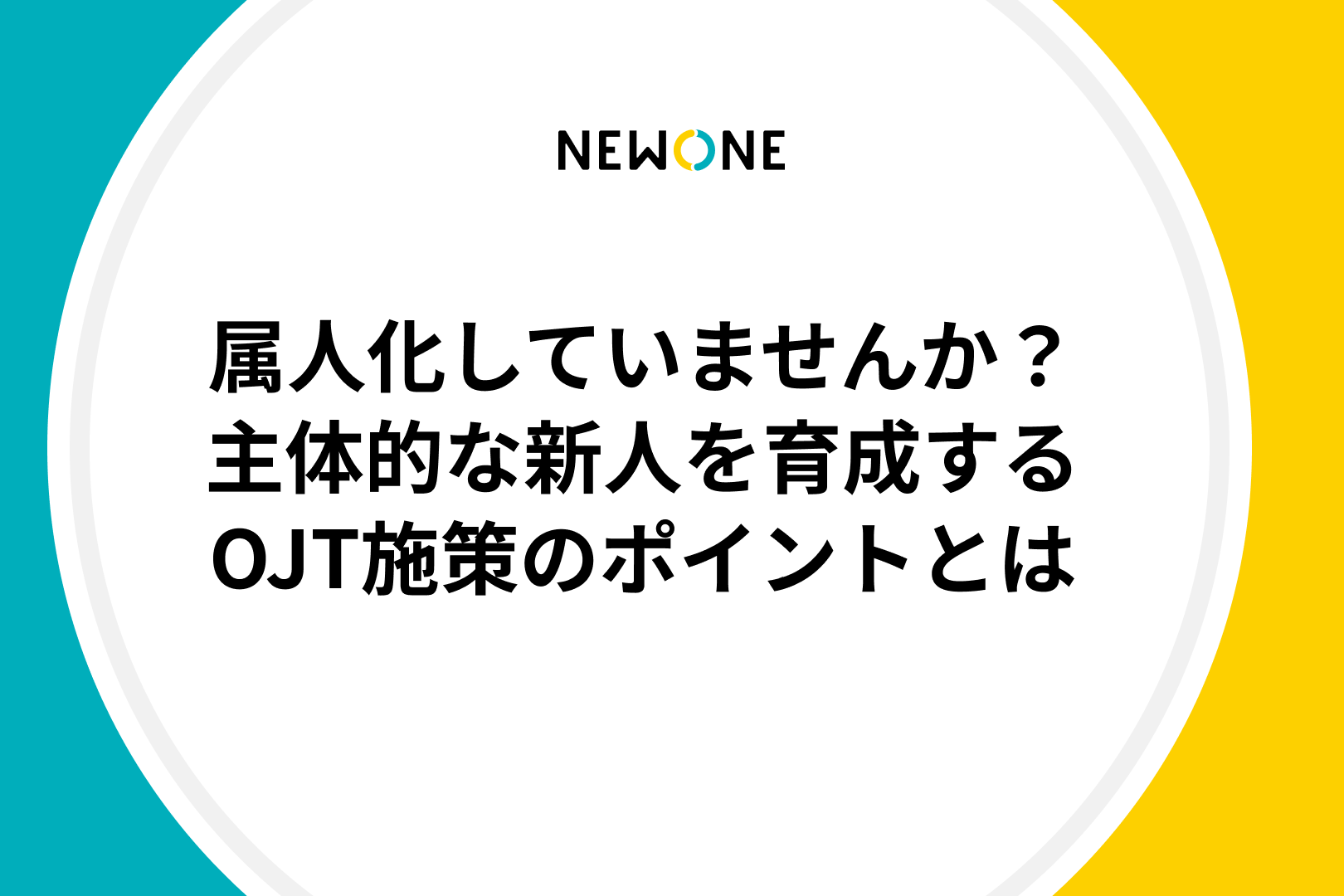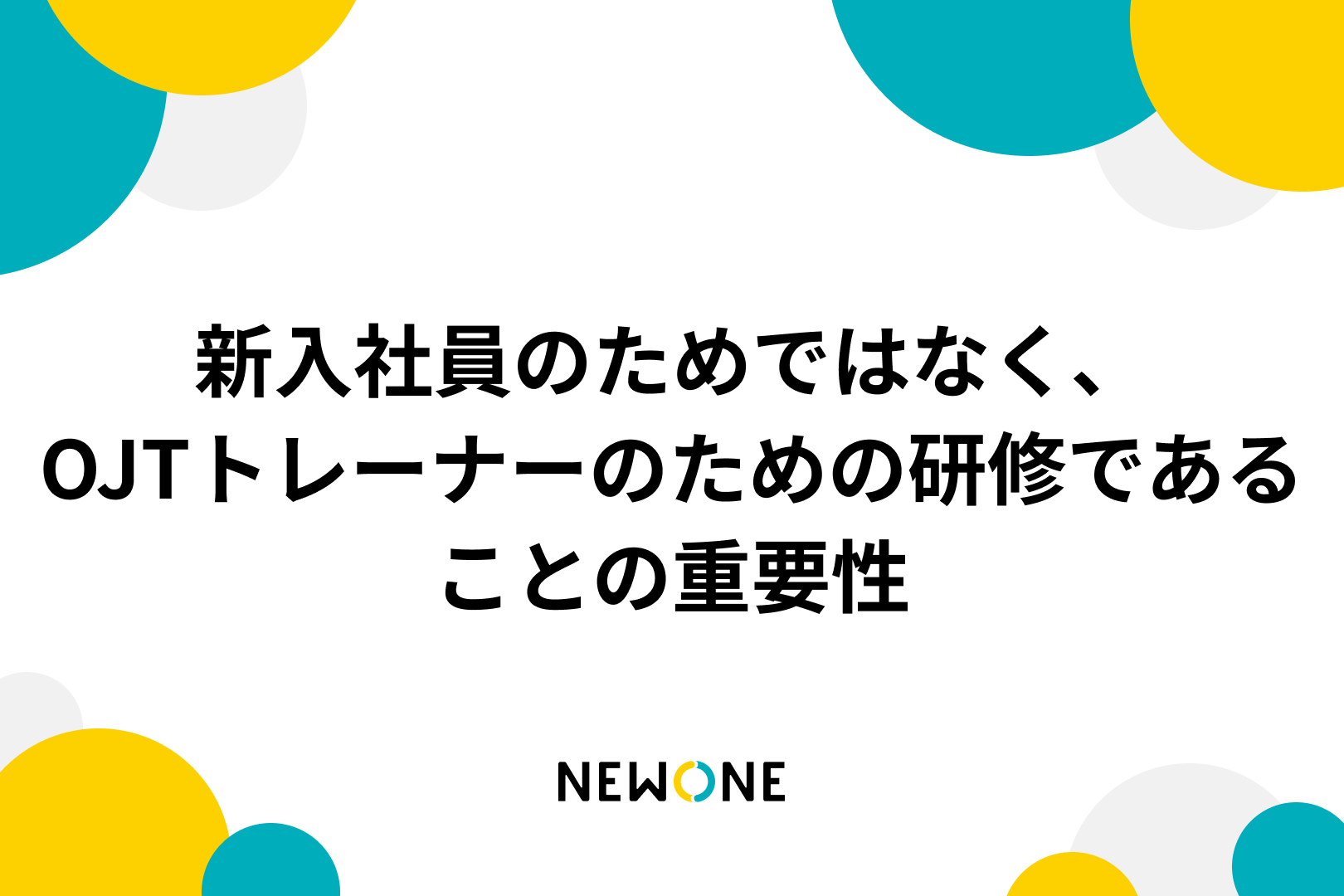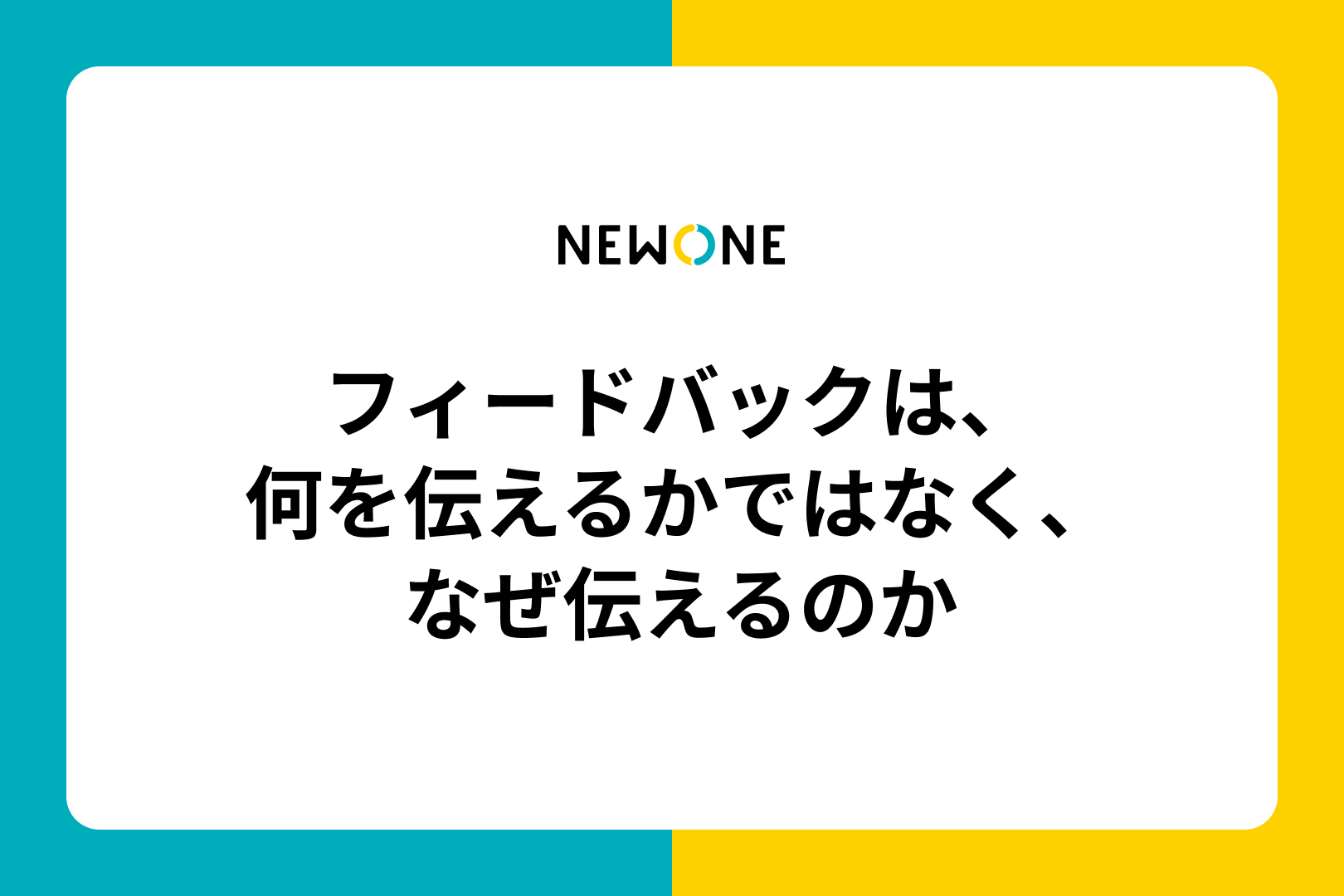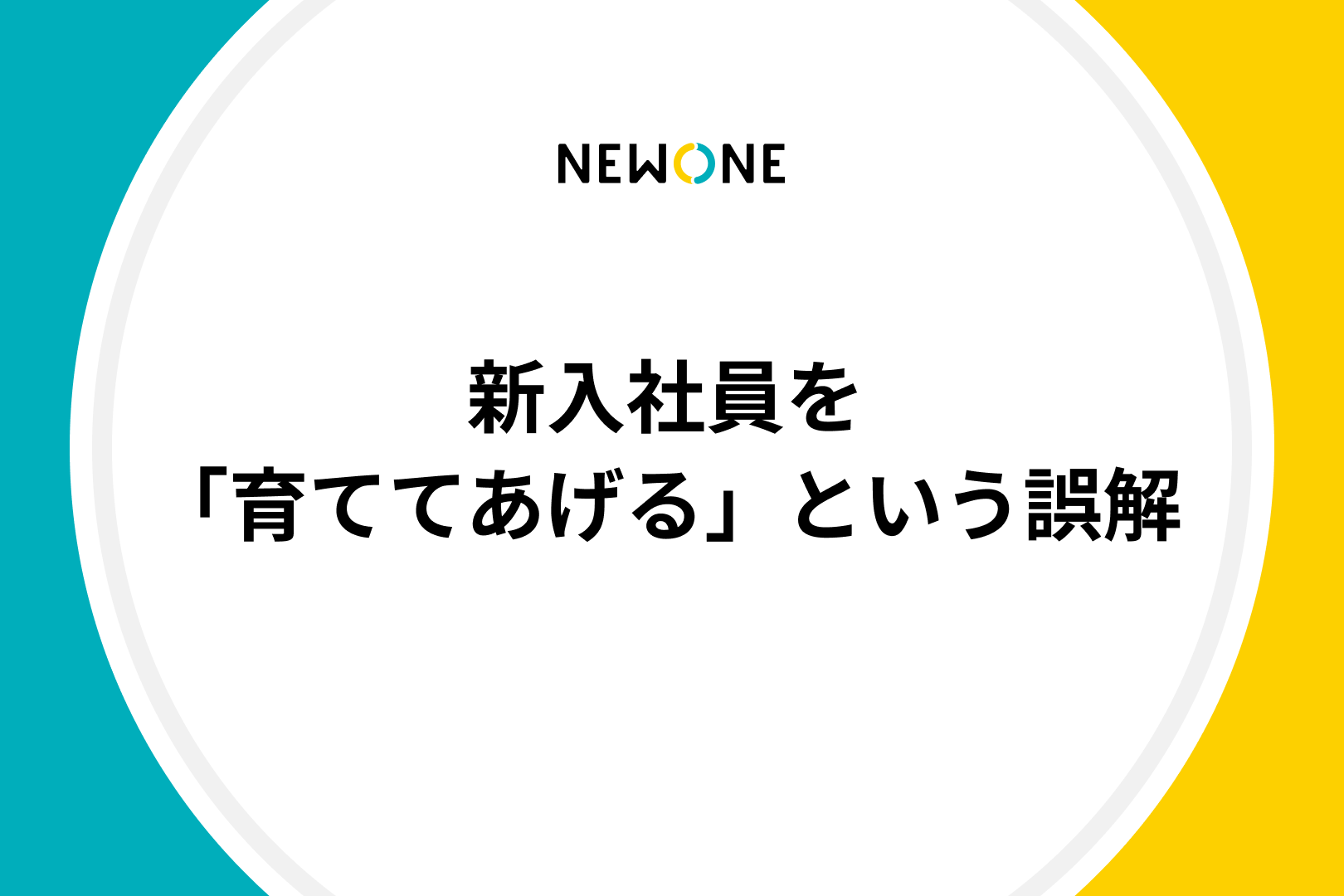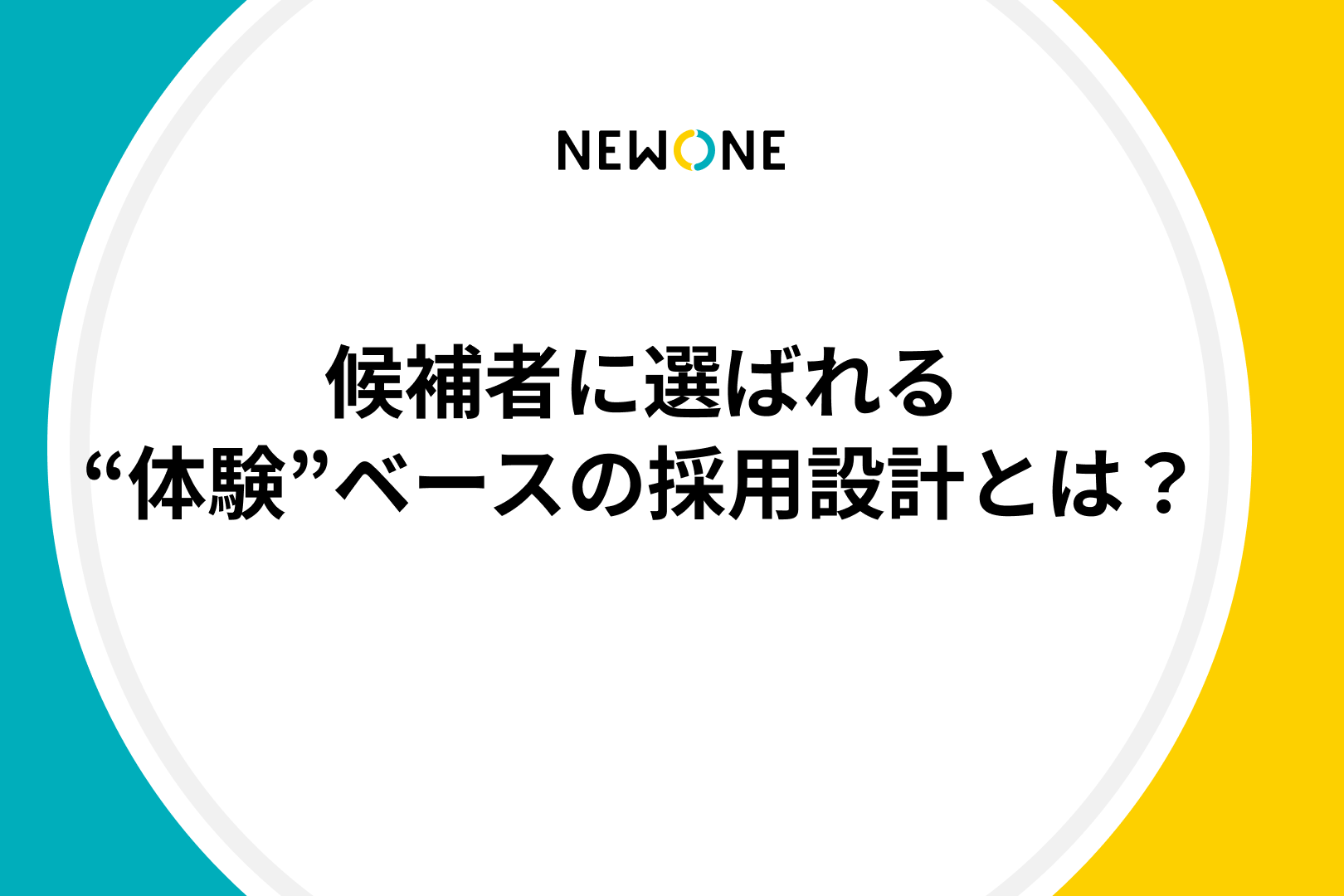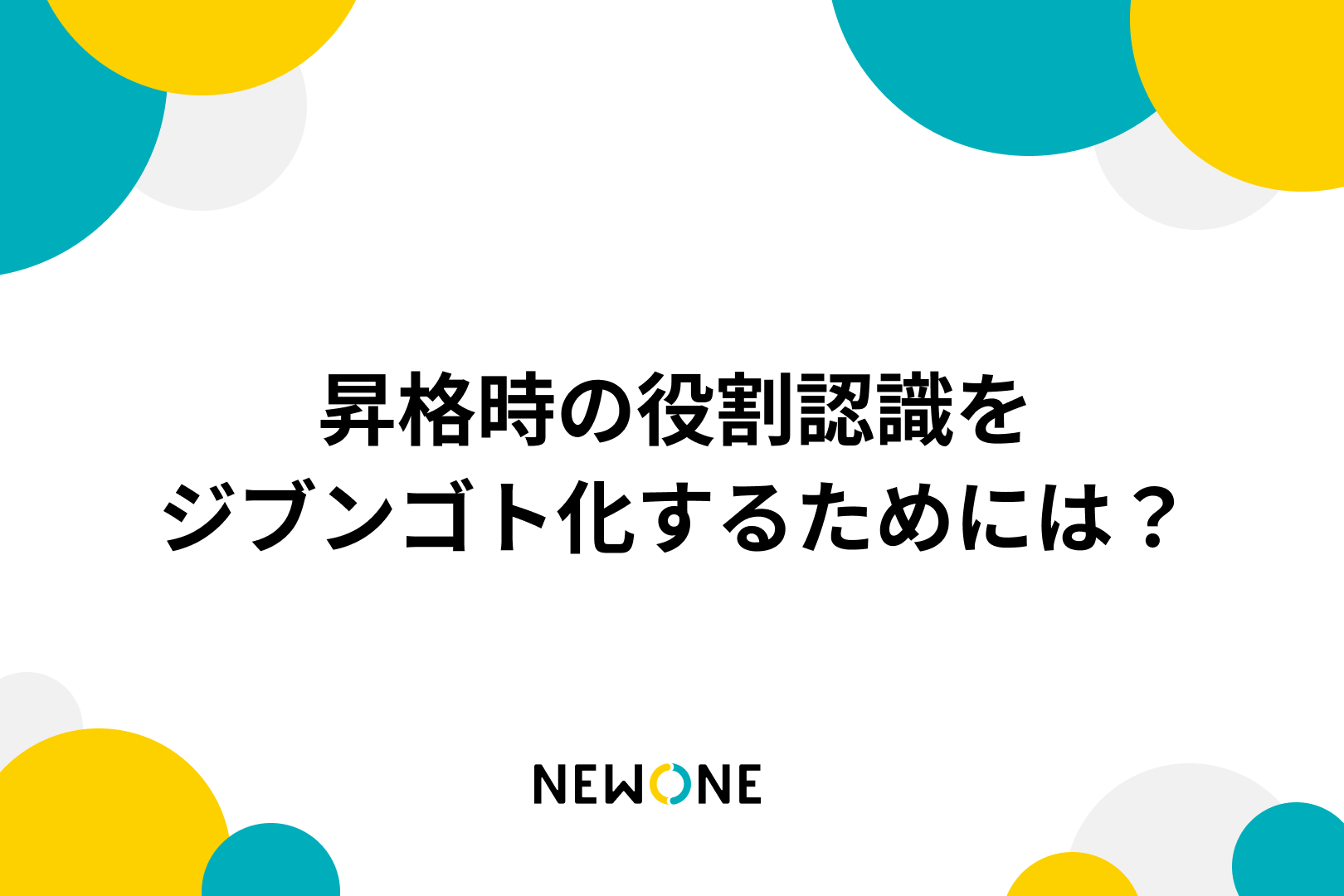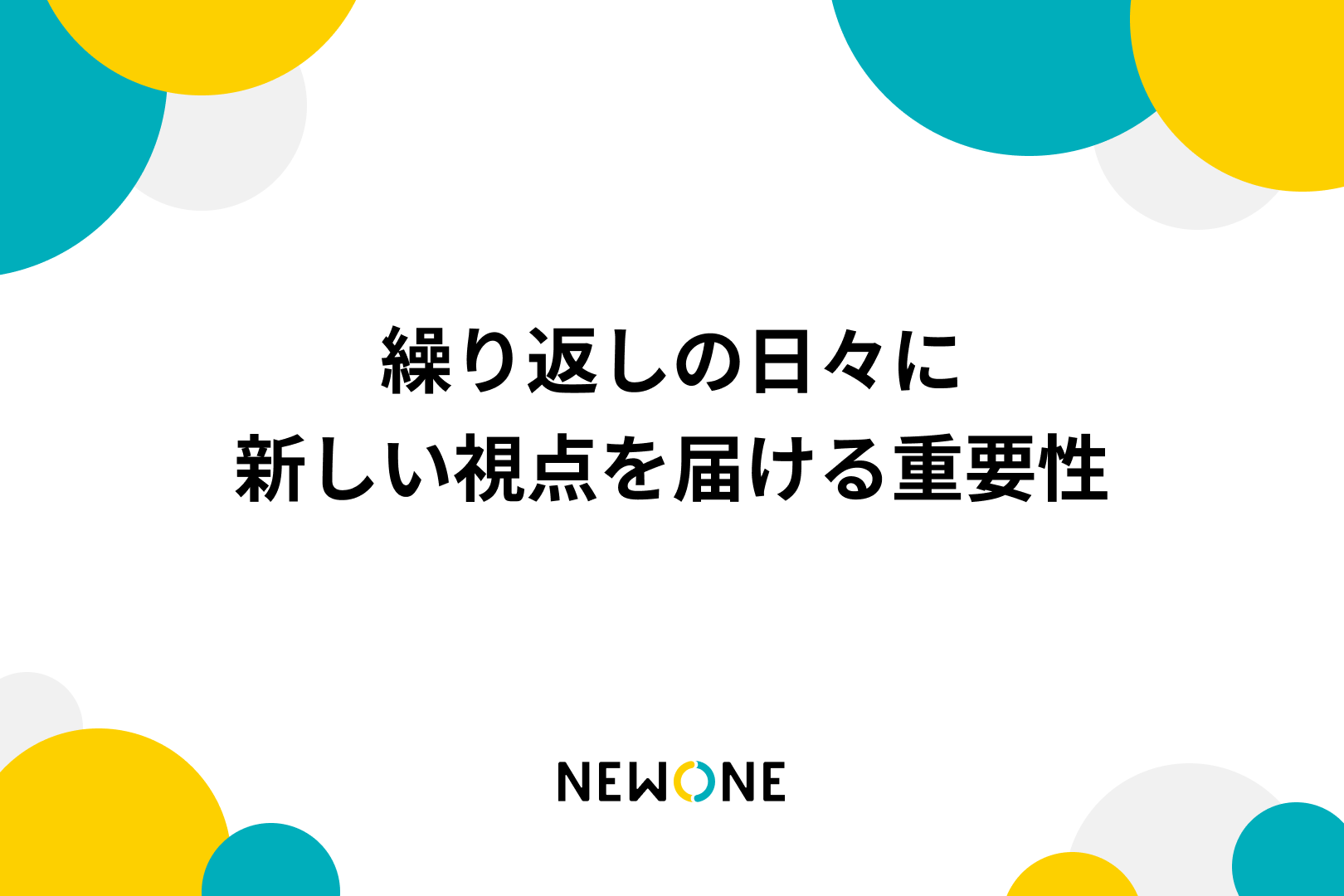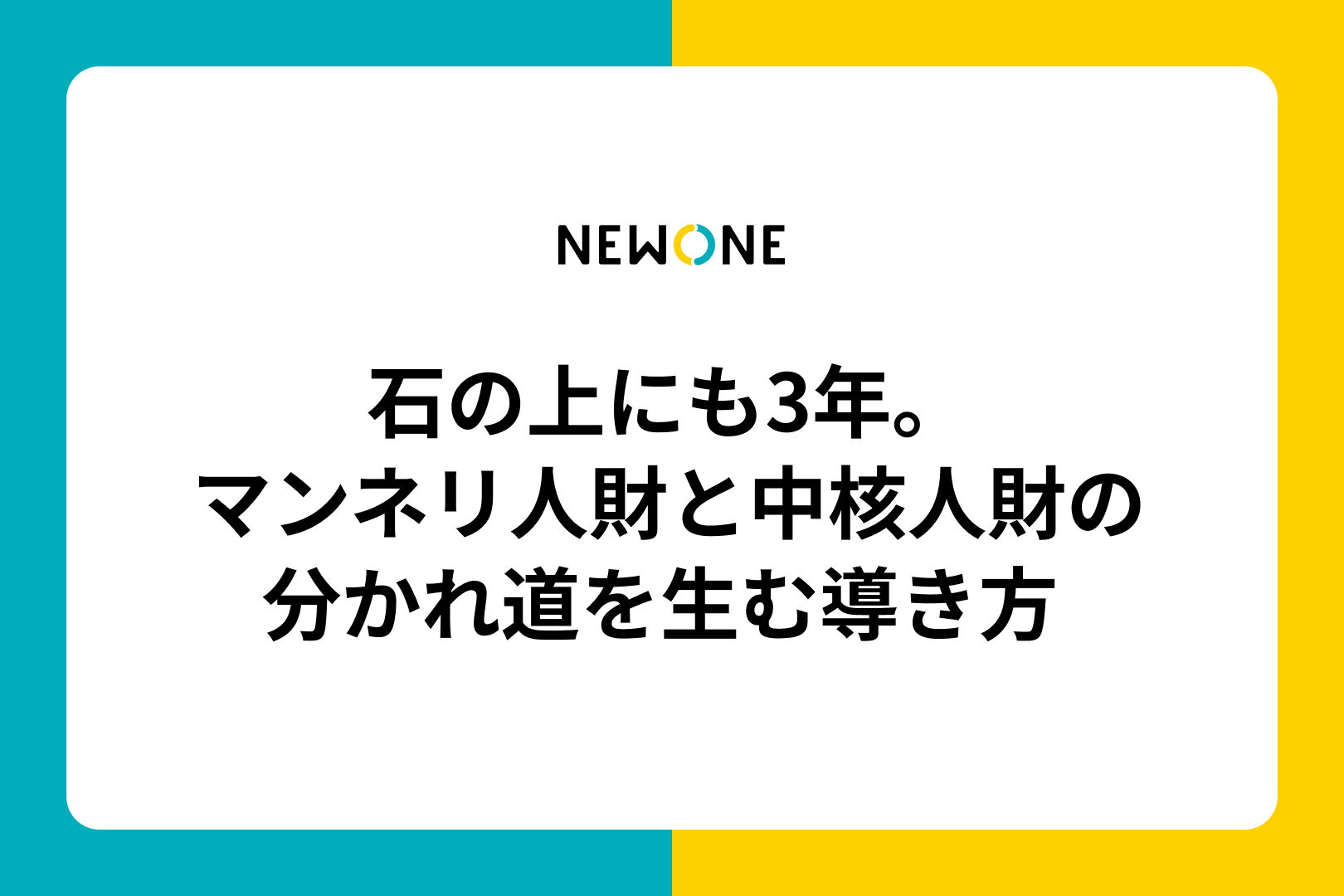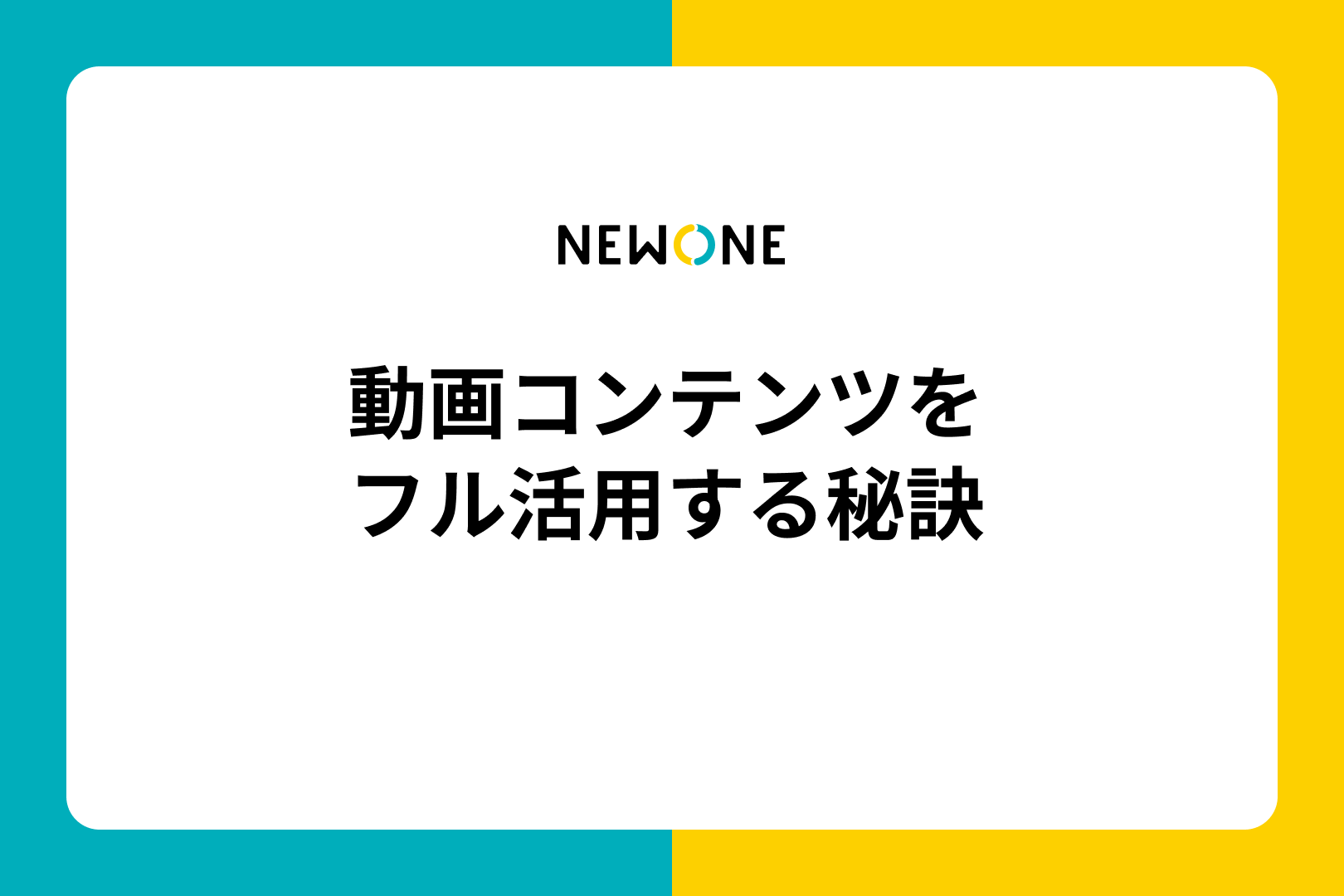NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
弊社では、4月の新入社員研修に呼応するように、育成担当者のトレーナーや所属長のマネジャーの方に、研修を行うことも多いです。
そういった多数のトレーナーやマネジャーと会うと、
組織の環境や働く価値観が変化する中で、新人にどのようにフィードバックをすれば良いかわからない、という悩みを持たれている方が非常に多いことが印象的でした。
そのような中で、研修などで発信したメッセージで、
トレーナーやマネジャーの方が共感していた点を中心に、イマドキの若手へのフィードバック方法について、大事な点をまとめていきたいと思います。
フィードバックは何のために行うのか
フィードバックとは何か?とChatGPTに確認すると、
フィードバックは、ある行動や作業の結果や進行状況に関する情報や意見を受け取ることを指します。
具体的には、他人やシステムからの評価やコメント、アドバイス、指示などが含まれます。
と返答があります。
指示やアドバイス等と書かれていますが、フィードバックはあくまで「手段」であって、
その「目的」は、フィードバックを受ける人の”パフォーマンスの向上”や”成長”にあります。
一方、最近の若者の傾向として、人材流動化が激しく、一社で一生安定という状況ではない中で、
“成長”を求める人が多くなっていると言われます。
成長を求める若手社員と、成長を目的として行うフィードバック。
本来的には、良い関係になるはずですが、そのためにはどういったポイントを押さえるべきでしょうか。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
イマドキの若手へのフィードバックのポイント
成長を求めるイマドキの若手に対するフィードバックのポイントとして、
研修等でトレーナーやマネジャーの共感が高かった点から3つ述べたいと思います。
① フィードバックとは目指す姿と現状のギャップを伝えること
現状だけを見て、”できている””できていない”を指摘すると、否定された気分や評価される気分になり、成長への前向きな気持ちが下がってしまいます。
フィードバックは、現状だけを見て伝えるのではなく、
本人も納得している”目指したい姿”を伝えた上で、現状との間にギャップがある点を伝え、どのようにしたら”目指したい姿”に近づくかまで伝えたり、問いかけたりすることが大事です。
そうすることで、受け身的な気分ではなく、成長の道筋が見えて受け取りやすくなります。
② 伝えるときはand moreを活用する
“最近の若者は、3回褒めて、1回指摘するくらいがちょうどよい”という声もよく聞かれます。
正解がわからない初めての環境で、できていることも伝えた上で、指摘をするのは重要です。
その通りなのですが、一方で、褒めた後に指摘をする際に、Butで展開されることがあります。
〇〇さんは、こういう点がより良くなったね、でも(しかし)、△△な点はもっと改善すると良いよね
という形です。
このButの文体を使うと、前段の褒めている点も前座のように聞こえ、承認している効果が薄れ、結果的に前に進んでいく気持ちが持ちづらいです。
Butではなく、and moreで伝える。
〇〇さんは、こういう点がより良くなったね、それをこれからも活かし、さらに良くなるためには、△△な点はもっと改善すると良いよね
このand moreのニュアンスが、成長課題を前向きにとらえるポイントになります。
③ 日頃から対話等で信頼関係構築を行う
フィードバックは突き詰めていくと、誰から言われるかが大事です。
信頼している人から言われると前向きになりますが、信頼関係ができていないと言い方を工夫しても効果が得にくいものです。
そうなると、日常でいかに信頼関係を築くことができるかが大事です。
信頼関係の築き方としては様々ありますが、
例えば、接待や会食などでは、ビジネスとは違う環境下でコミュニケーションし、意外な一面や背景になる想いを知ることで、ぐっと距離が縮まったり、関係性が強化されたりします。
概念化すると、
・今まで見えていなかった背景等を知る
・その上で、互いに知ったことを尊重しあう
こういったプロセスが大事です。
会食等はなかなかできない中で、1on1などでいかに違いを知り合う”対話”を行うかが大事なポイントです。
成長を加速するフィードバックが定着化につながる
一社で生涯を過ごす前提ではない現代において、将来への安心感のために成長は大事です。
だからこそ、成長実感と成長期待を得るフィードバックこそが、
エンゲージメント向上という観点でも非常に重要です。
こういった時代だからこそ、
新入社員にかかわる人たちのフィードバックレベルを高めてみるのはいかがでしょうか。

■プロフィール
上林 周平(kambayashi shuhei)
大阪大学人間科学部卒業。
アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)に入社。
官公庁向けのBPRコンサルティング、独立行政法人の民営化戦略立案、大規模システム開発・導入プロジェクトなどに従事。
2002年、株式会社シェイク入社。企業研修事業の立ち上げを実施。その後、商品開発責任者として、新入社員〜管理職までの研修プログラム開発に従事。
2003年より、新入社員〜経営層に対するファシリテーターや人事・組織面のコンサルティングを実施。
2015年より、株式会社シェイク代表取締役に就任。前年含め3年連続過去最高売上・最高益を達成。
2016年、若手からのリーダーシップを研究するLeadership Readiness Lab設立し、代表に就任。
2017年9月、これからの働き方をリードすることを目的に、エンゲージメントを高める支援を行う株式会社NEWONEを設立。
米国CCE.Inc.認定 キャリアカウンセラー
【書籍出版情報】
2022年7月に、弊社代表上林が「人的資本の活かしかた 組織を変えるリーダーの教科書」を出版しました。
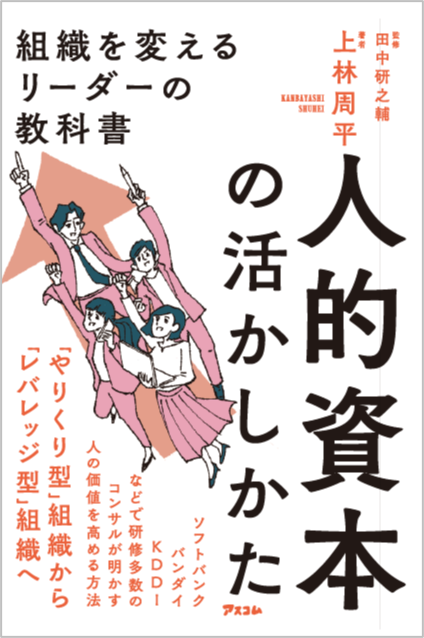
 上林 周平" width="104" height="104">
上林 周平" width="104" height="104">