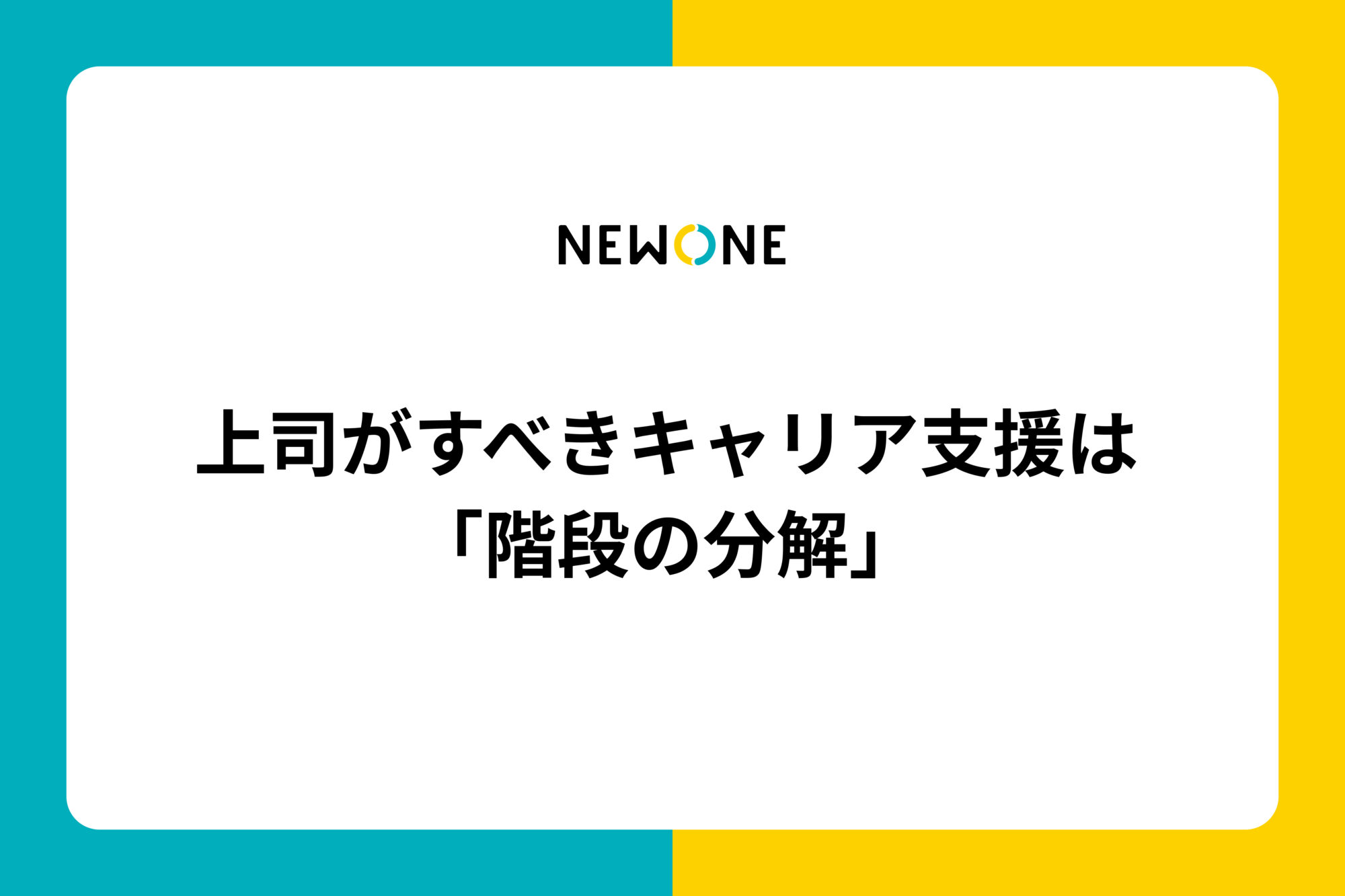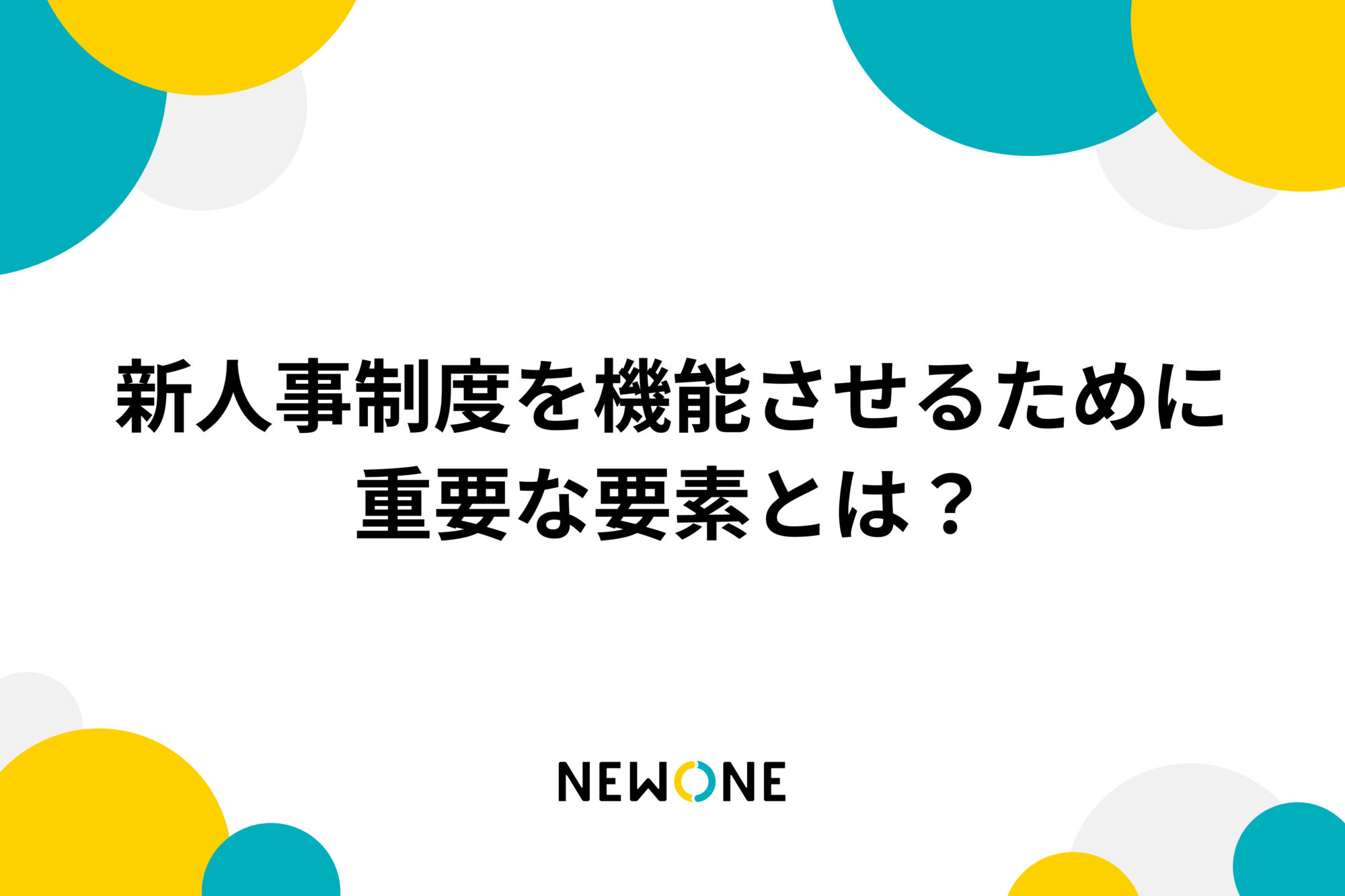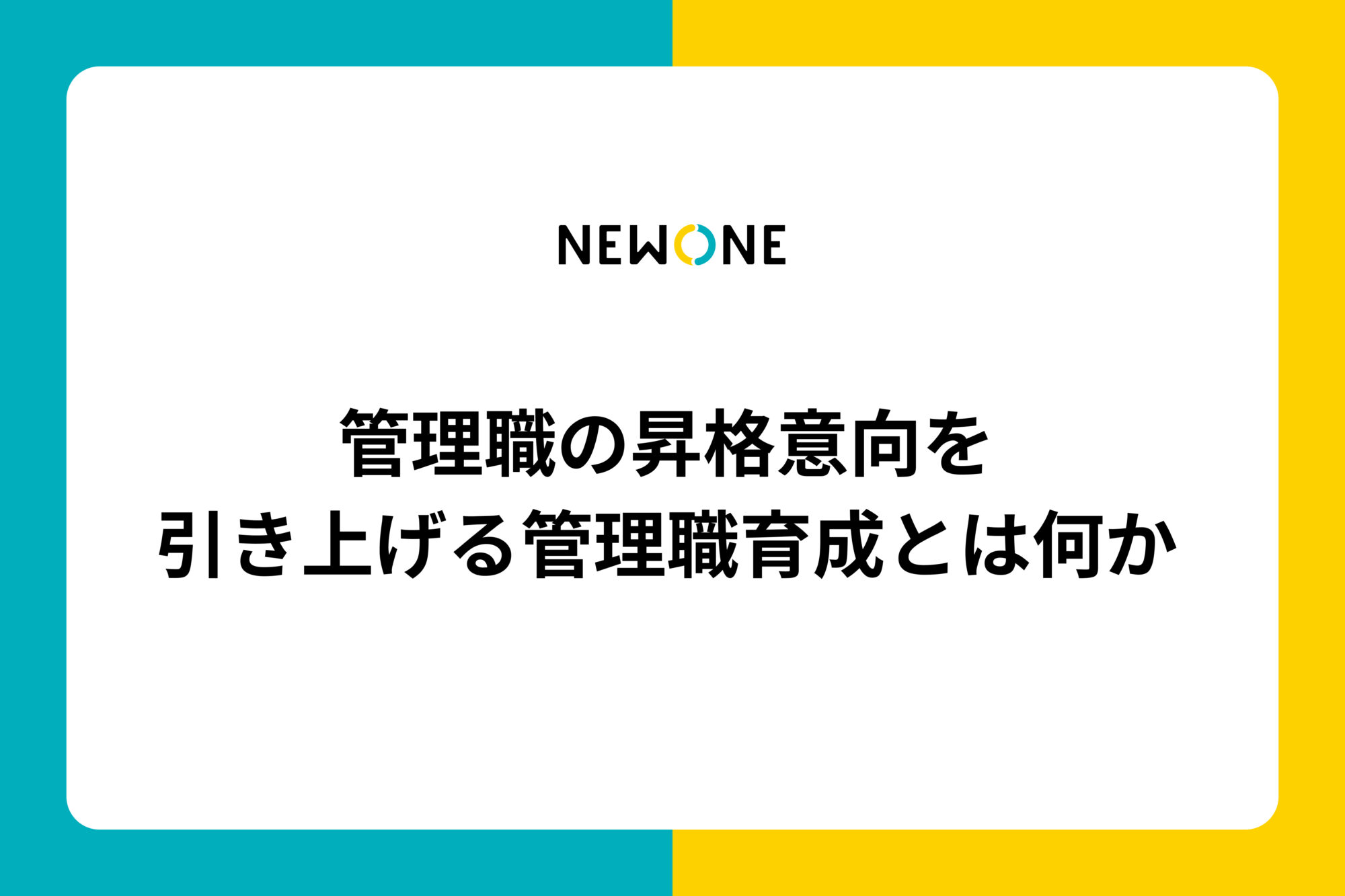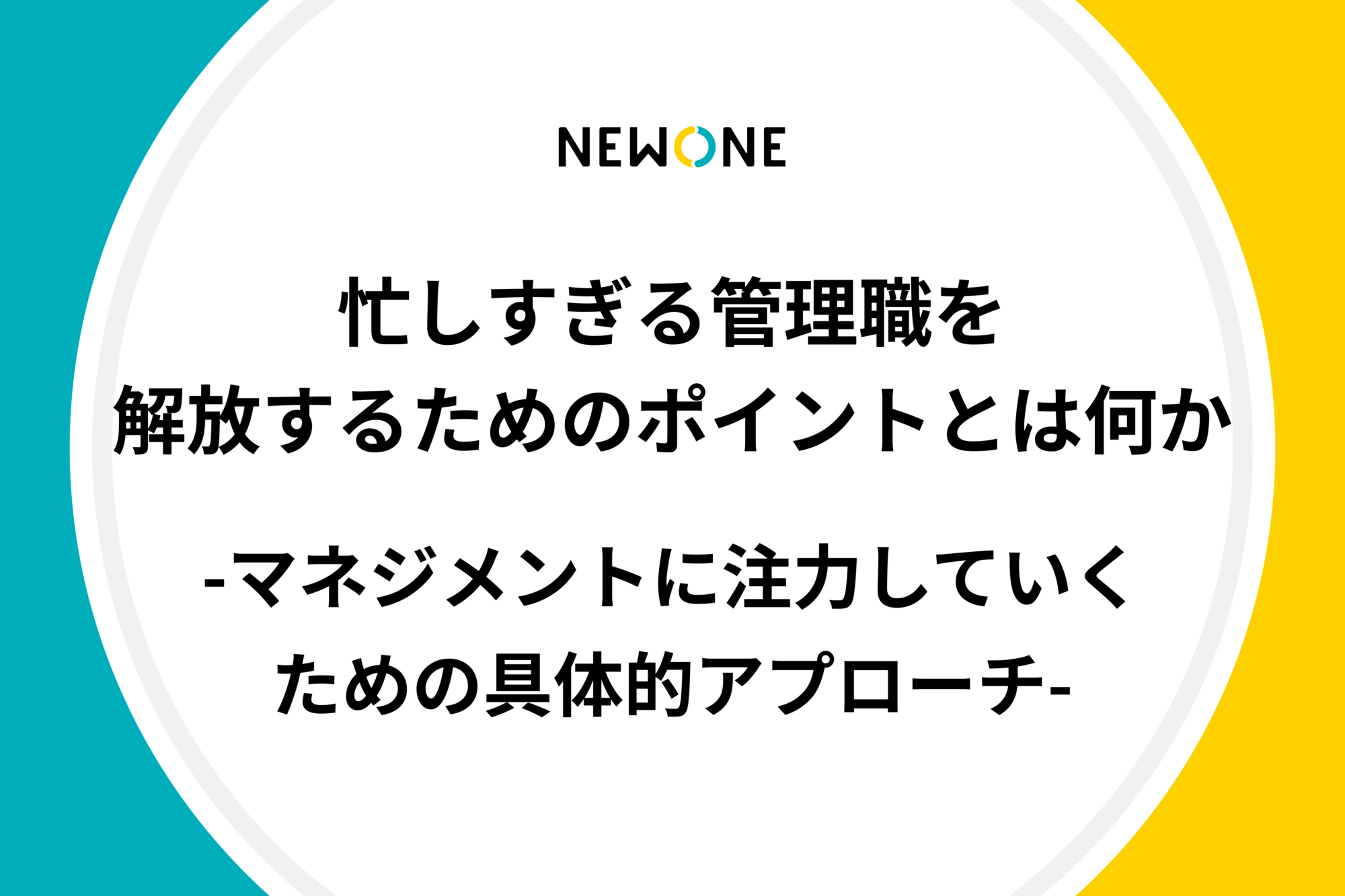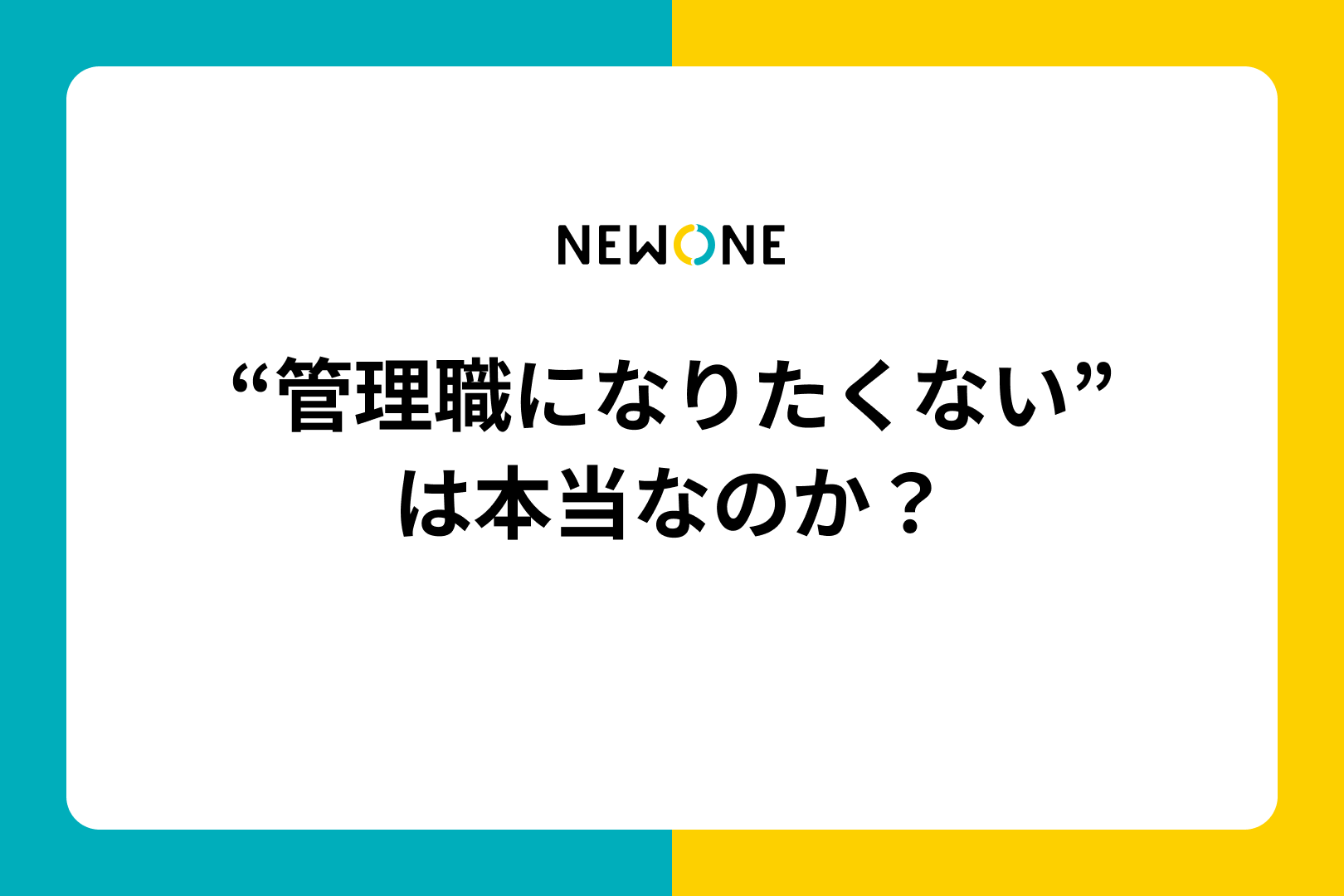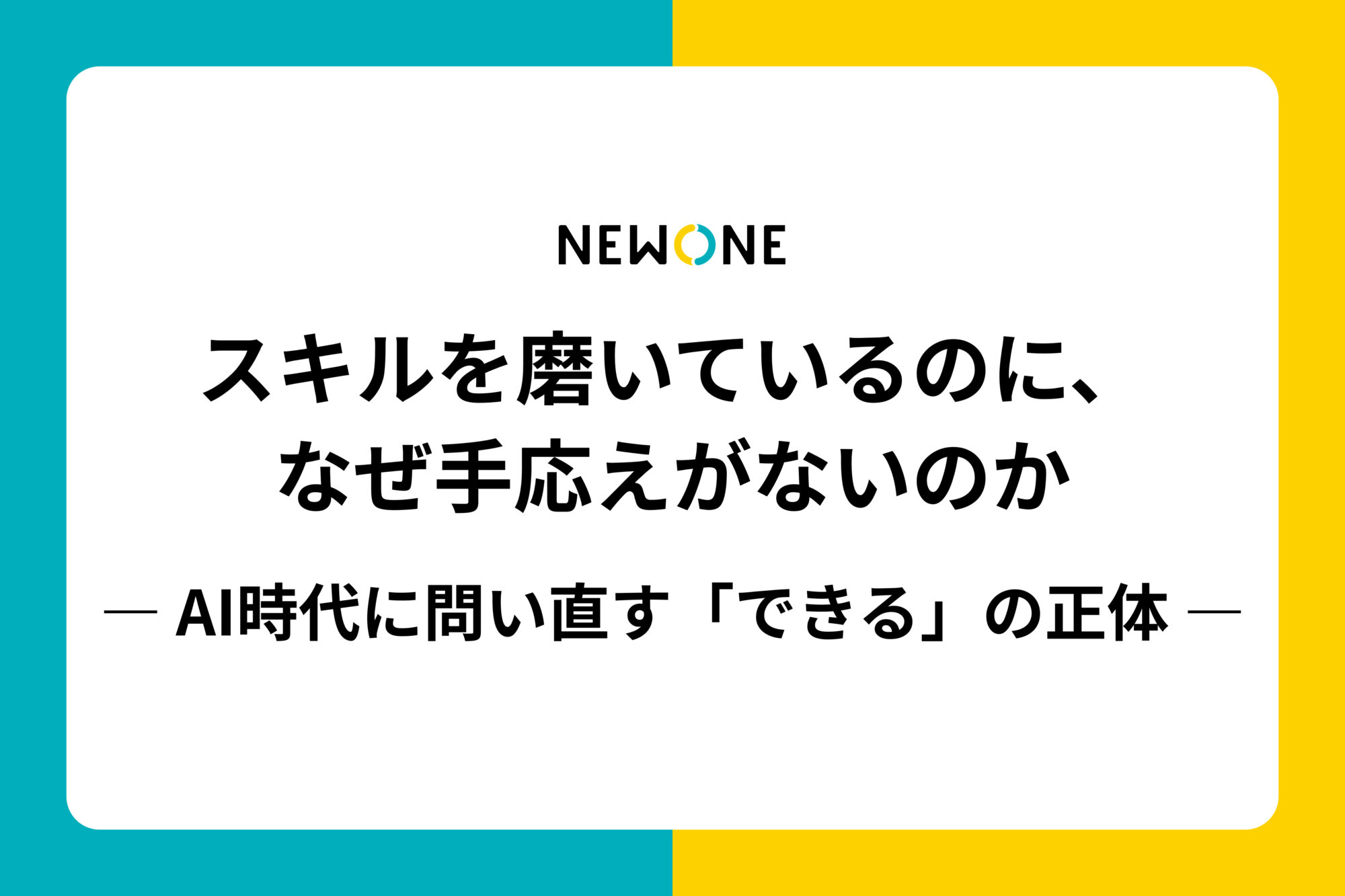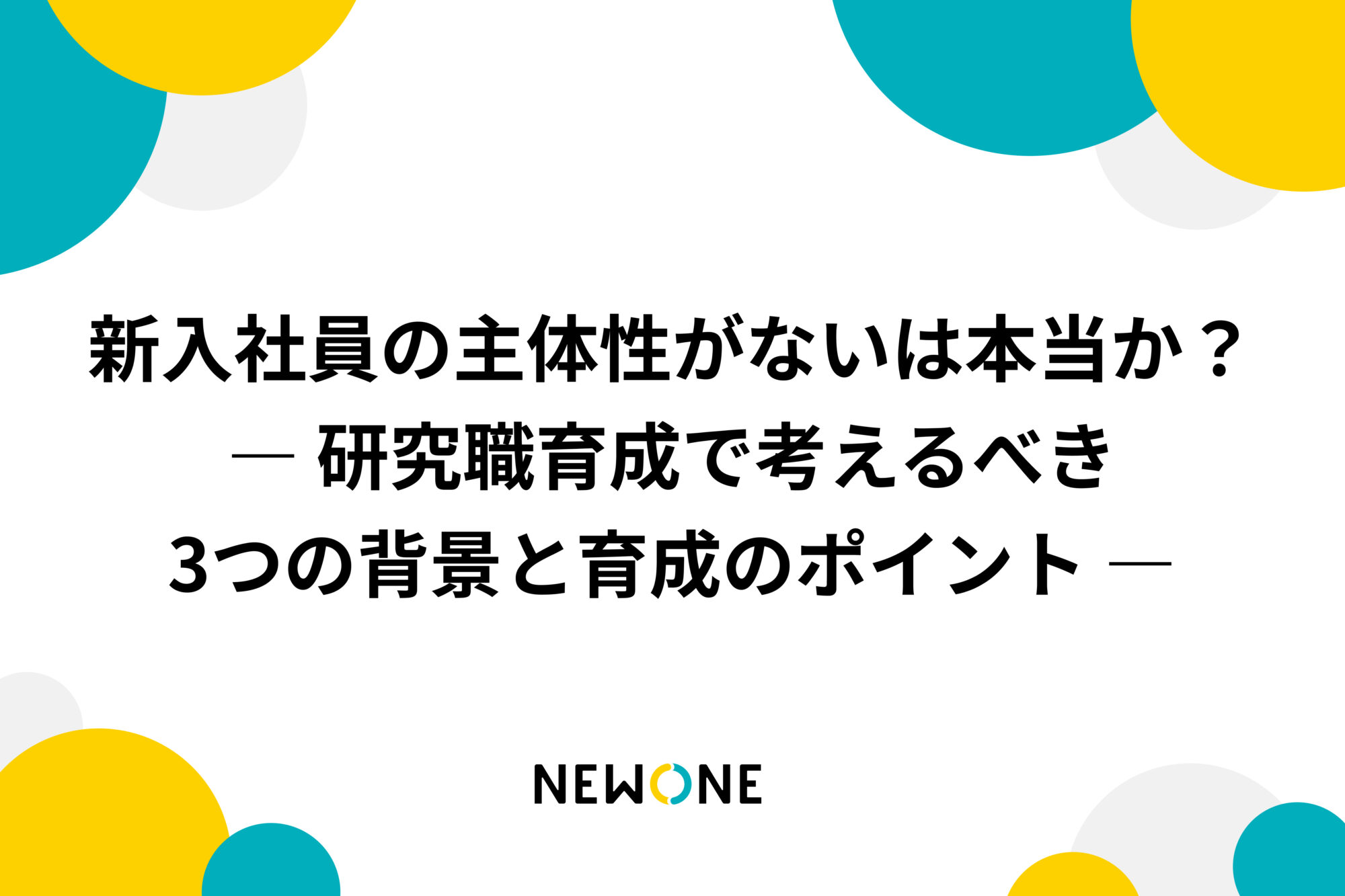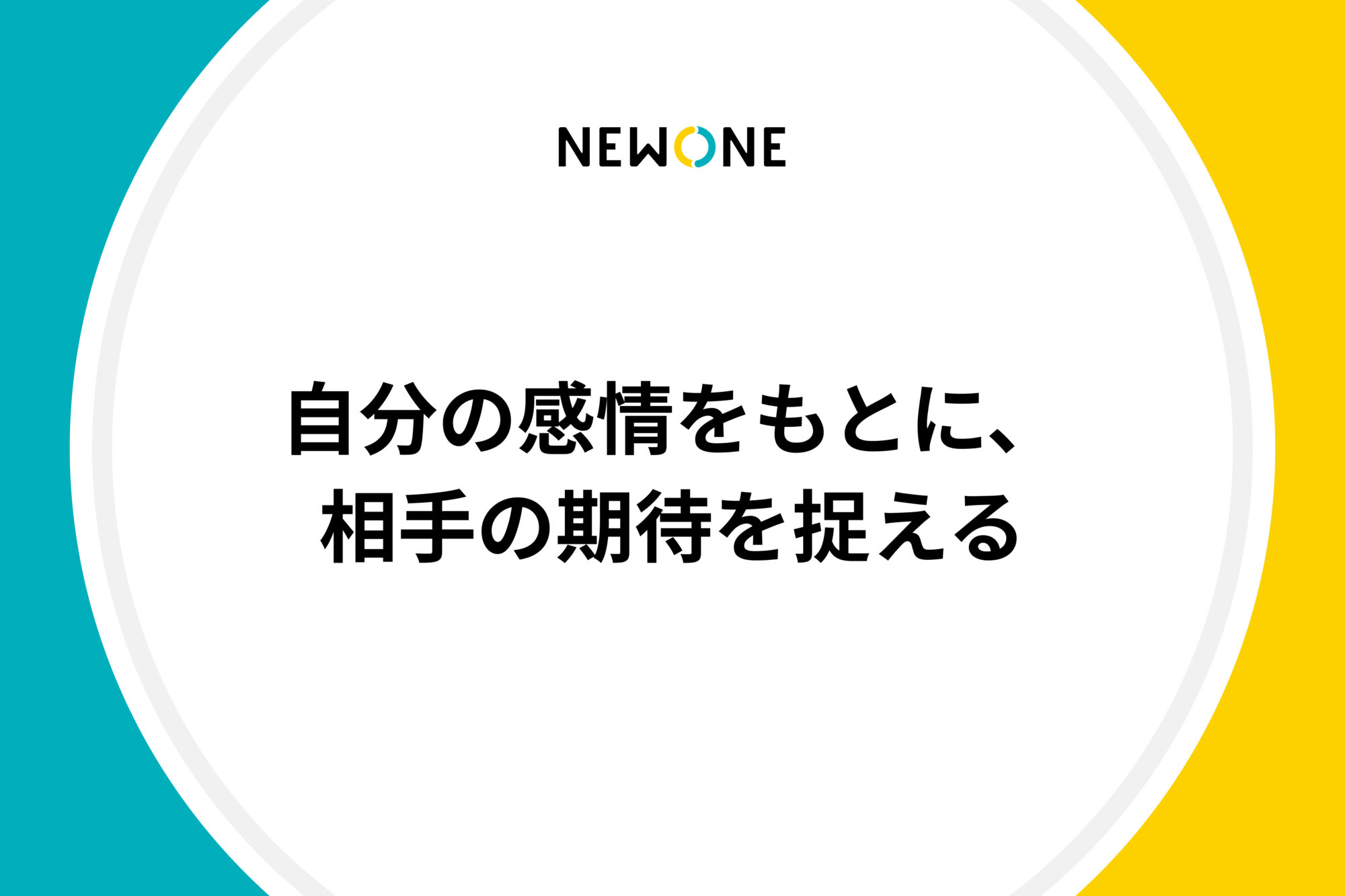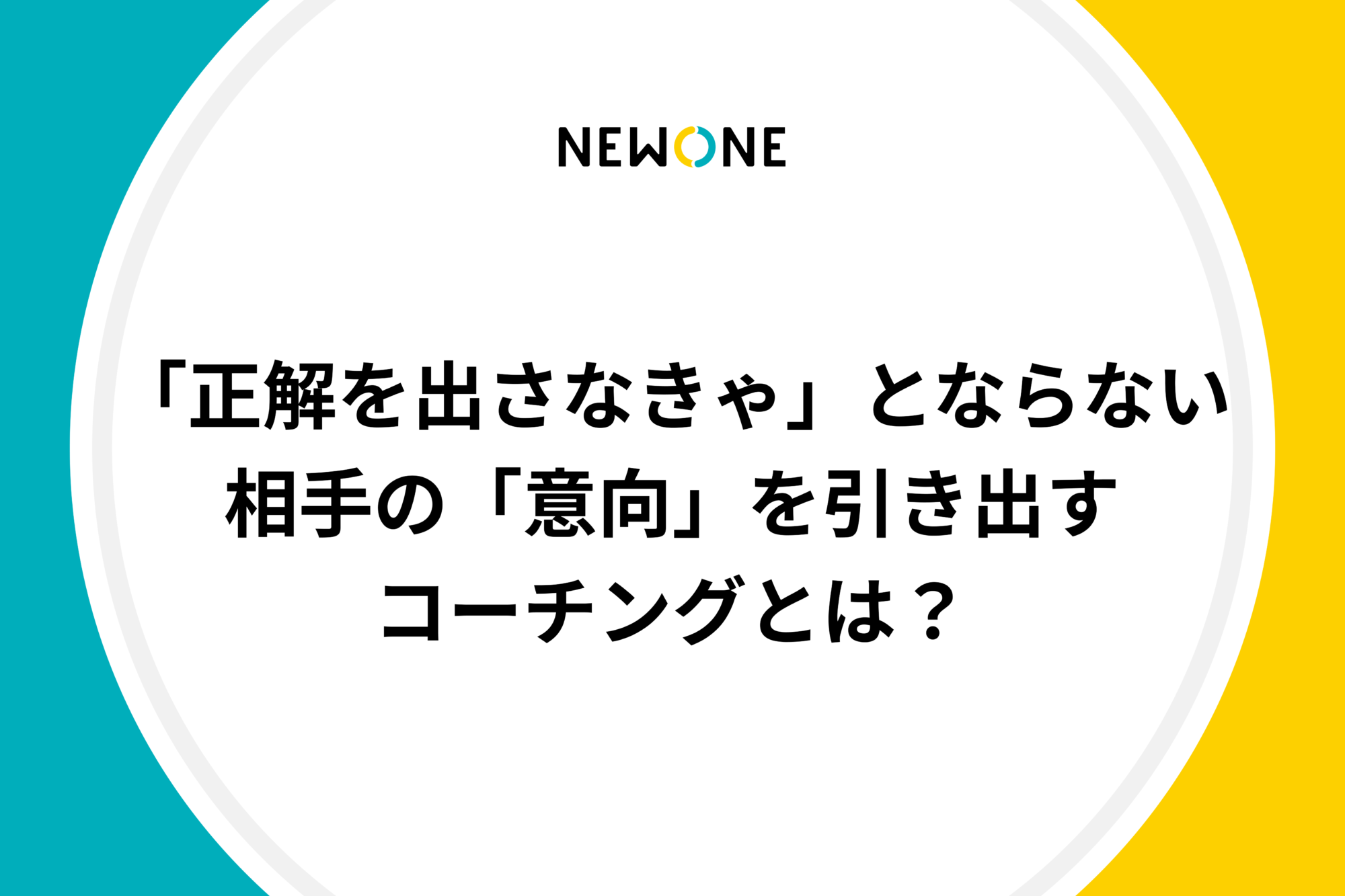
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
最近、マネージメントスキルの一環として、「コーチング」をテーマとした研修が多く実施されています。
コーチングがテーマの研修では、「ティーチングとコーチングの違い」や「部下への具体的なかかわり方」を中心に扱いますが、その中でもいざ実践してみると陥りやすい、1つの大きな落とし穴があります。
それは、「正解を出すことを暗に示唆する問いかけ」です。
皆さんももしかしたら心あたりがあるかもしれませんが、相手の意見を聞こうと意識しているものの、気づいたら自身の期待する答えが出るまで問いかけてしまったり、本人の考えより正解だと思う回答へ誘導しているケースは、かなり多く見られます。
ここで一つ、上司と部下のやり取りを見てみましょう。
<会話例>
上司: このプロジェクト、どう進めるのがいいと思う?
部下: そうですね、まずはチーム内で課題を整理して…
上司: うんうん、でもそれだとスピード感が足りないよね。ほら、A社みたいに先にスケジュールを固めた方が効率的じゃない?
部下: あ、そうですね…。では、スケジュールを先に決めて進めます。
上司: そうそう、その方がいい。やっぱり自分で考えてもらうのが大事だよね。
普段の業務の中で、このようなやり取りをしていませんか?
一見「質問をして、部下に考えさせている」ように見えますが、
実際は上司が自分の中の正解に誘導している状態です。
上司の視点から見ると、すぐに答えを提示するのではなく、一度部下に考えさせる工程を意識していることは伝わりますが、部下の視点から見ると「自分の考えを言ってもどうせ否定される」と感じ、次第に自発的に考える意欲を失いかねないやり取りに感じてしまいます。
結果として、このような「擬似的な主体性」は、部下の意向や価値観を無視している状態となり、部下の「考える力」や「自己効力感(自分にもできるという感覚)」が育たず、エンゲージメントを下げる原因にも繋がります。
とはいっても、この落とし穴は、意識していても陥ってしまいがちなものであるため
、ここで、上司も部下にとっても事故らないコーチングのポイントを、以下の3点に分けてご紹介いたします。
- 質問の目的を「答えを導く」から「考えを引き出す」に変える
- 沈黙を恐れず、相手の思考が生まれる時間を待つ
- 結論よりも、考えるプロセスを承認する
質問の目的を「答えを導く」から「考えを引き出す」に変える
まず1つ目の「質問の目的を『答えを導く』から『考えを引き出す』に変える」についてです。
これは質問のレベルを意識することで、上手くできるようになります。
たとえば、「あの案件の進捗は?」という事実確認レベル(レベル1)にとどまらず、「なぜそう思う?」「どんなときにやりがいを感じる?」といった思考・価値観レベル(レベル2・3)に踏み込むことで、相手の内面を理解しやすくなります。
価値観やビジョンといった、相手の“氷山の下”にある部分を引き出すことが、信頼関係の深化につながります。
沈黙を恐れず、相手の思考が生まれる時間を待つ
次に、2つ目の「沈黙を恐れず、相手の思考が生まれる時間を待つ」についてです。
コーチングを用いて、部下の意向を聞き出そうとしても、普段からあまり自身の価値観やビジョンについて考える機会が無いことで、意向がなかなか出てこない場合もあると思います。
このような場合は、沈黙を恐れず「待つ」姿勢が大切であり、場合によっては面談の場を改めて設定することも有効です。
また、普段から雑談や小さな対話を積み重ね、本人の思考の「種」を育てておくことが、1on1の質を高める土台となります。
急いで無理やり相手の意向を引き出そうとすると、それこそ上司側の期待に合わせた意見を、部下が作り出そうとします。
そして、その作り出された意見が、本人の意向であるかのように進んでしまうことが、最もコーチングで避けたい状態です。
もし、なかなか部下から意向が出てこない時は、関係性の構築から始めることも効果的です。
日頃から、チャットツール等で「いいね!」や「ありがとう」等のアクションをすることで、信頼関係と心理的安全性の形成につながります。
まずは小さなことからでも、部下との関係性構築から始めてみることも大切です。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
結論よりも、考えるプロセスを承認する
最後に、3つ目の「結論よりも、考えるプロセスを承認する」についてです。
相手から意向を引き出せたとして、それを「どのように仕事に結びつけるか」もポイントです。
単に部下に希望を聞くだけでなく、組織目標と関連づけて「意味づけ」することが、業務上のモチベーションを高める鍵となります。
仕事を任せる際には、「この仕事は君の強みを活かせる」「将来のキャリアにつながる」など、相手の価値観や目標に紐づけて伝えることが効果的です。
まとめ
ここまでで、具体的な「正解を引き出そうとしない」コーチングのポイントについてお伝えしてきました。
コーチングに上司も部下も慣れるまでは、手探りで進めている感覚が強くなってしまうかもしれませんが、まずは、無意識に陥りがちな落とし穴を「自分もついやってしまっていないか」の視点で見つめることから始めてみましょう。
貴重な部下との1on1やコーチングを通じて、双方の関係性構築により効果的に活かせるよう、ぜひ3つのポイントも意識しながら取り組んでみて下さい。
 飯田 桜" width="104" height="104">
飯田 桜" width="104" height="104">