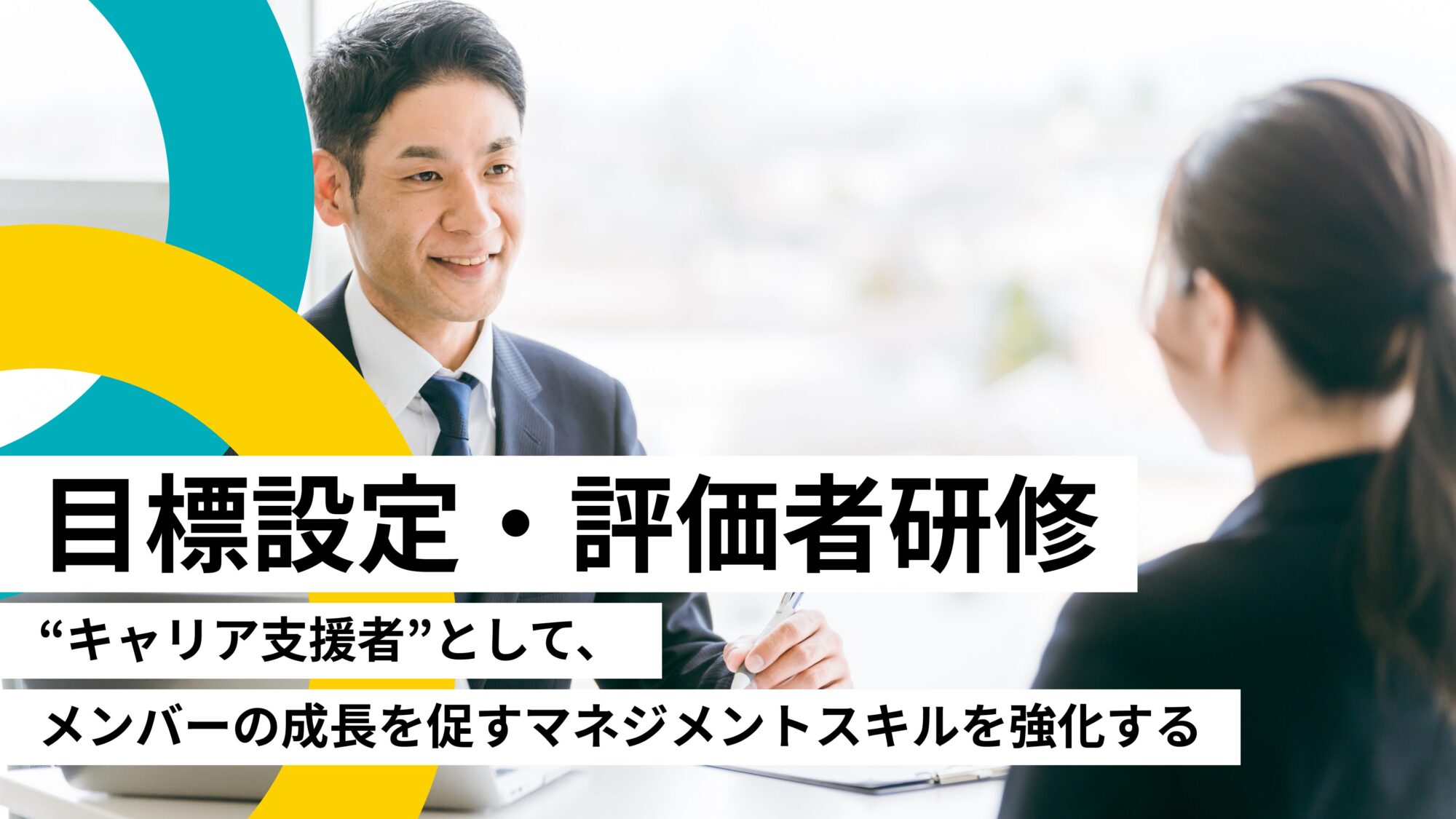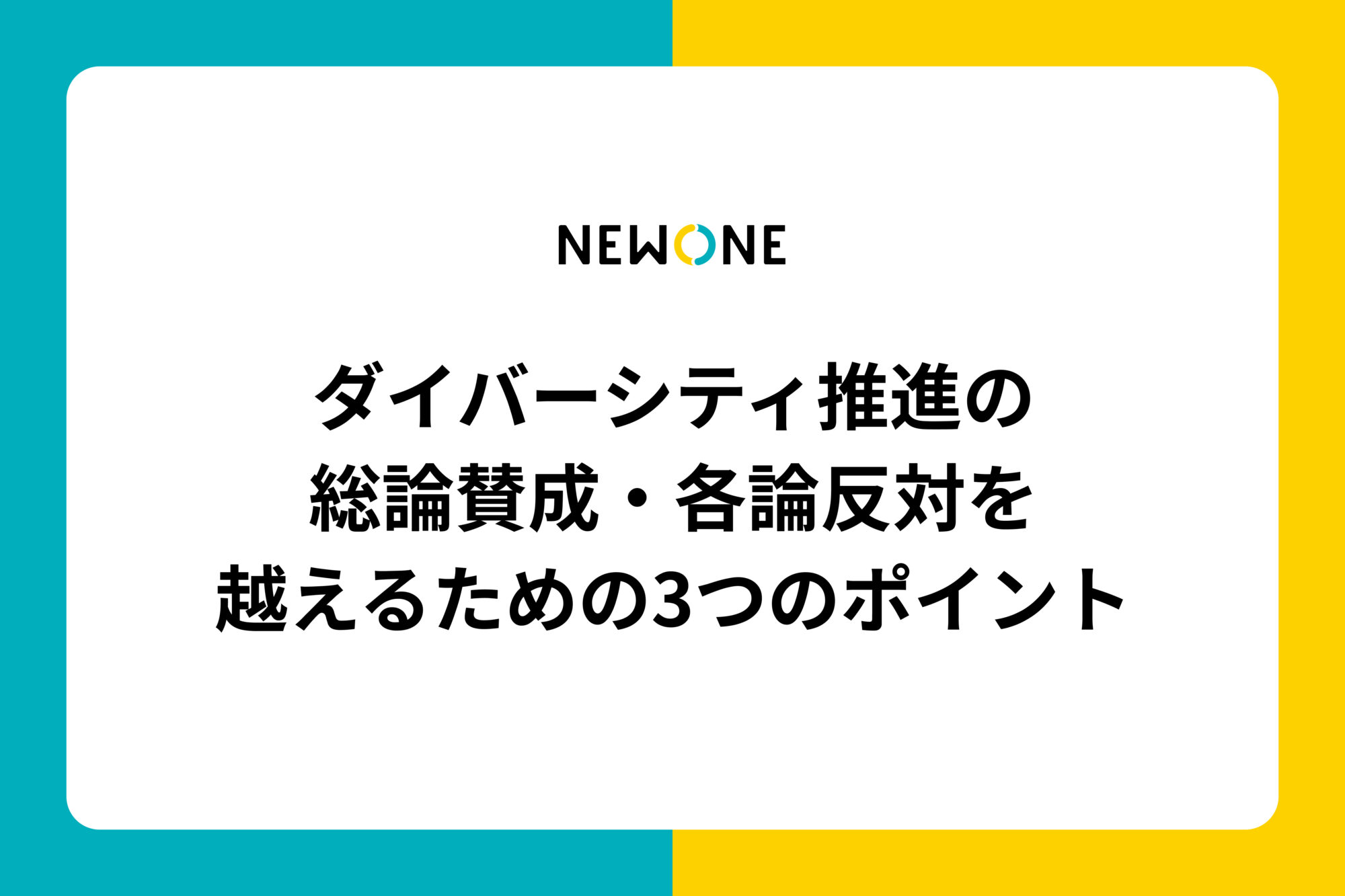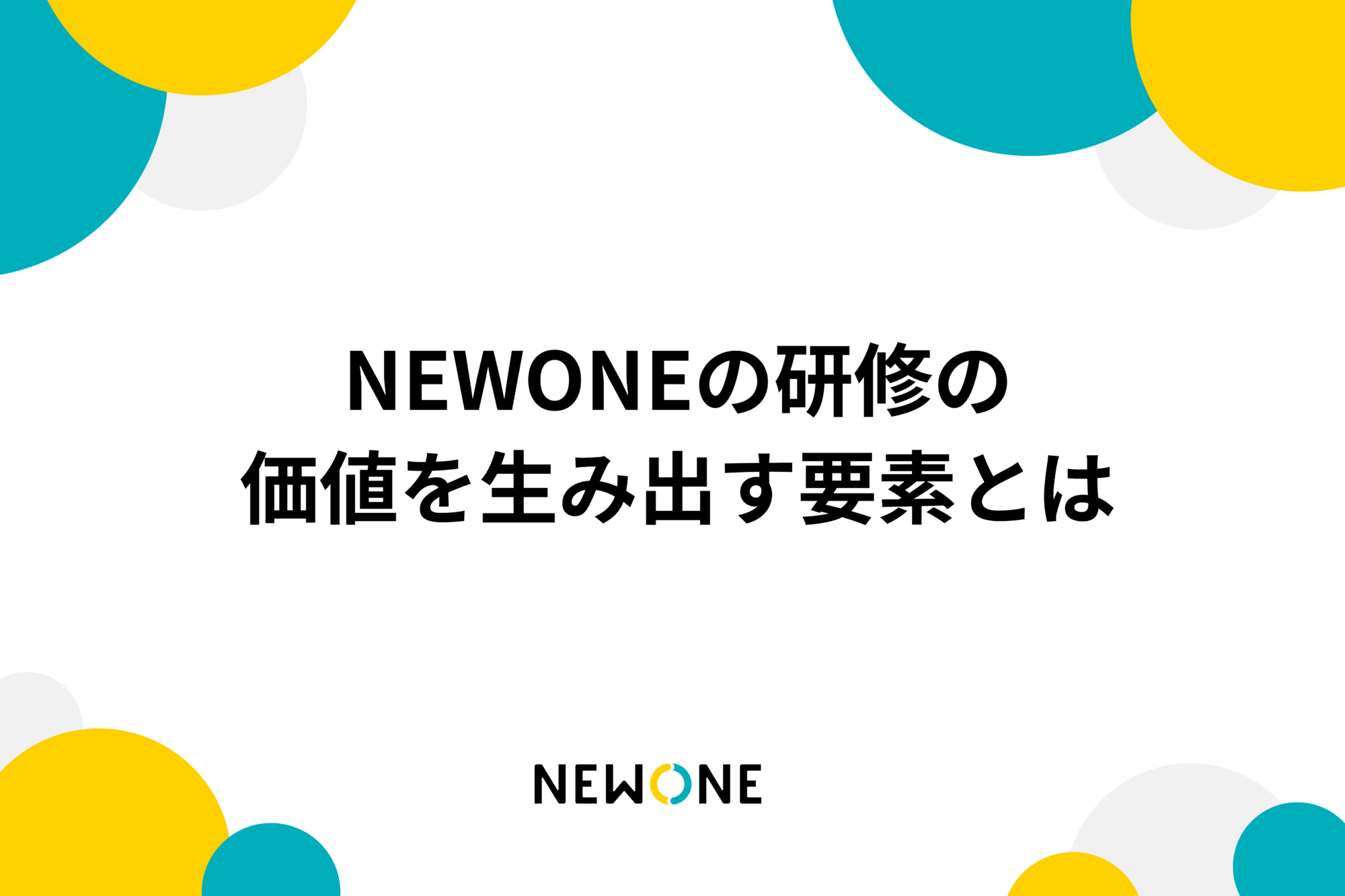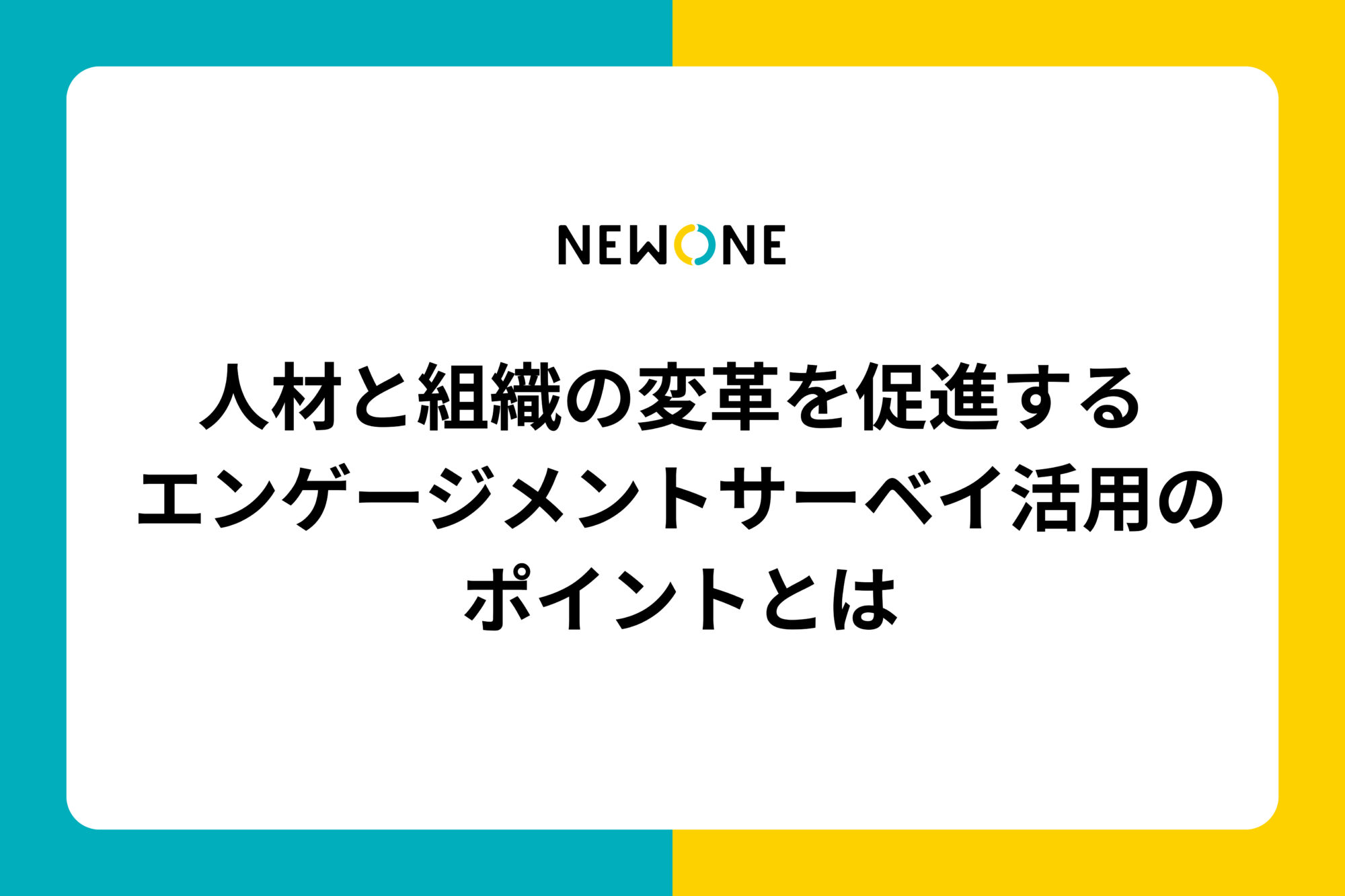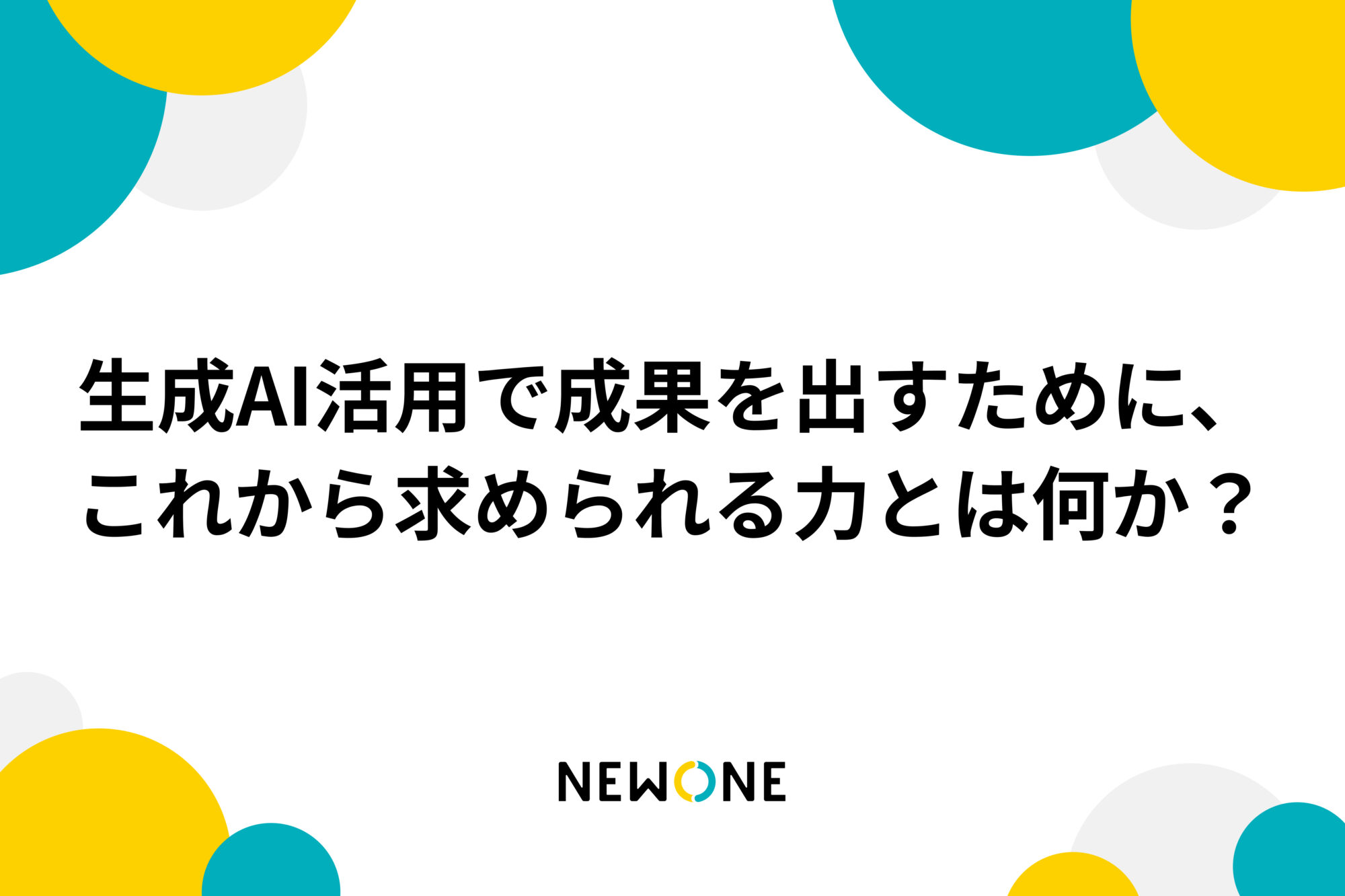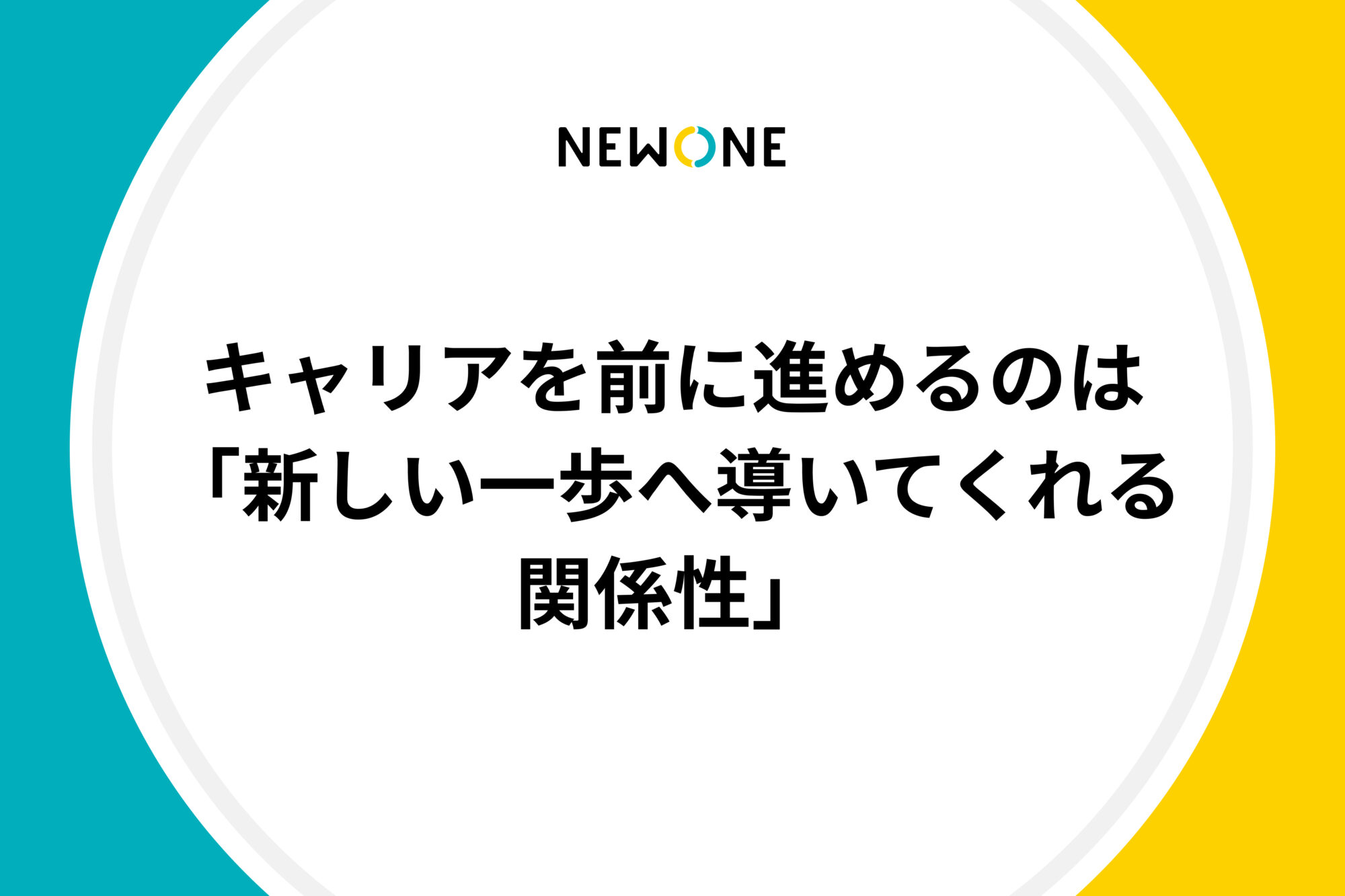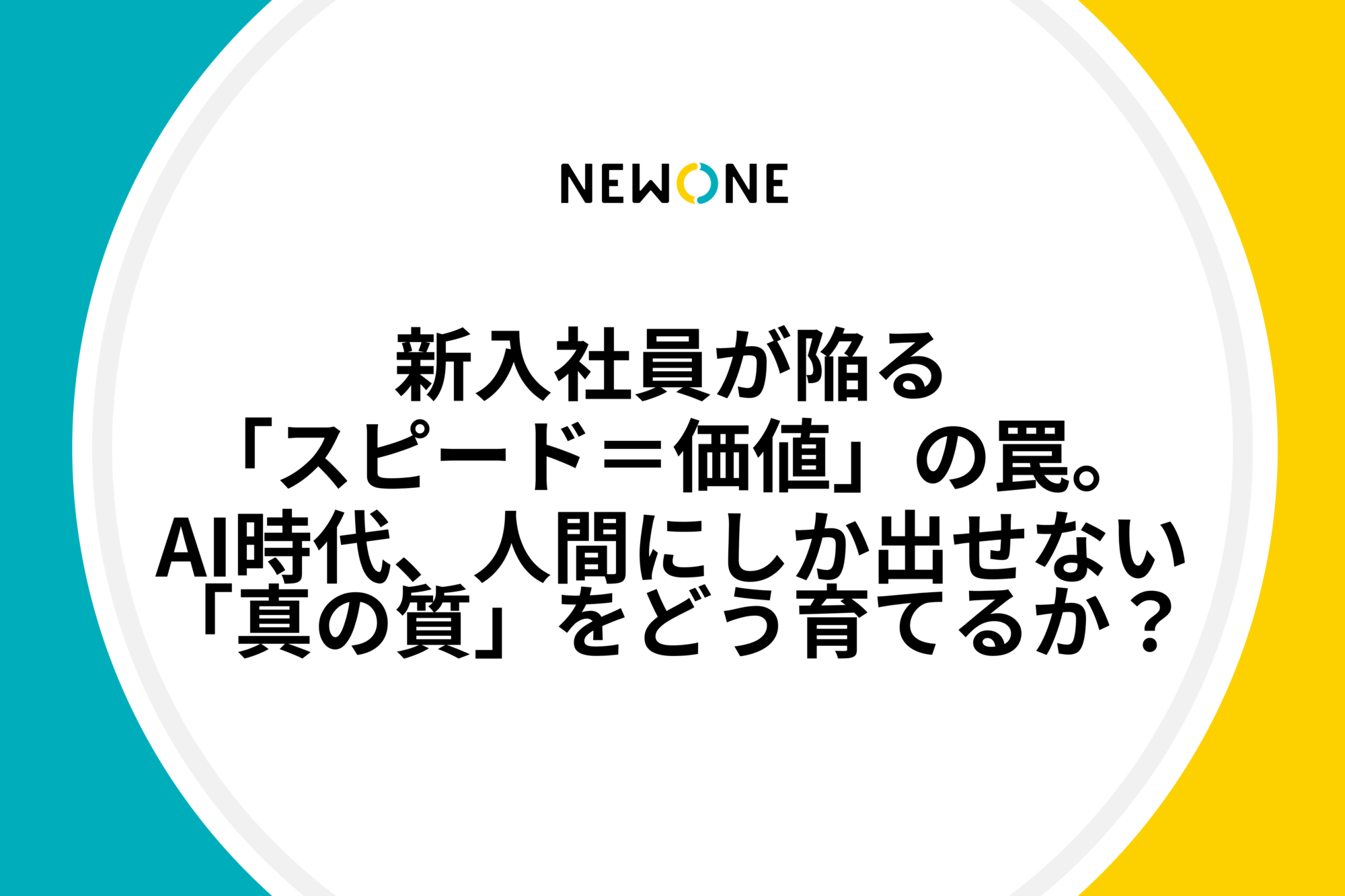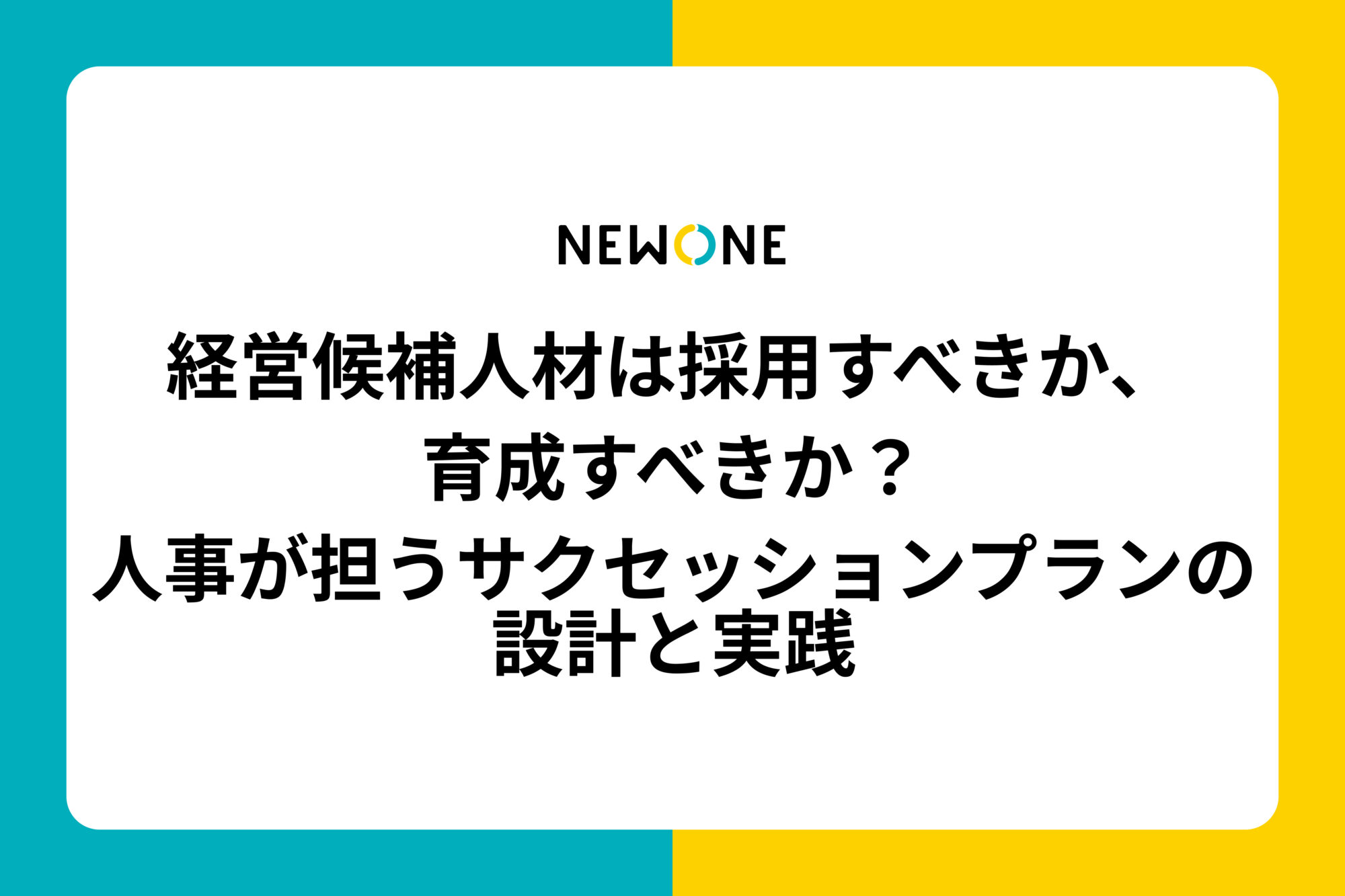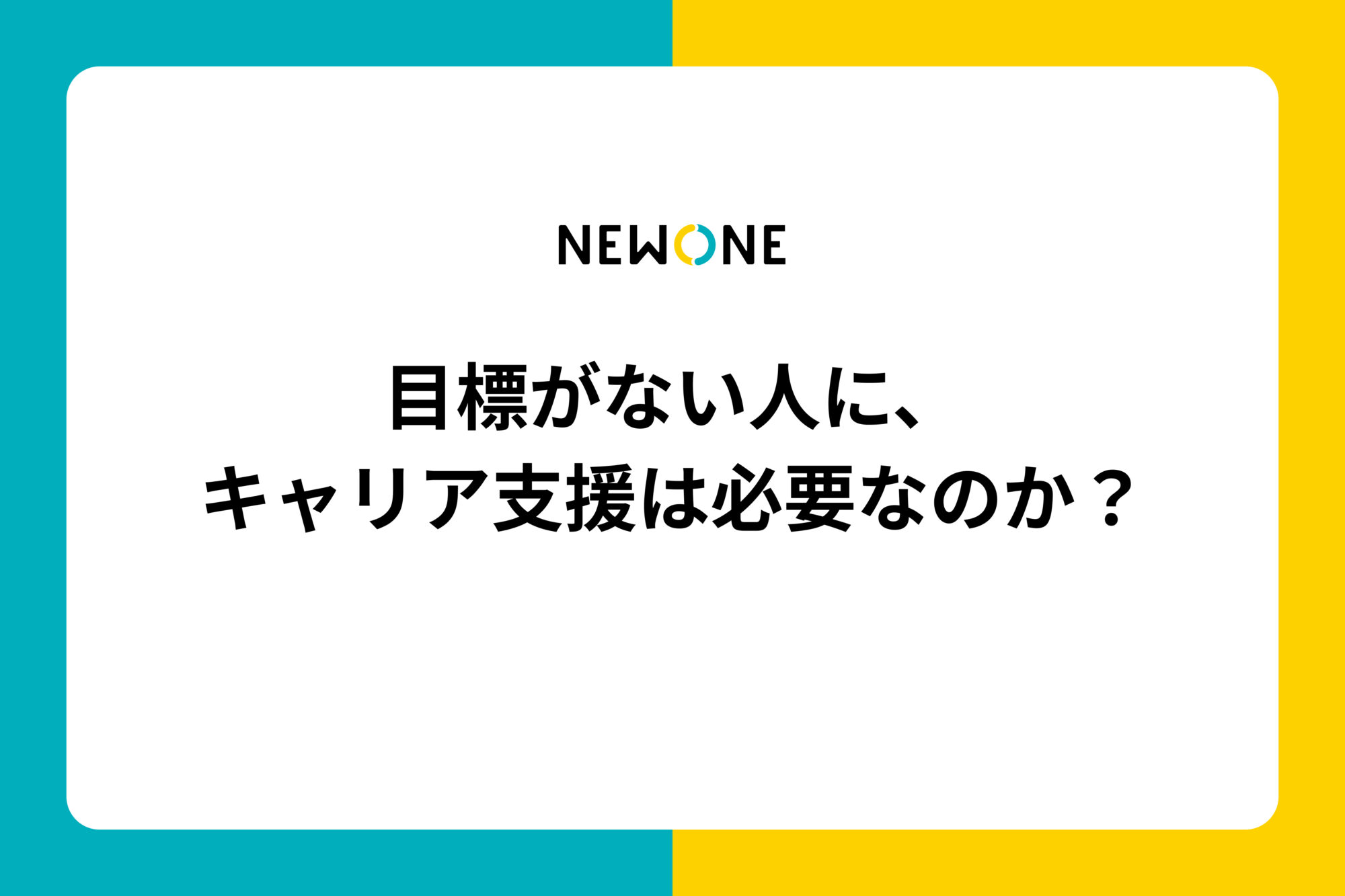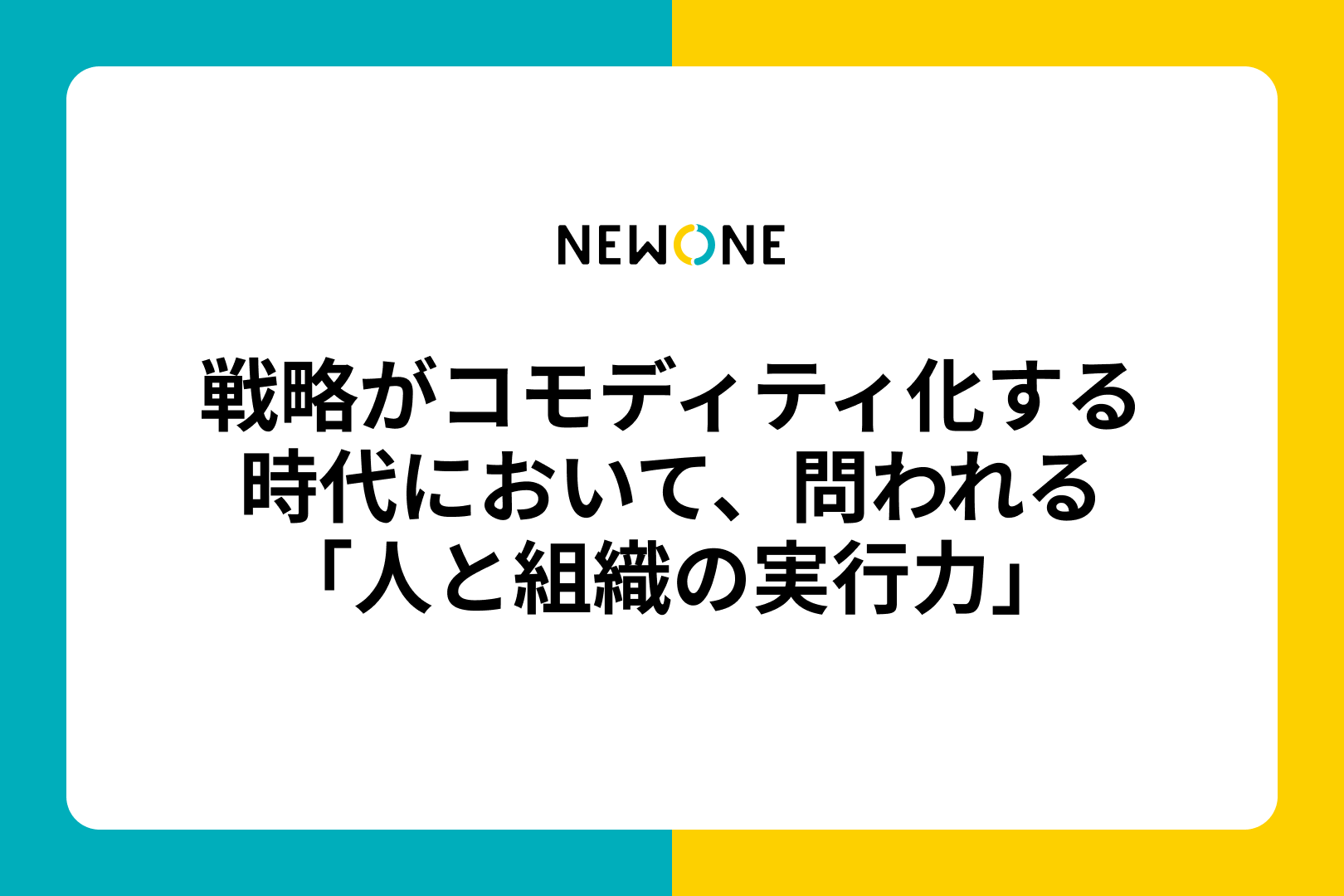
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
先日、ある企業で部長研修を行った際に、経営陣の方々が話されていた言葉が非常に印象的でした。
「これからは、戦略がコモディティ化していく時代になる」というメッセージです。
AIの発展により、膨大な情報をもとに最適解を導き出すことが容易になりました。
経営戦略の策定やシミュレーションも、AIが高精度で行えるようになりつつあります。
しかし、その最適解は競合他社も同様に導き出せる。
結果として、“戦略”そのものの差別化が難しくなりつつあるのです。
では、何が企業の競争優位を決めるのか。
その答えは「実行力」、すなわち「人と組織」にあると感じています。
人的資本経営の本質は「実行力の源泉を可視化すること」
人的資本経営という言葉を耳にする機会が増えました。
経済産業省では、「人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営の在り方」と定義しています。
しかし、実際にどう取り組めばよいのか分からない――そんな声も多く聞かれます。
人的資本経営の核心は、「経営戦略と人材戦略を連動させること」です。
伊藤レポートでも繰り返し示されているように、「経営の方向性」と「人材のあり方」を切り離して考えては、実効性のある経営は実現しません。
その連動を具体化するツールの一つが「人材ポートフォリオ」です。
人材ポートフォリオは“未来の実行力”を描く設計図
部長研修の中では、参加者の方々に実際に「自部門の人材ポートフォリオ」を作成していただきました。
まず、現在(As-Is)の状態を整理します。
どのような役割やスキルを持つ人材が何人いるのか、どの層がボトルネックになっているのか。
そのうえで、3年後(To-Be)の戦略やKPIを踏まえ、理想的なポートフォリオを描いていきます。
たとえば、新規事業を伸ばすフェーズに入るなら、「顧客起点で動ける企画人材を増やすべきだ」など、未来の戦略を実現するための人材構成を明確化するのです。
すると、現状と理想の間に“ギャップ”が見えてきます。
そのギャップに対し、「外部採用で補うのか」「他部署から異動してもらうのか」「既存メンバーを育成するのか」を考え、3年単位で実行計画を立てていきます。
人と組織の変化には時間がかかります。
今日の施策が明日の成果に直結するわけではありません。
だからこそ、3年先を見据え、今から打ち手を講じることが重要なのです。
現場の部長が描くことで、ポートフォリオが“血の通ったもの”になる
このプログラムを実施して感じたのは、部長層が自ら手を動かすことの重要性です。
人事主導で設計されたポートフォリオは、どうしても机上の計画に終わることが多い。
一方、現場の部長が自分のチームを見渡し、メンバー一人ひとりの顔を思い浮かべながら描くと、途端に現実味を帯びてきます。
「誰を育てるべきか」「誰にチャンスを渡すべきか」――。
業績を担う責任と葛藤の中で、部長たちは真剣に考えざるを得ません。
まさに“実行力をつくる思考”がここにあります。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
採用力は、これからの「職場力」を映す鏡
今回の取り組みを通じて、特に印象的だったのは「採用力の重要性」です。
いくら戦略や育成計画を立てても、必要な人材を惹きつけ、採用できなければ意味がありません。
そして今後は「職場単位の採用力」がますます問われていくでしょう。
なぜなら、内部異動においても“本人の手上げ”が主流になりつつあるからです。
職場そのものが魅力的であれば、社内外から人が自然と集まる。
逆に魅力がなければ、優秀な人材は去っていく。
人事任せではなく、部長自身が「自分の職場を推せる状態」にすることが求められます。
弊社では「推せる職場」という概念を研究していますが、まさにこの“採用力と魅力度”は表裏一体のテーマです。
人事だけでなく、職場単位での当事者意識が時代の要請となっています。
人事任せの時代から、部長が人事を担う時代へ
もう一つの大きな気づきは、「人事施策を部長が担う時代が来ている」ということです。
かつては人事部が制度を設計し、現場に展開するという構造でした。
しかし、変化が激しい今の時代、現場でのスピーディな意思決定と行動が不可欠です。
部長が自ら人材ポートフォリオを描き、キャリア開発の方向性をメンバーと対話する。
それは単に人事的な業務を増やすということではなく、「経営を担うリーダーとしての視座を持つ」ということです。
人的資本経営の時代において、人事の一部機能が部長や現場へとシフトしていく――それは避けられない流れだと感じます。
戦略よりも、人と組織の実行力が企業の価値を決める
AIが進化し、戦略がコモディティ化する中で、企業の競争力を左右するのは「どれだけ実行できるか」です。
その実行力の源泉は、人と組織。
そしてその力を最前線で体現するのが、部長層なのです。
「人的資本経営をどう実践するか」と悩む企業は多いですが、まずは自部門の現状を可視化し、未来の姿を描くことから始めることが重要です。
その一歩を部長自らが踏み出すことで、組織全体が変わり始める――。
弊社では、このような部長層などの上位者向けプログラムも多数実施しております。
課題を感じる方がいれば、ぜひおっしゃっていただければ幸いです。
 上林 周平" width="104" height="104">
上林 周平" width="104" height="104">