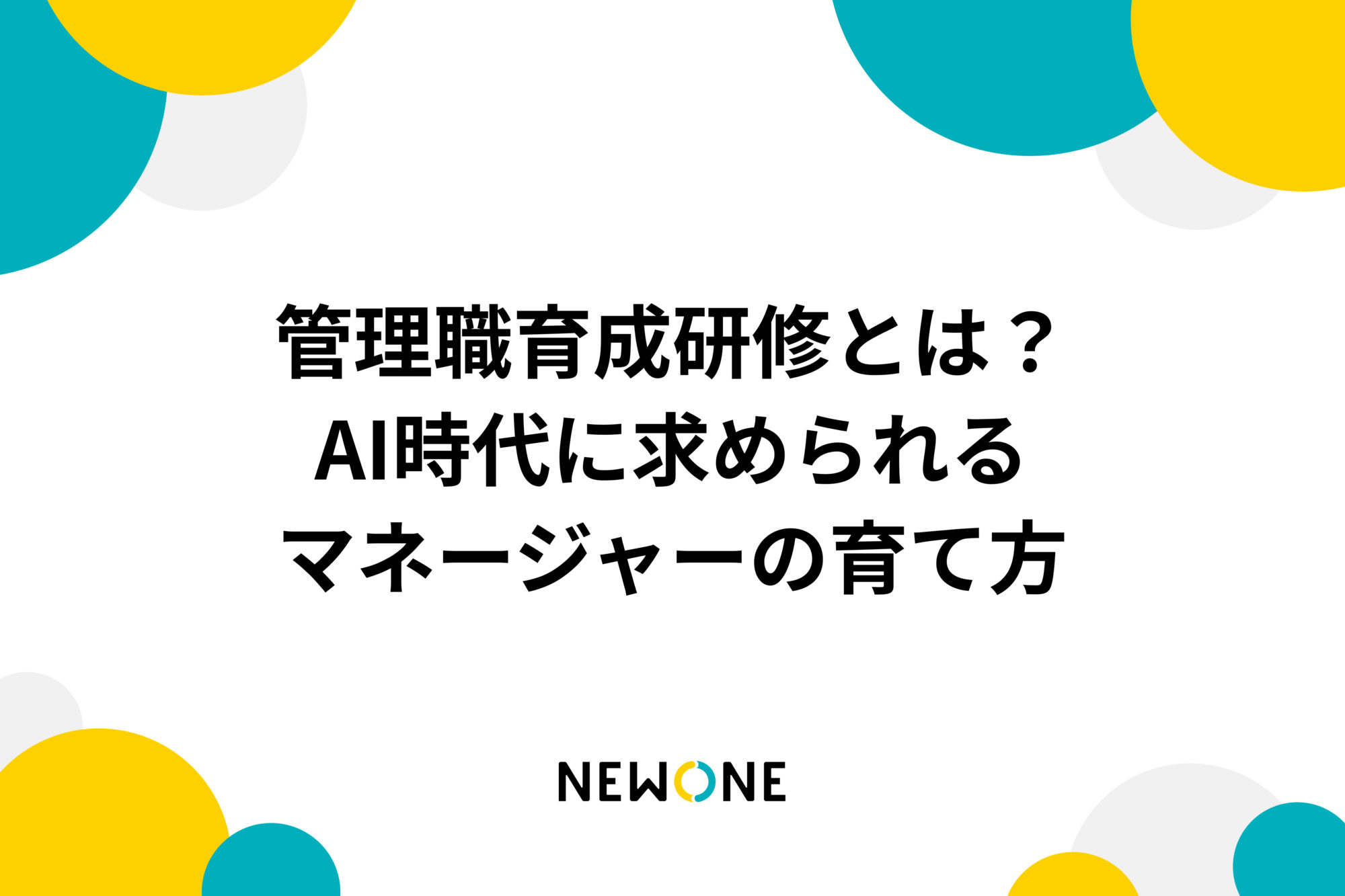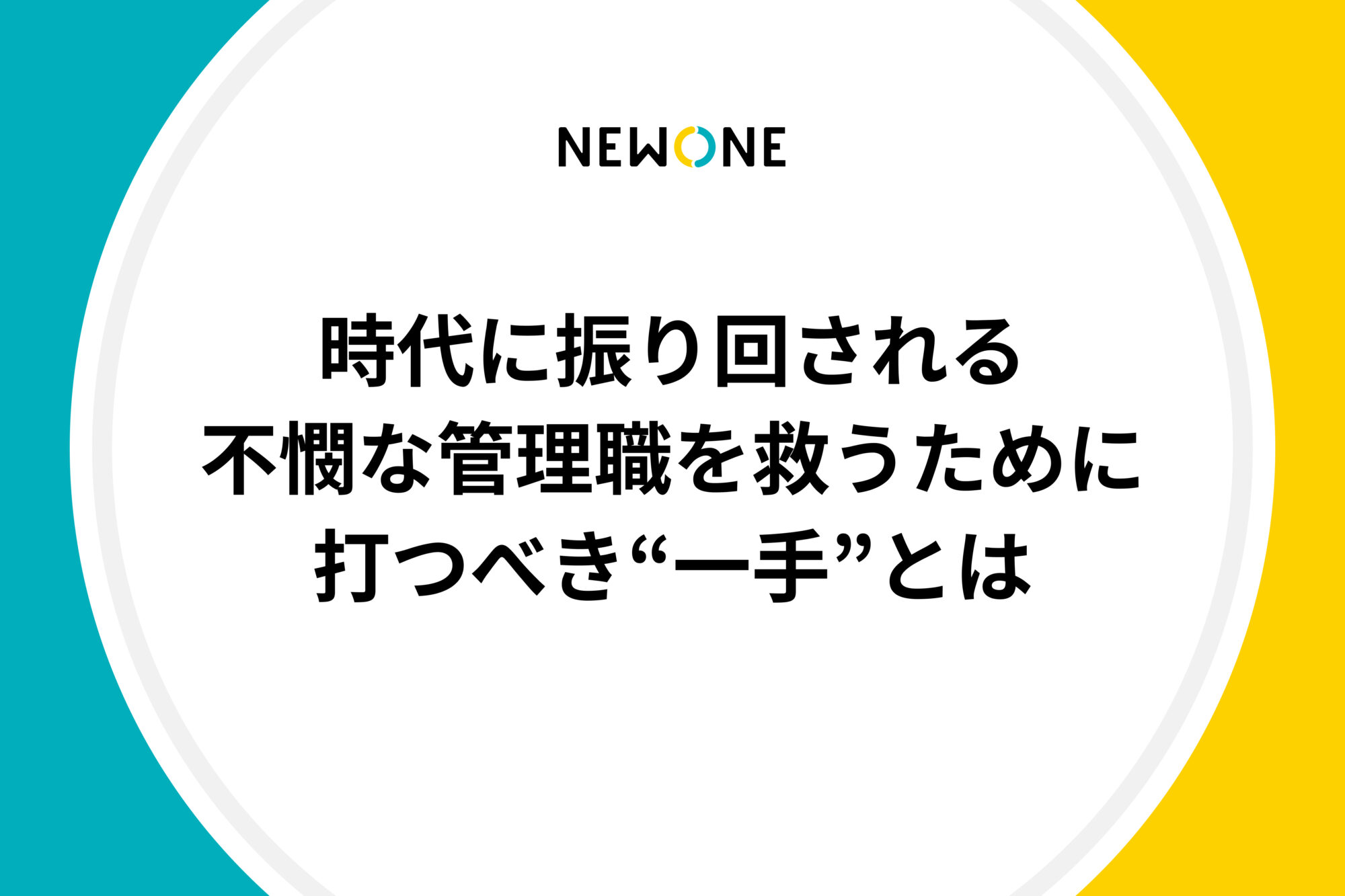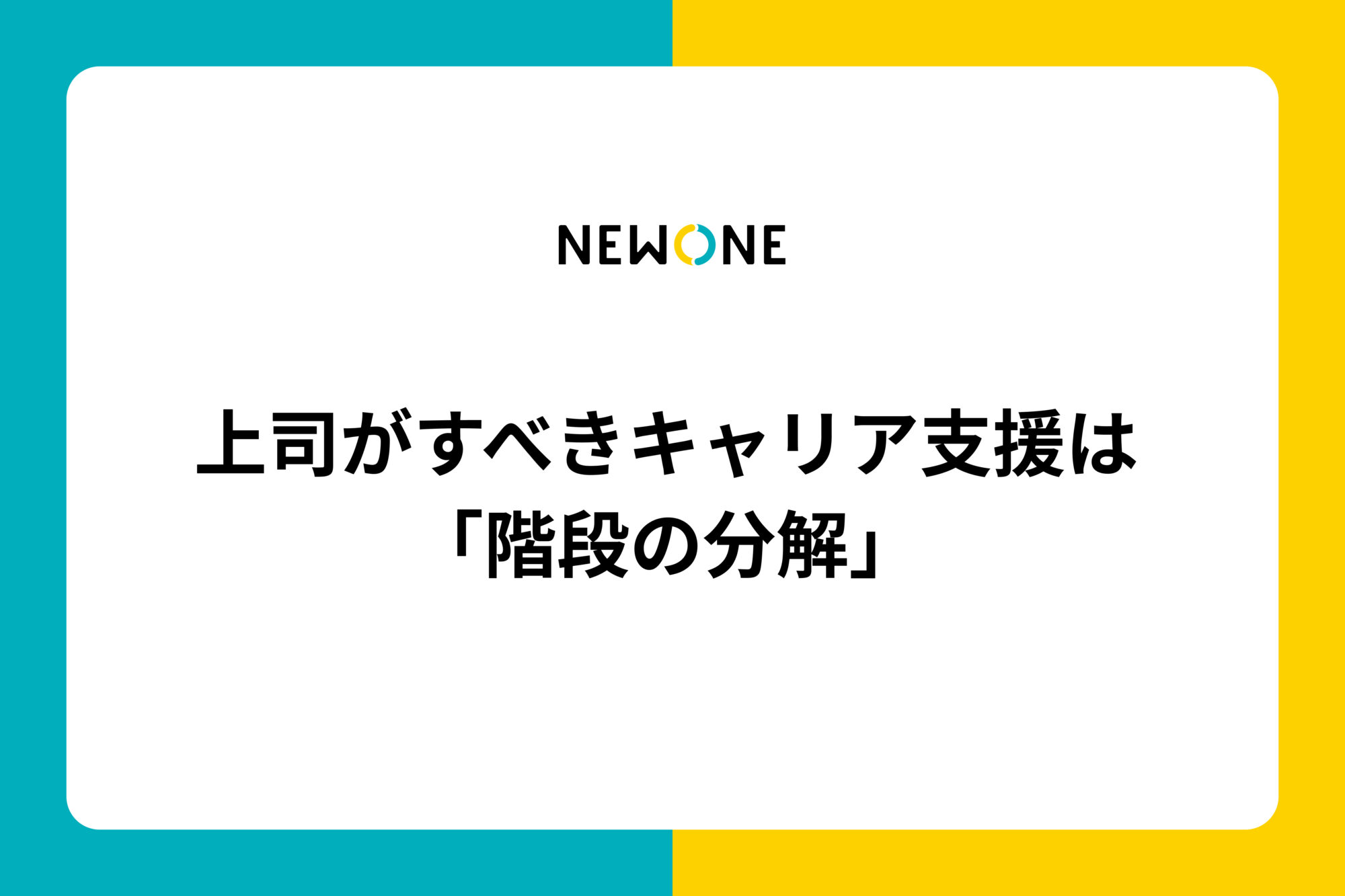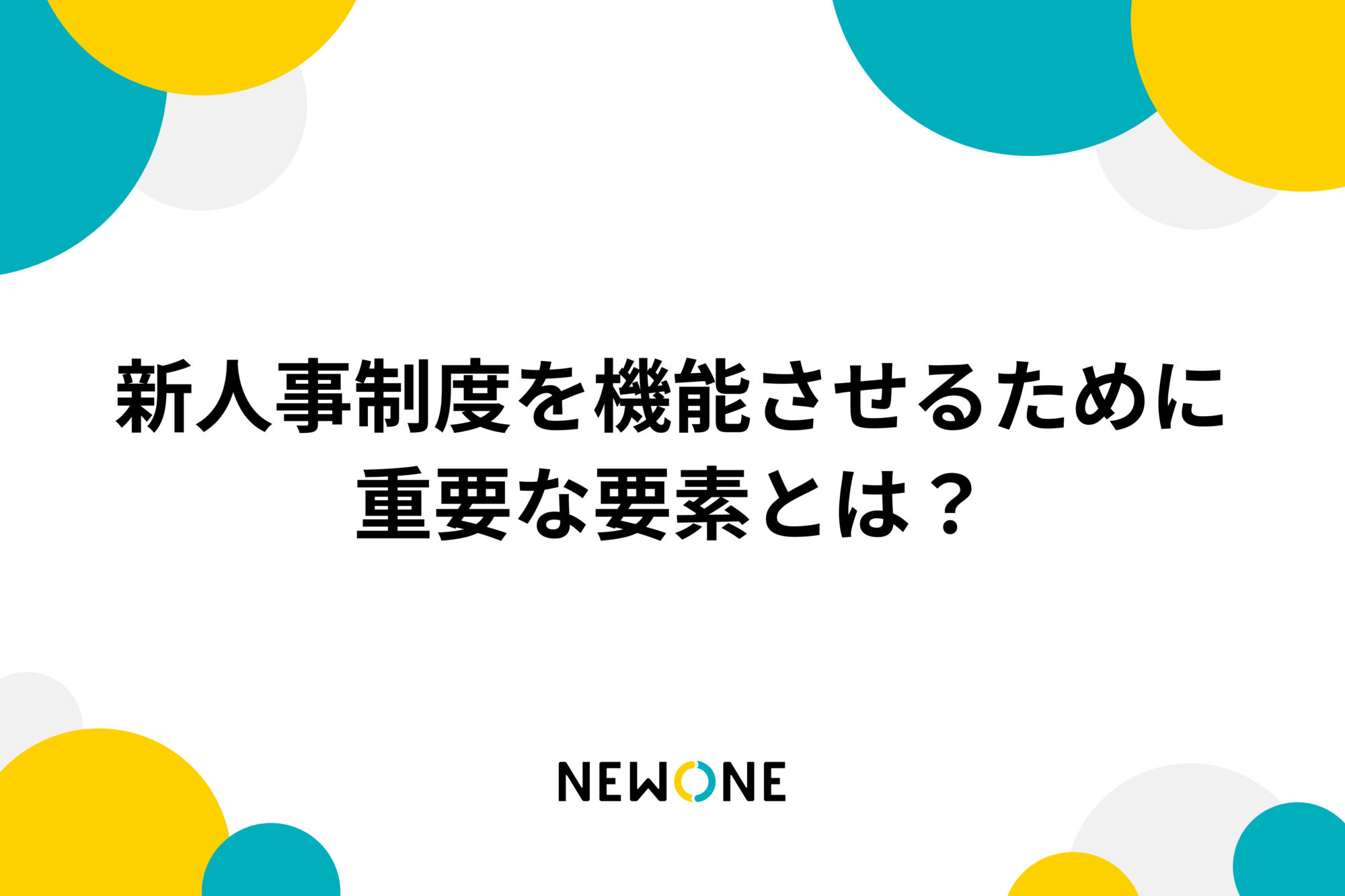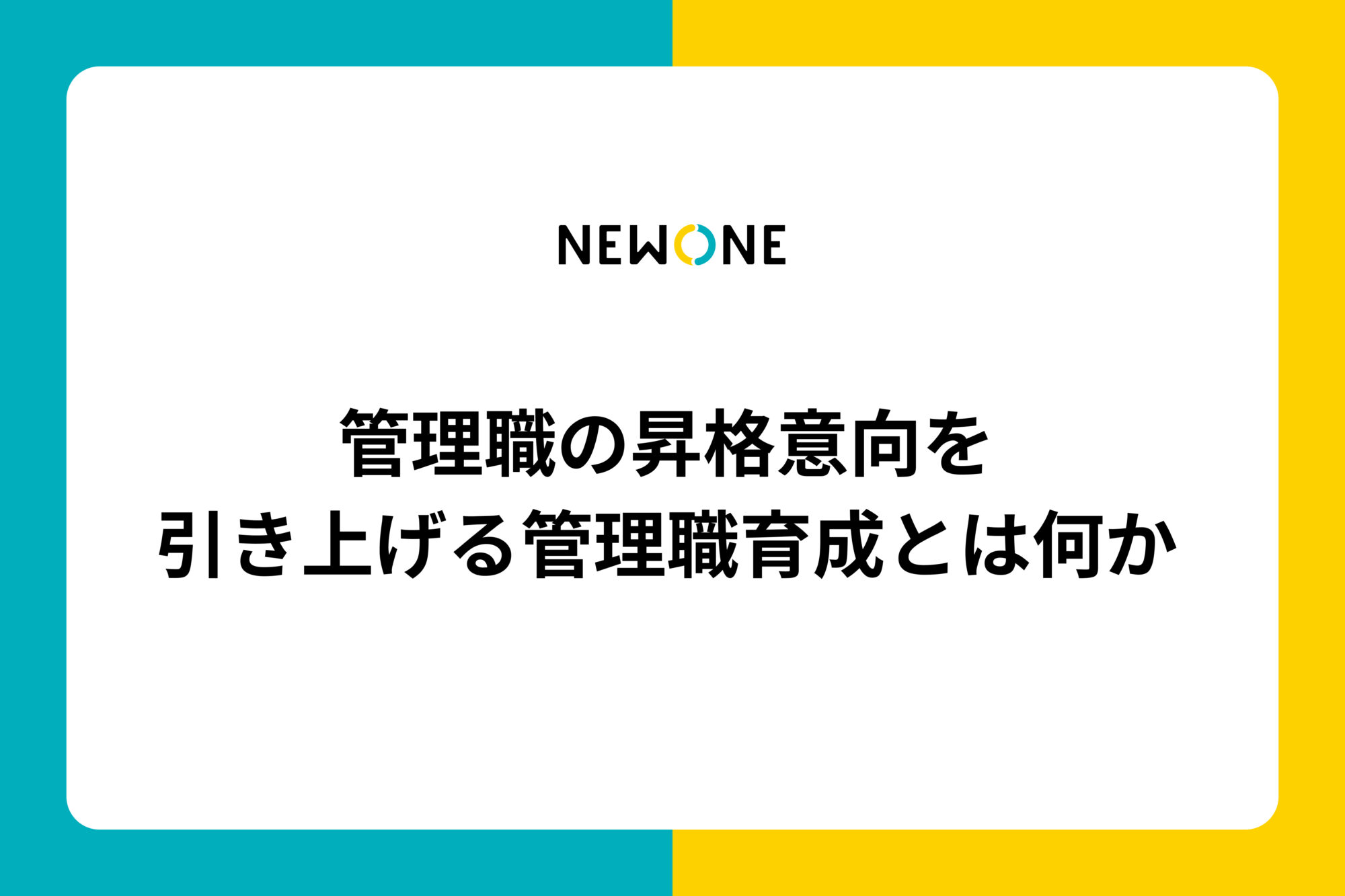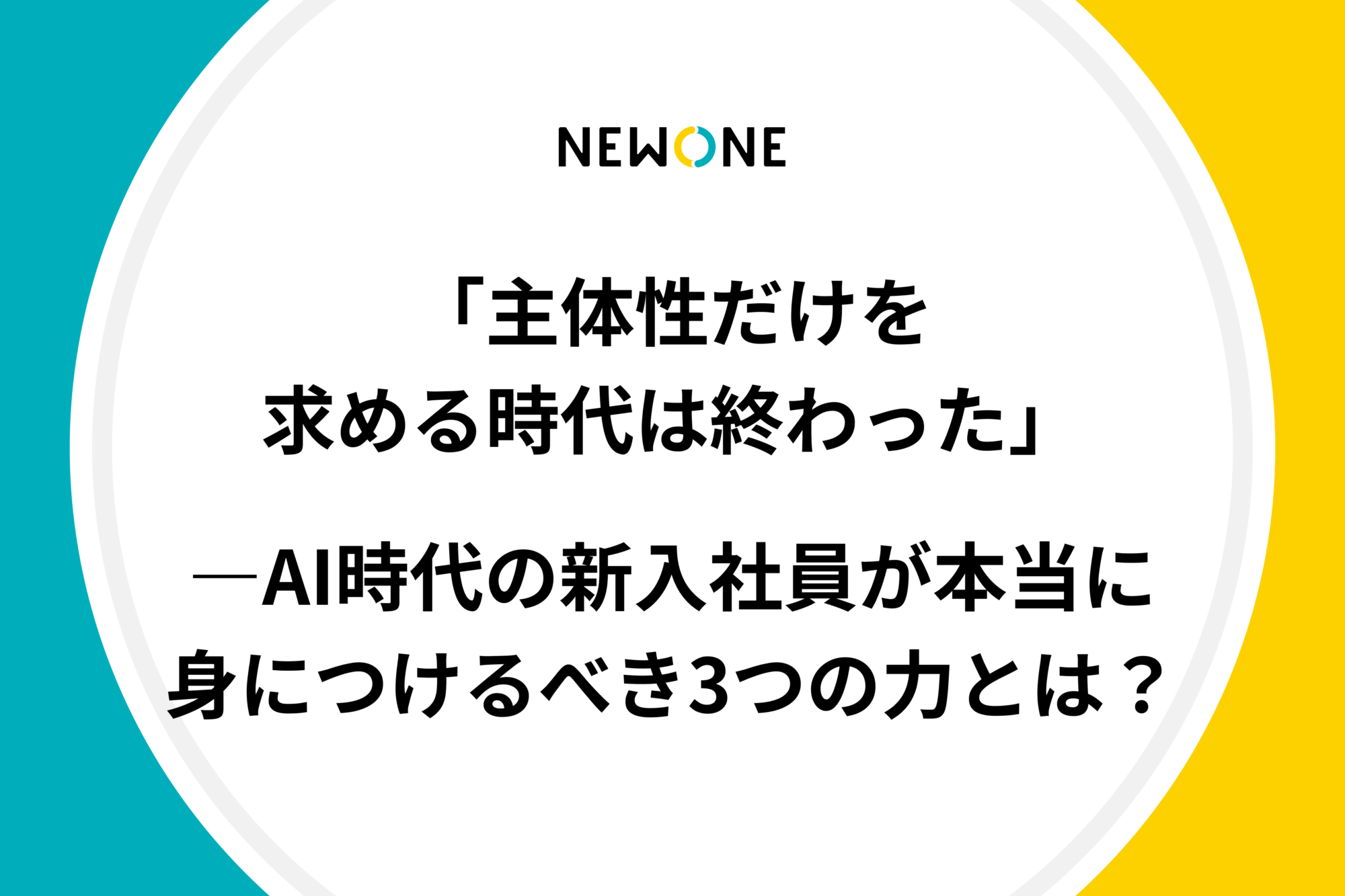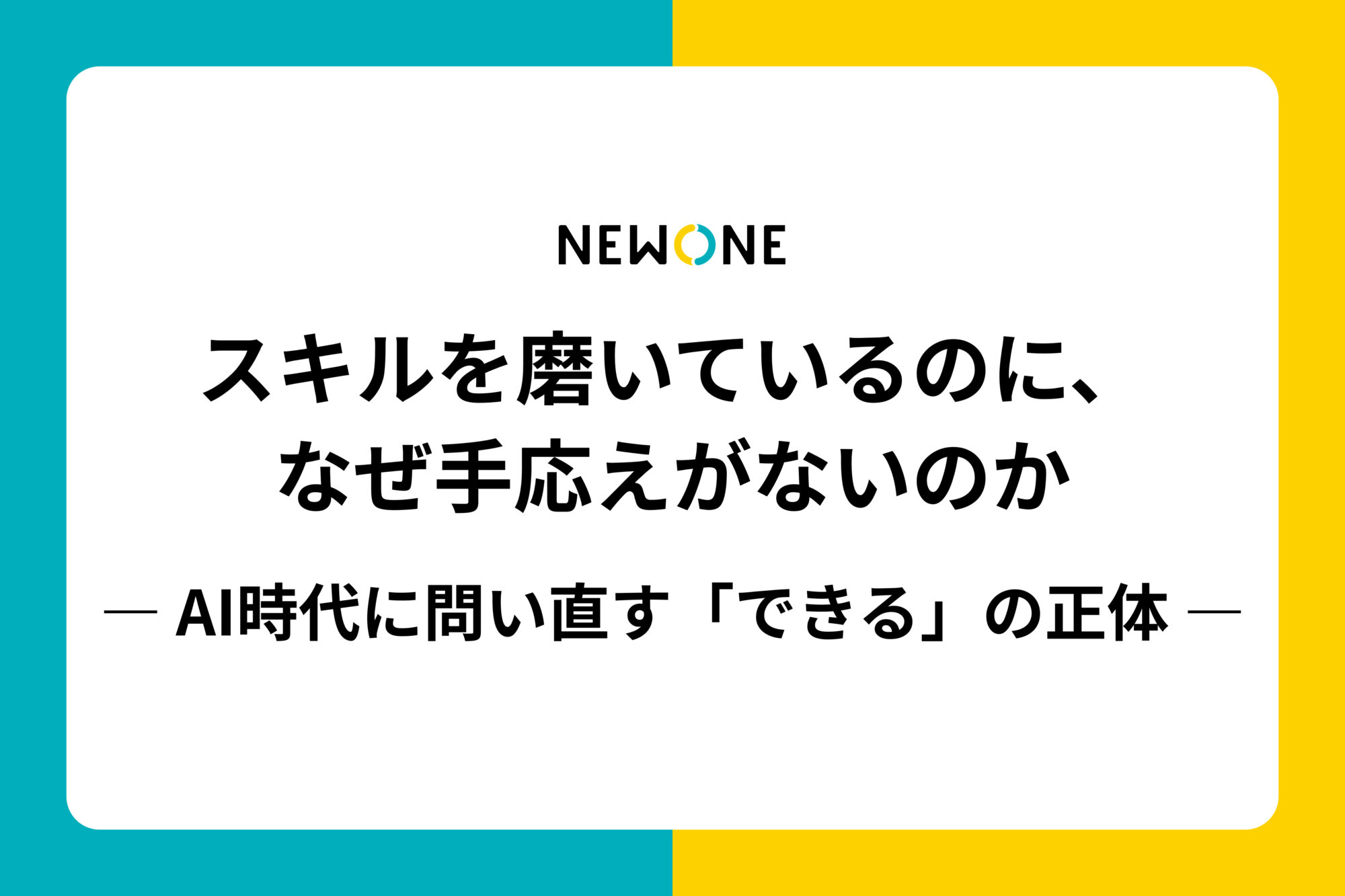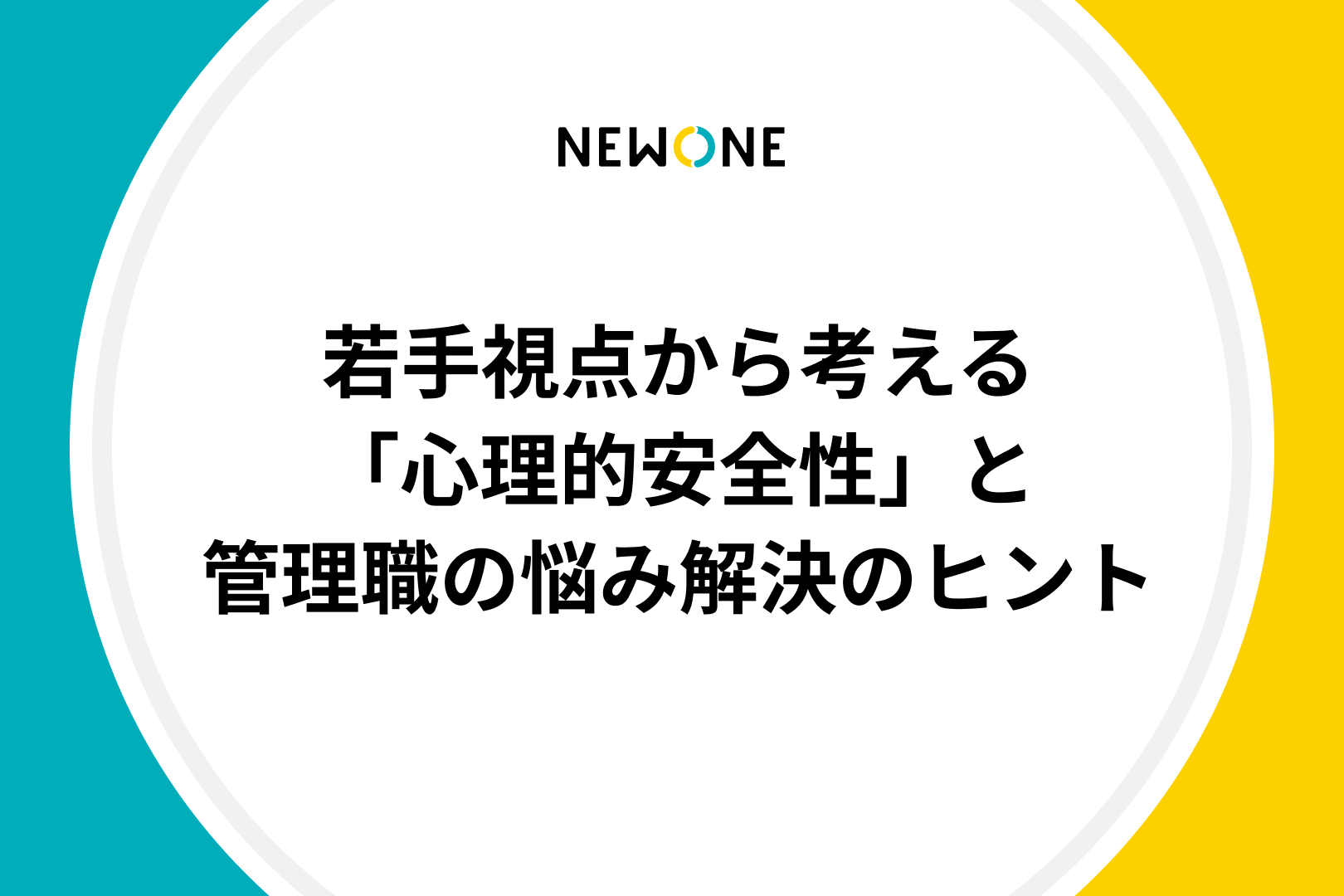
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
近年、多くの管理職が「心理的安全性の高い職場づくり」の重要性を考え始めています。
そのなかで、実際の現場では若手社員との関係性に悩む声も少なくありません。
管理職の方からは、具体的に次のような悩みをよく聞きます。
- 若手社員との対話が上手くいかず、距離が縮まらない
- 「心理的安全性」という言葉に縛られ、適切なフィードバックができなくなっている
- 心理的な安全性を重視するあまり、チームの成果につながらない
今回のコラムでは心理的安全な職場を作っていくために、管理職の皆様が明日からできるアクションを若手社員の目線でお伝えします。
①対話を通して意見を受け止める
そもそも心理的安全性とは、
「チームの他のメンバーが自分の発言を拒絶したり、罰したりしないと確信できる状態」
と定義されています。
とはいえ、管理職の皆様の視点だと、若手社員が持ってきた意見は拙く、思考が足りない部分が多くあり、「こんな意見を採用できるわけがないじゃないか」と思われることもあるのではないでしょうか。
管理職の皆さまに求められるのは、若手社員の「意見の背景を捉え、一旦受け止める」ことです。
例えばアクションとして下記のようなことがあります。
| ・傾聴だけでなく、対話質問を深くする(例:「なぜそう思ったの?」と聞く) ・反対意見に対して関心を示す(例:「面白い考え方だね」と関心を示す) ・失敗を責めず、学びに変える(例:「次に活かせることは?」と問いかける) |
通常のかかわりからもう少し深く対話をすることで、「意見が活かされる安心感」がチーム全体に広がり、取り組み向上につながります。
② フィードバックは「厳しさ」だけではなく「期待」を伝える
「心理的安全性」を意識しすぎると、「ハラスメントが気になり、フィードバックができない」と感じている管理職の方もいらっしゃるのではないでしょうか。ですが、実は若手社員も「成長するためにフィードバックをもらいたい」と思っており、むしろ「フィードバックがもらえないこと」に不安を感じる社員も多いと言われています。
このような若手の意向を汲み、効果的にフィードバックをするために、アクションとして下記のようなことがあげられます。
| ・「指摘」ではなく「期待」として伝える(例:「こうすればもっと良くなるよ」) ・良い点もセットで伝える(例:「ここはとてもよく頑張ったね。次はこうしてみよう」) ・定期的なフィードバックの場をつくる(例:1on1で「最近どう?」と話す) |
若手にとって、厳しさだけではなく、期待を伝えるフィードバックがエンゲージメントを高め、結果としてチームのパフォーマンス向上に貢献します。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
③成果のための対話である共通認識を取る
「心理的安全性を重視すると、成果に対して強く言えなくなるのではないか。
ゆるい職場になってしまうのではないか」という悩みも多く聞かれます。
しかし実際には心理的安全性が高いチームほど、意見交換が盛んになり、成果を上げやすい傾向があります。本当の心理的安全性が高いチームは、目標に向かって協力し合い、意見を出し合いながら仕事を進めることが特徴です。
例えばアクションとして下記のようなことがあります.
| ・チームの目的や目標を明確にする(例:「なぜこの仕事をするのか?」を伝える) ・意見を出したら、アクションにつなげる(例:「じゃあ試しにやってみよう」)とアクションを後押しする) ・挑戦を歓迎し、小さな成功を積み重ねる(例:「ナイスチャレンジ!」と評価する) |
心理的な安全性と成果は両立できるものです。意見を言いやすい環境を作りながら、チームの目標や成果を意識させることで、心理的安全性を高めつつ成果も出せるチームを作ることが可能です。
まとめ:心理的安全性とエンゲージメントを両立した職場づくり
「心理的安全性」は、「話しやすい環境」を作ることではありません。成果のため、建設的に議論され、成長を感じられる現場こそが、心理的安全性の高い職場と言えます。
| ・ただ話すだけでなく、対話を深める ・フィードバックは「厳しさ」ではなく「期待」として伝える ・心理的安全性と成果バランス考えてかかわる |
これらの小さなアクションからエンゲージメントを高め、チームの成果も上げる職場づくりが可能です。
管理職の皆さんが「心理的安全性の本当の意味」を正しく理解し、そのためのアクションを実践することで、チームの成果につながる職場づくりができるのではないでしょうか?
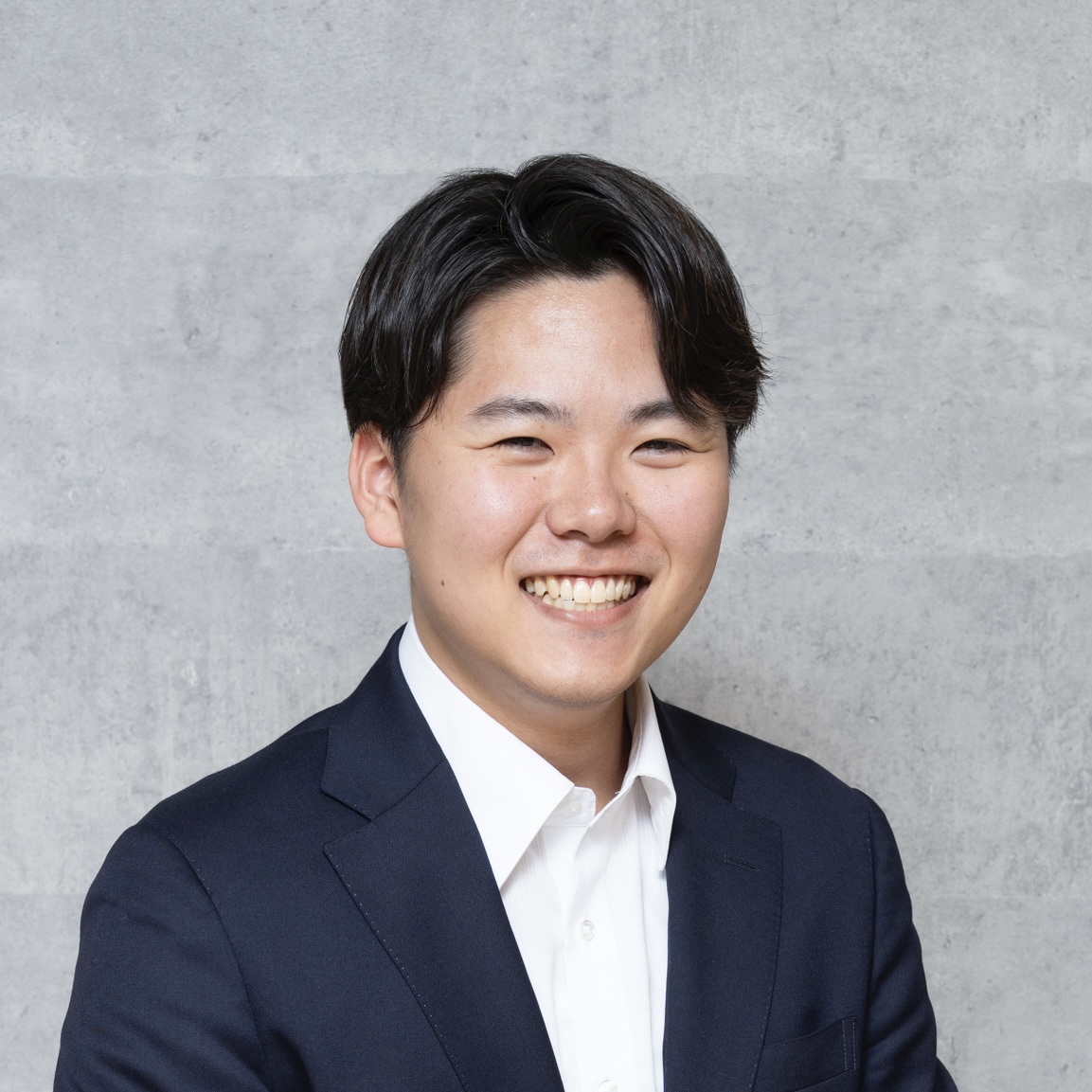 池本 大輝" width="104" height="104">
池本 大輝" width="104" height="104">