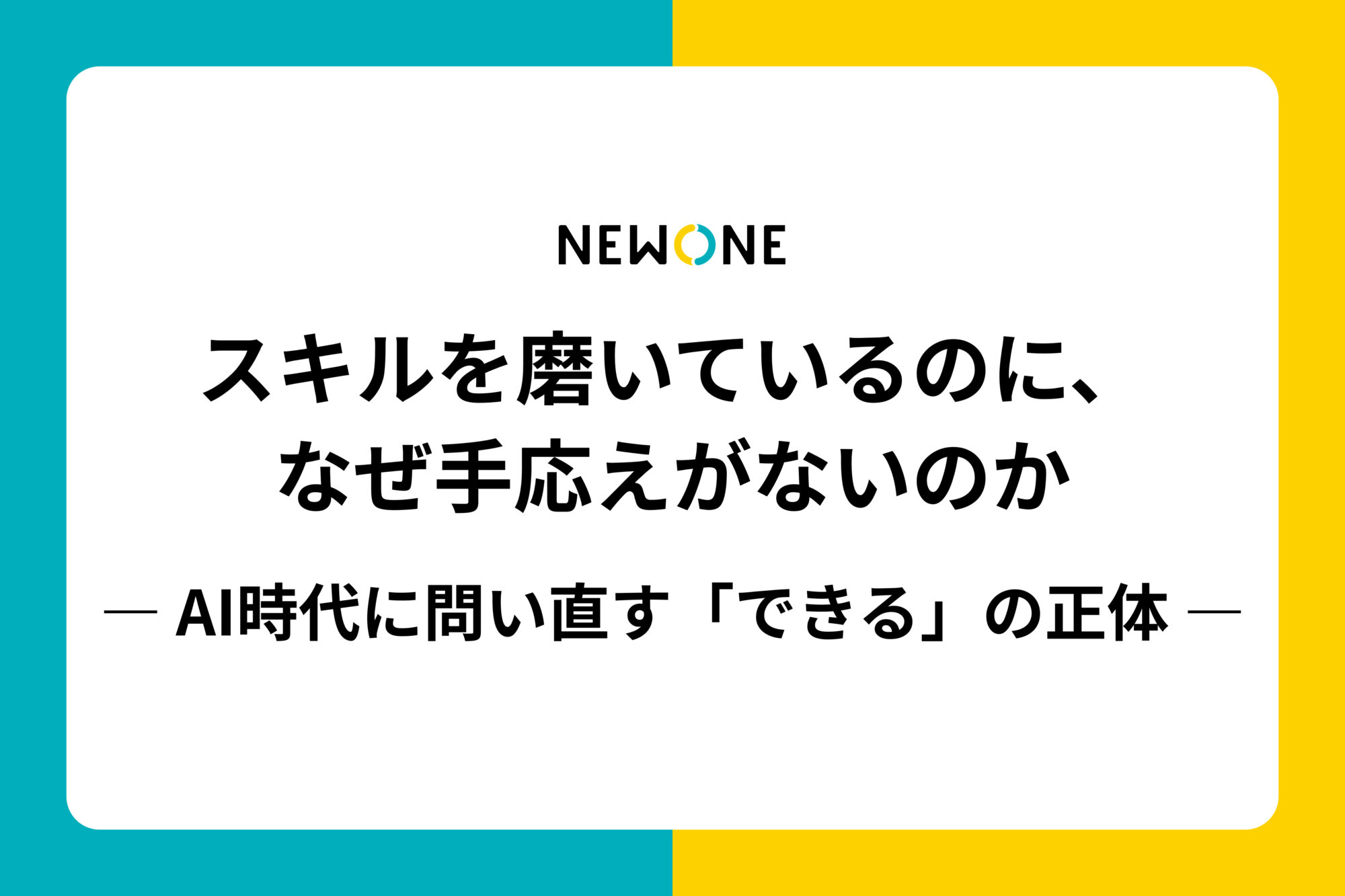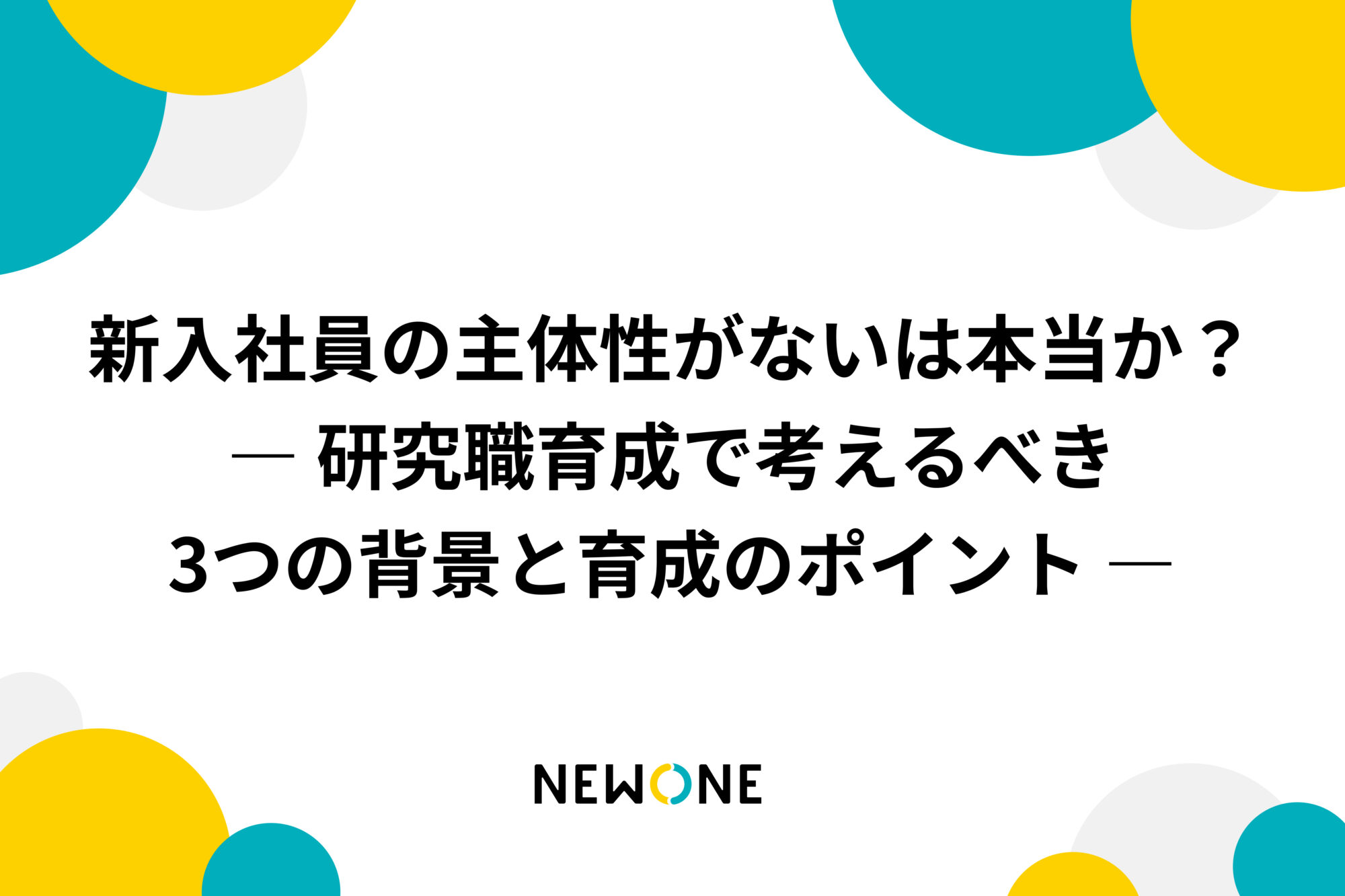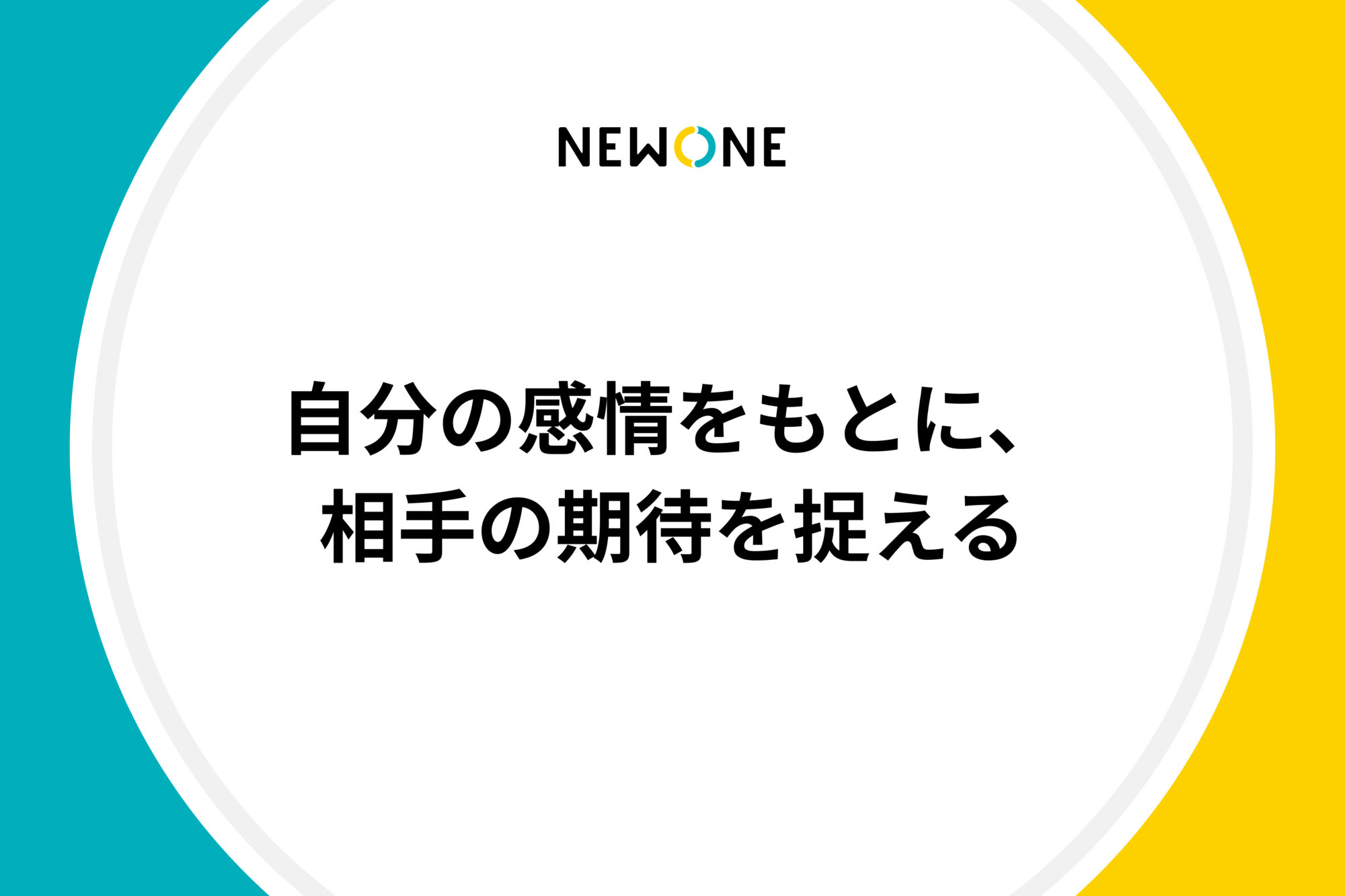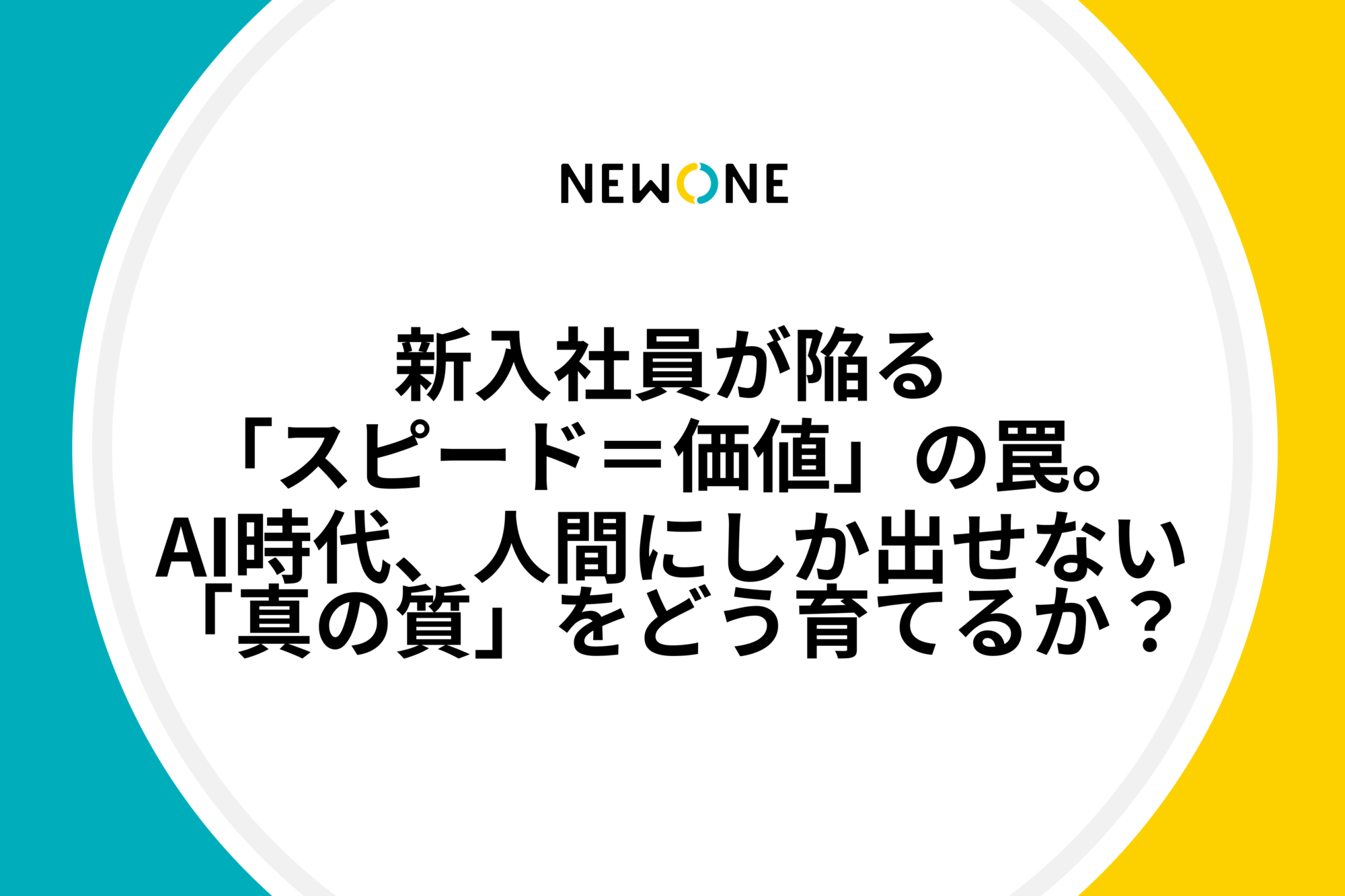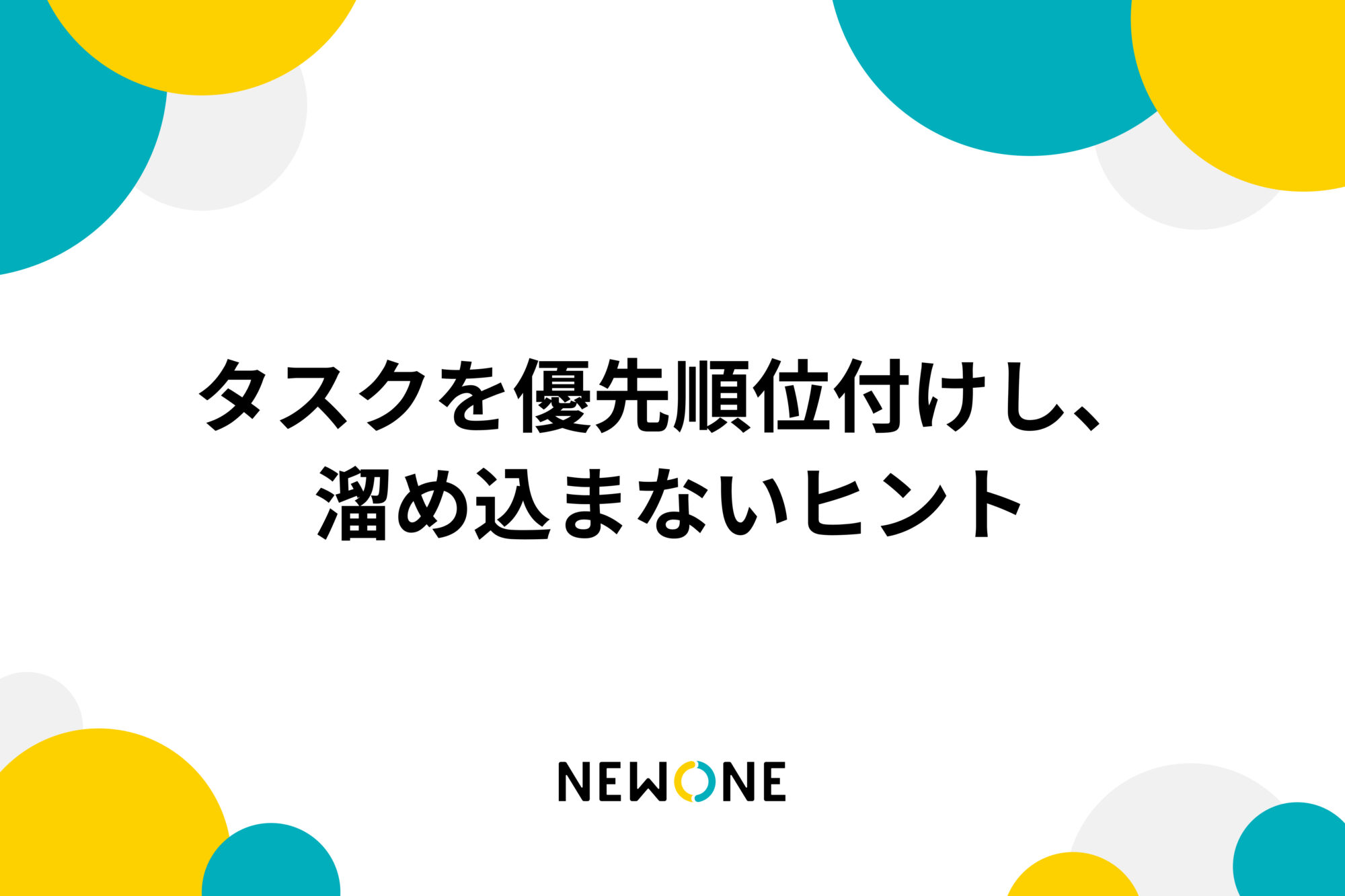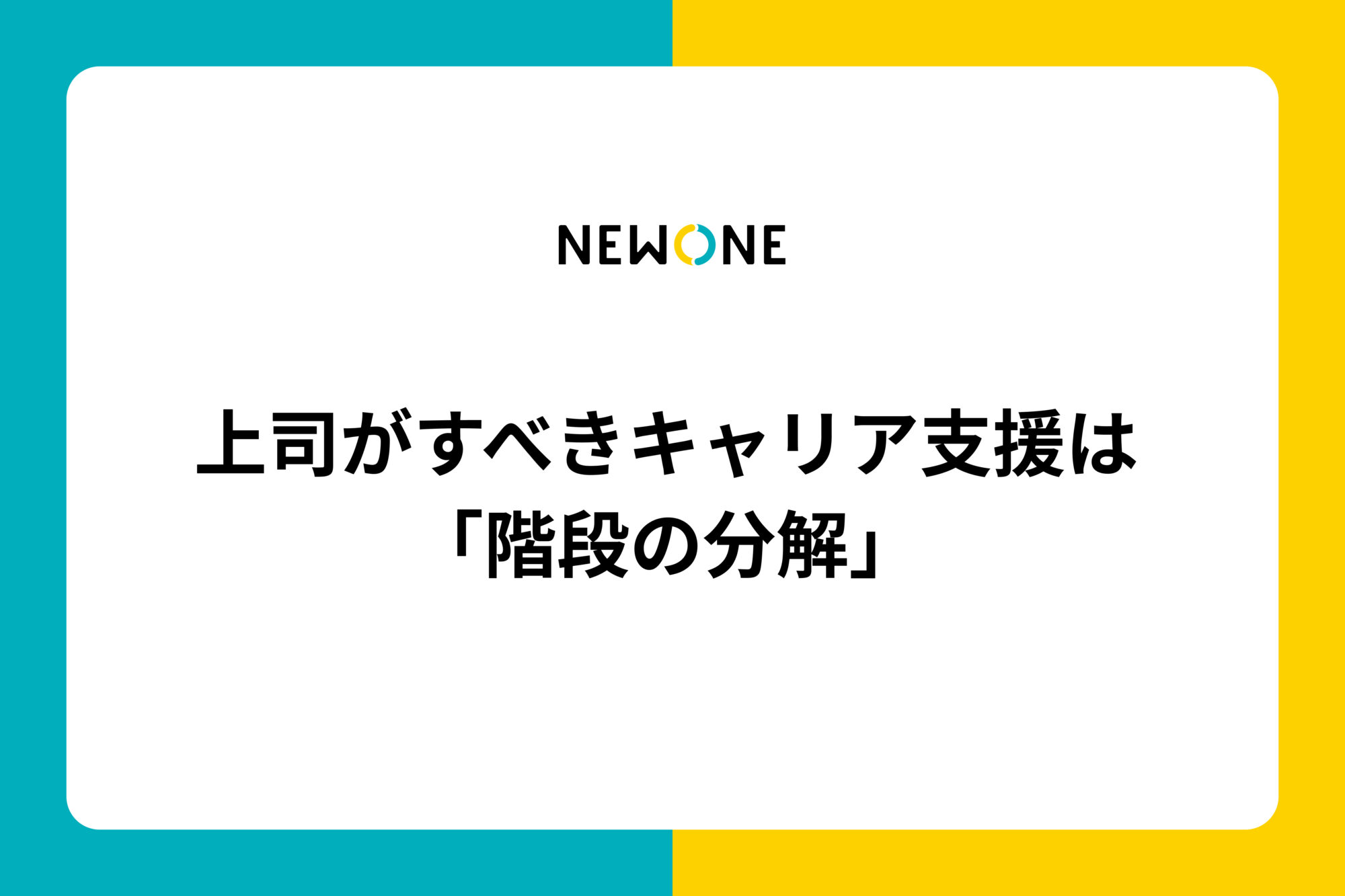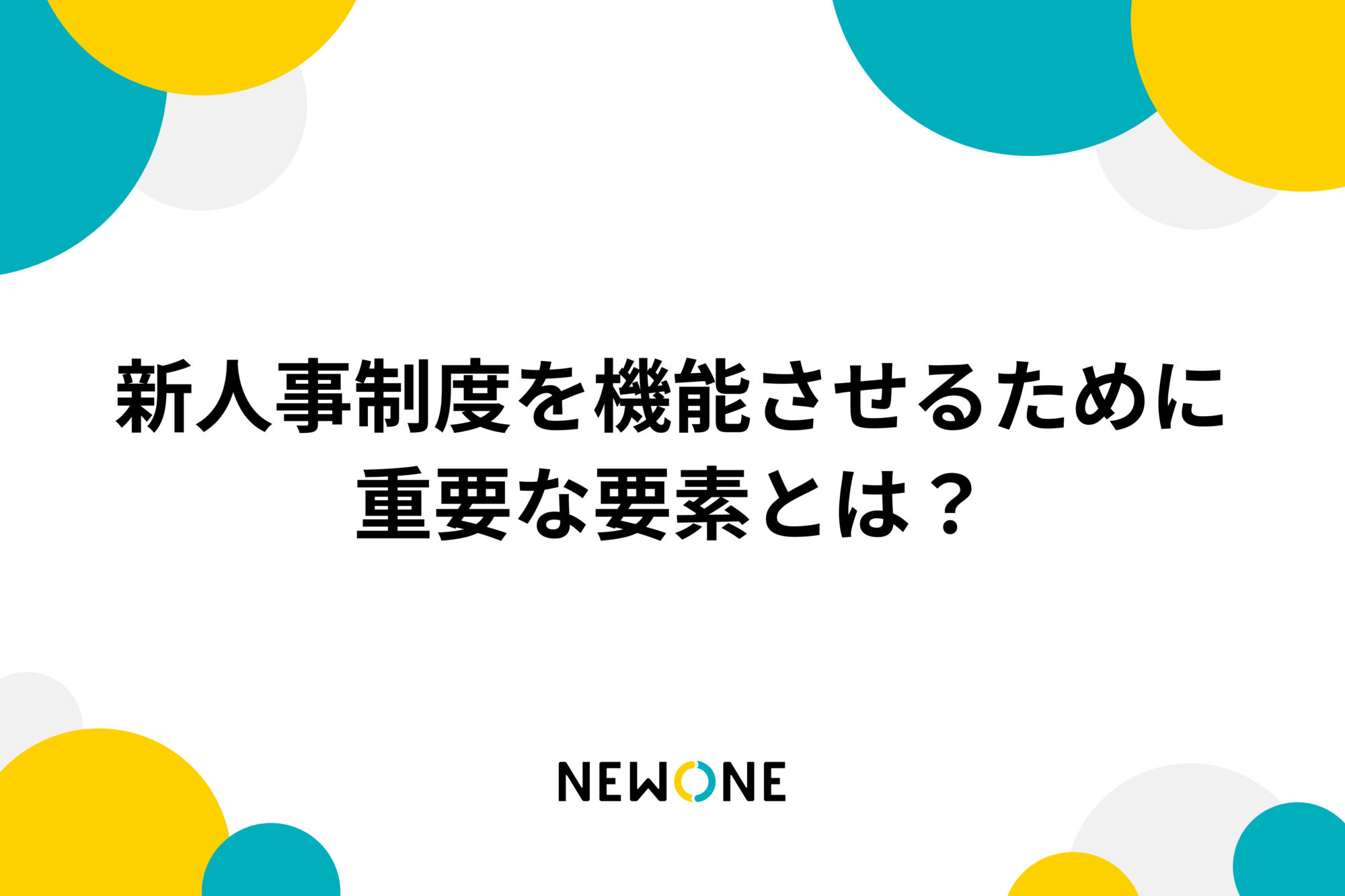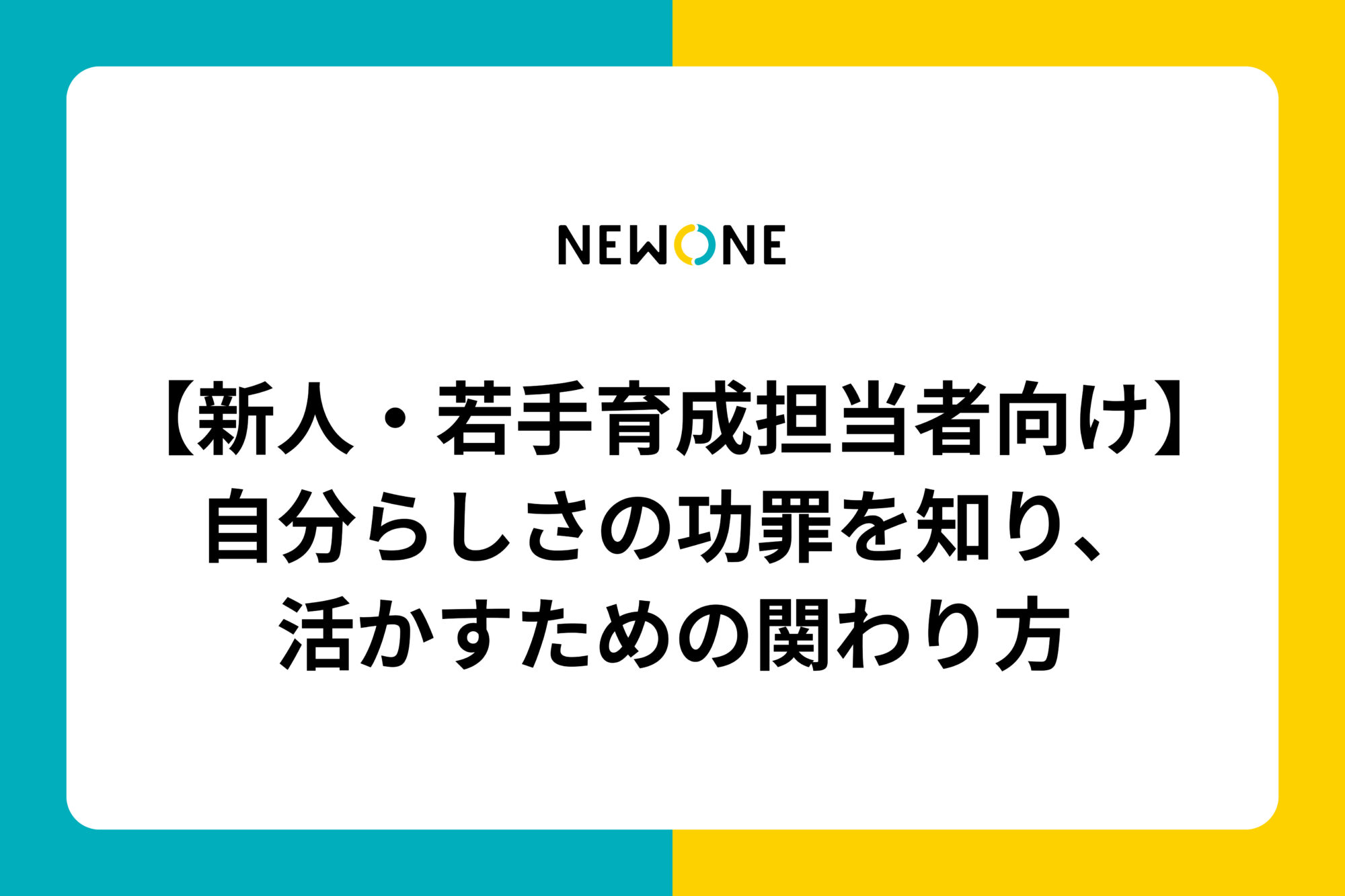
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
昨今、「自分らしく働きたい」という若手社員の言葉をよく耳にします。
しかし、現場の育成担当者の方からは、
「“自分らしさ”ばかりを気にして、組織に馴染もうとしない」
「“自分がやりたい方針とは異なるのでやりたくない”と言われて困っている」
という声も多く聞かれます。
実は、「自分らしくいたい」という思いは厄介なもので、その背景には、「とはいえ、ありのままの自分では受け入れてもらえないかもしれない」という恐れが潜んでいることが多くあります。そして、この“恐れ”を形づくっているのが、過去の経験から生まれたメンタルモデル(思い込みの構造)です。
たとえば、「成績が良くないと親に認めてもらえなかった」という経験をもつ人は、「努力して成果を出して初めて存在価値がある」というメンタルモデル(思い込みの構造)を持ちやすくなります。そのため、努力して成果を出すことを自然と続けられる一方で、成果が出せないと必要以上に落ち込み叱責を避ける等、自己防衛的になりやすい傾向があります。このように、メンタルモデルは人を成長させる原動力にもなりますが、同時に自分を過去の経験にとらわれさせる檻にもなり得るのです。
「自分らしさの2ステップ」
“自分らしさ”をより効果的に発揮するためには、次の2段階を意識することが大切です。
- メンタルモデルを知る
自分が何に強く反応するのか、どんなときに心がざわつくのかを知る
(例:「上司に否定されると必要以上に落ち込む」「他人と比べて焦る」など) - メンタルモデルが反応しているときの自分に気づく
「今の反応は自分の“こうあるべき”が刺激されたな」と一歩引いてとらえる
メンタルモデルは、自分ではなかなか気づけないものです。だからこそ、育成者の関わりが非常に重要になります。若手社員が“自分らしさ”にとらわれているとき、正面から否定するのではなく、対話を通して気づきを促すことが大切です。
たとえば、次のような問いかけが有効です。
「どんな言葉を言われると強く反応してしまう?」
「それは、どんなとき・どんな相手から言われることが多い?」
「その反応は、これまでのどんな経験から来ていると思う?」
こうした質問を通じて、本人が自分の中にある「自分らしさのとらわれ」に気づくことを支援します。さらに、「その考え方は今の環境でも役に立っていますか?それとも少し窮屈ですか?」と問い直すことで、本人が過去の延長線上から抜け出すきっかけを作ることができます。
このような対話によって、新人は“自分らしさを守る”段階から“自分らしさを活かす”段階へとシフトしていきます。
現代の“自分らしさ”とは、「好きなことをすること」ではなく、「自分の思い込みに気づき、それに縛られずに行動できる力」です。育成担当者は、新人の“とらわれ”を責めるのではなく、その背景を理解し、気づきを促す伴走者になることが求められます。
だからこそ、“本当の自分らしさ”に気づき、それを活かそうとする意識が、互いに気持ちよく働くための第一歩になるのです。
 桶谷 萌々子" width="104" height="104">
桶谷 萌々子" width="104" height="104">