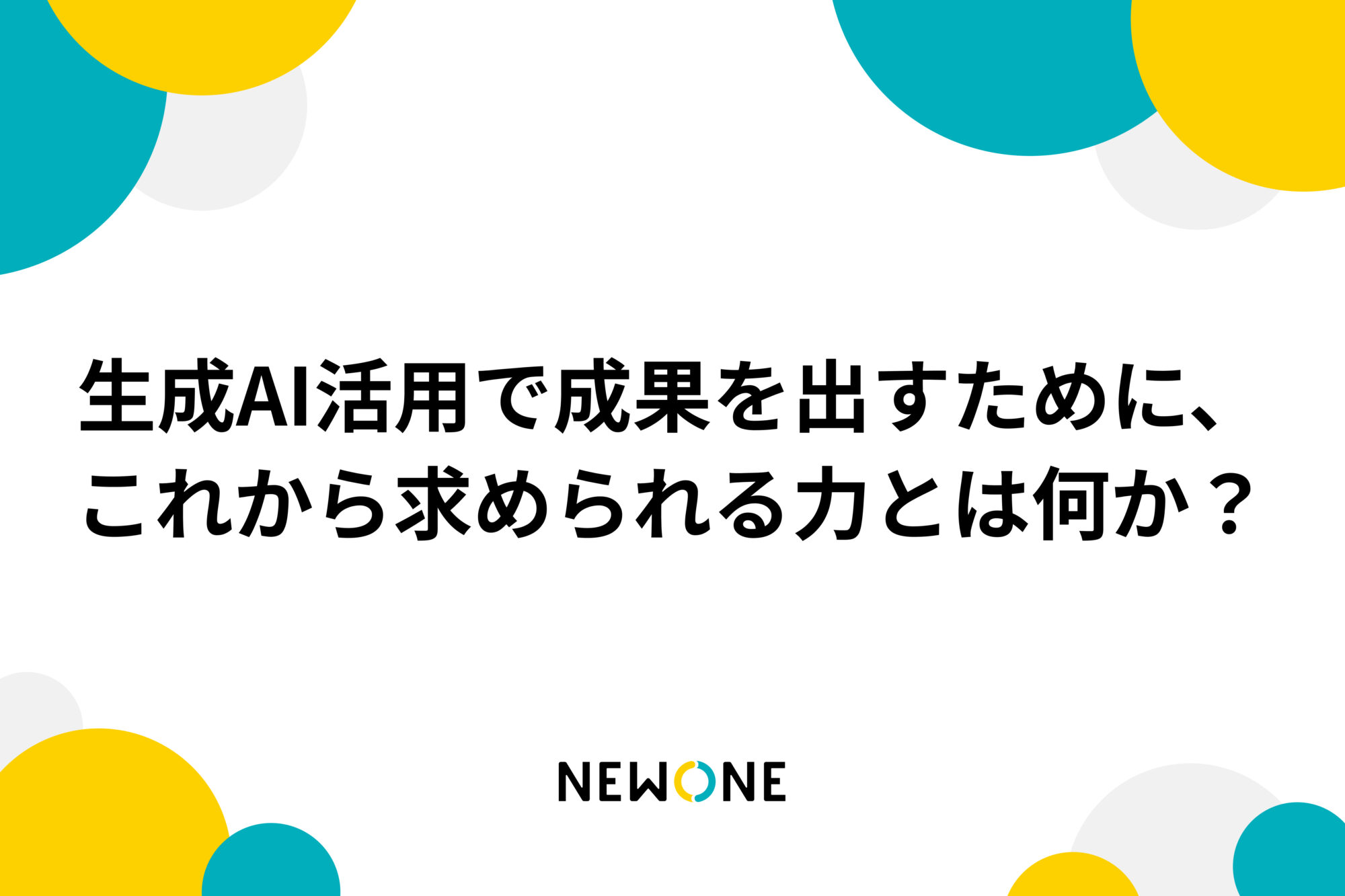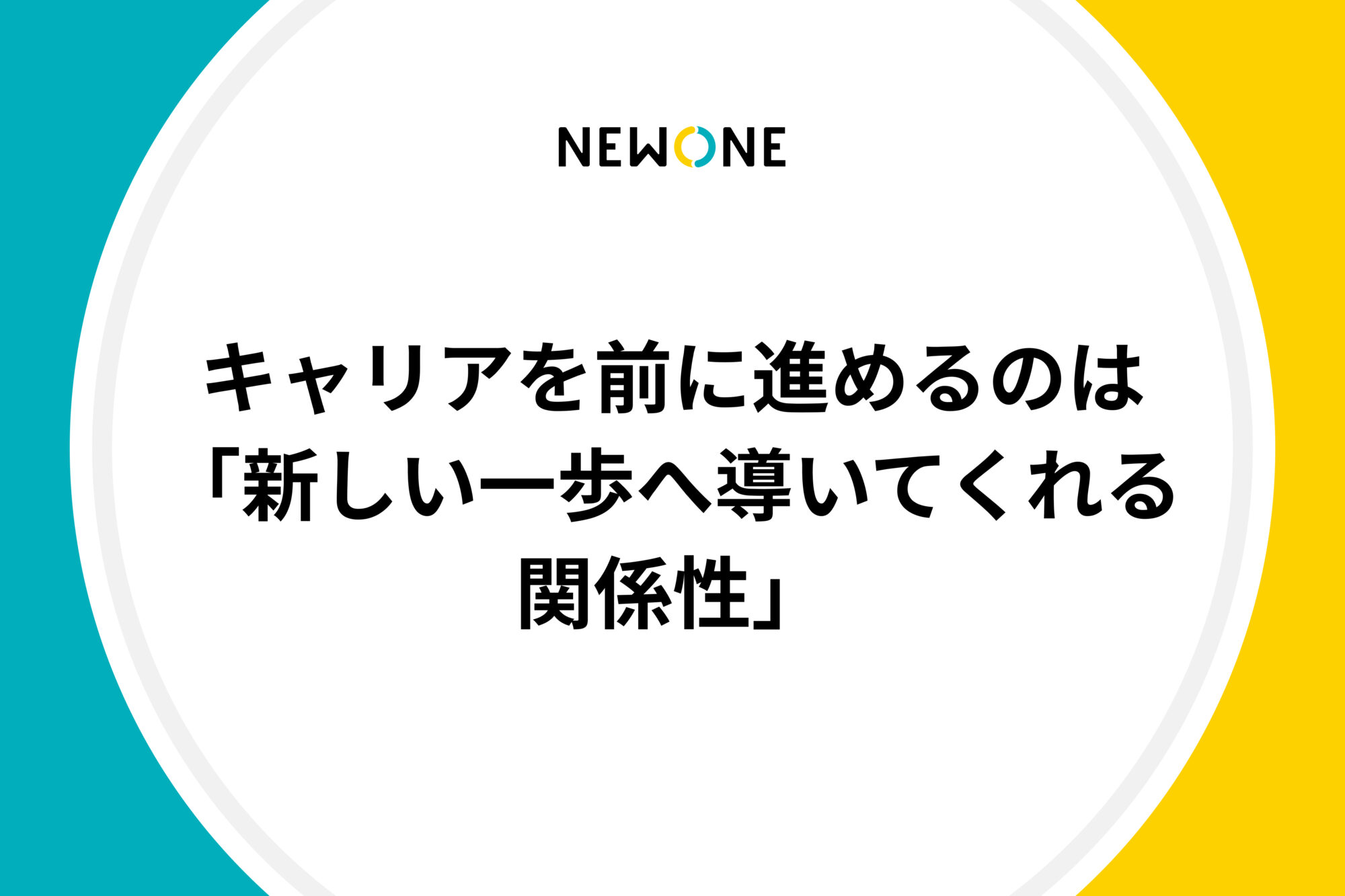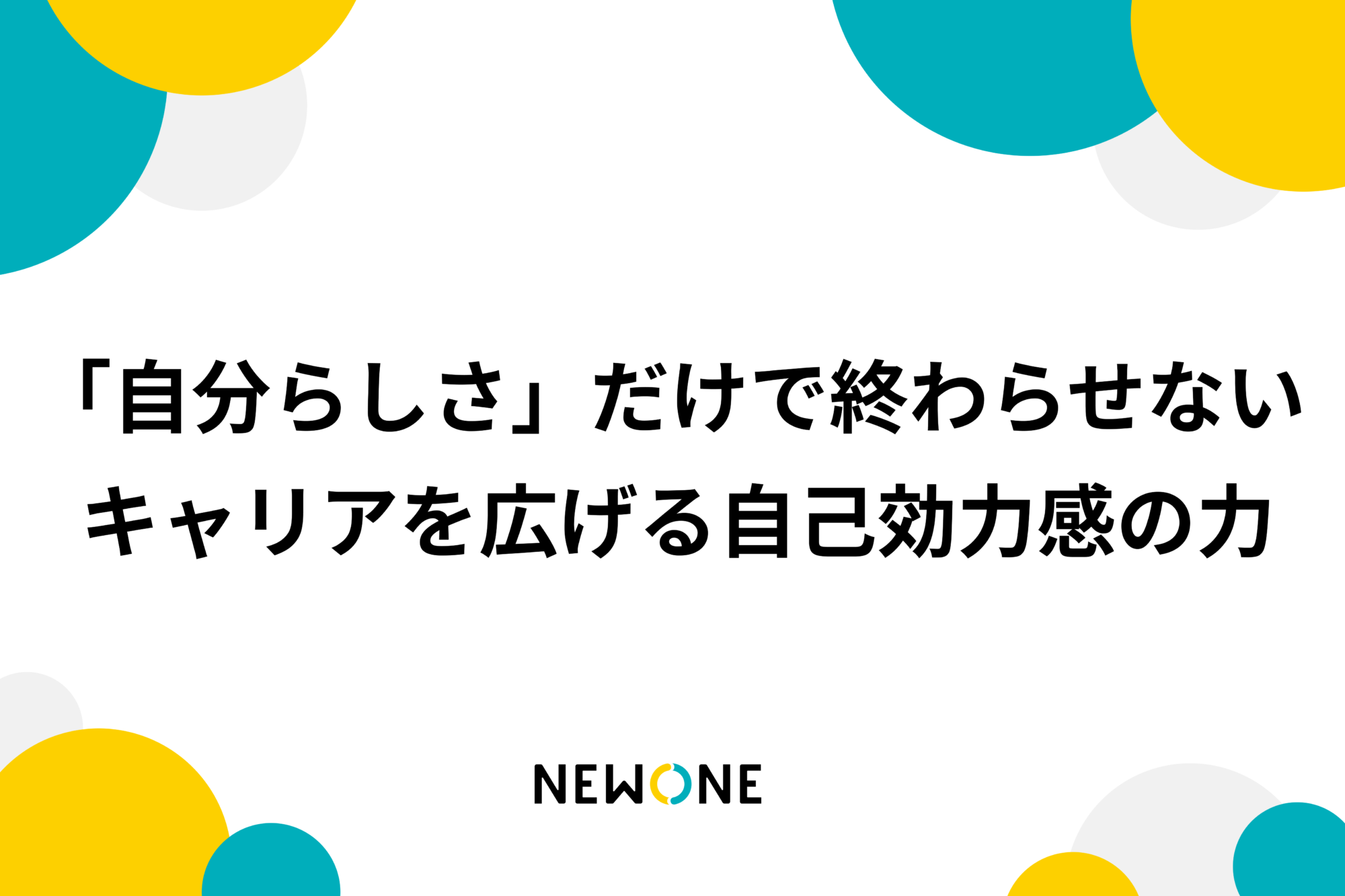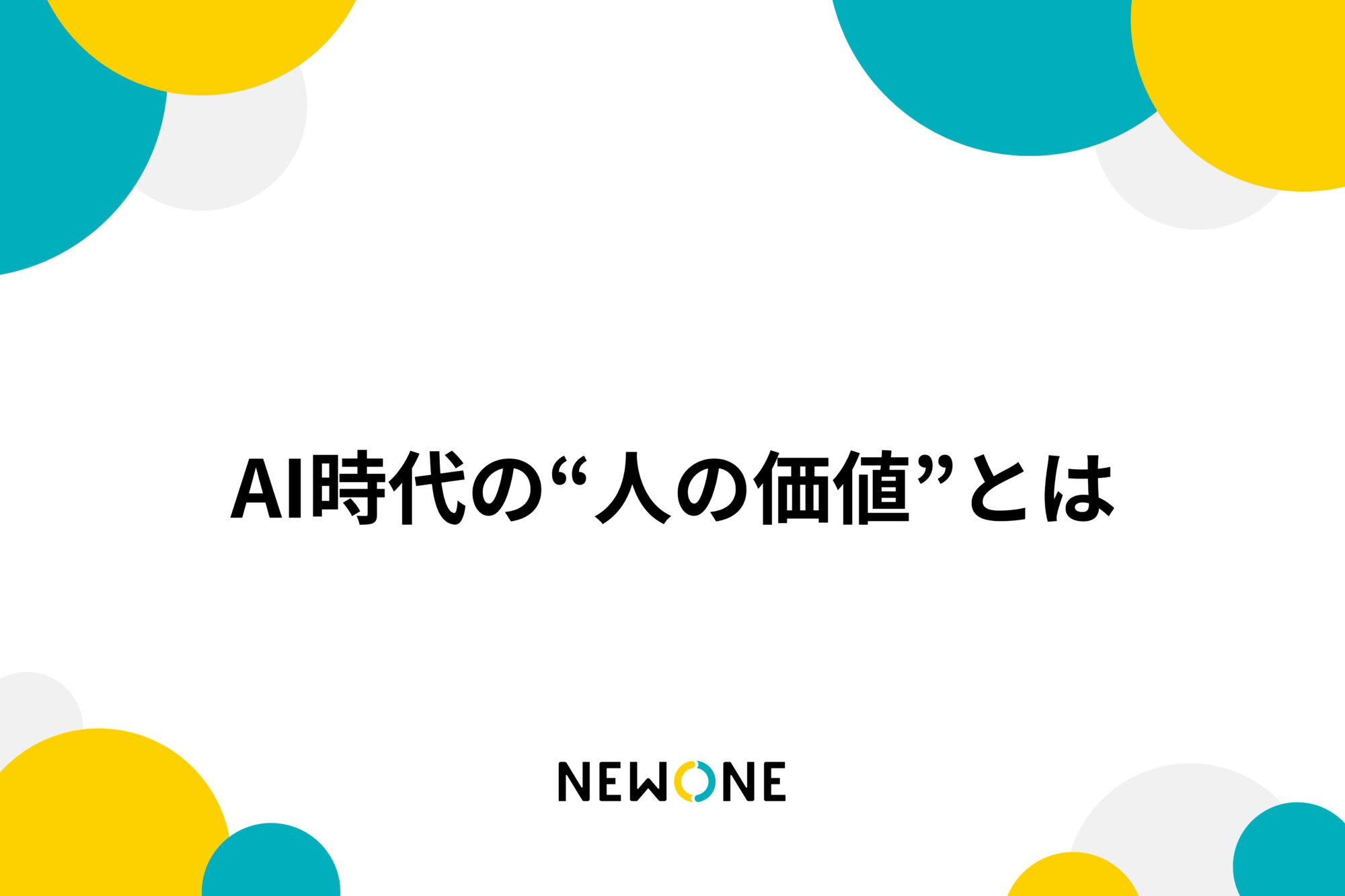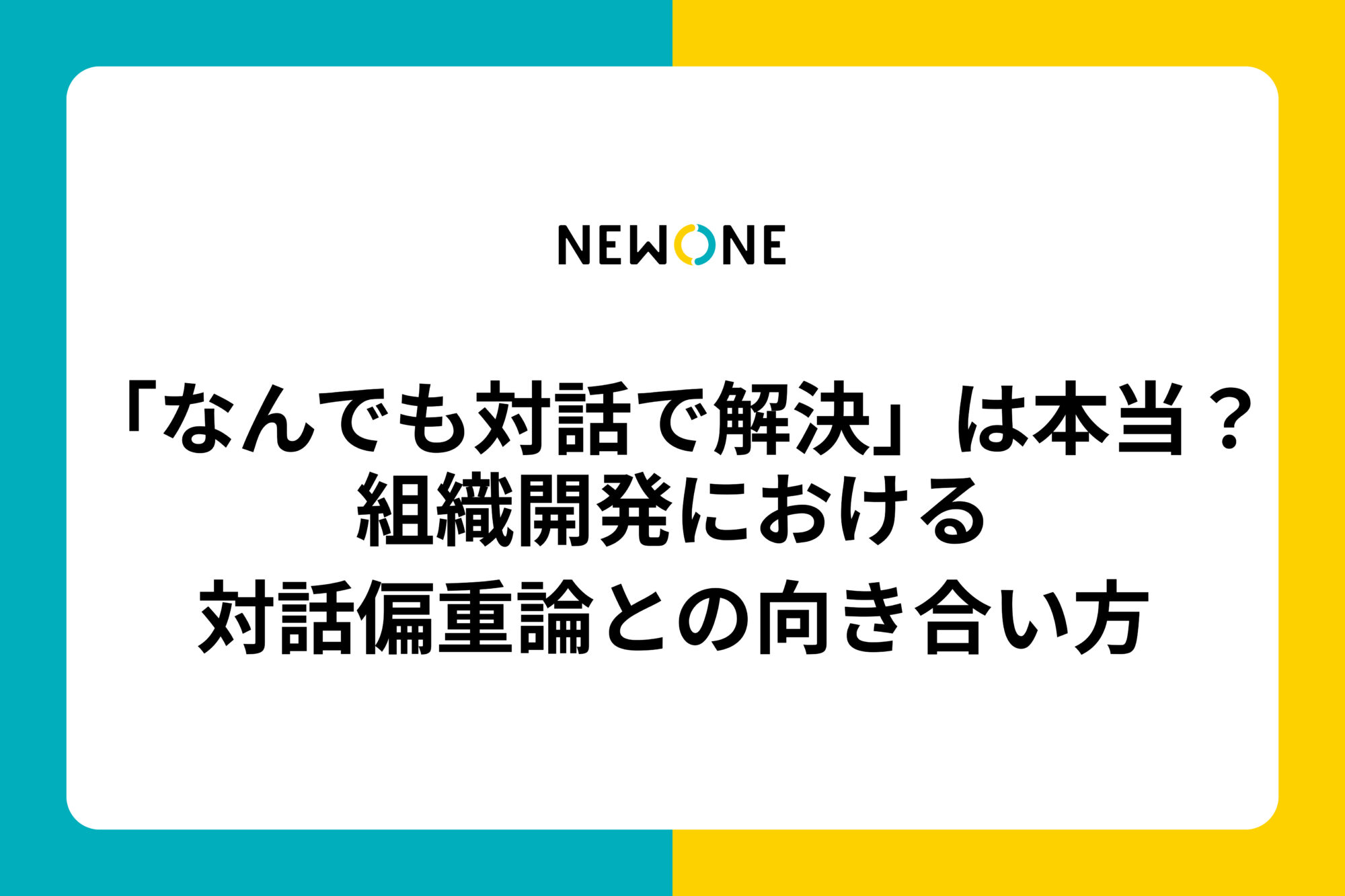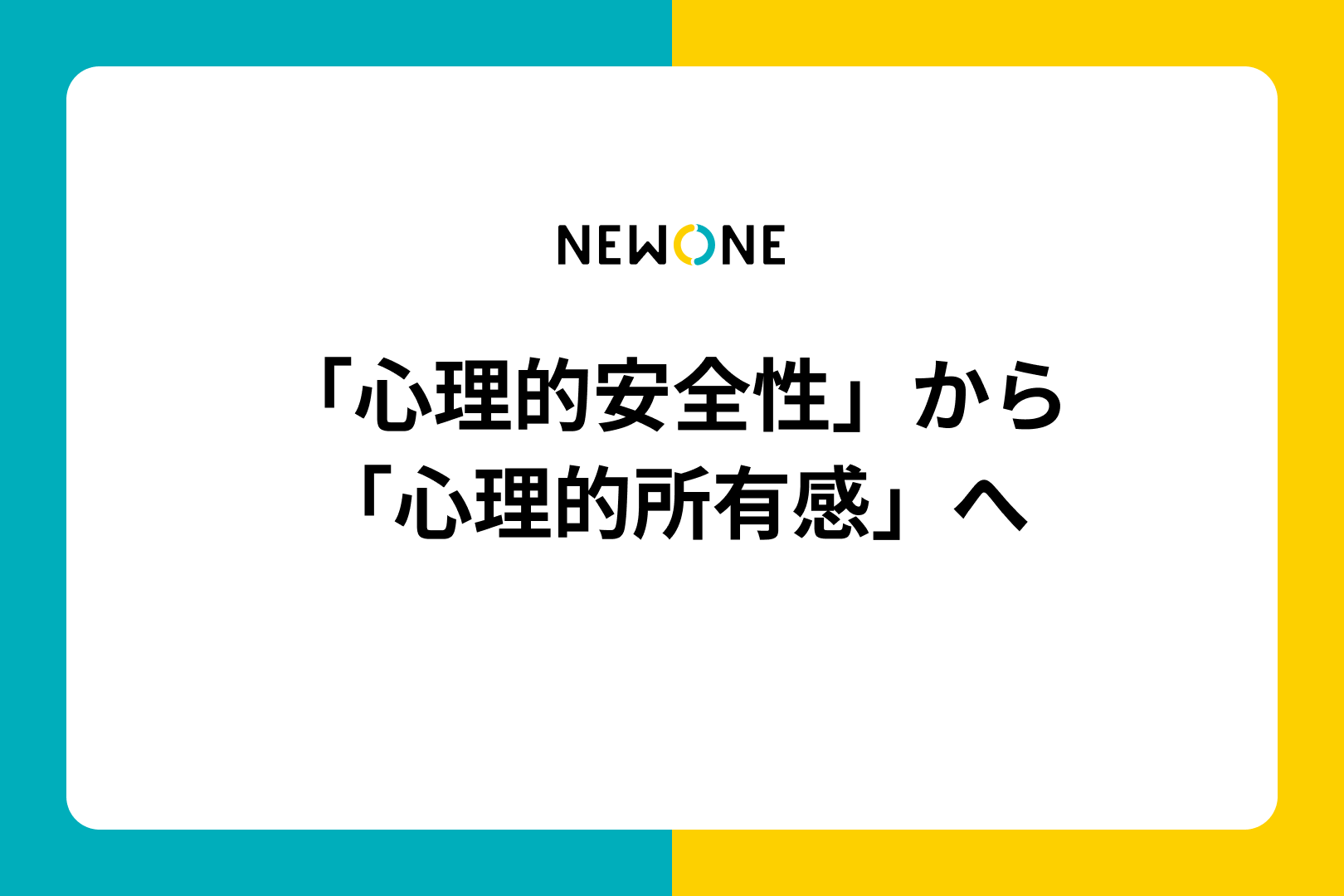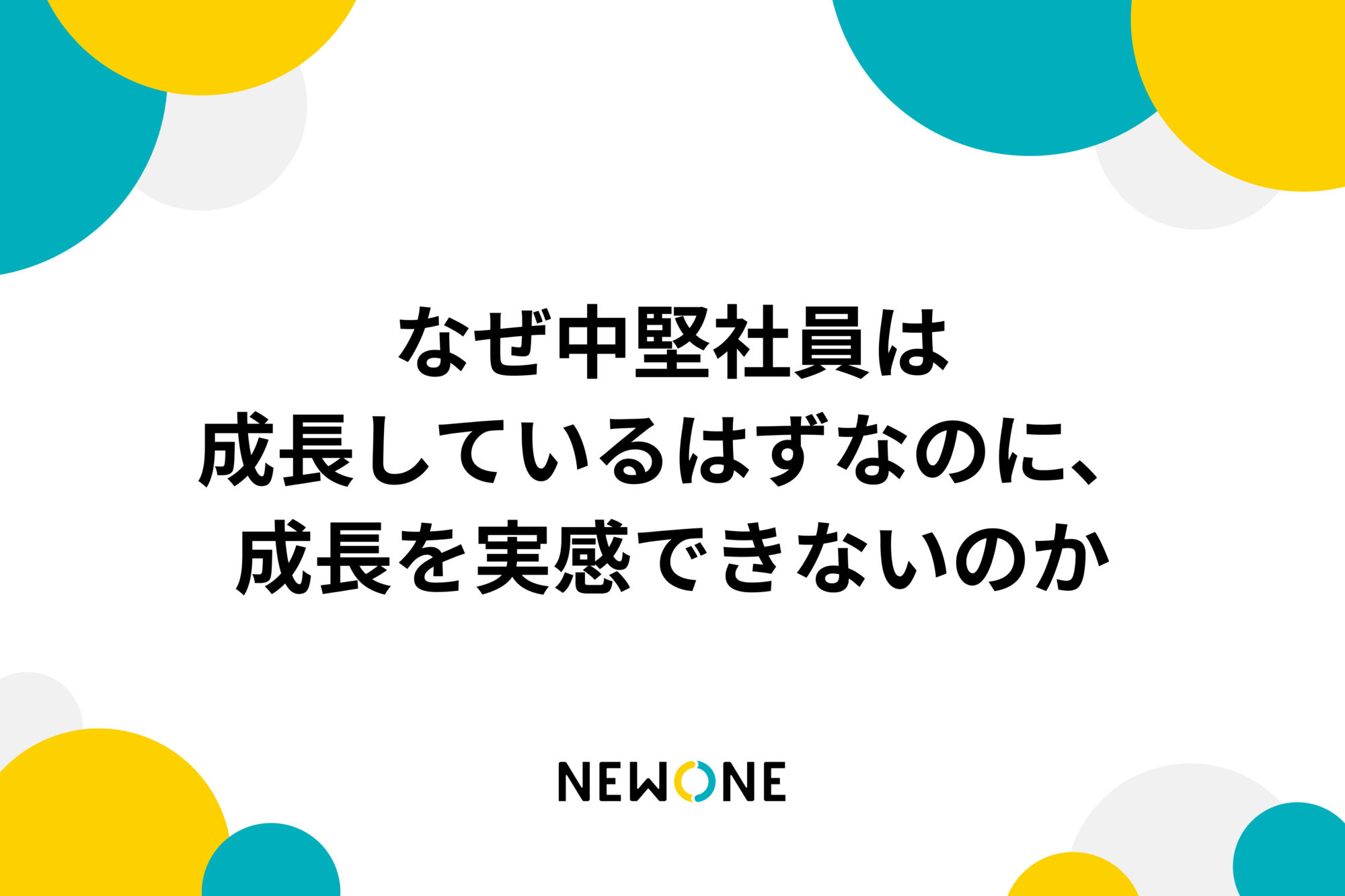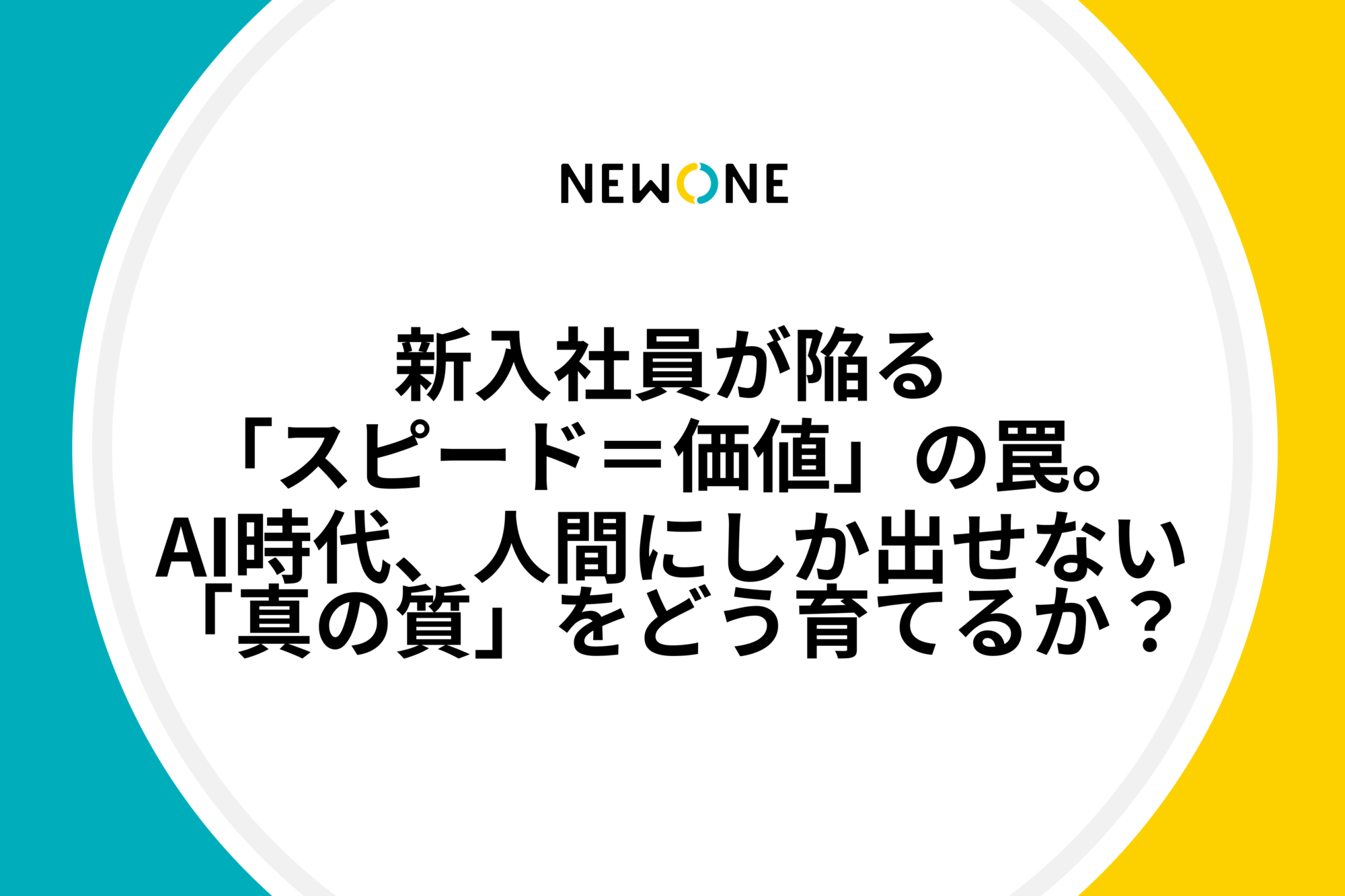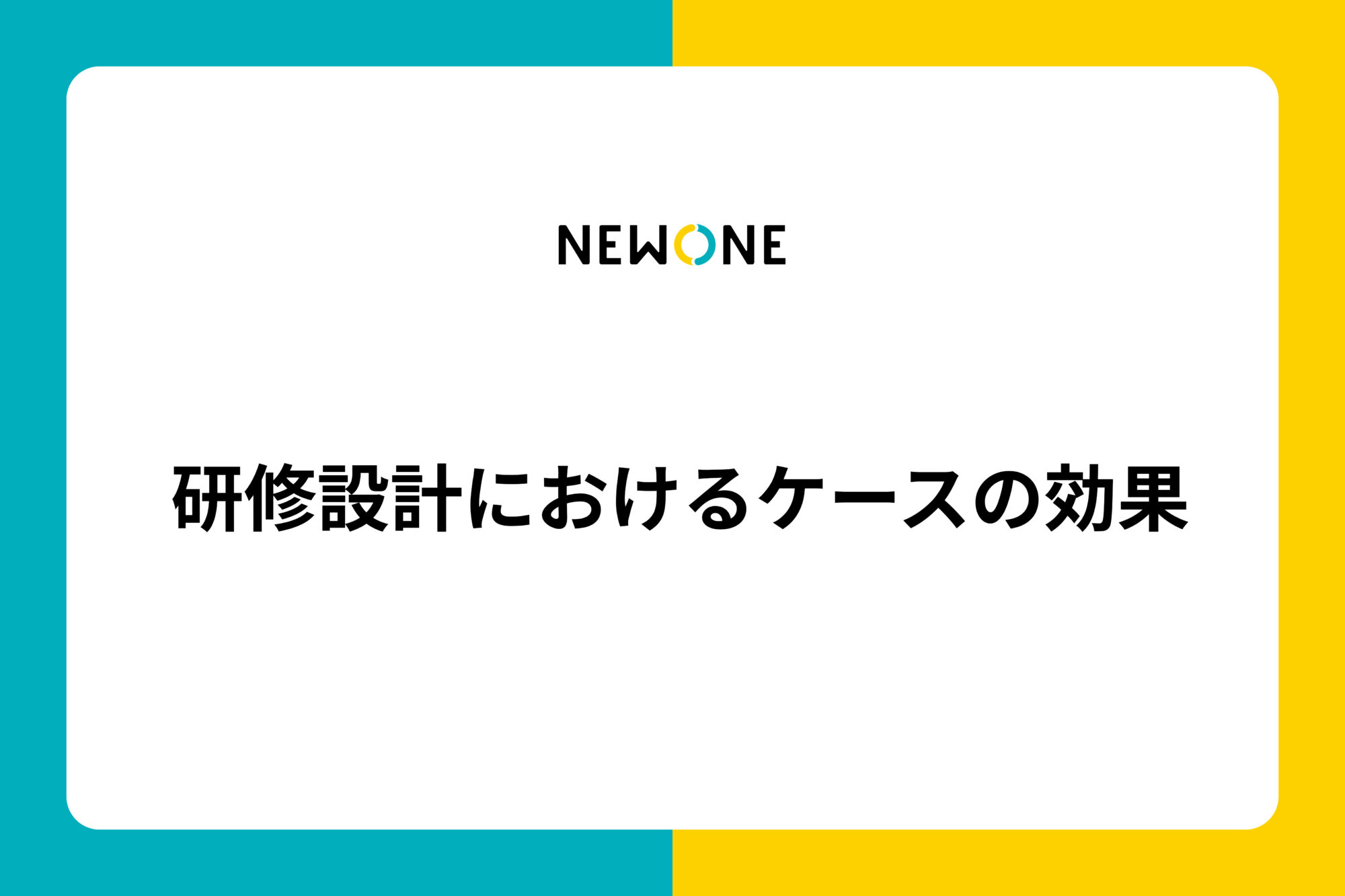
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
ケースを扱う研修を受けたり、実施したことがある方も多いのではないでしょうか。ケースとは、架空の事例や状況を題材に、参加者が意思決定や問題発見を行う研修手法です。例えば、
- 「この状況で適切なマネージャーの行動とは?」
- 「この部長の一日の仕事の中で、改善すべき点はどこか?」
- 「この特徴を持つ人に、どんな仕事を任せれば良いか?」
といった問いに取り組むイメージです。今回は研修における「ケース」を行う意義を考えていきます。
ケースを行う意義
ケースに対する批判的な見方として、
「ケースなんてやらなくていいから、直接スキルを教えてほしい」
「結局、学ばせたいことがあってケースをやらせているんでしょ?」
というように、狙いを見透かして、斜に構えてしまう方もいるかもしれません。
確かに、ケースは一見すると“遠回り”に見えて、もっと直接的に教えてほしいともどかしく感じるかもしれません。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
自分の癖や認知の傾向に気づく
勿論ケースをやる理由は、受講者に伝えたい内容や起こしたい変化を起こしやすくする、という目的もあります。一方で、研修で設計された目的を越えて、受講者各々に対しても効果があるものであると考えています。
特に大きいのは、自分のクセや認知の傾向に気づけることです。
- 同じ状況下で考えたとしても、人によって意思決定やアウトプットは異なる
- グループワークを通じてその違いに触れることで、自分の思考の偏りや特徴を知ることができる
この「違いに気づく」ことこそが、ケース研修の醍醐味です。
自分のクセや認知の傾向に気づけることは、自分らしさへの理解・キャリアアンカーの発見・リーダーシップ開発(自己認知の深化)など、さまざまな形で活かすことができます。
通常の会話ではなく、ケースを介することで、「環境のせい」として語られがちなことも、ケースでは環境条件が固定されているため、むしろ個人の特性が際立ちます。
まとめ
普段の会話では、環境の捉え方は不変の事実として語られる事が多いですが、意外と環境の捉え方に個人の特性が出る一方、そのクセを見逃してしまいがちです。一方ケースでは、その環境にあたる部分が固定されるため、まったく同じ状態から対話が始まり、同じ条件で意思決定するため、その人なりのクセに気づきやすくなります。
ケースは、単なる“研修を目的通りに進めやすくするツール”ではなく、自己理解につながるきっかけとなるものです。
NEWONEでは、多様なケースを活用し、対話とファシリテーションを通じて「違いから学ぶ」体験を提供しています。 ご興味のある方はぜひお問い合わせください。
 小関 一矢" width="104" height="104">
小関 一矢" width="104" height="104">