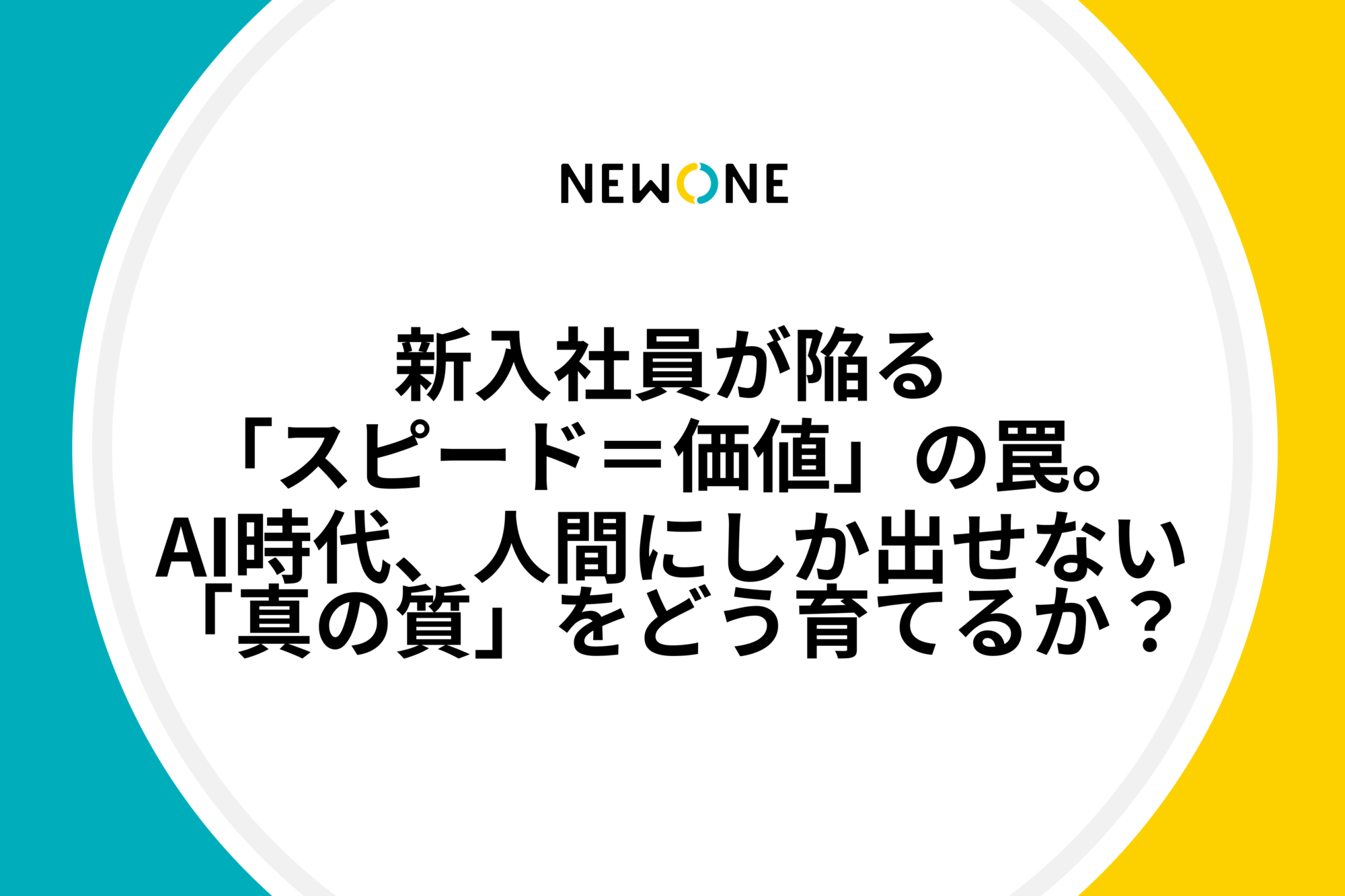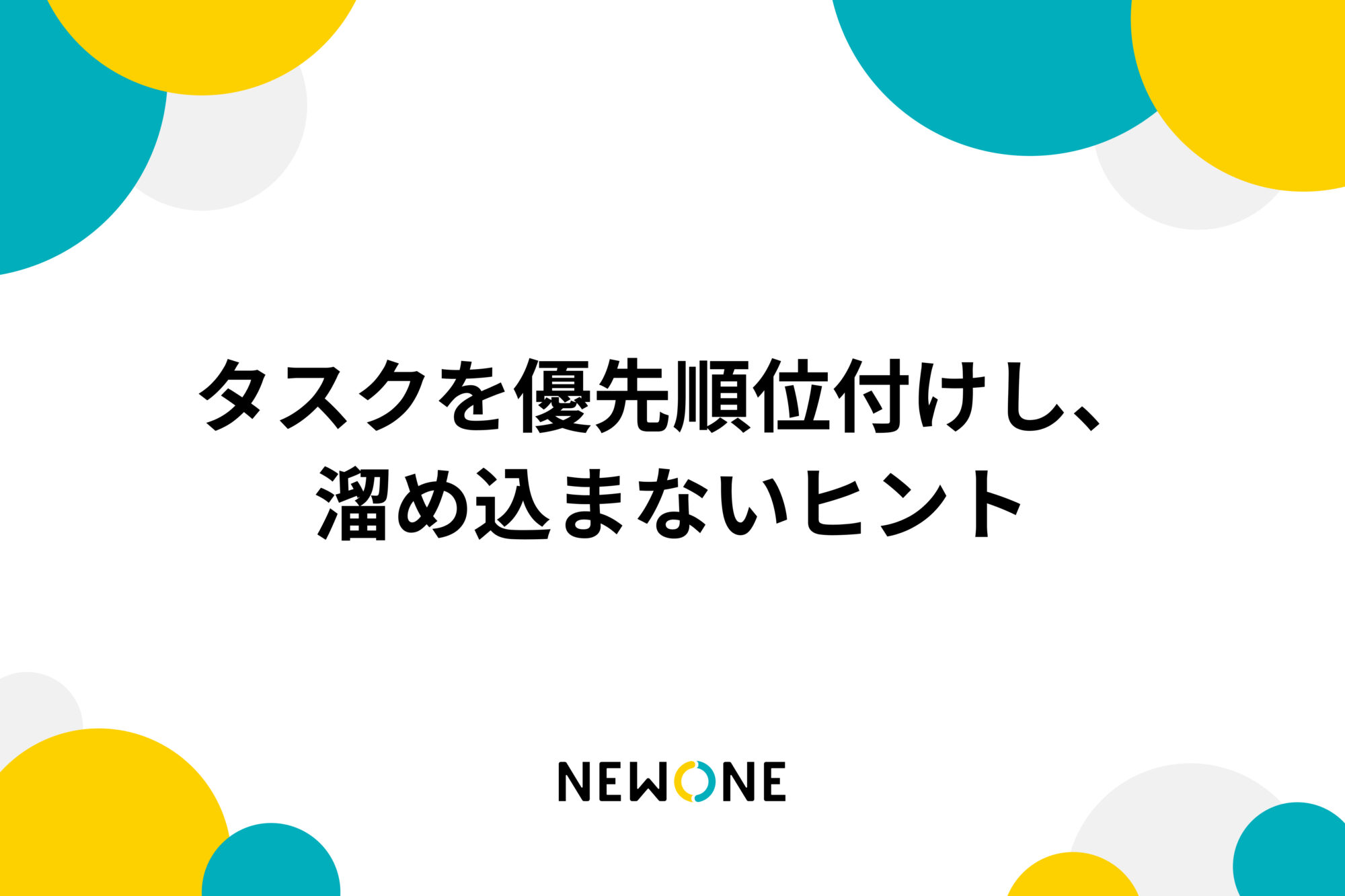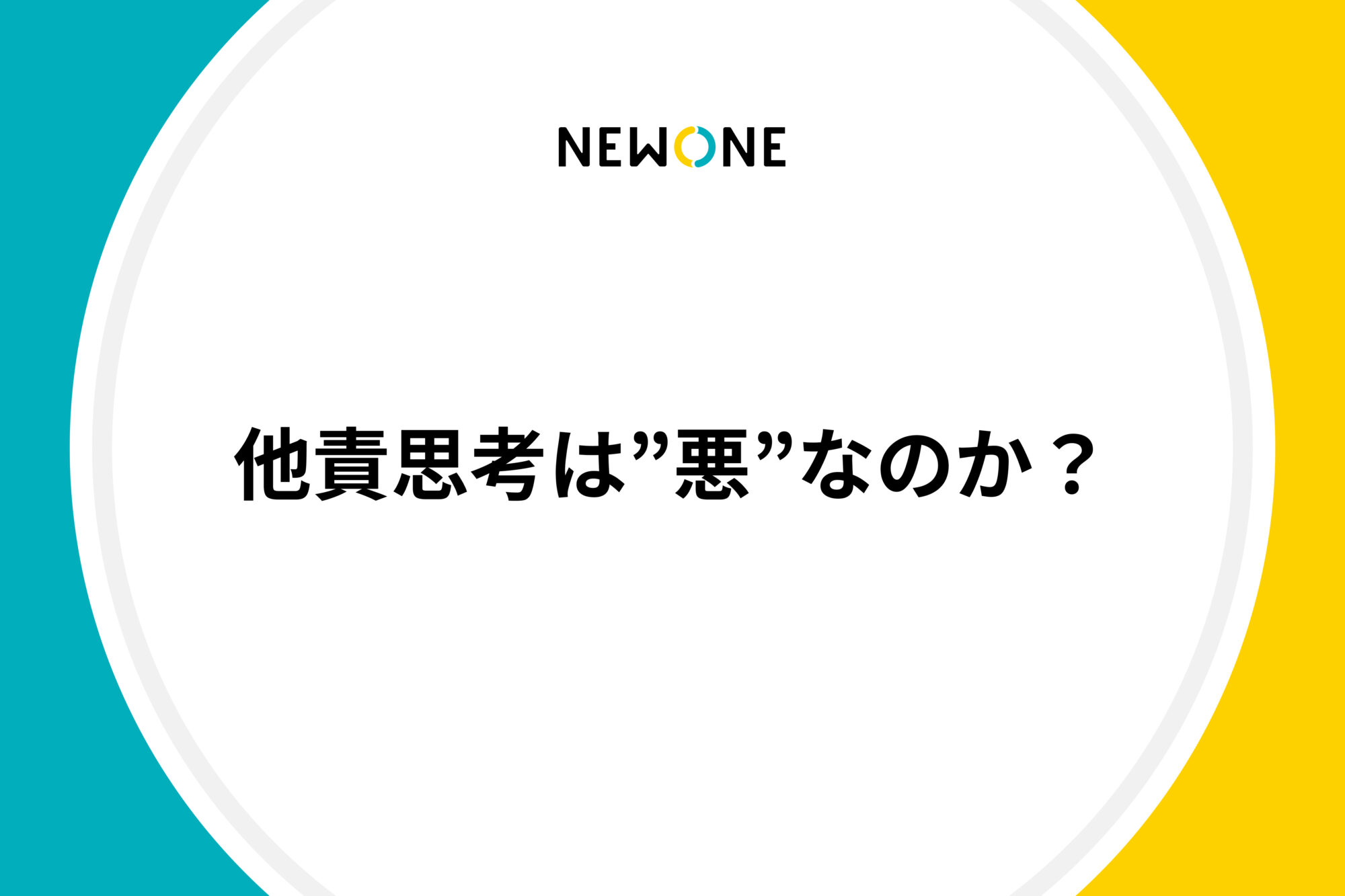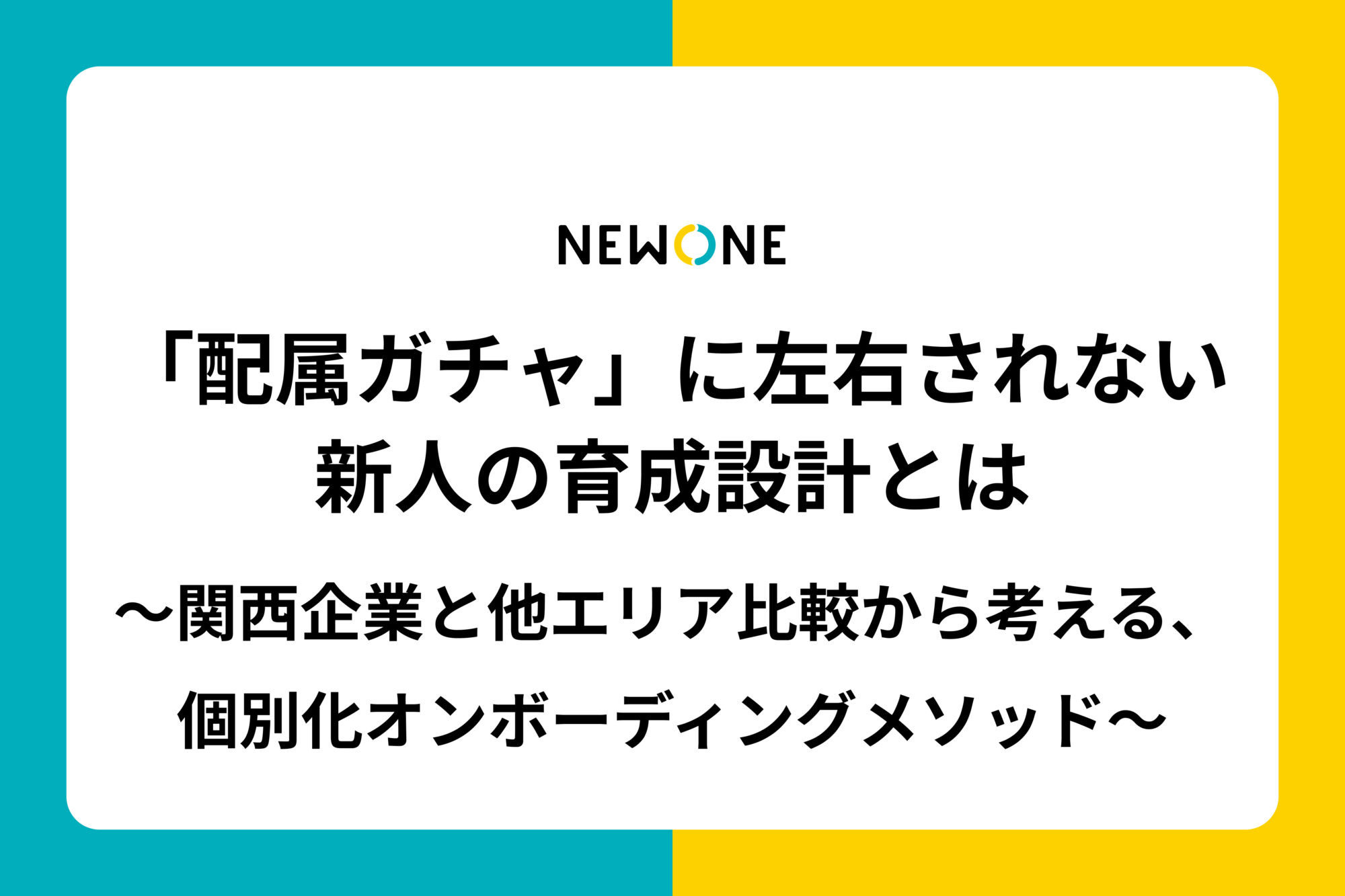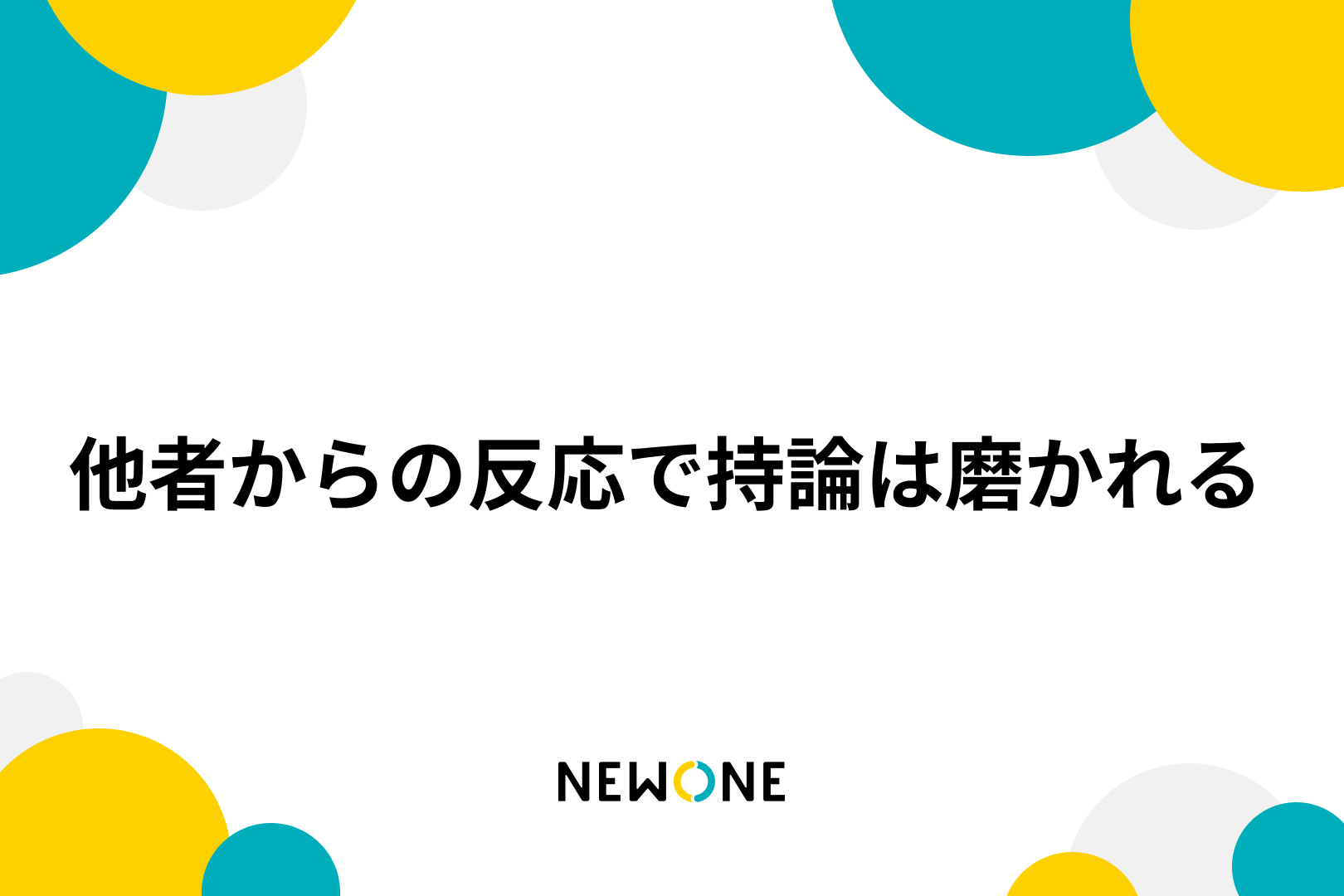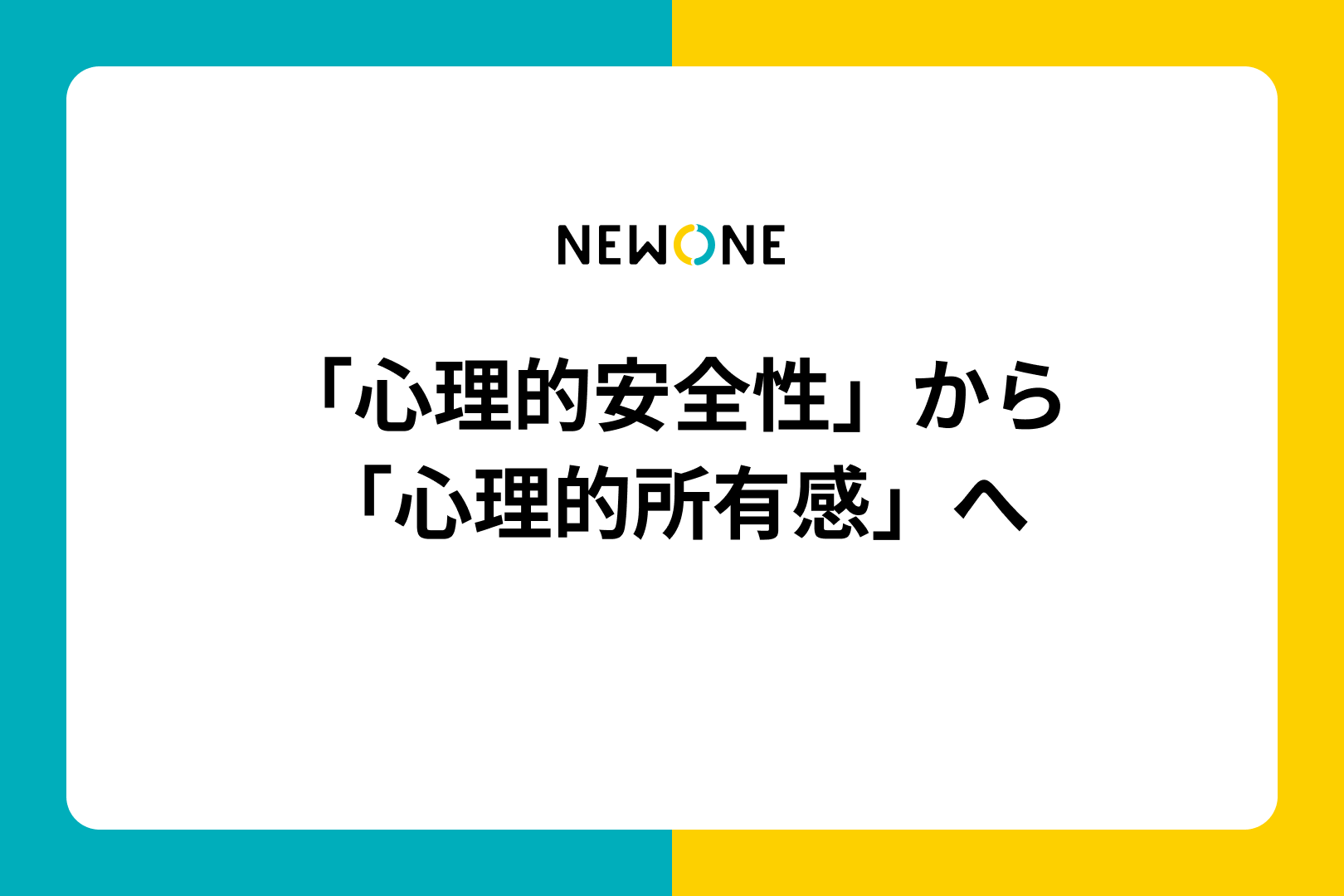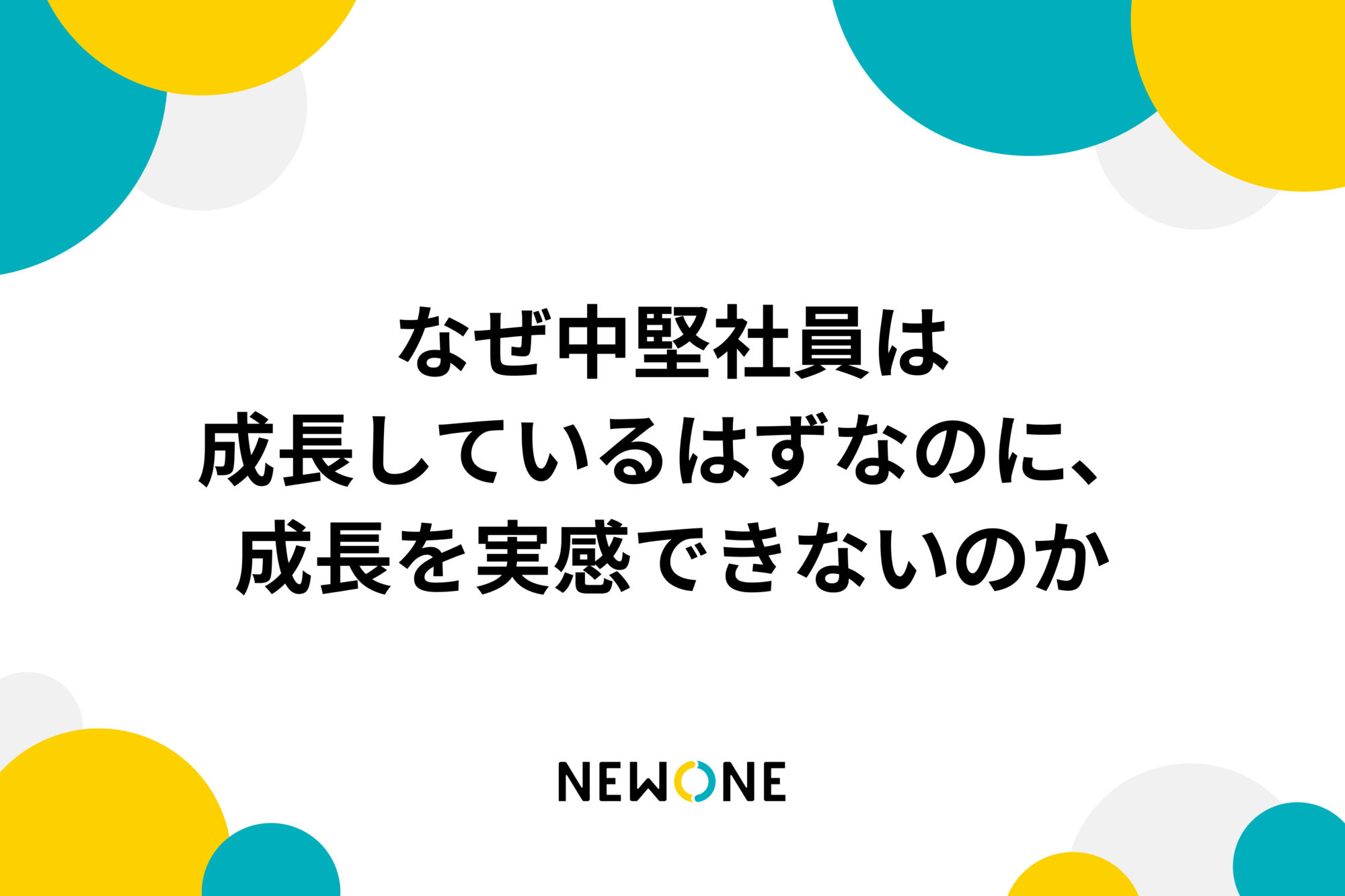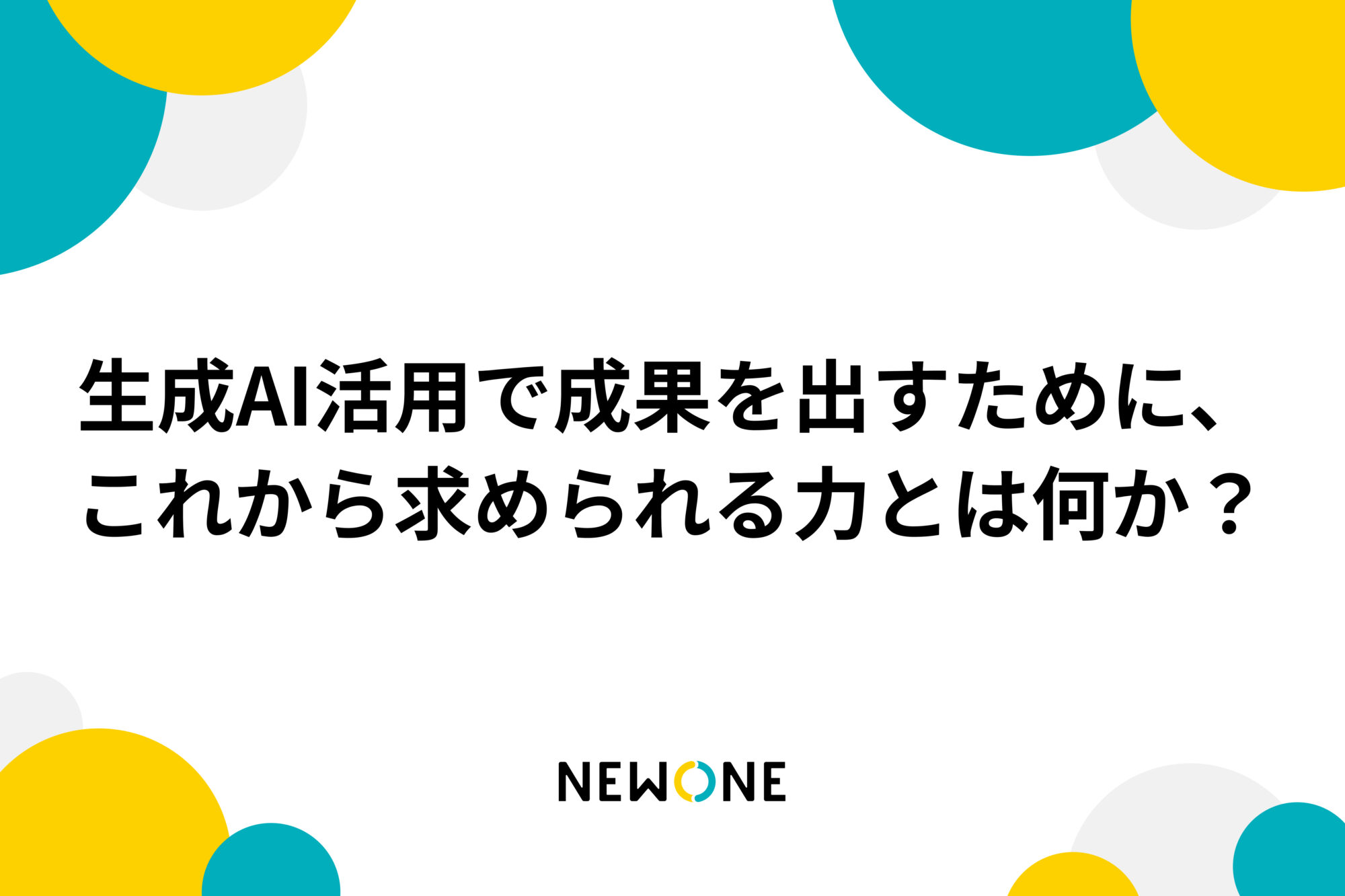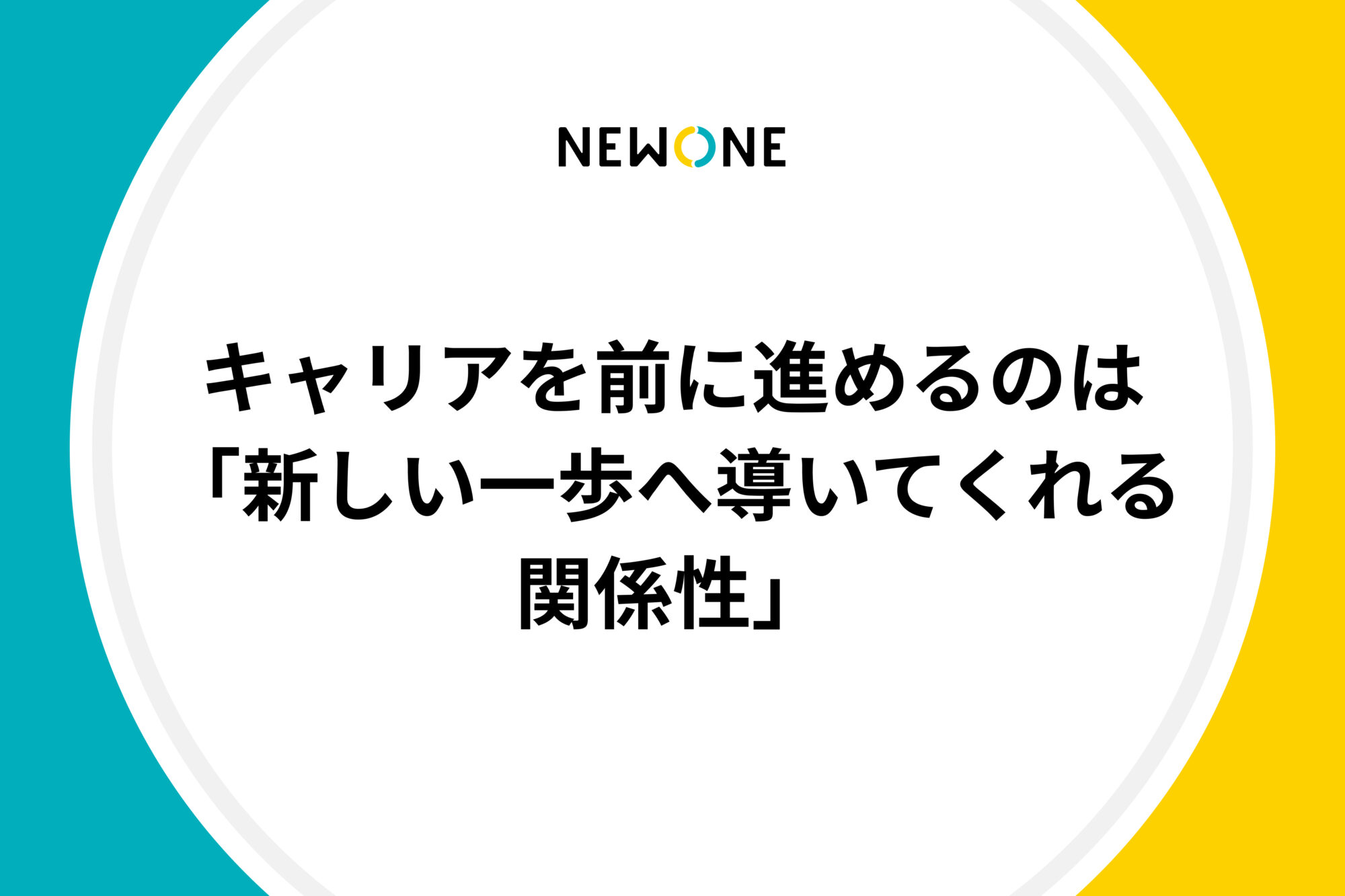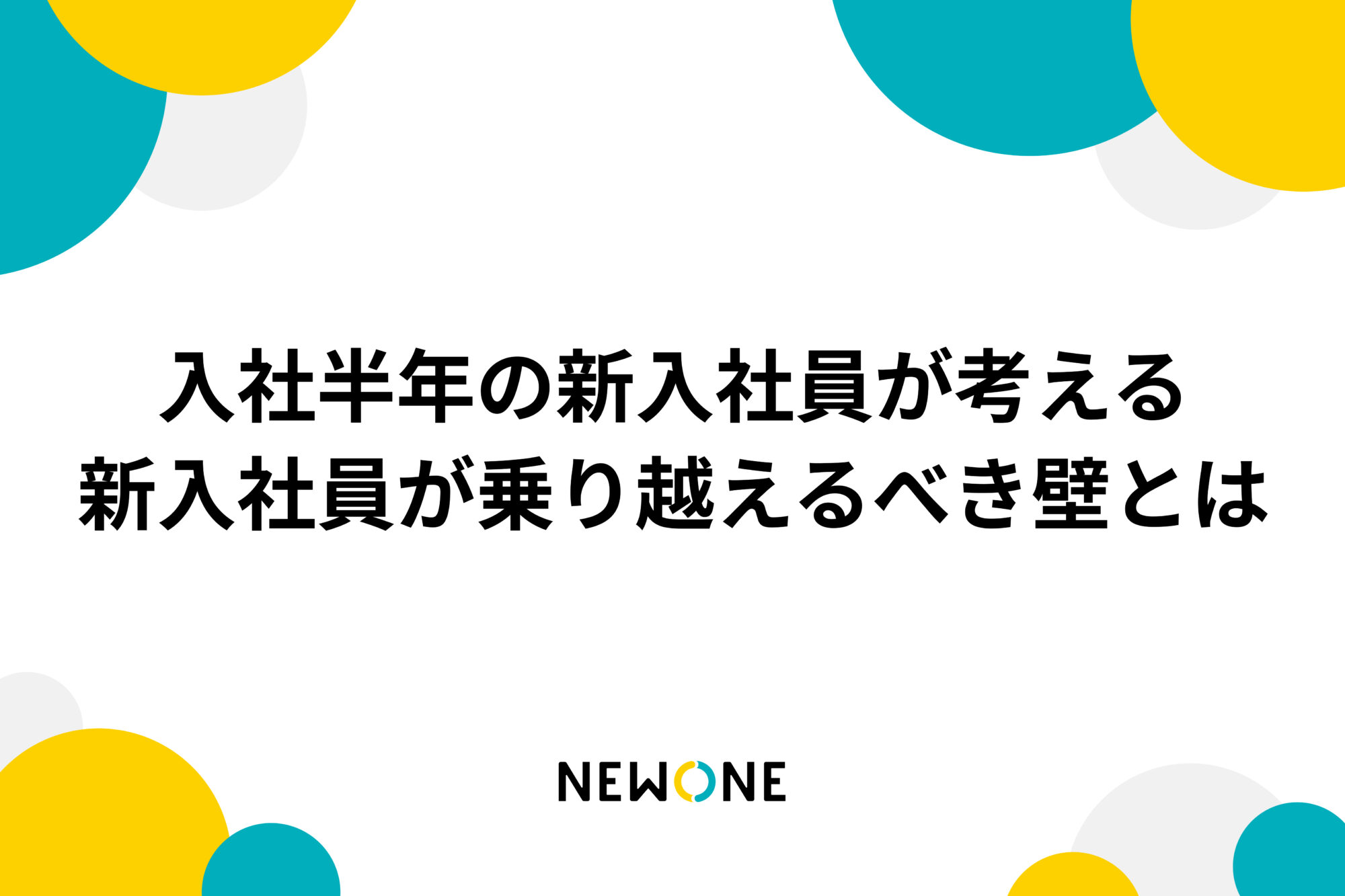
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
昨今人材不足が叫ばれるようになり、離職の低下に加えて、早期戦力化も求められるようになってきています。そろそろ入社から半年ほどが経ちますが、同じ新入社員でも仕事を上手く進められる人とそうでない人が分かれてくるタイミングなのではないでしょうか。仕事を上手く進めることができる新入社員と、そうではない新入社員ではどのような違いがあるか、実際に新入社員である立場から考えていきます。
「新入社員が仕事を進めるうえで直面する大きな壁」
新入社員が仕事を進めるうえでぶつかる最も大きな壁として、「周囲の巻き込み」があると思います。この背景としては2点あると考えられます。
1点目は、社会人と学生との責任の差です。学生時代は授業料を払って学ぶ立場であり、困ったときには先生が助けてくれる環境がありました。また、お金を稼いでいてもアルバイトとして働く人が多く、責任の範囲は限られていたと思います。これに対して社会人はお金を受け取る立場になるため、入社当初は周囲に助けてもらえても、時間が経つにつれて求められる責任が大きくなり、次第に自分で対応しなければならなくなります。
2点目は知識やスキルがない中で成果も求められる点です。様々な仕事はありますが、初心者用の仕事は何一つとしてありません。そのため社会人となり知識やスキルがない中で難しい仕事にも取り組む必要があります。この2点から社会人と新入社員とで人を巻き込む必要があるかどうかに違いが生まれます。本来であれば、成果を出すために必要に応じて上司や先輩などの人を巻き込む必要がありますが、信頼関係ができていない・忙しそうで話しかけづらいなどのブレーキがかかることで、結果的に1人で仕事を抱え込んでしまうという負のスパイラルが起こります。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
「壁の種類を知る」
この壁を乗り越えるためには、人を巻き込む上での壁の種類を知り、それに合わせた行動を行うことが重要です。人を巻き込む上での壁を私は3つのレベルに分類しました。
レベル1:関係も関連もある人を巻き込む(例:直属の上司・教育担当・同じチームの先輩)
レベル2:関係はあるが関連がない人を巻き込む(例:他部署の同期・以前OJTで関わった先輩など)
レベル3:関係も関連もない人を巻き込む(例:他拠点・他職種・初対面の人)
「関係」とは、「話したことがある」等、面識や信頼関係があることを示し、「関連」とは、「業務を一緒に進めているか」を意味しています。そのためレベル1→3になるほど巻き込むことが難しくなっていきます。
そのため、レベル1の人に対しては通用したことが、レベル2や3の人には通用しないということが多々起こります。これにより、レベル2や3の人を巻き込むときは、相手と認識を揃える姿勢や、他の人の力を借りる等+αの行動が必要になります。
それでは、それぞれのレベルの人を巻き込む際に、どのような工夫が必要なのでしょうか。
レベル1:関係も関連もある人を巻き込む
・相談を「報告+提案」で行う
例:「○○の件で、△△をやってみようと思うのですが、一度方向性を確認させてください」
・日常的な小さな感謝を伝える
例:「昨日のアドバイスを試したらうまくいきました!」
レベル2:関係はあるが関連がない人を巻き込む
・「相談」ではなく「意見を聞かせてほしい」と頼む
例:「○○の件で、他部署の視点から見てどう感じますか?
・上司・先輩を媒介に紹介してもらう
例:「○○の件なら、△△さんが詳しいよ」とつないでもらい、事前に根回ししてもらう
レベル3:関係も関連もない人を巻き込む
・「なぜあなたにお願いしたいか」を明確に伝える
例:「御社の○○の取り組みを拝見して、ぜひお話を伺いたいと思いました」
・最初は“お願い”ではなく“学びの姿勢”で接する
例:「○○の進め方を勉強したく、10分だけお時間を…」
このようなポイントを踏まえ、どのパターンの人を巻き込む必要があるのかを認識し、パターンに応じた動きを考えることが重要です。
この考え方ができるようになれば、人を巻き込む壁を乗り越え、人材の早期戦力化にもつながるのではないでしょうか。
 森 陽輝" width="104" height="104">
森 陽輝" width="104" height="104">