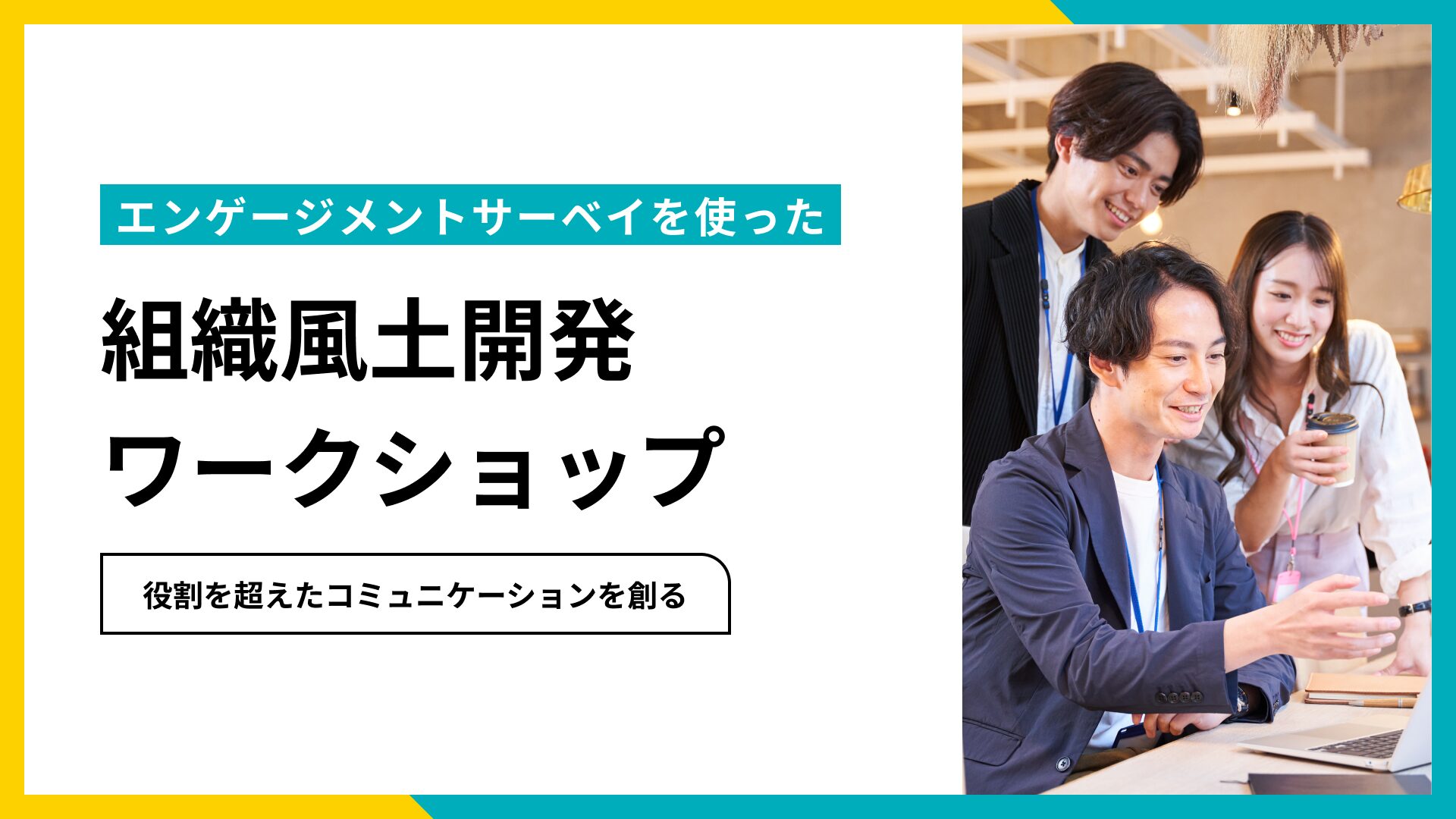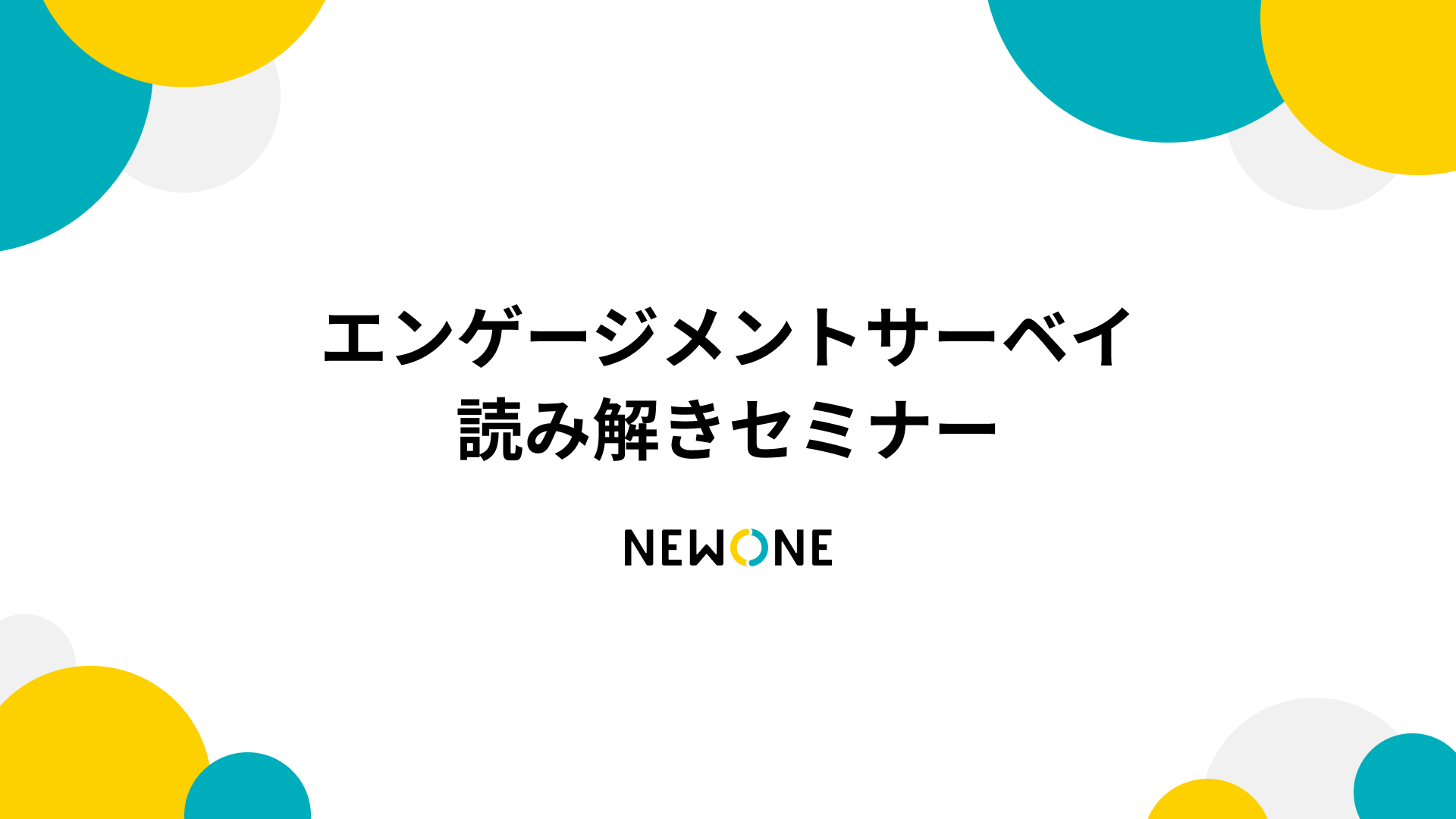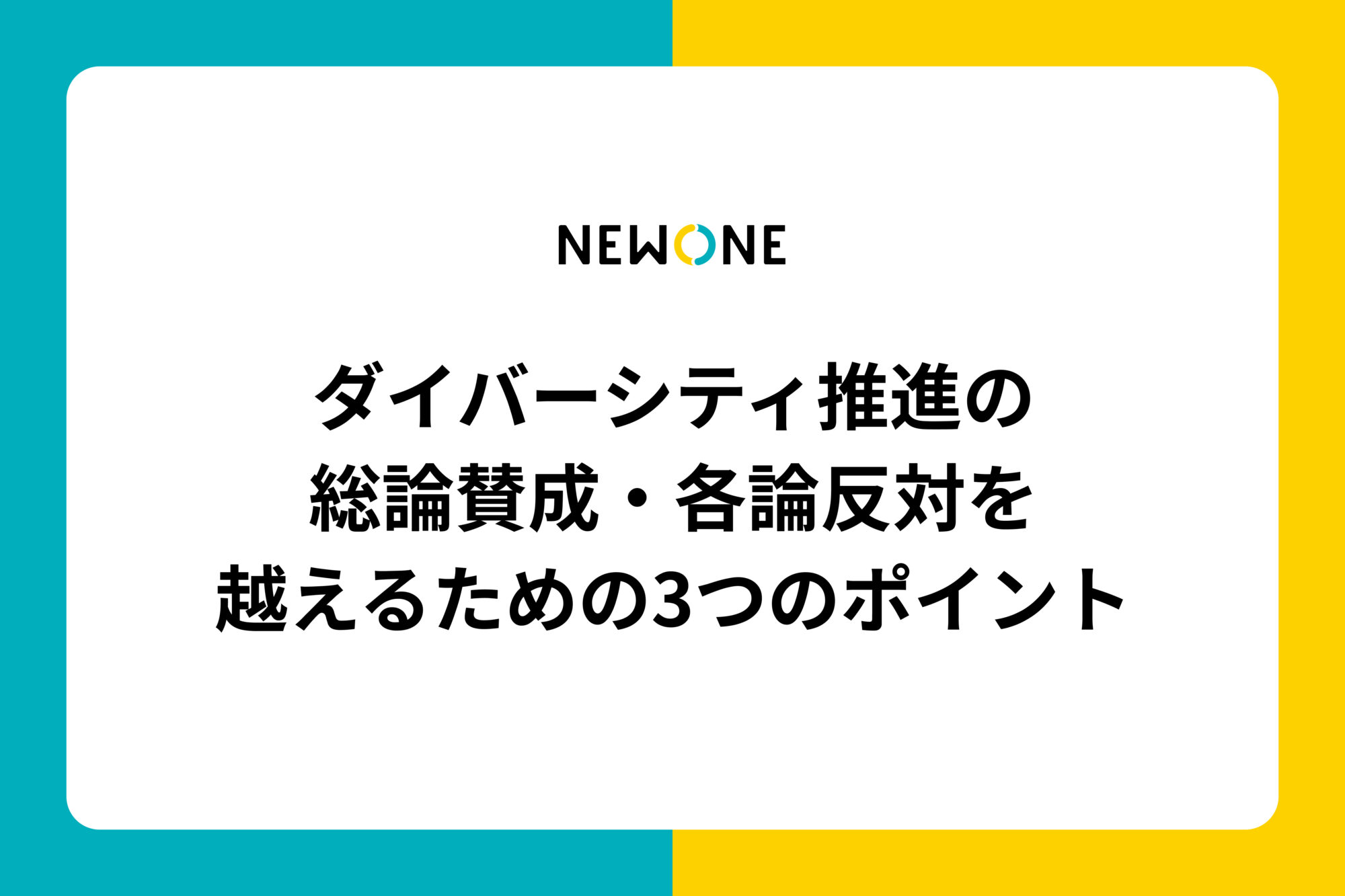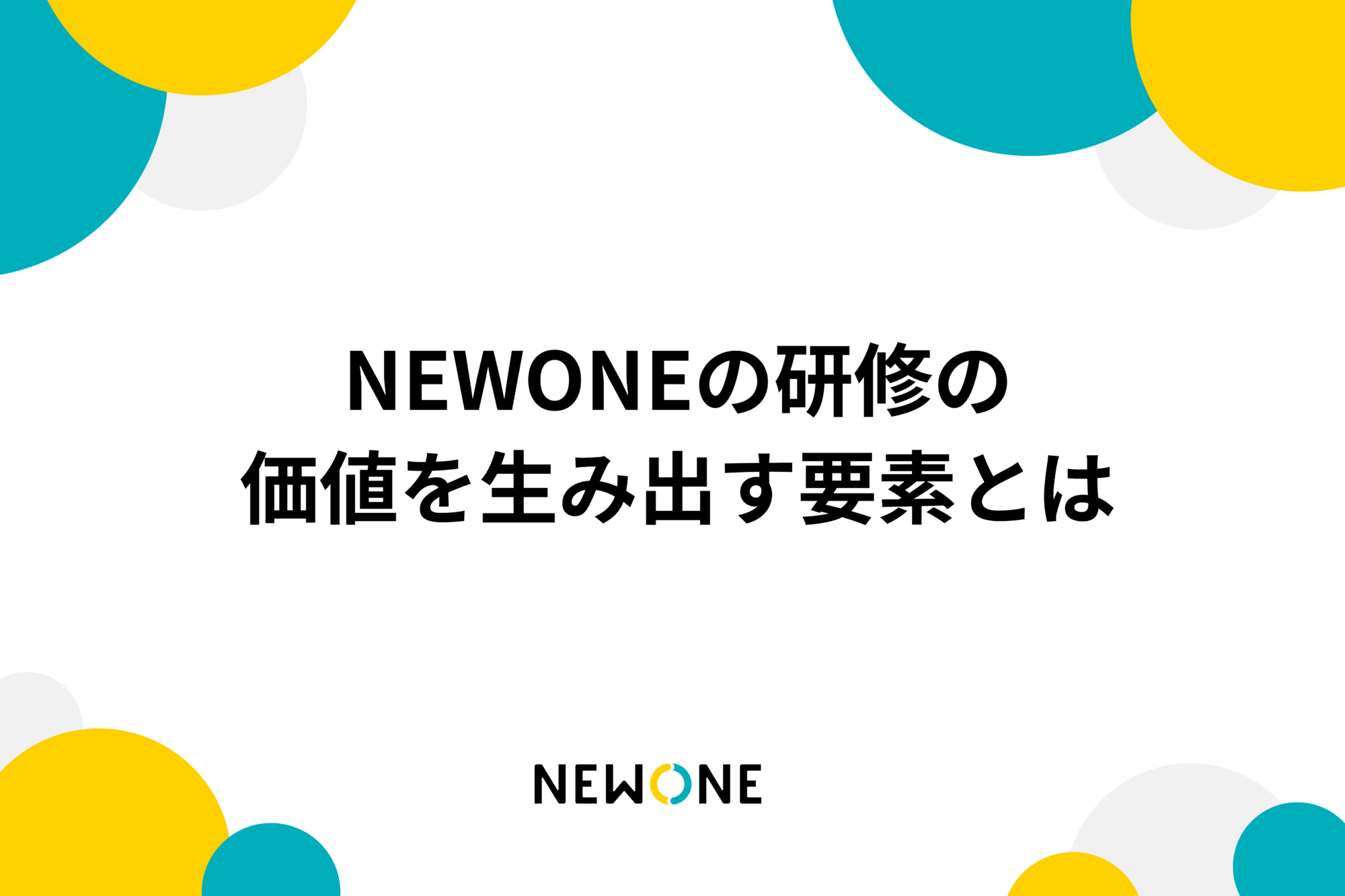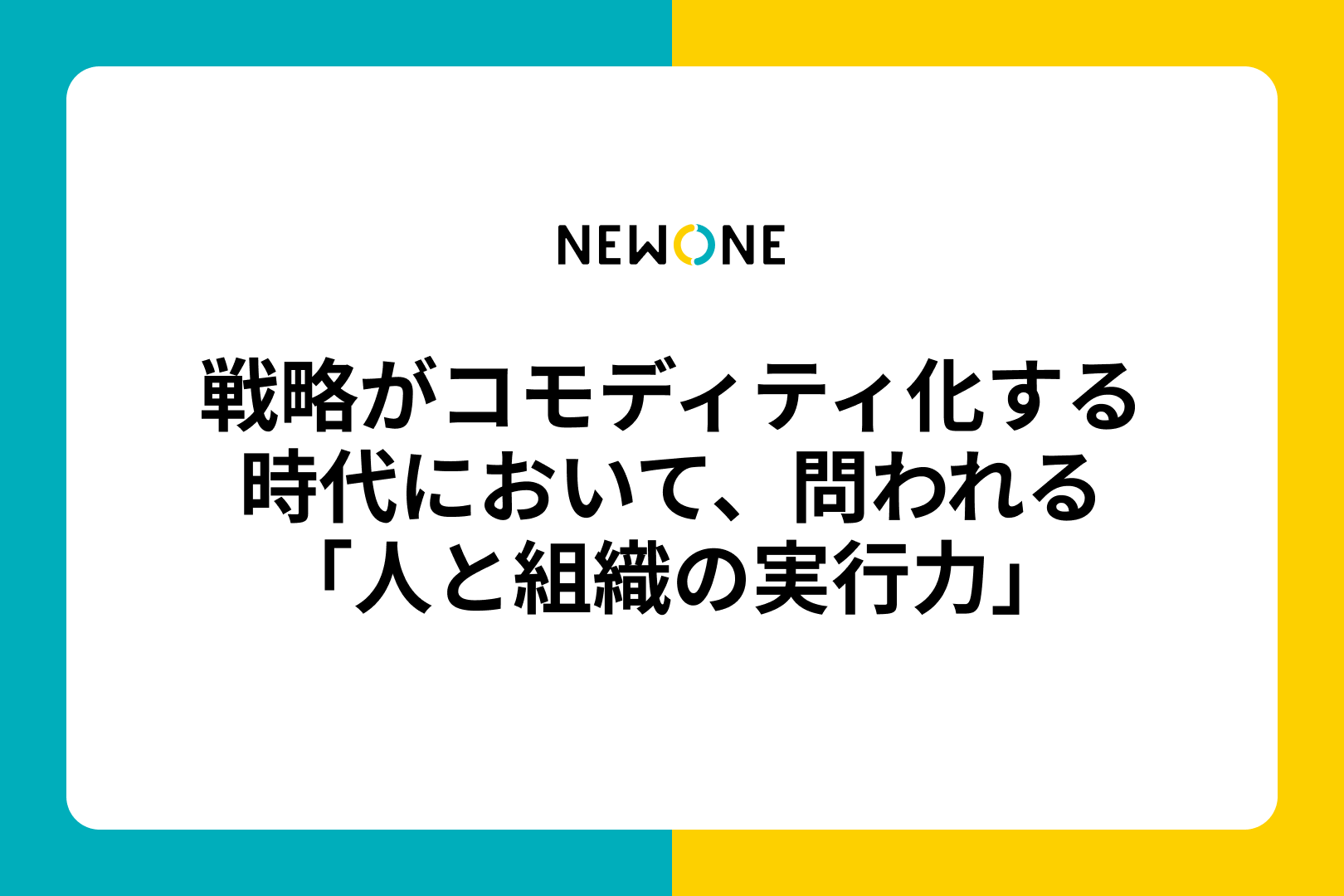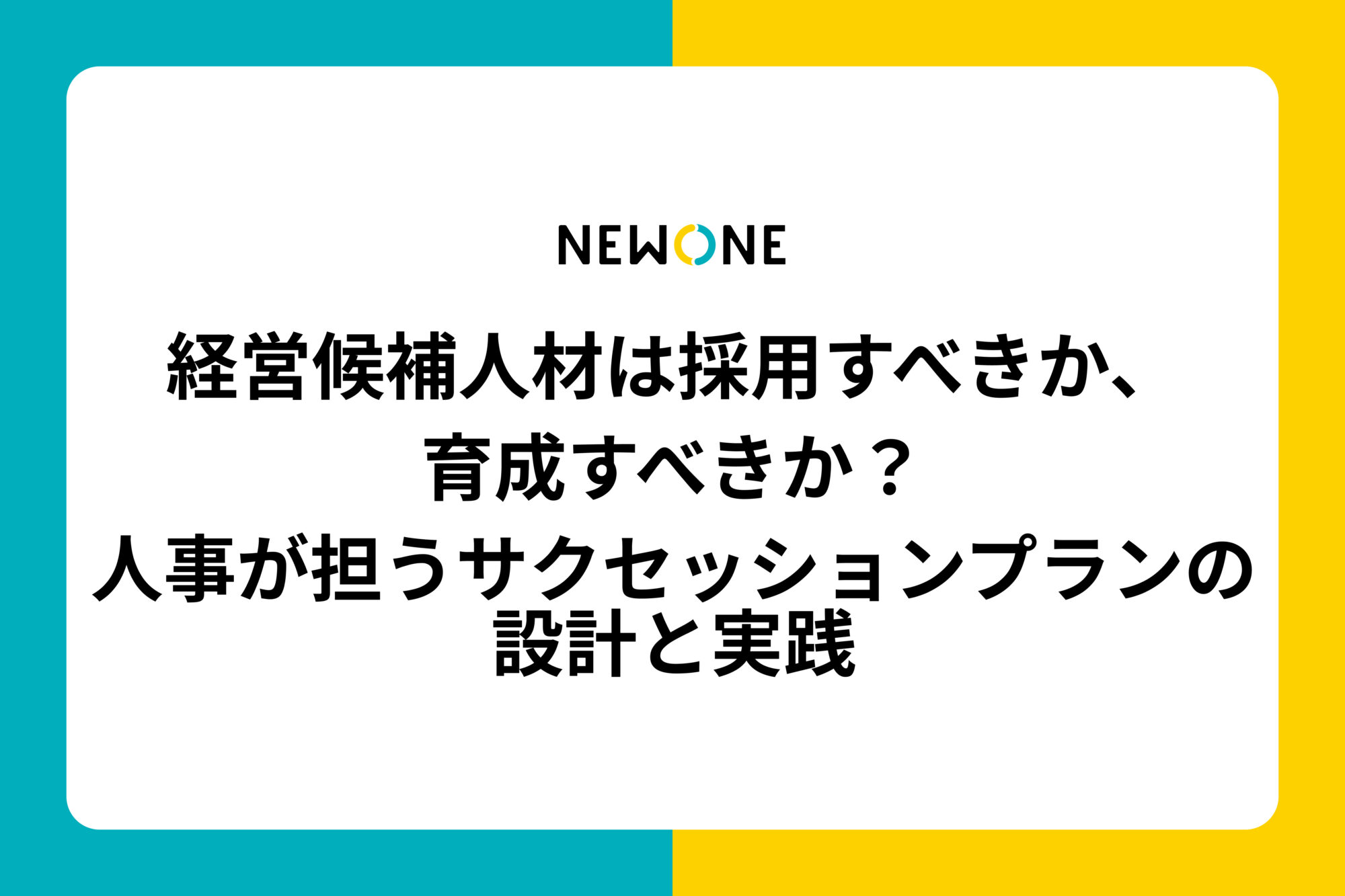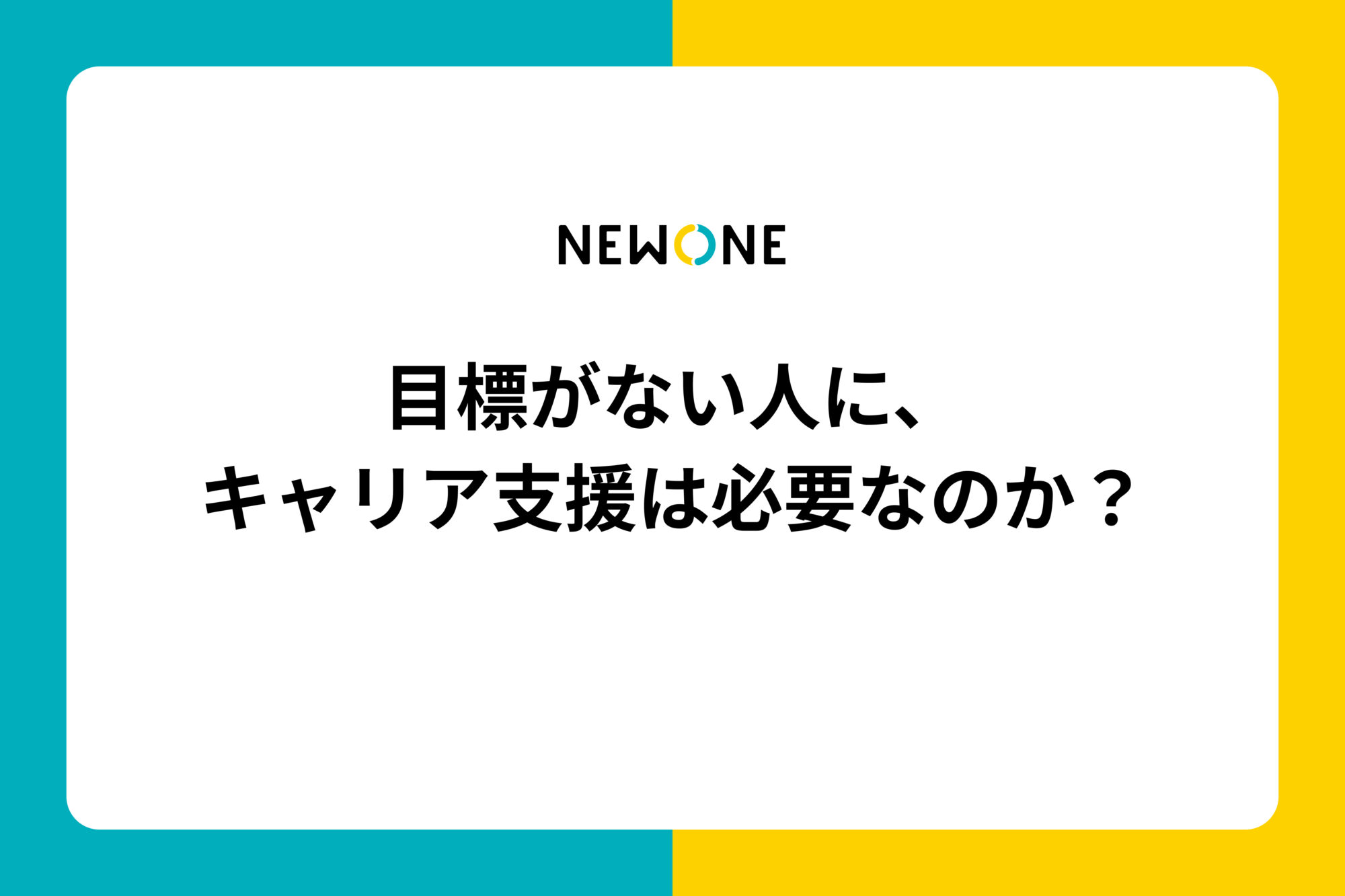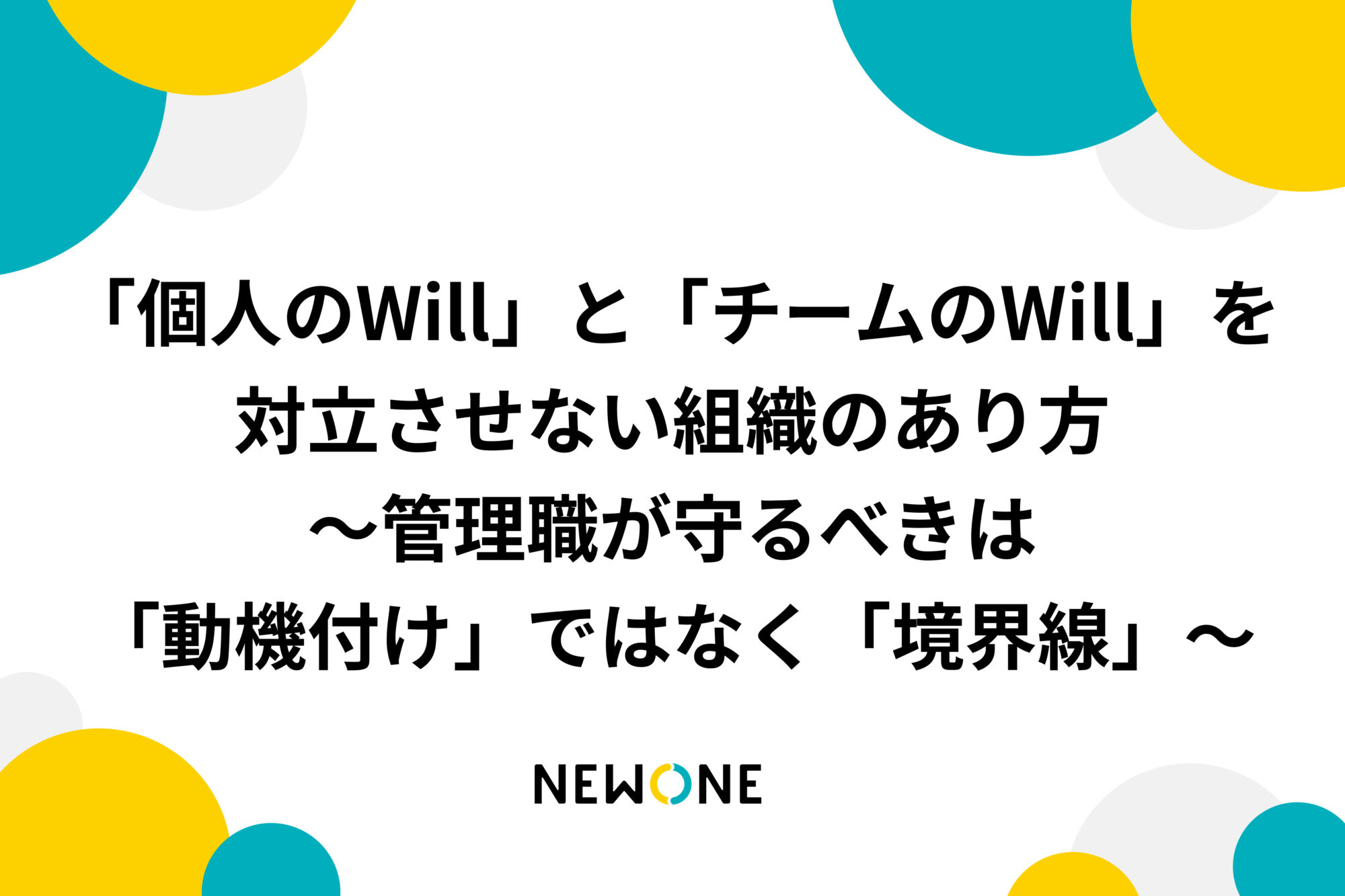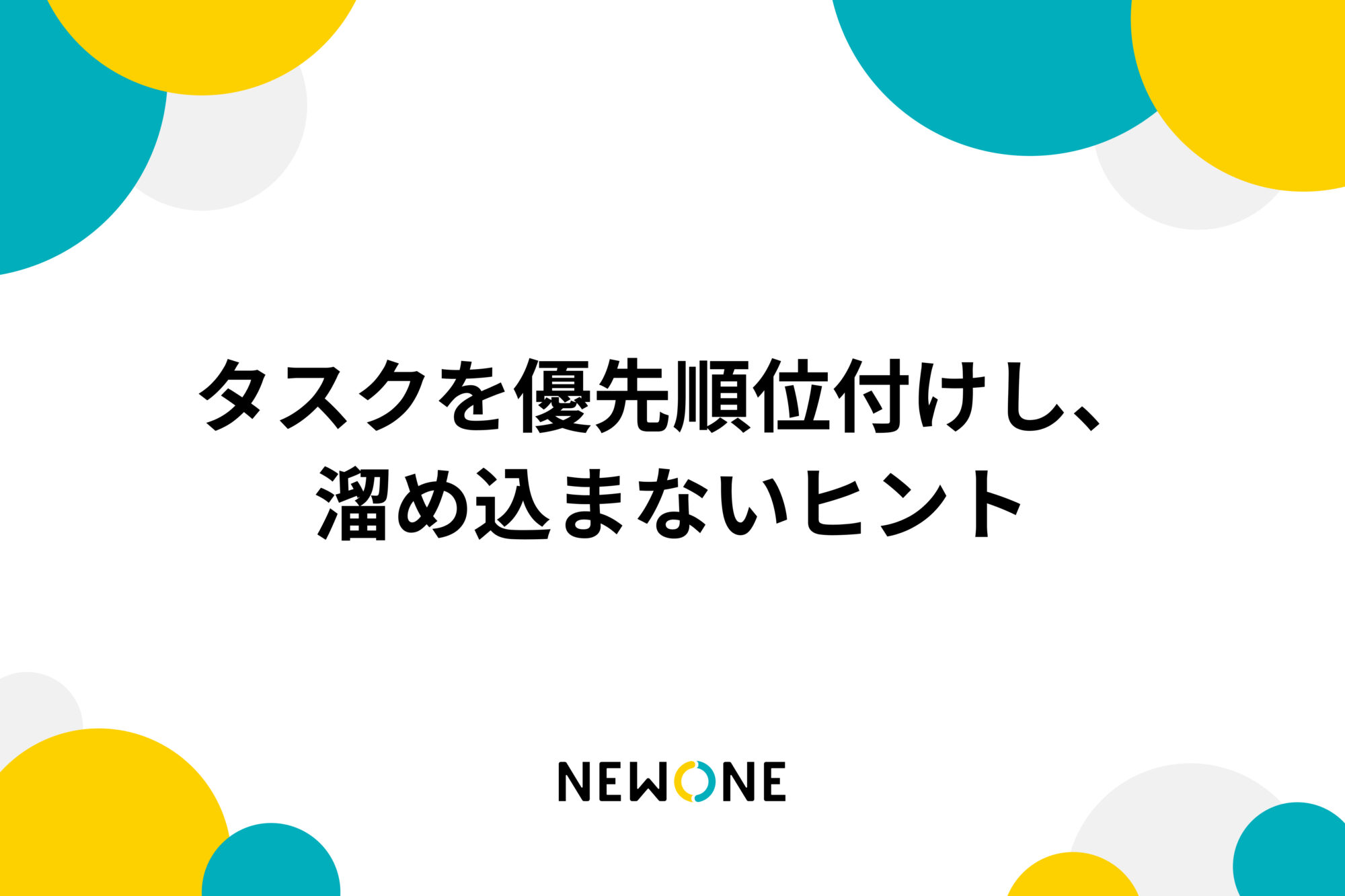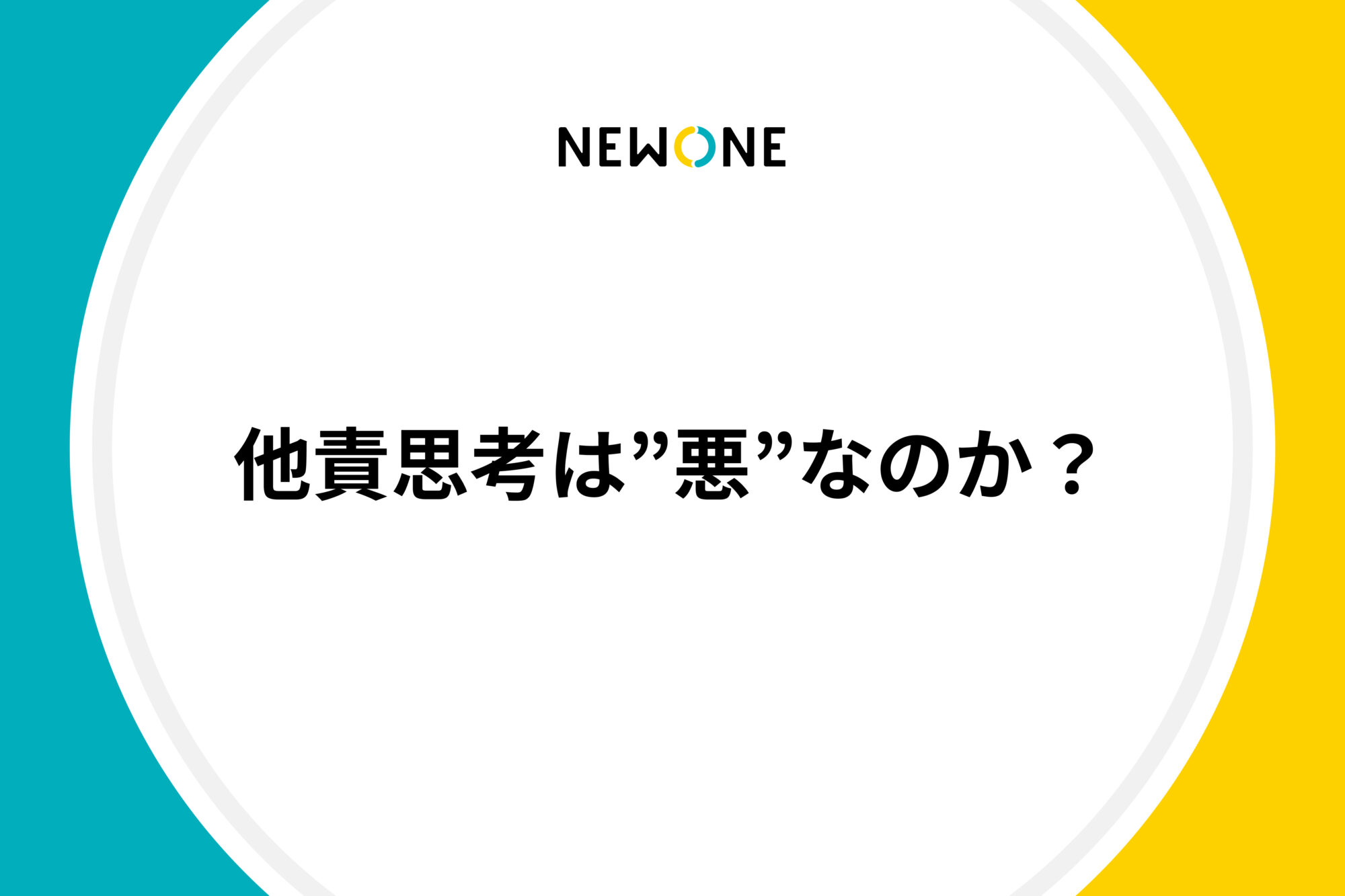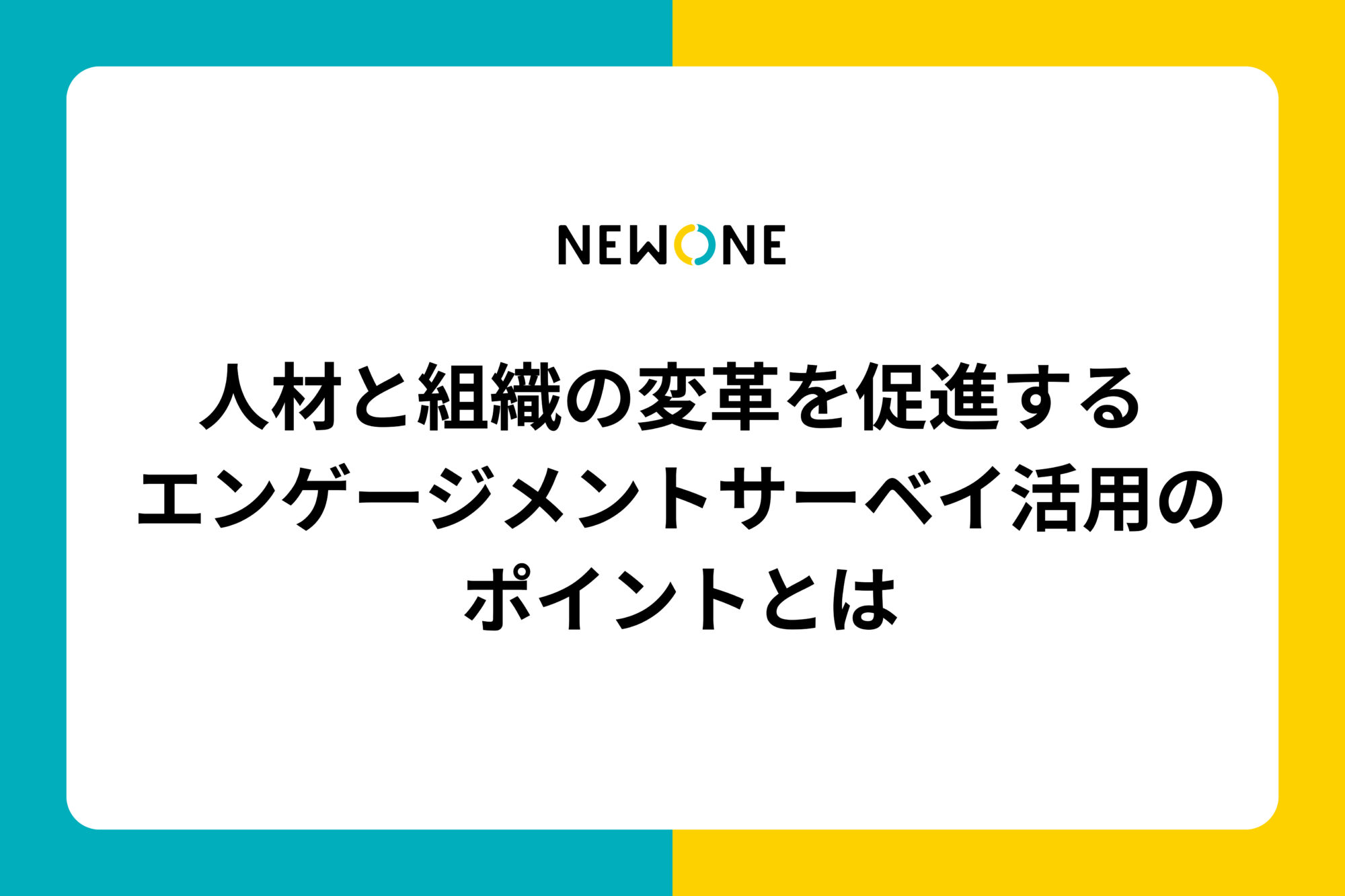
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
昨今、少子高齢化による労働人口の不足や人材流動化の加速といった背景から、従業員の定着と活躍が企業の重要課題となっています。そうした背景から、企業と従業員のつながりの強さを測るエンゲージメントサーベイを活用する企業も増えています。しかし、いざエンゲージメントサーベイを取得してみると、
「取得はしているが、活用の仕方が分からない」
「数値の低い項目が多くて何から着手すればいいかわからない」
「社員がエンゲージメントサーベイに対して積極的ではない」
といった悩みを抱えている方は多いのではないしょうか?
本記事ではエンゲージメントサーベイをとりっぱなしで終わらせず、活用につなげるためのポイントをご紹介できればと思います。
(※本内容は、2025年9月5日実施セミナーの内容をまとめたものです)
▶こんな方におすすめ
- エンゲージメントサーベイの活用の仕方が分からない方
- サーベイを取得したが、「やりっぱなし」で終えてしまっている方
- 社員のエンゲージメントサーベイに対する理解が得られず困っている方
サーベイを活用できるかどうかの分かれ道はどこにあるのでしょうか。本記事では、その成否を左右する壁を人事目線で5つに整理しました。
サーベイ活用の成否を左右する壁
- サーベイに対して現場が意味を感じていない
- 定性・定量の両面で組織の目指す姿が見えていない
- サーベイをとったら終わりになっている
- 大きな施策に着手して、頓挫する
- 実は人事がエンゲージメントの価値を信じていない
サーベイを活用しきれずに悩んでいる方の中には、上記で挙げた課題のいずれかに思い当たるものがあるのではないでしょうか。ここからは、各壁を乗り越えるために求められる意識や行動をご紹介します。
①サーベイに対して現場が意味を感じていない
−現場でのWhyを語る
(A)エンゲージメントサーベイを取得する意味は何ですか?と問われたとき、皆さんはどのような回答をしますか?
「社会的にエンゲージメントが注目されているから」「社内のエンゲージメントを向上させたいから」「会社の方針で決まったから」など様々な理由があると思います。
では少し問いを変えてみます。
(B)皆さんの会社の社員にとってサーベイを取る意味は何ですか?
少し答えづらくなった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
(A)の質問ではおそらく人事目線の立場に立って、市場や経営の観点から必要性を述べる方が大半であると想像しています。しかし、サーベイに回答するのは、現場で働く方々です。現場の方々の目線で、「なぜ、やるのか?」を、自分の意思を含めて語ることが大切になります。
②定性・定量の両面で組織の目指す姿が見えていない
−定性目標を立て、定量目標まで落とし込む
「サーベイの数値が低い項目=問題である」と短絡的にとらえてしまうことがあり得ると思います。
確かに数値が低い項目は注意が必要ですが、それだけを根拠に優先順位をつけ、モグラたたきのように次々と対策を講じるのは適切とは言えません。重要なのは、解決策を検討する前に自組織の理想的な状態を描き、その理想から見たときに何が本当の問題となるのかを定めることです。さらに、その理想状態を「〇点以上」といった数値に落とし込むことで、目に見えるゴールを設定でき、効果的な活用につながります。
③サーベイをとったら終わりになっている
−点としてではなく、面としての施策を打つ
サーベイは実施すること自体が目的ではありません。結果をどう活かすかが重要です。単発の施策(点)で終わらせず、サーベイ結果を読み解く研修で学びを広げたり、サーベイを用いた成功施策を社内広報で共有したりすることで、取り組みを全体に広げ(面)、組織全体の改善につなげていくことが求められます。
広報の方や現場の方など様々な方を巻き込み、点ではなく、面としての施策を企てることが大切になります。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
④大きな施策に着手して、頓挫する
−スモールステップで施策を実施する
組織全体を一度に変革しようとすると、スピードもエネルギーも膨大に必要となり、結果的に途中で頓挫してしまうケースがあります。大掛かりな改革を打ち出すよりも、まずは特定の部署やチームなど、取り組みやすい範囲で小さな成功事例を生み出すことが重要です。その成功体験を関係者で共有し、社内に「できる」という実感を広げていくことで、次の取り組みへの賛同や協力も得やすくなります。小さな成功を積み重ねていくことこそが、組織全体を変えていくための現実的かつ持続可能なアプローチなのです。
⑤実は人事がエンゲージメントの価値を信じていない
−まずは人事自身が本気でエンゲージメント向上を目指す
社員のエンゲージメント向上を考える以前に、少し考えたい問いがあります。
人事の皆さんはエンゲージメントの価値を本当に信じていますか?
もしくは
自分以外の人事の方や巻きこむべき経営の方、合意を取っておくべき事業部長ラインの方々はエンゲージメントの価値を本当に信じていますか?
こちらが本気でないのに、あちらを本気にさせることはできません。人事自らがモデルとなり会社をリードする行動を取ることで、周りに影響力を発揮していくことが第一歩となるのではないでしょうか。
セミナーアンケート(一部抜粋)
- 「エンゲージメントは伝播する」というのが最も印象に残った。弊社のエンゲージメントが高い組織やエンゲージメント向上に意欲的に取り組んでいる組織の組織長のエンゲージメントスコアを分析してみたいと感じた
- ご提示いただいた内容はうなずけることばかりでしたので、整理できました。自社の活動にどう具体的に落とし込めるように考えなければいけないと思っています
- 必要性を理解するまで、時間がかかることなど、継続力が重要だと感じました
- 結果の数値だけでなく、もっと多面的に見る必要があると感じた
登壇者の声
エンゲージメントサーベイが「とりっぱなし」になっていることを課題視している企業様が増えています。そして、その状況を打破するために、本セミナーの①~⑤のポイントは、様々な企業様が提唱しているのではないかと思います。
しかし、今回私が最も伝えたかったのは⑤の「人事自身がエンゲージメントの価値を信じること」です。「私」が本気でやっていないことを、「あなた」に求めても、人は動きません。逆に言うと、「私」の本気は「あなた」に伝わって、理屈を超えた原動力になります。
弊社顧問の島津先生は「エンゲージメントは伝播する」と仰っています。
だからこそ、我々NEWONEも、自分たち自身がエンゲージメントの価値を信じ、有言実行していくことを大事にしながら働いています。
「エンゲージメント」について、どんなに些細なことでも、一緒に真摯に考えます。
本記事を読んで少しでも気になったことがあれば、気軽にご連絡ください。
まとめ
本記事では、エンゲージメントサーベイを活用する上で人事が直面しやすい5つの壁を整理し、その乗り越え方を考えてきました。サーベイは単なる調査ではなく、組織を前進させるための強力な手段です。今回ご紹介した内容が、皆さまの組織におけるエンゲージメント向上の一助となれば幸いです。
関連資料リンク、お問い合わせリンク
株式会社NEWONEでは「すべての人が活躍するための、エンゲージメントを」をブランドプロミスとして研修やコンサルティングサービスを通じて様々な企業様とご一緒しております。