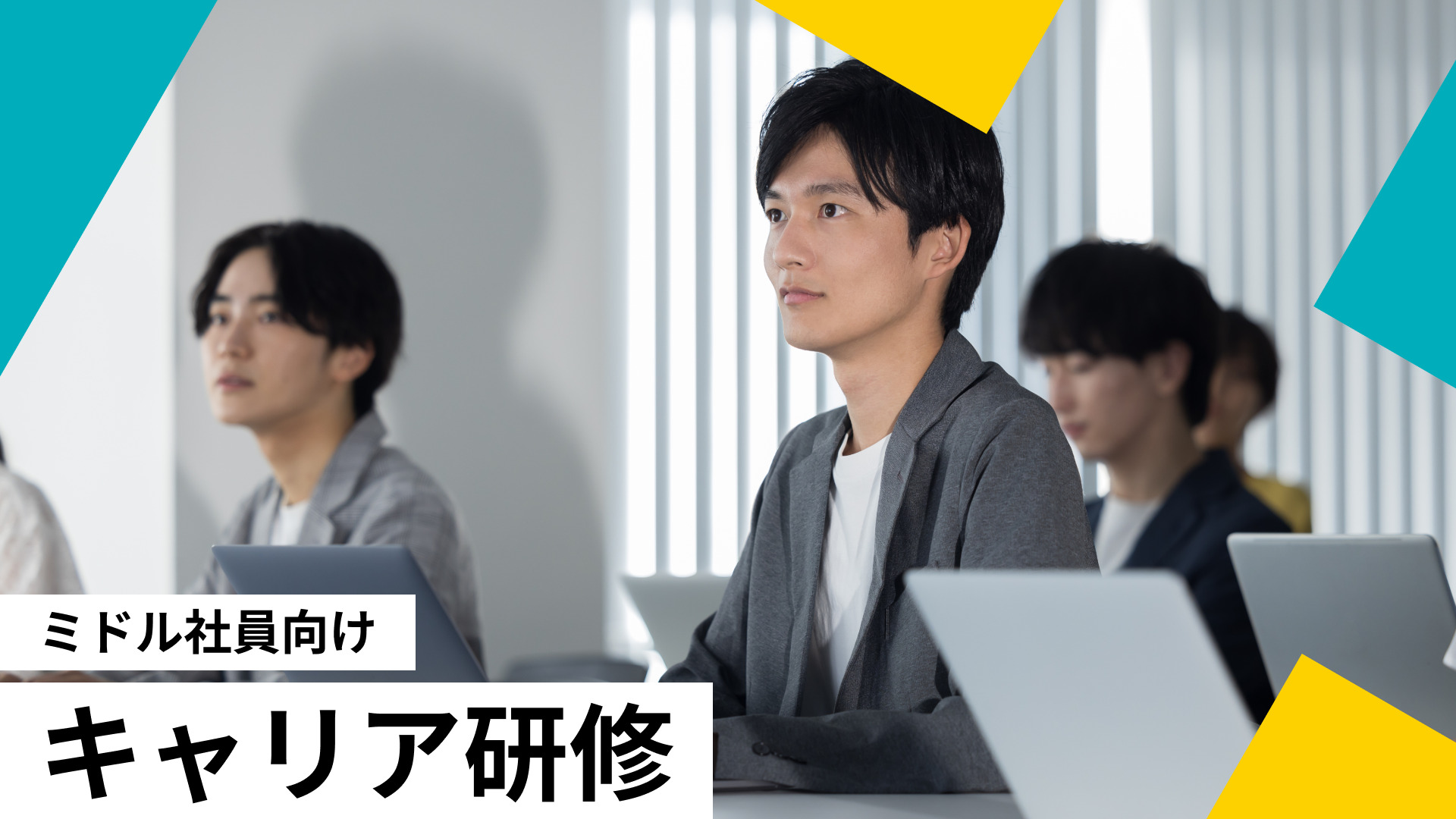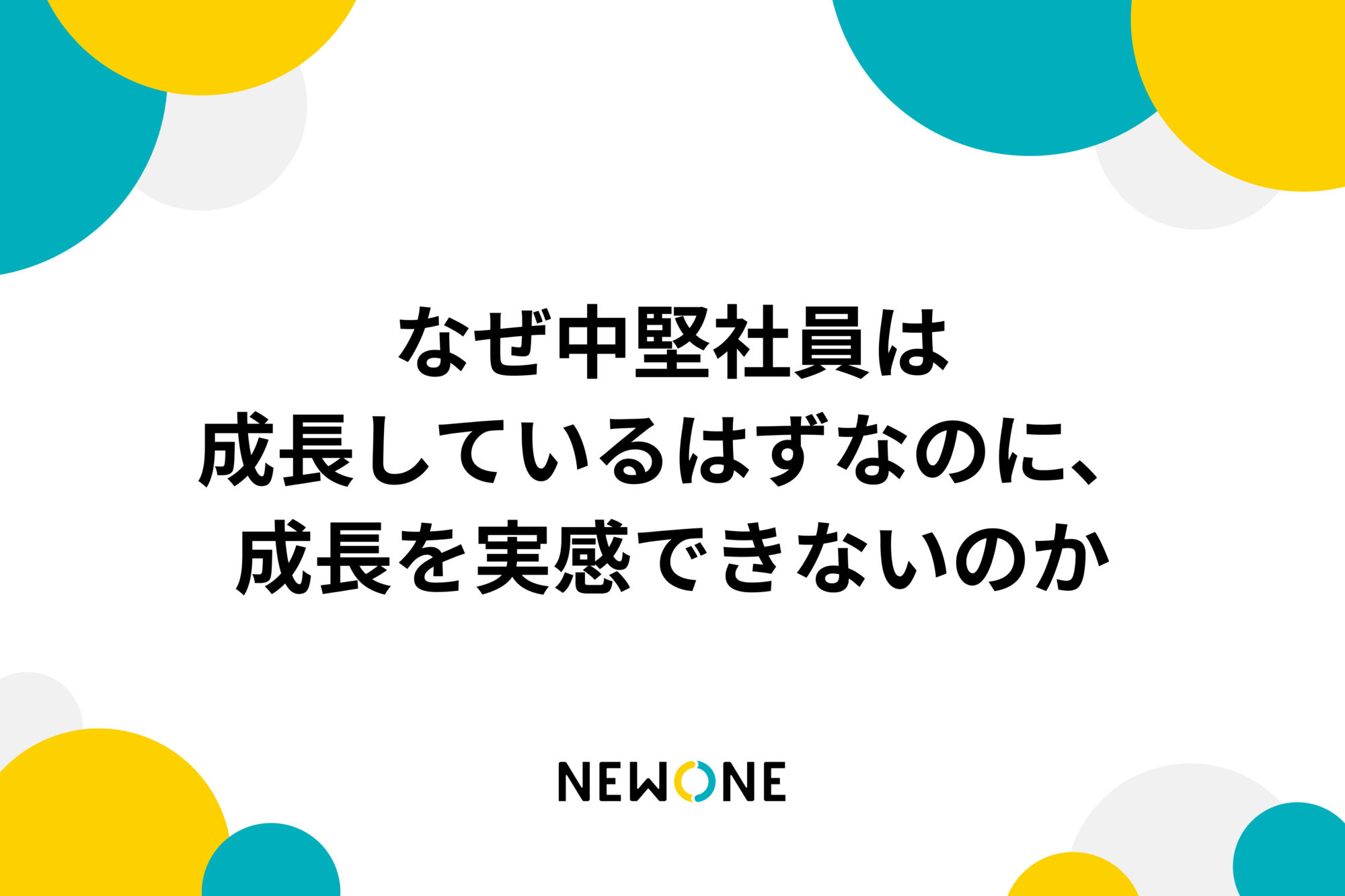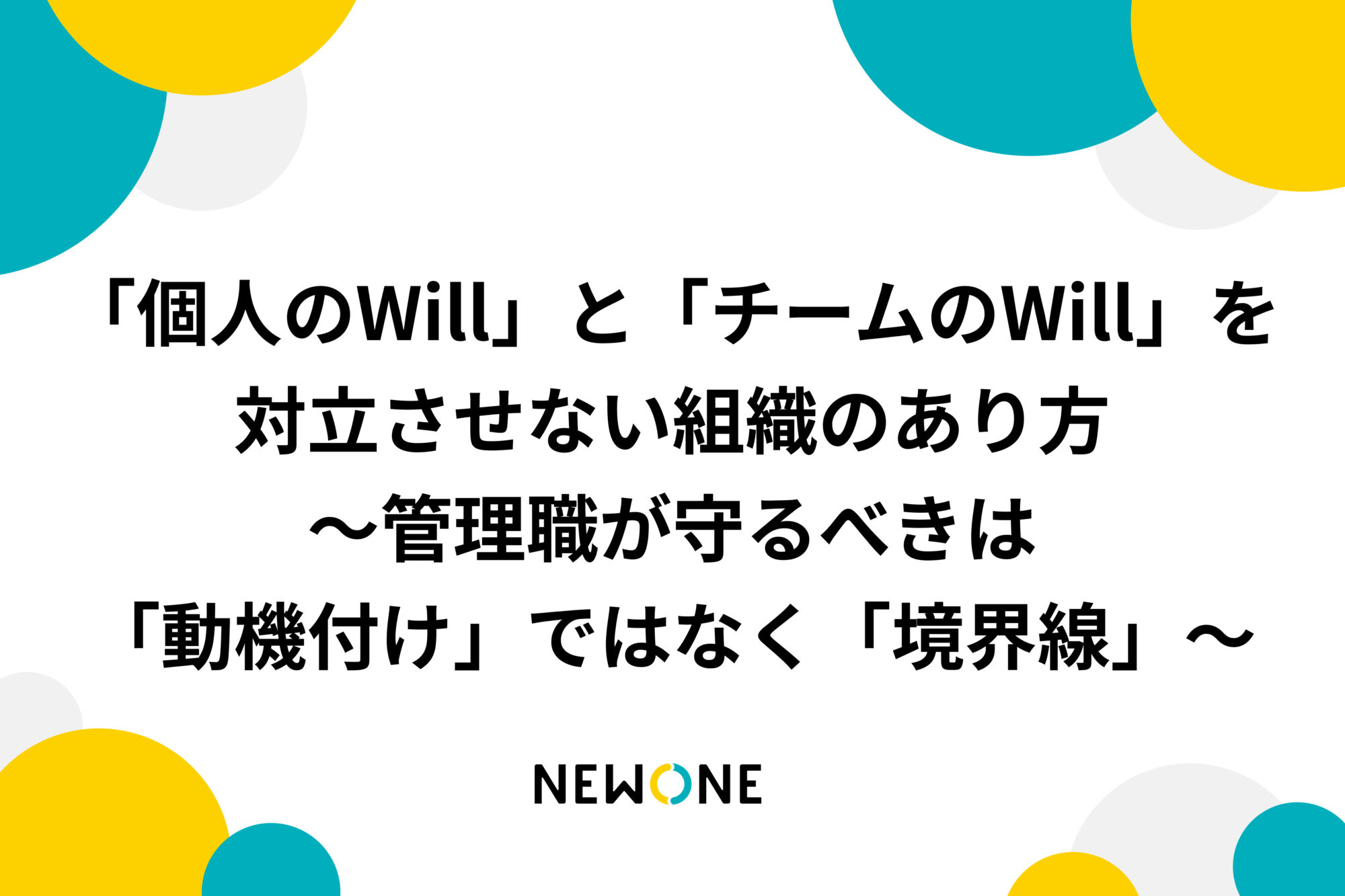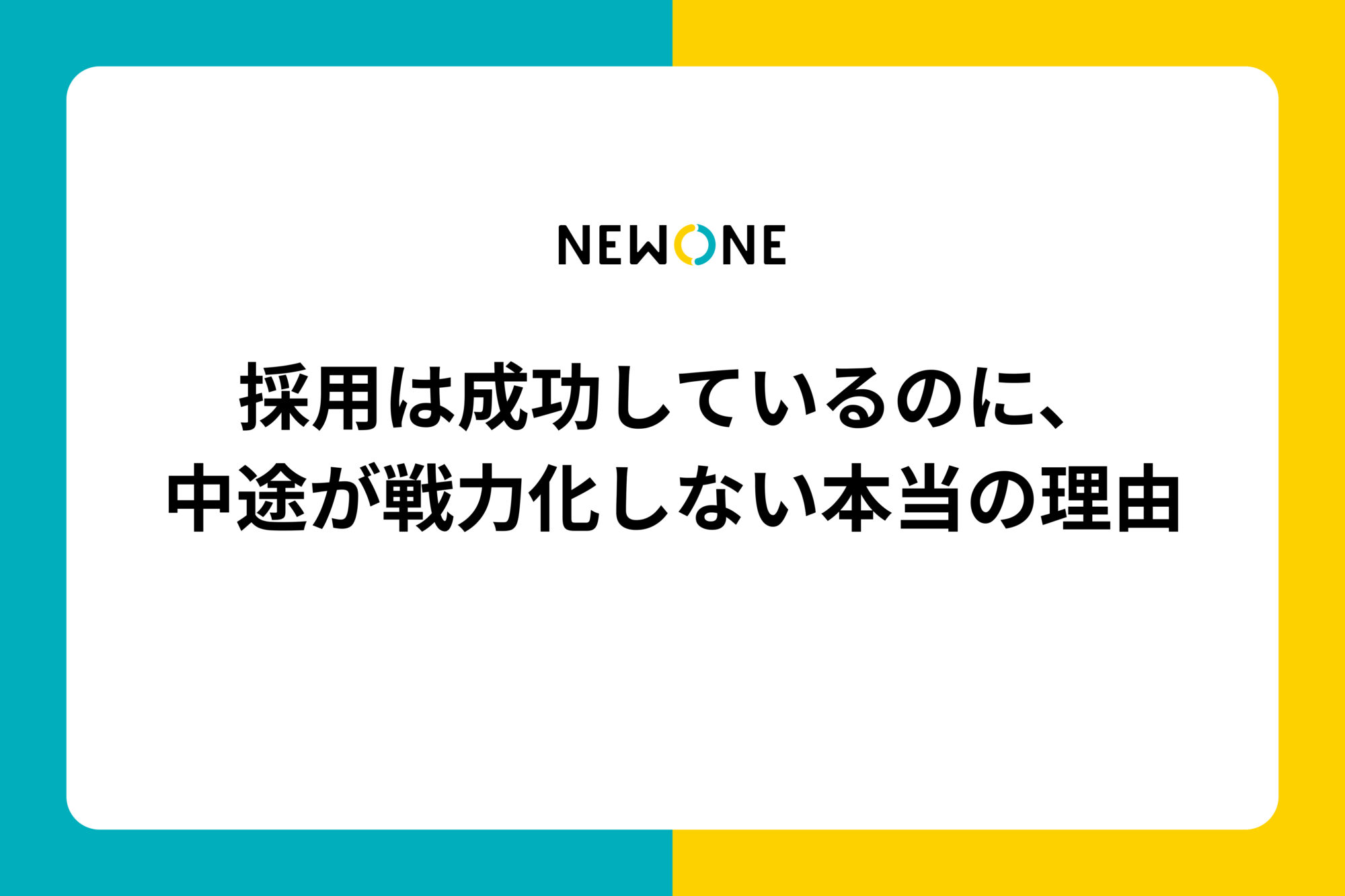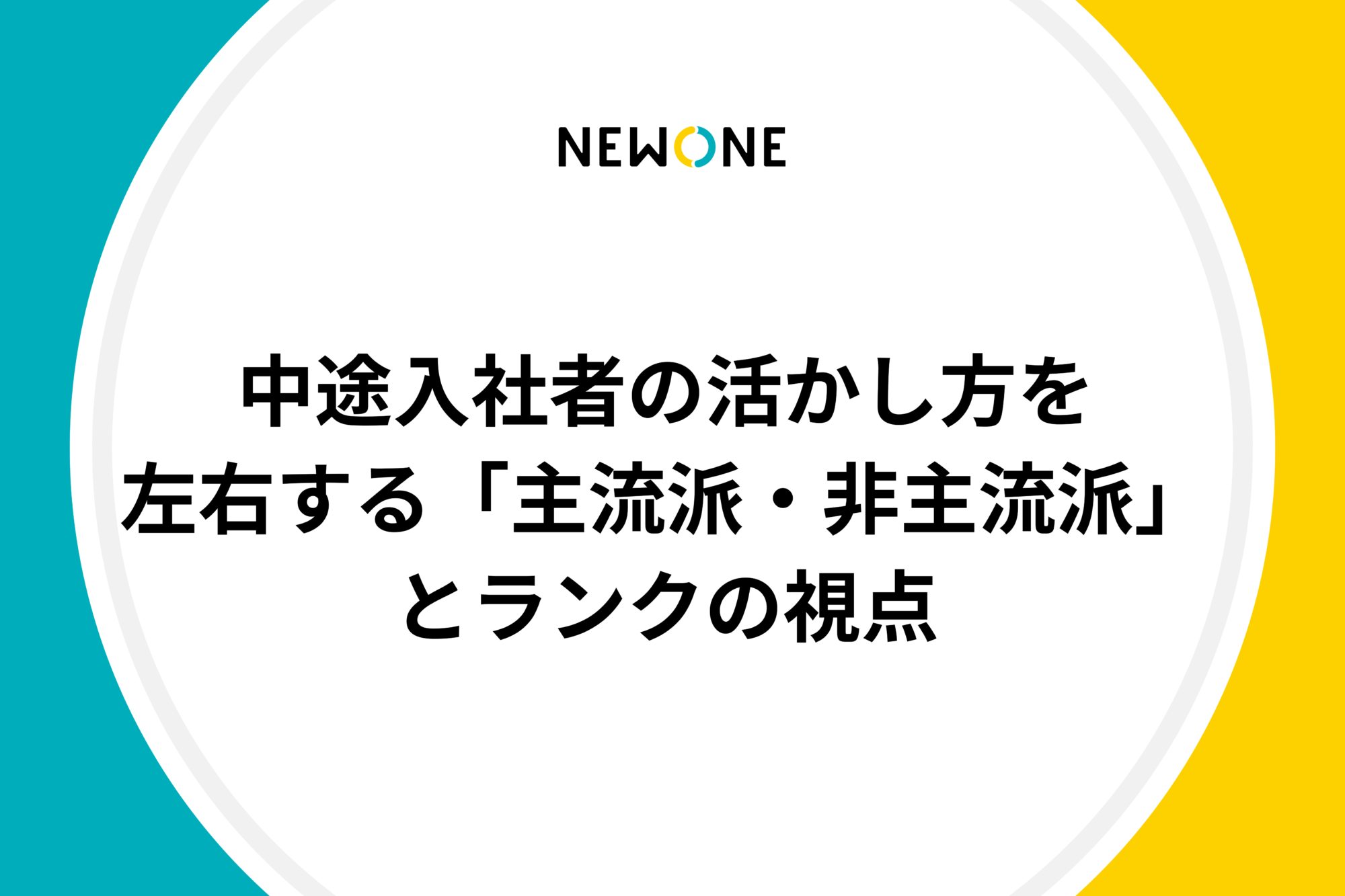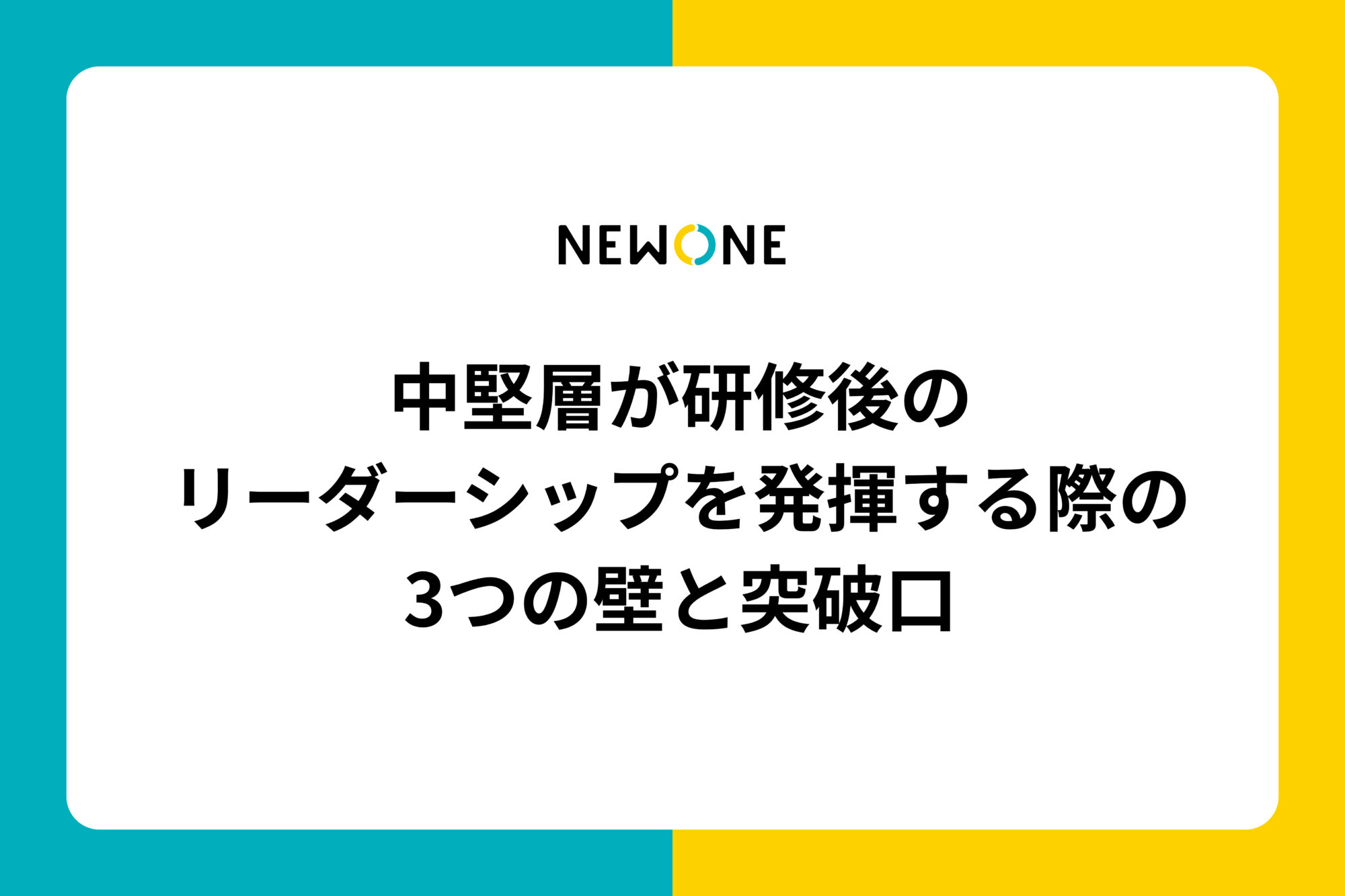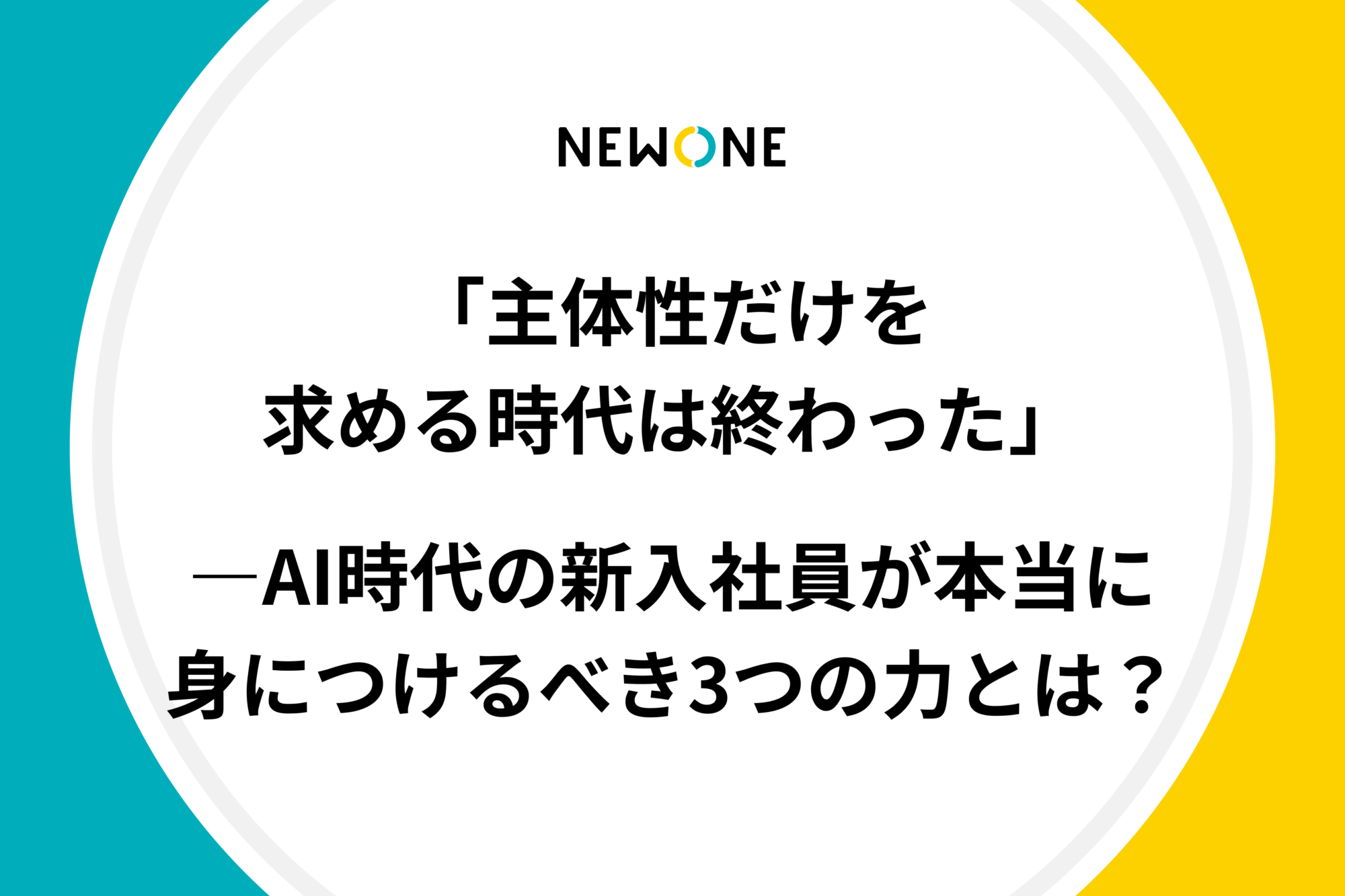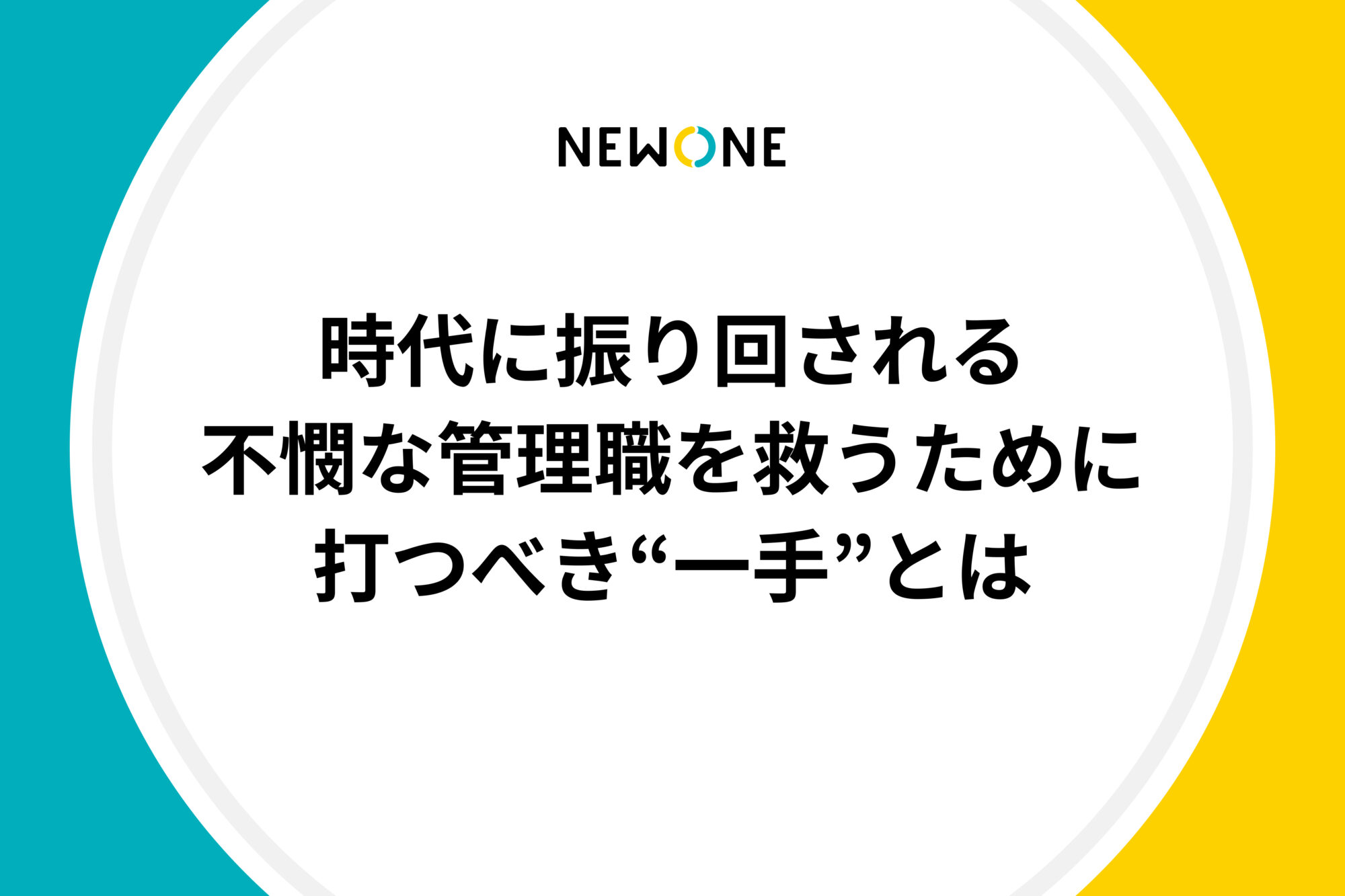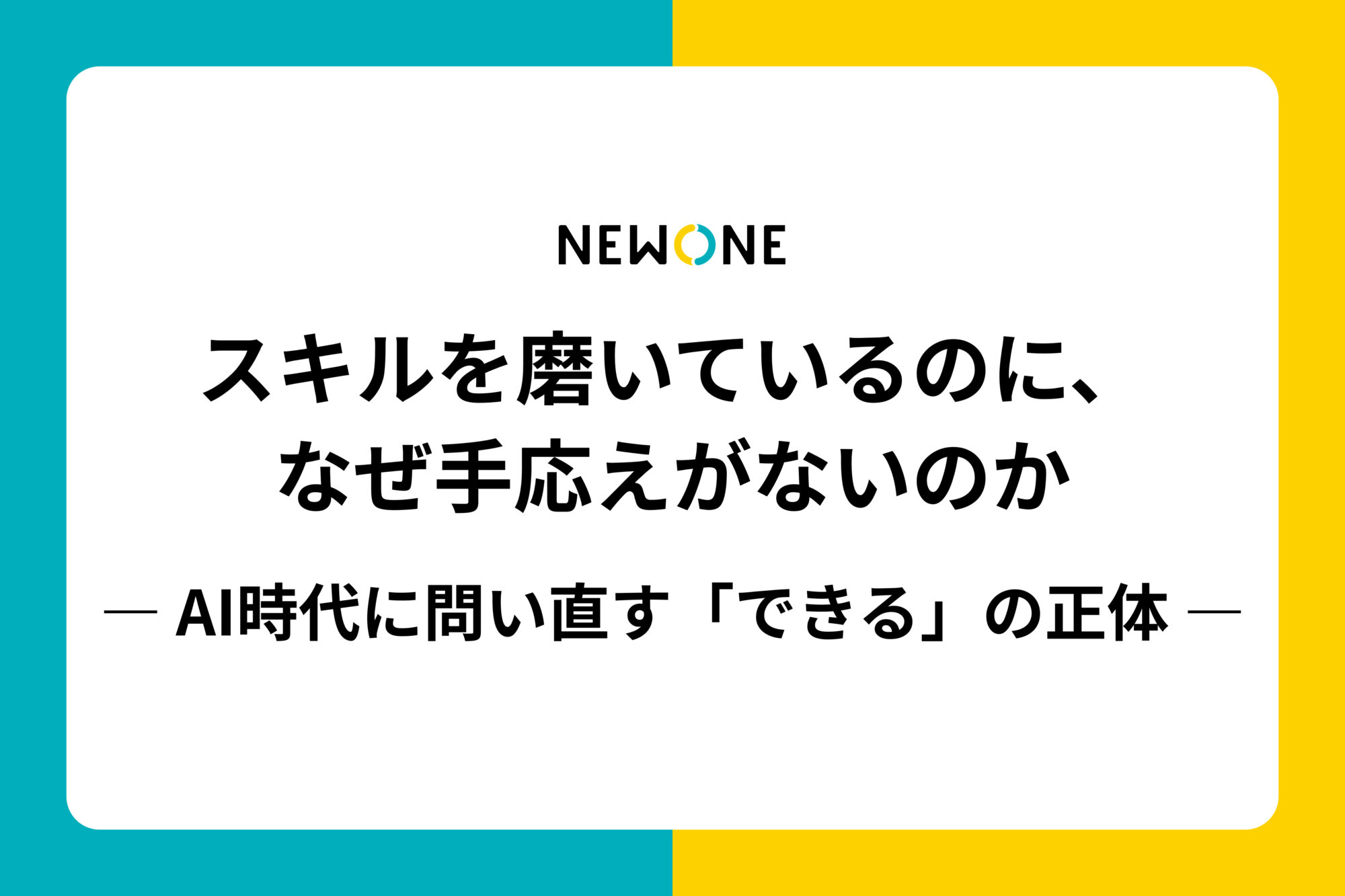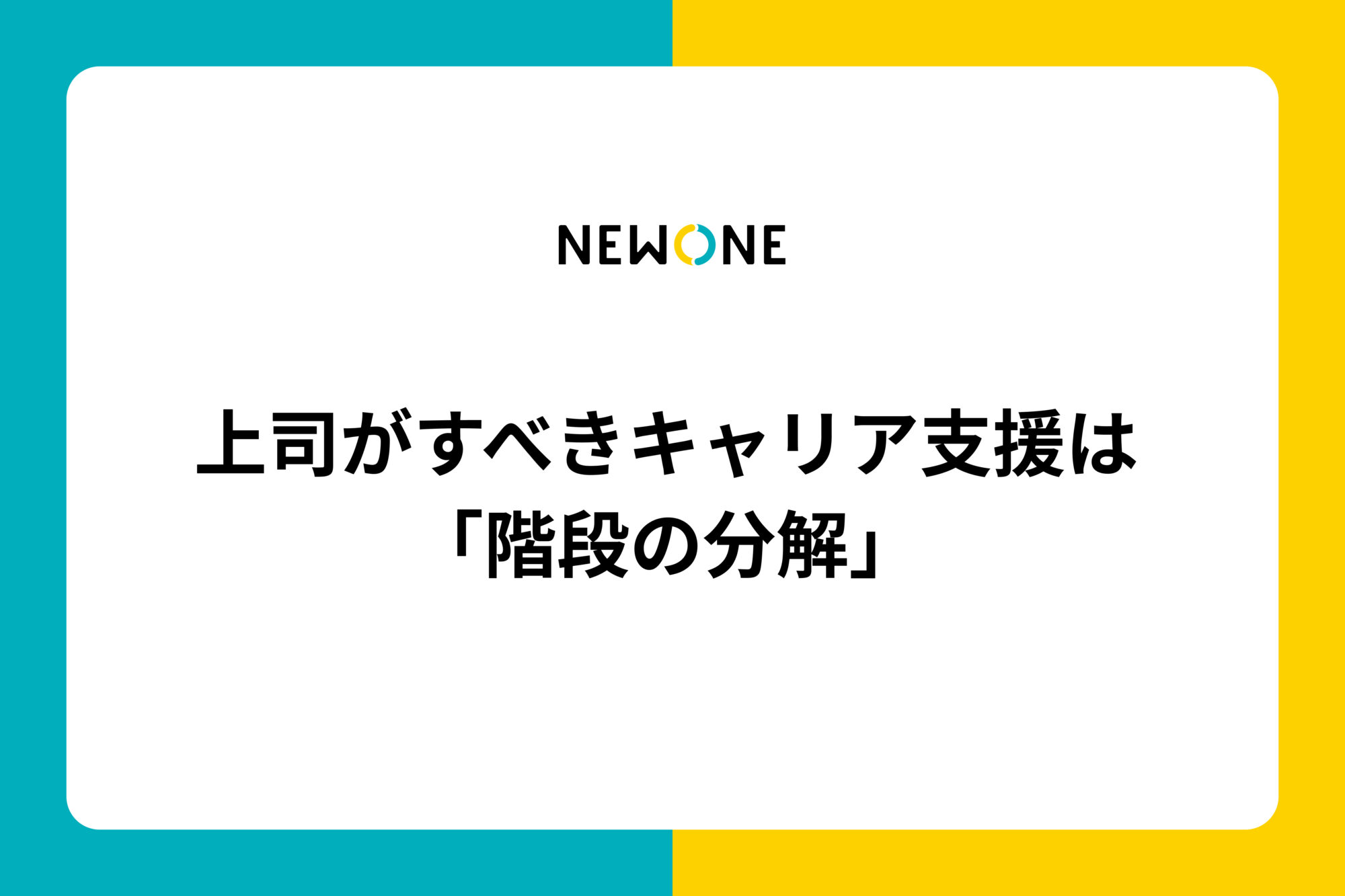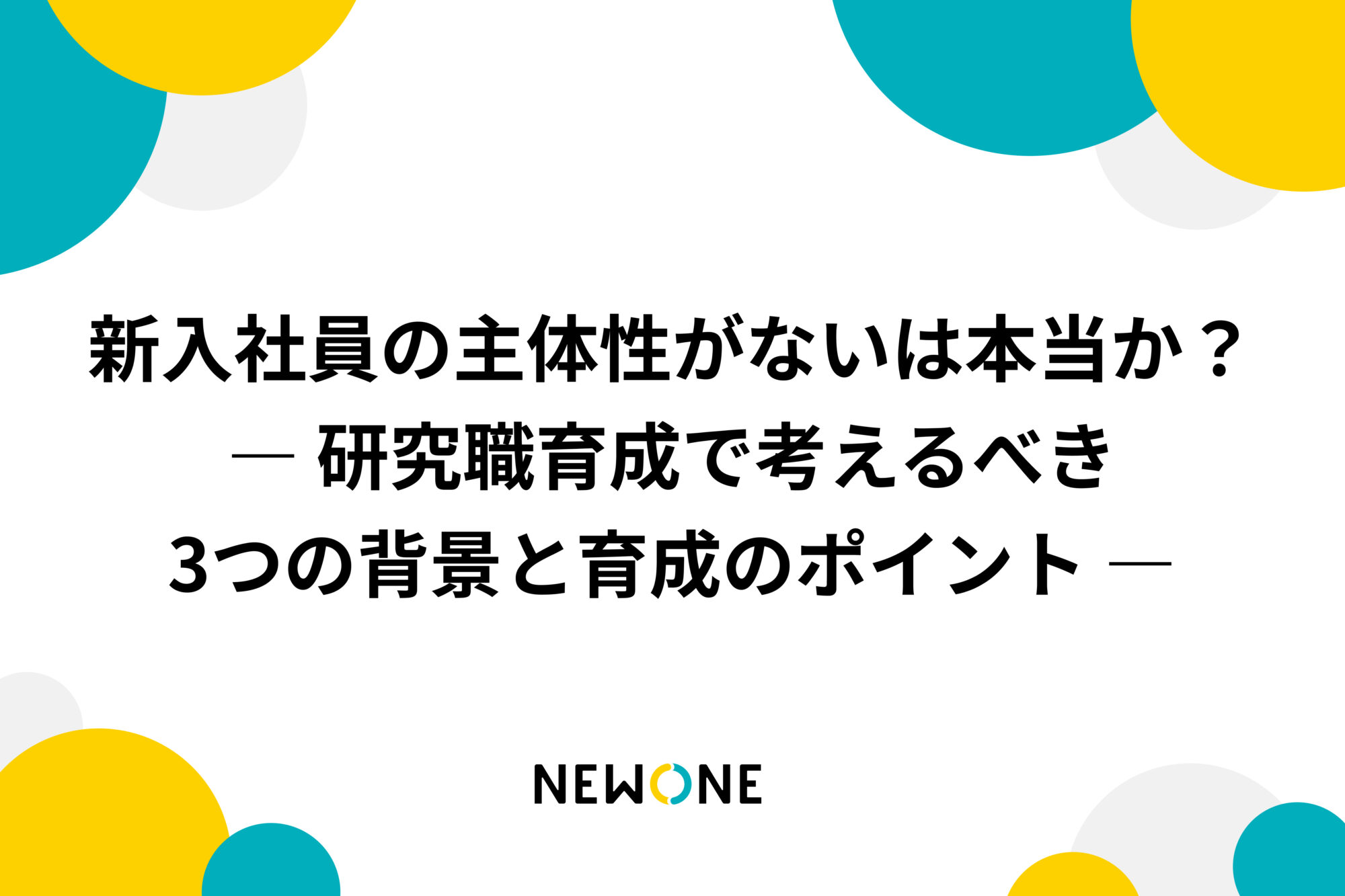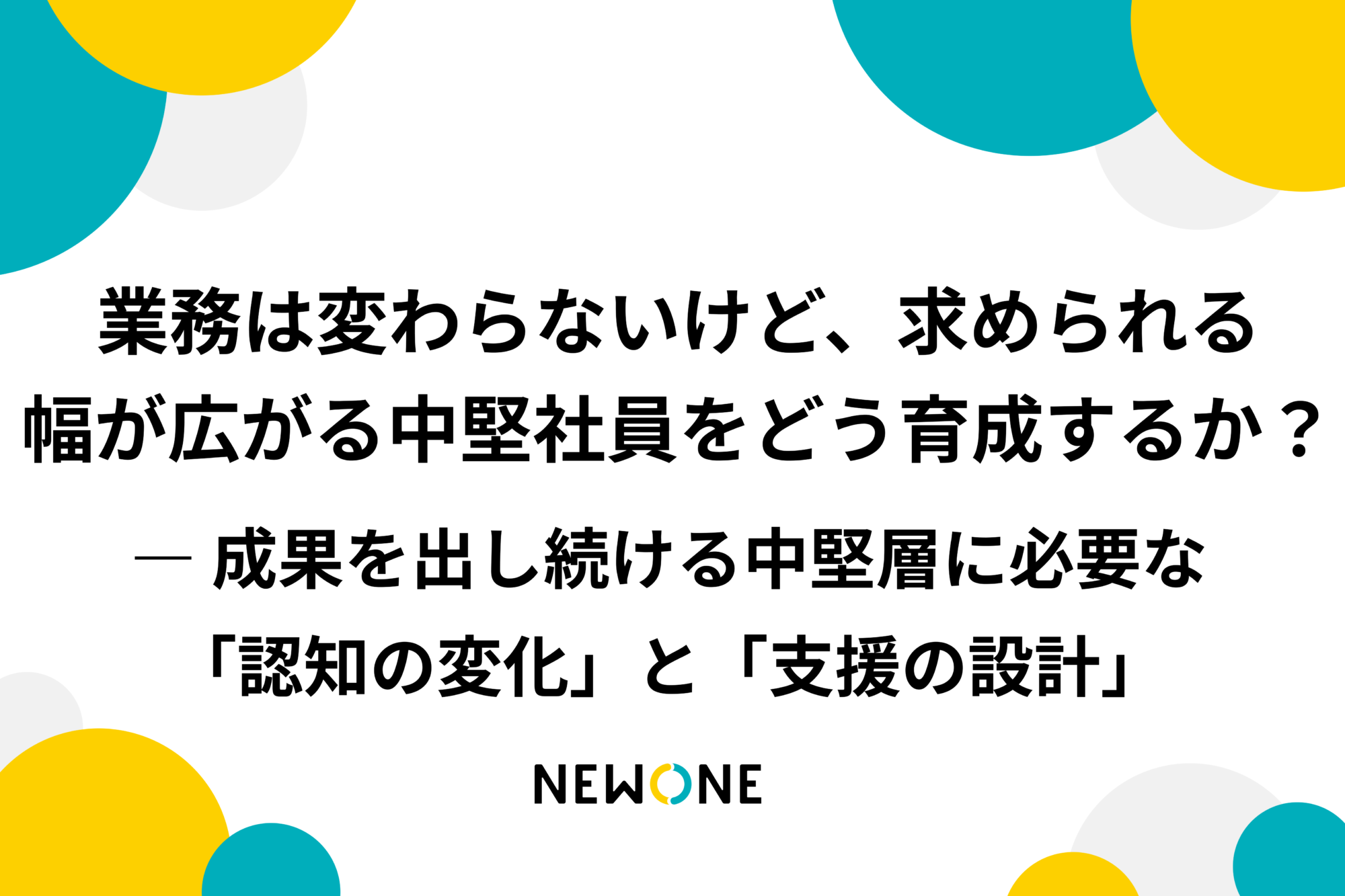
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
4~8年目あたりの中堅社員の育成について、こんな声を耳にします。
「業務自体は大きく変わらないが、求められる役割が増えている」
「プレイヤーとしては優秀だが、周囲を巻き込む力に課題がある」
いわゆる“中堅の壁”とも呼ばれるこの段階。
研修としてメッセージは伝えているけれど何となく腹落ち感がないなと感じている人事の方も多いのではないでしょうか。
なぜ「業務は変わらないけど求められる行動は変わるメッセージ」が響かないのか?
それは、本人たちが“成果の指標”をアップデートできていないからです。
若手の頃は、「任された仕事を正確にこなす」ことで評価を得てきました。
この経験が、“言われたことを正確に実行する=成果につながる”という成功法則として強く刷り込まれています。
しかし、組織が求めるのは「自分の成果」から「周囲の成果への貢献」へとシフトしています。
この転換点、本人たちからするとやったことがない領域なので、ピンとこない可能性が高いです。
結果として、本人は「今まで通り頑張っているのに、なぜ物足りないと言われるのか」と感じ、求められる変化を“理屈では理解しているが、腹落ちしない”状態に陥ります。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
どうすれば“幅の広がり”に応えられるようになるのか?
ここからは、研修設計の観点で考えたい2つのポイントを紹介します。
1. 「成果=自分の貢献×周囲の活躍」と捉え直す認知変化
中堅層になると、業務スキルよりも「影響力」が求められます。
自分だけで何とかするよりも、組織としてどうか?という観点が重要になります。
研修では、「自分が動いて成果を出す側」ではなく、「成果を生み出す土壌をつくる側」として、他者の視点で仕事を再定義する機会をつくることが有効です。
具体的には、上司の方にも若手と中堅へ求めることの違いを言語化してもらい、明確に上司からの期待として受講者にお伝えすることが効果的です。
2. 日々のもやもやを言葉にする
周囲へ影響力を発揮することは分かったけど、具体的に何をすればいいのか?が次の壁となりやすいです。
ここでは、“どんなに小さくても職場での問題に対して改善行動をとってみたい”と思ってもらうことが重要です。
そのためには、本人が感じている小さなもやもやを吐き出させてその裏にある本人なりのあるべき姿を引き出していくことが有効です。
影響力を上げていくことで、日々の仕事を改善できるという希望を持たせるように、
“もしその問題が解決したらどんな良いことがあるか?”などの未来を考える問いかけを行うと効果的です。
まとめ
いかがでしょうか。
中堅層の育成は、「何かをできるようにすること」が重要なのではなく、「視座・視野を少し高めること」の支援です。
業務が変わらなくても、本人の認知が変われば、見える世界は大きく変わります。
中堅社員が、次の成長段階に進むきっかけになれば幸いです。
 川合 裕貴" width="104" height="104">
川合 裕貴" width="104" height="104">