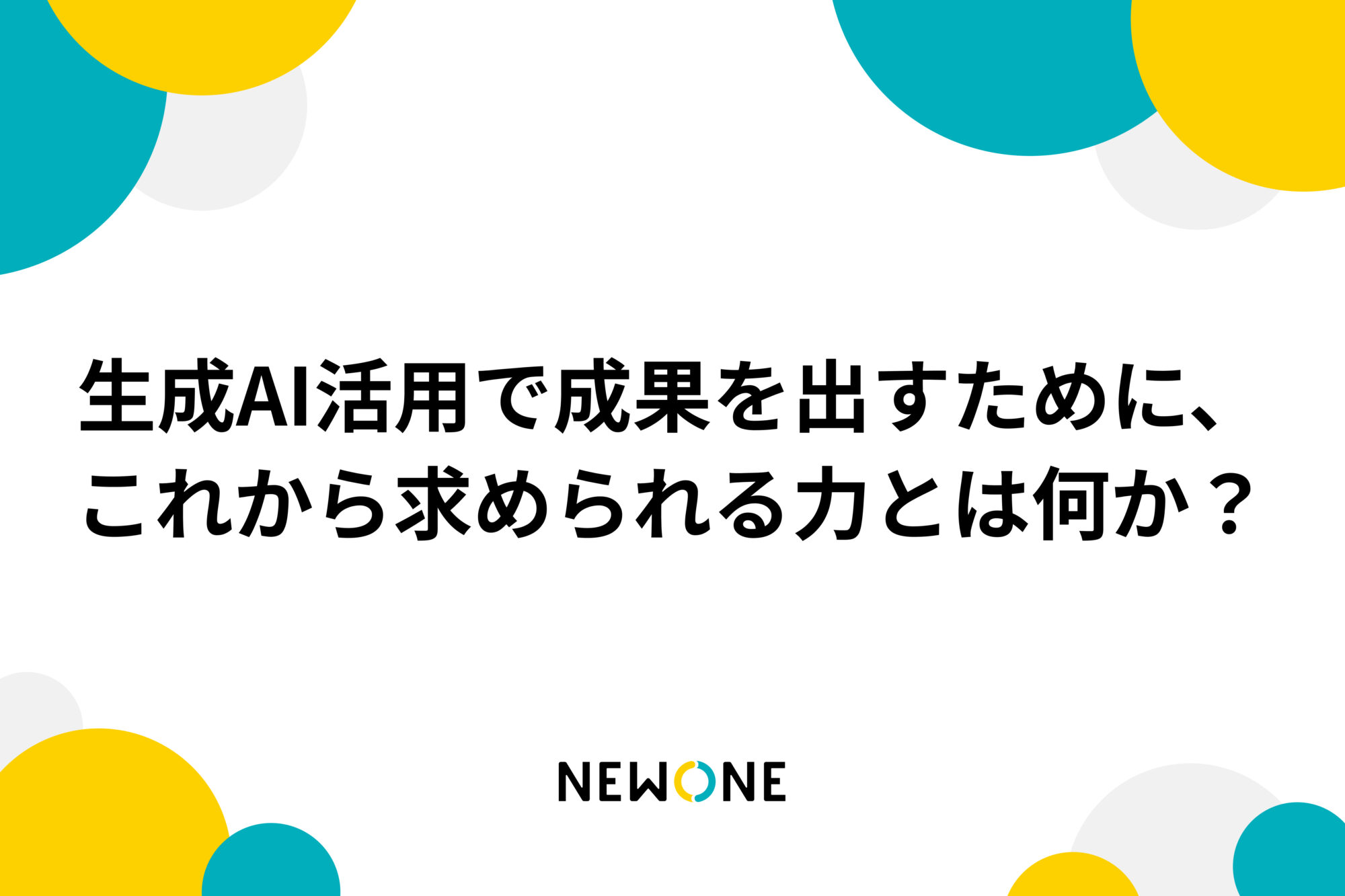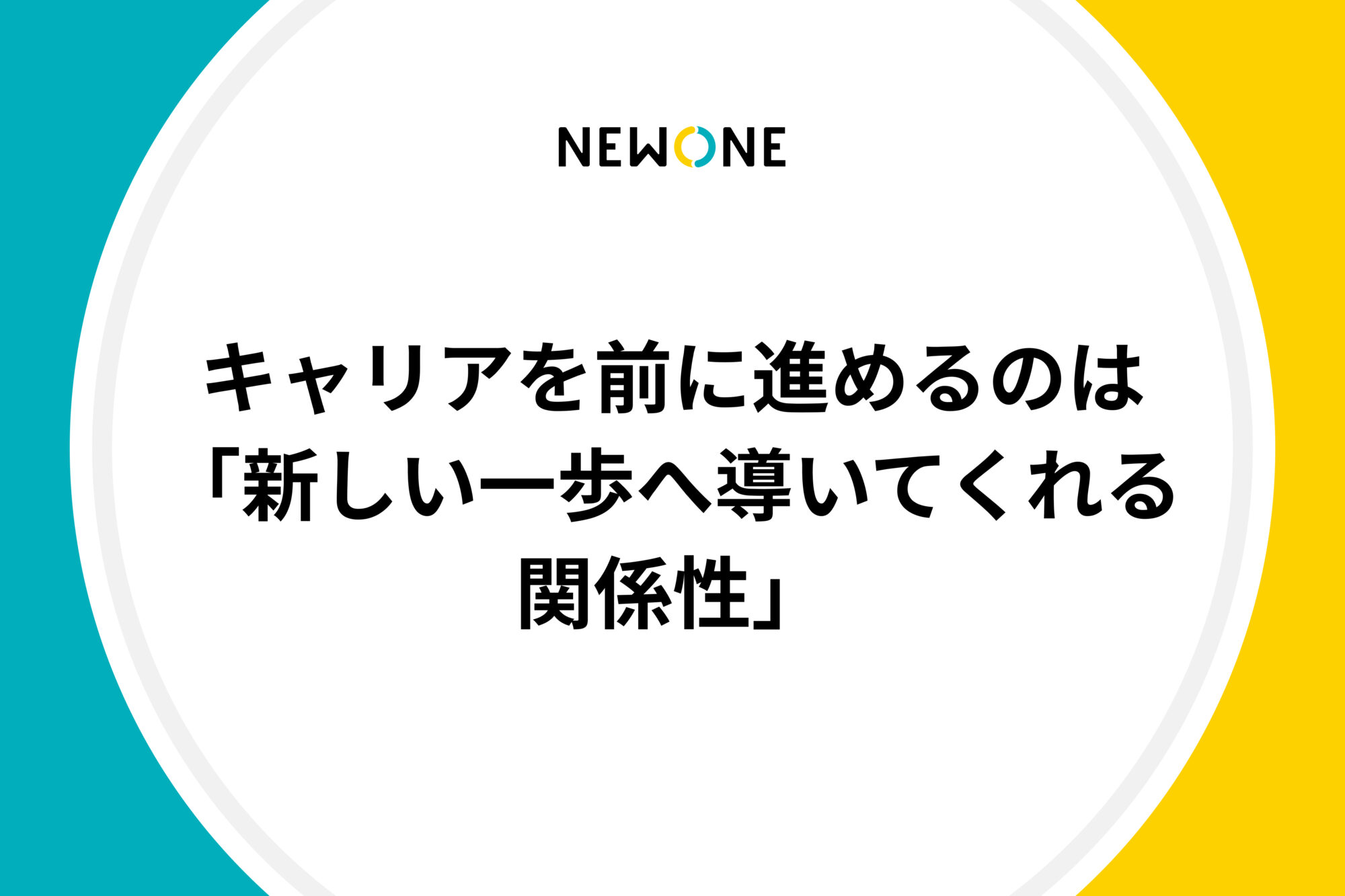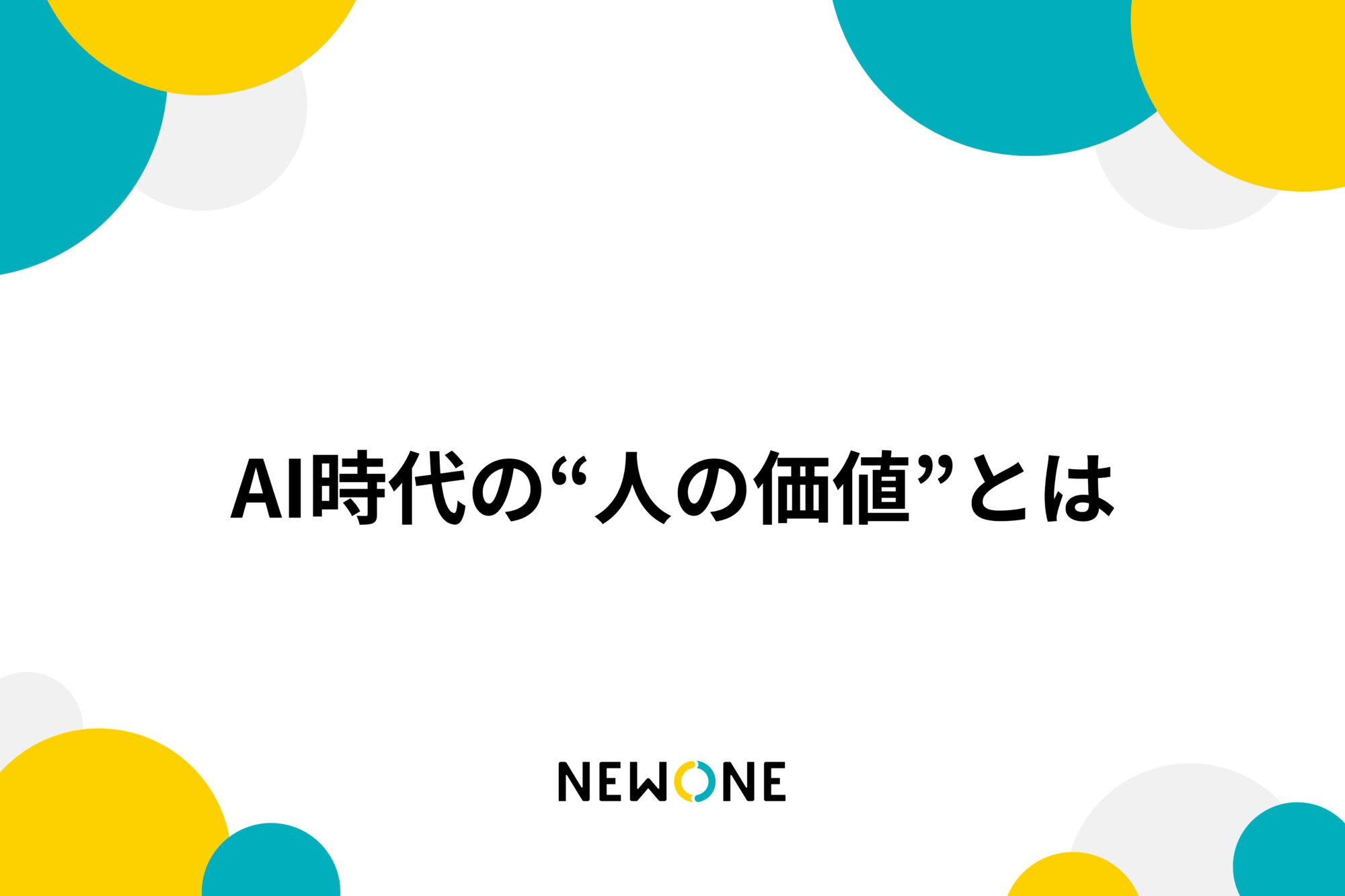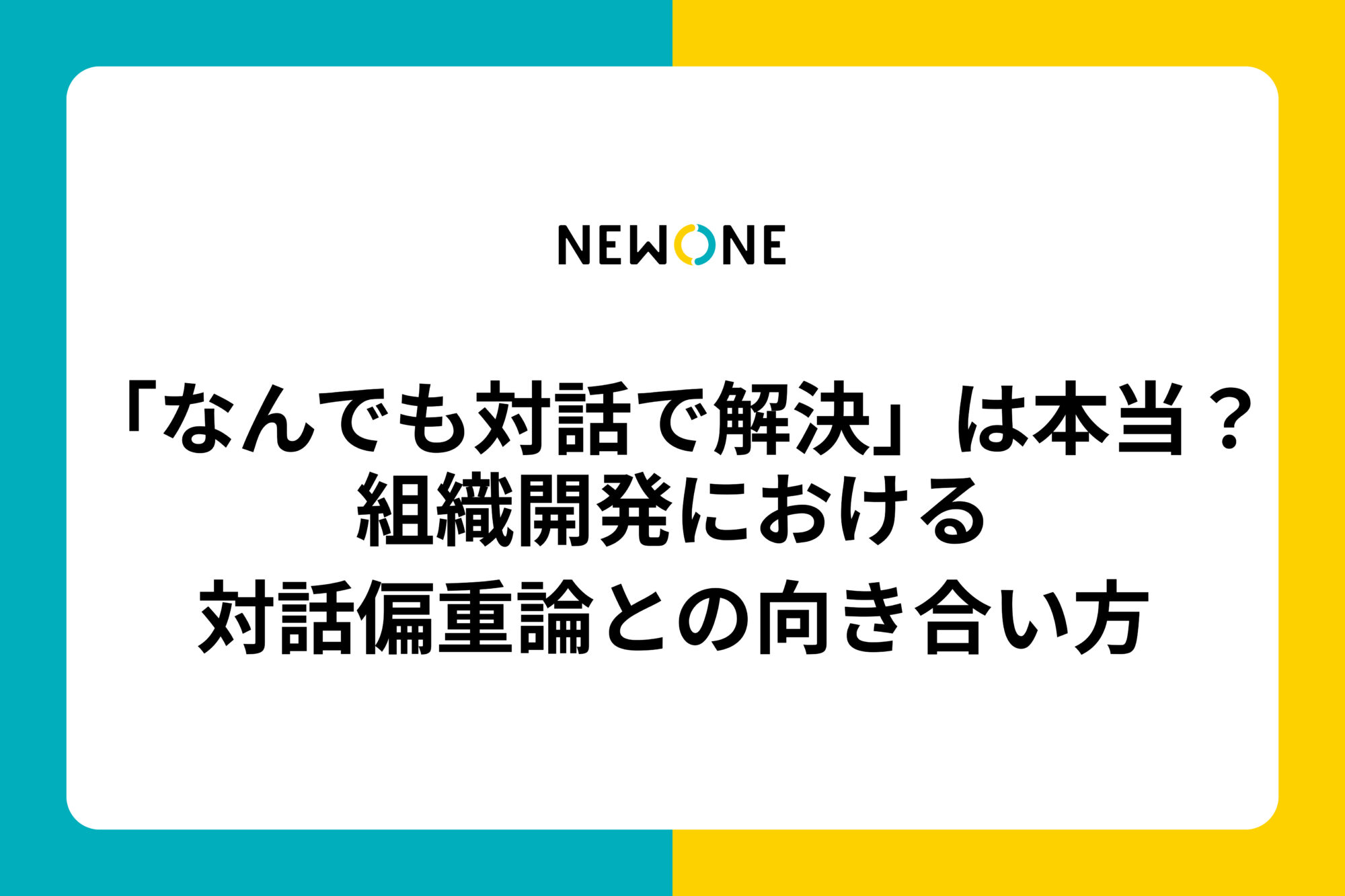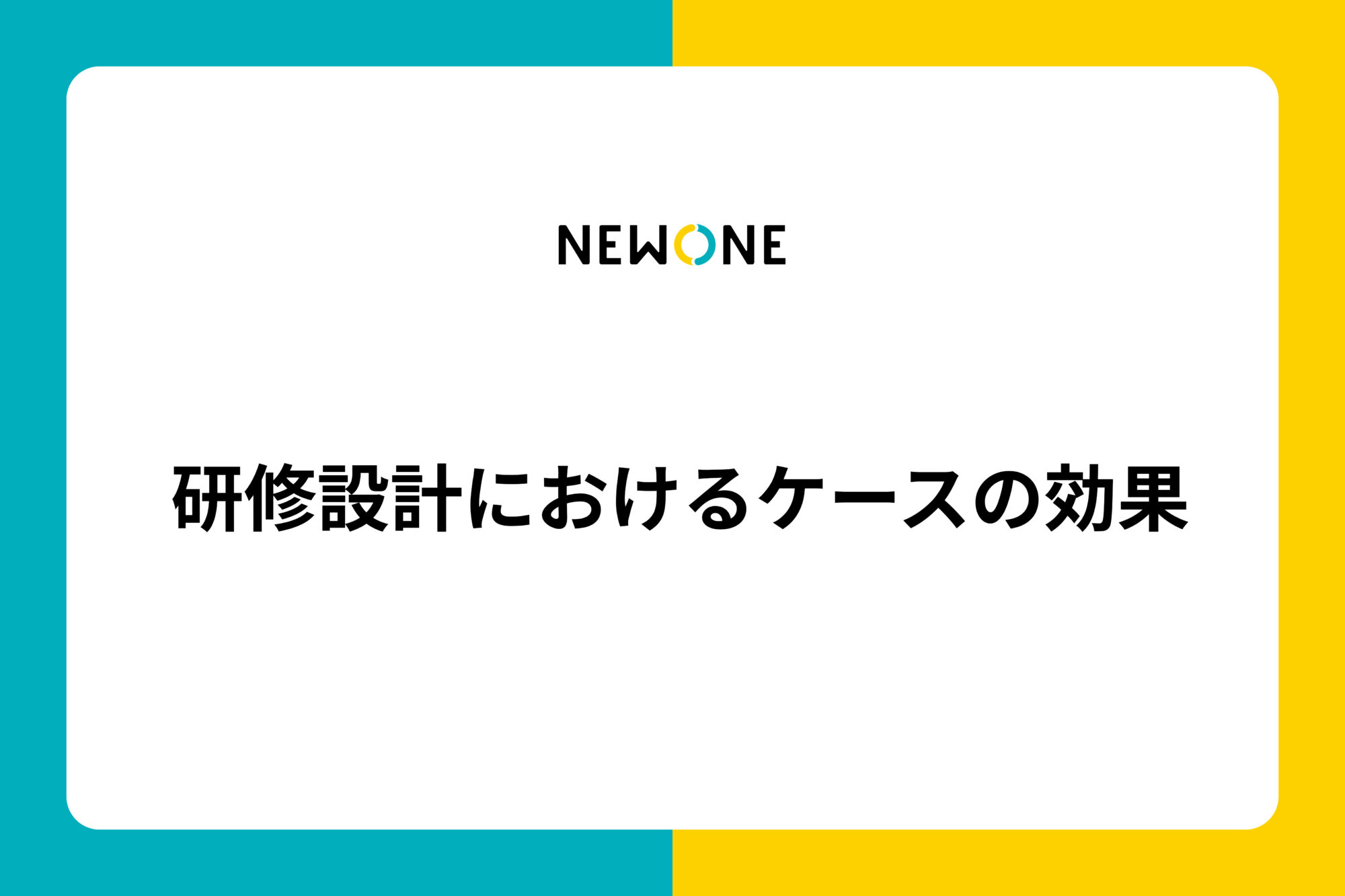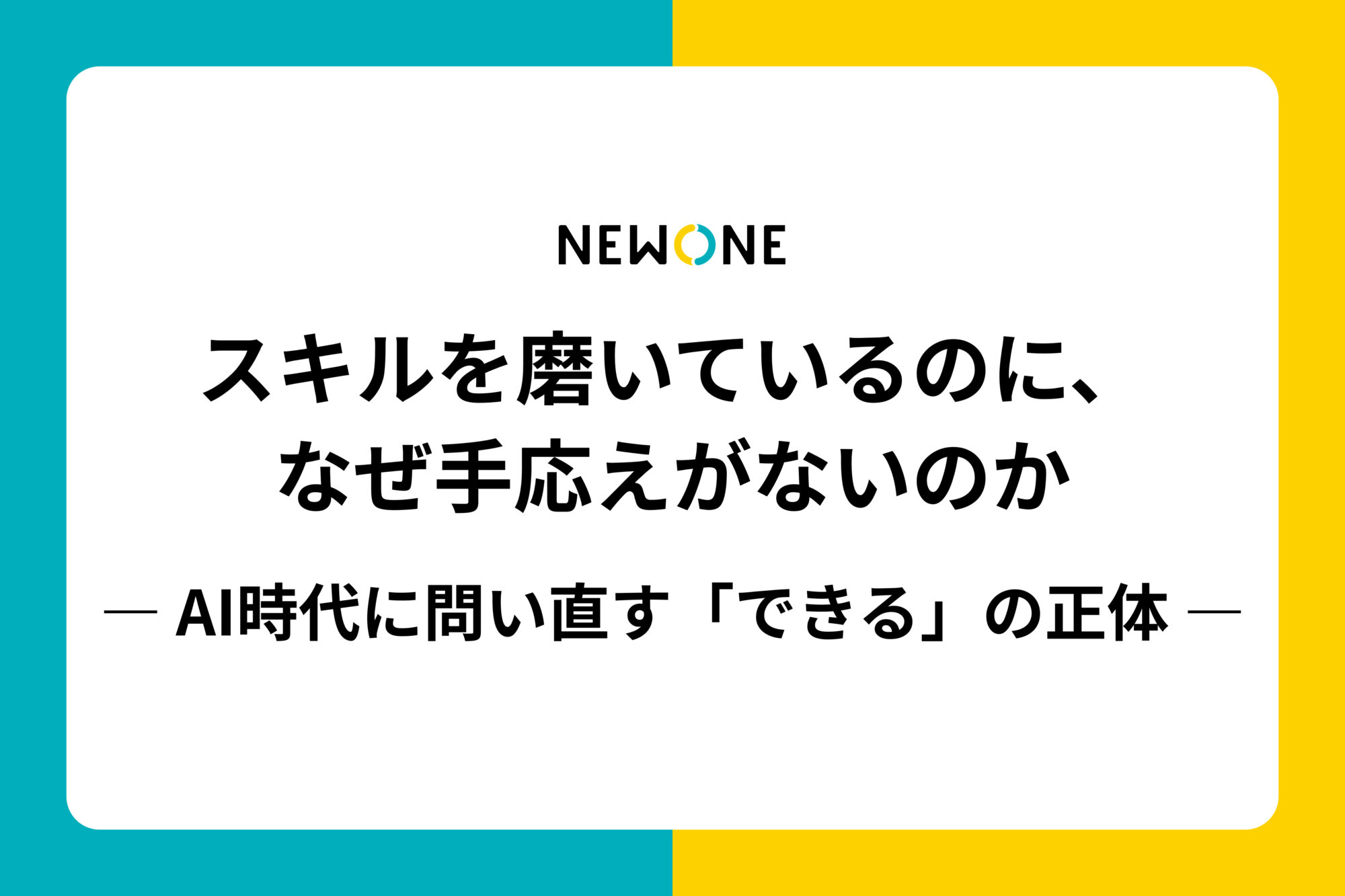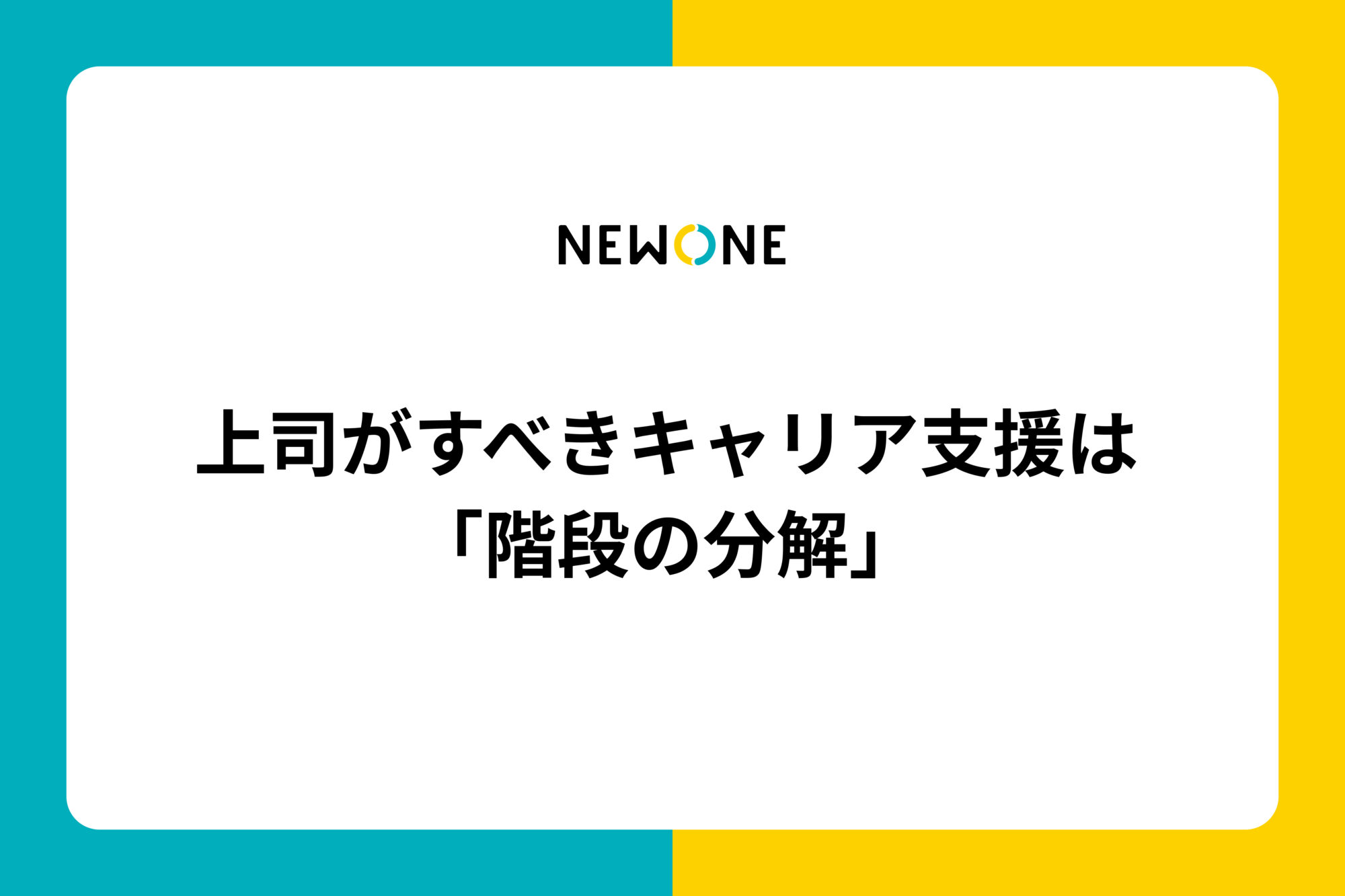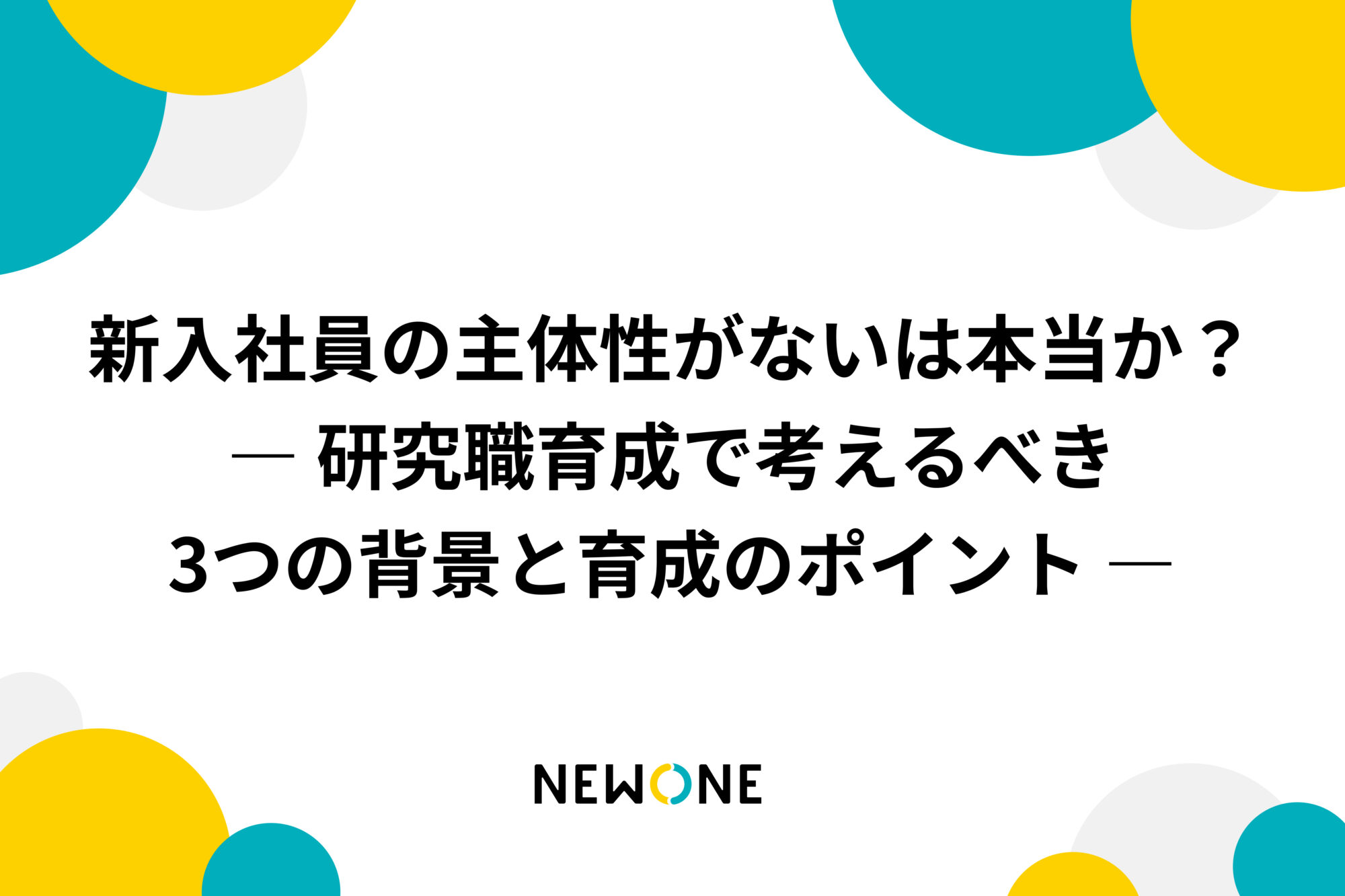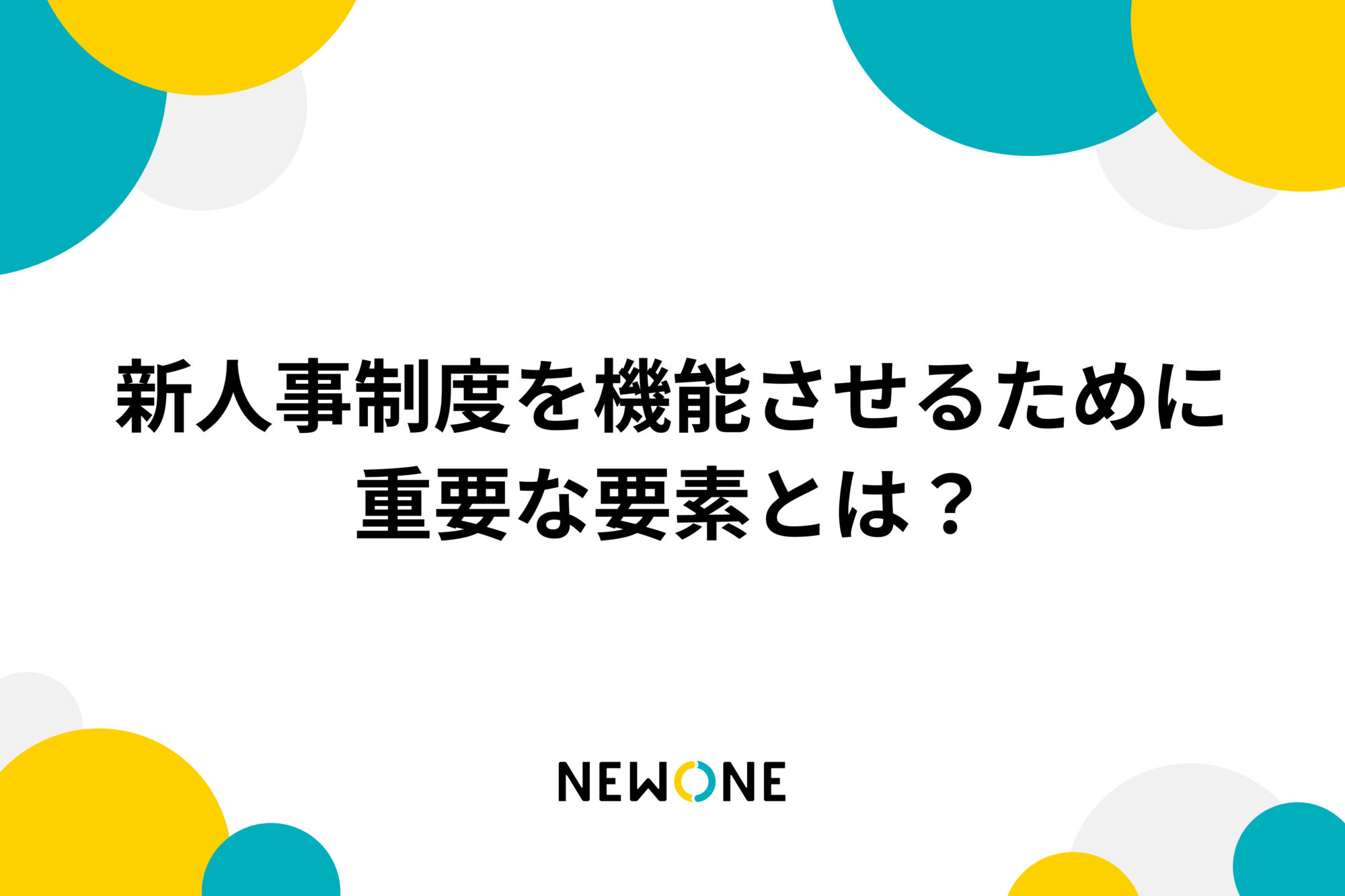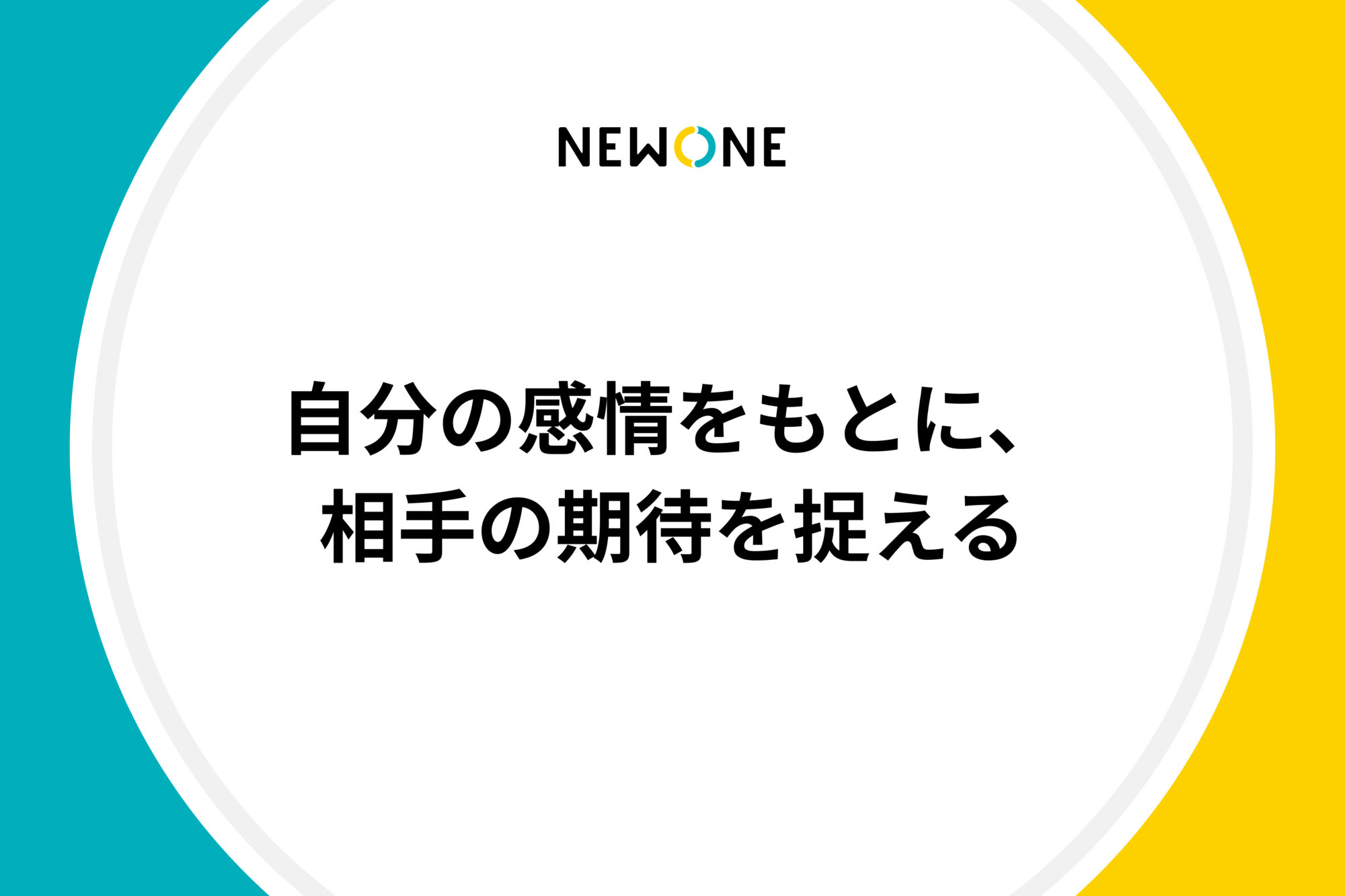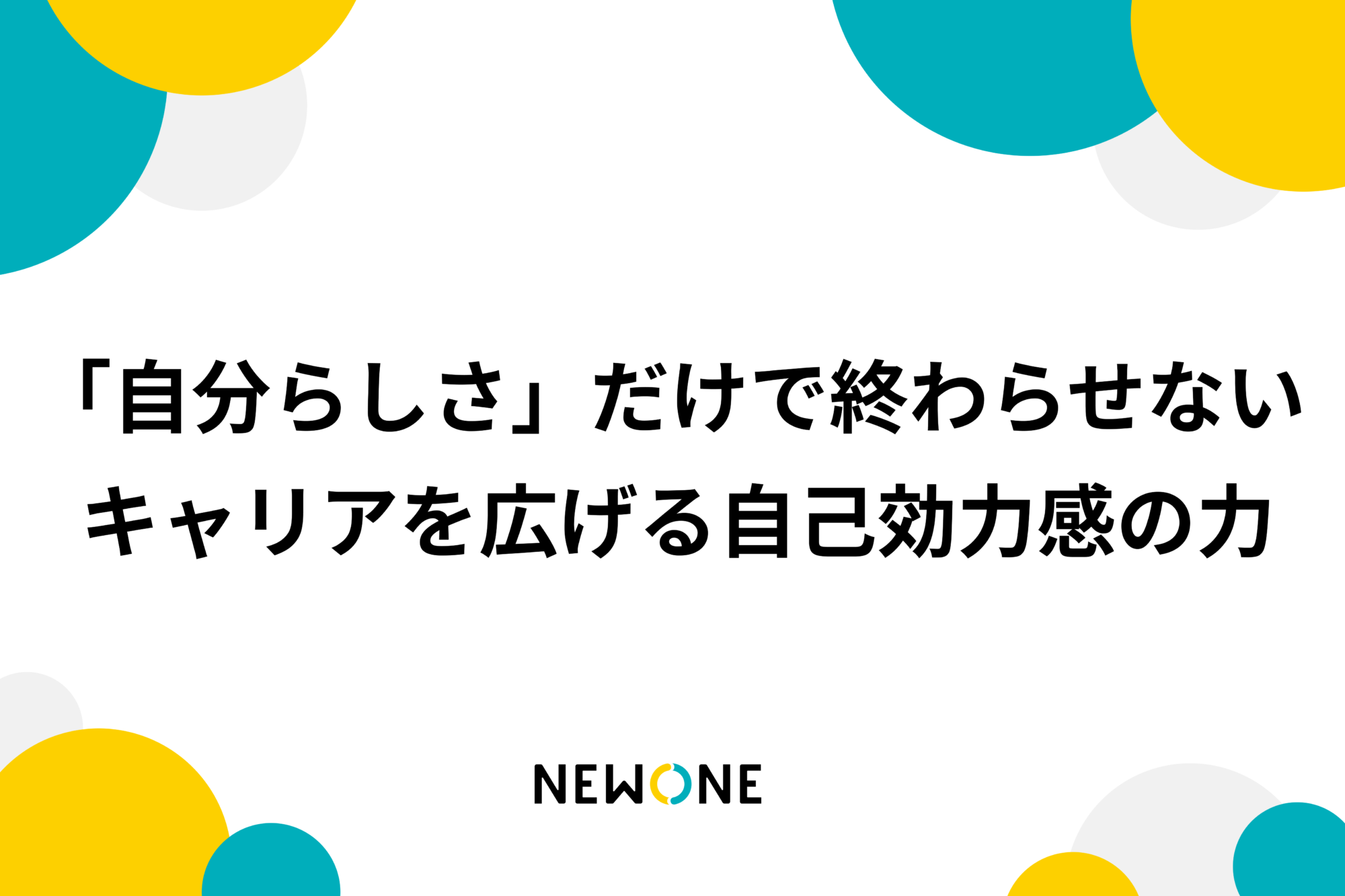
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
働き方のスタイルや選択肢が広がった今、「自分らしく働く」「自己肯定感を満たしながら働く」という言葉を耳にする機会が増えました。
フリーランスやインフルエンサー、ワーキングホリデーなど、多様な働き方が浸透するなかで、自分らしさを大切にしたいという願いは自然なことです。
一方で、私たちの研修では「自己効力感」を高めることも重要だと考えています。
一見似ているようで異なる「自己肯定感」と「自己効力感」という単語ですが、この記事では、この2つの単語がどう違うのか、 自身のキャリアや働くことを考えるうえで、自己肯定感や自己効力感とどう向き合っていくべきなのかを考えていければと思います。
自己肯定感と自己効力感の違い
まずは言葉の意味を整理してみましょう。
自己肯定感:自分自身の価値や能力を認め、受け入れる気持ち
自己効力感:課題や困難に直面したとき、「自分なら対処できる」と未来に向かって信じられる気持ち
私たちは研修の中で、自己効力感を「ある目標を達成できるという自分への信念」と説明しています。
つまり、
自己肯定感は 安心や安定を支える土台
自己効力感は 挑戦や成長を駆動する原動力と位置づけられるのです。
自己肯定感は安心感をもたらしますが、それだけでは現状維持にとどまりやすく、
一方、自己効力感は挑戦や成長を後押しし、キャリアを広げていく原動力となるのです。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
「今の自分」と「未来の自分」をどう見つめるか
自己肯定感だけにとらわれすぎると、「今・現状の自分」にベクトルが向いてしまいます。
その結果、周囲や環境の変化に適応できず、挑戦を避けてしまったり、変化を嫌い「今の自分が通用する現状」を維持しようとしてしまうことにもつながります。
さらには「これは自分らしくない」「自分には向いていない」とレッテルを貼り、結果として成長の機会を逃してしまうことにもつながりかねません。
一方で、自己効力感が高い人は未来を見据えています。
ある研修の場で、講師が受講者にこんな問いを投げかけました。
「先輩から“もっと積極的に発言してほしい”と指摘されたら、どう受け止めますか?」
すると、一人の受講者はこう答えました。
「今はまだできていないけれど、これから成長していけば自然にできるようになると思います。だから、できるようになるまで頑張ろうと考えます」
この言葉には、未来にベクトルを向ける自己効力感が表れています。
「できない今」ではなく、「できるようになる未来」を信じているからこそ、課題に前向きに向き合えるのです。
こうした姿勢は、キャリアを歩むうえで大きな違いを生みます。
「これは自分らしくない」「向いていない」と早々に線を引いてしまえば、成長の芽は摘まれてしまいます。
逆に「今は不慣れでもやってみよう」と挑戦を重ねる人は、未来の自分を更新し続けることができます。
まとめ
もちろん、自己肯定感を軽んじてよいわけではありません。
安心できる土台(自己肯定感)のうえに、未来に向けて挑戦する自己効力感があることが理想です。
変化が激しく、正解が見えにくいこれからのキャリアにおいては、「今の自分を守る」だけでなく「未来の自分を育てる」という自己効力感の視点を持って、自分のキャリアを歩むことはこれからさらに重要度が増していくことでしょう。
日々の業務の取り組み方一つからでも、積み重ねていくことで自己肯定感は育まれていきます。まずは自分で小さな目標でも良いので目標を定めて、その目標に向けて努力や改善を積み重ねる経験を増やしていけると良いのではないでしょうか。
 徳 若菜" width="104" height="104">
徳 若菜" width="104" height="104">