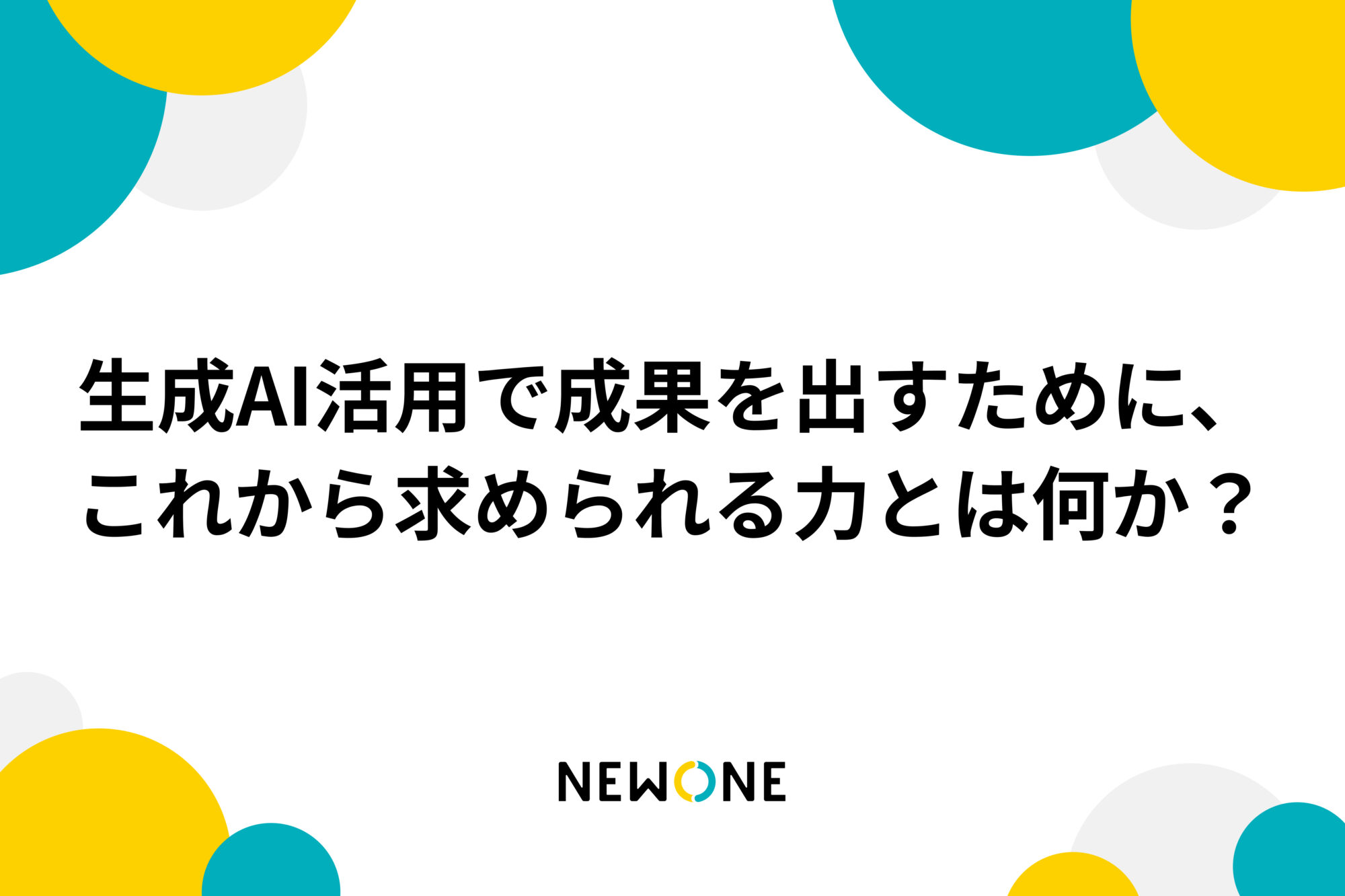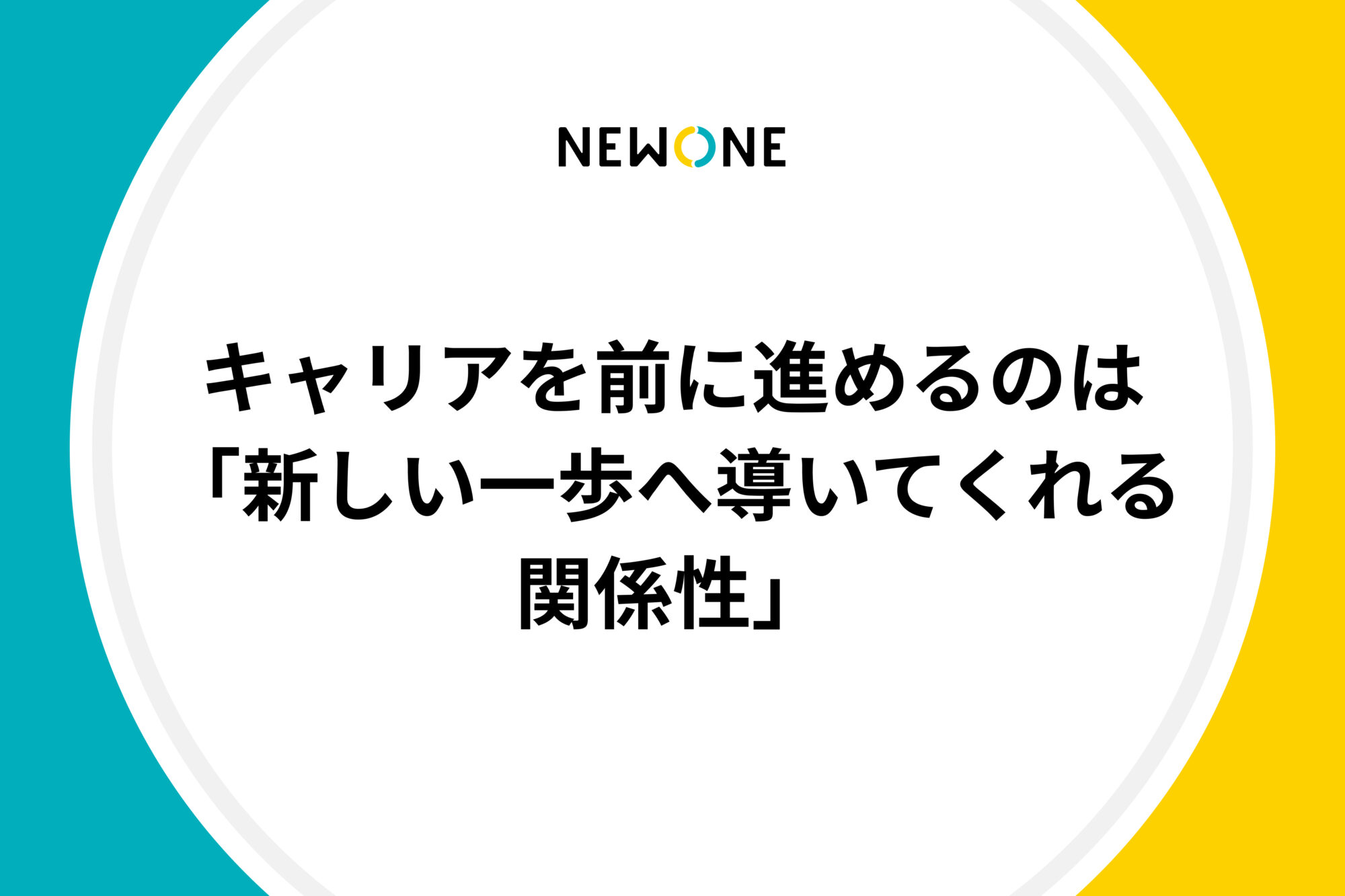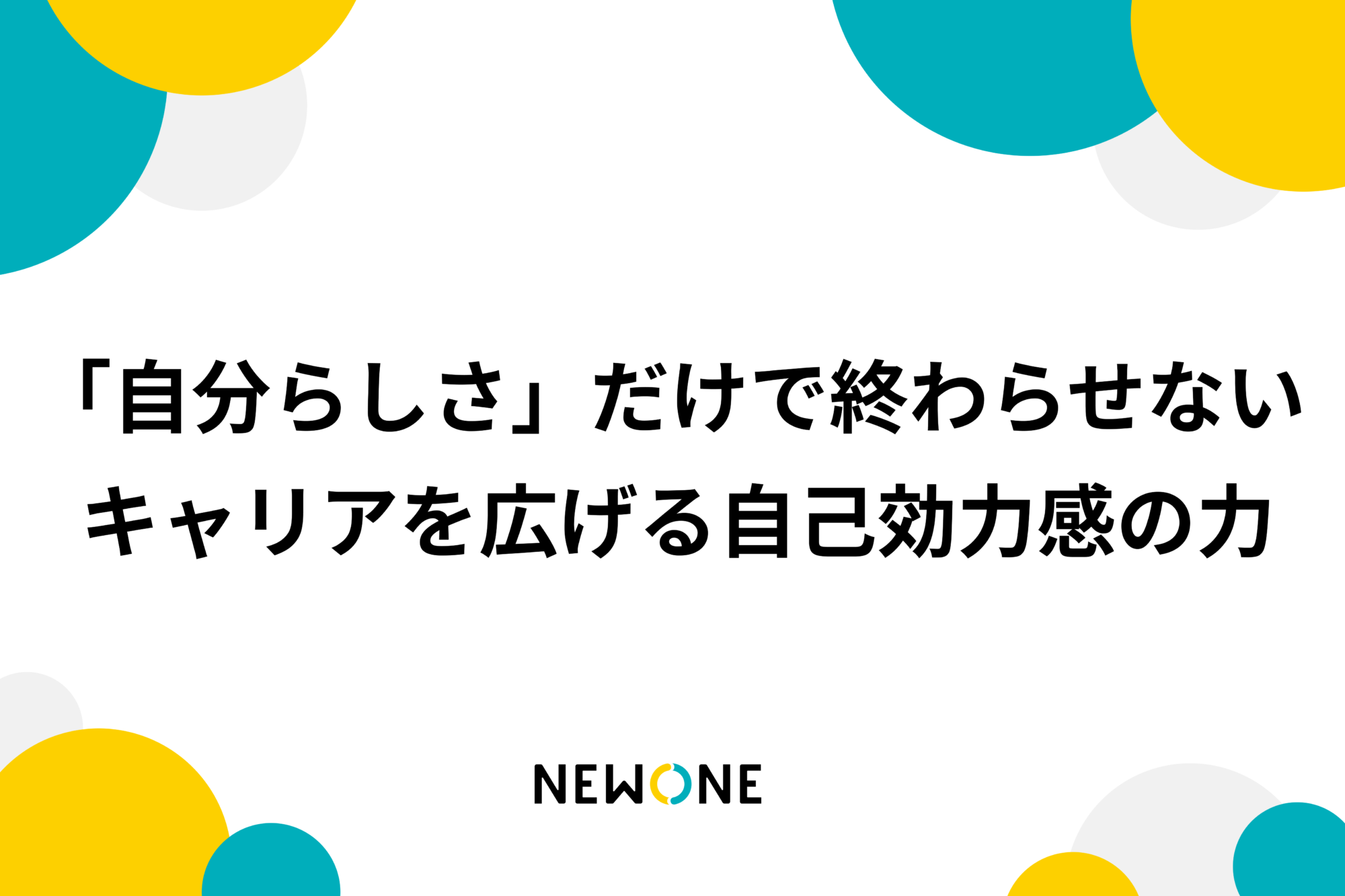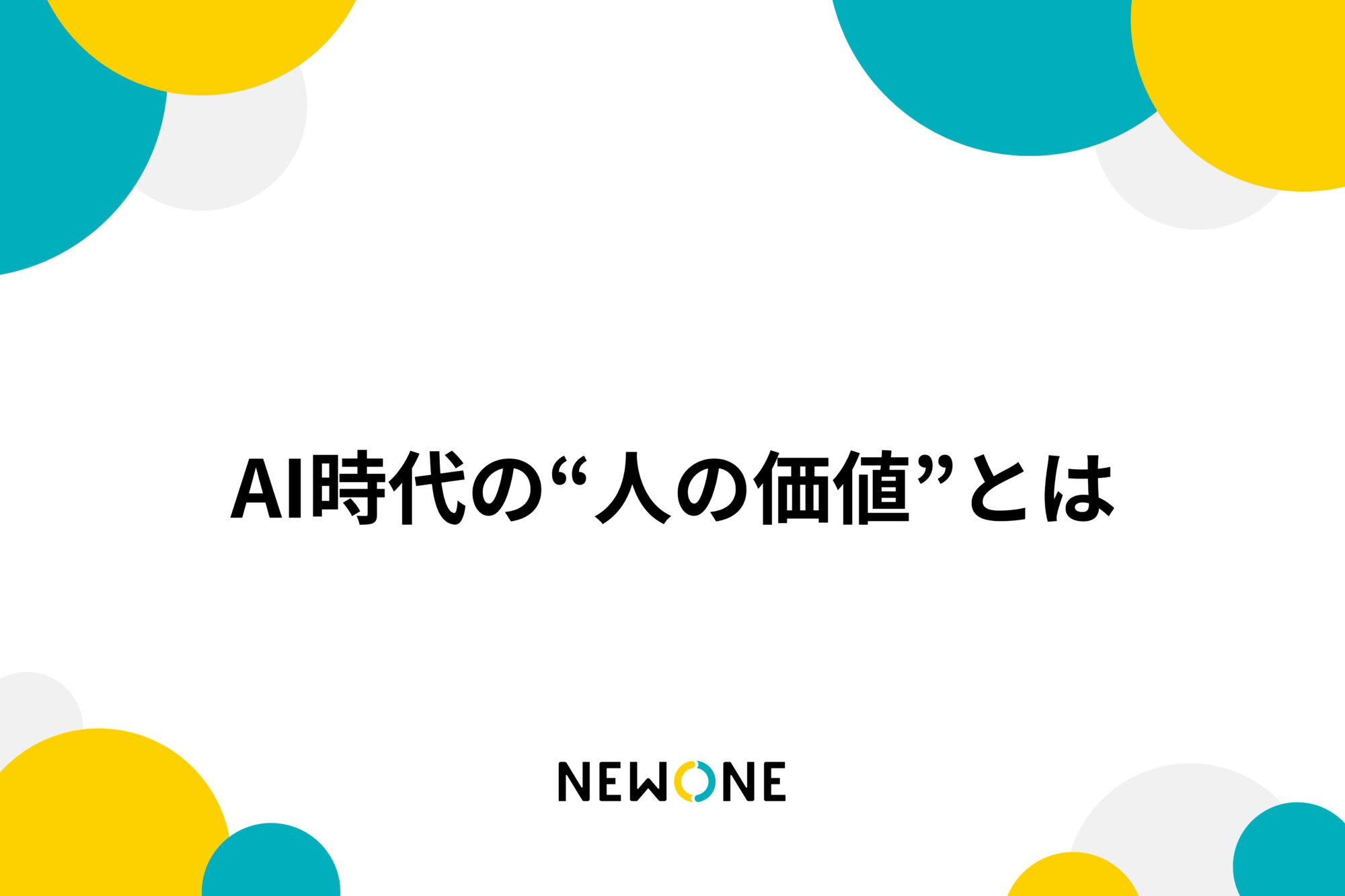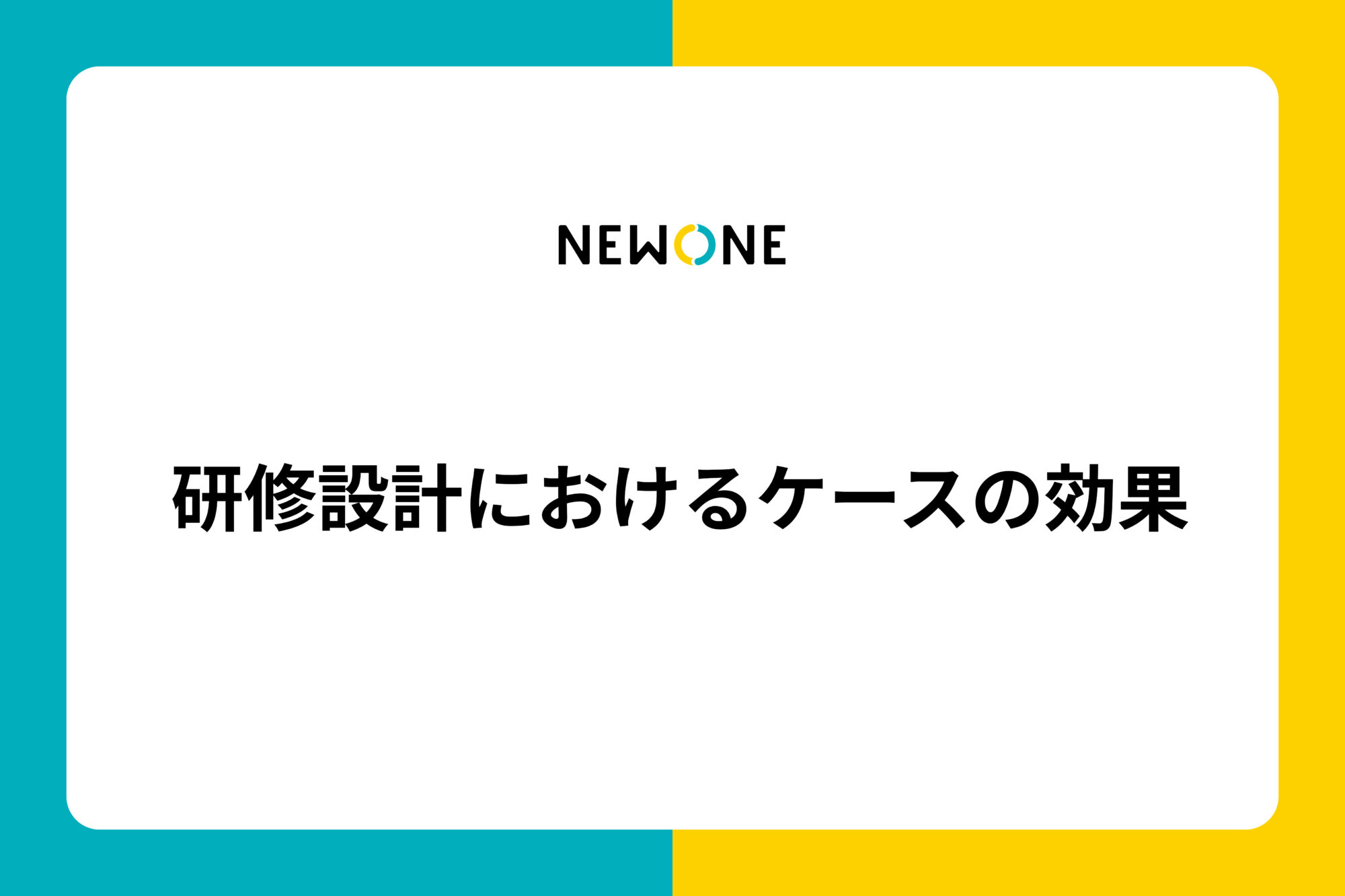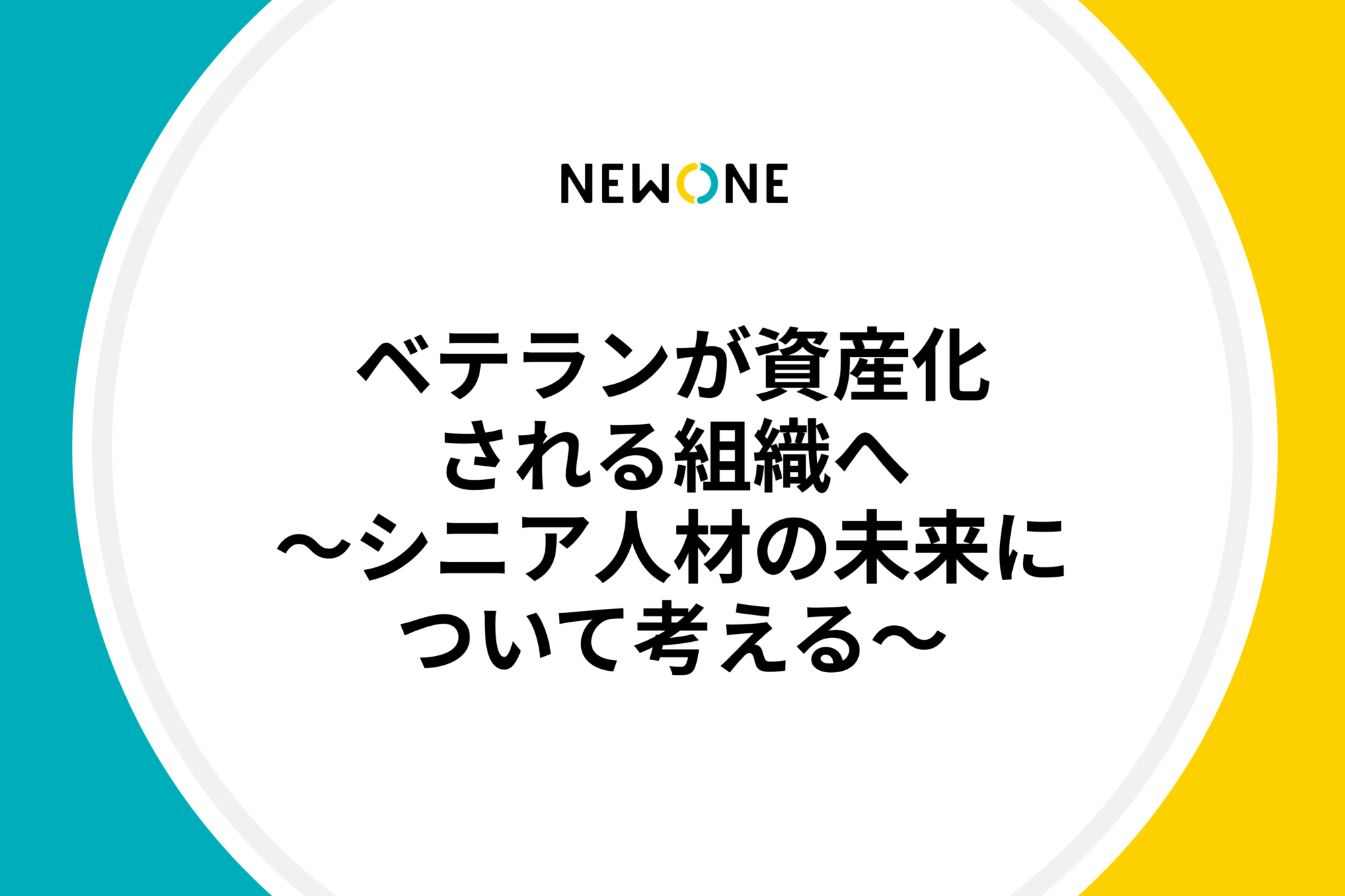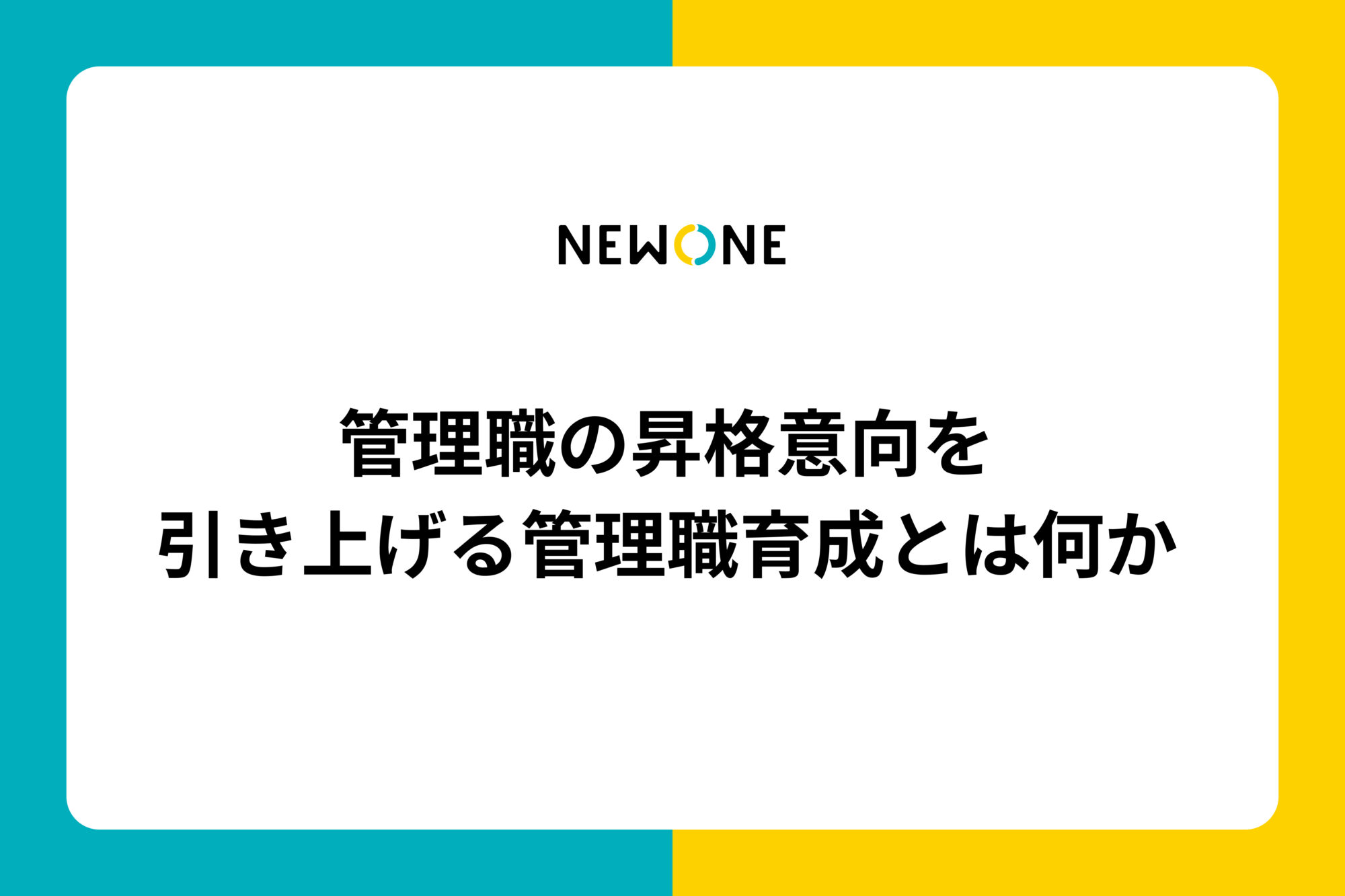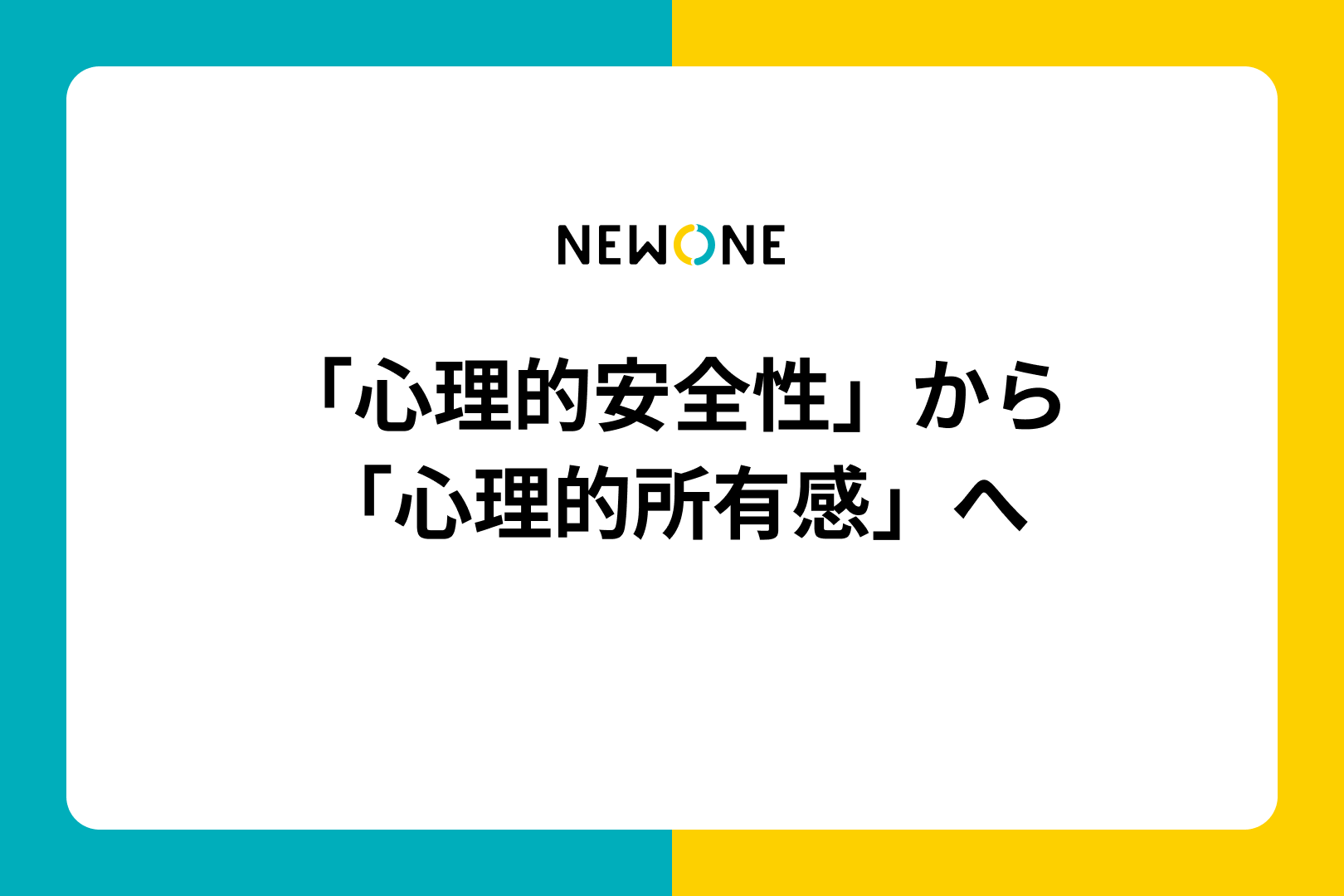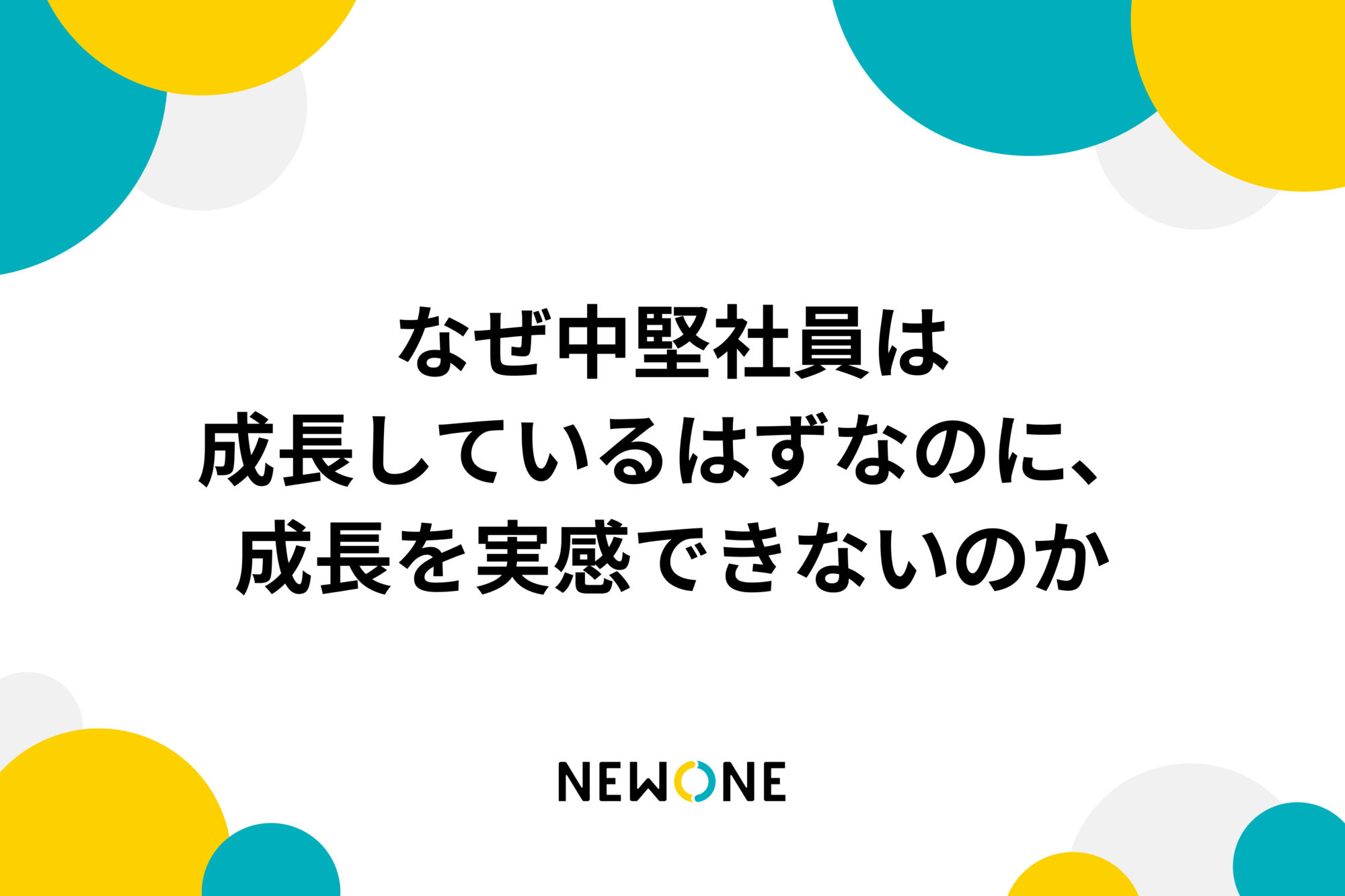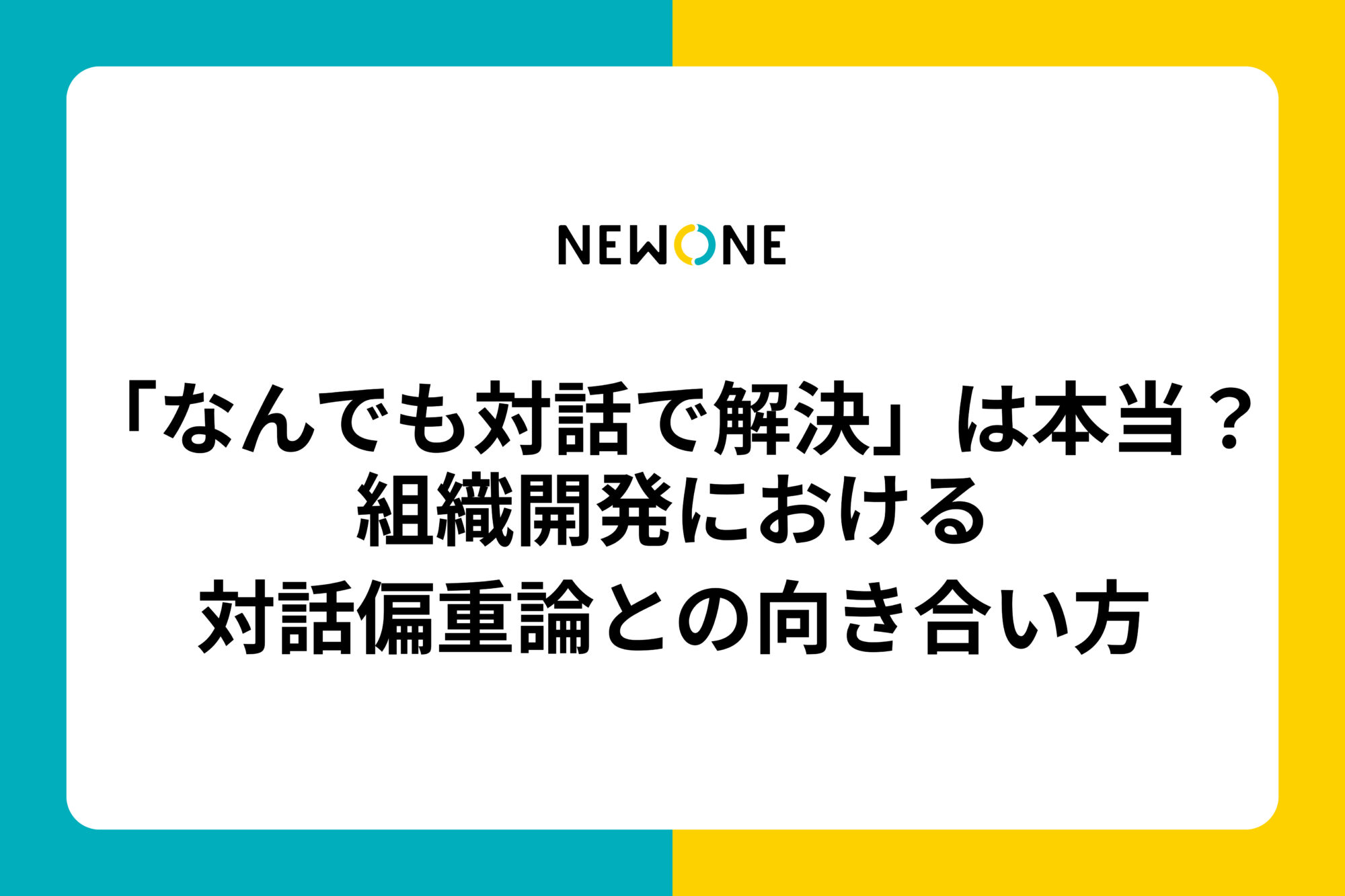
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
こんにちは。NEWONEの桶谷です。
最近、「組織開発」や「組織変革」に関する書籍や記事を読むと、最終的な解決策として「対話」が強調されるケースが多いと感じます。
しかし、「本当に対話だけで解決できるのか?」「組織開発における対話の限界はないのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
対話とは何か? 組織開発における役割
私たちは「対話」を、互いの前提や意見の違いを理解し、個々の特性や強みを成果につなげるコミュニケーション手法と定義しています。
つまり、対話は「あなたと私の違いを知り、その違いを力に変えるプロセス」です。
もちろん、対話を通して違いを知り、適応課題に取り組むことは組織変革の第一歩です。
ただし多くの「組織開発ノウハウ」では、「対話ができることを前提」にしており、現場でどう機能させるかという視点が不足しているように思います。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
対話偏重への違和感を突破する2つの方法
1. 巻き込める16%にまず投資する
組織全体を一度に変えるのは現実的ではありません。
「キャズム理論」でも言われるように、まずは変化を推進できる16%のメンバーに集中して働きかけることが、カルチャー変革の起点になります。
2. 対話的○○を導入する
必ずしも対話の「場」にこだわらず、対話の目的を果たす仕組みを導入することも有効です。
たとえばフルリモートを導入している企業様では、社内配信や動画コンテンツで「互いを知る機会」を設ける工夫をしています。ただし、これは相互関心がある風土だからこそ機能しているのだ、というツッコミもあると思います。業界・業種によってはお互いのことをさらけ出す意味そのものから話し合ってもらう必要があるかもしれません。それぞれの組織体質に合った「対話的○○」を模索する必要があるでしょう。
まとめ:組織開発における「対話」の再定義が必要
- 対話は組織開発に欠かせないが、「万能薬」ではない
- まずは「巻き込める16%」に注力する
- 組織の特性に合わせた対話的な仕組みを導入する
「対話が重要なのは理解しているけれど、具体的なアクションが見えない」「対話だけで変われるのか疑問」という方にとって、今回の視点が参考になれば嬉しいです。
今後も「組織開発」「対話の限界」「組織変革の実践」について継続的に発信していきます。
 桶谷 萌々子" width="104" height="104">
桶谷 萌々子" width="104" height="104">