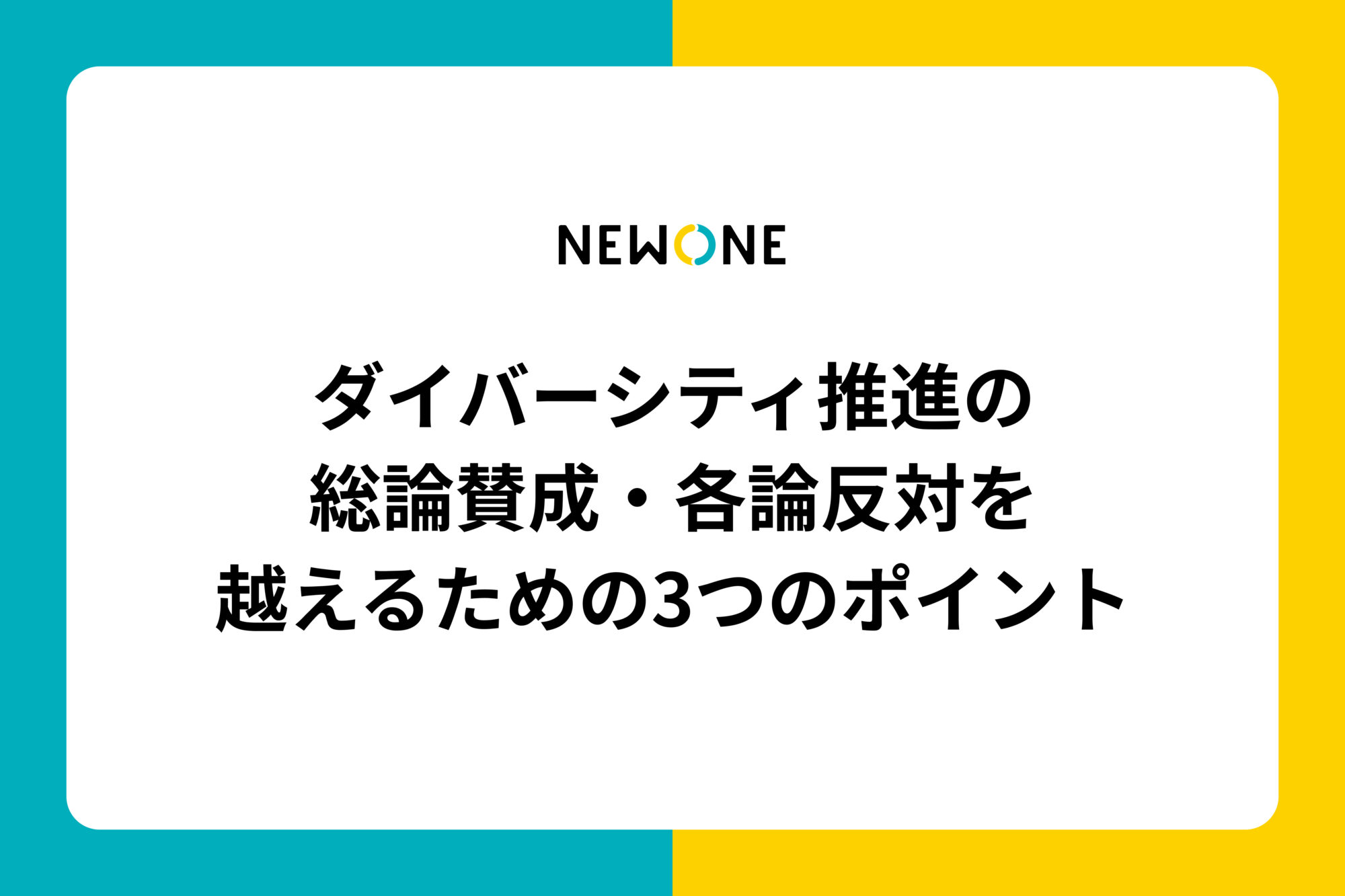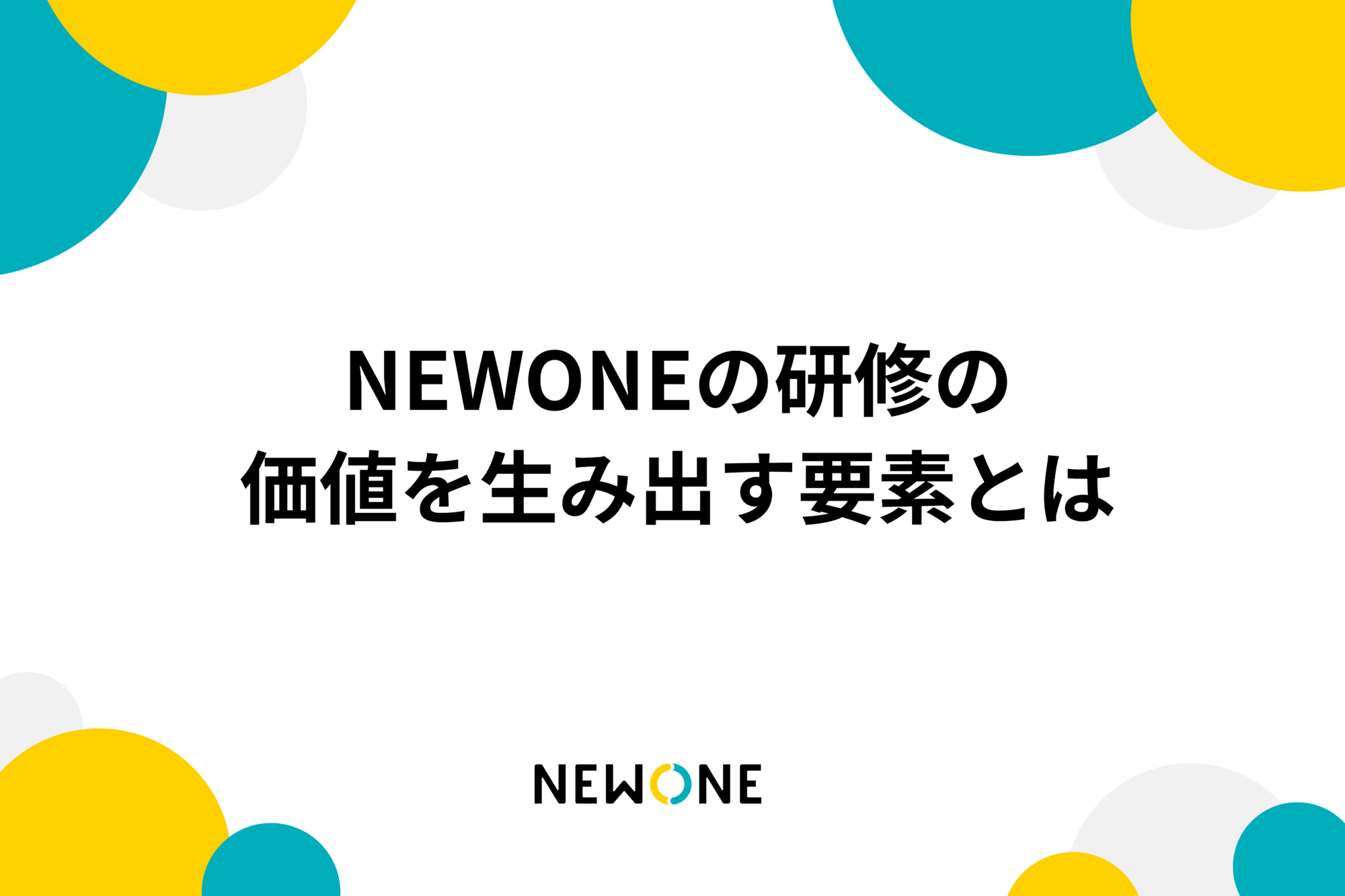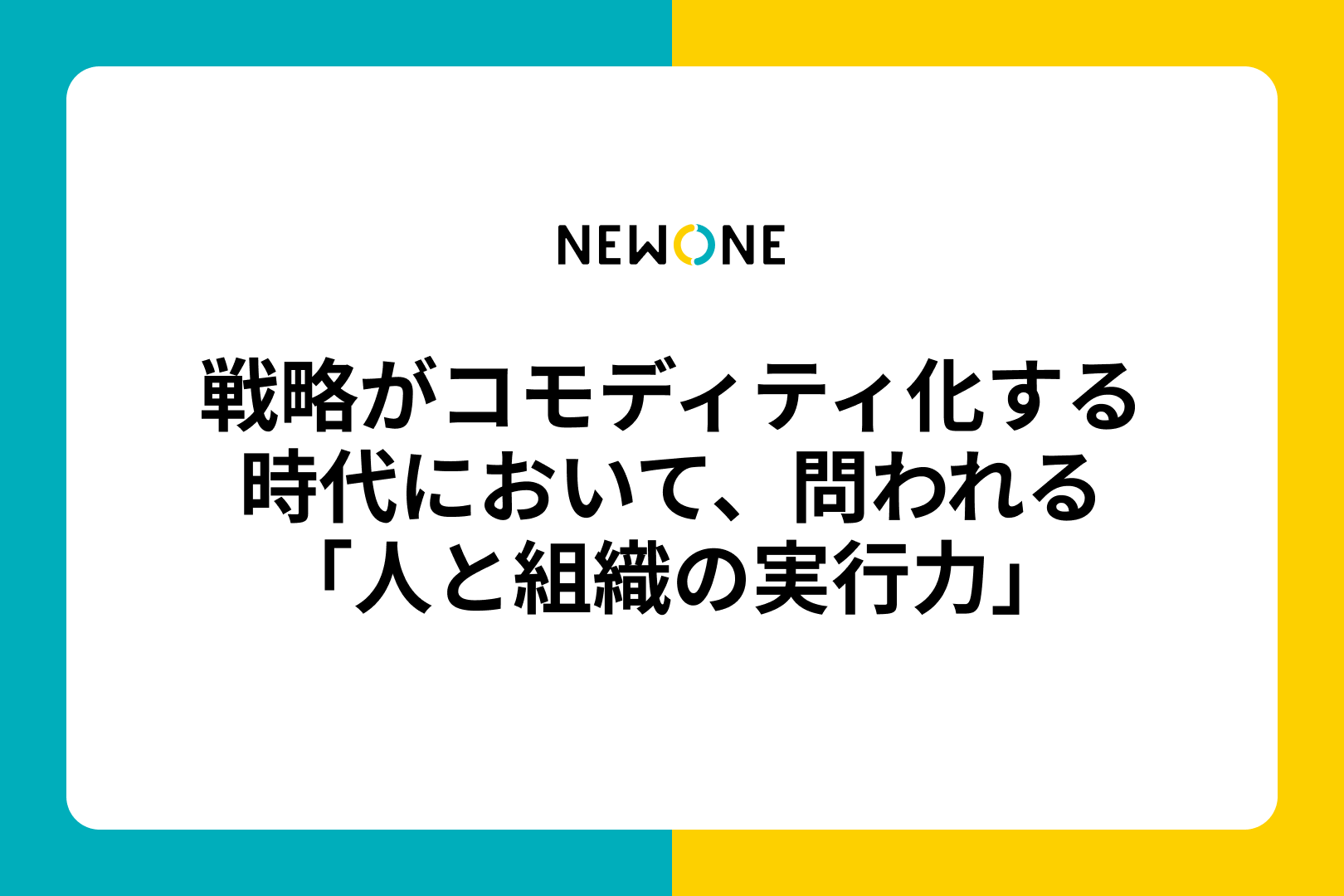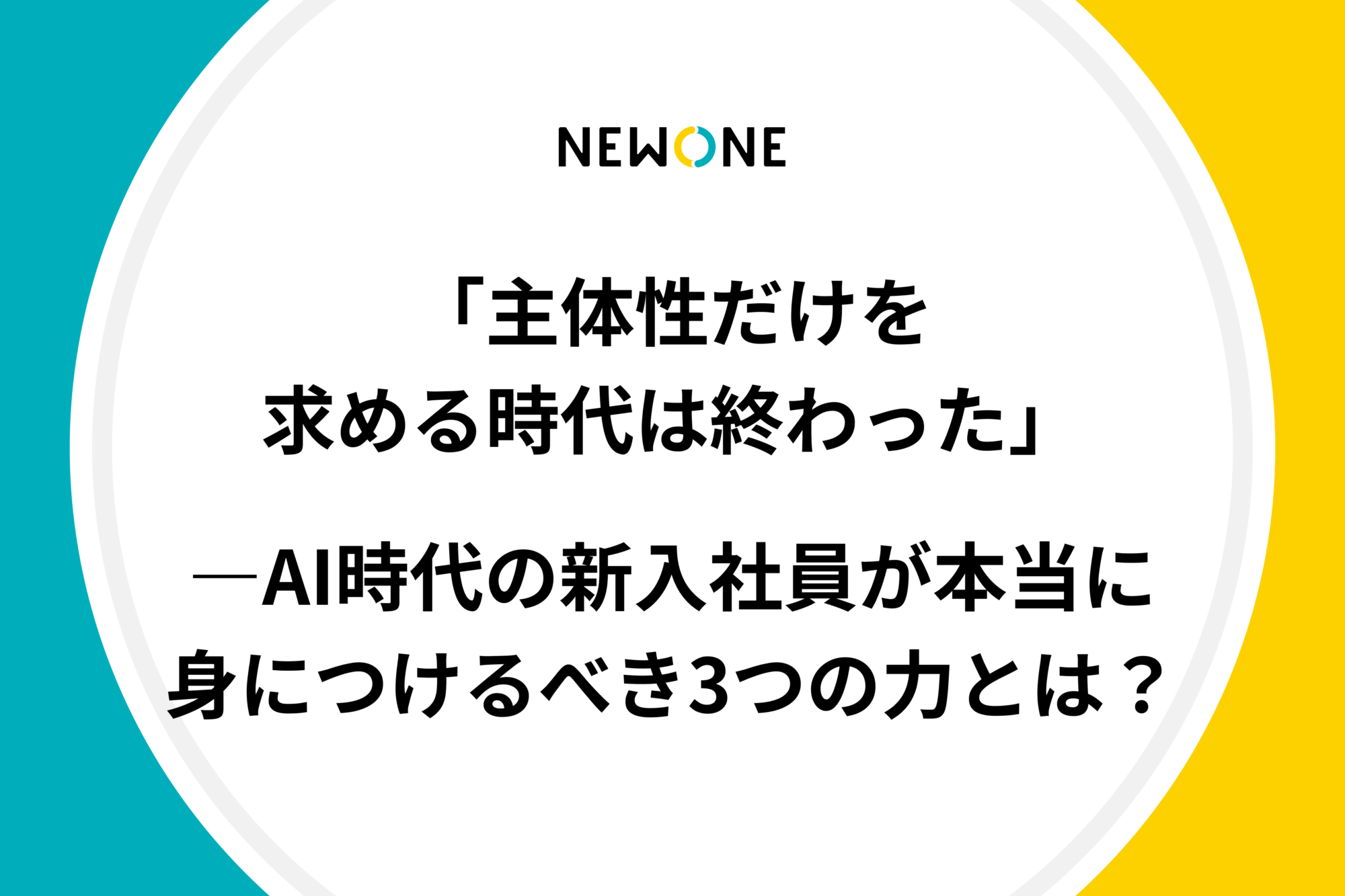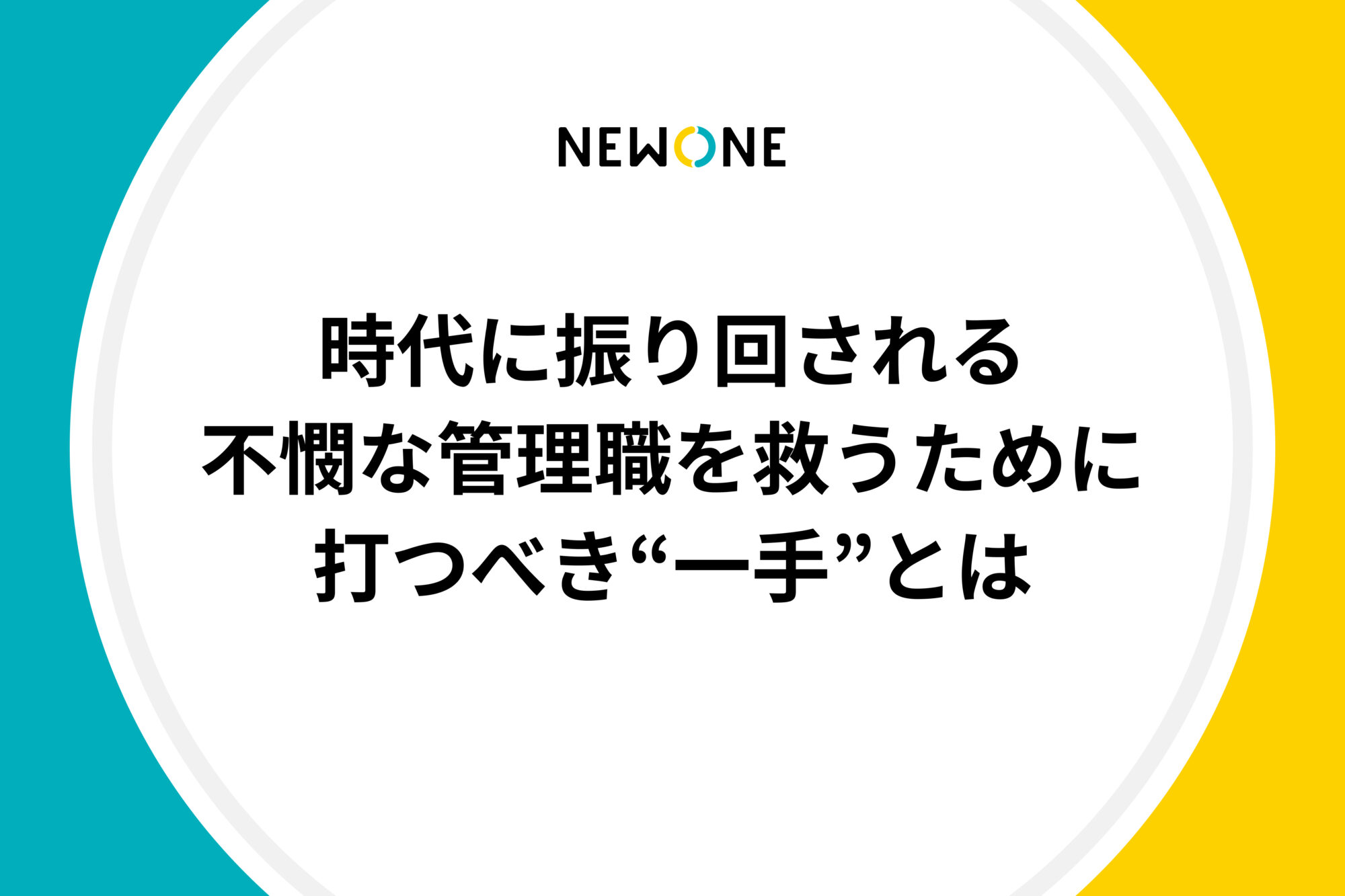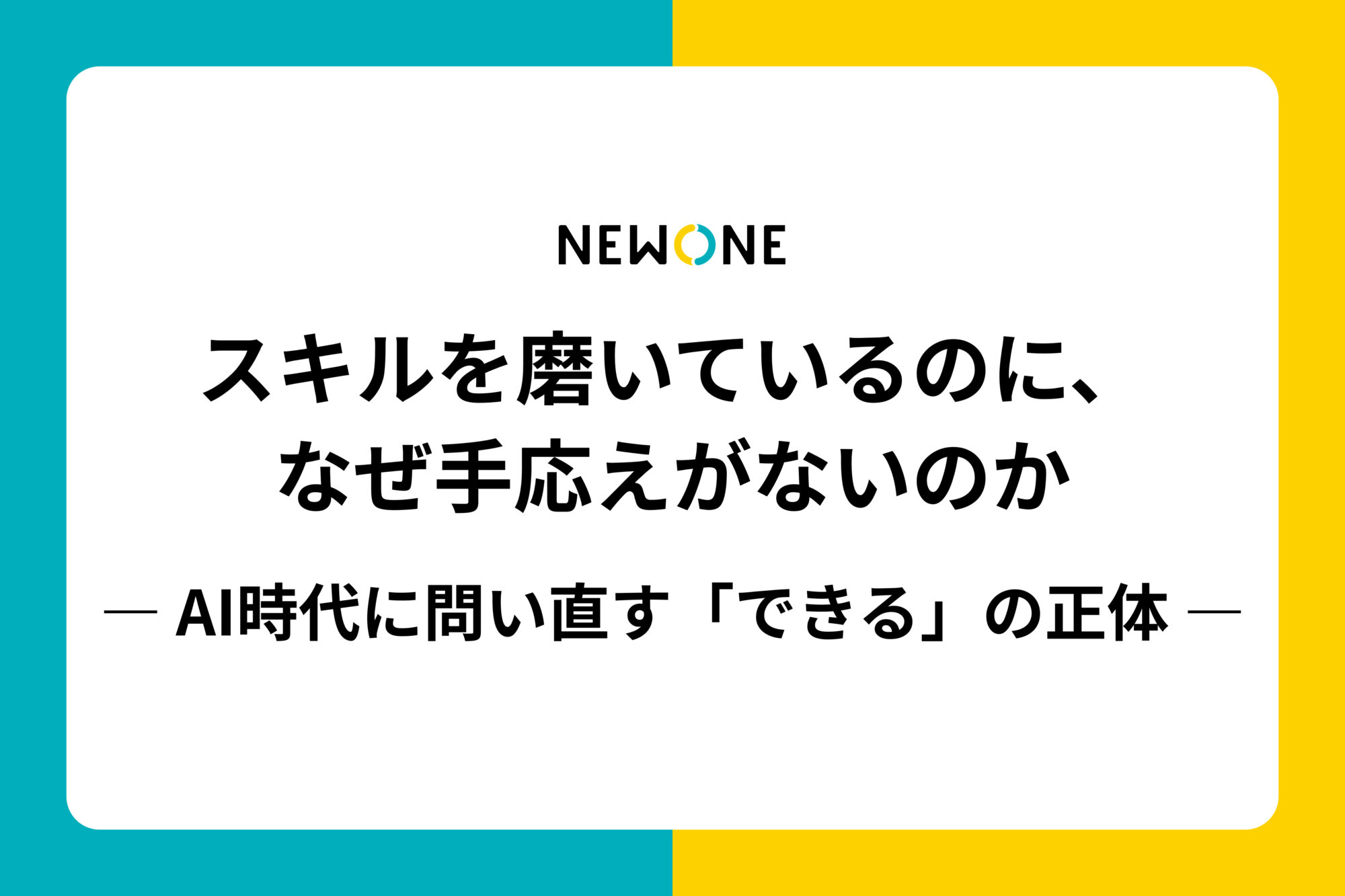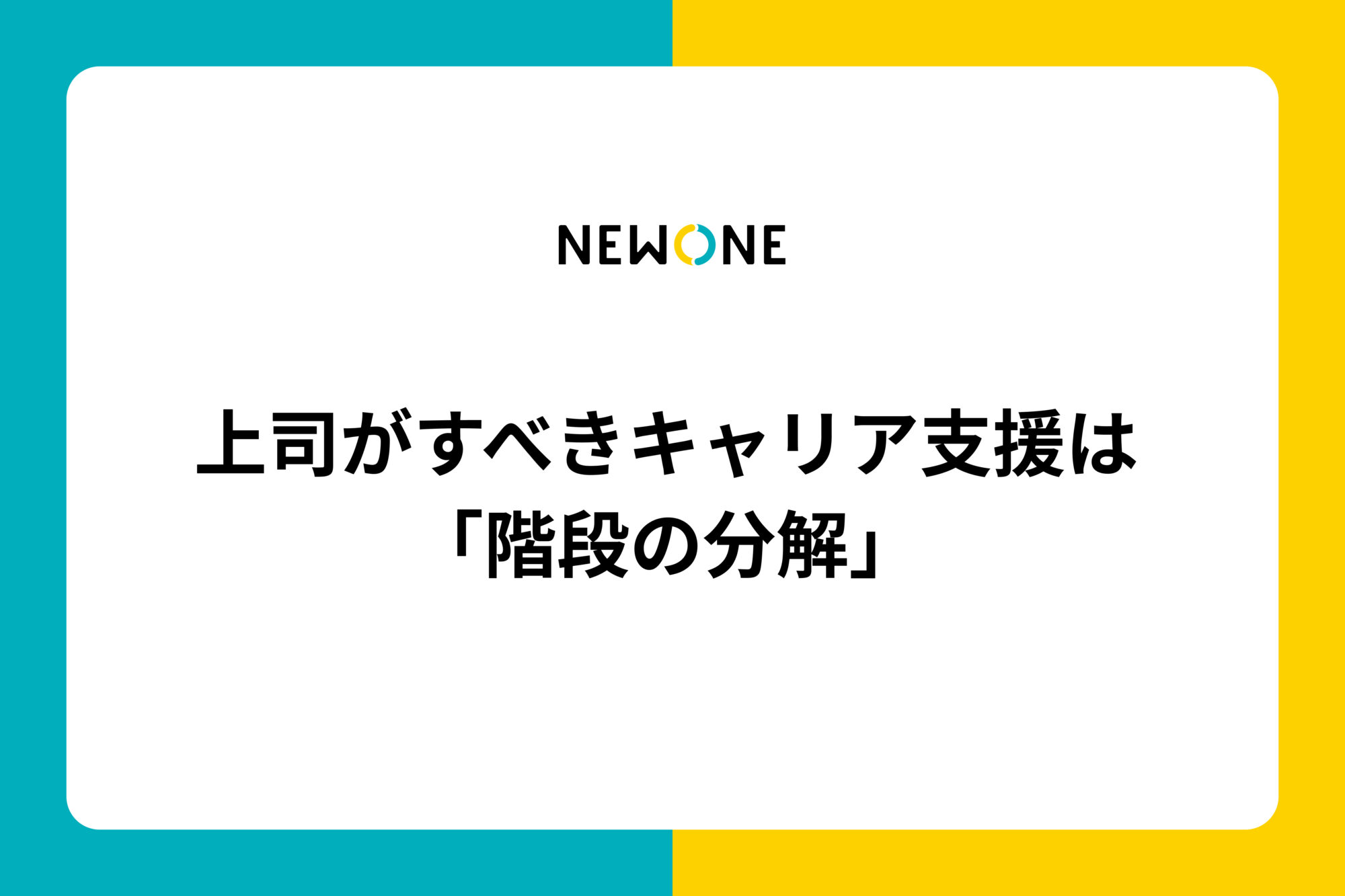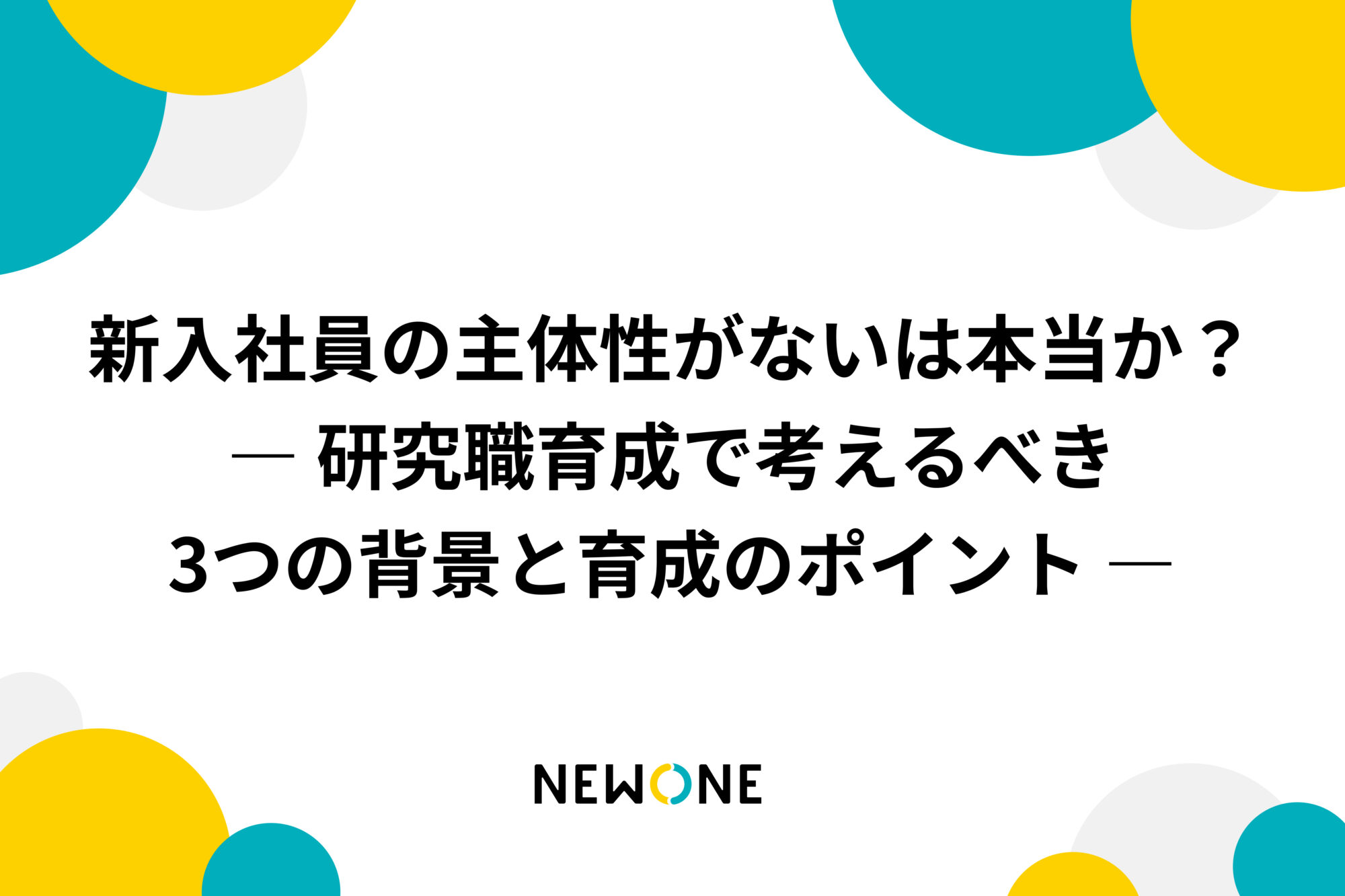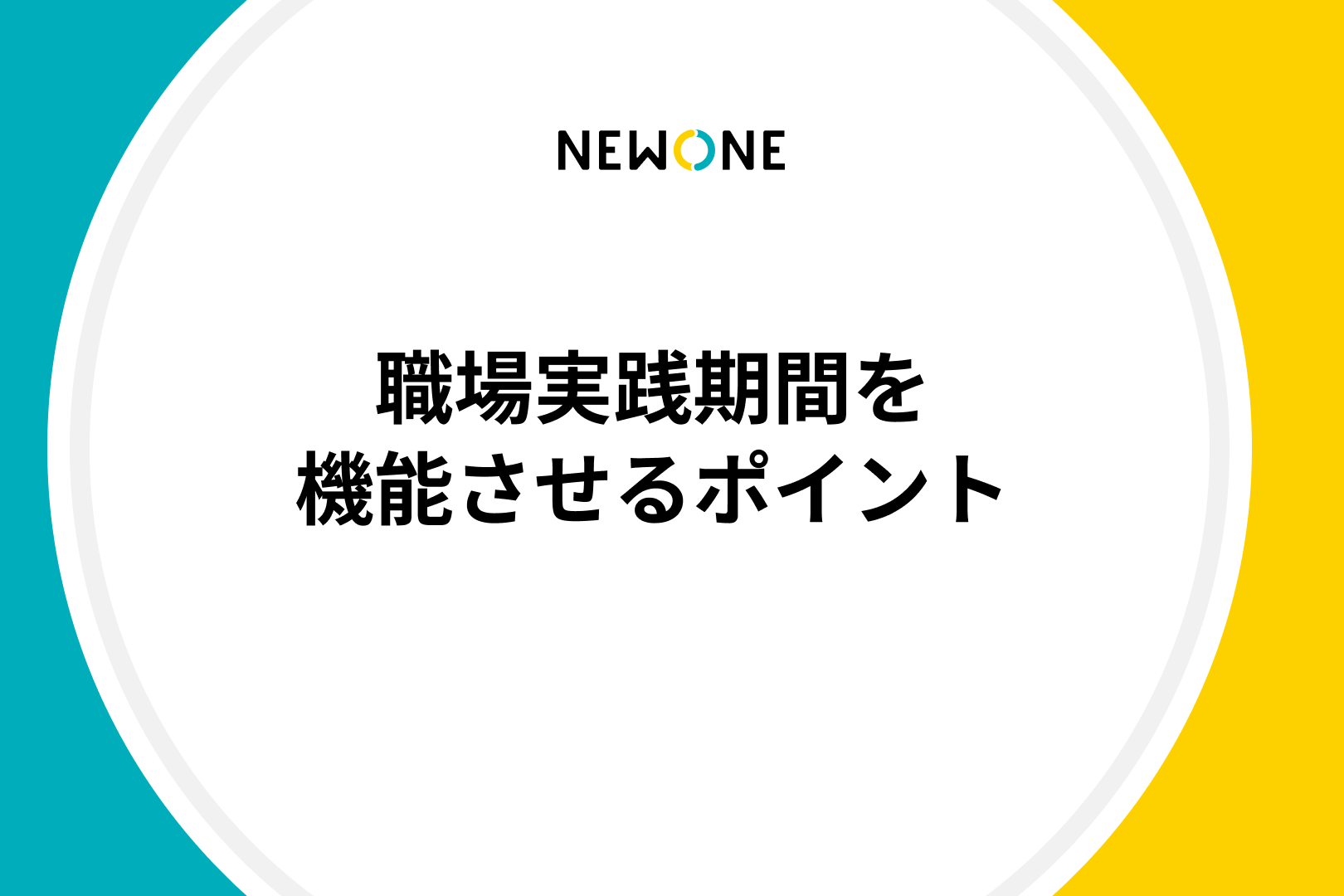
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
目次
研修を企画・運営するうえで最も重要なことの一つは、受講者の「行動変容」を促すことです。
しかし、多くの企業や人事担当者から「研修後に行動に移らない」「学んだことが定着しない」といった課題を耳にします。研修後の職場実践期間がうまく機能しないと、せっかくの研修も一過性のものになり、実際の業務に活かされることはありません。
では、どのようにすれば職場実践期間を効果的に機能させることができるのでしょうか? ここでは、研修後の行動変容を促進するための3つのポイントを紹介します。
ポイント①:振り返りの時間を半強制的に設ける
研修後の行動定着には、学んだことを振り返る機会を持つことが不可欠です。振り返りを通じて、自分がどのような行動をしたのか、どのような成果があったのかを整理し、次の行動へとつなげることができます。
しかし、多忙な日々の中で自発的に振り返りを行うことは容易ではありません。そのため、企業側が意図的に振り返りの機会を設ける必要があります。具体的には、以下のような施策が考えられます。
- 定期的な報告会を実施する:研修受講者同士が定期的に集まり、実践内容や課題を共有する場を設ける。
- 上司やメンターとの振り返りミーティング:研修後に上司やメンターと1on1ミーティングを行い、実践状況を確認する。
- 日報や週報の活用:受講者が研修内容を業務でどう活かしているかを記録し、定期的に振り返る習慣をつける。
このように、振り返りの時間を「半強制的」に設けることで、学んだことを実践する意識を高めることができます。
ポイント②:職場との関係性と研修内で促すアクションの整合性を取る
研修の効果を高めるためには、研修内で促すアクションと職場の文化・関係性が一致していることが重要です。
例えば、1on1ミーティングの習慣がない職場で「1on1を実施しましょう」と指導しても、実際には行動に移しづらいでしょう。同様に、上司との関係性が希薄な環境では、部下が積極的に上司と対話しようとすること自体が高いハードルになってしまいます。
このようなギャップを解消するためには、以下のような工夫が必要です。
- 研修前に現場の状況を把握する:現場の文化や習慣、受講者の上司との関係性を事前に確認し、それに応じた研修内容を設計する。
- 研修前に上司や関係者への働きかけを行う:受講者が職場で新しい行動を実践しやすいように、上司にも研修の目的や期待される行動を共有し、協力を求める。
- 職場の文化に合わせた実践方法を考える:例えば、1on1文化がない職場であれば、「簡単な雑談を増やす」「週に1回5分だけ進捗報告をする」など、小さなステップから始める。
研修で促すアクションが職場の実態とマッチしていなければ、行動変容は期待できません。研修の前後で職場の環境と整合性を取ることが、行動の定着につながります。
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
ポイント③:受講者の心理的ハードルを見極め、研修内でハードルを下げる
研修後に行動が定着しない理由の一つに、受講者の心理的ハードルの高さが挙げられます。「失敗したらどうしよう」「同僚にどう思われるか不安」といった感情が行動の妨げになっていることは少なくありません。
このような心理的ハードルを軽減するためには、研修内で「行動しやすい環境づくり」を行うことが重要です。具体的には、以下のような工夫が有効です。
- ロールプレイやシミュレーションを取り入れる:研修内で実際の場面を想定した練習を行い、実践のイメージを持たせる。
- 「小さな成功体験」を積ませる:いきなり大きな変化を求めるのではなく、「最初の1週間は○○をやってみる」など、無理のない範囲で実践を促す。
- 仲間と協力しながら実践できる仕組みを作る:受講者同士でペアを組んで実践をサポートし合う仕組みを導入する。
- 「やらないといけない」ではなく「やってみたい」と思わせる:研修の中で成功事例を紹介し、「やれば成果が出る」という期待感を持たせる。
研修内で心理的ハードルを下げることで、受講者が実際の職場で行動を起こしやすくなります。
まとめ
研修を効果的に機能させるためには、研修後の職場実践期間の設計が不可欠です。
そのためには、
- 振り返りの時間を半強制的に設ける(定期的な報告会やミーティングの実施)
- 職場との関係性と研修内で促すアクションの整合性を取る(職場文化に合わせた実践方法の導入)
- 受講者の心理的ハードルを見極め、研修内でハードルを下げる(ロールプレイや小さな成功体験の提供)
という3つのポイントを押さえることが重要です。
研修は、単なる「学びの場」ではなく、「行動を変えるきっかけ」として機能するべきものです。
職場実践期間を適切に設計し、研修をより実践的なものにすることで、組織全体の成長を促すことができるでしょう。
弊社では、職場で実践するポイントを押さえ、受講者の職場内の関係性や心理的ハードルに着目した研修設計を行っています。
職場実践の移行率にお悩みの方は是非お声掛けください。
 渡部 亮太" width="104" height="104">
渡部 亮太" width="104" height="104">