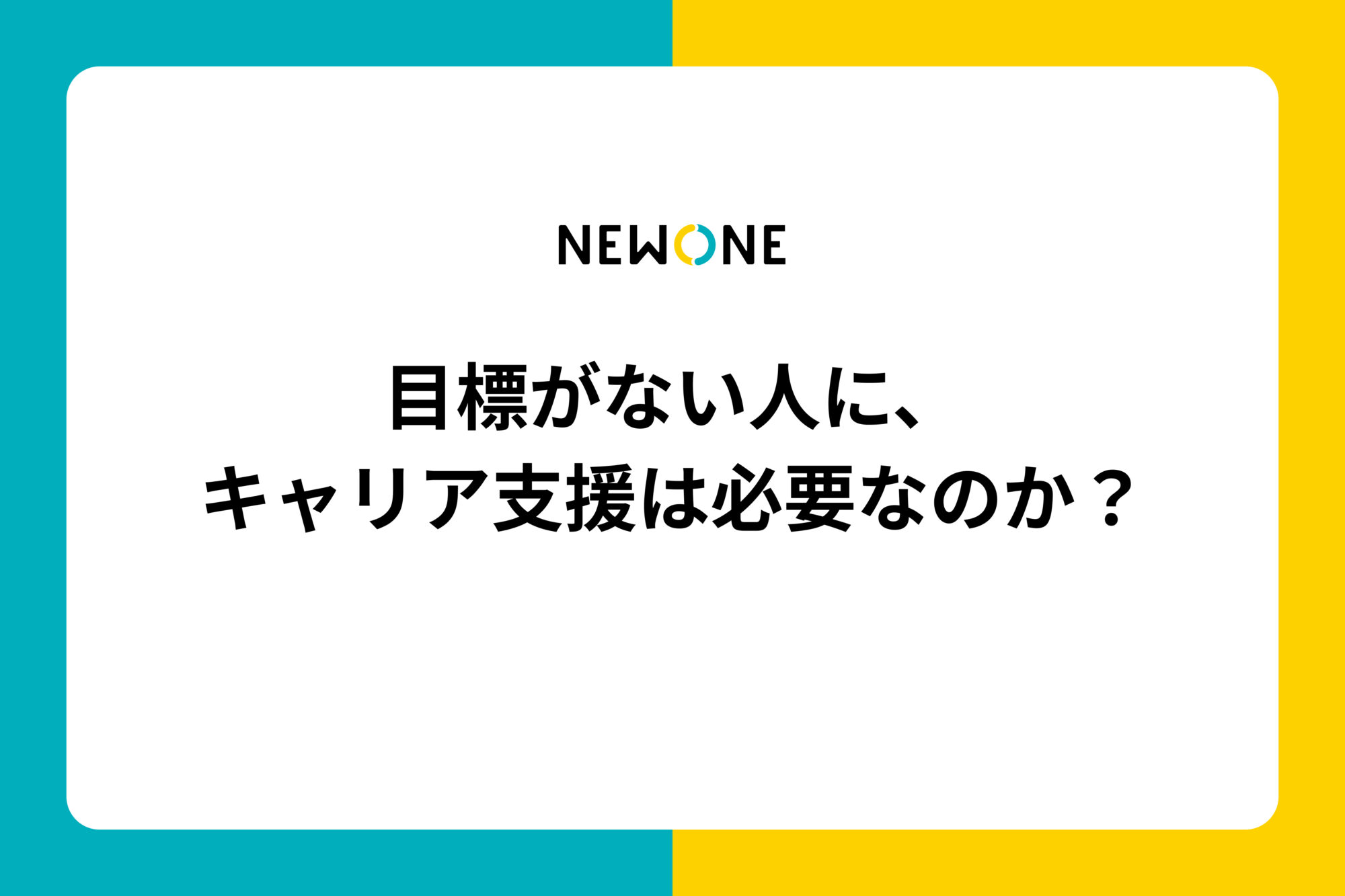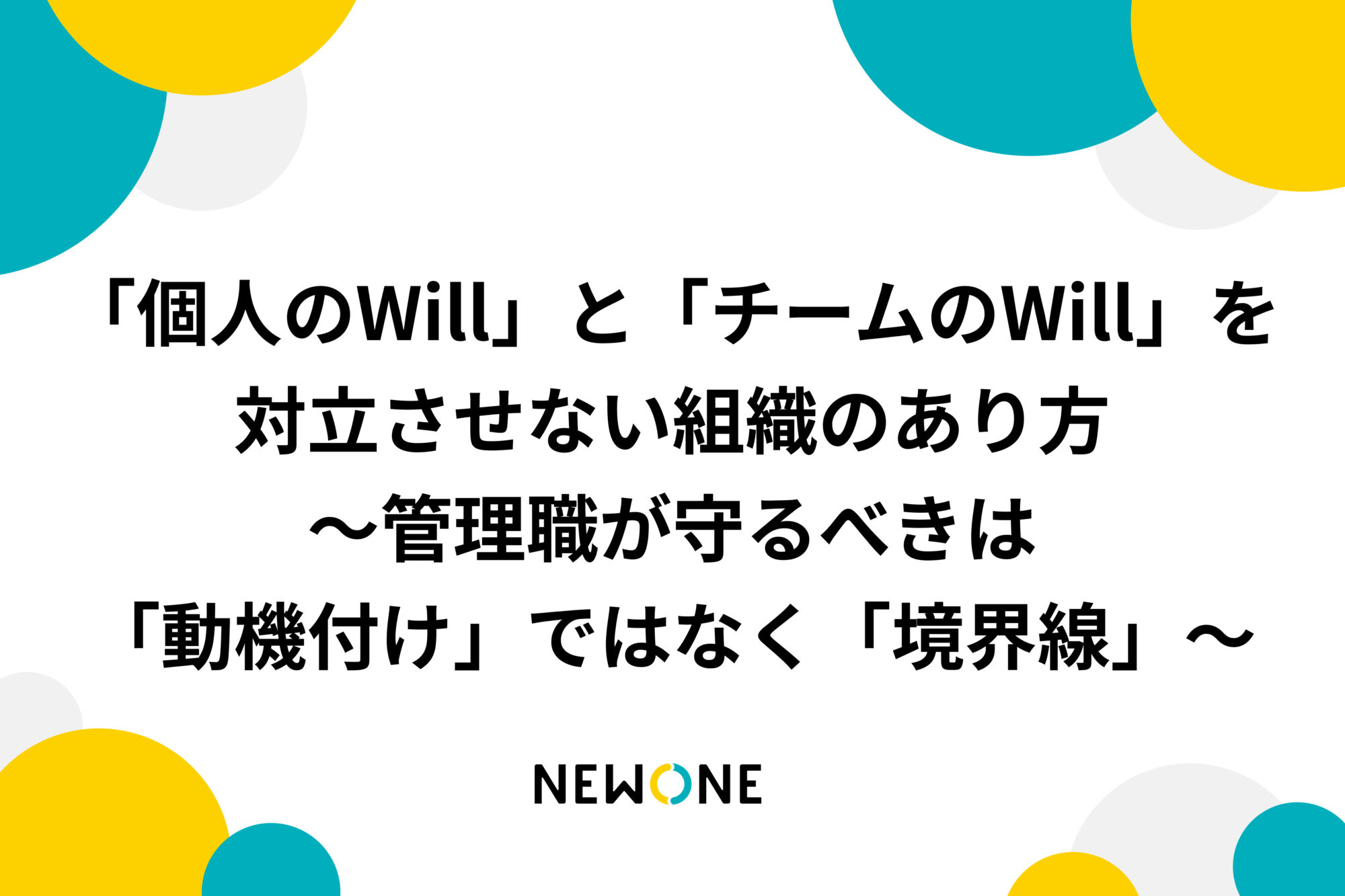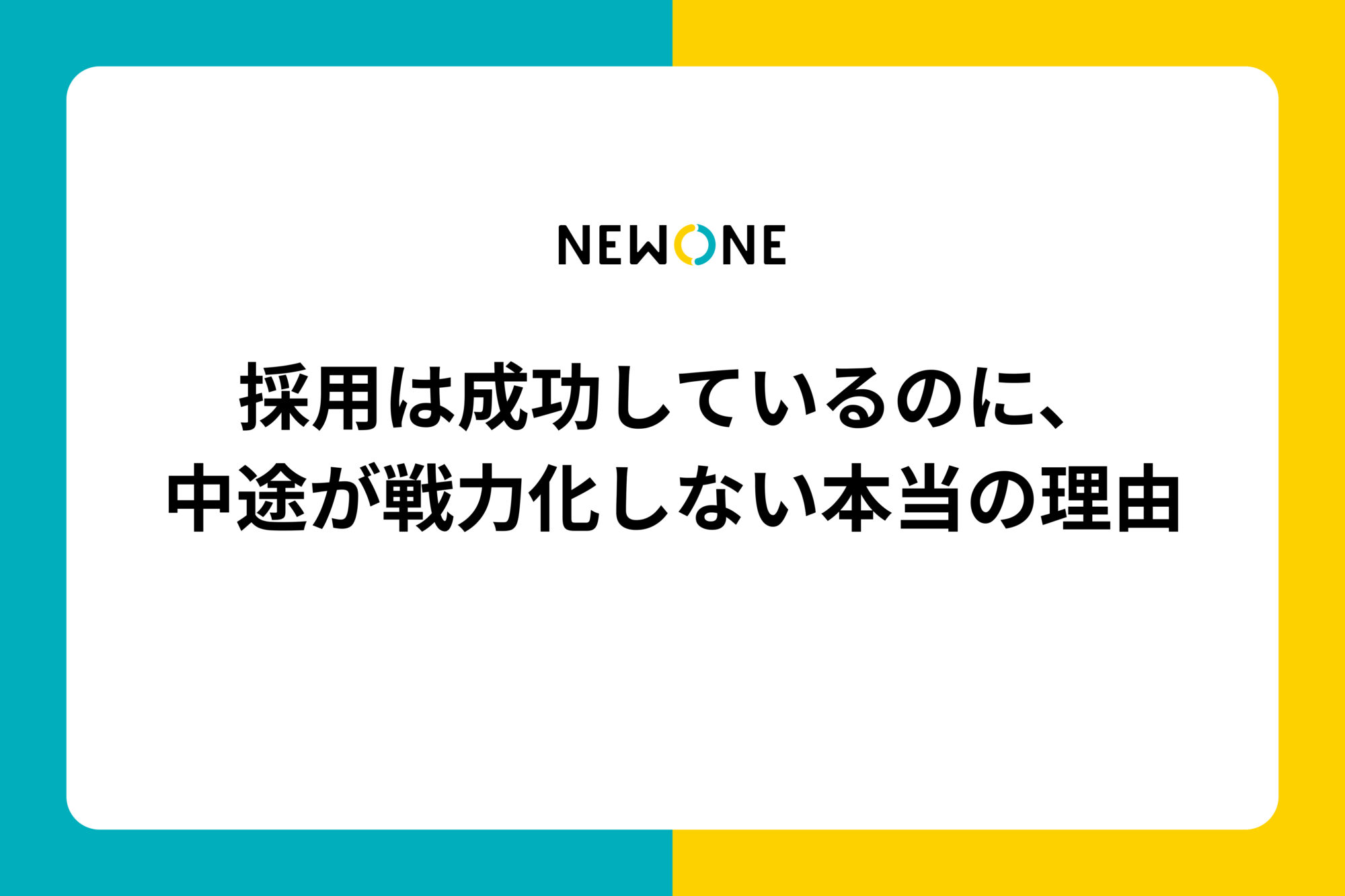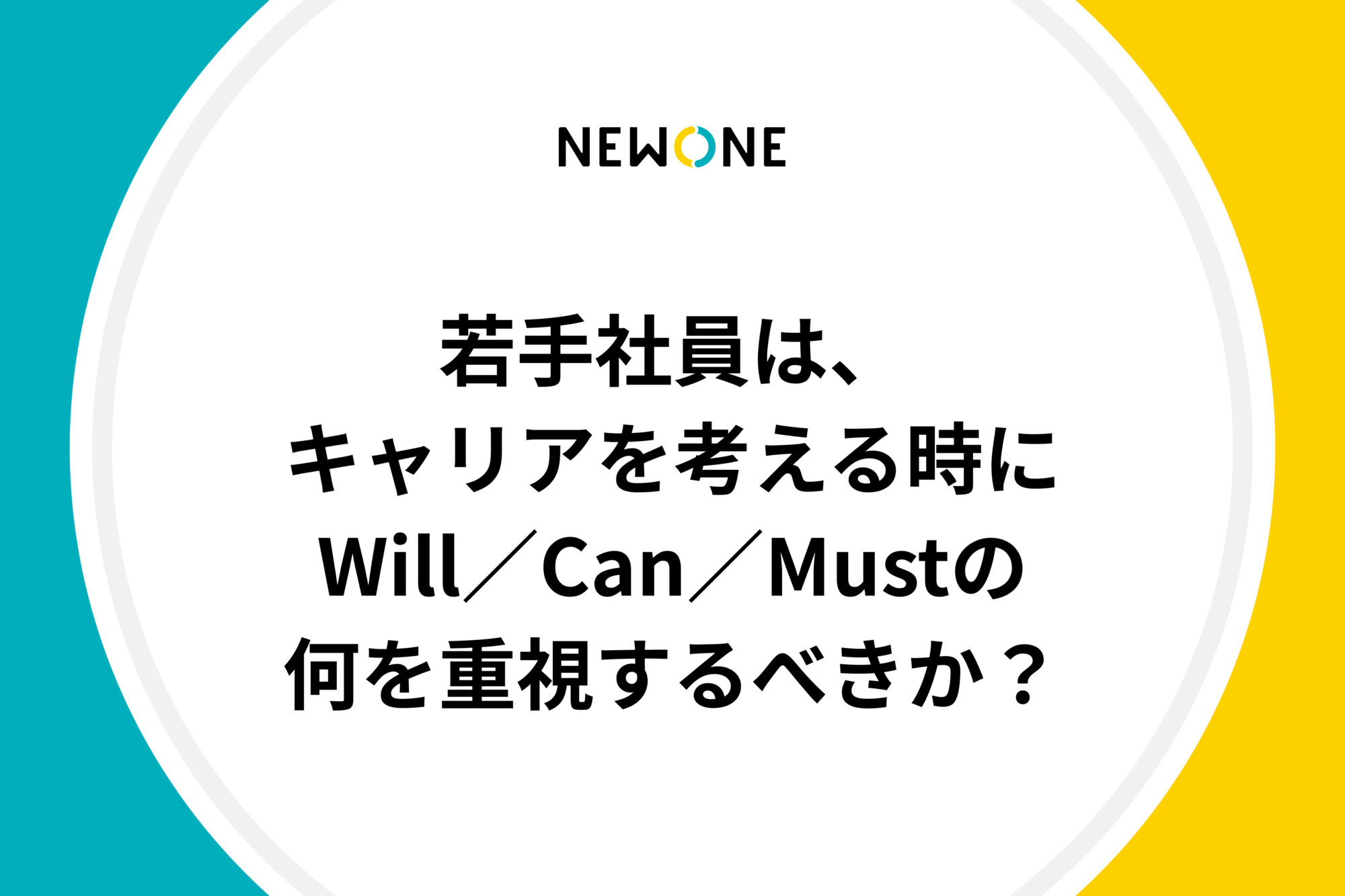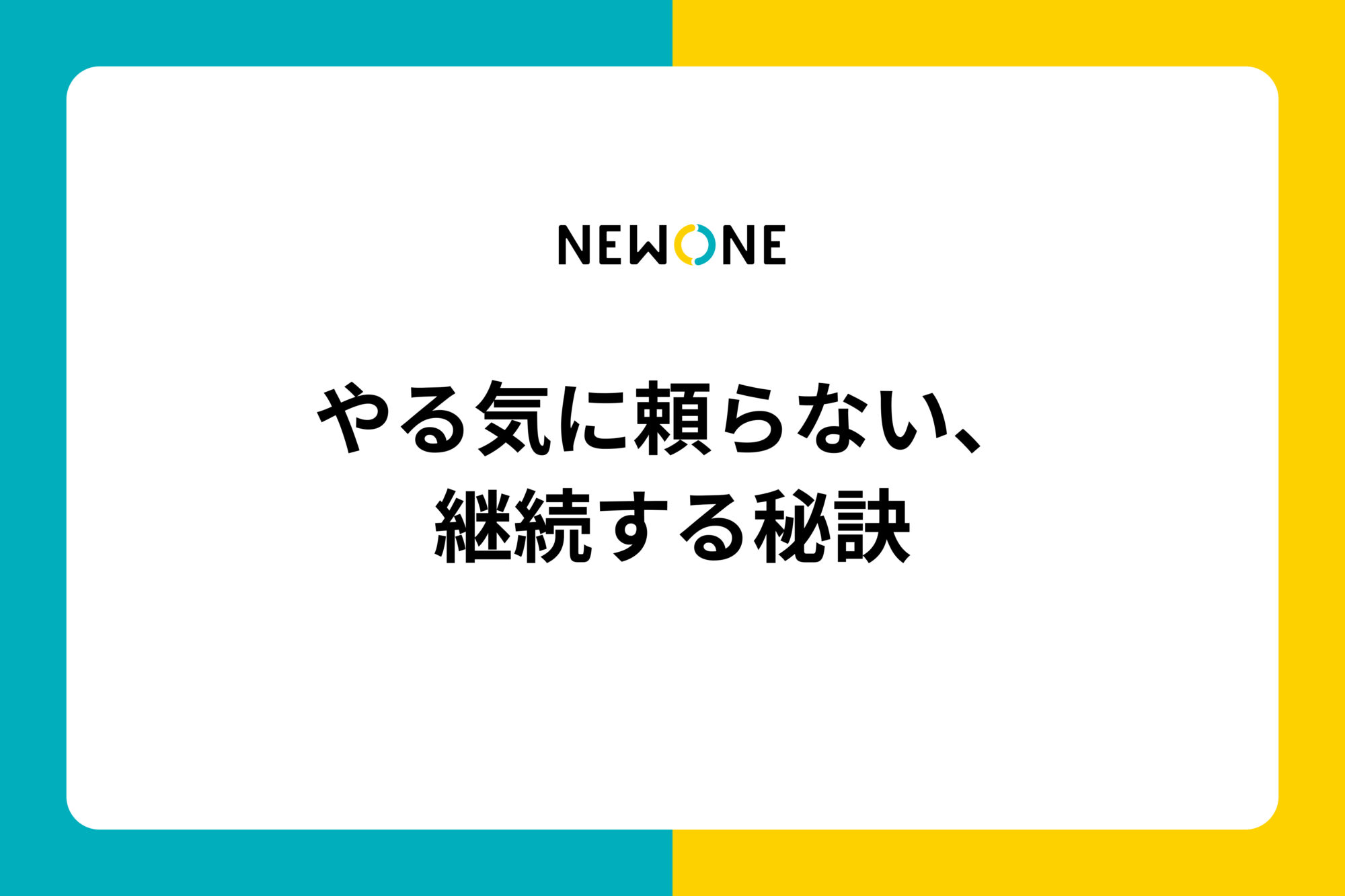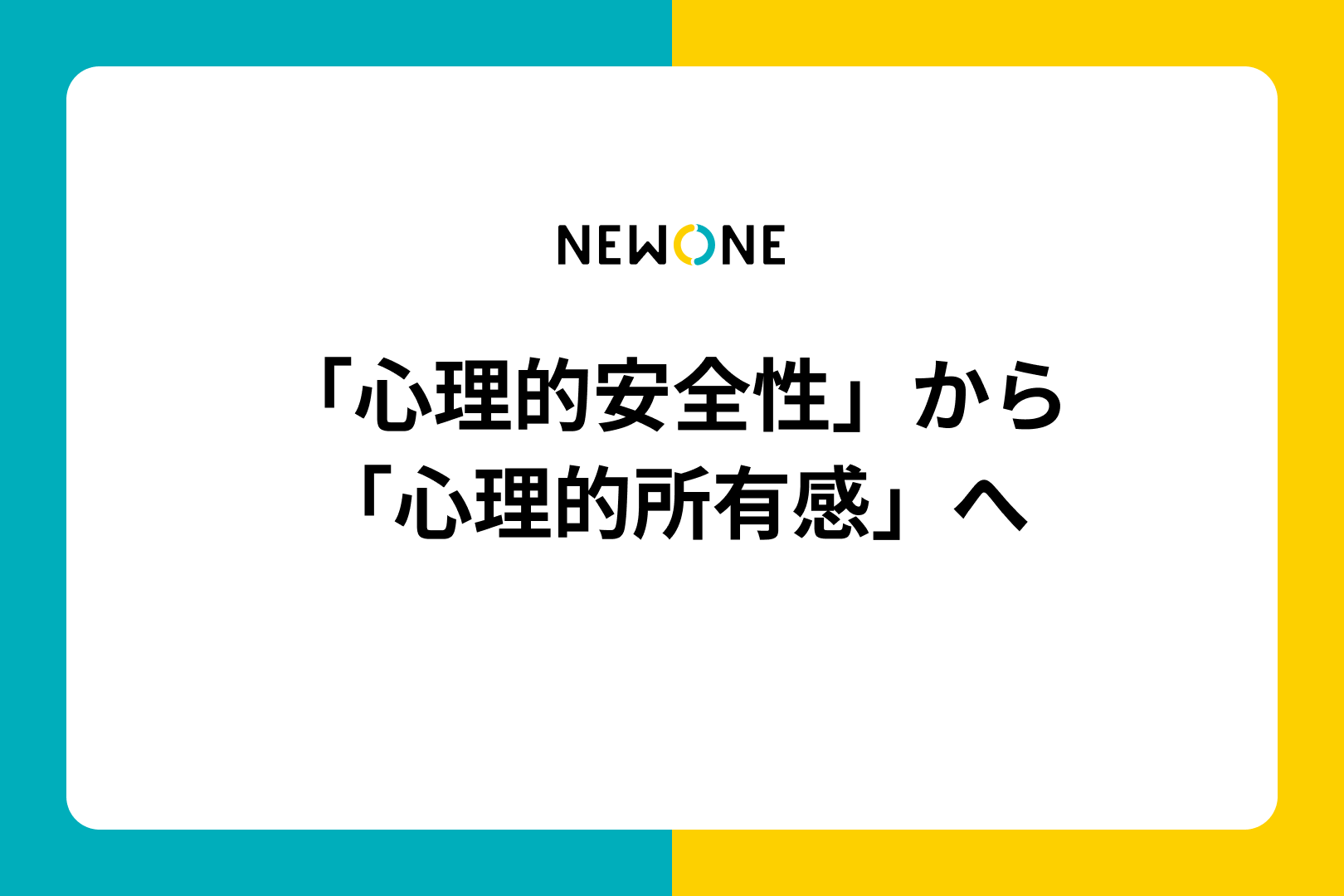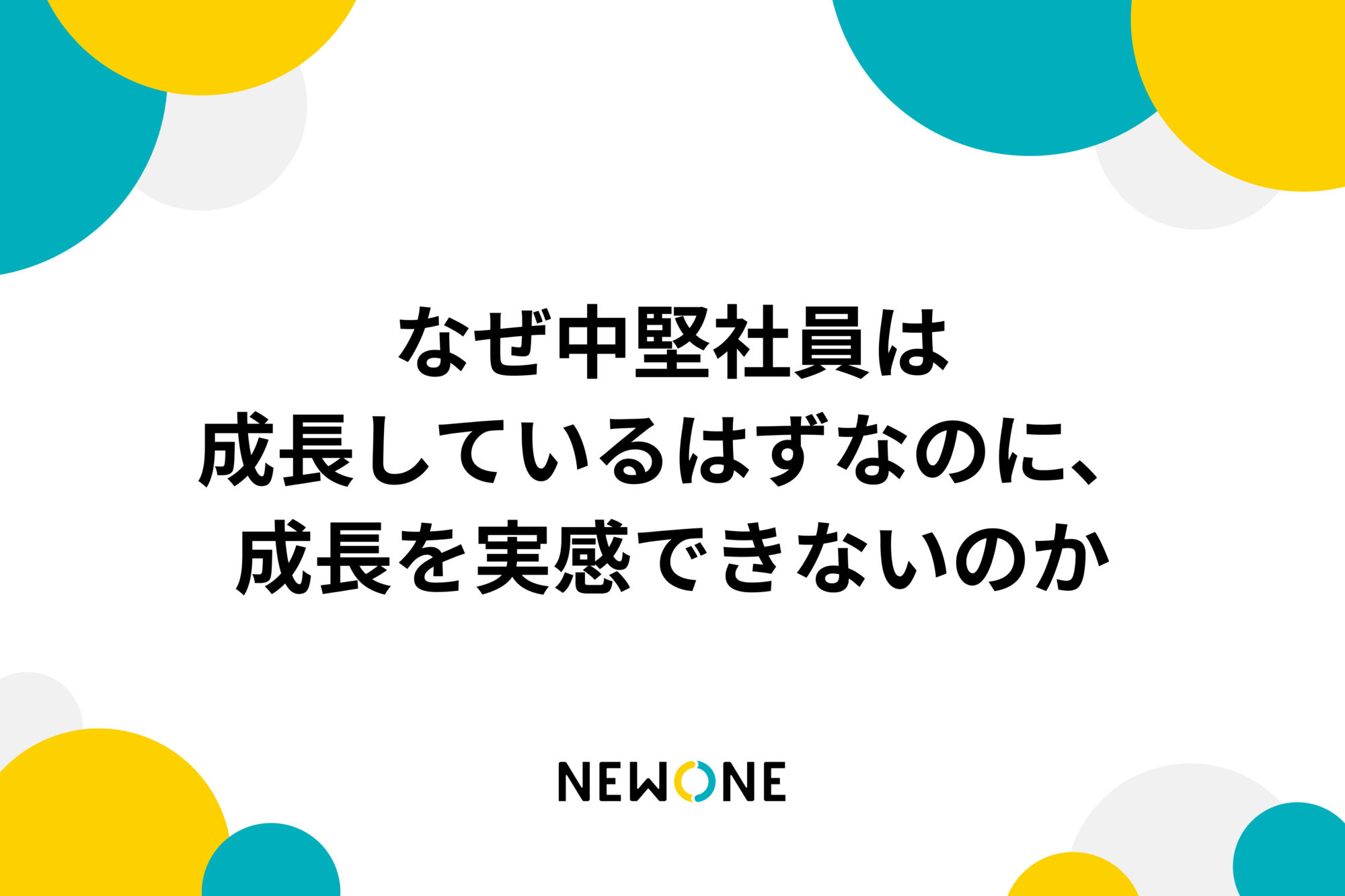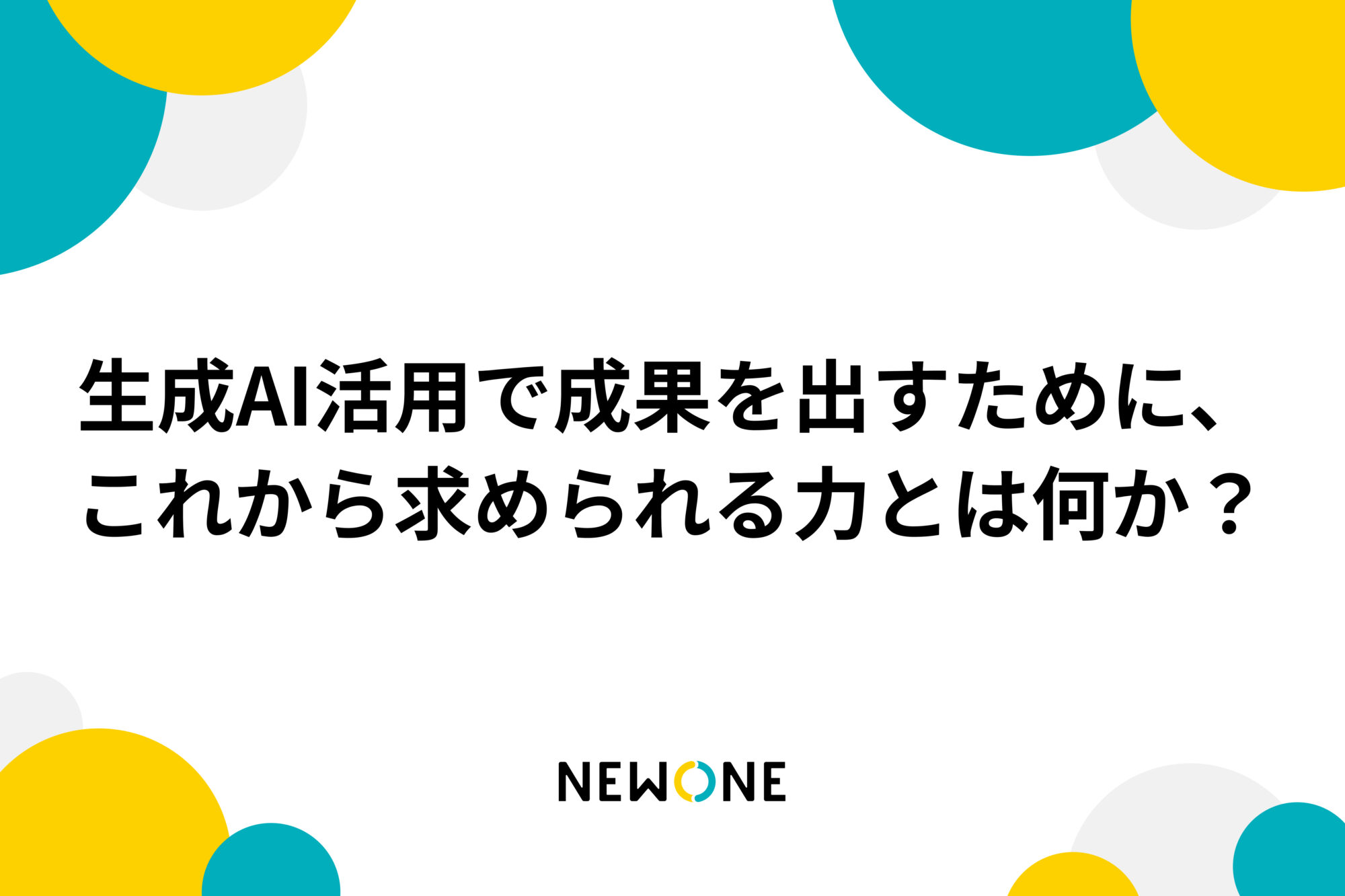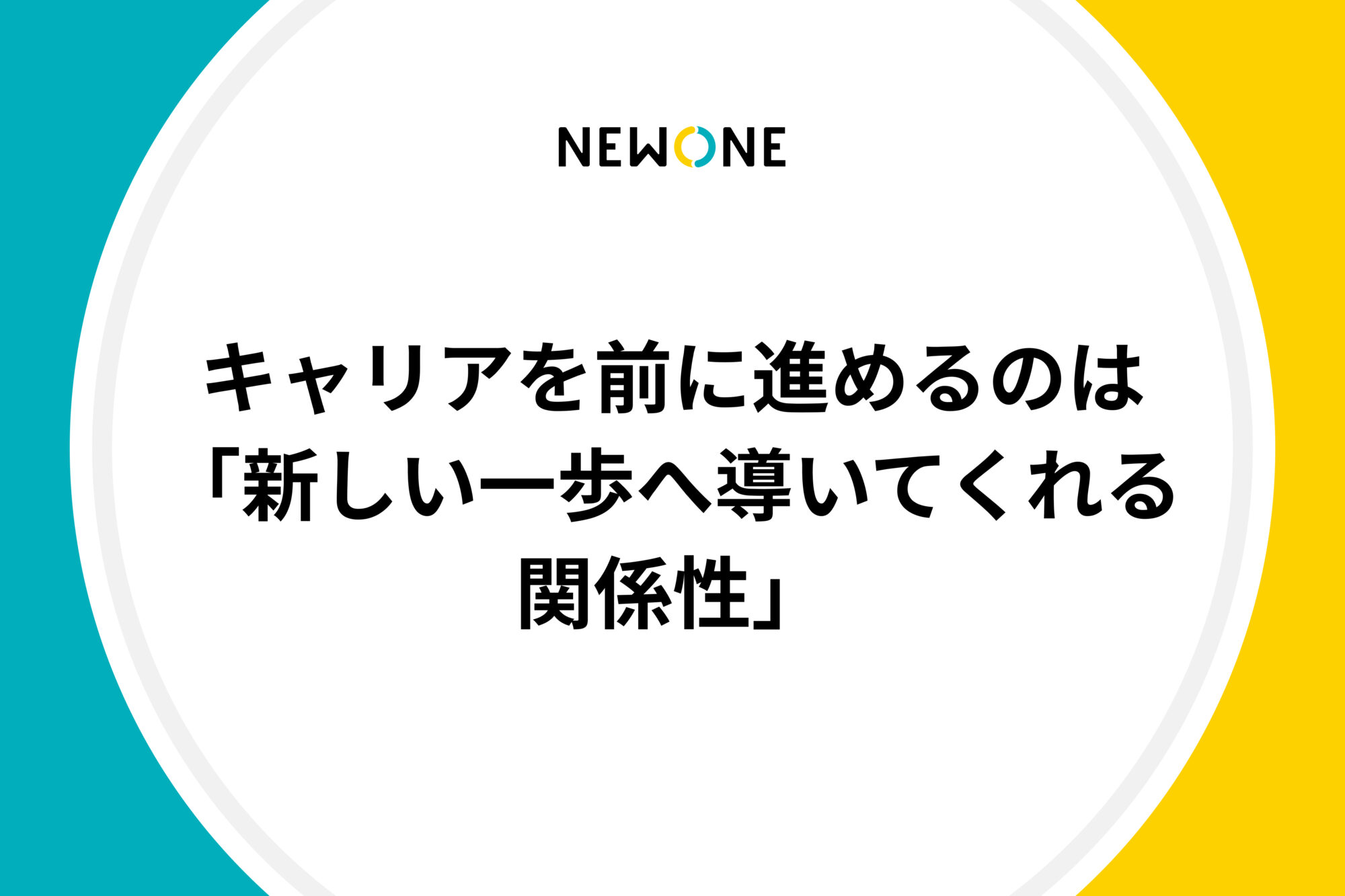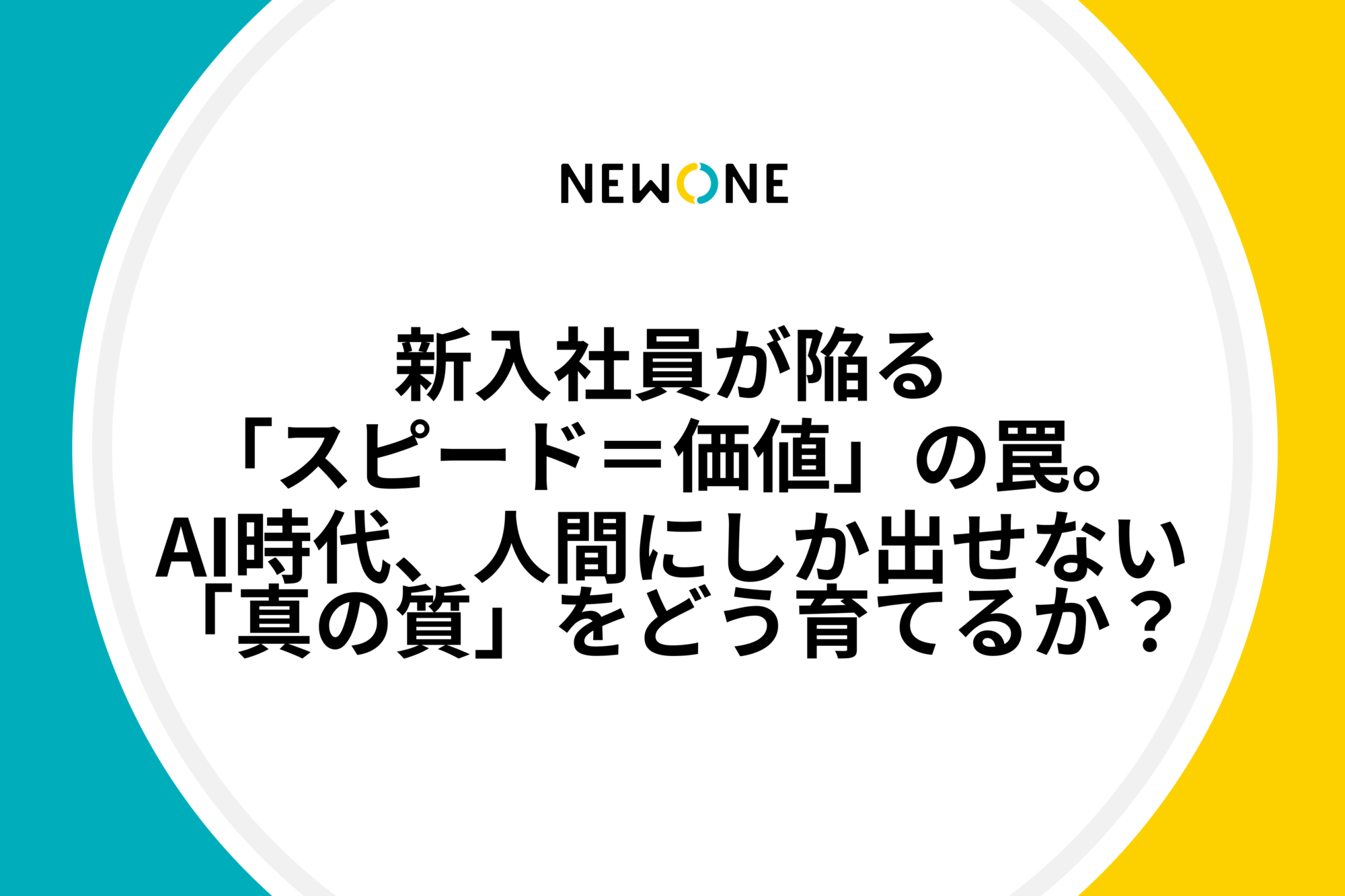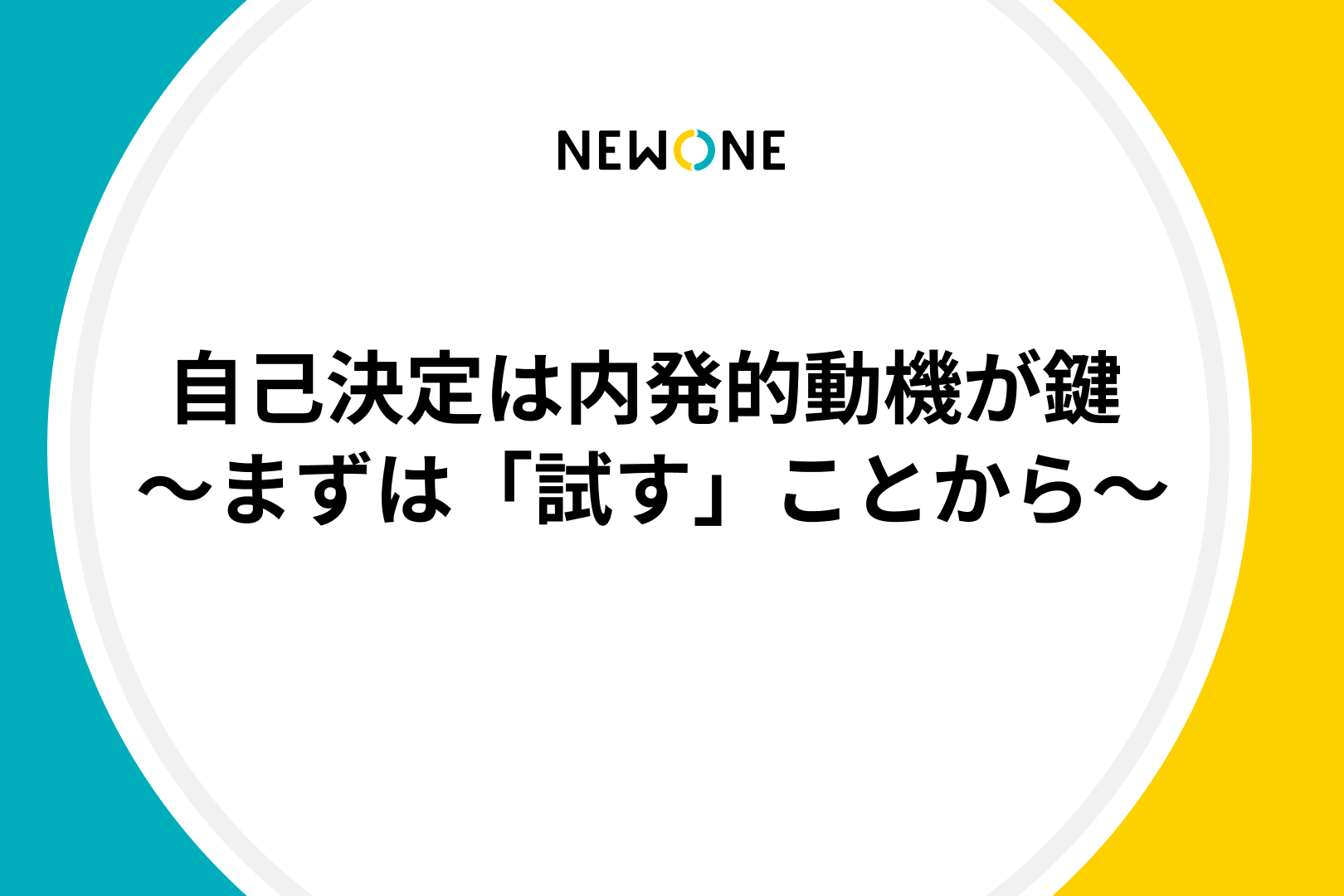
NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた
多種多様な研修を取り扱っております。
「自己決定は幸福度を高める」という「自己決定理論」をご存知でしょうか?エドワード・デシらによる理論で、人間は「自律性(自分で決めること)」、「有能感(成長を実感すること)」、「関係性(人とつながること)」の3つの基本的欲求が満たされると、より高い幸福感を得られるとされています。
特に、自律性は「自分で選んだことを実行する」という感覚を生み、それが満たされると、より充実感を感じやすくなると言われています。
とはいえ、最近若手の方々からよく聞くのは「自分で決めるほうが苦しい」「自分で決めたくない」という声です。
その背景には、結果に対する責任が伴うことが大きく関係していると思います。
これまであまり自己決定をしてこず、親や周囲の意見に従っていた人にとっては、「決めてもらうことが当たり前」になっています(そのような状態が悪いと言いたいのではありません。
このような状態になるのは、小さい頃からの周囲の関わりなどの環境要因が大きいためです。)その場合、上手くいかなかったときに、責任も分担することができますが、自分で決めるとなると、すべての責任を自分が背負うことになりそうで怖いと感じてしまうのではないでしょうか。
「自己決定=責任を負うこと」ではない
ただし、自己決定は「言ったからにはやらないといけない」という強迫観念を生むものではなく、「決めた本人にすべての責任を背負わせるためのもの」でもありません。
本来の自己決定とは、「自分で決めなければならない」と義務のように押し付けられるものではなく、「やりたい」と思って自然と決まっているような状態です。「自己決定しなきゃ」(あるいは育成担当者の方からすると「自己決定をさせなきゃ」かもしれません)と考えすぎると、自己決定の本来の意味から離れてしまいます。
では、どうすれば「自然と決まっている」状態になれるのでしょうか?
NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした
人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。
「試す」ことで内発的動機を見つける
自己決定が幸福につながるのは、それが内発的動機に基づいている場合です。
外からの期待や報酬を意識して決めたことでは、自己決定による満足感は得にくいものです。
ただ、そもそも「自分が本当にやりたいこと」を見つけるのは簡単ではありません。
そこで大切なのが、「試す」ことです。近年は「コスパ」が重視され、試行錯誤するよりも、短期間で成果が出る選択肢を優先しがちです。
しかし、最初から「これが正解」と決め打ちしてしまうと、自分にとって本当に合うものを見つける機会を逃してしまいます。「これは好き」「これは少し違うかも」という自分の中の違和感を見つけていく作業こそが、内発的動機を知るために必要なのです。
試すことで、より内発的に「やってみたい」と思えるものが見つかり、それが自然と「自分で決めたこと」になっていく。そんなプロセスを大切にすることで、無理なく自己決定を楽しめるようになるのではないでしょうか。
 桶谷 萌々子" width="104" height="104">
桶谷 萌々子" width="104" height="104">